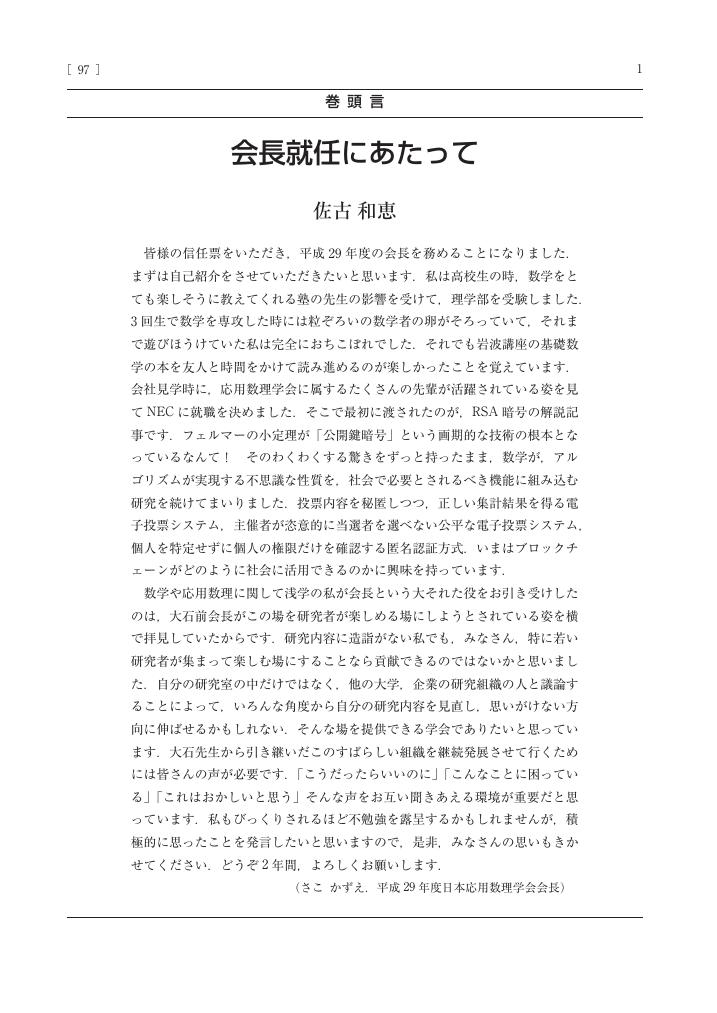1 0 0 0 OA ウラニル塩の種々溶媒中に於ける吸収スペクトル
- 著者
- 中井 敏雄
- 出版者
- 社団法人 日本分光学会
- 雑誌
- 分光研究 (ISSN:00387002)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.10, pp.25-32, 1954 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
It had long been known that uranyl salts have many sharp absorption bands when dissolved in various solvents1), 2). 3). Among these researches, in 1935 and 1939, Shibata et al.4). 5) showed that wave number of absorption hands of uranyl nitrate solution in acetone at lower temperature can be resolved with a general formula based on the theory of diatomic molecule. In this paper, the author wishes to report on the results gained when uranyl nitrate has been dissolved into many other organic solvents under varieties of temperature, for the purpose to examine the correct-ness of that formnla. Solvents used and the ranges of temperature (°C) estimated are as follows: water (ordinary temp.), urethane (<50°), acetamide (85°), methyl alcohol (15° and -70°), ethyl alcohol (15° and -70°), propyl alcohol (15° and -70°), ethyl ether (10° and -70°), ethyl acetate (-67°), methyl lactate (-40°). propyl valeriate (15°), ethyl acetoacetate (10° and -40°), acetophe-none (15°) and benzophenone (60°).
- 著者
- 小林 昭夫
- 出版者
- Japan Meteorological Agency / Meteorological Research Institute
- 雑誌
- Papers in Meteorology and Geophysics (ISSN:0031126X)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, pp.1-14, 2021 (Released:2021-01-21)
- 参考文献数
- 31
Kobayashi(2017)は、GNSSデータの共通ノイズを低減し、1年間の傾斜期間を持つランプ関数との相関を取ることにより、南海トラフ沿い長期的スロースリップの客観検出を行った。ここではこの手法を応用し、南海トラフ沿い短期的スロースリップの客観的な検出を行った。GNSS日値および6時間値について長期トレンドを除き、1週間の傾斜期間を持つランプ関数との相関を取った。本手法により検出された時空間分布は、深部低周波地震の活発化とよく一致していた。また、Kobayashi(2017)は長期的スロースリップに伴う変位を検出したが、ここではその手法を応用して検出された長期的スロースリップの規模推定を行い、先行研究とほぼ一致した結果が得られた。
1 0 0 0 OA 科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査2020)報告書
- 著者
- 科学技術・学術政策研究所 科学技術・学術政策研究所
- 出版者
- 科学技術・学術政策研究所
- 雑誌
- NISTEP REPORT
- 巻号頁・発行日
- vol.189,
1 0 0 0 IR <論文>モータリゼーションへの意志 : ナチズムにおける自動車と近代性
- 著者
- 田野 大輔
- 出版者
- 京都大学文学部社会学研究室
- 雑誌
- 京都社会学年報 : KJS = Kyoto journal of sociology
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.123-150, 1997-12-25
In diesem Aufsatz geht es um die kulturelle Reichweite der Motorisierung im Dritten Reich. Den kulturpolitischen Grundzug des Nationalsozialismus hat J. Herf als 》Reaktionare Modernitat《 charakterisiert, d.h. als Mischung von reaktionarer Politik und technischer Modernitat. Aber dieser Begriff ist irrefuhrend, weil sich die Haltung der Nationalsozialisten zur Modernitat nicht einfach als 》reaktionar《 definieren lasst. Eher sollte man den an sich ambivalenten Charakter der Moderne, der von D. Peukert als 》Janusgesicht des Modernisierungsprozesses《 gekennzeichnet worden ist, zur Diskussion stellen, um das Wesen des Nationalsozialismus zu erklaren. Darilber hinaus soll hier klargemacht werden, dass sich Hitlers Diktatur auf diese ambivalente Modernitat stutzte, die das deutsche Volk bis zum Zusammenbruch des Dritten Reiches faszinierte und nicht zuletzt im Autobahnbau und im Volkswagenprojekt ihren Niederschlag fand. Hitler trat mit dem Ziel an, eine motorisierte Volksgemeinschaft zu schaffen. Er gelobte, auch dem deutschen Arbeiter zu einem Wagen, dem Symbol der Modernitat, zu verhelfen und damit die spannungsgeladene Distanz zwischen den Schichten auszugleichen. Das war eine lockende Verheissung der NS-Zukunft. Der 》Fuhrer《 betrachtete das Automobil und andere Technologien als Mittel der Herrschaft, als 》elan vital《 des neuen faschistischen Menschen. Das Autobewusstsein des Dritten Reiches ist daher wohl als 》stahlerne Romantik《 zu kennzeichnen, wie Goebbels es nannte. Hier lasst sich die Ambivalenz der nationalsozialistischen Modernitat ganz klar erkennen, d.h. die Synthese von technologischem Fortschritt und diktatorischem Herrschaftsanspruch. Die Reichsautobahnen, 》die Strassen des Fuhrers《, sollten nicht nur 》Pyramiden des Reiches《 sein, sondern auch Symbol der Einheit der Nation, der raumliche Ausdruck der Gleichschaltung. Hier spiegelte sich die ganz moderne Vision einer integrierten Gesellschaft, der die Nationalsozialisten nur ihren eigenen Ausdruck gaben. Daruber hinaus sollten die Autobahnen nach Auffassung von F. Todt 》Kunstwerk《 sein, das den Versuch darstellte, Technik und Kultur zu versohnen und die NS-Ideologie in Stahl, Stein und Beton zu materialisieren. Wahrend aber die NS-Kunst grundsatzlich technologiefrei war, mit Ausnahme der Autobahnen, sah Hitler den Volkswagen eher im Kontext des Massenkonsums. Der Volkswagen sollte ein solides Gebrauchsgut sein und daher in seinem Design Einfachheit, Bescheidenheit, Zuverlassigkeit und Sparsamkeit darstellen. Bei seiner Stromlinienform, die die Geschwindigkeit formal zum Ausdruck brachte, ging es darum, den technologischen Fortschritt und die Modernitat des Regimes zu symbolisieren. Im Gegensatz zur Kunst, wo mit der Ausrottung der 》entarteten《 Kunst Modernitat nicht mehr thematisiert wurde, trat in der Autowerbung jedoch der moderne Massenkonsum als Hauptthema auf, in dem sich die Sehnsucht des Volkes nach einem bewegteren, individuelleren Leben widerspiegelte. Der Nationalsozialismus verstarkte also die Tendenzen zur Massenkonsumgesellschaft, denn die atomisierte Masse kam ihm hochst gelegen. Zusammenfassend lasst sich sagen, dass der Wille zur Motorisierung im Dritten Reich wohl als das 》Janusgesicht《 der Modernitat zu charakterisieren ist. Problematisch ist nur die Bewertung dieser Ambivalenz. Dieser ambivalence Charakter eignet sich nicht als Erklarungsmodell fur Verschleierungspraktiken oder Lugenhaftigkeit des Nationalsozialismus. Im Gegenteil zielten die Nationalsozialisten selbst auf einen Fortschritt in Harmonie und Ordnung, die Versohnung von Moderne und Kultur. Unverkennbar ist allerdings, dass diese Vision an sich im hochsten Grade modern ist. Man kann sogar die archaischen Elemente der NS-Kultur als Ausdruck der Modernisierungstriebkraft interpretieren, weil es ein ganz moderner Verhaltenskodex ist, zur ideologischen Legitimierung alte Symbole zu benutzen. Letztlich handelt es sich um die Durchmischung von progressiven und regressiven Tendenzen als typischen Phanomenen der Modernisierung.
1 0 0 0 IR 緋色の家族 : 家庭小説としての『緋文字』
- 著者
- 米山 正文
- 出版者
- 宇都宮大学国際学部
- 雑誌
- 宇都宮大学国際学部研究論集 (ISSN:13420364)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.89-104, 2012-09
1 0 0 0 OA 養液栽培トマトの湿気中根および水中根の生理活性と形態に及ぼす生育温度の影響
- 著者
- 中野 有加 渡邉 慎一 岡野 邦夫 巽 二郎
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE
- 雑誌
- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.5, pp.683-690, 2002-09-15 (Released:2008-01-31)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 6 6
湿気中根を形成する保水シート耕(WSC区)と水中根を形成する湛液水耕(DFT区)において, 人工気象室内で生育温度条件を15℃, 25℃および35℃の3段階に変えてトマトを栽培し, 根の生理活性や根系形態を比較することにより湿気中根と水中根の温度適応性の違いを検討した.DFT区における液中溶存酸素濃度は飽和量の93%以上で推移した.トマト植物体の生長は, 全ての温度条件下において, WSC区でDFT区より旺盛であった.根系当たりの出液速度は15℃区と35℃区ではWSC区でDFT区より大きかったが, 根乾物重当たりの呼吸速度は常にDFT区でWSC区より大きかった.根系形態は25℃区では両方式で差異はなかったが, 15℃および35℃区ではWSC区でDFT区より側根長および根投影面積が大きかった.また, フラクタル次元は15℃ではWSC区でDFT区より大きく, 根系がより複雑に発達したことを示した.これらの結果から, 湿気中根は水中根に比べて温度適応性に優れ, 不適温度条件下においても根系の拡大・発達と生理活性を維持できるため, 地上部生長の抑制が水中根と比較して小さかったものと考えられる.
1 0 0 0 OA 小型軽量な高速鉄道用空力ブレーキの開発
- 著者
- 高見 創
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- pp.19-00295, (Released:2019-12-16)
- 参考文献数
- 16
To shorten the stopping distance of the high-speed trains in case of emergency such as a huge earthquake, the author developed the small-size and light-weight aerodynamic braking device. The device increases an aerodynamic drag force of a train to achieve a high deceleration at the range of over 350 km/h without a friction between rail and wheel. The device is as miniaturized as possible in order to be installed flexibly on the train, whereby many devices with small-size drag panels are appropriately arranged throughout the train roof to obtain higher drag force. A pair of drag panels rotating around a horizontal axis which are connected by the gear can be actuated by the traveling wind without a large-size actuator. The full-scale prototype aerodynamic braking device is designed and manufactured. To examine its aerodynamic characteristics, one or two prototypes are tested on a wind tunnel facility at a maximum flow speed of 400 km/h (111 m/s). It was proven that the response time of motion from the folding position to the braking position took only 0.39 s, and the device could produce the aerodynamic drag of 2.3 kN per one unit at 400 km/h. Detached-eddy simulation (DES) is used to study the flow around a train roof with a large number of devices. The rate of change of the drag coefficient for devices with the staggered arrangement which aims to improve a total drag force of a train is compared against the standard parallel arrangement at U = 360 km/h. The staggered arrangement could increase the total drag coefficients 10.3 percent as compared to the standard parallel arrangement.
- 著者
- スギアンティ ゲック ラカ ウィラワン アイ マディ アディ ウタミ ニ ワヤン アリャ
- 出版者
- 学校法人 産業医科大学
- 雑誌
- 産業医大誌 (ISSN:0387821X)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.4, pp.353-362, 2019
- 被引用文献数
- 1
観光地プンリプランの伝統的な飲料であるロロチャムチャムはチャムチャムの葉(<i>Spondias pinnata </i>(L.f.) Kurz)を含み,バリ島各地に広く流通している.この研究は,ロロチャムチャムの微生物学的特性と製造工程の衛生との関連を調べることを目的としている.バリのプンリプランで,ロロチャムチャムのすべての家内生産者と取扱業者,4つの貯水池,そして3ヶ所の水源サンプルを対象に横断的研究を行った.衛生に関するデータは,観察とインタビューにより得た.サンプルの微生物学的特性は生菌数,大腸菌群の最確数(MPN),そして大腸菌(<i>E. coli</i>)汚染について調べた.強毒遺伝子を同定するためにポリメラーゼ連鎖反応(PCR)検査を行った.水源は腸管毒素原性大腸菌(ETEC)で汚染され,さらに貯水池の約25%とロロチャムチャムのサンプルの43.3%が大腸菌に汚染されていた.このことは,酸性条件下(平均pH 2.8)での大腸菌の生存を示している.30の家内生産者のうち,76.7%の衛生施設は安全基準を満たしていたが,器具の衛生管理(60.0%),取扱業者の衛生(50.0%),および生産現場の衛生管理(43.3%)は非常に低かった.取扱業者の不十分な衛生はロロチャムチャムの微生物学的特性と関連しており,調整オッズ比(AOR)は15.02(95%CI: 1.31-171.5,<i>P</i> = 0.029)だった.継続的な監視は,製造工程の衛生および事業従事者の衛生の改善に不可欠である.微生物学的研究は,酸性環境での生存能力を含む大腸菌の性質を理解する上で必要である.
1 0 0 0 カナダ,モントリオールにおける人口言語学的状況と英語系住民
- 著者
- 大石 太郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, pp.32, 2006
複数の言語集団が存在する地域では、多くの場合人口規模に対応する形で優勢な言語と劣勢な言語が存在するという状況が形成されやすい。そして、劣勢な言語を母語とする集団の構成員が優勢な言語を習得し、二言語話者になることが多くみられてきた。 カナダは、複数の言語集団が居住する地域の一例であり、具体的には、多数を占める英語を母語とする住民(英語系住民)に対して、フランス語を母語とする住民(フランス語系住民)が少数言語集団として存在してきた。その当然の帰結というべきか、カナダでは言語社会研究が非常にさかんであり、地理学はそこに一定の地位を占めている。そして、言語の社会的側面に関心を寄せる地理学的研究を意味する地言語学(geolinguistics)という名称も、人口言語学(demolinguistics)と並んで一般的になりつつある。 ところで、英語系住民が多数を占めるカナダにおいて、あるいは南の巨人アメリカ合衆国とあわせれば英語が圧倒的に優勢な北アメリカにおいて、フランス語系住民が8割以上を占め、1970年代よりフランス語のみを州の公用語とするケベック州はかなり特殊な存在である。そこで、ケベック州に居住する英語系住民は国家スケール、あるいは大陸スケールでは圧倒的多数派ながら、州スケールでは少数派という複雑な立場におかれている。それでも、「静かな革命」とよばれる1960年代の政治的・経済的・社会的変化と、それに続くカナダからの独立派政党の台頭までは、数の上では少数ながらも、英語系住民の地位が脅かされることはなかった。というのも、カトリック教会の強い影響力の下で、フランス語系エリートが政治を支配し、当時のカナダにおける経済の中心地モントリオール(モンレアル)に住む英語系エリートが経済を掌握するというすみわけがなされていたからである。モントリオールの英語系エリートがいかにフランス語を無視できたかということは、1958年にモントリオールのダウンタウンに建設された鉄道会社系の高級ホテルが多くの反対を押し切って「クイーンエリザベスホテル」と名づけられたことからもうかがわれる(Levine 1990)。しかし、カナダからの独立を目指すケベック党が勢力を強め、ついに政権を奪取してフランス語の一言語政策が強硬に進められるようになった1970年代後半以降、大企業の本社のトロントなどへの移転が相次ぎ、それに伴って英語系住民のケベック州からの流出が顕著にみられた。そのため、2001年センサスによればケベック州において英語を母語とする人口はわずか7.9%にすぎない(単一回答のみ)。そして、現在ケベック州に居住する英語系住民は、とくに若年層を中心にフランス語を習得して二言語話者となる場合がふつうになりつつある(大石 2003)。ケベック州の英語系住民に関する研究は、さまざまな分野においてかなりの蓄積がある。しかし、英語系住民がケベック州の言語環境にどのように適応してきたのかは十分に解明されているといえない。そこで本報告では、報告者が実施した聞き取り調査に基づいて、モントリオールにおける人口言語学的状況と英語系住民の生態を明らかにすることを試みる。
1 0 0 0 OA 丹羽保次郎先生を悼む
- 著者
- 阪本 捷房
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.6, pp.501-502, 1975-06-20 (Released:2008-04-17)
- 著者
- 北川 香子
- 出版者
- 東南アジア学会
- 雑誌
- 東南アジア -歴史と文化- (ISSN:03869040)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, no.38, pp.187-208, 2009
<p>This paper analyses the Khmer document entitled "<i>Affairee</i> 〔<i>Affaire</i>〕 <i>de Oknha Reachea Monty</i>〔<i>Ukañâ Râjâ Mupti</i>〕 <i>directeur Islamique sur le choix du chef de pagode, à Kompong Cham</i> (1914)" in the possession of the National Archive in Phnom Penh (Document No. 20811), which refers to the nomination of a Hakim Me Vat of Chams-Chhvéas in Kieng Romiet Village, Tboung Khmum Province. </p><p>Muslim Chams constitute "the second largest ethnic group" in the Kingdom of Cambodia, where Buddhist Khmers account for more than 90% of the population. From the late 1990s, numerous results of surveys on contemporary Chams have been released, but only few attempts have so far been made at historical studies on Chams in Cambodia. The principal reason is that there are few historical sources on Chams, especially those written by Chams themselves. Thus, Document No. 20811 is considered as a rare example. </p><p>From the analysis of this source, we can recognize the following points. (1) Chiefs of Muslim Chams-Chhvéas in Cambodia were given the highest title of ministers, Ukañâ, by the Cambodian King. (2) In order to enhance their power, they relied on the King and the Buddhist monks, who had supreme authority in Cambodia. Ukañâ Râjâ Mupti insisted that being appointed as Ukañâ by the Cambodian King, gave him the official authority to control every Cham-Chhvéa in Cambodia, and asserted his right to nominate Hakim Me Vat of each mosque. His rival Ukañâ Râjâdhipatî / Râjâbhaktî appointed a Hakim with the backing of a high priest of Vat Unnalom in Phnom Penh. (3) Chiefs of Chams-Chhvéas announced the appointment of Hakim to the village leader, Me Khum, and asked him to give his assistance to Hakim Me Vat. Me Khum, as well as Chaovay Srok, the governor of the province, only approved their decision after, and avoided becoming actively involved in a matter inside the community of Cham-Chhvéa. </p><p>However, it must be noted that Document No. 20811 provides only one account and that we need to compile more information in order to describe the history of Chams-Chhvéas in Cambodia.</p>
- 著者
- 秋山 仁志 坂元 麻衣子 赤間 亮一 安藤 文人 髙橋 幸裕
- 出版者
- 日本歯科医学教育学会
- 雑誌
- 日本歯科医学教育学会雑誌 (ISSN:09145133)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.27-34, 2020 (Released:2020-04-20)
- 参考文献数
- 9
抄録 日本歯科大学生命歯学部では, ICTを活用して最新の医療情報を収集, 分析, 評価する方法およびモラルに則って効果的に利用する技術や表現方法を含む能力を修得するため, 第1学年前期に歯科医療情報学実習を行っている. 第1学年学生は, G-suite, Moodleの利用方法, 情報倫理, 教育著作権, タッチタイプ習得, 画像処理法, データ分析, プレゼンテーション実践, 文書作成, ICTを用いた遠隔共同作業, インターネットによる歯科医学情報の収集を履修する. 「インターネットによる歯科医学情報の収集」 において, 第1学年学生はパソコンルームにて時間配分に従い与えられた5つの課題に対して初めて扱う医学中央雑誌Web (医中誌Web), PubMedを使用し, インターネットを利用して歯科医学情報を収集した. 学生は得られた情報と与えられた課題に適した文献1つを配布用紙に記載して提出した. 終了後に実施した学習後のフィードバックアンケートでは, 「インターネットによる歯科医学情報の収集の仕方が理解できた」 が98.4%, 「インターネットにより的確に調べることができると思う」 が94.6%, 「PubMedで文献を検索することができた」 が82.9%, 「医中誌Webを用いて文献を検索することができた」 が96.9%であった. 本実習により医中誌Web, PubMedを利用したインターネットによる歯科医学情報の収集は, 第1学年学生の歯科に対する意識の向上に有効であることが示唆された.
1 0 0 0 IR 沖縄海域におけるザトウクジラの鳴音の音響特性に関する研究
1 0 0 0 解熱鎮痛剤によるインフルエンザ脳炎・脳症の重症化に関する機構解明
【目的】緊急安全性情報や厚労省からの通達によって、インフルエンザ脳炎・脳症の発症とその重症化への一部の非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の関与が指摘されている。本症の特徴は、脳内でウイルスが検出されないこと、血清・脳脊髄液中において高濃度の炎症性サイトカインが検出されること、脳血管の損傷が認められることであり、脳血管透過性の上昇や血液脳関門(BBB)の破綻と密接な関わりがあると考えられる。本研究では、in vitroのBBBモデルのtight性に対する炎症性サイトカインやprostaglandin E_2 (PGE_2)の作用とそれに及ぼすNSAIDsの影響について検討した。【方法】ウシ脳毛細血管内皮細胞とラットアストロサイトをTranswell^<TM>に共培養させたBBBモデルを作成した。IL-6を単独またはTNFα・IL-1βと併用添加し、経時的にTranscellular endothelial electric resistance (TEER)値を測定した。PGE_2を添加し、経時的にTEER値を測定した。ジクロフェナクナトリウム(DCF)またはSC-560(COX-1選択的阻害剤)の存在・非存在下においてTNFαまたはPGE_2の添加がTEER値に与える影響を検討した。【結果・考察】TEER値はIL-6により濃度依存的に低下し、TNFα・IL-1βの併用によりさらに低下した。PGE_2の添加によりTEER値は低下し、DCFの存在下ではその低下は増強された。しかし、SC-560の存在下ではその増強は観測されなかった。以上より、炎症性サイトカインとPGE_2はBBB透過性を上昇させる作用を有していること、また既にPGE_2が産生している炎症状態おいて後からDCFが投与された場合にはPGE_2のBBB透過性の上昇作用が増強される可能性があることが示唆された。
1 0 0 0 OA 会長就任にあたって
- 著者
- 佐古 和恵
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 応用数理 (ISSN:24321982)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3, pp.1, 2017-09-26 (Released:2017-12-26)
- 著者
- 張 富士夫 吉野 浩行
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1105, pp.35-37, 2001-08-27
答 2人に1台の割合で自動車が使われると仮定すると、世界的には、これから自動車が増えていくであろう地域がたくさん残っています。一方で、化石燃料の制約がある。実際に全世界の2人に1人が車を使い出したら、大変な環境問題が生じます。自動車が増えるという仮説を成立させるには、クリーンさと安全をクリアすることが不可欠です。
1 0 0 0 日本海上の爆弾低気圧に起因する高波の発達機構
- 著者
- 猿渡 亜由未 渡部 靖憲
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集B2(海岸工学) (ISSN:18842399)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.I_1537-I_1542, 2015
急速な気圧の低下を伴い冬季に特に多く発生する爆弾低気圧は発生頻度,強度ともに増加傾向にあると言われており,近年の冬季の気候を決定する重要なファクターとなっている.2014年12月には日本海上で二つの大きな爆弾低気圧が相次いで発生し,北陸から北海道にかけての日本海側の広い範囲に高波被害をもたらした.本研究では過去36年間の気象再解析データと過去19年間に渡る波浪観測データを基に近年日本周辺における冬季の低気圧が頻発化傾向にあり,それに伴い高波リスクが増大していることを示す.さらに波浪推算結果から2014年12月に発生した爆弾低気圧に伴う高波の発生機構を説明し,本イベントがこれまでの典型的な西高東低の冬型の気圧配置に伴う高波とは全く異なる特徴を有していた事を示す.
1 0 0 0 伊奈製陶株式会社30年史 : 1924-1954
- 著者
- 伊奈製陶株式会社伊奈製陶株式会社30年史編集委員会 編
- 出版者
- 伊奈製陶
- 巻号頁・発行日
- 1956