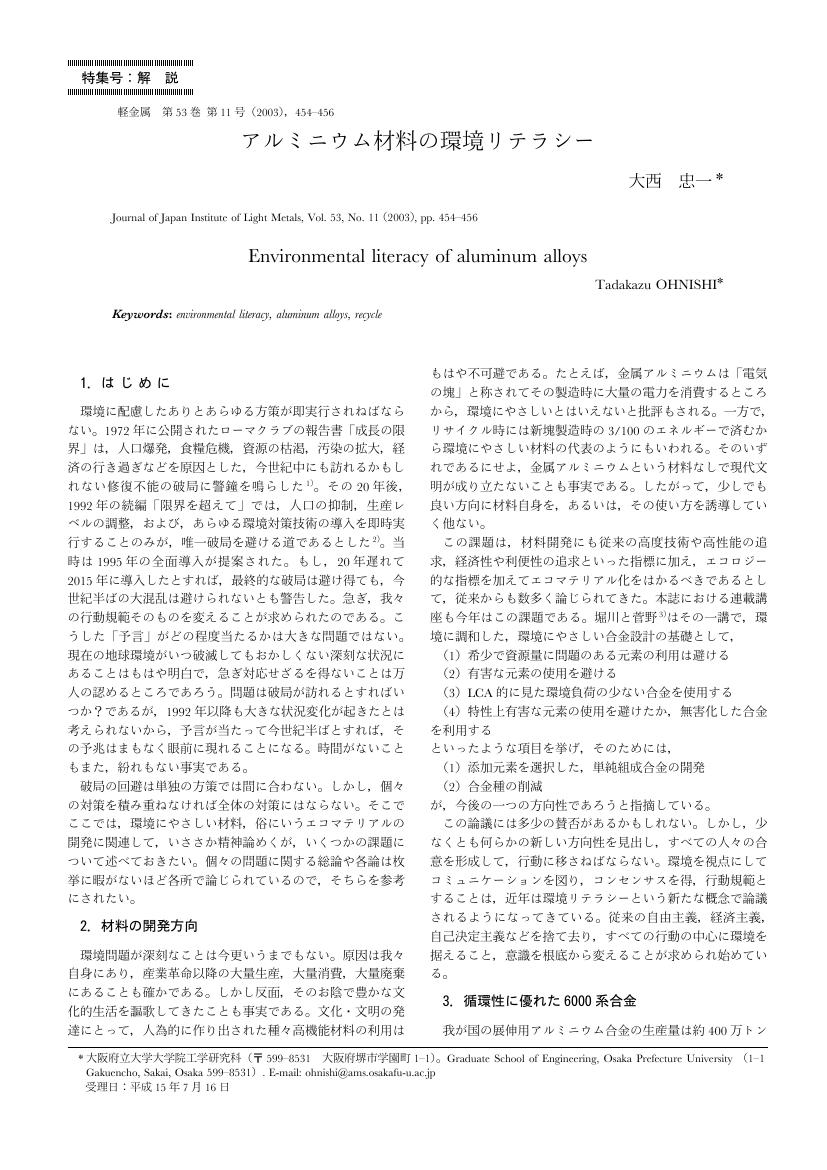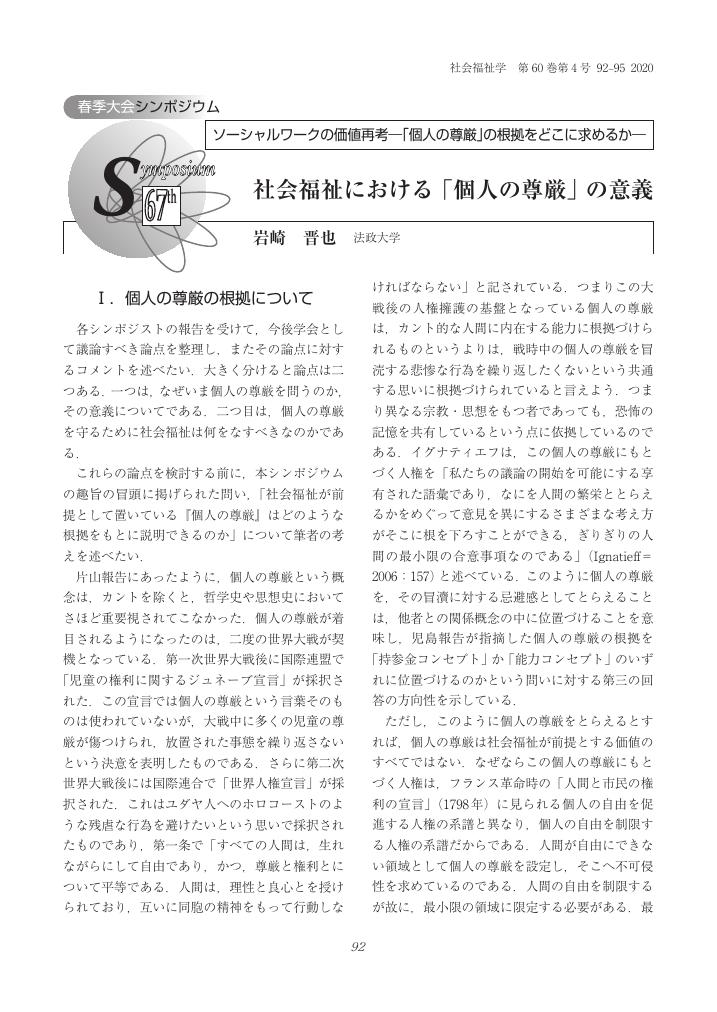1 0 0 0 नेपाली थर-गोत्र-प्रवर कोश
- 著者
- श्रीहरि रूपाखेती
- 出版者
- रत्न पुस्तक भंडार
- 巻号頁・発行日
- 2011
1 0 0 0 高齢者ケアスタッフの情意を構成する自我状態の評価と職種間比較
- 著者
- 安田 雅美 岩月 宏泰 岩月 順子
- 出版者
- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION
- 雑誌
- 日本理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, pp.G1743-G1743, 2008
【緒言】高齢者にケアサービスを提供する多くの関連職種は,職種間の協力及び連携無しにはサービスの質を維持し向上させることは困難となる.チーム医療には職種間の共働が欠かせない反面,顧客満足が重視される組織では役割期待の矛盾や,職業集団間での関心が相違するなど複雑な利害関係が生じやすい.この現状を踏まえ、適した協力体制を検討するために、各職業集団が持つ情意要因を明らかにすることも必要と思われる.今回,人間の心の要素を5つの自我状態から構成されるとする交流分析から,高齢者ケアに携わる職種間の特徴について検討した.<BR>【方法】対象は本調査の趣旨を理解した高齢者ケアに携わる職員に対し無記名自記式質問紙調査で回収し得た調査票151名(男性36名,女性115名)で.職種別に4群(看護職35名,介護職66名,療法士31名,その他19名)に分類した.調査票は基本属性(7項目),勤務状況(3項目),新版東大式エゴグラム(TEG2)ほかから構成されていた.TEG2は55項目から5つの自我状態(CP:批判的親,NP:養育的親,A:大人,FC:自由な子供,AC従順な子供)について各要素間の関係と外部に放出している心的エネルギー量を視覚化及びパターン分類したものである.統計学的検討は基本属性の項目とパターン分類間の関係についてX2検定を群間比較にKruskal-Wallis検定を行い,有意水準5%未満とした.<BR>【結果】全対象者のパターン分類ではN型(お人好し,殉教者,仕事中毒)37.8%と最も多く,次いで逆N型(孤高の人,自分勝手,気分屋)9.9%,平坦型(超人,凡庸,物静か)7.3%と続いたが,NP優位(世話焼き),NP低位(癇癪持ち)に属する者はみられなかった.<BR> 高齢者に日常的に接する職業では人間的,献身的に接することが求められる反面,サービスの成果を得るために客観的な態度も必要であり、その2つの心性を両立させることが期待される.全対象者のエゴグラムでN型(NPとACが同程度に高く,CPとAが相対的に低いパターン)が最も多かったのはこのような深刻な役割葛藤を要求させることの多い職業集団の情意を示すものといえる.一方,全対象者の基本属性の項目とパターン分類との関係では年齢階級に有意差を認めたが,性別,職種別及び就業年数との間で有意な差を認めなかった.なお,各自我状態の群間比較ではAに有意な差を認めたが,CP,NP及びACに有意な差を認めなかった.Aの一般的特徴である「現実的」,「冷静沈着」,「客観性の重視」の自我状態で看護職,療法士が他の2群より高値を示した.<BR>【結論】高齢者にケアサービスを提供する関連職種間の協力及び連携はサービスの質を維持し向上させるために欠かせない.そのため,組織内の各職業集団が持つ情意要因の客観的評価としてTEG2を活用することも有用と思われる.<BR><BR>
- 著者
- 柴田 清 杉山 静一 斎藤 文良 早稲田 嘉夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- 日本金属学会誌 (ISSN:00214876)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.7, pp.809-816, 1999 (Released:2008-04-24)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1 1
Automobile transportation is one of the predominant sources of air pollution, producing CO2, NOx, and SOx. The weight reduction of automobiles is essential for reducing the environmental burden during their life cycle. High-tension steel, aluminum alloy and resin are candidates for such purpose. However, substituting aluminum for steel is not always beneficial with respect to reducing the burden on the environment, because the energy consumption during aluminum production is considerably greater than that for steel. A generalized equation has been derived to describe the relationship between the driving distance, weight reduction, materials production route, and change in environmental performance. In particular, the effect of the difference of electricity source for aluminum smelting on life cycle CO2, NOx, and SOx, by substituting aluminum for steel in automobile parts, is discussed. The reduction of CO2 emission can be expected for all cases, if 50% of mass reduction is made. On the other hand, aluminum produced by the uncontrolled coal fire power is not capable of reducing NOx emission. It is also suggested that a reduction of SOx emission can only be obtained when using very clean aluminum.
1 0 0 0 OA アルミニウム材料の環境リテラシー
- 著者
- 大西 忠一
- 出版者
- 一般社団法人 軽金属学会
- 雑誌
- 軽金属 (ISSN:04515994)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.11, pp.454-456, 2003 (Released:2007-03-30)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 3 1
1 0 0 0 IR デザイン態度(Design Attitude)の概念の検討とその理論的考察
- 著者
- 安藤 拓生 八重樫 文
- 出版者
- 立命館大学経営学会
- 雑誌
- 立命館経営学 = The Ritsumeikan business review : the bimonthly journal of Ritsumeikan University (ISSN:04852206)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.85-111, 2017-01
1 0 0 0 OA 訳註大日本史
- 著者
- 徳川光圀 撰
- 出版者
- 建国記念事業協会・彰考舎
- 巻号頁・発行日
- vol.八, 1943
1 0 0 0 OA 枕慈童
- 著者
- 宝生新 [編]
- 出版者
- 下掛宝生流謡本刊行会
- 巻号頁・発行日
- 1934
1 0 0 0 OA 四庫全書総目提要 玉台新詠 訳注
- 著者
- 樋口 泰裕
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 文学部紀要 = Bulletin of The Faculty of Language and Literature (ISSN:09145729)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.97-81, 2000-10-01
陳の徐綾撰『玉台新詠』十巻とは如何なる書物で、また如何なる問題を孕んでいるのか、四庫提要の撰者は、成書の時期、本集の体裁及び内容、文学的及び資料的価値、そして版本といった幾つかの視点から解説する。当然、そこには時代の限界などによる問題点も若干窺えようが、当時第一級の知識と見識を誇る学者たちによって執筆されたそれは、現在もなお尊重されるべき指摘を富有した、『玉台新詠』という書物を理解していく上で看過できない基本的な文献なのである。
1 0 0 0 OA 扁桃における溶連菌抗体の局在に関する研究
- 著者
- 土屋 紀一
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.8, pp.1382-1390, 1970-08-20 (Released:2010-10-22)
- 参考文献数
- 38
1) 目的腎炎発症に際して, 扁桃が病巣感染源としてその発現機序の中で何らかの位置を占め, 特に溶連菌の感染が重要な意義を有していると考えられている. しかし溶連菌感染から如何にして腎炎が発症するかの機序については未だ結論が得られていない. 先ず扁桃において溶連菌に対する抗体が産生されるものと考えられるが, この点に関する免疫組織学的研究は多くない.著者は溶連菌のうちでもA群12型が催腎炎性が強いことに鑑み, その型特異物質であるM proteinを用いて, ヒト扁桃におけるその抗体の局在およびM proteinの局在などを, 免疫組織学的に研究し, 溶連菌感染に際し, ヒト扁桃内に惹起される免疫学的反応を明らかにすると共に, 腎炎発症との関連性を追求することを企図した.2) 実験方法M proteinの分離は次の如くに行った. 溶連菌A群12型の菌株をmouse passageにより強化し, 大量培養後, 菌体からpH2.0, 95℃の下にM proteinを抽出し, ribonucleaseにて核酸を除去し, 硫安分画を行った. 抗M protein抗体の証明には螢光抗体補体法を用いた. 補体はモルモット血清を, 抗補体血清はモルモット血清グロブリンを家兎に感作したものを使用した. 螢光物質にはfluorescein isothiocyanateを用い, sephadexにて遊離色素の除去を, DEAEセルローズにて非特異物質の除去を行った.M proteinの証明には螢光抗体直接法を行った. 抗血清には溶連菌12型の型血清を使用した.用いた材料は慢性扁桃炎患者および亜慢性腎炎 (木下) 患者の扁桃である. これらの扁桃より凍結切片を作製して染色を行った.3) 結果扁桃の上皮下組織には比較的多数の抗M protein抗体を含む細胞が局在していた. また被膜および中隔には多数の抗体含有細胞が局在し, 特に亜慢性腎炎患者の扁桃において著明であった. このことから溶連菌感染に際し扁桃内に溶連菌抗原に対する抗体が産生されていると考えられ, 溶連菌感染を繰り返しているうちに被膜結合織に腎障害性物質が生ずる可能性が推察された.またM proteinは腺窩内不全角化上皮に特徴的に認められたが, これは扁桃に対して抗原刺激が持続的に加わることを意味するものと思われた. 培養によっても溶連菌が検出されなかった扁桃において, 同様な所見を認めることから, 菌陰性でも溶連菌による抗原刺激が存在する可能性があることが示された.
1 0 0 0 近代郊外住宅地の萌芽的形成 : 住吉村を事例として
- 著者
- 山本 ゆかり
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.592, pp.233-238, 2005
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 2
The purpose of this research is clarifying manifestation of a suburban residential section for "Sumiyoshi-mura" located in the Hanshin area where the suburban residential section's developed in modernization. "Sumiyoshi-mura" is reconstructed and developed in early 20th century. Several points were revealed. "Sumiyoshi-mura" made the land of a village housing site in 1900. Moreover, the many businessmen of Osaka bought the land of Sumiyoshi-mura. "Mototaro Abe" borrowed and developed land from the village. These were before generating of the residential suburbs in Japan.
- 著者
- 坂本 勝比古 鈴木 成文 日色 真帆
- 出版者
- 一般財団法人 住総研
- 雑誌
- 住宅総合研究財団研究年報 (ISSN:09161864)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.147-157, 1994
この研究は,日本で有数な住宅地として発展を遂げた大阪・神戸間の地域を対象として,それがどのように発展してきたかを,多くの資料や地域の調査を行なうことによって明らかにすることを目的としている。まず,この地域が住宅地として発展した第1の理由は,大阪湾に臨んで北に山を負う恵まれた地形で,住宅地として最適な自然条件を備えていたこと,日本で2番目という大阪・神戸間の鉄道の開通(1874年)があり,さらに1905年に阪神電鉄,1919年に阪急電鉄が開通するなど,大都市間を結ぷ交通機関が整備されたこと,この沿線に私鉄が住宅地経営を積極的に行ない,郊外住宅地の発展に大きく貢献することとなった。また,大正時代には,芦屋市・西宮市で土地区画整理事業が盛んに行なわれ,宅地の供給が促進された。さらに民間土地会社の住宅地経営も計画され,現在の夙川,芦屋の六麓荘などが開かれている。これらの住宅地開発は,大都市の工業化が進み,空気の汚染や住環境の悪化によって,郊外住宅地が注目されるようになったものであるが,その状況は必ずしも良好な住宅地経営ぱかりではなかった。関西で優れた住宅地経営を目指した好例として,日本建築協会が大正11年(1922)に開催した住宅博覧会があり,このような動きに刺激されて,阪急電鉄では,新伊丹住宅地(1935),武庫之荘住宅地(1937)が,いずれも放射状の軸線を持つ住宅地経営で,良好な住環境を持つ住宅地が形成された。阪神間のなかで,住吉・御影地域(旧住吉村・御影町)も早くから住宅地として注目され,特に大邸宅が多く建てられた。なお,戦前に建てられた阪神間の中流住宅の意匠を見ると,和風要素を取り入れたものがかなり多く,これは関西人の住宅に対する考え方に,保守的な見方をする者が多かったからと言える。
1 0 0 0 OA 社会福祉における「個人の尊厳」の意義
- 著者
- 岩崎 晋也
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.4, pp.92-95, 2020-02-29 (Released:2020-05-23)
- 参考文献数
- 4
- 著者
- 坂口 由佳
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.290-310, 2013 (Released:2014-03-03)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2
本研究は, 自傷行為経験者の視点から, 自傷行為をする生徒たちに対する学校での対応を検討したものである。自傷行為経験者14名によって書かれたブログから学校の先生たちの対応に関する記事を抜粋し, グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いて分析を行った。その結果, 自傷行為をする生徒たちは先生からの対応について大きく2つの体験プロセスを経ていた。一つは《自傷行為をする生徒たちにとってサポートされたと感じる体験プロセス》であり, この体験を重ねる中で, 生徒たちは自傷行為をやめようと思えるようになっていく。もう一方は《自傷行為をする生徒たちにとって冷たく見放されたという形で体験がすすむプロセス》である。この体験を経ると, 自傷行為をする生徒たちは心を閉ざし, 先生たちとの関係を絶つようになる。一度つながったとしてもその後の先生たちの対応によっては容易に関係を切り, 一旦先生たちとの距離を置くようになるとサポートされたと感じる体験プロセスに戻ることはほとんどない。しかし, 先生たちからのこまめな声かけなど日常的なサポートを繰り返し受けることでサポートされたと感じるプロセスに戻っていくというルートが一つ認められた。
1 0 0 0 OA ソーシャルワークにおける尊厳概念をめぐって
- 著者
- 児島 亜紀子
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.4, pp.86-89, 2020-02-29 (Released:2020-05-23)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 忍藩阿部氏家臣団の形成
- 著者
- 根岸 茂夫
- 出版者
- 国史学会
- 雑誌
- 国史学 (ISSN:03869156)
- 巻号頁・発行日
- no.101, pp.p20-53, 1977-03
- 著者
- 秋山 幸
- 出版者
- 早稲田大学大学院日本語教育研究科
- 雑誌
- 早稲田日本語教育学 (ISSN:18823394)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.1-20, 2017-06-16
1 0 0 0 核分割コブラシャフトスパーテル
- 著者
- 吉富 文昭
- 雑誌
- 眼科手術 = Journal of ophthalmic surgery (ISSN:09146806)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.369-370, 2004-07-30
- 被引用文献数
- 4