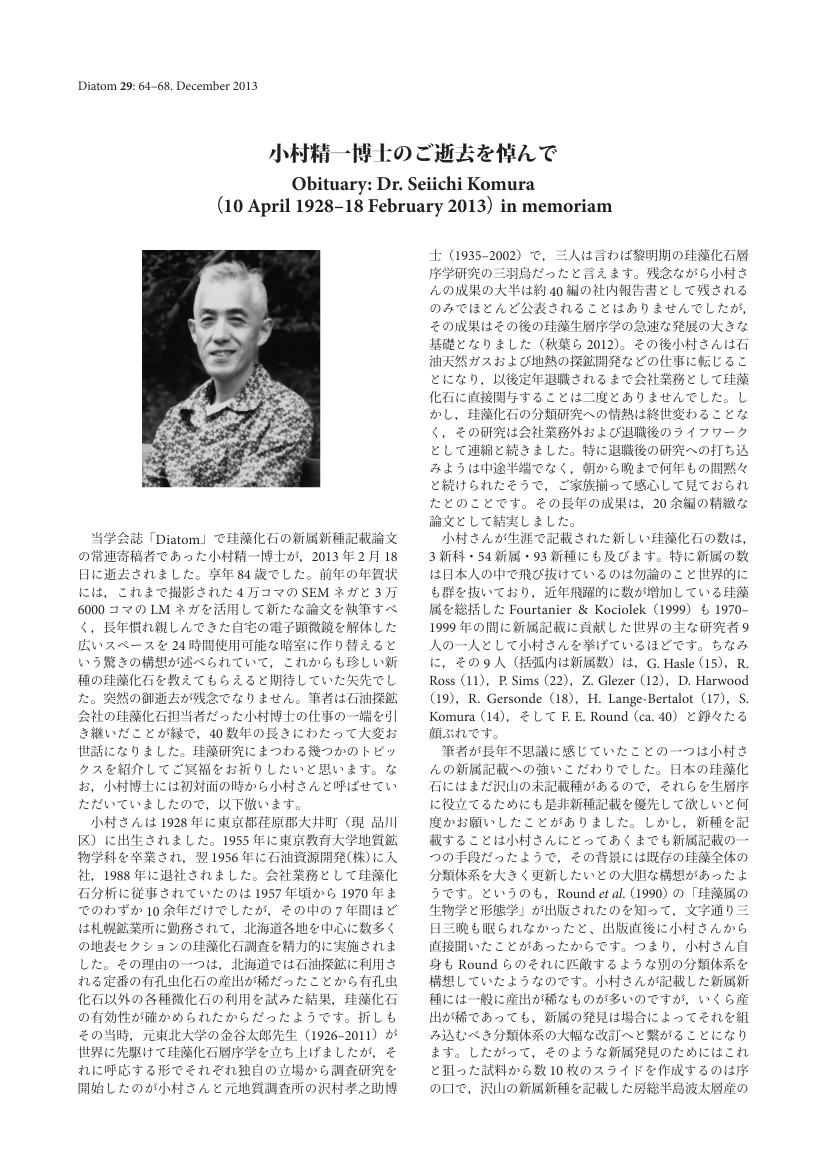1 0 0 0 OA 現代日本語における形容詞語幹の音韻構造について : 音素分布の分析と考察
- 著者
- 入江 さやか Sayaka Irie
- 出版者
- 同志社大学留学生別科
- 雑誌
- 同志社大学留学生別科紀要 = Bulletin of Center for Japanese Language Doshisha University (ISSN:13469789)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.31-40, 2004-12-25
現代日本語において,実際に用いられている形容詞を選出し,その語幹の音韻構造について調査した。4冊の国語辞書のうち,3冊以上の辞書に掲載されている形容詞を選出すると,ク活用形容詞452語,シク活用形容詞272語,合計724語である。そのうちの和語650語について,出現位置別に音素分布表を作成し,和語3拍名詞と比較すると,語頭に現れる母音音素,子音音素は,和語3拍名詞,和語形容詞ともにほとんど同じであった。ただし,和語形容詞語幹末の母音音素は,著しく偏った音素分布を見せる。すなわち,和語2拍名詞の場合は,/i/のあと,/a/ /e/ /o/ /u/と続く。和語3拍名詞の場合は,/i/のあと,次に多いのは,/e/であり,続いて/a/ /o/ /u/という順になる。名詞の場合は,/i/ /e/で終わるものが多いと言える。それに対し,形容詞語幹の場合は,/a/が最も多く出現し,/i/ /e/はほとんど出現しない。
1 0 0 0 IR 人はいつ人になるのか?--刑法から見た人の始期について
- 著者
- 塩見 淳
- 出版者
- 京都産業大学法学会
- 雑誌
- 産大法学 (ISSN:02863782)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.259-240, 2006-11
1 0 0 0 IR 胎児手術と人の始期
- 著者
- 滝本 良太
- 出版者
- 早稲田大学社会科学学会
- 雑誌
- 早稲田社会科学総合研究. 別冊, 2010年度学生論文集 (ISSN:13457640)
- 巻号頁・発行日
- pp.163-171, 2011-06-25
1 0 0 0 水温落差は副交感神経活動を促通する
- 著者
- 西山 保弘 工藤 義弘 矢守 とも子 中園 貴志
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.A1O2003, 2009
【目的】<BR> 本研究では温浴と冷浴との温度の落差が自律神経活動や体温に与える影響を検討したので報告する.<BR>【方法】<BR> 文書同意を得た健常男性5名(平均年齢23.8±4.91歳)に温浴41°Cと冷浴15°Cならびにその両方を交互に行う交代浴の3つの部分浴を実施した.交代浴の方法は水関らの温浴4分,冷浴1分を4回繰り返し最後は温浴4分で終わる方法に準じた.温浴のみは計20分、冷浴のみは計10分浸漬した.安静馴化時から部分浴終了後120分間の自律神経機能、舌下温度、血圧、心拍数、動脈血酸素飽和度、手足の表面皮膚温を検出した.測定間隔は安静馴化後、施行直後、以下15分毎に120分までの計7回測定した.表面皮膚温度は、日本サーモロジー学会の測定基準に準じサーモグラフィTH3100(NEC三栄株式会社製)を使用した.自律神経機能検査は、心電計機能を有するActivetracer (GMS社製 AC301)を用いて被検者の心拍変動よりスペクトル解析(MemCalc法)を行いLF成分、HF成分を5分毎に平均値で計測した.統計処理は分散分析(one way ANOVA testと多重比較法)を用いた.<BR>【結果】<BR> 副交感神経活動指標であるHF成分は、交代浴終了後60分以降より有意差をみとめた(P<0.05).温浴と冷浴は終了後60分で変化が一定化し有意差は認めなかった.交感神経活動指標とされる各部分浴のLF/HF比は、温浴と冷浴は変化が少なく交代浴は終了後60分から低下をみたが有意差は認めなかった.舌下温度は、交代浴と温浴(P<0.01)、交代浴と冷浴(P<0.01)、温浴と冷浴(N.S.)と交代浴に体温上昇を有意に認めた.表面皮膚温にこの同様の傾向をみた.最高血圧は、交代浴と温浴(P<0.01)、交代浴と冷浴(P<0.01)、温浴と冷浴(P<0.01)で相互に有意差を認め交代浴が高値を示した.<BR>【考察】<BR> 交代浴と温浴および交代浴と冷浴の相異はイオンチャンネル(温度受容体)の相異である.温浴は43°C以下のTRPA4、冷浴は18°C以下のTRPA1と8°Cから28°CのTRPM8、交代浴はこのすべてに活動電位が起こる.もう一つは温度幅である.温水41°Cと冷水15°Cではその差は26°C、体温を36°Cとすれば温水温度とは5°C、冷水温度とは21°Cの温度差がある.この温度幅が交代浴の効果発現に寄与する.単温の温浴や冷浴より感覚神経の刺激性に優れる理由は,温浴の41°Cと冷浴の15°Cへの21°Cの急激な非侵害性の温度差が自律神経を刺激しHF成分変化を引き起こす.また交代浴の体温上昇からは、温度差は視床下部の内因性発熱物質(IL1)を有意に発現させたことなる.<BR>【まとめ】<BR> 温度落差が自律神経活動に及ぼす影響は、単浴に比べ体温を上昇させること、副交感神経活動を一旦低下を惹起し、その後促通するという生理的作用に優れることがわかった.
1 0 0 0 OA 小村精一博士のご逝去を悼んで
- 著者
- 秋葉 文雄
- 出版者
- 日本珪藻学会
- 雑誌
- Diatom (ISSN:09119310)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.64-68, 2013-12-31 (Released:2013-12-19)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 音楽とスポーツ文化の関連に関する研究
- 著者
- 三小田 美稲子
- 出版者
- 国士舘大学体育学部附属体育研究所
- 雑誌
- 国士舘大学体育研究所報 = The annual reports of health physical education and sport science (ISSN:03892247)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.21-26, 2018-03-31
This study examined the effectiveness and forms of activities in which music and sports can intermingle and merge. Various forms of activities were compared, and their characteristics and ways in which music and sports were linked were examined. Findings were as follows: new approaches such as combined events or the concept of "play" are needed as a way to link music and sports. Appropriate facilities need to be provided and leaders who will implement and promote these new approaches need to be trained.
1 0 0 0 繊維法令通牒集報
- 著者
- 通商産業省通商繊維局 編
- 出版者
- 繊維年鑑刊行会
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和23年, 1900
1 0 0 0 麻酔中における呼吸シグナル行動の神経性調節機構の解明
平成14年度における研究成果は以下の通りである。1)経口麻酔前投薬としてのセロトニン1A受容体作動薬タンドスピロン:セロトニン1A受容体作動薬タンドスピロンを麻酔前投薬に用いることによって、鼓室形成術後の悪心嘔吐を抑制することが判明した。2)吃逆の系統発生学的起源:パリ、カルガリーの研究者と吃逆の系統発生学的起源について討論を行った。数多くの類似点を有することから、吃逆の系統発生学的起源は鰓呼吸であるという仮説を論文として作成した。この論文は雑誌BioEssaysに掲載された直後に雑誌New Scientistで紹介され、その後は英国BBC、オランダのテレビ放送などで取り上げられ、反響を呼んでいる。3)GABAの相反する吃逆への作用:ペントバルビタール麻酔ネコにおいて背側鼻咽頭部の機械的刺激による吃逆様反射がイソフルラン吸入によっていかなる影響を受けるかを検討した。GABA-A、GABA-B受容体の拮抗薬を中枢もしくは末梢投与することによって、イソフルランは吃逆様反射を中枢、末梢両方のGABA-A受容体を介して促進、GABA-B受容体を介して抑制することが判明した。この実験結果にかんしては、American Society of Anesthesiologistsの年次大会(オーランド)で発表し、現在論文投稿中である。4)全身麻酔導入時の咳、欠伸:日常の臨床において、フェンタニル静注による咳、チオペンタール静注による欠伸を免疫学的に検討した。前者はAmerica Society of Anesthesiologistsの年次大会(オーランド)、後者はAmerica Thoracic Society国際学会(シアトル)で発表し、今後、論文作成に向かう予定である。
1 0 0 0 OA アメリカにおける戦後の異文化研究
- 著者
- 菊地 敦子 福井 七子
- 出版者
- 関西大学外国語学部
- 雑誌
- 関西大学外国語学部紀要 = Journal of foreign language studies (ISSN:18839355)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.55-77, 2018-03
This section of An Anthropologist at Work that we are translating includes the chapters, "The Postwar Years: The Gathered Threads" by Margaret Mead and "Recognition of Cultural Diversities in the Postwar World" by Ruth Benedict. Both of these papers describe the urgent need after the war for Americans to understand the cultures of the countries that they defeated in the war and that they were now to occupy. Benedict felt this urgency more than anyone else. She wanted to make sure that the Americans understood the Japanese people and made their decisions wisely. She wrote the book Chrysanthemum and the Sword for this purpose. Benedict's commitment to seeking world peace by understanding ways in which other people live their lives is described in "Recognition of Cultural Diversities in the Postwar World". In "The Postwar Years" Mead describes somewhat bitterly, how after the death of Franz Boas, Benedict worked on the book Chrysanthemum and the Sword almost secretly without consulting her colleagues. The book was a huge success and offers of funding poured in, allowing Benedict to apply her analysis of national character to other countries. This research took Benedict to Europe. But on her return to New York Benedict passed away.
1 0 0 0 OA [書見台] 南アフリカの図書館 : ローズ大学コーリー図書館を中心に
- 著者
- 北川 勝彦
- 出版者
- 関西大学図書館
- 雑誌
- 関西大学図書館フォーラム = Kansai University Library forum (ISSN:13420828)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.3-7, 2012-03-31
1 0 0 0 OA 科學的價値に對する疑問(<特集>ルース・ベネディクト『菊と刀』の與えるもの)
- 著者
- 和辻 哲郎
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.4, pp.285-289, 1950 (Released:2018-03-27)
What makes the reviewer sceptical of the scientific value of The Chrysanthemum and the Sword consists not in the misunderstandings found in the data themselves which the author has used, but in the inadequate treatment of these data. The auther arrives at over-generalized conclusions on the basis of partial data, and very often makes judgements about the character of the Japanese people in general from such propaganda as the no-surrender principle or the superiority of spiritual to physical power, which were believed only by a small part of militarists for a definite time, or which these militarists made use of for their struggle within the country. Of course, there is another question, which Ruth Benedict has not fully taken into consideration, of why the Japanese people so meekly suc-cumbed to the dictatorship of a militarist clique. It is in this question that we should seek a key to the patterns of Japanese culture. The Japanese can perceive very clearly what elements in their culture are new and functional and what are antiquated and non-funtional, whereas to most foreigners these cultural elements appear to co-exist side by side with equal functional significance. Therefore it strikes the Japanese as queer that Benedict accepts certain nolonger-influential thoughts or customs of the past as characteristic of the present-day Japanese culture. For example, the reviewer's own experience for the past half-century contradicts both in social and family life what the author has called "the Japan's confidence in hierarchy".
1 0 0 0 OA 国際子ども図書館の窓
- 著者
- 北川 そら Sora Kitagawa
- 雑誌
- KGPS review : Kwansei Gakuin policy studies review
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.17-24, 2020-03-31
1 0 0 0 台風等の気象リスクを低減する飼料作物栽培の取り組み —はじめに—
1 0 0 0 OA 価格品質理論における最大利潤への調整過程と最適化
- 著者
- 山下 景秋 Kageaki YAMASHITA
- 出版者
- 和洋女子大学
- 雑誌
- 和洋女子大学紀要 = The journal of Wayo Women's University (ISSN:18846351)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, pp.113-121, 2021-03-31
In this paper, I consider the quality of products and agricultural products by setting the cost of producing quality (quality cost) and the number of sales as a result of quality. Since the number of sales is a function of price and quality cost, I consider that the profit of a company (farmer) is a function of price and quality cost. In this paper, in order to achieve maximum profit, there are three adjustment methods: (1) price adjustment, (2) average variable quality cost adjustment, and (3) price and average variable quality cost adjustment. The route by which profits are achieved is shown graphically. Based on this, I considered when and by what adjustment these three maximum profits would be achieved.
1 0 0 0 OA サウジアラビアの沙漠地域に持続可能な緑化システムを構築するプロジェクト
- 著者
- サウジアラビア海洋性沙漠開発プロジェクト緑化・生物
- 出版者
- Japanese Society for Root Research
- 雑誌
- 根の研究 (ISSN:09192182)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.13-16, 2007-03-26 (Released:2009-12-18)
- 参考文献数
- 4