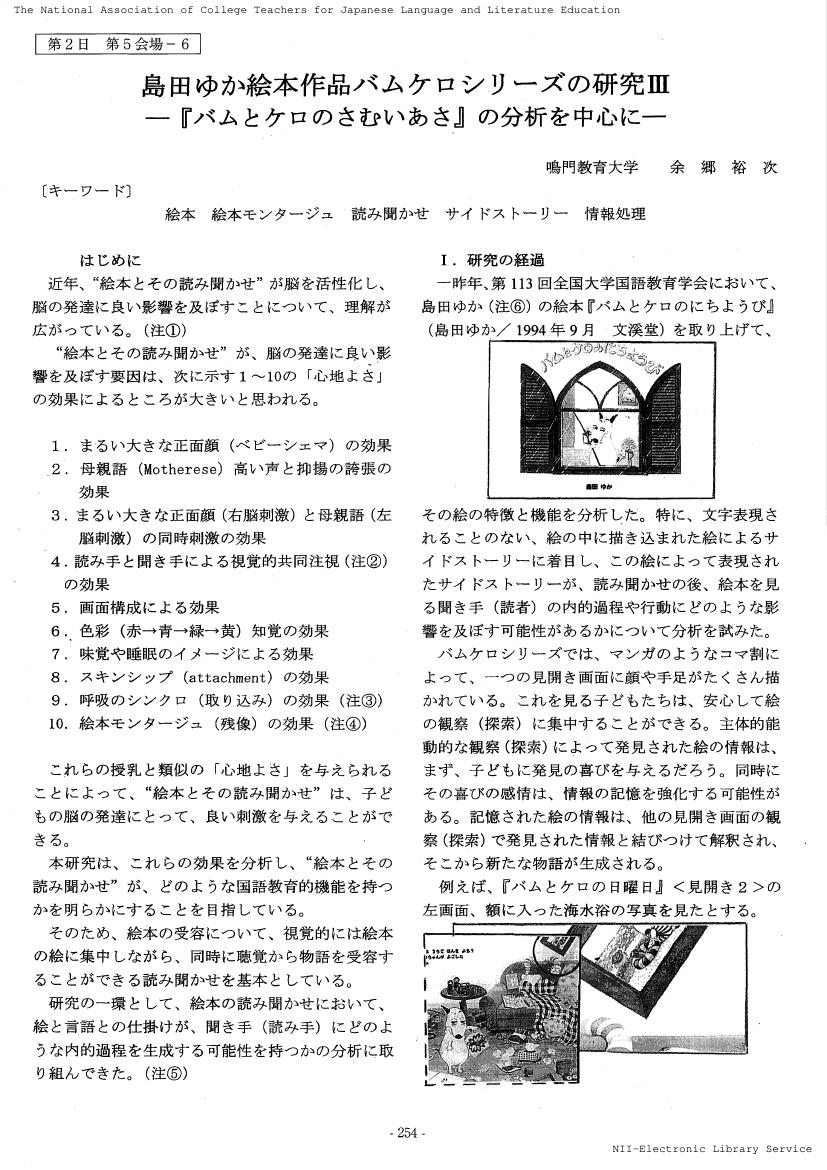1 0 0 0 翻訳・非翻訳小説における女ことば : 文末詞使用と読者受容
- 著者
- 古川 弘子
- 出版者
- 日本通訳翻訳学会
- 雑誌
- 通訳翻訳研究 (ISSN:18837522)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.93-111, 2017
1 0 0 0 OA クモを襲うクモ
- 著者
- 中平 清
- 出版者
- 日本蜘蛛学会
- 雑誌
- Acta Arachnologica (ISSN:00015202)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.1-2, 1960-03-10 (Released:2008-12-19)
1 0 0 0 OA 明治中期における少年非行への対応 ― 石井十次と留岡幸助の「実践」の意義 ―
- 著者
- 田中 和男 Kazuo Tanaka
- 出版者
- 同志社大学人文科学研究所キリスト教社会問題研究会
- 雑誌
- キリスト教社会問題研究 = The Study of Christianity and Social Problems (ISSN:04503139)
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.132-178, 1998-01-20
論説
1 0 0 0 OA 悪性腫瘍に伴う消臭対策:メトロニダゾールゲルの使用を試みて
1 0 0 0 OA 上顎癌・膀胱癌患者の腫瘍臭について
- 著者
- 鷺 真琴 永井 幹子
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会学術総会抄録集 第54回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- pp.210, 2005 (Released:2005-11-22)
【はじめに】 悪性腫瘍の臭気コントロールにおいて、現在までにいくつかの科学的・物理的方法で消臭効果が得られていることが分かっている。しかし頭頚部・膀胱の癌は再発・再燃を繰り返し、皮膚表面に露出するケースが少なくない。今回2つの事例で一時的に消臭効果はみられても、自壊しはじめた腫瘍と強くなる臭いに対して、薬剤やケアを試みた事例を紹介する。【目的】腫瘍臭における臭気コントロール【患者紹介】<事例1>患者 膀胱腫瘍 膀胱腫瘍浸潤に伴う膣・直腸瘻経過 腹部から腰部にかけての疼痛があったため、MSコンチン内服にて疼痛コントロールを行っていた。陰部(大陰唇)腫瘍から膿様滲出液と出血があった。膿様滲出液は便や帯下と混入することにより悪臭を伴った。<事例2>患者 左上顎腫瘍経過 平成12年より左上顎癌を発症し、左上顎洞開洞術・動注・放射線療法施行し、外来にてフォローしていた。しかし平成16年腫瘍への感染あり、左眼下部より膿汁流出、涙丘部より腫瘍が突出・増大し悪臭を伴った。看護問題事例1 腫瘍と排液の混入に伴う悪臭事例2 腫瘍増大・腐敗に伴う悪臭【看護の実際】病室に消臭剤設置腫瘍部にゲンタシン軟膏塗布事例1:対処療法 出血時硝酸銀焼灼 陰部洗浄・オムツ交換事例2:薬剤使用による対応とケア(1)ダラシンTゲル(2)フラジール軟膏+マクロゴール【実際と効果】 事例1では硝酸銀焼灼による止血によって血液の酸化臭が一時的に消失した。しかし、膿様滲出液や便・帯下が常時排泄されていたため、悪臭が消えることはなかった。 事例2においては(1)剤ではゲル状であったため、腫瘍部には不適切であった。(2)剤では臭気コントロールが行なえ一時退院が出来たが、再入院時には腫瘍の腐敗が進み消臭効果が減退していた。【考察】 腫瘍の増大に伴う腫瘍臭に対し対処的に関わったが、結果として長期的な効果が得られなかった。臭気についての分析が不十分であり、また患者自身も臭気に対して無頓着であったこと、腫瘍により臭覚が麻痺していたことで、快・不快が不明であった。今回は家族と看護師の臭覚で消臭効果を判断したが、臭気の程度については尺度を用いて評価すべきだった。【おわりに】 患者の最期を不快な感情を持たずに迎えるようにするには、臭気の分析と管理、適切な看護介入について見当が必要である。
- 著者
- 小野 浩
- 出版者
- 労働政策研究・研修機構
- 雑誌
- 日本労働研究雑誌 (ISSN:09163808)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.12, pp.15-27, 2016-12
長時間労働の是正は働き方改革の最優先課題である。労働時間を減らし,仕事と生活が両立できるような働き方を実現させるため,国は政策・法律を施行し,企業は報酬制度,インセンティブを改めるなど試みを重ねてきた。しかし日本の正規労働者の総労働時間は1990年代から一向に減っていない。本稿では長時間労働問題の本質は,政策や法制度といった「見える」ところではなく,社会規範や雇用慣行に埋め込まれた「見えにくい」ところにあると考える。長時間労働問題の説明力を高めるには,報酬・評価制度などを取り入れた経済学的アプローチと同時に,社会的コンテクストを考慮したより社会学的な考察が必要だ。長時間労働は日本的雇用慣行の制度補完性とその背景にある文化的特性が生みだした副産物である。問題の原因としては,インプット重視社会,シグナリングに頼る雇用慣行,働き方に組み込まれた集団意識と上下関係,内部労働市場,曖昧な職務内容,男女間性別分業といった要素を明らかにする。最後に,長時間労働を減らすにはどうすべきかを考える。
1 0 0 0 ダンス・セラピー : こころの健康と"踊り"
- 著者
- 鍛冶 美幸
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 = Journal of the Society of Biomechanisms (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.66-70, 2006-05-01
- 参考文献数
- 17
宗教儀式や祭事における巫女の舞,集落での集団の踊りなど,"踊り"は古来より人々の生活のなかにあり,人々の心をつなげ,神と通じる重要な活動であった.近代に入り身体と精神を分析的に区別してとらえる視点が広く定着し,精神生活と"踊り"は徐々に切り離されていく傾向があったが,昨今あらためて身体と精神の不可分性を唱え両者の統合を重視する視点が注目されている.本稿で紹介するダンス/ムーブメント・セラピーは,ダンスや動作を用いて統合体としての心身の機能回復・向上を目指す心理療法である.身体活動を通じた直接的な自己表現や心理的体験,人とのふれあいによってぬくもりを体感する機会が乏しくなっている現代において,"踊り"によってもたらされる交流と,芸術的で象徴的な表現/体験の機会の獲得は再び重要な心理社会的役割を担う可能性をもつのであると考えられる.
- 著者
- Shimada Takau
- 出版者
- 専修大学学会
- 雑誌
- 専修商学論集 (ISSN:03865819)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, pp.31-38, 2008-07-18
1 0 0 0 OA 1,000万倍に達するホヤのバナジウム濃縮 直接か間接か
- 著者
- 植木 龍也 ロマイディ
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.299-300, 2017-04-20 (Released:2018-04-20)
- 参考文献数
- 5
- 著者
- 余郷 裕次
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 全国大学国語教育学会国語科教育研究:大会研究発表要旨集 117 (ISSN:24321753)
- 巻号頁・発行日
- pp.254-257, 2009-10-17 (Released:2020-07-15)
1 0 0 0 OA 絵入都々逸辻占八卦
- 著者
- 黒坂重助 (南北) 著
- 出版者
- 電雲堂
- 巻号頁・発行日
- 1887
1 0 0 0 OA 新発見の『逸見(へみ)古歌抄』とその周辺の研究 : 千百餘年間不明だった和風軍歌
1 0 0 0 IR 平安時代の儀軌訓読に於ける音義の利用 : 仁和寺蔵金剛頂経一字頂輪王儀軌音義を中心に
- 著者
- 安岡 武紀
- 出版者
- 久留米医学会
- 雑誌
- 久留米医学会雑誌 (ISSN:03685810)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.1, pp.14-22, 2011-02
1 0 0 0 OA 抗体開発のための抗原抗体相互作用解析
- 著者
- 津本 浩平
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.5, pp.412-423, 2013-11-25 (Released:2014-03-01)
- 参考文献数
- 47
抗体はその高い抗原特異性、親和性から、治療薬、診断薬に用いられており、各分野で抗体開発が盛んに行われている。抗体配列遺伝子が手に入れば、我々は、その抗体が持つ機能を認識素子として利用し、さまざまな改変抗体を構築することができるようになっている。しかしながら、抗体がどのように抗原に対して高い特異性・親和性を創出するかについて、構造的に、またエネルギー的に理解されるようになったのはごく最近のことである。本稿では、抗原抗体相互作用を生物物理学的にどのように性格づけするかについて、まず、代表的な解析方法についてまとめ、つづいて抗体が標的分子をどのように認識し、高親和性を創出しているかについて述べる。