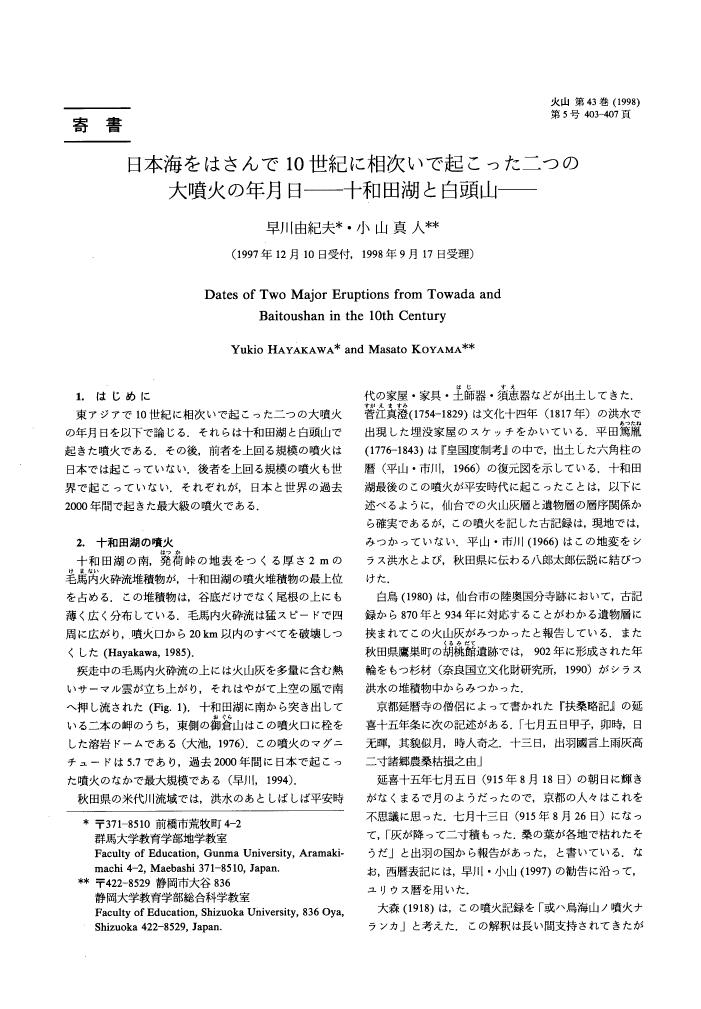165 0 0 0 OA 草津白根火山の噴火史
- 著者
- 早川 由紀夫 由井 将雄
- 出版者
- Japan Association for Quaternary Research
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.1-17, 1989-05-31 (Released:2009-08-21)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 22 23
The eruptive history of the Kusatsu Shirane volcano is well described by means of 14 beds of key tephra and intercalating loess soil. Three eruptive stages are recognized. During early or middle Pleistocene the Matsuozawa volcano was formed; this is the first stage. The second stage was initiated by effusion of the Horaguchi lava, which was followed by eruptions of the Oshi pyroclastic flow, older lava flows, 3P pumice fall, and Yazawahara pyroclastic flow. Brown loess soil about 10m thick covering these deposits indicates that a dormant period of more than 100, 000 years followed this stage. The summit area upheaved about 400m or more against the foot of the volcano during this period, as is suggested by the extraordinarily steep (6.1°-3.0°) surface of the Oshi ignimbrite plateau. The third stage, which started about 14, 000 years ago, is the formation of three pyroclastic cones on the summit and contemporaneous effusion of the younger lava flows, e. g. the Kagusa lava of 7, 000 years ago and the Sessyo lava of 3, 000 years ago. In historic times, phreatic explosions have frequently occurred on the summit crater, Yugama. This means that the present belongs to the third stage. It is unlikely that eruptions of the third stage are caused by cooling of the magma chamber which was active in the second stage. The activity of the third stage seems to denote arrival of a new magma chamber at shallow depth.
122 0 0 0 OA インターネットを活用した情報共有による新しい地学教育
福島第一原発の2011年3月事故によって大気中に放出された放射性物質は、短軸5km程度の楕円形をした霧のひとかたまりとして、地表から数十mまでの高さを速さ2~6m/sでゆっくり移動した。放射性物質の大量放出は大きく分けて3回あった(3月12日、15日、20-21日)。放射性物質はグローバルに広がったが、その6割が日本列島上に降り注いだ。大気中に放出されたセシウム総量は1京1000兆ベクレル。チェルノブイリ原発事故の1/12だった。原発事故に際して、以上の地学的知見をインターネットを利用してツイッターやブログですみやかに発信し、広く情報共有した。
99 0 0 0 OA 多環芳香族炭化水素から見た海洋油汚染
- 著者
- 早川 和一・鳥羽 陽・亀田 貴之 鈴木 信雄
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.85-92, 2011-04-15 (Released:2016-08-31)
- 参考文献数
- 15
今から14 年前の冬,日本海でタンカーが沈没し,流出したC-重油が日本海側沿岸に大量に漂着した.それまで原油の回収に効果を発揮した手法や機材も,原油より遥かに粘度が高いC-重油には殆ど機能せず,回収は人力作業に頼った.漂着した油は,岩や礫・石の海岸,特に手前に岩礁を有する遮蔽海岸に長期残存する傾向があった.C-重油に含まれる多環芳香族炭化水素類を指標にして,油の異同識別や汚染状況の把握が行われた.C-重油で汚染した海水を清浄海水に混ぜてヒラメの卵を飼育したところ,孵化した稚魚に脊柱彎曲が現れた.酵母two-hybrid 法を適用して調べた結果,水酸化多環芳香族炭化水素の中に強い攪乱作用を有する化合物があり,さらに構造活性相関があることがわかった.また,最近,日本海の多環芳香族炭化水素類の汚染の現状調査を開始した.
90 0 0 0 OA 日本海をはさんで10世紀に相次いで起こった二つの大噴火の年月日 : 十和田湖と白頭山
- 著者
- 早川 由紀夫 小山 真人
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山 (ISSN:04534360)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.5, pp.403-407, 1998-10-30 (Released:2017-03-20)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 9
52 0 0 0 OA 査読の作法
- 著者
- 早川 智
- 出版者
- 日本大学医学会
- 雑誌
- 日大医学雑誌 (ISSN:00290424)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.4, pp.207-211, 2019-08-01 (Released:2019-09-20)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
Peer review system is one of the most important processes to secure objectivity in sciences. Manuscripts submitted by any author, even if he or she is new comer or veteran, must be read critically by other scientists who have enough experience and extensive knowledge on related fields. While any person such as self-proclaimed scientists can publish their “new discoveries” in blogs, general books and/or open access predatory journals without undergoing review and editing process, their findings offer very little scientific information and occasionally cause health problems. Critical reading and reviewing scientific manuscripts takes times and efforts for scientists who would like to spend their own precious time for clinical or research activities. However any member of scientific community has moral obligations to read critically unpublished manuscripts as well as published ones in order to reach better scientific truth. In this sense, it is important to learn authentic manner to review manuscripts. For young scientists, peer-review experiences are also useful for responding to peer-reviewed opinions against their own manuscripts.
50 0 0 0 OA 成人における麻疹・おたふくかぜ・風疹混合(MMR)ワクチンの 安全性と副反応
45 0 0 0 OA 伊豆大島火山カルデラ形成以降の噴火史
- 著者
- 小山 真人 早川 由紀夫
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.2, pp.133-162, 1996-04-25 (Released:2009-11-12)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 17 17
We reveal the detailed syn-and post-caldera eruptive history of Izu Oshima Volcano, Japan, by tephra and loess stratigraphy. Twenty-four tephra layers, which overlie the slope outside the caldera, show that 24 eruptions occurred since the formation of the caldera (about 1, 450 years ago). These eruptions are separated by 10-200 years clear dormant periods, which can be identified by eolian dust (loess) interbedded with tephra layers. The 24 eruptions can be classified into three types : 1) eruption with scoria and ash falls (12 eruptions), 2) eruption only with scoria falls (7 eruptions), and 3) eruption only with ash falls (5 eruptions). While tephra discharge mass of the type 1 is generally large (1.5×1010 to 7×1011 kg), that of the type 2 or 3 is small (0.6 ×109 to 1 ×1011 kg). The 1986 eruption is classified into the type 2. Debris avalanches, which occurred just before the caldera formation and covered almost all of the Izu Oshima island, demonstrate that the present caldera wall was formed by slope failure of an old edifice. The tephra-discharge stepdiagram, which shows a relationship between time and cumulative discharge volume / mass of magma, shows : 1) the average tephra-discharge rate is constant (92 kg/ s before the N1.0 eruption and 25 kg/s after the N1.0 eruption), showing an abrupt decrease of the rate at about the time of the N1.0 eruption, which occurred about 900 years ago and was the most voluminous eruption for the past 1, 450 years, 2) both before and after the N1.0 eruption, the type 1 eruption shows volume-predictability, that is, the discharge volume / mass of a next type 1 eruption can be predicted, 3) a type 1 eruption should occur sometime in the future again, and when it occurs, the discharge mass of tephra should attain to as much as 2×1011 kg or more.
44 0 0 0 IR 中世後期日本貨幣史の再構築―地方史とアジア史の観点から―
42 0 0 0 OA 2型糖尿病における短期強化インスリン療法による糖毒性解除の評価―未治療患者と既治療患者の比較―
- 著者
- 中島 弘二 田邉 昭仁 岡内 省三 早川 尚雅 久野 裕輝 高田 景子 元佐 慶子 小西 由記 羽井 佐裕子 桶口 三香子 萬納寺 聖仁 矢部 博樹 大本 明義 三澤 眞人
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.8, pp.551-559, 2013 (Released:2013-09-07)
- 参考文献数
- 29
HbA1c(NGSP)8.4 %以上の174名の2型糖尿病患者に9日間の短期強化インスリン療法(Short-Term Intensive Insulin Therapy以下STIIT)を行い糖毒性解除の解析をした.STIIT後ボグリボース・メトホルミンを基本薬とする未治療群74名・既治療群64名(以下未群・既群)の2年間の効果を比較した.STIITは血糖値,高感度CRP, HOMA-IR, HOMA-βを有意に改善した.STIIT前(以下前)HbA1cが前_血糖値に正相関し,前_HOMA-βおよび糖尿病罹病期間(以下罹病期間)に逆相関した.STIIT施行3ヶ月後のHbA1cは罹病期間に正相関し,患者本来の糖尿病状態を反映した.未群のほうがHbA1cは高いが6ヶ月後のHbA1c 6.9 %未満達成率は有意に高かった(未群66 %,既群30 %).多重ロジスティック回帰分析で未群・既群と罹病期間は独立してHbA1cの目標達成に貢献した.既群でコントロール不良な患者のなかにもβ細胞機能が温存された例もあった.コントロール不良患者では早期に糖毒性を解除しβ細胞に負担をかけない治療で糖毒性を再発させないことが大切である.
40 0 0 0 原爆被爆者の骨髄異形成症候群(MDS)に関する疫学的、分子生物学的研究
原爆被爆者の高令化に伴い、骨髄異形成症候群(MDS)の増加がみられているが、当血液内科において過去15年間に診断されたMDSの病型診断を確定し、個人線量は当研究所の開発したABS93Dを用いてCox比例ハザードモデルにより統計学的解析を行った。その結果、個人被爆線量が得られたMDS例は26例であり、被曝線量反応関係を明らかにした。すなわち1 Sv被爆の0 Sv被爆に対する相対リスクは2.4であり、被曝線量反応関係に影響する因子として、被爆時年令を明らかにした。被爆者MDSの遺伝子レベルでの異常を明らかにするため、分化型急性骨髄性白血病の原因遺伝子として同定され、二次性白血病にも関与している可能性が指摘されている転写因子AML1遺伝子に注目し検索をすすめた。AML1遺伝子内のラントドメインの変異をPCR-SSCP及び塩基配列決定により検索したところ、非被爆者MDSでは74症例中2例(2.7%)に変異が認められ、これまでの報告と同程度の頻度であった。しかし、原爆被爆者で低線量被曝を受けたと推測されるMDSにおいては、13症例中6例(46%)と高頻度に点突然変異が認められた(ミスセンス3例、ノンセンス1例、サイレンス2例)。これらの点突然変異体について二量体形成能、DNA結合能、転写活性能についての解析を実施した。これらの結果より放射線関連MDS/AMLにおいてAML1の点突然変異が関与していることが明らかになった。次にMDSの病態には遺伝的不安定性が関与していると考えられるが、患者の単核球について、4種類のDNA修復酵素の遺伝子(ERCC 1,ERCC 3,ERCC 5,XPC)発現を検討したところ、低下〜消失した症例を高頻度に認め、MDSの病態に関与することが示唆された。
40 0 0 0 OA リュウグウとメインベルト内帯の低アルベド小惑星族の可視スペクトル比較
- 著者
- 杉田 精司 巽 瑛理 長谷川 直 鈴木 雄大 上吉原 弘明 本田 理恵 亀田 真吾 諸田 智克 本田 親寿 神山 徹 山田 学 早川 雅彦 横田 康弘 坂谷 尚哉 鈴木 秀彦 小川 和律 澤田 弘崇
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2018年大会
- 巻号頁・発行日
- 2018-03-14
リュウグウの近接観測の本番が目前に迫っている。これに備えて、我々は3つの重要な準備を進めている。1) 低アルベド小惑星の可視スペクトルの見直し。2)リュウグウの地上観測スペクトルの解析とメインベル小惑星との比較。3)可視分光カメラONC-Tのスペクトル校正観測。本講演では、これらについて簡潔に紹介する。 まず、メインベルトの低アルベド小惑星のスペクトル解析である。先駆的な小惑星のスペクトルのサーベイ観測であるECAS(Tedesco et al.,1982)の後、地上望遠鏡による多バンド分光のSDSS(Ivezic et al. 2001)、地上望遠鏡のよる連続スペクトルのデータベースであるSMASS2の整備(Bus and Binzel, 2002)、天文衛星WISE/NEOWISEによる多バンド分光のデータベース(Masiero et al. 2011)など多数の強力な小惑星のスペクトルのデータベースが整備されてきた。特に、SDSS やWISE/NEOWISEによって膨大な数がある小さな小惑星のスペクトルアルベドの分布が定量的に計測されたおかげで、RyuguやBennuが由来するメインベルト内帯の低アルベド族の分布については最近に大きな理解の進展があった。まず、以前にNysa族と言われていた族は、E型スペクトルのNysa族の中にF型(or Cb~B型)のPolana族とEulalia族が隠れていることが明らかになった。さらにPolana族とEulalia族は形成時期が古くて広範囲に破片を分布させており、ν6共鳴帯にも多くの1kmクラスの破片を供給していることが分かった。その一方で、より若いErigone, Klio, Clarrisaなどのぞくはずっと若いため、ν6共鳴帯への大きな破片の供給は限定的であることが分かってきた。この事実に基づいて、Bottke et al. (2015)はRyuguもBennuもPolana族由来であると推論している。 このようにSDSS やWISE/NEOWISEのデータは極めて強力であるが、0.7μmのバンドを持たないため、広義のC型小惑星のサブタイプの分類には適さない。その点、ECASは、小惑星スペクトル観測に特化しているだけあって0.7μmのバンドの捕捉は適切になされている。しかし、ECASではあまり多くのC型小惑星が観測されなかったという欠点がある。そのため、現時点ではSMASS2のデータが広義C型のスペクトル解析に適している。そこで、我々はSMASS2の中の広義のC型の主成分解析を行った。紙面の関係で詳細は割愛するが、その結果はCg, C, Cb, Bなど0.7μm吸収を持たないサブタイプからなる大クラスターと、Ch, Cghなど0.7μm吸収を持つサブタイプからなる大クラスターに2分され、両者の間にPC空間上の大きな分離が見られること、またこの分離域はPC空間上で一直線をなすことが分かった。この2大クラスターに分離する事実は、Vernazza et al. (2017)などが主張するBCGタイプがCgh, Chと本質的に異なる起源を持っていて水質変成すら受けていない極めて始源的な物質からなるとの仮説と調和的であり、大変興味深い。 これに引き続き、世界中の大望遠鏡が蓄積してきた23本のRyuguの可視スペクトルをコンパイルして、SMASS2と同じ土俵で主成分解析に掛けた。その結果は、Ryuguの全てのスペクトルがBCGクラスターに中に位置しており、その分布は2大クラスターの分離線に平行であった。これはRyuguが極めて始源的な物質であることの現れかもしれず、BCGクラスター仮説の検証に役立つ可能性を示唆する。 しかし、現実は単純ではない。Murchison隕石の加熱実験で得られたスペクトルもPC空間ではRyuguのスペクトルの分布と極めて近い直線的分布を示すのである。これは、Ryuguのスペクトル多様性がMurchison隕石様の物質の加熱脱水で説明できるとの指摘(Sugita et al. 2013)とも調和的である。この2つの結果は、Ryuguの化学進化履歴について真逆の解釈を与えるものであり、はやぶさ2の試料採取地の選択について大きな影響を与えることとなる。 この2つの解釈のどちらが正しいのか、あるいは別の解釈が正しいのかの見極めは、0.7μm吸収帯の発見とその産状記載に大きく依存する。もし、Murchison隕石様の含水鉱物に富む物質がRyuguの初期物質であって加熱脱水で吸収帯が消えただけの場合には、Ryugu全球が表面下(e.g., 天体衝突などで掘削された露頭)まで含んで完全に吸収帯を失ってしまうことは考えにくい。したがって、0.7μm吸収帯が全く観測されない場合には、VernazzaらのBCG仮説やFやB型の水質変成によってCh, Cghが生まれたと考えるBarucciらのグループの仮説(e.g., Fornasier et al. 2014)が有力となるかも知れない。しかし、0.7μm吸収が見つかって、熱変成を受けやすい地域ではその吸収が弱いことが判明すれば、スペクトル多様性は加熱脱水過程でできたとの考えが有力となろう。 最後に、はやぶさ2ONCチームは打ち上げ後も月、地球、火星、木星、土星、恒星など様々な天体の観測を通じて上記の観測目標を達成できるための校正観測を実施している。それらの解析からは、0.7μm帯および全般的なスペクトル形状の捕捉に十分な精度を達成できることを示唆する結果を得ており(Suzuki et al., 2018)、本観測での大きな成果を期待できる状況である。引用文献:Bottke et al. (2015) Icarus, 247 (2015) 191.Bus and Binzel (2002) Icarus, 158, 146.Fornasier et al. (2014) 233, 163.Ivezic et al. (2001) Astron. J.、 122, 2749.Masiero et al. (2011) Astrophys. J. 741, 68.Sugita et al. (2013) LPSC, XXXXIII, #2591.Suzuki et al. (2018) Icarus, 300, 341Tedesco et al. (1982) Astrophys. J. 87, 1585.Vernazza et al. (2017) Astron. J., 153,72
33 0 0 0 OA 人工地震の役割
- 著者
- 早川 正巳
- 出版者
- Tokyo Geographical Society
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.1, pp.27-47, 1972-02-25 (Released:2010-02-25)
- 参考文献数
- 7
人工地震・地震探査あるいは地震探鉱という言葉はすでに我々には耳なれたものであるが, 案外, その利用や現状については知られていないこともある。編集委員会からの要望に応えて, ここに筆をとつた。利用などかなり広範囲なので不充分な点があると思う。おゆるしいただきたい。上にしるした三つの言葉の意味は, 大体同じようなものであるが, はじめの方ほど広い意味ぐらいにとつてもらえばよかろう。本文でははじめの人工地震を用いることにする。人工地震はどのようにして発展してきたのであろうか, 最初は石油, 石炭などの地下資源をしらべることから始まつたのであるが, 次第にその応用も広まり, 更には地殻の構造解明にまで発展してきた。そのためには陸地のみならず, 海洋においての人工地震の技術が大いにあずかつて力となつたのである。ここではまず, 前半ではこれらの人工地震の歴史をひもとき, またその歴史と関連して, その技術の進歩が如何にその時々の関連学問, 技術の発展や社会情勢の影響をうけたかをふり返つてみる!後半では人工地震でしらべられる構造をその規模の大小に応じて, 小さな方から順次大きな方に実例を用いて説明してゆくことにする。
32 0 0 0 OA ミドリゾウリムシにおける細胞内共生研究の現状と課題
- 著者
- 早川 昌志 洲崎 敏伸
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.108-115, 2016-09-29 (Released:2016-10-17)
- 参考文献数
- 64
- 被引用文献数
- 1
ミドリゾウリムシは,共生クロレラと呼ばれる単細胞緑藻類を細胞内共生させている繊毛虫類の一種である。ミドリゾウリムシは,共生クロレラを除去する「白化」と,共生クロレラの「再共生」が容易に行えることから,細胞内共生研究における有用なモデル生物であり,以下のように多くの研究がなされている。ミドリゾウリムシには,宿主由来の共生クロレラのみだけでなく,別株や別種の宿主に由来する共生クロレラや,自由生活性の藻類,さらには酵母や細菌などの微生物も共生させることができる。共生クロレラに特徴的な生理学的特性として,外液が酸性の条件で細胞外にマルトースを放出する性質がある。共生クロレラはPV膜と呼ばれる生体膜によって近接して包まれており,PV膜の内部が酸性環境に維持されていると考えられており,共生と関連したクロレラからの糖の放出システムが構築されていることが予想されている。PV膜には宿主ミトコンドリアが密着・融合しており,細胞内共生において何らかの役割を果たしている可能性がある。ミドリゾウリムシは分子生物学的な研究は遅れているが,比較トランスクリプトーム解析などが行われており,共生と関連して発現が変動する遺伝子も報告されている。
30 0 0 0 OA 小児粉砕薬における医薬品含有量および損失の評価
- 著者
- 湧井 宣行 大久保 哲生 岩崎 雄介 伊藤 里恵 小林 岳 早川 和宏 三井 みゆき 矢野 裕一 斉藤 貢一 中澤 裕之
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.7, pp.425-430, 2011 (Released:2012-08-30)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 6 4
The pulverization of tablets for the preparation of pediatric medicines causes problems with respect to content uniformity and amount of the main ingredient. We compared these 2 factors in a pediatric medicine prepared by 2 methods: tablet grinding and tablet dilution. We also investigated causes of drug loss by means of high-performance liquid chromatography (HPLC).Three pharmacists prepared cortril powder by each method. When the main ingredient content was calculated by quantitative analysis by means of HPLC, there was no significant difference between the 2 methods, and adhesion to the mortar and the package were considered to be major reasons for drug loss.We also examined the effect of the amount of diluent on the loss of the main ingredient in the grinding process, finding that increasing the amount of diluent minimized the loss of the main ingredient content. When the amount of diluent per package was 1.5g, the main ingredient content was 90.8% (n=3).These results suggest that when dispensing small amounts of ground tablets, more attention should be paid to the amount of diluting agents than to the grinding technique.
28 0 0 0 OA 性はなぜあるのか―進化生物学の視点から
- 著者
- 早川 智
- 出版者
- 日本大学医学会
- 雑誌
- 日大医学雑誌 (ISSN:00290424)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.3, pp.126-128, 2013-06-01 (Released:2014-12-20)
- 参考文献数
- 7
Sexual reproduction evolved as a consequence of evolutionary requirement for diverse phenotypes that can cope with infectious parasites, which mutate much more rapidly than the hosts. Of great interest, we can understand complicated animal (and plant) behaviors as strategies to maximize their reproductive successes. Sexual selection was first advocated by Charles Darwin and is still regarded as one of the most important factors in intra-species evolution. In the present special issue, I have organized reviews of our recent understanding of sexual differentiation, sexual dysfunctions, sexual identity disorders, sexually transmitted infections and gender-related immune disorders. I appreciate the efforts of the contributors, all of whom are my old friends and colleagues, and dedicate this issue to my mentor, the late Dr. Susumu Ohno (1928-2000) who guided me to this field of reproductive genetics and immunology.
- 著者
- 早川 由紀夫
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山 (ISSN:04534360)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.177-190, 1995
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 24
Loam is an international scientific term, however, it has been used in a peculiar way in Japan. Japanese loam is a massive, brown, weathered rock unit composed of silt, clay, sand and occasional lapilli. It extensively covers coastal terraces, river terraces, ignimbrite plateaus and other uplands around volcanoes. Loam is not a product of soil forming process operated beneath the earth surface against rock bodies ; but it is a sediment accumulated slowly on the earth surface. Small-magnitude volcanic eruptions play a very minor role for the sedimentation. An eolian reworking process of pre-existing fine-grained deposits by the wind plays a major role. This is proved by following facts : 1) loam has accumulated even during the time when no ash-fall was observed ; 2) a volcano infrequently erupts explosively and the intensity of ash fallout is far lower than the sedimentation rate of loam ; it is about 0.1 mm/year ; 3) loam is hardly thickening toward a volcano. Very small particles carried from continental China by the westerlies at a high altitude are contained in loam, however, in the area around volcanoes their contribution is little for the formation of loam compared with eolian dust carried from nearby bare grounds by local winds at a low altitude. Loam does not accumulate all the year round. Just before and during fresh verdure, occasional strong winds pick up fine particles into the air from a bare ground which is dried up by a high-angle sunlight and high-temperatures. Eventually fine particles will settle down in vegetation. The most favorable season for loam deposition is April to May, in which more than half of an annual amount is achieved. It is convenient and practical to define a single eruption by a tephra layer which is not interbedded with loam. The thickness of loam can be used for the quantitative measurement of geologic time intervals, in years to thousands years, on certain conditions. Lithology of Japanese loam and the mechanism of sedimentation are identical to those of loess in other areas, such as China, northern Europe, northern America and New Zealand. There is no reason to hesitate to designate Japanese loam loess.
24 0 0 0 OA <論説>「鹿苑院殿厳島詣記」と「鹿苑院西国下向記」
- 著者
- 小早川 健
- 出版者
- 神戸市立工業高等専門学校
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:09101160)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.95-100, 1995-02-28
In the first year of Kooh, 1389,Ashikaga Yoshimitsu, third shogun of the Muromachi goverment, set out on a trip to Shikoku and the Chugoku disstrict, Western Honshu, paying a special visit to the Itsukushima Shrine. Imagawa Ryoshun, Chief Commissioner of Kyushu, attending the shogun on the trip, wrote Rokuon'in-dono Itsuhushima-mode-ki, as an account of their trip. This work seeks to show its high literary flavour, comparing all the details of this work with those of Rokuon'in Saigoku-geko-hi, another account of the same trip written by Mototsuna who accompanied the shogun as well.
22 0 0 0 火山噴火とその災害を三次元立体表示と動画でまなぶ学校内LAN教材の作成
当初は、CDなどのメディアで配布して学校内LANで使う火山教材を作成しようとしたが、回線やマシンスペックの性能向上が予想したより早く、インターネット上にコンテンツを置いて学校や家庭からユーザーにアクセスしてもらっても私たちの目的を十分達成することができるようになった。そのため予定を変更して、ユーザーにとって使いやすく、私たちにとって配布と更新が容易なポータルサイト「火山の教室」を作成した。http://vulcania.jp/school/ポータルサイトには、「子どものページ」への入り口と「先生のページ」への入り口がある。「子どものページ」は、「ニュース」「火山の学習」「火山がいっぱい」「電子掲示板」「リンク」からなる。「先生のページ」は、「ニュース」「授業素材」「研究レポート」「電子掲示板」「リンク」からなる。児童生徒と教諭はそれぞれのページを利用する。ただし他方のページを開くことを禁じてはいない。教諭は、授業で使う教材をここから選び出す。インターネットに接続して使っても良いし、手元に保存しておいてオフラインで使っても良い。児童生徒は、調べ学習などに利用する。作成したコンテンツのおもなものは、次のとおりである。・ウェブ紙芝居(おはなし編):「マグマのしんちゃん(鳥海山)」、「赤い岩のかけら(浅間山)」・ウェブ紙芝居(立体地形編):浅間山、阿蘇カルデラ、富士山・弁当パックで立体模型:各地の火山と震源分布・地震波シミュレーション:地震波形、縦波と横波、地震観測シミュレーション・生きている火山:噴火動画とライブカメラ・フィールド火山学:火山と噴火の体系的写真解説・見学案内:浅間山、草津白根山、富士山、伊豆大島
20 0 0 0 OA タイ米ネズミ混入流言の理論構造
- 著者
- 早川 洋行
- 出版者
- 滋賀大学教育学部
- 雑誌
- 滋賀大学教育学部紀要, 人文科学・社会科学・教育科学 (ISSN:05830044)
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.37-46, 1995
This paper is a study on "rumors of rats in Thai rice" in Japan. These rumors circulated in Japan in March, 1994. I have published two papers on theories of modern rumors. This paper is based on those theories. In thispaper I discuss the conditions and socio-psychological background in which the rumors occurred, what the functions of the rumors were and the relation between the rumors and the modern journalism in Japan. I pointed out that there were three conditions (objective, subjective and social)at that time which persuaded the people that the rumors were fact. There rumors were urban rumors, rumors people made up to confirm theirIn-group, and to develop and express an ideology. Also discussed is the fact that the rumors were cultivated by sensationalism in the mass media.
18 0 0 0 IR 『源平盛衰記』全釈(一五―巻五―2)
- 著者
- 早川 厚一 曽我 良成 近藤 泉 村井 宏栄 橋本 正俊 志立 正知 森田 貴之
- 出版者
- 名古屋学院大学総合研究所
- 雑誌
- 名古屋学院大学論集 人文・自然科学篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; HUMANITIES and NATURAL SCIENCES (ISSN:03850056)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.75-138, 2020-01-31