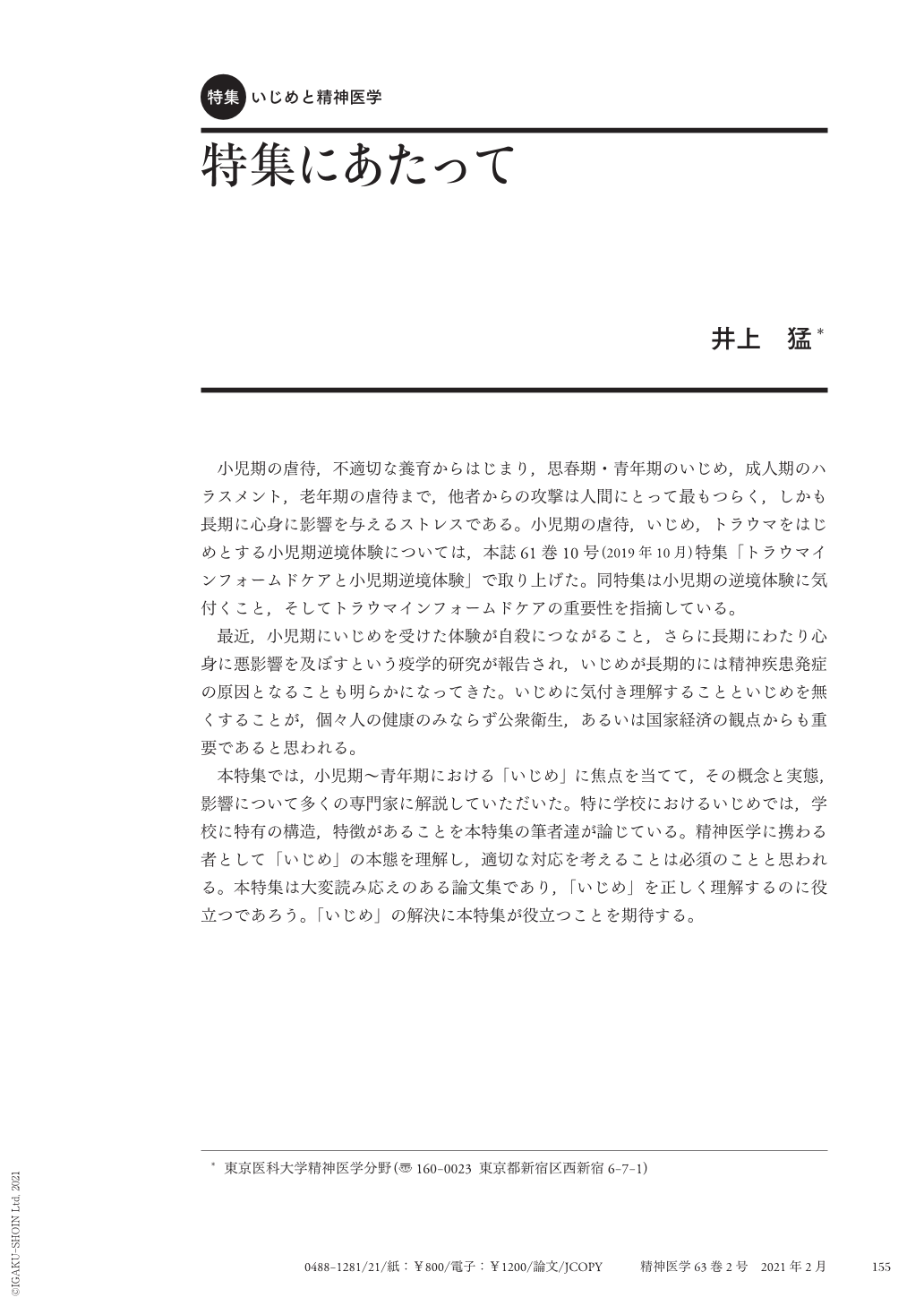- 著者
- 須田 智之 茂木 龍太 兼松 祥央 三上 浩司 近藤 邦雄
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.89-90, 2013
- 参考文献数
- 2
本研究では、キャラクターの中で特に重要とされる頭部に着目する。3Dキャラクターの頭部を変形させ、プロデューサーの意図したキャラクターの顔を効率的に作成し、任意の角度からも顔を見ることができるシステムを開発する。絵の描けないプロデューサーとデザイナーのコミュニケーションギャップを解消することを目的としている。
- 著者
- 倉島 宏明
- 出版者
- 日本病院薬剤師会
- 雑誌
- 日本病院薬剤師会雑誌 = Journal of Japanese Society of Hospital Pharmacists (ISSN:13418815)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.553-555, 2019-05
1 0 0 0 OA 2.Flash Glucose Monitoringについて
- 著者
- 廣田 勇士
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.12, pp.809-811, 2018-12-30 (Released:2018-12-30)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 街娼 : 実態とその手記
- 著者
- 竹中勝男, 住谷悦治 共編
- 出版者
- 有恒社
- 巻号頁・発行日
- 1949
1 0 0 0 OA 軍隊書簡文範
- 著者
- 四宮憲章, 安西鼎 著
- 出版者
- 東洋社
- 巻号頁・発行日
- 1902
1 0 0 0 ドイツの幹線鉄道網発達に伴う主要都市間の移動時間の特徴分析
- 著者
- 波床 正敏 吉村 晟輝
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.5, pp.I_991-I_1004, 2018
ドイツでは高速新線の開通にあわせて1991年にICEが運行開始され,在来線改良区間も活用しながら,現在ではほとんどの主要都市に対してICEのサービスが提供されている.本研究では,ドイツにおける高速新線建設や在来線改良に伴う影響を分析するため,日本の東海道新幹線開業とほぼ同時期の1963年以降概ね10年ごとに2015年までの6年次について,主要都市間の各種所要時間指標を計測し,その特徴を考察した.<br>その結果,広域的には東西ドイツ統一が都市間の所要時間変化に大きな影響を与えたこと,東西統一以前は速度向上と運行頻度や乗り継ぎ利便性向上がともに行われていたが,近年は運行頻度や乗り継ぎ利便性向上が重点的に実施されており,スイスのBahn 2000政策と同様の鉄道システムが導入されつつあることがわかった.
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)
- 巻号頁・発行日
- no.216, pp.66-69, 1998-09-25
パリのセーヌ川に架かるポン・デ・ザール(芸術橋)の理念を生かした橋を鴨川に架ける──。フランスのシラク大統領の提案から具体化したこの計画に,市民が「京都にフランスの橋は要らない」と反発。反対運動が全国規模に発展するなか,8月6日に突然,市長が計画を白紙撤回した。市長に振り回された感もあるこの顛末てんまつ,残された課題は何なのか。
1 0 0 0 OA 公共 Wi-Fi サービスを偽装した攻撃用アクセスポイントの検出
- 著者
- 大橋 翔 廣津 登志夫
- 雑誌
- 第79回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.1, pp.553-554, 2017-03-16
様々な施設で公共Wi-Fiサービスが運用されるようになった。不正に情報を取得するようなAP(偽装AP)の設置は容易であり、共施設の管理者は偽装APを即時に検出する必要がある。また、公共施設によって監視端末を配置する条件が異なる。既存手法ではイントラネットに監視端末を設置することで偽装APの検出を行っていた。しかし、イントラネットを経由しない偽装APの検出は不可能であった。本研究ではインターネット上に通信経路調査用サーバーを設置し、偽装APの接続形態に依存しない検出手法を提案する。各公共施設の配置条件に対応可能なAP監視網を小型端末で実装し、高密度監視網の実現を目指す。
1 0 0 0 OA <研究ノート>エヴァンキ族の祀る神の種類と偶像について
- 著者
- 汪 立珍 Wang Lizhen
- 出版者
- 筑波大学比較民俗研究会
- 雑誌
- 比較民俗研究 : for Asian folklore studies (ISSN:09157468)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.166-170, 2000-03-30
エヴァンキ族は、主として中国の内モンゴル自治区呼倫貝爾盟に分布している。1992年に行われた中国の人口調査によると、全国のエヴァンキ族の”エヴァンキ”という言葉は、この民族の自称であり、”山から降りた人”、或いは”山から降りてきた人達”という意味である。・・・
1 0 0 0 OA 翁と乙女
- 著者
- 赤羽根 龍夫 Tatsuo Akabane 神奈川歯科大学
- 雑誌
- 基礎科学論集 : 教養課程紀要 = Bulletin of liberal arts and science
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.1-23, 1985
1 0 0 0 OA 霊異記の道場法師系説話について
- 著者
- 黒沢 幸三
- 出版者
- 同志社大学国文学会
- 雑誌
- 同志社国文学 = Doshisha Kokubungaku (ISSN:03898717)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.1-12, 1972-02
- 著者
- 大水 博 岩崎 為雄
- 出版者
- 公益社団法人 電気化学会
- 雑誌
- 電気化学および工業物理化学 (ISSN:03669297)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.2-5, 1987-01-05 (Released:2019-09-30)
1 0 0 0 OA 里山における子ども時代の自然体験と動植物の認識
- 著者
- 大越 美香 熊谷 洋一 香川 隆英
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.5, pp.647-652, 2004 (Released:2005-12-12)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 8 6
The purpose of this study is showing relationship between the recognition of plants and animals and experiences in the nature. In this study, the recognition is regarded as the recollection in the childhood and the experiences is regarded as play and lifestyle in their childhood. First, the natural and social environments of Satoyama (including of forests, grasslands, ponds and streams) were gotten hold. As a result, the environment s were divided into times 3 types by playing spaces respond to the change of the times. Next, the kinds of plays in Satoyama and using plants and animals were cleared by the way that children asked their parents and grandparents about their childhood. The characters of the plays are catching animals, picking plants and gathering mushrooms and nuts, and that the character of the using is eating these. Finally, the results of examination of the relationship between recognition with experience are as follows. The recognition of insects are connected with catching and hearing chip, the recognition of birds are connected with catching, hearing chip and seeing, the recognition of small animals are connected with seeing, the recognition of plants are connected with picking, eating and seeing beautiful flowers.
- 著者
- 高橋 豪仁
- 出版者
- 社団法人日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.65, 2014
1 0 0 0 灯火の設置による原子力発電所の視認性向上
- 著者
- 山田 研二
- 出版者
- 火力原子力発電技術協会
- 雑誌
- 火力原子力発電 (ISSN:03871029)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.12, pp.p1689-1697, 1991-12
1 0 0 0 OA Closed-Loop てんかんケア実現に向けたてんかん発作予知技術の開発
- 著者
- 藤原 幸一 坂根 史弥 宮島 美穂 山川 俊貴 加納 学 前原 健寿
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第32回全国大会(2018)
- 巻号頁・発行日
- pp.4C1OS27a05, 2018 (Released:2018-07-30)
京都市祇園で起きた軽ワゴン車の暴走により,多数の死傷者が出た痛ましい事故は記憶に新しい.事故原因としてドライバのてんかん発作が挙げられている.てんかんとは脳細胞のネットワークに起きる異常な神経活動のため,けいれんや意識障害などのてんかん発作を来す疾患である.てんかん治療の第一選択は抗てんかん薬であるが,3割の患者は薬剤では発作を抑制できない.しかし,数十秒前に発作を予知できれば,患者は発作までに身の安全を確保し,生活の質を改善できる.我々はこれまでに心拍変動(HRV)と異常検知アルゴリズムを組み合わせたてんかん発作予知技術を開発した.オフライン解析によると,感度90%以上,擬陽性率0.7回/hが達成されている.発作予知技術が実用化できれば,発作起始の前に即効性抗てんかん薬の服薬することなどにより,発作を抑制または軽減できると期待される.このような治療法をClosed-Loopてんかんケアと呼ぶ.現在,AMED先端計測プログラムにて,Closed-Loopてんかんケアの実現に向けた研究開発を行っている.本発表ではてんかん発作予知システム開発の現状と今後の見通しについて発表する.
1 0 0 0 OA 特集にあたって
小児期の虐待,不適切な養育からはじまり,思春期・青年期のいじめ,成人期のハラスメント,老年期の虐待まで,他者からの攻撃は人間にとって最もつらく,しかも長期に心身に影響を与えるストレスである。小児期の虐待,いじめ,トラウマをはじめとする小児期逆境体験については,本誌61巻10号(2019年10月)特集「トラウマインフォームドケアと小児期逆境体験」で取り上げた。同特集は小児期の逆境体験に気付くこと,そしてトラウマインフォームドケアの重要性を指摘している。 最近,小児期にいじめを受けた体験が自殺につながること,さらに長期にわたり心身に悪影響を及ぼすという疫学的研究が報告され,いじめが長期的には精神疾患発症の原因となることも明らかになってきた。いじめに気付き理解することといじめを無くすることが,個々人の健康のみならず公衆衛生,あるいは国家経済の観点からも重要であると思われる。
1 0 0 0 IR 『方丈記』「養和の飢饉」考--事実と虚構の間
- 著者
- 松本 昭彦 Matsumoto Akihiko
- 出版者
- 三重大学教育学部
- 雑誌
- 三重大学教育学部研究紀要 (ISSN:18802419)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, pp.74-63, 2010
鴨長明『方丈記』の「五大災厄」の部分は、当時起きた災害の事実を基に記しているとされるが、中には「虚構」とされる部分もある。確かに、「養和の飢鯉」について見るに、養和二年の二ヶ月間に供養された遺棄遺体数・四万二千三百や、行き倒れた母の乳にすがる幼子、仏像・寺院を損壊して薪に売る行為等の記事は、古記録等で直接確認できず、事実でない可能性が高い。しかしそれらの記事も、いくつかの状況証拠から、事実でないからといって「虚構」に直結させる必要はなく、長明においては〈事実〉として記憶されていたからこそ、「人と栖の無常」を証拠立てるものでありえたし、それが「閑居の気味」を意義づける条件であったのだと思われる。
- 著者
- 櫻井 芳雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.1080, pp.916-919, 2008-11-05 (Released:2017-06-21)
- 参考文献数
- 3