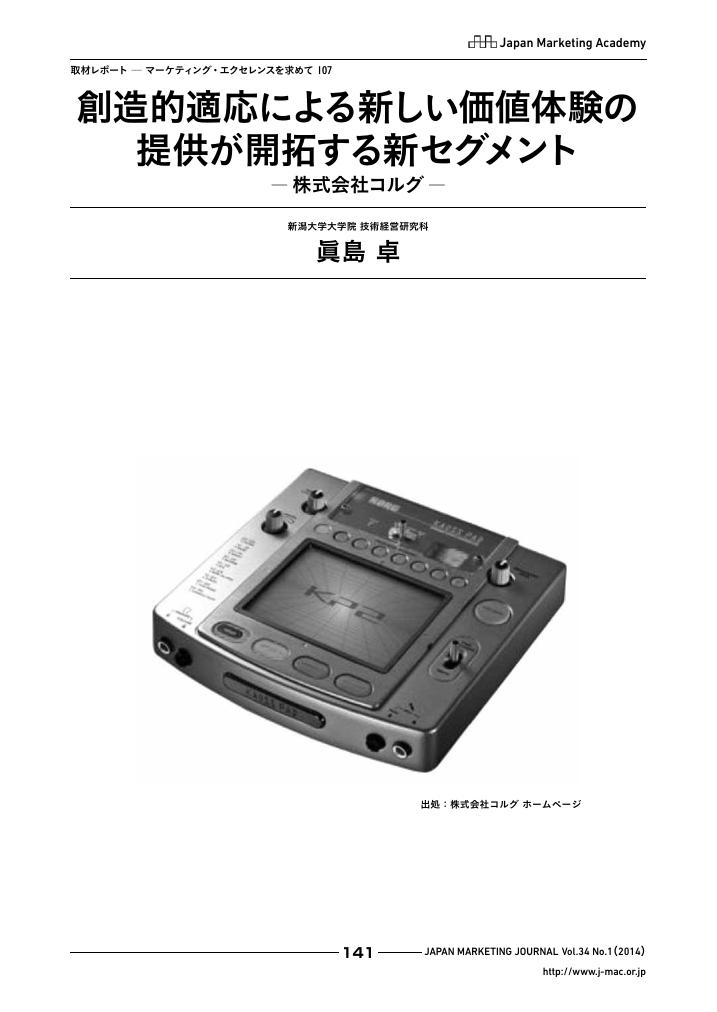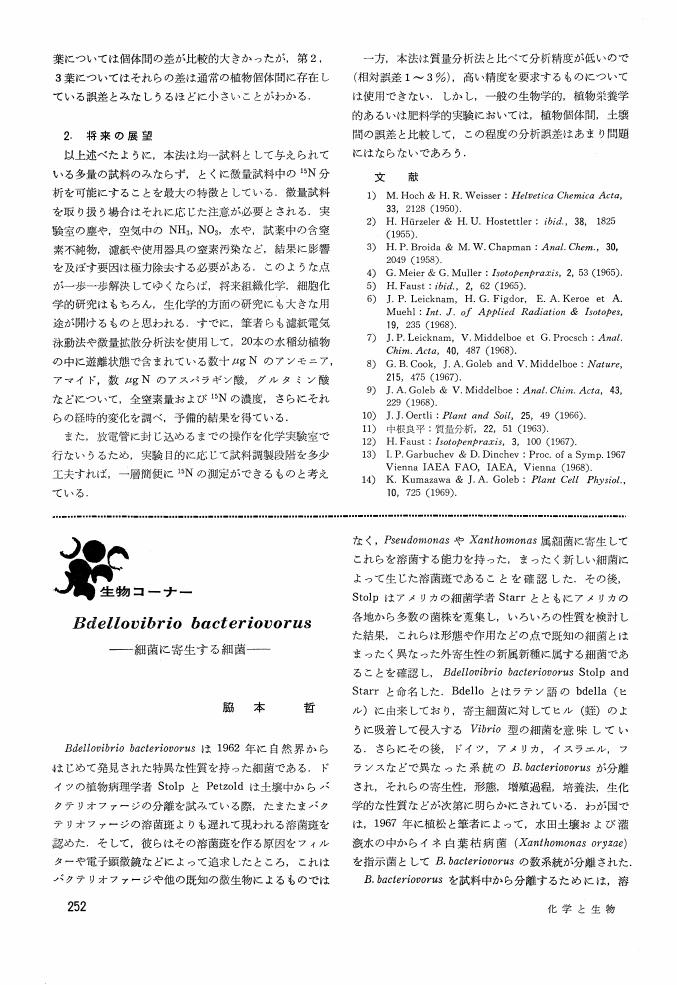1 0 0 0 鳥居龍蔵の朝鮮半島調査実施時期をめぐって
- 著者
- 石尾 和仁
- 出版者
- 考古学研究会
- 雑誌
- 考古学研究 (ISSN:03869148)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.101-110, 2010
- 著者
- 李 炳鎬 井上 直樹
- 出版者
- 帝塚山大学考古学研究所
- 雑誌
- 帝塚山大学考古学研究所研究報告
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.49-70, 2017-03
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経レストラン (ISSN:09147845)
- 巻号頁・発行日
- no.440, pp.45-52, 2011-06
チラシや割引券は配った数に比例して、効果を見込めます。しかし、ただ多くの人に配るだけでなく、相手に「できるだけ気持ちよく、確実に受け取ってもらう」ことができれば、さらにその効果は上がります。
1 0 0 0 OA 御行幸次第
- 巻号頁・発行日
- vol.上,
1 0 0 0 OA 中年者及び高齢者の家族メンバーに対するパーソナル・スペースの検討
- 著者
- 今川 峰子 譲 西賢 齊藤 善弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.212-222, 2000-12-31 (Released:2017-07-20)
- 被引用文献数
- 2
この研究の第一の目的は, 親子間, 夫婦間, 義理の親子間のパーソナル・スペースを中年者と高齢者で比較し, 発達的な視点から検討することにある。第二の目的は, 三世代同居が家族メンバーとのパーソナル・スペースに, どのような影響を与えるのかを検討することである。パーソナル・スペースは会話場面での相手との対人距離により測定した。すなわち, 会話場面を想像させ気づまりにならない程度にまで接近した位置を, 被験者に求めるシミュレーション法を用いた。被験者は35歳〜59歳までの中年世代の285名と65歳以上の高齢者世代の219名であった。対人距離は, 中年者の方が高齢者よりも, 息子や娘とは接近していた。中年者と高齢者に共通して, 母親→娘の対人距離は, 母親→息子, 父親→娘, 父親→息子よりも接近していた。特に女性中年者では, 娘との距離が近い。配偶者との距離は, 世代による差が認められなかった。中年者と高齢者は共に, 義理の関係になる相手とは離れ, 実の親子問は接近していた。義理の親子間の対人距離は, 同居・別居による差が認められなかったが, 女性中年者では, 婿養子として同居している夫との距離が離れていた。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経レストラン (ISSN:09147845)
- 巻号頁・発行日
- no.287, pp.158-161, 2000-06-08
「インターネットにはパソコンが必要」という時代は終わった。今や,携帯電話やPHSがあれば,ホームページの閲覧もEメールのやりとりも簡単にできてしまうのだ。飲食店探しも,もちろんOK。やっとパソコンに慣れ,インターネットの威力も実感した板長だが,今回はまたまたショックを受けることに……。板長 しかし驚いたね。
1 0 0 0 OA う蝕象牙質に対する2ステップ・セルフエッチ接着システムの接着性能の改良
- 著者
- 中島 正俊 谷口 玄 Kunawarote SITTHIKORN 保坂 啓一 高橋 真広 岩本 奈々子 岸川 隆蔵 田上 順次
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会
- 雑誌
- 日本歯科保存学雑誌 (ISSN:03872343)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4, pp.396-402, 2008-08-31 (Released:2018-03-30)
- 参考文献数
- 26
う蝕象牙質へのレジンの接着性能は,健全象牙質に比べ低いことが知られている.その原因として,う蝕象牙質の形態学的構造,生化学的性状および機械的性状が,健全象牙質とは著しく異なっていることなどが挙げられている.また,被着象牙質表面を覆っているスミヤー層の性状も接着性能に影響を及ぼす可能性がある.象牙質切削時に表面に形成されるスミヤー層は,被切削体と構成成分は同じであると考えられている.したがって,う蝕象牙質削面に形成されるスミヤー層は,健全象牙質のスミヤー層と比べて有機成分の割合が多いと思われる.本研究では,う蝕象牙質内層(う蝕罹患(影響)象牙質:caries-affected dentin)へのレジンの接着性能の改良を目指して,スミヤー層の構造がう蝕象牙質と健全象牙質とで異なることに着目し,スミヤー層表面の有機成分を溶解・除去することができる次亜塩素酸ナトリウム水溶液による前処理が,う蝕罹患象牙質への2ステップ・セルフエッチ接着システム(クリアフィルメガボンドFA®,クラレメディカル)の接着強さに及ぼす影響について検討した.その結果,次亜塩素酸ナトリウム水溶液30秒処理後,還元効果のある芳香族スルフィン酸塩を主成分としたアクセル®(サンメディカル)にて30秒間処理することにより,う蝕罹患象牙質に対するクリアフィルメガボンドFA®の接着強さを,無処理-健全象牙質に対する接着強さと同程度に改善させることができた.また,健全象牙質を次亜塩素酸ナトリウム水溶液30秒処理後,アクセル®にて30秒間処理した場合と無処理-健全象牙質に対する接着強さの間に有意差は認められなかった.健全象牙質とう蝕罹患象牙質におけるスミヤー層の性状の違いが,2ステップ・セルフエッチ接着システムのう蝕罹患象牙質に対する接着強さの低下の大きな要因である可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA 創造的適応による新しい価値体験の提供が開拓する新セグメント ─ 株式会社コルグ ─
- 著者
- 眞島 卓
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.141-157, 2014-06-30 (Released:2020-06-16)
- 参考文献数
- 11
- 著者
- Izuru Takayabu Noriko N. Ishizaki Tosiyuki Nakaegawa Hidetaka Sasaki Waranyu Wongseree
- 出版者
- Japan Society of Hydrology and Water Resources (JSHWR) / Japanese Association of Groundwater Hydrology (JAGH) / Japanese Association of Hydrological Sciences (JAHS) / Japanese Society of Physical Hydrology (JSPH)
- 雑誌
- Hydrological Research Letters (ISSN:18823416)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.1-8, 2021 (Released:2021-02-13)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 3
The diurnal cycle of precipitation over northeast Thailand during the Southeast Asian summer monsoon season was examined using non-hydrostatic (5-km grid) and convection-permitting (2-km grid) regional climate models. The results indicate that these fine grid models exhibit a better performance in terms of representing the diurnal cycle of precipitation due to the realistic orographic representation. The models successfully simulated the local circulation corresponding to the intensification of precipitation and were consistent with the satellite-based observed diurnal cycle of precipitation. The model simulation indicated that the convergence area over the mountain on the south of the Khorat Plateau occurred in the afternoon in association with the occurrence of precipitation. The convergence area migrated northward and contributed to the precipitation peak over the plateau during the nighttime. A bias in terms of the amount of precipitation in the 5-km grid model was partially removed through the convection-permitting 2-km grid model.
1 0 0 0 OA 南北朝期長門国府の構造とその認識
- 著者
- 山村 亜希
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.217-237, 2000-06-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 93
Many studies of medieval Kokufu regarded the provincial constable's spatial control as a principal issue. They often equated spatial cognition, either of the provincial constable or of the town's people in opposition to it, with real spatial structure. Some studies concluded that provincial constables had reorganized ancient Kokufu into their provincial capitals, consequentially emphasizing the differences between medieval and ancient Kokufu.However, it is more likely that people living in medieval Kokufu were separated by class and various occupations and powers, and that the interaction of these factors affected spatial form and structure. The actual space within medieval Kokufu did not always correspond to the intentions or conceptualizations of one actor like a provincial constable. Furthermore, referring to recent studies on ancient Kokufu, the heritage of the structure of ancient Kokufu may be an important component of medieval Kokufu.This paper aims to reconstruct the morphology and function of Kokufu in the fourteenth century and to examine the social relationships among its people and to clarify the spatial structure, comparing it with ancient times. A medieval map is presented which illustrates a local power conceptualization of medieval Kokufu and the paper discusses the relationship between the real and perceived world. The example selected for this paper is Nagato Kokufu, which is shown on the medieval map, "Shrine Grounds Map of Iminomiya".The second section of the paper shows the direction and pattern of roads and allotments and the distribution of facilities and then examines the transformation of local powers. The ancient frameworks of the structure of Kokufu, consisting of the pattern of roads, allotments and facilities were maintained until the fourteenth century. Moreover, the awareness of ancient Kokufu frameworks was also preserved, and in part was even strengthened. At that time, the central government was unstable because of the struggles between warriors and Emperors. The Iminomiya Shrine had always been given financial guarantees from the provincial constable, Shugo, and the Kamakura or Muromachi shogunates. The Iminomiya had inherited the powers and officials of the Kokuga, which succeeded the ancient Kokufu government. Kokubunji Temple, which was established during the eighth century but had declined, recovered its land, relying on the traditional power of the Emperors in the fourteenth century. Shugo, always closely related with Iminomiya, continued as an independent local power. The locational patterns of these important facilities were similar to those of departmental facilities in ancient times. Other social groups also enjoyed a close relationship with the central polity in Kamakura or Kyo.In the third section of the paper, an analysis of the characteristics of the Shrine Grounds Map explains why and by whom the map was made, and how the map maker's spatial cognition was represented. It must be noted that Iminomiya is situated in the context of fourteenth-century political process. The characteristics of the Grounds Map undoubtedly show that it was made by Iminomiya. However, the map does not represent the whole real landscape; for example, some of the things that existed at that time do not appear in the map, some are emphasized and yet others are understated. This points out that the Grounds Map was intended to represent Iminomiya lands and the other facilities with which the Shrine was associated. The purpose of the map was to exhibit its territories to Shugo and to obtain the constable's protection, guarantee and tax exemption. Furthermore, the Grounds Map shows that the space of medieval Kokufu, as a squared world, was surrounded by mountains and sea;
1 0 0 0 OA 生物コーナー
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.4, pp.252-254, 1970-04-25 (Released:2009-05-25)
1 0 0 0 OA 砒素混入毒物カレー事件の被災者にみられた急性期の皮疹
- 著者
- 上出 康二 塩谷 昭子
- 出版者
- Meeting of Osaka Dermatological Association
- 雑誌
- 皮膚 (ISSN:00181390)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.5, pp.511-517, 1999 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
平成10年7月25日和歌山市園部地区の夏祭り会場で出されたカレーに砒素が混入された事件の被災者で急性期に皮疹が認められた3名について報告した。症例1: 31歳男性。第6病日に肝機能異常の出現と同時に両腋窩, 両股部, 下腹部に点状赤褐色丘疹が左右対称性に集籏して認められた。病理組織学的に血管周囲に稠密なリンパ球の浸潤があったが汗腺などの付属器には異常は認められなかった。症例2: 17歳男性。第6病日に肝機能異常の出現と同時に両大腿, 両肘窩に左右対称性に症例1と同様の皮疹が認められた。組織学的にも症例1と同様であった。症例3: 48歳男。第12病日より四肢末端の葉状落屑が認められた。砒素暴露3ヵ月後の23名の検診時の問診から, 急性期にみられた皮疹は紅色丘疹を示した症例が6名, 顔面浮腫3名, 水痘様皮疹が3名, 指趾尖の落屑3名, 紅皮症が1名であり, 経口亜砒酸推定摂取量との関連性はみられなかった。(皮膚, 41: 511-517, 1999)
- 著者
- 森田 美里
- 出版者
- 日本フランス語教育学会
- 雑誌
- Revue japonaise de didactique du français (ISSN:18805930)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.80-96, 2015
日仏コミュニケーションにおいて「舌打ち」(非肺気流子音の歯茎吸着音)は誤解を招く原因の一つである。本研究では,まず実例に基づき舌打ちを観察し,次に日本人学習者の知覚と評価に関するアンケート調査を行い,さらに日本人に対するフランス語教育での舌打ちの取り扱いに関する条件を考察する。一つ目の調査結果から,舌打ちが談話標識のように現れ,主に注意喚起機能を持っていることが明らかになった。また,二つ目のアンケート調査により,この音がフランス語文法の基礎が十分ではない,なおかつ外発的に動機づけられている学習者には「聞こえる」ことがわかった。これらの者が渡仏を控えている場合,日本語の舌打ちとフランス語のそれとが異なる用法を持っているということを教えることは有用であろう。一方,基礎力が十分あり,なおかつ内発的に動機づけられた学習者は,日本人フランス語教師も含め「聞こえていない」。よって,この知識は全ての学生に必要であるとは言えないが,教師はこの現象を把握し,機能および用法を知っておくべきである。
- 著者
- Nakagawa Kayako Matsumura Reo Shiomi Masahiro
- 出版者
- 富士技術出版株式会社
- 雑誌
- Journal of Robotics and Mechatronics (ISSN:09153942)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.86-96, 2020
- 被引用文献数
- 4
<p>This paper focuses on "play-biting" as a touch communication method used by robots. We investigated an appropriate play-biting behavior and its effect on interaction. The touching action has positive effects in human-robot interactions. However, as biting is a defenseless act, it may cause a negative effect as well. Therefore, we first examine biting manner and the appearance of the robot using a virtual play-biting system in Experiment 1. Next, based on the result of experiment, the play-biting system is implemented in a stuffed animal robot. We verified the impressions created by the robot and its effect on mitigating stress in Experiment 2. Consequently, the play-biting communication gave positive and lively impression, and effect of reducing the physiological index of stress, in comparison to only touching the robot.</p>
1 0 0 0 IR 裁判員のストレスと「苦役」に関する一考察
- 著者
- 南部 さおり
- 出版者
- 横浜市立大学学術研究会
- 雑誌
- 横浜市立大学論叢. 人文科学系列 (ISSN:09117717)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.37-73, 2015
1 0 0 0 IR 二〇一九年度 春季公開講演会講演録 西行と芭蕉に開かれる親鸞 : 日本人の宗教心
- 著者
- 山折 哲雄
- 出版者
- 大谷学会
- 雑誌
- 大谷学報 (ISSN:02876027)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.1, pp.77-94, 2019-11
1 0 0 0 OA 子宮頸部神経内分泌細胞癌2例の細胞診所見および病理組織化学的検討
- 著者
- 平園 賢一 篠塚 孝男 伊藤 仁 川井 健司 堤 寛 長村 義之
- 出版者
- 公益社団法人 日本臨床細胞学会
- 雑誌
- 日本臨床細胞学会雑誌 (ISSN:03871193)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.37-41, 1995 (Released:2011-11-08)
- 参考文献数
- 5
今回われわれは, 子宮頸部の神経内分泌細胞癌2例を経験し, 検討したので報告する.症例は32歳と50歳の主婦. ともに子宮頸部Ib期の臨床診断にて, 広汎子宮全摘および所属リンパ節郭清施行後, 50Gyの外照射を行ったが6ヵ月から1年で血行転移を来し, 化学療法 (CAP) を施行したが効果なく術後2年足らずで死亡した. 細胞像は, 孤立散在性または集団状に出現し, いわゆる対細胞もみられた。細胞はリンパ球よりやや大きく円形ないしは楕円形で大小不同を認めた. 細胞質は乏しく裸核状のものも多く, 核クロマチンは中等度増量し粗大顆粒状, 核小体は著明ではないが出現する場合は数個認められた. 組織像は, 主に小型で未分化な腫瘍細胞が充実性シート状に配列し, 一部カルチノイドにみられるような索状およびロゼット形成が認められ, 腺癌病変も一部に認められた. また腫瘍細胞に一致してグリメリュウス, 神経内分泌マーカーであるクロモグラニンA, NSE, Leu 7, 上皮性マーカーであるサイトケラチン, EMAが陽性を示した. 電顕的には細胞質に神経内分泌顆粒が認められた.
1 0 0 0 OA 子宮頸部に発生した小細胞性神経内分泌癌の1例
- 著者
- 広瀬 隆則 山田 順子 山本 洋介 佐野 暢哉 日野 明子 古本 博孝 山田 正代 佐野 壽昭
- 出版者
- 公益社団法人 日本臨床細胞学会
- 雑誌
- 日本臨床細胞学会雑誌 (ISSN:03871193)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.233-237, 1997-03-22 (Released:2011-11-08)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 4 4
子宮頸部にはまれに神経内分泌癌が発生することが知られている. 30歳, 妊娠29週の女性の子宮頸部に発生した小細胞性神経内分泌癌の1例を経験したので, 細胞所見を中心に報告した. 患者は不正性器出血を主訴として来院し, 頸部前唇にピンポン玉大の腫瘍が見出されたため, 広範子宮全摘出手術が行われた. 術後, 大量化学療法と末梢血幹細胞移植が施行されたが, 合併症のため約7ヵ月後に死亡した. 擦過細胞診では, 小型で裸核状の腫瘍細胞が壊死物質を背景に孤立散在性ないし結合性の弱い小集塊として認められ, 肺小細胞癌の細胞所見に類似していた. 組織学的に腫瘍細胞は, 胞巣状, 索状ないしリボン状に配列し, 多くの細胞でGrimelius法により好銀顆粒が証明された. 免疫組織化学的に, Chromogranin A, neuron specific enolase, synaptophysinなどの神経性マーカーが陽性を呈しており, 小細胞性神経内分泌癌と診断された. 本腫瘍は, 小細胞性扁平上皮癌や低分化腺癌との鑑別が難しいが, これらの腫瘍より進行が早く悪性度が高いので, 早期に診断し強力な治療を開始することが大切である. 診断上, 細胞診のはたす役割は大きいと考えられた.
1 0 0 0 ユリウス・グットマン--ユダヤ教の哲学者(上)
- 著者
- Bamberger Fritz 北岡 幸代 関根 真保
- 出版者
- 神戸・ユダヤ文化研究会
- 雑誌
- ナマール
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.96-108, 2001
1 0 0 0 OA 法学会記事(2010年度分)
- 出版者
- 南山大学法学会
- 雑誌
- 南山法学 = Nanzan Law Review (ISSN:03871592)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3-4, pp.239-240, 2011-03-31