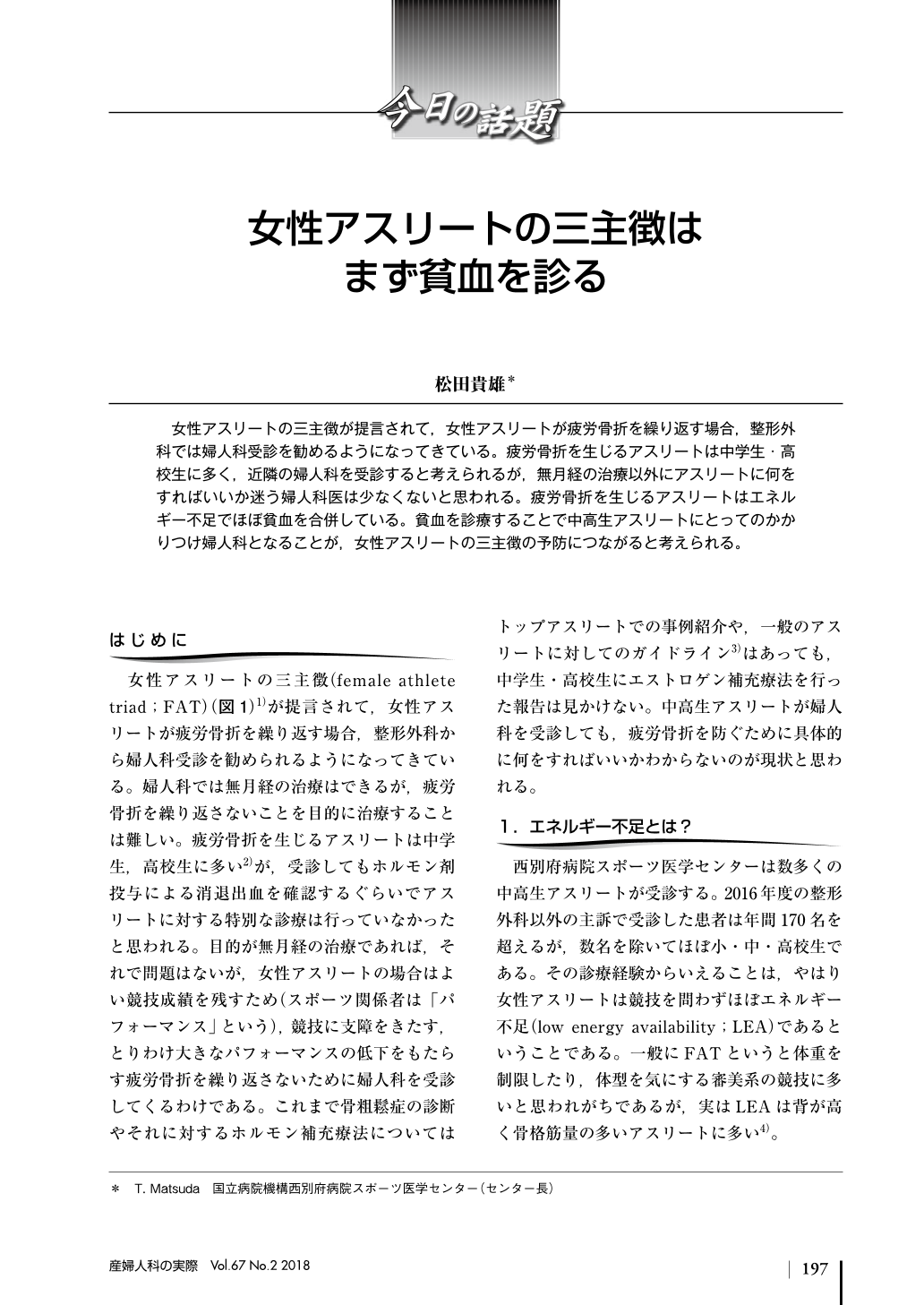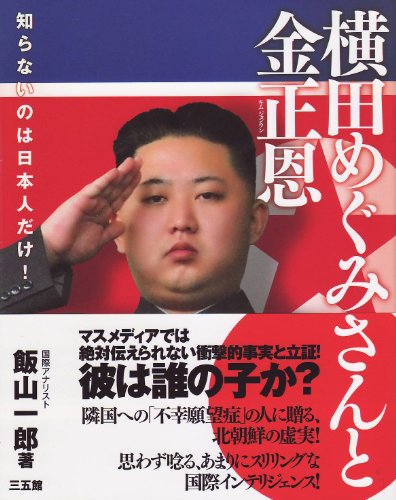- 著者
- KATO Kenji NISHIMURA Yukio
- 出版者
- Japanese Society for Brain Function and Rehabilitation
- 雑誌
- Journal of Rehabilitation Neurosciences (ISSN:24342629)
- 巻号頁・発行日
- pp.200731, (Released:2020-08-23)
Motor impairment following stroke is one of the most important issues to be addressed in clinical care. In this review, we summarize a study in which lost volitional motor control of the hand was regained in a monkey model of stroke using an “artificial cortico-muscular connection” (ACMC) via a neural interface that bypassed the damaged neural pathway after stroke. The ACMC was produced by a computer interface that can detect the high-gamma cortical oscillations and converted in real-time to activity-contingent electrical stimuli delivered to the paralyzed muscles. As a result, within 20 min, the monkeys learned rapidly to use the ACMC and reacquired volitional motor control of the affected hand. Learning to use the ACMC was achieved regardless of whether the input signal was extracted from the primary motor area or the primary somatosensory area, and the activation areas of the input high-gamma signals were changed to concentrate around the arbitrarily-assigned input electrode as learning progressed. This study may have the potential to lead to the development of a clinically effective neural prosthesis to regain lost motor function by bypassing the lesion site and activating paralyzed muscles via an artificial neural connection, even after a limb is paralyzed due to stroke.
1 0 0 0 OA Powered-hand tools and vibration-related disorders in US-railway maintenance-of-way workers
- 著者
- Eckardt JOHANNING Marco STILLO Paul LANDSBERGIS
- 出版者
- National Institute of Occupational Safety and Health
- 雑誌
- Industrial Health (ISSN:00198366)
- 巻号頁・発行日
- pp.2020-0133, (Released:2020-08-28)
- 被引用文献数
- 10
Maintenance-of-way workers in North America who construct railroad tracks utilize specialized powered-hand tools, which lead to hand-transmitted vibration exposure. In this study, the maintenance-of-way workers were surveyed about neuro-musculoskeletal disorders, powered-hand tools and work practices. Information about vibration emission data of trade specific powered-hand tools for the North American and European Union markets was searched online to obtain respective user information of manufacturer and compared to non-commercial international data banks. The survey showed that maintenance-of-way workers frequently reported typical hand-transmitted vibration-related symptoms, and appear to be at a risk for neuro-musculoskeletal disorders of the upper extremity. Of all of the powered-hand tools used by this trade, 88% of the selected tools exceeded a=5 m/s2 and were above vibration magnitudes of common tools of other comparable industries. This may create a risk if these tools are used throughout an 8-h work day and management of vibration exposure may be needed. In the North-American market, limited or no vibration emission data is available from manufacturers or distributors. Vibration emission information for powered-hand tools, including vibration emission levels (in m/s2), uncertainty factor K, and the applied testing standard/norm may assist employers, users and occupational health providers to better assess, compare and manage risk.
1 0 0 0 OA 3. 家庭用カメラの特性•画質評価方法
- 著者
- 吉田 英明
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.6, pp.735-740, 2009-06-01 (Released:2011-06-01)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 OA 臨床認知科学 : 個人的知識を超えて
1 0 0 0 OA フランス急進社会党研究序説
第1章 フランス革命とフランス急進派の系譜……………………………………………… 1第2章 急進社会党と第三共和制……………………………………………………………… 34第3章 地方史の急進社会党…………………………………………………………………… 60第4章 急進派議員の政治行動 : 急進社会党史のなかで…………………………………… 105第5章 急進社会党と圧力団体………………………………………………………………… 121第6章 アベ・ルミール小論 : 十九世紀末フランス政治史の一側………………………… 139第7章 初期ド・ゴールの政治思想 : 「フランスの栄光」という保守主義……………… 162第8章 M・アンダーソン「フランスの保守政治」(紹介) Malcolm Anderson, Conservative Politics in France, London, 1974.………………… 198
1 0 0 0 OA ローレンス・スターン論集 : 創作原理としての感情
1 0 0 0 月刊アドバタイジング
1 0 0 0 女性アスリートの三主徴はまず貧血を診る
1 0 0 0 OA 鉄道高架橋を対象とした三次元モデルと解析ソフトウェアとの連携に関する検討
- 著者
- 藤澤 泰雄 矢吹 信喜
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集F3(土木情報学) (ISSN:21856591)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.I_1-I_8, 2012 (Released:2013-03-29)
- 参考文献数
- 6
土木分野での三次元モデルの利用は,設計・施工などの各分野の中の一部で利用されているにすぎない.特に設計においては解析が重要な位置を占めているが,発注者も受注者も三次元モデルに慣れていないため三次元モデルの利用は進んでいない.本研究では,鉄道高架橋を対象に,三次元モデルから二次元解析ソフトウェア用の解析データと三次元解析ソフトウェア用の解析データを出力することにより三次元モデルと解析ソフトウェア,IAI日本が発表しているST-BRIDGEとの連携方法を示し,その課題を検討した.
1 0 0 0 OA 成人発症の髄内頸髄脂肪腫の1例
- 著者
- 中井 啓 丸島 愛樹 松村 明
- 出版者
- 日本脊髄外科学会
- 雑誌
- 脊髄外科 (ISSN:09146024)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.80-84, 2009 (Released:2017-05-11)
- 参考文献数
- 14
Intramedullary lipomas of the cervical spinal cord without dysraphism are rare lesions, accounting for only 1% of spinal cord tumors. We experienced a 60-year-old male with cervicothoracic (C6 to T2) lipoma who complained of dysesthesia in his lower extremities. Magnetic resonance imaging identified a tumor which was dorsolateral to the cord in the intramedullary legion. In these cases, a fat suppression sequence is useful for diagnosis. He underwent surgery for partial removal of the tumor and expansive laminoplasty. Postoperative course of the patient was uneventful and follow-up showed an improvement in sensory disturbance.
1 0 0 0 OA 急性胃粘膜病変に関する臨床的・基礎的研究
- 著者
- 原田 一道
- 出版者
- Japan Gastroenterological Endoscopy Society
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.3-17, 1995-01-20 (Released:2011-05-09)
- 参考文献数
- 80
1988~1992年の5年間に上部消化管内視鏡検査を26,162例に行い,そのうちAGMLが360例であった(平均年齢45.5±16.4歳,M±SD;男:女2.1:1).AGMLの成因としては,精神的ストレス(55.6%),各種薬剤(22.2%),飲食物(6.9%),内視鏡検査(GF)後のもの(3.3%),その他(4.2%),不明(7.8%)であったが,最近,薬剤によるAGMLが増加傾向にあった.AGMLの季節発生は夏季(6~8月)に有意に少なかった.また,都市に住む人の方が地方の人よりAGMLの発生頻度が多かった. ストレスによるAGMLは青壮年に多いのに対して,薬剤によるAGMLは65歳以上の老年者に有意に多く発生していた.誘因薬剤ではNSAIDsが72.5%と最も多く,ついで抗生物質製剤が17.5%,ステロイド剤が5.0%,その他が5.0%であった.NSAIDsに起因する胃病変の発生を予防する方法を確立する目的で,健常ボランティアにおいてDiclofenac単独投与群,防御因子増強剤併用群,H2-受容体拮抗剤併用群の3群にわけて検討した.その結果,H2-受容体拮抗剤併用群が有意に胃病変の発生を抑制した.実験的にIL-1をラットの腹腔内投与(0.01~1μg/rat)すると胃酸分泌と胃排出を用量依存性に抑制し,水浸拘束ストレスおよびNSAIDsやエタノールによる胃病変に対して強力な胃粘膜保護作用を発揮した.この事実はAGMLの病態生理や治療体系に大きなインパクトを与え将来の発展が望まれる.
1 0 0 0 OA 仮説実験授業のたのしさを決めるもの(5)全脳参与の可能性
- 著者
- 守屋明佳
- 雑誌
- 日本教育心理学会第61回総会
- 巻号頁・発行日
- 2019-08-29
問題と目的教育心理学は「学び手による」学習とも関わるはずだが,「学習者の認知的個性」,いわんやその「脳科学的基盤」についての関心はまだ高くない。本稿第一の目的は,教育心理学にとっての脳科学研究の有用性を示すことである。筆者には思わぬ発見があった。仮説実験授業(以下「仮説」)で学び手が感じる「多様なたのしさ」が,実は彼らの「認知的個性」(学習において優勢な脳内ニューラルネットワーク(以下NN)の種類)を反映したものである可能性が判明したのだ。それを虫明元(2018)の「学ぶ脳」理論に依拠しつつ明らかにする。また,つまり「仮説」の「個性を選ばないたのしさ」が,学習で前提とされるNNが「執行系」に限定されていないことに依ること,即ち学習への「全脳参与」が許されているからこそのものであることを示し,「全脳参与型学習」としての「仮説」の望ましさを主張したい。なお,「全脳参与型学習」の提案は過去の構成論的人工知能研究の失敗にも学んでおり(命題形式の記号演算モデルのみでは人間の知能の再現は不可能だった),現在の虫明理論にまだ不足があったとしても,提案の妥当性は減じない。学び手の個性に優しく,人間らしくもある学びの実現には,「全脳参与型学習」は極めて有効であると考える。本稿第二の目的は,教育心理学的方法論の拡大である。教育心理学が脳科学に学ぶことはこれまで余りなかったようであるが,もし仮に脳科学研究に学び「推論における情動の重要性」(例,ダマシオ,1994)を意識するようになっていたなら,情動抜きの「干からびた教育論」(品川嘉也にヒントを得た命名)で他でもない人間の学びを機械化してしまう暴挙は避けられたであろうし,大隅典子(2016)と同じ洞察に辿り着いていたなら(「脳の複雑さはバグの生まれやすさをも含意しており,完全な脳など存在しない」),誰しもが出発点とする他ない「不完全な脳」(つまり「認知的個性」)について,またそこからの出発しかあり得ないという事実について,より深い理解が可能になっていたのではないかと考える。教育心理学には脳科学との対話が有用だ。それを本稿では示したい。方 法授業書《花と実》の授業記録(西川,1988;出口,2006;小池,1986,1988;竹田,2012;田中,2013)他から生徒たちが口にする「授業のたのしさの色々」を抽出し,虫明(2018)の「学ぶ脳」モデルとの対応づけを試みた。虫明のモデルは以下である。「学ぶ脳」には主体となる脳内NNによって4種類ある。「学習脳0」は感覚運動ネットワーク(SMN)主体の「身体脳」,「学習脳1」は皮質下ネットワーク(SCN)主体の「記憶脳」,「学習脳2」は執行系ネットワーク(CEN)主体の「認知脳」,「学習脳3」は基本系ネットワーク(DMN)主体の「社会脳」であり,これらの脳のそれぞれが,学習経験を蓄積してゆく。(学習脳1と2は,それぞれデュアル・プロセス・モデルの「速い自動的思考システム1」と「遅い熟慮型思考システム2」,学習理論における「行動主義」(ボトムアップな連合説)と「認知主義」(トップダウンでメタ的な把握)にも対応させられており含意に富む)。学習脳0(身体脳)は最も早くに形成されて意識下での自動運転を可能にし,学習脳1(記憶脳)が無意識・意識双方の記憶を支えているかんに記号操作による意識的学習を司る学習脳2(認知脳)が徐々に形成されてゆく(認知脳の主部である前頭前野は髄鞘化の完成を20歳代に待つ形成の遅さである)。上記のように,異なる学習脳にそれぞれ参加する各NNであるが,それらは互いに協働関係にもあり,例えば仮説検証型認識活動においては仮説生成の為のDMNと仮説検証の為のCENとが協働している。帰納的枚挙を待たない仮説生成は一種の「物語り」であると考えられ(筆者),仮説を案出することが好きな子においてはナラティブ的発散的思考を司るDMNが活動的であり,考えを生むというよりは実験にかけて吟味することが好きな子においては分析的収束的思考を司るCENが活動的であると考えることが合理的である。優勢・劣勢のNNの組み合わせが,認知的個性を決定する。結果と考察「仮説」のたのしさを「学習脳」毎に以下数例ずつ記述する。「仮説」ではどのような個性にもたのしさが保証されている。「身体脳」:運動的たのしさ(思わず身体の動きに顕れてしまう授業での喜怒哀楽はなんら拘束の対象ではない),感覚的たのしさ(観察対象である果物は観るだけでなく食べもする)。「記憶脳」:作業記憶が小さくCENに負荷がかかり易い子には皮質下での学びのたのしさが用意されている(予想が外れれば「危険回避」の扁桃体による学習が,予想が当たれば「報酬接近」の大脳基底核による学習が発生するが,これは概念的理解には媒介されない「現象の規則性の直接的学習」を可能にする。西川浩司はこれを「直観の科学化」と呼んだ。命題学習が苦手でも事象からの直接学習が可能となる経路である),予想が当たるたのしさ(報酬系である大脳基底核が活躍する)。「認知脳」:仮説的思考のたのしさ,立論するたのしさ,反証に学んで概念を覆すたのしさ(反証に敏感な概念的思考は,記憶脳による意識下のパターン学習とは異なり反証事例の帰納的枚挙を待たない。それが概念的思考の可能性でもあり限界でもある),予想が外れるたのしさ(「予想は外れてこそ新たな発見を生む」という,皮質下の記憶脳にはなかった意識的な学び。記憶脳では外れて悔しかった予想が,認知脳ではたのしくなる)。「社会脳」:意見の異なる他者と議論するたのしさ,真理が多数決では決まらないことを発見するたのしさ。「学習脳全て」:乳児にも見られる「脱馴化」のたのしさ(当然視できず説明不可能な出来事の出現は最も原初的な学びの動機づけであり,古くはソクラテスも「エレンコス」として概念化した),発見のたのしさ(発見の感動は記憶の中でも基礎的な「感情記憶」に痕跡を残す。何がたのしいかは認知的個性に依っても,たのしいという感情記憶自体は個性共通である。認知機能が衰えた認知症患者においても頑健に残るのが感情記憶とされており,いわば深部に位置するその重要性を顧慮すれば,「感情記憶の土台」づくりは「全脳参与型学習」においては要とすべきものかもしれない),ベイジアン・プロセス(BP)のたのしさ(「誤差最小化原理」に従いつつ予測の修正を繰り返すことでランダムなモデルからでも正しいモデルを生み出しうるのがBPである。BPがあるからこそ多様な個性に始まる認識活動が(個性を残しつつも)最終的には普遍的理解を生んでくれる(意識・無意識のBPがある)。正しくとも学び手の手には余るモデルを最初から教え込むのではなく,学び手の関心にも認知的個性にも適合した出発点を用意した上でそこからのBPを支援することが,「仮説」成功の鍵であると考える。予想が外れる悔しさは発見を伴うことで甘受可能となるが,更にBPを介することで,当たる予想のたのしさへと変化する。学び手達をわくわくさせ,自信をも生み出すBPである)。結 語虫明理論の援用で明らかとなったように,「仮説」では全ての学習脳(全ての個性)に学習参加が開かれている。又,学習に関わる脱馴化とBPは乳児期より脳に備わる個性以前の原初的学びの機構で,これらも個性に依らず学習機会を保証してくれる。つまり「仮説」は学び手を選ばない。が,それだけではない。全学習脳の参加は学習活動に(生き甲斐ともなり得るような学びなら持つであろう)躍動性と全体性とを回復させ,命題学習には尽きない有機的な学びを実現している。研究者も自由に全脳を使いながら研究している。そのたのしさを子ども達には拒否できるのか。全脳を巻き込む「全脳参与型学習」に学びたい。
- 著者
- 月嶋 紘之
- 出版者
- スポーツ史学会
- 雑誌
- スポーツ史研究 (ISSN:09151273)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.1-14, 2008-03-20 (Released:2017-03-18)
'Football Spectators Act 1989' was expected to be a strong fort against football violence in England. The purpose of enforcement of this decree was to eradicate all "hooligans" in all the stadiums inside and outside of England, which was one of the points of the greatest concerns for the British Government's policies. However this law betrayed the hope of the British Government and this led to an institution of a change in the law. The purpose of this study is to examine the matters skeptically and consider the reason why this law did not satisfy the policy by referring to a concept of "Gewalt" propounded by Walter Benjamin (1892-1940). The conclusions of this study follow below. 1. In this Act, legal definition about physical exertion displayed by spectators in stadiums was absolutely unconcerned. On top of this, the Crown Court was authorized as making every judgment that was based on their own criteria. 2. According to the concept of "Gewalt" by Benjamin, the power of "Gewalt" is indispensable in a law-enforcement. Therefore, this act was enforced by the power of "Gewalt", that is the British Government itself. However, Benjamin also reveals that a law never presents a valid reason for making every decision. 3. To enforce a law has a pursuit of personal interests and it always has to remain skeptical. Intensification of "hooligan" activities since 1970s and eruption of violence such as "Heysel tragedy" in 1985 were regarded as "crisis" for the British Government, since "hooligans" breached their ideals in English football.
- 著者
- 中房 敏朗 Toshiro NAKAFUSA 仙台大学 Sendai College
- 雑誌
- 仙台大学紀要 = Bulletin of Sendai College (ISSN:03893073)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.71-80, 1995-03-01
It is commonly thought that the origin of football in Europe was derived from "Folk-Football", which still exist here and there within Britain. But Heiner Gillmeister claimed that Europian football was invented in medieval France and by the lower social classes who had adopted certain principles of "pas d'arms", which has been identified as having served as the chief model for football. His theory may be considerably bold and some do not accept his theory with good grace. But we do not have arguments and facts to completely dismiss his theory nor another strong theory of the origine of Europian football to replace Gillmeister's theory. We should not be permited an intellectual neglect of his theory when we think about the origine of ball-games in medieval Europe, whethere we rate his theory accurate or not.
- 著者
- 三重野 清顕
- 出版者
- 東洋大学国際哲学研究センター
- 雑誌
- 国際哲学研究 = Journal of international philosophy (ISSN:21868581)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.23-30, 2020-03
1 0 0 0 OA 此君亭小曲集 : 自作肉筆版
1 0 0 0 OA 炭素14年代キャリブレーションと水月湖年縞堆積物
- 著者
- 北川 浩之 Kitagawa Hiroyuki
- 出版者
- 名古屋大学年代測定資料研究センター
- 雑誌
- 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.56-61, 2013-03
Radiocarbon (14C) provides a way to date material that contains carbon with an age up to 50,000 years and is also an important tracer of the global carbon cycle. To obtain the calendar year, radiocarbon age is calibrated using radiocarbon calibration dataset such as IntCal09. However there is still uncertainty in the available radiocarbon calibration dataset prior to 12.5 thousand years before the present. Recently,the radiocarbon calibration dataset from the annual laminated (varve) sediments of Lake Suigetsu, Japan (35°35'N, 135°53'E), have been updated by more than 800 14C analyses of terrestrial materials which provide a comprehensive record of atmospheric (or terrestrial) radiocarbon to the present limit of the 14C method (Bronk Ramsey et al., 2013).炭素14年代測定法は、過去5万年間の年代決l定には無くてはならない年代測定法である。しかし、炭素14年代は暦年代とは一致しなく、炭素14年代から暦年代を推定するには炭素14年代キャリブレーションデータセットを用いた較正が必要である。過去12500年間の炭素14年代キャリブレーションセットは、年輪年代学の手法で年代決定された木材の高精度炭素14年代測定によって求められている。それ以前は、海洋試料の高精度炭素14年代測定結果に海洋のリザーバ効果の補正が行われデータから推定され、不確かさが残されていた。水月湖年縞堆積物の研究で、海洋のリザーバ効果の補正が必要がなくなり、考古学試料などの陸域試料に適用できる炭素14年代キャリブレーションデータセットが、炭素14年代測定法が適用できる全期間について求められた。