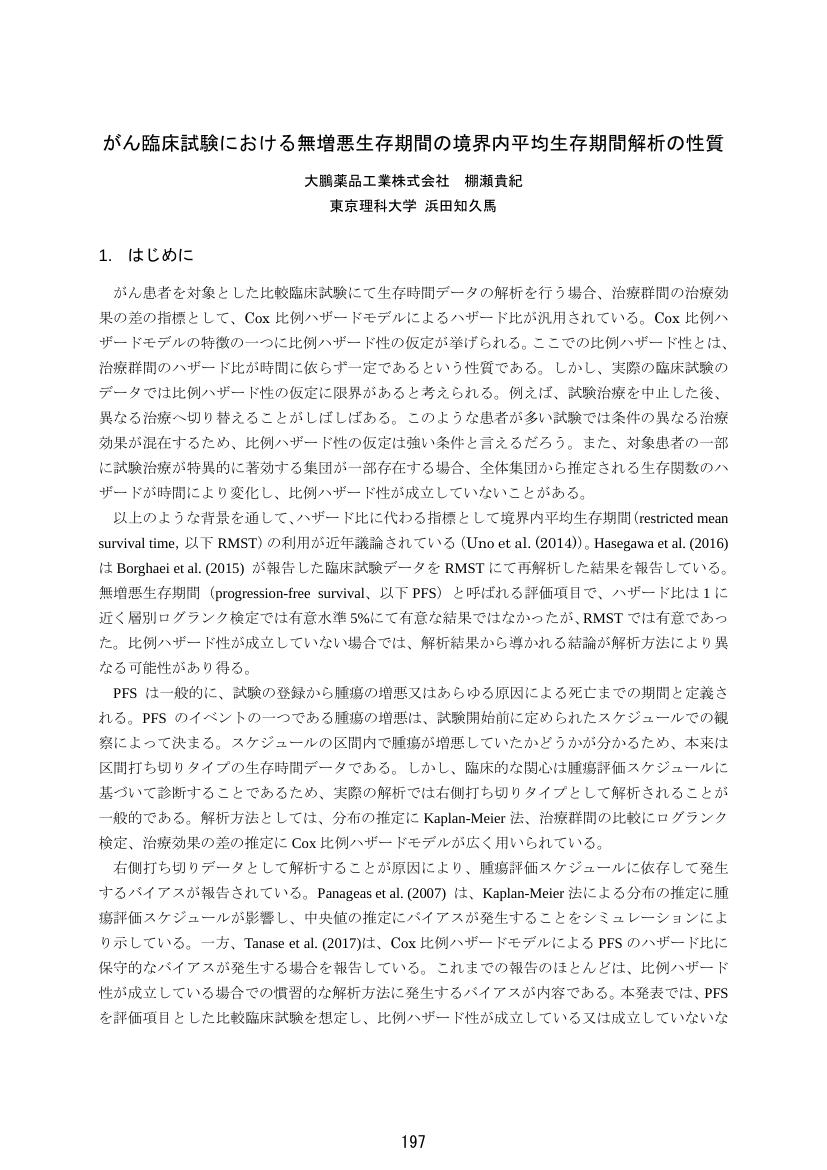1 0 0 0 OA ダーウィン『ビーグル号航海記』におけるフィールドワーク
1 0 0 0 IR ボールルーム・ダンスの歩行に関する比較人類学の試み : 歩行を身体技法として分析する
- 著者
- 板垣 明美
- 出版者
- 横浜市立大学学術研究会
- 雑誌
- 横浜市立大学論叢. 社会科学系列 = The bulletin of Yokohama City University Social Science (ISSN:09117725)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.123-142, 2017
1 0 0 0 OA がん臨床試験における無増悪生存期間の境界内平均生存期間解析の性質
- 出版者
- 日本計算機統計学会
- 雑誌
- 日本計算機統計学会シンポジウム論文集 (ISSN:21895813)
- 巻号頁・発行日
- pp.197-200, 2017 (Released:2019-04-26)
1 0 0 0 IR 平安時代の臨時祭における《東遊》--場の論理より奏楽の脈絡を読む
- 著者
- 平間 充子
- 出版者
- 桐朋学園大学
- 雑誌
- 桐朋学園大学研究紀要 (ISSN:03855627)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.155-169, 2008
1 0 0 0 OA 船舶へ搭載した縦軸型風力発電装置について
- 著者
- 浅治 邦裕 村井 宏行 池田 和人 Asaji Kunihiro Murai Hiroyuki Ikeda Kazuhito
- 出版者
- 宇宙航空研究開発機構
- 雑誌
- 宇宙航空研究開発機構特別資料: 第76回風洞研究会議論文集 = JAXA Special Publication: Proceedings of the Wind Tunnel Technology Association 76th Meeting (ISSN:1349113X)
- 巻号頁・発行日
- vol.JAXA-SP-06-020, pp.27-29, 2007-03-30
資料番号: AA0063330005
- 著者
- 髙橋 悟
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.117-120, 2014 (Released:2014-12-25)
- 参考文献数
- 20
Rett症候群は, 主に女児に発症する神経発達障害である. その診断は, 臨床症状に基づいて行われ, 回復期や安定期が後続する神経症状の退行があることを必要要件とする. 病因遺伝子は, メチル化DNAに結合して遺伝子の転写を制御するmethyl-CpG-binding protein 2 (MECP2) をコードする. Rett症候群に類似するが異なった臨床経過を示すものを非典型的Rett症候群とよび, “早期発症てんかん型” や “先天型” が知られている. 前者の病因遺伝子は, 樹状突起棘に局在するリン酸化酵素cyclin-dependent kinase-like 5 (CDKL5) をコードしている. 後者の病因遺伝子は, 終脳の発生に重要な転写因子forkhead box G1 (FOXG1) をコードしている. このように非典型的Rett症候群の病態は, 典型的Rett症候群とは異なることを理解する必要がある.
1 0 0 0 OA 鼻腔壁面における粘膜の乾燥と加湿を考慮した鼻腔の熱流体解析
- 著者
- 北川 和佳
- 巻号頁・発行日
- 2010-03
Supervisor:松澤照男教授
1 0 0 0 OA 死の隠喩と死生観 : メキシコ・シティにおける「死者の日」を中心に
- 著者
- 佐原 みどり
- 出版者
- 名古屋大学大学院国際開発研究科
- 雑誌
- 国際開発研究フォーラム (ISSN:13413732)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.165-179, 2005-03-11
Talking about death by way of metaphor is something inevitable in all societies for its incomprehensible nature. But in some cultures, the theme of death is emphasized more than others. Mexican popular culture of death doubtlessly belongs to this category, and has enormous variations of metaphors, phrases, and proverbs related to death. Mexican language of death has been developed through the 20th century, which experienced the Mexican revolution and the rise of nationalism in which the indigenous culture obtained new values. Through the rapid social changes in the 20th century, the metaphors of death have been newly produced and their implications in those words have changed depending on the social situation. In this article I will focus on the Mexican expressions of “to die” and by categorizing them I will try to see the connections between Mexican national identity, social problems, historical consciousness and the way they perceive death. Other than language aspect, I will also discuss self-other relationship in the way they celebrate “the days of dead”, Mexican national festival in Mexico City.
1 0 0 0 OA 中将棋と詰みの概念における将棋種の変遷に対する考察
- 著者
- 古村 沙智代 佐々木 宣介 橋本 剛 飯田 弘之
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告ゲーム情報学(GI)
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, no.27(2001-GI-007), pp.33-39, 2002-03-15
将棋種の起源に関する研究はたくさんなされているが,文献上の記述があいまいで,実際にどのようにプレイされていたのかを正確に知ることはできない.そのような中で,将棋種の進化論的変遷を解明するためにゲーム情報学的アプローチと呼ばれる,コンピュータ解析を用いたゲーム比較が注目されるようになった.本稿では,その過程と,今後の課題,そして,現時点で取り組むべき,重要な課題について述べる.本稿で焦点を当てる2点は,将棋種の進化の過程で盤サイズの大きい将棋種はほぼ絶滅したにもかかわらず生き残っている中将棋,そして,詰めの概念が導入された経緯,についてである.
1 0 0 0 IR 書評 須永恵美子『現代パキスタンの形成と変容 : イスラーム復興とウルドゥー語文化』
- 著者
- 拓 徹
- 出版者
- 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科附属イスラーム地域研究センター
- 雑誌
- イスラーム世界研究 = Kyoto bulletin of Islamic area studies (ISSN:18818323)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.324-329, 2017-03
1 0 0 0 OA リビングラジカル重合の進展
- 著者
- 藤田 健弘 山子 茂
- 出版者
- 合成樹脂工業協会
- 雑誌
- ネットワークポリマー (ISSN:13420577)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.4-13, 2017-01-10 (Released:2017-06-14)
- 参考文献数
- 81
リビングラジカル重合(LRP)はラジカル重合において分子量と分子量分布,およびブロック共重合体を通じてモノマー配列を制御する合成法である。1993 年のGeroges らの報告以来,新しい方法の開発と高分子材料への応用が広がってきている。本稿では,LRP の鍵である休止種の活性化に焦点を絞り,最近の二つの進歩について紹介する。一つは,光を用いる休止種の活性化である。これにより,生成ポリマーの構造の制御の向上や,触媒の低減化などが可能になってきている。もう一つは非共役モノマーのLRP である。非共役モノマーの成長末端ラジカルは共役モノマーの末端に比べて不安定であり,休止種の活性化が難しいため,その進展は限られていた。しかし,重合系をうまく選択することで,さまざまな非共役モノマーがLRP に利用できるようになってきている。これらの進展により,LRP の可能性がさらに広がってきている。
- 著者
- 武田 和也
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 国立国会図書館月報 = National Diet Library monthly bulletin (ISSN:00279153)
- 巻号頁・発行日
- no.711, pp.1-6, 2020-07
1 0 0 0 OA 蕗原拾葉
- 著者
- 長野県上伊那郡教育会 編
- 出版者
- 鮎沢印刷所
- 巻号頁・発行日
- vol.第16輯, 1940
1 0 0 0 OA 立位大腿拳上動作における体幹・骨盤・大腿リズムの加齢変化
- 著者
- 本島 直之 関屋 昇 山本 澄子
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- pp.11570, (Released:2019-09-28)
- 参考文献数
- 34
【目的】立位での大腿拳上運動は日常生活動作と密接な関わりがある。そこで,立位大腿拳上運動を三次元的に解析し,大腿挙上,骨盤傾斜および体幹運動の関係と,それらへの加齢の影響を明らかにすることを目的とした。【方法】対象は健常成人20 名(若年者,高齢者各10 名)とし,運動課題は静止立位と立位からの片脚大腿拳上運動とした。三次元標点計測により体幹傾斜,体幹屈曲,骨盤傾斜,大腿傾斜角度および骨盤と体幹の位置を,床反力計測により足圧中心位置を求め,それらの関係を検討した。【結果】立位姿勢は両群に差は認められなかった。骨盤後傾,骨盤側方傾斜および体幹前屈運動は若年者,高齢者ともに大腿挙上角度に対して一定の割合で直線的に増大し,その割合は高齢者において小さかった。【結論】立位での大腿挙上運動における体幹・骨盤・大腿リズムの存在と加齢の影響が明らかとなり,大腿挙上運動を評価する際に体幹も含めて行う必要性が示唆された。
1 0 0 0 アイヌ文献目録 : 資料紹介
- 著者
- アイヌ文献目録編集会 [編]
- 出版者
- 北海道立アイヌ民族文化研究センター
- 巻号頁・発行日
- 2005
- 著者
- Tomoko FUKUUCHI Shun-suke MORIYA Toru SUGIYAMA Hidetsugu TABATA Kiyoko KANEKO
- 出版者
- The Japan Society for Analytical Chemistry
- 雑誌
- Analytical Sciences (ISSN:09106340)
- 巻号頁・発行日
- pp.20P252, (Released:2020-09-11)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 霧島火山群高千穂複合火山の噴火活動史
- 著者
- 井ノ上 幸造
- 出版者
- Japan Association of Mineralogical Sciences
- 雑誌
- 岩鉱 (ISSN:09149783)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.1, pp.26-41, 1988-01-05 (Released:2008-03-18)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 11 10
Takachiho composite volcano, located in south Ky ?? sh ??, Japan, is one of major members of the Kirishima volcano group. The composite volcano consists of four volcanic edifices which are partly overlapping and aligned in E-W direction. On the basis of field geology and tephrochronology, its growth-history can be divided into four stages. During the first stage, a conical stratovolcano, Futagoishi, was formed in the eastern end of the composite volcano. It is com-posed of an alternation of pyroclastic beds and lava flows. The activity of Futagoishi ended before the eruption of Ito pyroclastic flow deposit (22, 000 yBP) from the Aira caldera. The second stage activity started about 10, 000 years ago, after a repose of more than 12, 000 years. It was characterized by vulcanian eruption which continued semi-persistently through a long period of time, probably more than a thousand years. During this period a stratovolcano, Old-Takachiho, was built up on the western flank of Futagoishi, and a large amount of volcanic ash accumulated concentrically around the volcano. The third stage activity was characterized by the eruption of several thin lava flows and scoria from the vent close to Old-Takachiho Volcano. This activity resulted in formation of a small conical stratovolcano, Takachiho-no-mine, on the western slope of Old-Takachiho. At the end of this stage, enormous lava flows were successively effused from the top crater and flowed downward widely. Later lava flows, however, did not reached the foot of the slope due to decrease in effusion rate and piled up around the crater, resulting in the construction of an exogeneous lava dome on the summit. After several hundred years of quiescence, the present stage activity began about 2, 500 years ago. This activity was characterized by sub-plinian eruptions which occurred intermittently and produced thick scoria and ash beds on the eastern foot of the composite vlocano. By repeated eruptions of a great volume of scoria and lava flows, a new vlocano, Ohachi, was born on the western flank of Takachiho-no-mine volcano, and has been active since then. The growth-history of Takachiho composite volcano revealed the following two features: 1) the volcanic activity may have been controlled by the underlying E-W fracture, as suggested by the shifting of the vent position from east to west, and 2) the styles of explosive activity of the composite volcano have gradually changed with time from vulcanian eruption to sub-plinian one.
1 0 0 0 IR 普遍的観点からみた象徴天皇制
- 著者
- 山下 正男
- 出版者
- 京都大学人文科学研究所
- 雑誌
- 人文学報 (ISSN:04490274)
- 巻号頁・発行日
- no.66, pp.p133-156, 1990-03
英文目次誤植修正済. (原文)The Tenno (The Emperor) in the Present Constitusion of Japan
1 0 0 0 OA 不等ピッチ2段ばねのサージング防止効果
- 著者
- 柴田 蔵六
- 出版者
- Japan Society of Spring Engineers
- 雑誌
- ばね論文集 (ISSN:03856917)
- 巻号頁・発行日
- vol.1969, no.14, pp.55-60, 1969-03-15 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1