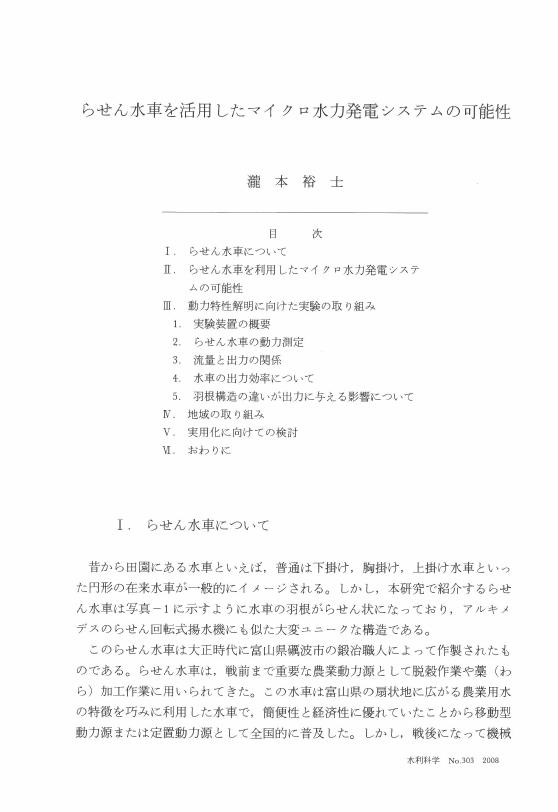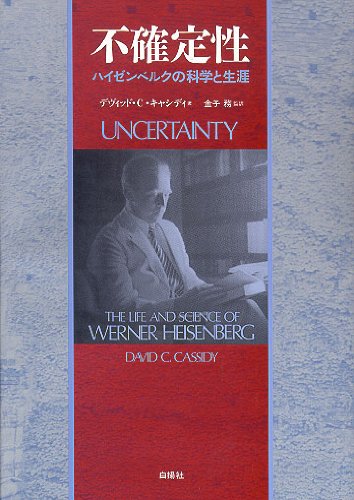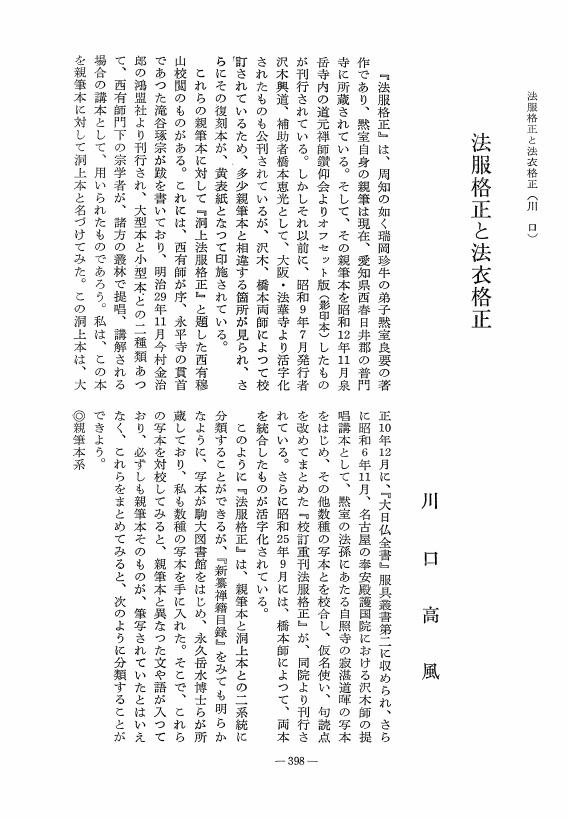1 0 0 0 OA P. ブルデュー社会学における「国家と教育」論
- 著者
- 小澤 浩明
- 出版者
- 日仏社会学会
- 雑誌
- 日仏社会学会年報 (ISSN:13437313)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.89-112, 2014-11-30 (Released:2017-05-29)
Dans cette étude,nous voulons reconstituer la théorie de « État et Système d’éducation » par la sociologie de Pierre Bourdieu. Premièrement,nous étudions la definition de l’État par P. Bourdieu et sa valeur. Nous avançons que il considére l’ État comme «la dernière instance » du pouvoir symbolic ,donc il doit l’analyser pour la théorie du pouvoir symbolic. Deuxièmement,nous prouvons trois traits de l’analyse de l’État par P. Bourdieu. :1) l’analyse de la concentration du capital dans la genèse de l’État, 2) l’analyse du champ pouvoir(bureaucratique), 3) l’analyse de la relation entre l’ État et l’institution ecole qui contibue la reproduction de capital. Troisièmement, nous examions “La Nobless d’État” (1989) à quatre points de vue. 1) Sur un rôle essentile de la sociologie de éducation comme l’analyse des «mécanismes » de la reproduction de structures sociales et de la reproduction structure mentales dans la sociologie que P.Bourdieu construit, 2) Sur la relation entre la genèse de nobless de l’État et le système d’éducation, 3)Sur la transformation de la mode de reproduction de classe dominante, 4)Sur la légitimation de domination par méritocratie. Enfin,P.Bourdieu pense que la genèse de l’Éta fait inévitablement avancer l’universel, donc nous devons discuter comment on peut changer l’insitution école comme le champ de reproduction en comme le champ d’accès à l’universel.
1 0 0 0 OA らせん水車を活用したマイクロ水力発電システムの可能性
- 著者
- 瀧本 裕士
- 出版者
- 一般社団法人 日本治山治水協会
- 雑誌
- 水利科学 (ISSN:00394858)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.4, pp.1-14, 2008-10-01 (Released:2017-10-27)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 検見川浜を対象にした人工海浜の侵食過程に関する研究
- 著者
- 熊田 貴之 小林 昭男
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 海洋開発論文集 (ISSN:09127348)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.315-320, 2000 (Released:2011-06-27)
- 参考文献数
- 4
In this paper, the results of the field survey on the coastal erosion at Kemigawa beach as the artificial beach are presented, and causes of the erosion are discussed using the sea conditions and the grain-size distribution of sands of the beach. The results of the investigation are summarized as follows:(1) The erosion at Kemigawa beach is intense compared with neighbor artificial beaches that has a characteristic like the Kemigawa beach.(2) The result of the numerical analysis using the cross section of the construction plan shows that the wave conditions of near shore at Kemigawa beach is calmness in the stormy weather.(3) The results of the grain-size analysis of sands show that the small-size sands that flow away from the center of Kemigawa beach maybe deposit at the base of the breakwater.(4) The result of the comparison between d50 of the sands and the gradient of the foreshore about the construction plan of Kemigawa beach shows that the beach has the tendency of the erosion.
1 0 0 0 OA 針葉樹人工林における強度間伐後の広葉樹侵入に及ぼすシカ採食の影響
- 著者
- 島田 博匡 野々田 稔郎
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.1, pp.46-50, 2009 (Released:2009-03-24)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 4 5
シカの生息密度が高い地域内で強度間伐 (本数間伐率47.5∼71.2%) を行った針葉樹人工林に獣害防護柵を設置し, 間伐後の広葉樹侵入に及ぼすシカ採食の影響を調査した。獣害防護柵内では先駆種を中心とする多数の広葉樹が間伐後に侵入し, その生残率は高く, 樹高成長も良好であった。しかし, 柵外では柵内よりも広葉樹の侵入が少なく, 生残率も低かったため, 2年後まで生残した個体はわずかであった。このことから, 柵外ではシカの採食により間伐後の広葉樹侵入が強く阻害されていると考えられた。シカ生息密度が高い地域において, 人工林の針広混交林への誘導を目指すには, 強度間伐を行った場合にシカ採食が顕在化する生息密度の解明と施業地へのシカの集中を防ぐ簡便な手法の開発が必要である。
1 0 0 0 OA ベルクソン的直観における実在性と形式性
- 著者
- 清塚 明朗
- 出版者
- 東洋大学国際哲学研究センター
- 雑誌
- 国際哲学研究 = Journal of International Philosophy (ISSN:21868581)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.195-202, 2020-03
1 0 0 0 OA 高標高域における標高傾度がカシノナガキクイムシの脱出消長と捕殺飛翔数に与える影響
- 著者
- 福沢 朋子 新井 涼介 北島 博 所 雅彦 逢沢 峰昭 大久保 達弘
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.1, pp.1-6, 2019-02-01 (Released:2019-04-01)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1 1
カシノナガキクイムシ(以下,カシナガ)によるナラ類集団枯損被害(以下,ナラ枯れ)は標高300 m以下で多く発生するが,富山県などで標高1,000 mを超える被害が確認されているため,被害が高標高域へと拡散している可能性がある。カシナガの繁殖成功度などは標高の上昇・気温の低下と負の関係があり,今後ナラ枯れの拡大予測や予防を行う上で,高標高域におけるカシナガの脱出・飛翔に関する生態的知見は重要である。本研究では,標高傾度に沿ったカシナガ成虫の脱出消長や数,林内における飛翔数とその季節変化を明らかにすることを目的とした。2015年6~12月,2016年6~11月にかけて,標高600~1,000 mの標高100 mごとに衝突板トラップと脱出トラップを設置し,カシナガ成虫を捕殺した。本研究の結果,標高600 m以上の高標高域では低標高域に比べてカシナガの繁殖成功度は極めて低く,標高600~900 mの範囲では,標高傾度の影響はなかった。さらに標高900 m以上では,樹種組成の変化で主な寄主であるミズナラが減少する影響を受けて,飛翔成虫が極めて少ないと考えられた。
1 0 0 0 「欅坂46」の「不協和音」と青年期の発達課題
- 著者
- 夏目 誠
- 出版者
- 産業医学振興財団
- 雑誌
- 産業医学ジャーナル (ISSN:0388337X)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.77-79, 2018-03
1 0 0 0 OA 卓上走査型電子顕微鏡による細菌バイオフィルムの観察
- 著者
- 今野 法子 安川 洋生
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.27-28, 2013 (Released:2018-04-07)
- 参考文献数
- 3
私たちヒトは約 60 兆個の細胞が情報交換しながら一つの個体を作る多細胞生物だが,細菌は個々の細胞が独立して生活する単細胞生物である.そのため細菌は独自に生活していると考えられていたが,最近の研究により細菌は集合体を形成し,互いに共存していることが分かった.その細菌の集合体をバイオフィルムという.本演題では,子供たちが身の回りの細菌について理解を深め,科学教育への興味を増してもらえるように,食品微生物や環境微生物のバイオフィルム形成と,操作の簡単な卓上走査型電子顕微鏡によるバイオフィルムの観察法を紹介する.
1 0 0 0 OA テーラワーダ仏教と大乗仏教
- 著者
- 長崎 法潤(訳) ラーフラ W.
- 出版者
- 大谷大学佛教学会
- 雑誌
- 佛教学セミナー = BUDDHIST SEMINAR (ISSN:02871556)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.89-97, 1978-10-30
1 0 0 0 OA 電波再帰反射攻撃の実用性評価
- 著者
- 若林 哲宇 丸山 誠太 星野 遼 森 達哉 後藤 滋樹 衣川 昌宏 林 優一
- 雑誌
- コンピュータセキュリティシンポジウム2017論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.2, 2017-10-16
電波再帰反射攻撃(RFRA: RF Retroreflector Attack)とはサイドチャネル攻撃の一種である.盗聴を行いたいターゲットにFETとアンテナから構成されるハードウェアトロイ(HT)を埋め込み,そこへ電波を照射するとHTを流れる信号が反射波で変調されて漏洩する.攻撃者はこの反射波を復調することでターゲットの信号を盗聴することが可能となる.反射波の復調にはSDR(Software Defined Radio)を利用する方法が安価で簡単であるが,性能の限界が専用ハードウェアと比較して低い.本研究ではSDRによる電波再帰反射攻撃の脅威を示すとともにその限界を調査した.
1 0 0 0 OA 鉄道会社による駅ビル・駅ナカ事業の展開 : JR東日本グループを事例として
- 著者
- 長岡 亮介
- 出版者
- 法政大学地理学会
- 雑誌
- 法政地理 = JOURNAL of THE GEOGRAPHICAL SOCIETY OF HOSEI UNIVERSITY (ISSN:09125728)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.47-58, 2013-03-21
本稿では,鉄道会社の関連事業について,これまでの空間的展開と戦略性を明らかにする.私鉄企業の不動産事業が中心であった先行研究とは異なり,国鉄時代を含めたJR東日本グループの商業施設(駅ビル・駅ナカ事業)を対象とした国鉄時代~現在に至る駅ビル・駅ナカの開発は,当時の法律・社会情勢の違いにより,時期区分ごとの内容が大きく異なるこのような背景のもとJR東日本は,国鉄から引き継いだ優良な資産と豊富な資金力を活用し,各駅に見合った開発を進めてきた.その結果,バブル経済崩壊やリーマンショックにより苦戦している他の商業施設と対照的に,順調に収益を上げることに成功した.しかし今後は,更なる利用客の減少に備えて,まちづくりやバリアフリーの観点を取り入れた新たな事業展開が必要とされている.
1 0 0 0 不確定性 : ハイゼンベルクの科学と生涯
- 著者
- デヴィッド・C・キャシディ著 伊藤憲二 [ほか] 訳
- 出版者
- 白揚社
- 巻号頁・発行日
- 1998
1 0 0 0 松雲公採集遺編類纂
- 著者
- 金沢市立図書館 砺波図書館協会複製
- 出版者
- 富山県図書館協会
- 巻号頁・発行日
- 1965
1 0 0 0 高齢期難聴がもたらす影響と期待される介入の可能性
- 著者
- 内田 育恵
- 出版者
- 日本音声言語医学会
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.143-147, 2015
聴覚障害は加齢とともに有病率が高くなる代表的な老年病で,われわれが地域住民対象研究から算出した推計値によると,65歳以上の高齢難聴者は全国で約1,500万人に上る.わが国が対応すべき緊要な課題の一つである.<br>個人や社会に対して高齢期難聴がもたらす負の影響は,抑うつ,意欲や認知機能の低下,脳萎縮,要介護または死の転帰にまで及ぶと報告されている.一方,高齢期難聴に対する介入の有効性検証はいまだ限定的である.現時点では,補聴器使用により認知機能維持や抑うつ予防が可能かどうか結論にいたっていない.<br>年齢がより高齢になると,語音明瞭度は悪くなり補聴効果をすぐに実感するのは困難になる.補聴による聴覚活用は"リハビリテーション"であって,トレーニングによる恩恵が,耳以外にも波及する可能性があることを,難聴者本人や社会に向けて啓発する必要がある.
1 0 0 0 OA 難治性喘息の新規非薬物療法:気管支サーモプラスティ
- 著者
- 杉山 温人
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, no.4, pp.836-842, 2017-04-10 (Released:2018-04-10)
- 参考文献数
- 8
BT(bronchial thermoplasty)とは,気管支鏡を使ってカテーテルを気管支にまで到達させ,気管支に直接,高周波電流を流すことによって,気管支平滑筋量を減少させるという非薬物的治療法である.高用量の吸入ステロイド薬と長時間作用性気管支拡張薬の合剤によってもコントロール不十分な難治性喘息に対する新規治療法として,2015年4月より保険収載された.大規模試験として行われたAIR2試験では呼吸機能の改善は認めないものの,QOL(quality of life)の改善や重篤な喘息増悪回数,救急受診回数の減少が認められた(最長5年間の経過観察にて).副反応としては,喘息増悪,喘鳴,呼吸困難,胸痛,下気道感染,無気肺,血痰などが認められたが,重篤な事象はみられなかった.我々の施設でも,今までに計17症例のBTを安全に施行してきており,一部の症例では著明な呼吸機能の改善も認められた.今後,症例のさらなる集積が望まれる.
1 0 0 0 OA 法服格正と法衣格正
- 著者
- 川口 高風
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.398-401, 1975-12-25 (Released:2010-03-09)
- 著者
- 小林 博
- 出版者
- 日本産科婦人科学会
- 雑誌
- 日本産科婦人科学会雑誌 (ISSN:03009165)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.5, pp.521-530, 1968-05
生体にstressが加わるとcatecholamines〔(以下CAと略), adrenaline (以下Aと略), noradrenaline (以下NAと略), dopamine (以下DAと略) の総称で特にA, NAを指す〕が増量することは基礎的並びに臨床的な実験によって確かめられている. Selyeのstress学説による適応ホルモンの概念の導入によりCannonのemergency reaction と stressとの関連が問題とされて来たが, Selye自身も強調している如く, 適応ホルモンの機転が唯一の非特異的防禦手段ではなく, 自律神経系も又重要な役割を演じていることは疑いがない. 妊娠という試練を母体はどう受け止めるか. 妊娠中毒症はこの様な負荷に対する異常反応に基づく生体のbalanceの破綻 (換言すれば適合不全) によって起ると解されないだろうか. 著者はこの様な観点から自律神経系のneurotransmitterであり昇圧物質でもあるCAの妊娠中毒症における動態について検討を加えた. 尚測定に当っては尿中CAの測定に際し問題となっていたDOPAを除去する為, イオン交換樹脂Duolite C-25を使用した. その概要は以下の如くである. 1) 妊娠後半期になるとNAの平均値は上昇し, 高値を示すものもあり, かつバラツキも著明となり自律神経系の不安定性が示唆された. 2) 妊娠中毒症では毎日連続的に測定すると, NA値は必ずし.も血圧の動きとは関係なく, 周期的な波状の変動を示した. 全平均値は妊娠末期と差がない. この事から血圧上昇には血管のNAに対する感受性の光進も又重要な因子となることが推測される. 3) 分娩子癇の患者では子癇発作後 pheochromocytoma に於てのみみられる様な, 正常人の約30倍にも達するNAがspike状に放出され, 一たん減少後, 再び一見rebound的に上昇している. これは子癇独自の現象で, その意味ずけはいまだ困難である. 4) 尿中CA値と血圧とは相関関係が明らかでなく, CAが一次的に昇圧機序レこ関与するとしても, 二次的には, 他の昇圧機構ないし血圧維持機構が作働することが推測される. すなわちCAが妊娠中毒症の一元的な原因とはいえないが, 交感神経系が妊娠中毒症発症に関与していることは充分考えられる.
1 0 0 0 OA コンポーネント解析が診断に有用であった豆乳による重症アレルギー症例
- 著者
- 白崎 英明 関 伸彦 氷見 徹夫
- 出版者
- 日本口腔・咽頭科学会
- 雑誌
- 口腔・咽頭科 (ISSN:09175105)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.69-72, 2014-03-31 (Released:2014-08-20)
- 参考文献数
- 10
症例は71歳男性. 50歳頃より, 毎年春に花粉症症状あり. 同時期よりバラ科果物摂取時に口腔咽頭の掻痒感あり. 51歳時と2ヵ月前に豆乳摂取でアナフィラキシー症状あり, 精査目的で当科紹介受診した. Immuno CAP法による各抗原特異的IgE抗体値の検索では, シラカンバ花粉とバラ科果物 (リンゴ, モモ) に対する特異的 IgE は陽性であったが, 大豆特異的IgE抗体値は陰性であった. アレルゲンコンポーネント解析では, 大豆の Gly m4, とシラカンバ花粉の Bet v1 が陽性を示し, シラカンバ花粉と大豆の交差反応による花粉食物アレルギー症候群と診断した. アレルゲンコンポーネント解析は, 花粉抗原と食物抗原の交差反応の診断に有用であった.
はじめに 切開式重瞼術の術後は左右差のないこと,瘢痕が目立たないこと,閉瞼時の不自然な陥凹を生じないこと,重瞼線が消失しないことが重要であると筆者らは考えています。 切開法による重瞼作成は重瞼作成予定線より尾側の瞼板前組織の除去により,瞼板と皮膚裏面を癒着させ重瞼を作成する腱板固定法1〜3)が最も簡便であり手術時間も短いとされていますが,術後,閉瞼時に重瞼線の頭側と尾側で癒着による不自然な陥凹を生じることがあります。 瞼板固定法で生じた不自然な陥凹は,時間の経過とともに軽快すると考えている術者もいますが,実際は陥凹の修正目的で来院される患者も多いです。 昨今,眼瞼下垂症手術時の重瞼作成法として挙筋腱膜前転を併用した術式4)が報告されており,自然な重瞼術として知られています。また,一重瞼の患者は潜在的な眼瞼下垂症であることも多く,挙筋腱膜の前転と重瞼術を同時に行うことにより,開瞼をより大きくする美容外科手術5,6)も報告されています。 挙筋腱膜を前転させ,その尾側端と重瞼線の皮膚ないし皮下眼輪筋とを縫着し重瞼を作成する方法であるため,挙筋腱膜と重瞼線への連結を重瞼の正常構造にきわめて近く再建することで重瞼を作成しており1),理にかなった方法です。しかし,これらの術式は挙筋腱膜の前転幅が重瞼溝の皮下まで十分到達する長さの線維性組織を得られることが前提であると筆者らは考えています。 この方法を,下垂が軽度である若年者の厚い瞼に適応させると,挙筋腱膜の前転幅は2〜3mmにもかかわらず,瞼板から皮膚までの厚みがあるため連結に必要な長さを得ることができないことがあります。無理に縫合すると重瞼線の陥凹が強くなり,不自然となります。 筆者らは患者の瞼の厚さに見合った挙筋腱膜から重瞼線への線維性組織の再構築を行うことが,結果として自然な重瞼を得られるのではないかと考えており,挙筋前転と重瞼術を同時に施行する若年患者に対して,前転させた挙筋腱膜の余剰部分をフラップとして挙上し,皮下線維性組織として重瞼線を作成しています。フラップの長さを変えることで皮下組織の厚い瞼に対しても,閉瞼時に陥凹のない自然な重瞼が得られると考えています。本稿では実際の手術についての考え方と手順を紹介します。