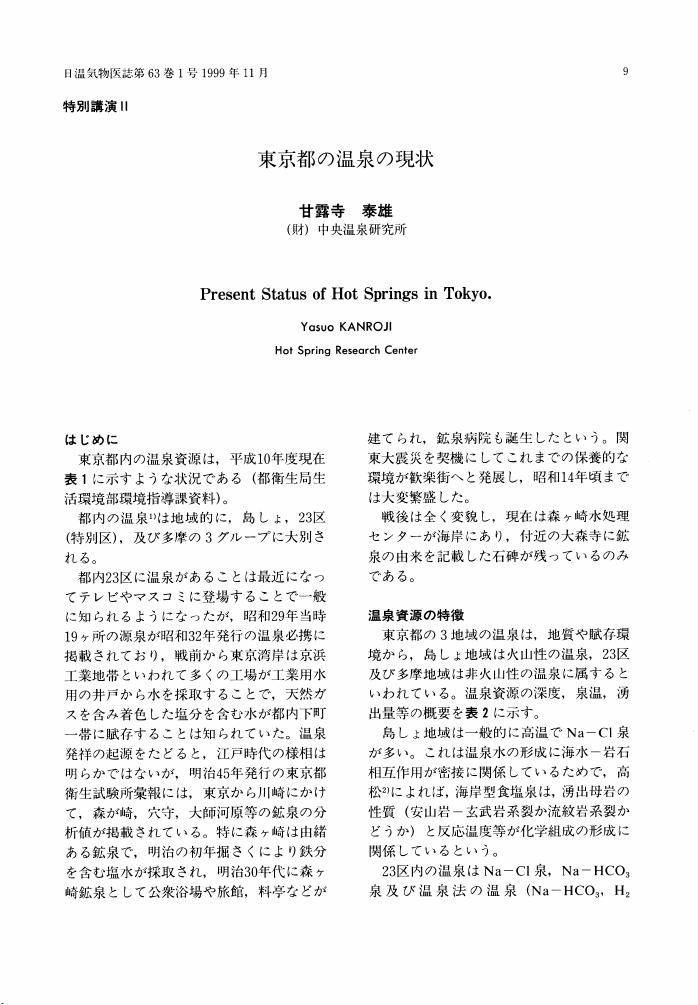1 0 0 0 OA 固体表面の濡れ性に対する表面粗さの効果
- 著者
- 今林 慎一郎
- 出版者
- 日本ポーラログラフ学会
- 雑誌
- Review of Polarography (ISSN:00346691)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.115-121, 2008 (Released:2008-11-07)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 9 13
Recent papers discussing the effect of surface roughness on wettability of solid surfaces are reviewed. Wenzel's and Cassie-Baxter's wetting models, factors determining the relative stability of the wetting models, and the control of the surface wettability by electrowetting are introduced.
1 0 0 0 IR 映画はいかにして「物語」から自由になりうるか
- 著者
- 坂尻 昌平
- 出版者
- 和光大学総合文化研究所
- 雑誌
- 東西南北
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, pp.115-126, 1998-03-20
1 0 0 0 IR 映画における時間--物語分析の観点から
- 著者
- 原田 邦夫
- 出版者
- 愛知県立大学
- 雑誌
- 愛知県立大学外国語学部紀要 言語・文学編 (ISSN:02868083)
- 巻号頁・発行日
- no.40, pp.145-170, 2008
1 0 0 0 OA 子育ち環境からみた子どもの育ち ─コホート研究成果とエンパワメントの必要性─
- 著者
- 安梅 勅江
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.4_28-4_33, 2010-04-01 (Released:2010-10-18)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 OA 好古麓の花
- 著者
- 高畠藍泉 (瓶三郎) 編
- 出版者
- 青山堂
- 巻号頁・発行日
- 1890
1 0 0 0 OA 2)生活習慣病と体内時計
- 著者
- 土居 雅夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.9, pp.1669-1674, 2016-09-10 (Released:2017-09-10)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 OA 単品定期通信販売における次回購入予測モデルの検証について
- 著者
- 北爪 聖也 松本 知己
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第34回全国大会(2020)
- 巻号頁・発行日
- pp.4Rin117, 2020 (Released:2020-06-19)
単品定期通信販売のECサイトのデータを使い、顧客が定期通販を継続するかを予測する次回購買予測モデルを作成した。 どのような特徴量が単品定期通信販売のECにおいて、顧客の定期購入の継続に影響を与えているのかを解釈する。 ロジスティック回帰を使用して特徴量の解析を行った。また、LightGBMを使用して、予測モデルを構築し、精度を評価した。 定期購入の継続に影響を与えていたのは、購入月や支払い方法やターゲット別に作成したランディングページであることが判明した。
- 著者
- 斉藤 利彦
- 出版者
- 佛教大学
- 雑誌
- 佛教大学総合研究所紀要 (ISSN:13405942)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.2, pp.77-156, 2004-12-25
1 0 0 0 相撲節会の勝負楽
- 著者
- 廣瀬 千晃
- 出版者
- 古代学協会
- 雑誌
- 古代文化 (ISSN:00459232)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.6, pp.322-333, 2004-06
- 著者
- 沼田 稔
- 出版者
- 一般社団法人 数学教育学会
- 雑誌
- 数学教育学会誌 (ISSN:13497332)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3-4, pp.13-15, 1997 (Released:2020-07-06)
代数的な式をグラフを使って解くという発想はどこから生まれているか。代数学の発展の中で,空間を解析するのに強力な方法を与えるために座標は導人された。グラフで方程式の解を求めると言うのはデカルトの精神に反する。また,この問題は具象と抽象についての本質的な問題を含んでいる。方程式に対応するグラフを描くのは方程式の一つの表現,描かれたグラフは具象であって,抽象的な方程式そのものではない。グラフをいくら読んでも方程式の解は得られないと言うことを意識化しなければならない。この問題は,小学校の算数,中学校の数学の間の数学教育の連続性と質の変化,さらには現代数学の方向とも係わっており,こうした視点から問題点を整理した。
- 著者
- 得丸 公明
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. TL, 思考と言語 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.244, pp.31-36, 2010-10-16
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 4
論理と感情は,原初的には生命の生存本能の不可分一体な発現であり,感情は感覚と遺伝子記憶とのパターン認識,論理は感覚と記憶の演算結果にもとづいて行動を引き起こす引き金として発展したと考えられる.高等生物は,後天的記憶を獲得・蓄積できるようになり,変転する世界に対応したより柔軟な記憶体系を構築するようになった.ヒトは,言語というデジタル符号メカニズムを獲得したために,感覚も記憶も決断もすべて言語の表現型で代用できるようになった.自然言語も人工言語もデジタルであり,表現型である.その背後にある遺伝子型の論理や感情を評価するためには,表現型を生みだす回路をモデル化することが必要である.筆者は言語を生みだす回路のモデルとして,3つの神経系(生理)モデルを提案する.神経系モデルは,論理が生命の生存本能の発現であることを前提としており,論理と感情が未分化で知能を持たない「反射モデル」,論理と感情が分化して知能の記憶をもつ「適応モデル」,言語による符号化処理が行われるヒトの「言語情報処理モデル」という3つの進化の段階に対応するため,言語に固有の問題を特定しやすい.
1 0 0 0 OA Lattice QCD Tool Kit in Fortran90
- 著者
- S. Choe 中村 純 野中 千穂 室谷 心
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子論研究 編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, no.1, pp.1-43, 2003-10-20 (Released:2017-10-02)
数値計算は専門ではないが,格子QCDのシミュレーションを道具として利用したい研究者のために開発されたコードLTKf90(Lattice Tool Kit in Fortran90)について報告する.プログラムの構造,使用法を紹介し,記述に使われたFortran90と格子QCDの簡単な解説を付録に与える.
1 0 0 0 OA 戦後新教育における経験主義国語教育摂取の実態 : 日米の国語教育観の差異を観点として
- 著者
- 坂口 京子
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 国語科教育 (ISSN:02870479)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, pp.43-50, 2007-09-30 (Released:2017-07-10)
In 1946, Helen Heffernan of the CIE (Civil Information and Education Section) introduced the concept of a "unit of work" in social studies. A unit of work involved most aspects of language teaching : knowledge, skill, habit, communicative attitude and criticism. In the subject of language teaching, Heffernan attached special importance to the expressive function and usefulness of language. Heffernan emphasized a "child-centered" principle in which teachers were required to develop the student's learning environment. Teachers focused on selecting teaching materials that were in line with the students' needs and interests. As a result, educators began to integrate the teaching of subjects with student experiences. On the other hand, a Japanese committee suggested that the Japanese language included a mentality centering on the self and relations with others. This rationale, of a mentality separate from the subject of Japanese, was in evidence in the prewar history of Japan as well. However, it was still possible to develop a unit teaching approach in Japanese class since the Japanese language overlapped most, if not all, language based teaching. Therefore, the child centered principle could be crystallized through the teaching of the Japanese language.
- 著者
- 谷口 英喜 牛込 恵子
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.381-391, 2017-07-25 (Released:2017-08-29)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2
目的:本研究では,自立在宅高齢者におけるかくれ脱水(体液喪失を疑わせる自覚症状が認められないにもかかわらず,血清浸透圧値が292から300 mOsm/kg・H2O)の実態調査を行い,非侵襲的なスクリーニングシートを開発することを目的とした.方法:65歳以上の自立在宅高齢者222名を対象に血清浸透圧値を計測し,かくれ脱水の該当者を抽出した.該当者において,脱水症の危険因子および脱水症を疑う所見に関してロジスティック回帰分析を行い,オッズ比を根拠に配点を行った.配点の高い項目から構成される自立在宅高齢者用かくれ脱水チェックシートを作成し,該当項目の合計点数の陽性的中率を求めリスク分類を行った.結果:自立在宅高齢者においてかくれ脱水の該当者は,46名(20.7%)であった.先行研究のかくれ脱水チェックシートを改良し,①トイレが近くなるため寝る前は水分補給を控える傾向がある(3点),②利尿薬を内服している(8点),③随時血糖値が126 mg/dl以上である(9点),④80歳以上である(3点),⑤男性である(4点),⑥体重60 kg以上である(3点),の6項目から構成される,自立在宅高齢者用かくれ脱水チェックシートを考案した.このシートにおいて,13点以上(合計30点)であればかくれ脱水である危険性が高いと考えられた(陽性的中率72%,陰性的中率85.6%;P<0.0001).結論:自立在宅高齢者においては,脱水症の前段階であるかくれ脱水が20.7%の割合で存在し,非侵襲的なチェックシートにより抽出が可能である.
1 0 0 0 OA 超高齢者大腿骨頸部骨折の歩行自立と自宅退院における問題点
- 著者
- 辻村 康彦 高田 直也
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.5, pp.303-306, 2006-08-20 (Released:2018-08-25)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2
超高齢者大腿骨頸部骨折の治療目標である,歩行自立能力の獲得や自宅退院は,身体・精神機能や社会的要因などの諸問題により困難を極めているのが現状である。そこで,当院にて治療を行った90歳以上の29例を対象に,退院時歩行能力,自宅退院率,自宅退院患者のADL能力の経時的推移につき調査し,その問題点を検討した。退院時歩行自立能力の獲得には,認知症の有無が大きな影響を与えていたが,合併症数は,ほぼ全例が複数の合併症を有していたことからそれによる影響はなかった。また,認知症に関しては,単に計画的な術後リハビリテーションの遂行が困難であることのみではなく,徘徊の危険性から患者家族の多くが,患者の積極的な歩行を望んでいないという特徴があった。また,自宅退院を困難とする原因は,歩行自立の可否よりも,超高齢者世帯における介護者自体が高齢者であることや,介護可能者数不足などの受け入れ体制の不備であった。一方,ADL自立レベルにて自宅退院した症例に対しては,家庭環境整備や外来通院での経過管理がその能力維持に有効であった。
1 0 0 0 OA 羽ばたき飛行における柔軟翼の有効性と三次元渦構造
- 著者
- 石出 忠輝 前野 一夫 劉 浩
- 出版者
- 木更津工業高等専門学校
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2016-04-01
本研究では,生物飛行の優位性を明らかにするために,主翼を柔軟な素材とし,ヒービング運動を付加した模型の空力特性を調査した.具体的には,ABS樹脂を造形剤とし三次元プリンタを用いて,翼幅及び翼弦方向にテーパを有する翼を種々製作し空気力測定を行った.その結果,翼幅及び翼弦方向共に,程良いテーパを与えると最大揚力係数が増加する事が確認できた.翼幅方向に適切なテーパを与えた場合,低迎角領域で揚抗比が大きくなることが見出された.空力特性と流体現象との関連性をPIVトリガー計測手法を用いて調査し,前縁剥離渦と後縁剥離渦との位置関係及びヒービング運動と空気力変動との位相差が重要である事が見出された.
1 0 0 0 OA 東京都の温泉の現状
- 著者
- 甘露寺 泰雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会
- 雑誌
- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.9-12, 1999 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 IR 日系カナダ人二世芸術家ロイ・キヨオカの生涯と芸術
- 著者
- Seki Yoshiko Lingley Darren Kiyooka Fumiko Nakagawa Fusa
- 出版者
- 高知大学人文学部国際社会コミュニケーション学科
- 雑誌
- 国際社会文化研究 (ISSN:1345871X)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.57-95, 2012-12-28
1 0 0 0 OA インフルエンザワクチンの効果を高める腸内細菌の同定
腸内細菌叢がインフルエンザウイルスに対する免疫応答の誘導に役立つ理由は不明である。今回、36℃で飼育したマウスは、22℃で飼育したマウスと比較して、インフルエンザウイルス、ジカウイルス、SFTSウイルスの感染後に誘導される免疫応答が低下することを見出した。36℃で飼育したマウスは摂食量が低下しており、この摂食量の低下が免疫応答の低下につながる要因のひとつであった。そこで36℃で飼育したマウスに腸内細菌由来代謝産物である酪酸、プロピオン酸、酢酸やグルコースを投与すると、低下していたウイルス特異的な免疫応答が部分的に回復することを見出した。
1 0 0 0 のろんじ考 -呪禁師のながれ-
- 著者
- 岩佐 貫三
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.414-417, 1975