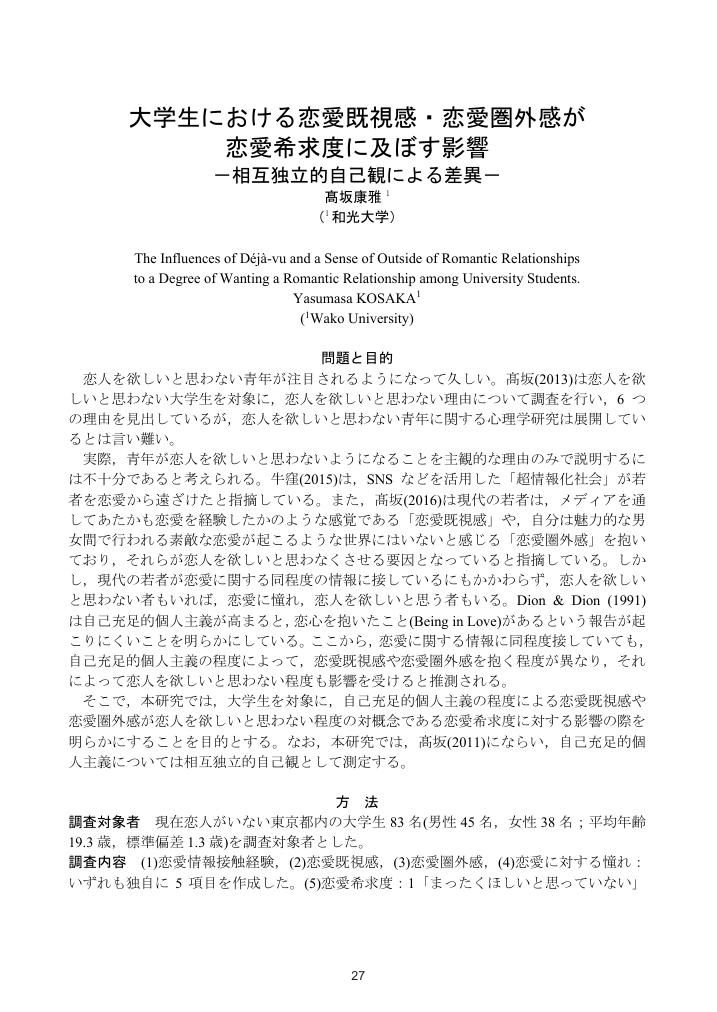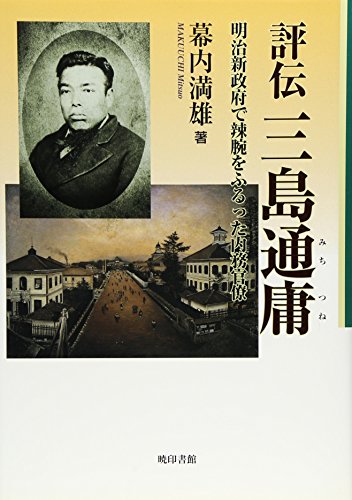1 0 0 0 OA 大学生における恋愛既視感・恋愛圏外感が恋愛希求度に及ぼす影響 相互独立的自己観による差異
- 著者
- 髙坂 康雅
- 出版者
- 日本青年心理学会
- 雑誌
- 日本青年心理学会大会発表論文集 日本青年心理学会 第27回大会 大会準備委員会 (ISSN:24324728)
- 巻号頁・発行日
- pp.27-28, 2019 (Released:2020-01-19)
1 0 0 0 IR シンポジウム 近世の公家文書と学芸 (シンポジウム報告 近世の公家文書と学芸)
- 著者
- 海野 圭介
- 出版者
- 人間文化研究機構国文学研究資料館
- 雑誌
- 調査研究報告 (ISSN:02890410)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.1-3, 2011
1 0 0 0 短冊の愉しみ (小特集 書が語る日本文化)
- 著者
- 海野 圭介
- 出版者
- [勉誠出版]
- 雑誌
- 書物学 = Bibliology
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.2-7, 2015-11
1 0 0 0 IR 国文学研究資料館蔵「古筆手鑑」(99-136)影印・解題
- 著者
- 海野 圭介
- 出版者
- 人間文化研究機構国文学研究資料館
- 雑誌
- 調査研究報告 = Report on investigation and research (ISSN:02890410)
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.161-207, 2016-03
1 0 0 0 OA 両大戦間期ドイツ児童文学における都市ベルリンの表象についての研究
1 0 0 0 明末清初の文芸思潮と仏教
1 0 0 0 OA 日本電気における原価管理システム進化の考察(3)
- 著者
- 前田 陽
- 出版者
- 小樽商科大学
- 雑誌
- 商学討究 (ISSN:04748638)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.187-206, 2008-07-25
論説
1 0 0 0 OA 誰を「日本人」らしいと見なすのか : 多文化社会におけるナショナルアイデンティティと教員
- 著者
- 髙橋 史子
- 出版者
- 東京大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 東京大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13421050)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.563-582, 2019-03-29
This article examines the national identity of Japan, by using a mixed method approach: a comparative study of a statistical analysis of the International Social Survey Program and a qualitative analysis of data obtained from interviews with public school teachers concerning ethnic and cultural diversity. The study finds that (i) “Japanese” is imagined as an ethnic and cultural sense of belonging, (ii) however, it is not imagined and shared in a civic sense, as national identities in the other countries are, (iii) the school teachers who teach the immigrant children express three different types of national identities : civic, ethnic, and cultural, and (iv) most teachers expect the immigrant children to maintain the ethnic and cultural identities associated with their (or their parents’) home countries. Based on the findings, the article discusses the role of schools and teachers in a multicultural society, and whether respecting ethnic and cultural diversity promotes or hinders the immigrant children’s equal participation in the host society, particularly within the social context where the ethnic and cultural national identities are widely shared, but the civic national identity is not. In addition, the author argues that within an ethnically and culturally diverse context, school is a place where the traditional ethnic Japanese national identity is challenged and reconstructed, and a civic Japanese national identity (which may enable the children to have a “hyphenated Japanese” identity) emerges.
1 0 0 0 OA イギリスにおけるエスニック・マイノリティ教育 : ロンドン市内の小学校を訪問して
- 著者
- 園部 陽子 Sonobe Yoko ソノベ ヨウコ
- 出版者
- 東京家政大学人文学部英語コミュニケーション学科
- 雑誌
- 英語英文学研究 (ISSN:13419129)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.60-70, 2009-09
1 0 0 0 OA Successful Vancomycin Desensitization with a Combination of Rapid and Slow Infusion Methods
- 著者
- Takatoshi Kitazawa Yasuo Ota Nanae Kada Yuji Morisawa Atsushi Yoshida Kazuhiko Koike Satoshi Kimura
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.5, pp.317-321, 2006 (Released:2006-04-03)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 9 13
Vancomycin, an antibiotic to which methicillinresistant Staphylococcus aureus (MRSA) is sensitive, frequently induces hypersensitivity reactions. Lowering the vancomycin infusion rate and/or premedicating with antihistamine effectively reduce hypersensitivity in most cases. However, vancomycin desensitization is sometimes the only way to ensure safe use. Two types of desensitization protocols have been reported, and these utilize different infusion intervals; rapid desensitization and slow desensitization. We herein report a case of vancomycin hypersensitivity with methicillinresistant Staphylococcus aureus infection. A combination of the two desensitization protocols, rapid desensitization followed by slow desensitization, effectively inhibited the hypersensitivity reaction during vancomycin infusion, and methicillinresistant Staphylococcus aureus was successfully eradicated.
1 0 0 0 OA 趙汀陽の「天下体系」についての一考察
- 著者
- 張 強
- 雑誌
- 国際学研究 = International studies (ISSN:21859779)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.94-111, 2020-03-20
1 0 0 0 OA 関係性についての一考察 : 贈与の視点から『千と千尋の神隠し』をよむ
- 著者
- 金子 亮太
- 雑誌
- 人文 (ISSN:18817920)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.86-102, 2014-03-01
人と人との関係を意識せずにはいられない。今日のこころの病とは他者との関係そのものの失調であるとさえ言える。河合(2004)は、現代人の病理が“関係性喪失の病”として現れることを指摘しており、またこの関係性の喪失は神話の喪失に他ならないとする。ここで言う「関係性」とは、単に対人的な関係を示すのではなく、個人の根源的な帰属意識やアイデンティティの基盤となるものであり、現代においてはそれが希薄になっているとの指摘である。また、神話は無意識的な経験知の体系として帰属意識やアイデンティティの根元たるコミュニティを形成すると考える。ここから、関係性が希薄になることと神話が失われることは表裏一体であるといえる。帰属意識やアイデンティティを形成するコミュニティが解体したことで、他者との結びつきも必然的に衰退したのである。\ところで、Mauss(1925/2008)は古代的社会における贈与が互恵的な関係を生み出すことを記述している。そこでは贈与が他者との関係性を結ぶものであったと考えられる。贈与とは、実在性やエネルギーの受け渡しであり、またその関係性そのものである。贈与によって、〈自〉と〈他〉は向かい合い、そこには体験やイメージが生み出され、〈自〉の主体感覚が生成されていく。また、それは同時に〈自〉/〈他〉の境界を再定義することでもある。〈自〉という主体が〈他〉という未知性・異質性と交わることで、ひるがえって〈自〉の同一性再認識することでもある。\贈与によって〈自〉は再構成され新たな可能性に開かれる。しかし、これは同時に〈他〉という未知性・異質性と交わることで主体はコントロールを失い、〈自〉が〈傷〉つき〈死〉にさえ直面する危機的な体験でもある。古代的文化においては、神話は経験知の体系として、コミュニティへの帰属意識として、このような〈傷〉つきにさえ意義を与えるものであったといえる。しかし、神話の失われた現代では、〈自〉の再構成する過程の中で主体は不可避に〈傷〉を負うこととなる。関係性の失われた現代において、心理臨床はこの〈傷〉つきの問題に向かい合わねばならない。\ In this paper, the relationships arise out of gift-giving. In modern clinical psychology, everything is associated with the relationships between people. It can be said that mental illness is a disorder in relationships with others.\ is has been indicated in modern pathology as a “disease of loss of relationships” by Kawai (2004). He also considers the loss of relationships as a counterpart to the loss of myth. “Relationships” signi es not only relationships with others, but also the primitive foundation of a sense of belonging or identi cation. He points out that these foundations have weakened in modern times. And It can be said that myths as the unconscious system of empirical knowledge can also make communities which is the root of a sense of belonging or identi cation. So the feebleness of relationships and loss of myths are referring to the same thing. And connection with others also inevitably declines.\ Incidentally, Mauss(1925/2008) has pointed out that the gift in ancient society produces a mutually bene cial relationship. e gift in ancient times is considered as a thing that creates relationships with others. e gift is commutation of substantiality or energy and the relationship itself. e gift is intended to match opposite <self> as subject to an <other>, then <self> obtains subjective senses by produced experiences or images. At the same time, it rede nes the borderline between <self> and <other>, and contributes to recognitions of identity of <self> concerned with <other> as strangeness or heterogeneousness.\ e gift is not only the experience of new possibility by <self> rede ning, but also critical experience of the confrontation of <pain> or <death> of <self>, through the subject’s losing controls when involved with <other>. In ancient culture, myths as the empirical knowledge or sense of belonging to community give signi cance to these <pain>. But, in modern age, the loss of myths, leaves the subject vulnerable to <pain> in the process of <self> reorganization. So in modern times, in clinical psychology the problem of <pain> has to be confronted when dealing with the loss of relationships.
1 0 0 0 OA 身体表現性障害が疑われた患者の予後―ペインクリニックにおける介入の効果についての考察―
- 著者
- 米本 紀子 米本 重夫 小林 俊司 神移 佳 井戸 和己 森本 正昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.61-64, 2020-02-25 (Released:2020-03-04)
- 参考文献数
- 9
身体表現性障害とは「検査所見に異常が無く,医師がその症状には身体的根拠が無いとするにもかかわらず,身体症状を反復して訴え,絶えず医学的検査を要求する」と定義される.身体表現性障害として紹介された8人が,当院ペインクリニックでの介入により,どのような経過をたどったか報告する.症例A~Cは未治療であった身体的根拠があり,その器質的原因に対する治療によって痛みが軽減し,生活機能が改善した.症例D~Fは生活機能が保たれており「慢性痛の治療目的は生活の質を改善していくことである」という説明を理解し,身体症状を反復して訴え完治を期待する言動をやめた.症例Gは8カ月後に解離性障害と診断され精神科入院となった.症例Hは,生活機能は保たれていたが慢性痛の説明に納得できず,1年後も身体表現性障害の言動を継続していた.以上より,身体表現性障害と診断されても,ペインクリニックの介入が有効なケースもあると考える.
1 0 0 0 OA 有機電子論の基礎となる cross-conjugation
- 著者
- 細矢 治夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会・情報化学部会
- 雑誌
- ケモインフォマティクス討論会予稿集 第37回情報化学討論会 豊橋
- 巻号頁・発行日
- pp.O06, 2014 (Released:2014-11-20)
- 参考文献数
- 7
現在世界的に流布している有機化学の成書や教科書の中で、不飽和共役炭化水素に関 する交差共役(cross conjugation)の概念の重要性について説いてあるものはほとんどない。演者は、グラフ理論的分子軌道法による解析を行った結果、この概念が有機電 子論の基礎的な裏付けに重要な役割を果たしていることを明らかにし、その適用限界の指摘も行うことができた。この理論は、芳香族性、反芳香族性の議論にまで展開することができる。なお、この議論はHMO法レベルのものであるが、より精度の高い理 論にも十分耐え得るものである
- 著者
- Yoshino Fukui Takeshi Uchida Hiroyuki Motomura
- 出版者
- The Japanese Society of Systematic Zoology
- 雑誌
- Species Diversity (ISSN:13421670)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.115-120, 2018-05-25 (Released:2018-05-26)
- 参考文献数
- 9
Ammolabrus dicrus Randall and Carlson, 1997, originally described from 14 specimens (21.0–94.1 mm standard length; SL) from Oahu, has to date been collected only from Wake Atoll and the Hawaiian Islands. Two juvenile specimens (18.4–21.4 mm SL) of A. dicrus, collected at a depth of 12 m off Taketomi Island, Yaeyama Islands (Ryukyu Islands) and described here in detail, represent the first specimen-based records from Japan. Ontogenetic changes and geographic variations are noted.
1 0 0 0 評伝三島通庸 : 明治新政府で辣腕をふるった内務官僚
- 著者
- 三谷 潤
- 出版者
- 日本全体構造臨床言語学会
- 雑誌
- 臨床言語研究 = JIST journal (ISSN:18834639)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.49-52, 2020
1 0 0 0 OA タレントマネジメント論(Talent Managements)に関する一考察
- 著者
- 守屋 貴司
- 出版者
- 立命館大学経営学会
- 雑誌
- 立命館経営学 = 立命館経営学 (ISSN:04852206)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2/3, pp.23-38, 2014-09
1 0 0 0 映画における昆虫の役割II
- 著者
- 宮ノ下 明大
- 出版者
- 日本家屋害虫学会
- 雑誌
- 都市有害生物管理 (ISSN:21861498)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.147-161, 2011-12-20
- 参考文献数
- 9