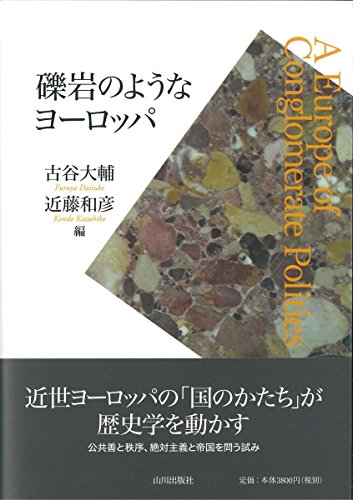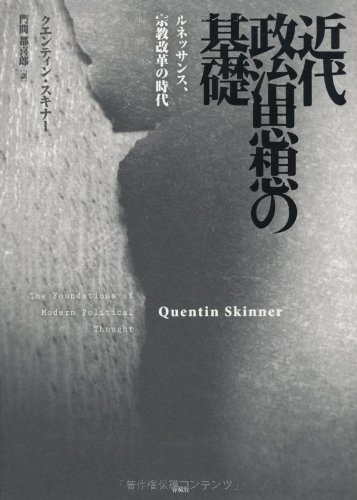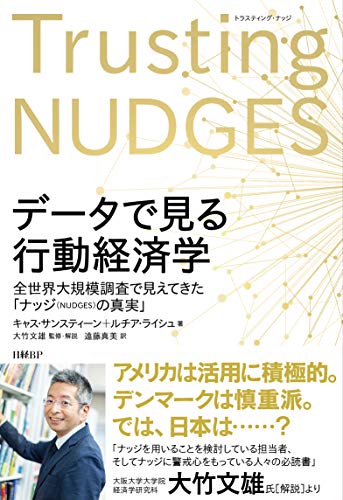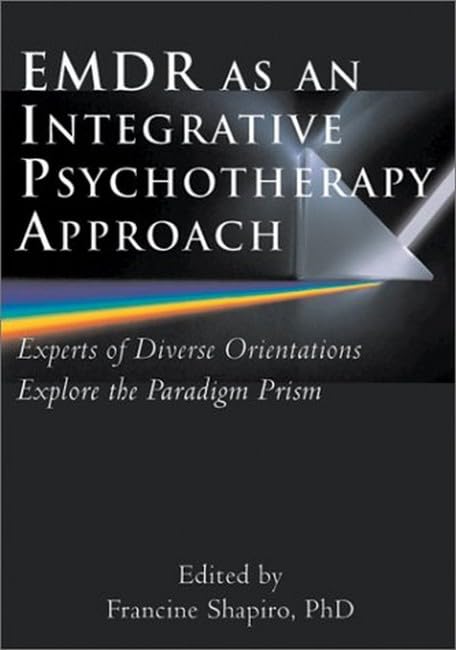1 0 0 0 一神教世界の中のユダヤ教 : 市川裕先生献呈論文集
- 著者
- 勝又悦子 [ほか] 編
- 出版者
- リトン
- 巻号頁・発行日
- 2020
1 0 0 0 礫岩のようなヨーロッパ
- 著者
- 古谷大輔 近藤和彦編
- 出版者
- 山川出版社
- 巻号頁・発行日
- 2016
1 0 0 0 近代政治思想の基礎 : ルネッサンス、宗教改革の時代
- 著者
- クエンティン・スキナー著 門間都喜郎訳
- 出版者
- 春風社
- 巻号頁・発行日
- 2009
1 0 0 0 IR 生まれ月が子供の心身におよぼす影響について
- 著者
- 今村 修 沢木 康太郎
- 出版者
- 東海大学体育学部
- 雑誌
- 東海大学紀要 体育学部 (ISSN:03892026)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.p73-79, 1989
A number of handicaps found in children who were born between January and March can be seen as related to the age cut-off date for entering the Japanese educational system. However, because problems related to classroom studies are usually resolved in the middle years of elementary school, and problems related to physical exercise are usually resolred at the junior high school level, the question of the month of birth has not been considered a serious problem. These conclusions have come into question as it has been observed that the effects related to the month of birth tend to remain over a long period. The purpose of this study is to challenge the above assumptions and to study the relationship between the month of birth and a child's physical and mental development. The results of this survey are as follows : 1) At some national high school sports events, including baseball, football, and track and field, the number of participants born between January and March was very low. 2) Female students born between January and March are able to overcome physical shortcomings at a comparatively early age. 3) Athletes born between January and March are able to overcome physical shortcomings through exercise. 4) Children born between January and March generally score lower on high school and university entrance exams. 5) Children born between January and March tend to exhibit serious personality and behavioral problems. 6) Parents, teachers, school adminitrators and other leaders must fully realize the above facts. Such children need special care and confidence-building.
1 0 0 0 ビザンツ帝国史
- 著者
- ゲオルグ・オストロゴルスキー著 和田廣訳
- 出版者
- 恒文社
- 巻号頁・発行日
- 2001
- 著者
- 染井 正徳 加藤 恵子 井上 里美
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.8, pp.2515-2518, 1980-08-25 (Released:2008-03-31)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 18 29
An improved procedure which avoids prolonged reaction at high temperature and handling under reduced pressure was found for the reduction of heteroaromatic and aromatic nitro compounds with aqueous titanium (III) chloride.
1 0 0 0 OA 力覚デバイスによる仮想彫刻訓練システムの構築
- 著者
- 神原 利彦 岩切 大知
- 雑誌
- 第82回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.1, pp.3-4, 2020-02-20
チェーンソーアートのような彫刻で美しい作品を作り出すには、刃物をどのように操り、どうやって削り出して行くかを経験を重ねて習熟する必要がある。だが、刃物自体が危険な物体であり、どんなに安全面で気をつけていても習熟の途中で疲労から負傷するおそれがある。そこで、本研究ではCGロボットアーム先端に付けた刃物を力覚デバイスで少し離れた場所から遠隔操縦し力加減などを仮想空間上で経験しながら安全に習熟していく彫刻訓練支援システムを提案する。刃物と物体の両方をボクセルで表現し、互いのボクセルが衝突した際に、物体ボクセルを消滅させることで、切削跡を表現する。お手本となる像を削らないよう切削する実験を行った。
1 0 0 0 OA ジーキル博士はなぜ自殺したのか : 「ジーキル博士とハイド氏」に描かれた悪「偽善」
- 著者
- 豊島 冴子
- 雑誌
- 北星学園大学大学院論集 = Hokusei Gakuen University Graduate School Review (ISSN:18845428)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.295-306, 2012-03
- 著者
- キャス・サンスティーン ルチア・ライシュ著 遠藤真美訳
- 出版者
- 日経BPマーケティング (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2020
- 著者
- 尾形 明子
- 出版者
- 日本民主主義文学会
- 雑誌
- 民主文学 (ISSN:13425587)
- 巻号頁・発行日
- no.623, pp.106-112, 2017-08
1 0 0 0 OA 中学校教員の異動後の困難に関する研究
- 著者
- 町支 大祐
- 出版者
- 日本教師学学会
- 雑誌
- 教師学研究 (ISSN:13497391)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.37-45, 2019 (Released:2019-07-09)
- 参考文献数
- 28
近年,異動が教員にネガティブな影響を与える可能性が指摘されている。本研究は,その要因の一つになっていると考えられる「異動後の困難」の様相を明らかにすることを目的とする。加えて,本研究では初めての異動に着目する。異動の影響はキャリアの長さ等によって異なり,かつ初めての異動が最も大きな影響を与えると言われているが,そこに着目した先行研究はないからである。教員10名を対象にインタビュー調査を行い,定性的コーディングを行なった結果,【ステークホルダーの特徴の違いへの対応困難】【仕事のやり方の違いへの対応困難】【周囲からの視線に関する難しさ】【信念とのズレに関する難しさ】という4つのカテゴリーが生成された。前者2つは先行研究でも指摘されてきたが,本研究を通じて,【周囲からの視線に関する難しさ】【信念とのズレに関する難しさ】という新たな2点を確認することができた。
1 0 0 0 OA 鉄道運転におけるセンサ技術の動向
- 著者
- 松本 雅行
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌E(センサ・マイクロマシン部門誌) (ISSN:13418939)
- 巻号頁・発行日
- vol.127, no.11, pp.461-466, 2007-11-01 (Released:2007-11-01)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 3
“Security” and “Stability” are an important pair in transport by rail, and to be important with both. Recently railway system supporting this becomes gigantic and becomes complicated. It means that it goes without saying that sensing technology is necessary to move these precisely.In this paper sensing technologies used for various fields of a railroad are described.
- 著者
- 天野 宏敏 原澤 彩貴 眞野 容子 細井 淳裕 古谷 信彦 藤谷 克己
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
- 雑誌
- 医学検査 (ISSN:09158669)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.339-346, 2019-04-25 (Released:2019-04-25)
- 参考文献数
- 16
尋常性痤瘡(ニキビ)は,90%以上の人が経験する一般的な疾患であり,角化異常および皮脂分泌の亢進などにより,Cutibacterium acnes(C. acnes)が増殖した結果,引き起こされる慢性炎症性疾患である。外見へ影響があるため,感情面での生活の質(QOL)への影響が大きい。本研究では,健常人におけるニキビ治療の実態把握やC. acnesの年代別保有状況を疫学的に調査,分析を行うことを目的とした。10代19名,20代20名,30代20名,40代20名の計79名を対象に,検体採取を行った後に,質問表式調査法による調査を行った。両頬におけるC. acnesの検出率は全体で82.3%であった。また検出率における年代および性別間では差が認められず,年代・性別を問わずC. acnesを保有していた。ニキビに対する対処法として,全体では洗顔をするが50.0%と最も多かったが,何もしないが16.4%であった。発症時期(自覚した時)は10代に最も多く認められた。治療を始めた理由として全体では,ニキビ痕が残ることが心配になった,人からの目が気になった,の2つが多く半分以上を占めていた。ニキビに関して,全体ではとくに関心をもっていないが最も多く,特に30代と40代で顕著であった。
- 著者
- edited by Francine Shapiro
- 出版者
- American Psychological Association
- 巻号頁・発行日
- 2002
- 著者
- 今井, 信治
- 巻号頁・発行日
- 2015
1 0 0 0 OA 土岐薬箱の調査
- 著者
- 服部 昭
- 出版者
- 日本薬史学会
- 雑誌
- 薬史学雑誌 (ISSN:02852314)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.69-74, 2018 (Released:2020-07-15)
I investigated the Toki Medicine Chest, named after its owner Takanobu Toki (Okayama Prefecture). The Toki Medicine Chest consisted of two boxes, one large and one small. This combination of large and small boxes is similar to that of the Katagiri Medicine Chest reported previously. However, in the case of the Toki Medicine Chest, it is believed that the chest was owned by the same person after confirming an analysis of the contents, which were crude drugs. In terms of medicine chest design, there wasn't any big difference between the Toki Medicine Chest and Katagiri Medicine Chest. Judging from the contents of the drugs found in it, the Toki Medicine Chest was likely used at the beginning of the Meiji era, not Edo. There were different types of medicines in the chest; not only local powdered drugs, but also imported drugs. Moreover, there were a few different drugs in glass bottles. The results reflect modernization of the medicine chest. The Toki Medicine Chest represents the end of the medicine chest era, and this report also reveals the beginning of the medicine cabinet.
- 著者
- 牧野 均 生駒 一憲
- 出版者
- 北海道文教大学 ; 2004-
- 雑誌
- 北海道文教大学研究紀要 = Bulletin of Hokkaido Bunkyo University (ISSN:13493841)
- 巻号頁・発行日
- no.40, pp.55-68, 2016-03
運動イメージ課題をリハビリテーションに効果的に応用するために,一人称イメージと三人称イメージの運動イメージ想起の方法の違いに着目し,機能的磁気共鳴画像法(functional magnetic resonance imaging ,以下f-MRI)を用いて脳活動部位の比較を行った。対象は,一人称イメージ課題群19名,三人称イメージ群17名である.結果,一人称イメージ課題群では,被験者自身の動く足趾映像を見ながら運動イメージ課題を行った場合,第三者の動く足趾映像を見ながら運動実行課題を行った場合と比較して,左角回と右紡錘状回の活動が増加した.三人称イメージ課題群では,第三者の動く足趾映像を見ながら運動イメージ課題を行った場合,被験者自身の動く足趾映像を見ながら運動実行課題を行った場合と比較して,左中前頭回ブロードマンの9野の後部領域の活動が増加した.一人称イメージ課題群と三人称イメージ課題群の群間比較では,三人称イメージとしての被験者自身の動く足趾映像を見ながら運動イメージ課題を行った場合,一人称イメージとしての第三者の動く足趾映像を見ながら運動イメージ課題を行った場合と比較して,左右の舌状回と右前帯状皮質の活動が増加した.これは,一人称イメージ課題と三人称イメージ課題に被験者自身と第三者を組み合わせることで相補的な制御で課題の遂行を行った可能性があることを示す.以上の結果より,一人称イメージを運動イメージ課題として用いる場合は被験者自身の足趾を見つめさせつつセラピストが他動的に足趾を動かすこと,三人称イメージ課題を用いる場合は向かいに座ったセラピストの足の動作を模倣しつつ同時にセラピストが他動的に足趾を動かすことが自己を認識しつつ効果的にリハビリテーションを行う可能性があると考える.
1 0 0 0 OA 文章要約課題遂行の間に提示された生活音の妨害感について
- 著者
- 東山 篤規 村上 嵩至 佐藤 敬子
- 出版者
- 日本環境心理学会
- 雑誌
- 環境心理学研究 (ISSN:21891427)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.1-9, 2014 (Released:2017-05-08)
- 参考文献数
- 13
文章理解に及ぼす無関連な聴覚刺激の有害的効果について研究した。実験1では,12人の参加者が3種類のテキストを読んで要約するという課題を行い,その課題の間に,雑踏音,人混み音,音楽,会話あるいはそれらの結合音を聴いた。課題の遂行が妨害されたと感じる閾が決定された。会話がもっとも有害的であり(低い閾),雑踏音と人混み音は比較的有害でない(高い閾)ことが見出された。実験2では,18人の参加者が,通常の雑踏音,音楽,会話だけでなく,それらを反対方向に再生した音も聴取した。正常あるいは逆再生された会話の平均騒音閾は,雑踏音や音楽よりも5dbほど低かった。これらの結果より,文章理解は,聴覚刺激の意味的特徴ではなく,音響的特徴によって,すなわち振幅パターンの豊富な分節によって妨害されることが示唆された。
1 0 0 0 OA PDE III阻害薬
- 著者
- 飯田 充 塩野 元美
- 出版者
- 日本大学医学会
- 雑誌
- 日大医学雑誌 (ISSN:00290424)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.5, pp.256-257, 2013-10-01 (Released:2014-12-30)
- 参考文献数
- 8
Phosphodiesterase III (以下 PDE III) 阻害薬は,PDE III を選択的に心筋および,血管平滑筋で阻害し,心筋収縮力増強と血管拡張作用を惹起するため,inodi-lator と呼ばれている.循環器領域では,現在では第一選択としては使用されてはいないが,ドブタミン,βブロ ッカーとの併用がよい成績をあげている.心臓外科領域においては,人工心肺中からの離脱時,冠動脈バイパス術のグラフト攣縮予防,腹部臓器灌流障害が起こりうる急性大動脈解離で使用している.