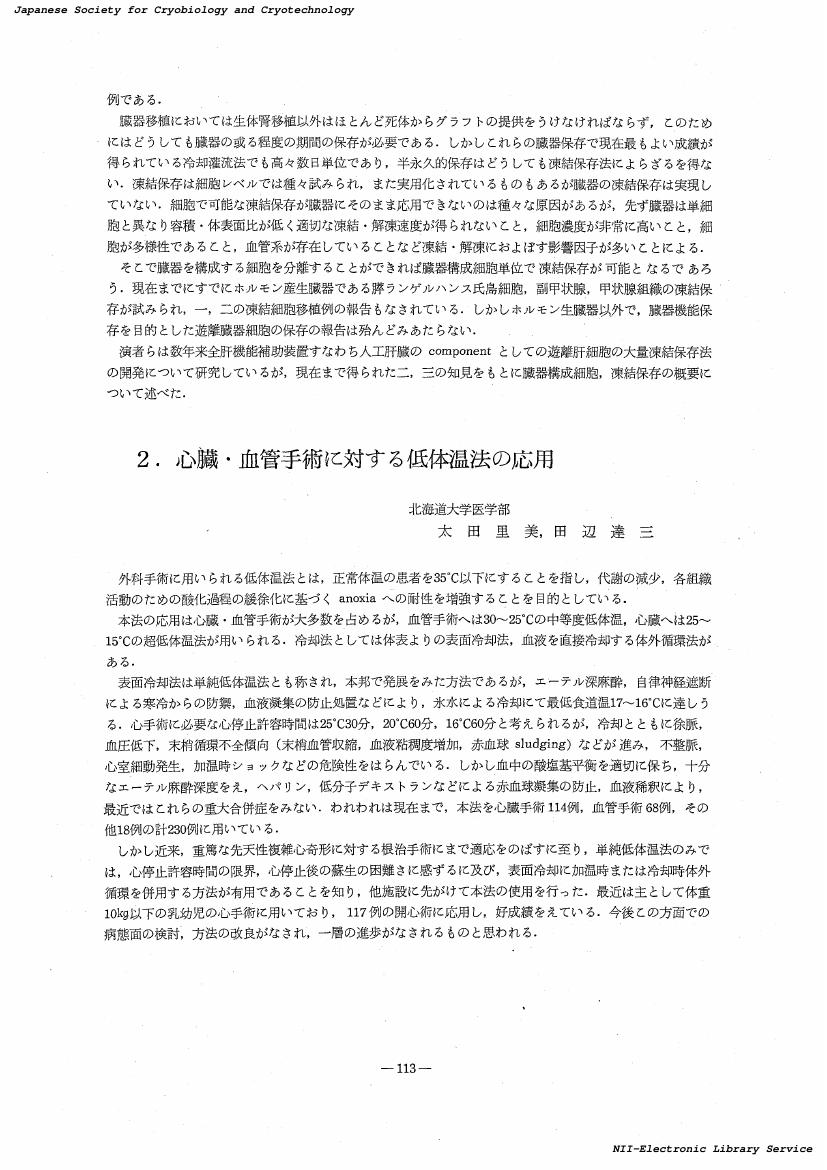1 0 0 0 OA 超撥水表面
1 0 0 0 OA クロアチア紛争後のコメモレーションによるナショナル・アイデンティティの強化と継承
- 著者
- 木戸 泉
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.74-100, 2020 (Released:2020-02-22)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 3
バルカン半島西部に位置するクロアチアは,1990年代のクロアチア紛争を経て,多民族国家ユーゴスラヴィアから独立を果たした.紛争終結から20年以上が経過した現在,クロアチア国内では紛争の記憶を強固にし,さらに次世代へ継承しようとする動きが見られる.特に激戦地となった都市ヴコヴァルでは,クロアチア系住民の紛争の記憶を強化し継承する行事の開催やモニュメントの設立が積極的に行われている.本研究では,それらの表象内容や設置主体を分析し,地域レベルと国家レベル,またナショナル・マジョリティとナショナル・マイノリティの間で,紛争に対する受け止め方に差異が生じていることを明らかにした.そしてこれを踏まえて,EU加盟を果たしたクロアチアという国家のナショナル・アイデンティティをめぐるダブルスタンダードについて検討を加えることができた.
1 0 0 0 OA 淡中双対定理の別証明
- 著者
- 岩堀 信子
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.34-36, 1958-12-15 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 2
- 著者
- 太田 里美 田辺 達三
- 出版者
- 低温生物工学会
- 雑誌
- 凍結および乾燥研究会会誌 (ISSN:02888297)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.113, 1981-09-20 (Released:2017-08-01)
1 0 0 0 OA 飛行機
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空學會誌 (ISSN:18835422)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.97, pp.365-379, 1943-05-05 (Released:2009-07-09)
1 0 0 0 OA 日本人の宗教意識に関する一考察
- 著者
- 加藤 智見 Chiken KATO 東京工芸大学女子短期大学部 Women's Junior College TOKYO INSTITUTE OF POLYTECHNICS
- 雑誌
- 飯山論叢 = Iiyama memoirs (ISSN:02893762)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.177-162, 1994
1 0 0 0 OA 新規レーザー光学技術を用いた生体マウス脳深部イメージングの現状
- 著者
- 根本 知己 川上 良介 日比 輝正 飯島 光一郎 大友 康平
- 出版者
- 日本植物形態学会
- 雑誌
- PLANT MORPHOLOGY (ISSN:09189726)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.31-35, 2014 (Released:2015-04-21)
- 参考文献数
- 15
2光子励起レーザー顕微鏡(2光子顕微鏡)は,低侵襲性や深い組織到達性といった特徴のため,神経科学を中心に,免疫,がんなどの他領域にもその使用が爆発的に広がっている.植物の研究領域においても,葉緑体の自家蛍光を回避することが可能であるため,2光子顕微鏡の利用は増加している.我々は2光子顕微鏡の開発とその応用に取り組んで来ているが,最近,生きたままでマウス生体深部を観察する“in vivo”2光子顕微鏡法の,新しいレーザー,光技術による高度化に取り組んでいる.特に共同研究者の開発した長波長高出力の超短パルスレーザーを励起光源として導入することで,生体深部観察能力を著しく向上させることに成功した.この新規“in vivo”2光子顕微鏡は,脳表から約1.4 mmという世界最深部の断層イメージング,すなわち,生きたマウスの脳中の大脳新皮質全層及び,海馬CA1領域のニューロンの微細な形態を観察することが可能になった.一方で,我々は超解像イメージングの開発にも取り組み,細胞機能の分子基盤を明らかにするために,形態的な意味での空間分解能の向上にも取り込んでいる.特に,我々は新しいレーザー光「ベクトルビーム」を用いることで,共焦点顕微鏡や2光子顕微鏡の空間分解能の向上にも成功した本稿では,我々の最新の生体マウス脳のデータを紹介しつつ,2光子顕微鏡の特性や植物組織への可能性について議論したい.
1 0 0 0 小島成斎の用印
- 著者
- 田村 南海子
- 出版者
- 書学書道史学会
- 雑誌
- 書学書道史研究 (ISSN:18832784)
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, no.22, pp.81-94, 2012
Kojima Seisai 小島成齋 (1796-1862) is referred to as one of the four great calligraphers of the <i>bakumatsu</i> 幕末 period, but there is much about his calligraphy and achievements that remains unclear. I have been conducting research on his works of calligraphy and his views on calligraphy, and in this article I focus on his signatures and seals added to completed works and the manner in which they were applied as part of an investigation into his calligraphic works.<br> First, I take up thirty-seven dated calligraphic specimens among publications and inscriptions and forty-two dated works bearing seals, and I carefully investigate the seal impressions of thirty-one seals used by Seisai, their wording and measurements, and the frequency with which they were used. I further undertook examinations of seals that were used especially frequently, and I determined that seals bearing his surname, his given name Chikanaga 親長, and his literary name Shisho 子祥 (島, 親長, 島親長, 子祥氏) may be considered to have been used from the age of seventeen to his early twenties when he was studying under Ichikawa Beian 市河米庵 (1779-1858); the seal 庫司馬印 is a seal carved in imitation of the <i>Qianziwen</i> 千字文 in cursive script by Huaisu 懷素 and may be supposed to have been used during his fifties; and the seals 源氏子節 and 源知足章 may be regarded as representative seals of his later years in view of the fact that both of these seals have been affixed to works mounted on hanging scrolls dating from when he was sixty-seven. Since there also exist forgeries of these last two seals, I point out that works attributed to Seisai may include forgeries, but the elucidation of further details will be a task for the future.<br> Next, I examined a distinctive method of affixing seals used by Seisai, namely, that of first writing his name or literary name and then affixing his seal on top of it. In view of the fact that similar examples can be found in the works of the Song-period Ouyang Xiu 歐陽脩, Su Dongpo 蘇東坡, Huang Tingjian 黄庭堅, and Mi Fu 米〓 and in Japanese works of calligraphy, I infer that Seisai followed this method because he regarded it as a traditional style of affixing seals. This can be understood as an example of his basing himself on revivalist thought and taking the Chinese classics as his norm in seals and methods of affixing seals too, just as he did in works of calligraphy in which he followed classical works. I believe that this examination of Seisai's use of seals will be useful for inferring the dates of his undated works too.
1 0 0 0 OA 和紙の変遷と未来像
- 著者
- 山下 実
- 出版者
- 公益社団法人 日本表面科学会
- 雑誌
- 表面科学 (ISSN:03885321)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.6, pp.307-309, 2017-06-10 (Released:2017-06-20)
- 参考文献数
- 6
歴史における日本の文化と和紙の変遷について振り返り,歴史に残る和紙製品の背景には大きな文化の発展があることを確認した。続いて,現代から将来にかけて社会情勢と和紙のあるべき姿について筆者の希望を含めて考察し,オリジナリティとデザインの力を借りること,小規模ながら精度の高い製造技術を持つこと,和紙生産者自らの未開拓用途の発掘をすること,環境性能のアピールと観光産業とのコラボレーションに需要拡大の道を切り開く可能性があるという考えを述べた。
1 0 0 0 OA 論文において研究データを引用するURLの同定
- 著者
- 角掛 正弥 松原 茂樹
- 雑誌
- 第82回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.1, pp.377-378, 2020-02-20
オープンサイエンスは、論文や研究データの参照や利活用を促進するための活動である。そしてその動きの一つとしてオープンデータが存在する。オープンデータは研究データを共用することで研究の加速化や、研究データへのアクセス促進を図る運動である。例えば、論文で引用された研究データを整備したリポジトリが存在すれば研究データへのアクセス促進に繋がる。そのようなリポジトリを構築・拡充する際に、研究データを自動的に論文から抽出できれば非常に有用である。そこで本研究では論文から研究データを抽出することを目指す。研究データの多くがインターネット上で利用可能であることから、URLによる研究データの引用に着目する。
1 0 0 0 OA 研究データを参照する文献の引用文脈に基づく識別
- 著者
- 生駒 流季 松原 茂樹
- 雑誌
- 第82回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.1, pp.379-380, 2020-02-20
近年のオープンサイエンスの広まりに伴い、研究において用いられたデータへの参照情報の抽出への需要も高まっている。また、学術論文では本文中で引用した論文や著者が参考文献として参照されるが、研究データへの参照に関しては明確な参照方法等の規定がなく、執筆者が個人の判断で研究データを参照しているという現状がある。本研究では、自然言語処理の国際会議における発表論文を対象に、参照先の文献から研究データとして参照されているものを識別する。その手掛かりとして、本研究では参照先文献のタイトルを含む書誌情報に加え、本文中で文献を参照した節のタイトルと、参照タグの含まれる本文から抽出した特徴量を利用する。
1 0 0 0 OA 離婚後の母親の面会交流の受けとめ尺度の作成と信頼性・妥当性の検証
- 著者
- 直原 康光 安藤 智子
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.91.19215, (Released:2020-07-30)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 2
The aim of this study was to develop the Mother’s Cognition of Father’s Parenting Time following divorce (MCFPT) scale and examine its reliability and validity. MCFPT items were developed from a questionnaire administered to 281 divorced mothers living with their children. Factor analysis identified six factors that influence mothers’ cognition of fathers’ parenting time: (a) belief that fathers’ parenting time benefits children, (b) concerns about their own safety and the safety of their children, (c) concerns about remarriage, (d) expectations of financial support, (e) jealousy of the father, and (f) disappointment with the father’s lack of interest in the children. These factors had a high degree of internal consistency. The MCFPT scale was significantly correlated with the State-Trait Anxiety Inventory, Caregiving System Scale, and others. The effect of the manner in which the divorce took place, children’s age, violence perpetrated by the father, and the father’s parenting time on MCFPT were evaluated using the t-test or one-way ANOVA. The MCFPT scale is reliable and valid for measuring mothers’ cognition of fathers’ parenting time after divorce.
1 0 0 0 OA 連続する2つのメッセージにおける同化と対比
- 著者
- 長峯 聖人 外山 美樹 湯 立 肖 雨知 海沼 亮 三和 秀平 相川 充
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.91.19315, (Released:2020-07-30)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
Tormala and Clarkson (2007) demonstrated the effects of assimilation and contrast with two consecutive messages. We investigated the effects of regulatory focus on assimilation and contrast in a multiple message situation in an experimental study. We hypothesized that the effect of assimilation would be observed among people with a promotion focus and the effect of contrast would be observed among people with a prevention focus. The results partially supported our hypothesis. There was a contrast effect in people with a prevention focus when evaluating the perceived credibility of the message. Moreover, the effect of assimilation was observed mostly in people with a promotion focus when evaluating the perceived credibility of the message, although this effect was not statistically significant. Finally, possible explanations for why our hypothesis regarding the evaluations of attitudes about the message was not supported are discussed.
1 0 0 0 シリーズ現代の天文学
- 出版者
- 日本評論社
- 巻号頁・発行日
- 2007
1 0 0 0 OA 代謝
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.6, pp.596-611, 2014 (Released:2014-12-05)
1 0 0 0 OA 鍼刺激の臨床効果に関する循環生理学的考察
- 著者
- 無敵 剛介
- 出版者
- 日本良導絡自律神経学会
- 雑誌
- 日本良導絡自律神経学会雑誌 (ISSN:09130977)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.5, pp.107-115, 1987-05-15 (Released:2011-10-18)
1 0 0 0 OA 食品の乾燥(2)
- 著者
- 林 弘通
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.66-75, 1992-02-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 4
- 著者
- 井實 充史
- 雑誌
- 福島大学人間発達文化学類論集 (ISSN:18803903)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.148-132, 2020-06