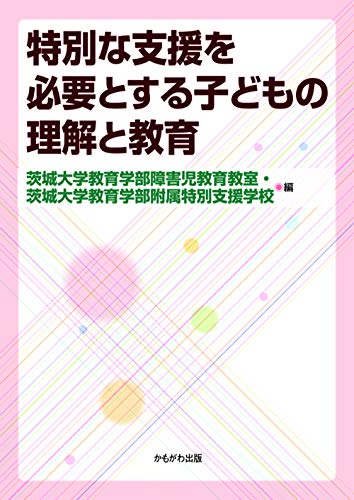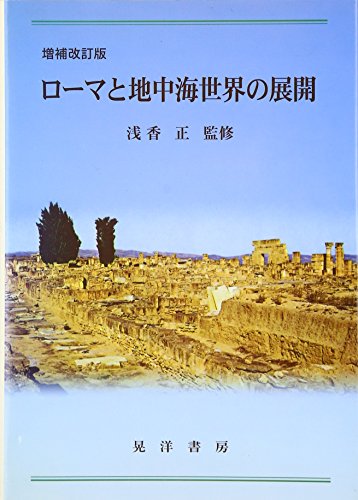1 0 0 0 OA 日本ノ大地震ニ就キテ
1 0 0 0 OA 中国語と日本語本文書体の 調和ある混植のための書体類似性評価
- 著者
- 楊 寧 伊原 久裕
- 出版者
- 一般社団法人 芸術工学会
- 雑誌
- 芸術工学会誌 (ISSN:13423061)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.76-83, 2014 (Released:2018-12-04)
国際交流の盛んな現代において、多言語タイポグラフィの必要性が増しているが、複数の言語が併存する印刷紙面では、それぞれの言語の特性を理解しつつ調和を図ることが重要なデザイン課題となる。本研究では特に中国語と日本語の調和のとれたタイポグラフィのあり方を探る。日本語と中国語は、漢字という共通した文字言語を持っていることから、その組み合わせは容易なようだが、実際にはそれぞれ独自の組版ルールを有し、書体デザインも同じものはほとんどない。したがって、両国語の文字の組版ルールの比較検討によって共通化できる組版の範囲をあきらかにし、書体についても調和すると判断可能な書体の対照関係を求め、その根拠を示す必要がある。本研究では、このうち書体―本文用の標準的な書体―に着目し、中国語と日本語フォントの調和のとれた対照関係を探るために、共通文字種の漢字のみに着目し、日本語、中国語それぞれの書体デザインを同一基準で評価する方法を探った。終端処理など中国語と日本語の漢字には、細部の処理に違いがあるが、本研究では、予備調査での観察結果に基づいて、計量可能な属性である字幅と字高、字面率、フトコロ率を取り上げ、計測を行うことで、類似性を評価することにした。 書体は、中国語では宋体と方黒体、日本語ではそれに対応する明朝体と角ゴシック体から選び、計測結果をクラスター分析したところ、宋体と明朝体、方黒体と角ゴシック体それぞれを大きく3つのグループに分類でき、それぞれ字幅と字面率の数値が小さい特徴のグループ(A)、字幅と字面率の数値が中間的なグループ(B)、字幅と字高、字面率の数値が大きなグループ(C)の3つとなった。同じグループの書体では属性データが近似しており、類似性の高い書体デザインと判断できることから、これらの組み合わせが調和ある混植の条件となると仮定できた。実施した検証実験においてもグループ同士の照応性は比較的高かった。 以上から、本研究で提案する書体の類似性評価は中国語と日本語の調和ある混植を容易に実現する方法として有効であることがわかった。
- 著者
- Yuzo TSUYUKI Sayaka NAKAZAWA Setsuko KUBO Mieko GOTO Takashi TAKAHASHI
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.20-0294, (Released:2020-07-27)
- 被引用文献数
- 3
We aimed to clarify antimicrobial susceptibility patterns of anaerobes from diseased companion animals. Bacterial identification was based on the Japanese 2012 guidelines for the testing of anaerobic bacteria. AST was performed using the broth microdilution method. The anaerobe-containing samples collected from 2014 to 2018 included blood (anaerobe recovery rate, 5.0%), bile (9.4%), joint fluids (0.6%), pleural effusions (42.6%), ascites (64.1%), cerebrospinal fluids (3.0%), and punctures (75.0%). The anaerobes identified included Bacteroides spp. (33.2%), Peptostreptococcus spp. (19.6%), Prevotella spp. (13.6%), Propionibacterium spp. (10.3%), Clostridium spp. (9.3%), and Fusobacterium spp. (7.5%). Bacteroides fragilis group isolates were resistant to penicillin G (100%), ampicillin (100%), cefmetazole (63.6%), ceftizoxime (90.0%), and clindamycin (40.0%). Our observations demonstrated antimicrobial susceptibility in anaerobes isolated from Japanese companion animals.
1 0 0 0 OA 方言の方言化とジェンダー 「不使用」という再生産
- 著者
- 熊谷 滋子
- 出版者
- 社会文化学会
- 雑誌
- 社会文化研究 (ISSN:18842097)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.92-115, 2005 (Released:2020-03-15)
- 著者
- 鈴木 厚子 福井 美園 中安 寿美子 滝谷 玲子 多田 敬三
- 出版者
- 慶應義塾大学
- 雑誌
- 共立薬科大学研究年報 (ISSN:04529731)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.1-15, 1984-03-25
The reaction of N-nitroso-N-butylurea (NBU) with an equivalent of L-α-aminoacid was made in the buffer solution of pH 7.2 at 37℃ for 3 weeks. α-Carbamoyl-aminoacid was isolated and identified for each α-aminoacid examined together with the decomposition-products of NBU such as 1-and 2-butanols, urea and a slight amount of butylurea. A quantitative research was also carried out for L-methionine and L-leucine by high performance liquidchromatography. It was found that about 60% of L-methionine and 53% of L-leucine was carbamoylated respectively with an equivalent of NBU during 5 days, but, thereafter, no appreciable further carbamoylation was observed, and also that 83% of methionine reacted with twice equivalent of NBU. The velocity and products of decomposition of NBU in the buffer solutions of various pH were reinvestigated. The minimum rate constant for the apparent first-order decomposition was found in the region of pH3. The determination of butanols produced by gaschromatography of ether extracts from the reaction mixture showed that not only their total amounts were practically unvaried but also the ratio of 1-butanol to 2-butanol was almost equal value of 2.0 in various pH regions. The amount of urea or butylurea produced in each pH solution was relatively estimated by semiquantitative thin-layer chromatography. In the case of urea, no appreciable difference was observed except in the regions of pH3 and pH4,where urea was found to be a minor product and, instead, an unknown product was detected, whereas the formation of butylurea was slight in higher pH regions than pH5,however, in more acidic medium denitrosation seemed to be considerable although it might be a side reaction in the whole decomposition-pathway. Some considerations and discussions were made on the mechanism of decomposition of NBU, and also on the results from the quantitative study for the reaction of NBU with α-aminoacids.
1 0 0 0 OA 楠木正行 : 少年歴史小説
- 著者
- 松川 恭子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.108, 2011
世界におけるメディア技術の拡大は均質ではない。儀礼・演劇など旧来メディアとマスメディアの連続性及び利用の現状を微細にみることで、グローバリゼーション下の共同体意識・実践の現代的あり方について明らかにすることが可能だ。本発表では、インド西部ゴア州で主に上演されている演劇ティアトルを取り上げる。CD、VCD、DVD、インターネットによるティアトルの展開とゴアとゴア外に居住する人々のネットワークについて考察する。
1 0 0 0 OA 興奮性および抑制性神経回路における同期現象
- 著者
- 青柳 富誌生
- 出版者
- 日本神経回路学会
- 雑誌
- 日本神経回路学会誌 (ISSN:1340766X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.99-105, 2003-06-05 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 OA Weis-Fogh (ヴァイスフォー) メカニズムを応用した船舶の推進
- 著者
- 蔦原 道久 木村 雄吉 盧 基徳
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- 日本舶用機関学会誌 (ISSN:03883051)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.8, pp.474-479, 1988-08-01 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2 2
A two-dimensional model of the Weis-Fogh mechanism, which is a mechanism of hovering flight of small insects, is applied to ship propulsion. A model of the propulsion mechanism consisting of one or two wings in a square channel is proposed. The thrust and the drag on the wing, which are defined, respectively, the force in the direction of progress of the ship and that of movement of the wing, are measured. The propulsive efficiency is calculated and is high when the moving speed of the wing is small compared with the advancing speed of the ship. A model ship equipped with this propulsion mechanism is made and working tests performed. The applicability of this propulsion mechanism to actual ships is expected to be good.
1 0 0 0 OA 藤木久志先生ありがとうございました。
- 著者
- 蔵持 重裕 クラモチ シゲヒロ Shigehiro Kuramochi
- 雑誌
- 史苑
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.2, pp.189-190, 2020-03
1 0 0 0 特別な支援を必要とする子どもの理解と教育
- 著者
- 茨城大学教育学部障害児教育教室 茨城大学教育学部附属特別支援学校編
- 出版者
- かもがわ出版
- 巻号頁・発行日
- 2019
1 0 0 0 OA 『兵隊やくざ』論序説
- 著者
- 李 建志 Kenji Lee
- 雑誌
- 関西学院大学先端社会研究所紀要 = Annual review of the institute for advanced social research (ISSN:18837042)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.27-46, 2014-03-31
1 0 0 0 2050年の情報処理:11. グループウェアから共助社会へ
グループウェアとネットワークサービス研究会の対象とする研究領域は,CSCWと呼ばれ,人間と社会と技術の融合によって成り立っている.当研究会の歩みは1990年代初頭に始まっている.1990年代初頭は,コンピュータネットワークの普及を前提にした研究をしていたが,インターネットの普及以降は,現実世界での問題解決のための研究に進展し,現在に至っている.本稿では,これまでのグループウェアとネットワークサービス研究の変遷を踏まえて,30年後の2050年に向けて人間と社会と技術を融合した研究分野としてどのような研究テーマがあるかについて述べた.
1 0 0 0 OA 湯原町における腹部症状を伴う脳脊髄炎症(スモン)の疫学的研究(第1報)
- 著者
- 大平 昌彦 青山 英康 吉岡 信一 加藤 尚司 太田 武夫 吉田 健男 長谷井 祥男 大原 啓志 上畑 鉄之丞 中村 仁志 和気 健三 柳楽 翼 五島 正規 合田 節子 深見 郁子 板野 猛虎
- 出版者
- The Japanese Society for Hygiene
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.5-6, pp.502-509, 1970-02-28 (Released:2009-08-24)
- 参考文献数
- 18
In a restricted area of the northern part of Okayama Prefecture, Yubara Town, an outbreak of SMON (subacute myelo-optico-neuropathy) was observed from the beginning of 1967. An epidemiological investigation has been made on this outbreak and the results are as follows:(1) Concentration of cases occurred in the summer of 1968, though cases have been reported sporadically in the area from the beginning of 1967. The incidence ratio against the population was 659/100, 000 during 22 months.(2) The incidence was the highest in summer and the ratio in females was 3 times higher than in males. Concerning age group, males showed a peak in the thirties, whereas in females many cases were evident between the twenties and sixties.(3) Relatively enclosed districts are apt to expand over a period of time. Cases which occurred in neighboring families as well as those within the same families tend to give the impression that the disease coule be infectious.(4) Among the cases, a close contact relation was observed.(5) Physical exhaustion before the onset of the disease was observed to be 43.2% among the total cases.(6) In occupational analysis, a higher rate was revealed among workers who had close human relations such as hospital workers and public service personnel.(7) The tendency to other diseases of the nervous system as well as those of the digestive organs was checked by inspecting receipts of the National Health Insurance from the beginning of 1965. Nothing related to SMON was recognized before the outbreak.(8) Diseases of the intestinal tract and tonsillitis were observed in higher rates in the history of the patients.(9) The investigation of environmental conditions has revealed the fact that there is a higher rate of incidence in families who do not use service water compared to those who do.
1 0 0 0 OA 《卒論報告》成長過程と書き文字の変容
- 著者
- 數本 好慧
- 出版者
- 横浜国立大学国語教育研究会
- 雑誌
- 横浜国大国語教育研究 (ISSN:13411950)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.54, 2020-03
1 0 0 0 OA 下腿傾斜角と後足部アライメトの関係
- 著者
- 加藤 彩奈 宮城 健次 千葉 慎一 大野 範夫 入谷 誠
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.35 Suppl. No.2 (第43回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.A0078, 2008 (Released:2008-05-13)
【はじめに】変形性膝関節症(以下膝OA)は立位時内反膝や歩行時立脚相に出現するlateral thrust(以下LT)が特徴である。臨床では膝OA症例の足部変形や扁平足障害などを多く経験し、このLTと足部機能は密接に関係していると思われる。本研究では、健常者を対象に、静止立位時の前額面上のアライメント評価として、下腿傾斜角(以下LA)、踵骨傾斜角(以下HA)、足関節機能軸の傾斜として内外果傾斜角(以下MLA)を計測し、下腿傾斜が足部アライメントへ与える影響を調査し、若干の傾向を得たので報告する。【対象と方法】対象は健常成人23名46肢(男性11名、女性12名、平均年齢29.3±6.1歳)であった。自然立位における下腿と後足部アライメントを、デジタルビデオカメラにて後方より撮影した。角度の計測は、ビデオ動作分析ソフト、ダートフィッシュ・ソフトウェア(ダートフィッシュ社)を用い、計測項目はLA(床への垂直線と下腿長軸がなす角)、HA(床への垂直線と踵骨がなす角)、LHA(下腿長軸と踵骨がなす角)、MLA(床面と内外果頂点を結ぶ線がなす角)、下腿長軸と内外果傾斜の相対的角度としてLMLA(下腿長軸への垂直線と内外果頂点を結ぶ線がなす角)とした。統計処理は、偏相関係数を用いて、LAと踵骨の関係としてLAとHA、LAとLHAの、LAと内外果傾斜の関係としてLAとMLA、LAとLMLAの関係性を検討した。【結果】各計測の平均値は、LA7.1±2.4度、HA3.0±3.9度、LHA10.5±5.5度、MLA15.3±3.9度、LMLA8.1±4.0度であった。LAとLHAでは正の相関関係(r=0.439、p<0.01)、LAとLMLAでは負の相関関係(r=-0.431、p<0.01)が認められた。LAとHA、LAとMLAは有意な相関関係は認められなかった。【考察】LHAは距骨下関節に反映され、LAが増加するほど距骨下関節が回内する傾向にあった。したがって、LA増加はHAではなく距骨下関節に影響するものと考えられる。LA増加はMLA ではなくLMLA減少を示した。これらの関係から下腿傾斜に対する後足部アライメントの評価は、床面に対する位置関係ではなく下腿長軸に対する位置関係を評価する必要性を示している。LA増加に伴うLMLA減少は距腿関節機能軸に影響を与えると考えられる。足関節・足部は1つの機能ユニットとして作用し、下腿傾斜に伴う距腿関節機能軸変化は距骨下関節を介し前足部へも波及する。今回の結果から膝OA症例のLTと足部機能障害に対し、距腿関節機能軸変化の影響が示唆された。今回は健常者を対象とした静的アライメント評価である。今後、症例との比較も含め運動制御の観点から動的現象であるLTと足部機能障害の解明につなげていきたい。
- 著者
- 平井 規央 石井 実
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会大会講演要旨
- 巻号頁・発行日
- no.46, 2002-03-10