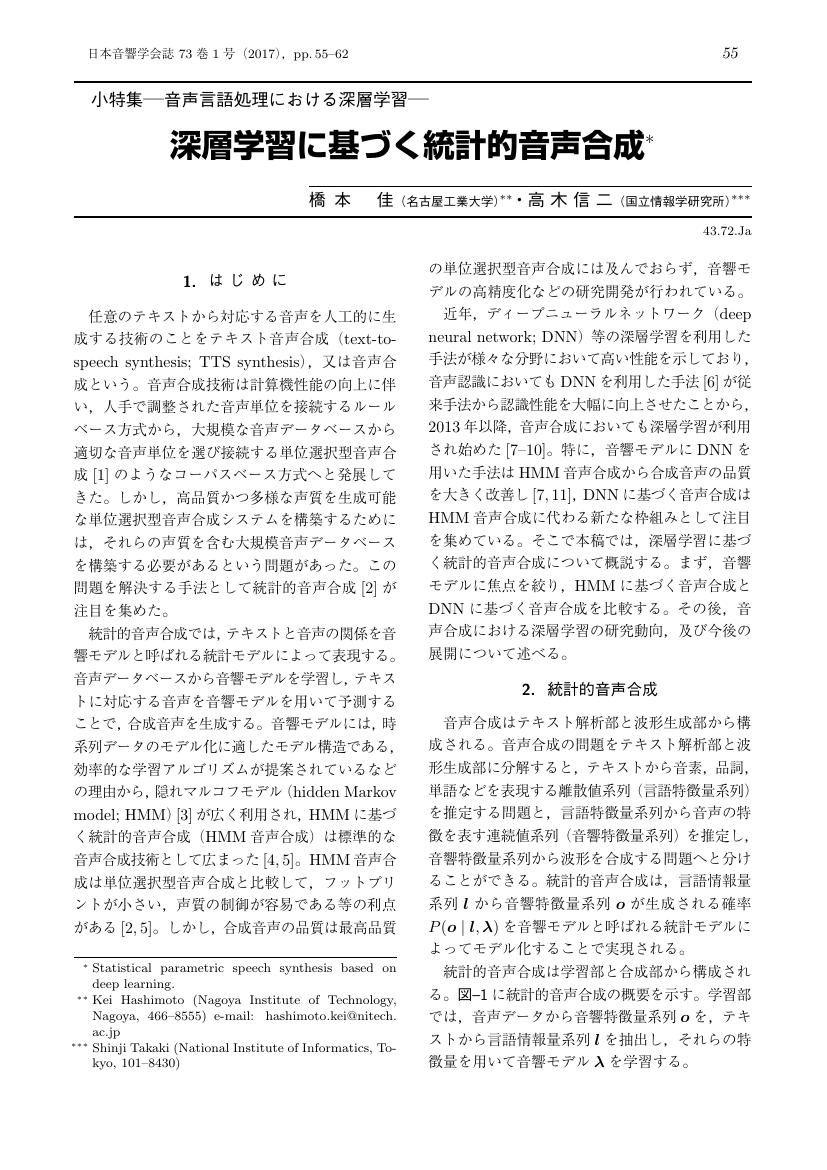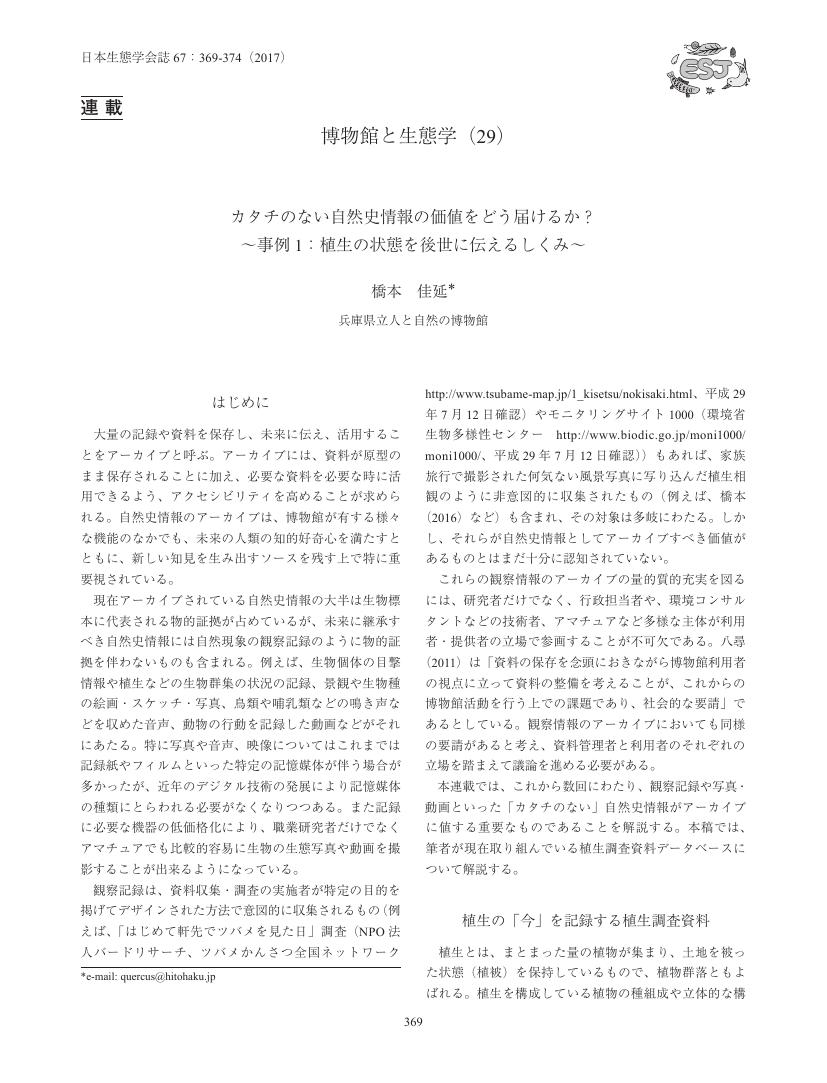33 0 0 0 OA 隠れマルコフモデルに基づく日本語音声合成ソフトウェア入門
- 著者
- 大浦 圭一郎 橋本 佳 南角 吉彦 徳田 恵一
- 出版者
- 一般社団法人 システム制御情報学会
- 雑誌
- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.57-62, 2018-02-15 (Released:2018-08-15)
- 参考文献数
- 8
30 0 0 0 OA アレルギー性鼻炎と喫煙との関係
- 著者
- 橋本 佳明 二村 梓
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.4, pp.652-655, 2010 (Released:2013-07-31)
- 参考文献数
- 11
目的:喫煙習慣の有無によりアレルギー性鼻炎(以下鼻炎と略す)の有病率が異なるかどうかを検討した.対象:職域健診受診男性9,733名,女性3,071名.方法:生活習慣および常用薬剤情報は自記式アンケート調査で得た.有病率の比較はカイ2乗検定で,オッズ比はロジスティック回帰分析で求めた.成績:男性の鼻炎有病率は10.5%で,喫煙状態別では,非喫煙者14.5%,過去喫煙者10.6%,少量喫煙者(1~19本/日)9.7%,中等量喫煙者(20~39本/日)5.8%,多量喫煙者(40本以上/日)3.7%であった.重回帰分析により鼻炎と関連していた年齢で調整して,非喫煙者に対する鼻炎有病率のオッズ比を求めたところ,過去喫煙者0.76,少量喫煙者0.64,中等量喫煙者0.38,多量喫煙者0.25でいずれも有意に低値であった.一方,女性の鼻炎有病率は14.7%で,男性と比較し有意に高率であったが,非喫煙者では差が認められなかった.結語:鼻炎有病率は喫煙量が多いほど低率であることが判明した.また,鼻炎有病率は男性と比較し女性の方が高率であったが,この原因は喫煙量の違いによるものであると考えられた.
8 0 0 0 OA 深層学習に基づく統計的音声合成
- 著者
- 橋本 佳 高木 信二
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.1, pp.55-62, 2017 (Released:2017-07-01)
- 参考文献数
- 56
5 0 0 0 OA ゴルフ場の半自然草原を活用した生物多様性の保全
歴史の長いゴルフ場の植生を調査した結果,全国版・地域版のレッドデータブックに掲載の絶滅危惧種および多くの草原生植物の生育を確認した.つまり,これらの場所は草原生植物の逃避場所や種子供給源として機能する可能性がある.管理方法と種多様性との関係では,草刈り頻度および草刈高が種多様性に大きく影響を与えており,草刈り頻度が低く,草刈高が高い地点においては種多様性が高く,逆の地点では種多様性が低かった.また,ゴルフ場関係者の意向を把握する質問紙調査からは,ゴルファーの多くは野草の生育に対して好意的であることが示された.
4 0 0 0 OA Faa di Brunoの公式とその応用(1)
- 著者
- 岡野 節 奥戸 雄二 清水 昭信 新倉 保夫 橋本 佳明 山田 浩
- 雑誌
- Annual review (ISSN:13429329)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.35-44, 2001-03
Faa di Brunoの公式を証明し,組み合わせ論とHermite多項式へのその応用を議論する.
3 0 0 0 OA 著しい高血糖と低ナトリウム血症を呈した高浸透圧性非ケトン状態の1例
- 著者
- 渡邊 浩之 魚住 信泰 川崎 三紀子 反町 千里 村田 英紀 高雄 泰行 上野 秀之 藤澤 和彦 笠原 成彦 浜 英永 井上 富夫 橋本 佳明
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.287-289, 2006 (Released:2009-01-19)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2
症例は47歳,男性.5年前に血糖の軽度高値を指摘されたが放置していた.入院2週間前より口渇感が強くなり,1週間前には含糖清涼飲料水を約5,000 ml飲むようになっていた.食欲不良と倦怠感が増悪し,意識混濁状態が出現したため入院となった.血糖2,531 mg/dl, HbA1c 12.4%, 血清ナトリウム98 mEq/l, K 7.1 mEq/l, Cl 60 mEq/l, 血清クレアチニン1.56 mg/dl, 尿素窒素40.9 mg/dl, 尿ケトン体(-), 動脈血pH 7.349, HCO3-21.1 mmol/l, 血漿浸透圧407 mOsm/kgH2O(計算値346 mOsm/kgH2O)より高浸透圧性非ケトン状態と診断した.生理食塩水とインスリン静脈内投与により高血糖,低ナトリウム血症が是正され入院翌日には意識清明となった.本症例は著しい高血糖,低ナトリウム血症および浸透圧ギャップが認められた興味ある症例と考えられた.
3 0 0 0 OA 宮崎県東諸県郡綾町川中の照葉原生林におけるニホンジカの採食の影響
- 著者
- 服部 保 栃本 大介 南山 典子 橋本 佳延 藤木 大介 石田 弘明
- 出版者
- 植生学会
- 雑誌
- 植生学会誌 (ISSN:13422448)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.35-42, 2010-06-25 (Released:2017-01-06)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 12
1. 宮崎県東諸県郡綾町川中の照葉原生林において,シカの採食による顕著な被害が発生する以前の1988年当時の植生調査資料と激しい被害を受けている2009年現在の植生調査資料とを比較し,照葉原生林の階層構造,種多様性,種組成へのシカの採食の影響を調査した. 2. 階層構造についてはシカの採食によって,第2低木層と草本層の平均植被率がそれぞれ約1/2,1/5に大きく減少した. 3. 階層別の種多様性については全階層と第2低木層において平均照葉樹林構成種数がそれぞれ約3/4,1/2に大きく減少した. 4. 生活形別の種多様性については照葉高木,照葉低木,照葉つる植物,多年生草本において平均種数がそれぞれ2.4種,3.8種,1.2種,2.4種減少した. 5. 減少種数は25種,消失種数は35種,増加種数は6種,新入種数は33種となり種組成は変化した. 6. 他地域から報告されている不嗜好性植物と比較した結果,増加種のうちバリバリノキ,マンリョウ,マムシグサなどの12種が本調査地の不嗜好性植物と認められた. 7. 本調査地の照葉原生林の階層構造,種多様性,種組成はともにシカの採食によって大きな被害を受けており,照葉原生林の保全対策が望まれる.
3 0 0 0 OA 基礎系教員と実務家教員の連携による実務実習事前学習の試みとその評価
- 著者
- 清水 忠 西村 奏咲 安田 恵 村上 雅裕 橋本 佳奈 大野 雅子 桂木 聡子 上田 昌宏 天野 学
- 出版者
- 日本薬学教育学会
- 雑誌
- 薬学教育 (ISSN:24324124)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.2018-014, 2018 (Released:2018-08-24)
- 参考文献数
- 7
薬学実務実習終了生を対象としたアンケート調査によれば,大半の学生は実習中に基礎薬学の知識を活用する機会は少なかったと感じていることが報告されている.その要因として,教員が基礎薬学は臨床現場でどのように役に立つかを具体的に説明できていないことが指摘されている.しかし,臨床現場での問題は基礎薬学が問題解決に有用となることもある.そのため,基礎系教員と臨床系教員が連携し基礎薬学の臨床現場での有用性を理解させ,それが可能であることを示すことが必要であると考えた.そこで,実務実習事前学習において有機化学を専門とする基礎系教員と実務家教員が連携した医薬品の配合変化に関する実習を実施し,終了後にアンケートを行った.この結果,受講生の90%以上が基礎薬学の内容が臨床の問題を解決するのに有用であることを意識できた.すなわち,基礎薬学が臨床現場でどのように役に立つかを意識させる実習を提供できたと考えられる.
3 0 0 0 タケ類天狗巣病による西日本の竹林の衰退
- 著者
- 橋本 佳延 服部 保 岩切 康二 田村 和也 黒田 有寿茂 澤田 佳宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.151-160, 2008
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 4
タケ類天狗巣病は、麦角菌科の一種Aciculosporium take Miyakeの感染によって生じるタケ類を枯死に至らしめる病気で、日本国内では野外においてマダケおよびモウソウチクを含む6属19種8変種8品種2園芸品種のタケ類、ササ類で感染することが確認されており、近年では国内各地で本病による竹林の枯損被害が報告されている。本研究は、兵庫県以西の西日本一帯を中心とした地域において、マダケ群落およびモウソウチク群落のタケ類天狗巣病による枯損の現状を明らかにし、天狗巣病の影響による今後の竹林の動態を考察することを目的とした。西日本の17県および新潟県、宮城県、静岡県の3県において、本病によるマダケ群落およびモウソウチク群落の枯損状況を調査した結果、西日本におけるマダケ群落における本病発症率は全体では93.2%、各県では75%以上と高い水準であったほか、本病による重度枯損林分は10県で確認された。一方、モウソウチク群落における本病発症率は、西日本全体では3.9%、発症率10%未満の県が15県(うち6県が0%)と極めて低い水準で、重度枯損林分も島根県で1ヵ所確認されたのみと被害の程度は低かったが、参考調査地の静岡県においては発症率が50%と高かった。これらのことから、本病は、(1)西日本各地でマダケ群落を枯損に至らしめる可能性のある病気であり、ほとんどのマダケ群落で発症していること、(2)西日本ではモウソウチク群落を枯死させることはまれな病気であり発症率も低いが、局所的に発症率の高い地域もみられることが明らかとなった。また、今後はマダケ群落の発症林分における病徴が進行し国内の広い範囲でマダケ群落の枯損林分が増加すると予想されたが、モウソウチク群落については発症林分や枯死林分の事例が少ないことから今後の動向についての予測は難しくモニタリングにより明らかにする必要があると考えられた。
2 0 0 0 OA 集中治療室の病棟業務における臓器系統別患者評価法導入の効果
- 著者
- 吉廣 尚大 冨田 隆志 橋本 佳浩
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.6, pp.445-452, 2016-06-10 (Released:2017-06-10)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 5 2
This study investigated whether the review of systems (ROS), an evaluation method that covers all organ systems, improves the quality of pharmaceutical care provided in intensive care units (ICUs). We retrospectively examined patients from the respiratory and emergency intensive care departments admitted to the ICU of our hospital in 2012 (before the introduction of ROS; non-ROS group, n = 93) and in 2014 (after the introduction of ROS; ROS group, n = 65). The number of pharmaceutical interventions and adverse drug events prevented by pharmacists per 1000 patient days were higher in the ROS group (265.7 and 57.8 for the ROS group and 190.8 and 39.9 for the non-ROS group). Pharmacists' proposals were accepted at a significantly higher rate in the ROS group than in the non-ROS group (89.5% vs 72.3%, P < 0.01), and the accepted proposals in the ROS group were implemented for a wider range of organ systems. These results indicate that the ROS was helpful in terms of identifying the patients' clinical manifestations and evaluating the adequacy and safety of medication administered in the ICU, which resulted in improved and precise proposals by pharmacists. Moreover, the ROS approach introduced in this study was considered to be suitable for pharmaceutical activities in the ICU and to contribute to improving the quality of pharmaceutical care.
2 0 0 0 OA 高校生の数学的問題解決方略使用を促す授業外学習教材の開発 自己調整学習との関連に着目して
- 著者
- 橋本 佳蓉子 渡辺 雄貴
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.Suppl., pp.137-140, 2021-12-20 (Released:2022-02-02)
- 参考文献数
- 15
自ら振り返り次につなげるような学習活動として,自己調整学習が注目されている.自己調整学習は数学的問題解決と過程の段階において関連が考えられる.そこで,本研究では自己調整学習との関連に着目した,高校生の数学的問題解決方略使用を促す授業外学習教材の開発を目的とした.高校1年生を対象に数学Ⅰの2次方程式・不等式の単元で実践した.質問紙調査の結果,数学的問題解決方略は,問題の得点の上位群で問題解決の見通しに関する点で改善が見られた.しかし,授業外学習での自己調整学習方略と動機づけに改善が見られず,成績に応じて問題内容を変えることや授業内容と関連させることなどの教材の課題が明らかとなった.
2 0 0 0 OA 塩酸アンブロキソールの気道粘液および肺表面活性リン脂質分泌に対する作用
- 著者
- 内田 勝幸 野口 裕司 荒川 礼二郎 橋本 佳子 五十嵐 康子 本多 秀雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.4, pp.293-300, 1992 (Released:2007-02-13)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1 1
塩酸アンブロキソール(アンブロキソール)の気道粘液分泌および肺表面活性リン脂質分泌に対する効果をそれぞれラットおよびモルモットを用いて検討した.気道粘液分泌に対しては組織学的および生化学的に検討した.アンブロキソールは用量依存的に気道のムコ多糖を増加させ,肥厚した杯細胞数も用量依存的に増加した.また,中性ムコ多糖も有意に増加し,組織学的には気管腺の肥厚およびPAS陽性物質の増加が認められた.このことは,アンブロキソールが気管腺においては漿液性の粘液分泌を亢進させることを示唆する成績と考えられた.一方,肺洗浄液中のホスファチジルコリンはアンブロキソール投与により有意な増加を示さなかったが,飽和のホスファチジルコリンが占める割合は有意に増加し,アンブロキソールの肺表面活性リン脂質の分泌亢進作用を示唆する成績であった.以上の結果からアンブロキソールの去痰作用の機序として気道粘液分泌および肺表面活性リン脂質分泌の亢進作用が考えられた.
2 0 0 0 OA 血清分離遅延による偽低カリウム血症率の上昇
- 著者
- 橋本 佳明 二村 梓
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.650-652, 2007-12-28 (Released:2012-08-20)
- 参考文献数
- 3
目的:血液検体の血清分離遅延により血清カリウム値が変動すること,さらにその変動は放置温度や放置時間により異なることが報告されている.今回,東京の某健診機関で見られた血清分離遅延による低カリウム血症率の上昇について分析した.方法:2003年4月から10月の間に職域健診をうけた2,645名のデータを解析した.4月から7月の検体は採血後7-10時間で,8-10月の検体は採血後0.5-1時間で血清分離された.成績:各月の低カリウム血症(3.4mEq/1以下)率は,4月12.7%,5月14.1%,6月21.5%,7月24.5%,8月1.6%,9月0.8%,10月0.6%であった.高カリウム血症(5.1mEq/l以上)率は4-7月0.28%,8-10月0.58%であった.結論:東京の4月から7月の気温で全血を7-10時間放置すると低カリウム血症率が著しく上昇することが判明した.血液検体の血清分離は速やかに行う必要がある.
2 0 0 0 新段階の情報化社会における私法上の権利保護のあり方
- 著者
- 潮見 佳男 橋本 佳幸 村田 健介 コツィオール ガブリエーレ 西谷 祐子 愛知 靖之 木村 敦子 カライスコス アントニオス 品田 智史 長野 史寛 吉政 知広 須田 守 山本 敬三 横山 美夏 和田 勝行
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2017-04-01
平成30年度は、前年度に引き続き、ゲストスピーカーを交えた全体研究会の開催を通じて、情報化社会における権利保護のあり方をめぐる従来の議論の到達点と限界を検討し、知見の共有を図った。個別の研究課題に関しては、次のとおりである。第1に、個人情報の収集・利活用に関する私法的規律との関連では、全体研究会を通じて、EU一般データ保護規則(GDPR)の全体的構造のほか、EUにおけるプライバシー権の理論構成について理解を深めた。また、プラットフォーム時代のプライバシーにつき、プロファイリング禁止やデータ・ポータビリティーなどの先端的課題を踏まえた理論構成のあり方を検討した。第2に、AIの投入に対応した責任原理との関連では、全体研究会において、ドイツでの行政手続の全部自動化立法の検討を通じて、AIによる機械の自動運転と比較対照するための新たな視点が得られた。第3に、ネットワーク関連被害に対する救済法理との関連では、担当メンバーが、ネットワークを介した侵害に対する知的財産権保護のあり方を多面的に検討し、また、オンライン・プラットフォーム事業者の責任について分析した。以上のほか、私法上の権利保護の手段や基盤となるべき法技術および法制度に関しても、各メンバーが新債権法に関する一連の研究を公表しており、編著の研究書も多い。さらに、外国の法状況の調査・分析に関しては、ドイツやオーストリアで在外研究中のメンバーが滞在国の不法行為法の研究に取り組み、複数のメンバーがヨーロッパ諸国に出張して情報収集を行った。また、研究成果の国際的な発信も活発に行っており、国際学会での日本法に関する報告が多数あるほか、新債権法に関して、その翻訳、基本思想を論じる英語論文が挙げられる。
2 0 0 0 障害をもつ人たちの憲法学習 : 施設での社会科教室の試み
- 著者
- 橋本佳博 玉村公二彦著
- 出版者
- かもがわ出版
- 巻号頁・発行日
- 1997
2 0 0 0 OA カタチのない自然史情報の価値をどう届けるか?
- 著者
- 橋本 佳延
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.369-374, 2017 (Released:2017-12-05)
- 参考文献数
- 10
- 著者
- 橋本 佳延 中村 愛貴 武田 義明
- 出版者
- 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.103-111, 2007-11-30
- 被引用文献数
- 4
中国原産のトウネズミモチは近年、日本において都市の空地、都市林、里山、都市河川等に逸出、急速に分布拡大していることが確認されており、生育と繁殖力が旺盛で早期に優占群落を形成することから在来の生態系や生物多様性に多大な影響を与える侵略的外来種となることが危惧されている。本研究では都市河川に侵入した外来樹木トウネズミモチの個体群が洪水によって受ける分布拡大への影響を明らかにするために、平成16年10月に大規模な洪水が発生した兵庫県南西部を流れる猪名川低水敷の5.3haの範囲において、その洪水直後と洪水翌年にトウネズミモチ個体群の調査を行い、結果を洪水前に行われた既存研究の結果と比較した。調査ではトウネズミモチの個体数、各個体のサイズ、結実の有無、倒伏状況を記録したほか、空中写真撮影を行い調査地における裸地面積および植被部分の面積を測定した。結果、洪水によって陸域に占める裸地の面積は洪水前に比べ871%拡大し、個体群の主要な構造を形成するサイズ1m以上の個体の1/3が消失した一方で、実生・稚樹個体数は洪水直後の24個体から洪水翌年には49個体に増加した。また洪水によってサイズ1m以上の個体の1/3が倒伏し、洪水後の個体群の平均樹高は洪水前の3.3mから2.2mに低下した。個体群に占める結実個体の割合は洪水翌年が24.5%となり、洪水前の46.8%の約1/2に低下した。洪水翌年における立木個体に占める結実個体の割合は37.5%であったのに対し倒伏個体に占める結実個体の割合は4.5%であった。これらのことから、河川敷のトウネズミモチ個体群は洪水による個体数の減少によってその規模が縮小するとともに、個体の倒伏に伴い結実状況は悪化する一方で、洪水によって形成された裸地に新規個体が参入し、残存個体の繁殖力も立木個体を中心として翌年より緩やかに回復するものと考えられ、洪水によるトウネズミモチ個体群の分布拡大を抑制する効果は軽微であることが示唆された。
2 0 0 0 OA ササ優占型に遷移した草原における刈り取りによる草原生植物種多様性の回復効果
- 著者
- 橋本 佳延 石丸 京子 黒田 有寿茂 増永 滋生 横田 潤一郎
- 出版者
- 社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究(オンライン論文集) (ISSN:1883261X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.69-76, 2012 (Released:2012-08-10)
- 参考文献数
- 63
- 被引用文献数
- 1
Miscanthus sinensis grasslands can be dominated by dwarf bamboo such as Pleioblastus chino var. viridis after abandonment, leading to decrease diversity in the communities. We investigated the effect of mowing on recovery of grassland species richness and cover, and overall species composition over three years. Two treatments were tested: mowing above ground vegetation every autumn and mowing above ground vegetation every autumn with selective cutting of P. chino var. viridis in the first summer. The number of grassland plant species increased slightly under both treatments, although M. sinensis did not return as the dominant species in either treatment after the restoration. The addition of selective cutting of P. chino var. viridis resulted in greater cover of M. sinensis and higher richness and cover of grassland species. These results show that selective cutting of P. chino var. viridis in summer enhance the effect of management for restoring grassland species diversity in long-abandoned semi-natural grassland communities.
1 0 0 0 OA 緊急帝王切開で出産した初産婦の出産に対する思い
- 著者
- 橋本 佳奈子 小林 康江
- 出版者
- 一般社団法人 日本助産学会
- 雑誌
- 日本助産学会誌 (ISSN:09176357)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.103-114, 2019 (Released:2019-06-30)
- 参考文献数
- 30
目 的緊急帝王切開で出産した初産婦の産後4か月までの出産に対する思いを明らかにする。方 法研究デザインはライフストーリー法を参考にした質的記述的研究である。母児ともに妊娠産褥経過が良好な緊急帝王切開で出産した初産婦3名に対し,診療録からデータ収集をした上で,半構成的面接を産後2週・4から6週・4か月の3回に縦断的に実施した。面接は出産体験について,体験したことや思考したことを自由に語ってもらった。結 果本研究では,3名の初産婦の緊急帝王切開に対する思いと,出産体験を意味づけるストーリーが語られた。母乳育児の成功体験により出産への後悔を払拭するA氏のストーリー,育児への自信と子供との絆を高めることで,経膣分娩への気持ちを整理し出産を肯定的に捉えていくB氏のストーリー,体験を語ることや自分がこの子の母親であると思える過程を経て,出産体験を意味づけしようとしているC氏のストーリーであった。緊急帝王切開に対する思いは,出産後育児を行う中で変化していた。結 論緊急帝王切開で出産した女性は,出産への自信や母親としての自信を喪失し,出産を不本意に思う気持ちと児が無事であったことに安心する気持ちの間で揺らいでいた。育児を行い子供や家族との関係を築く中から,産後4か月には緊急帝王切開であっても自分の出産に他ならない体験であると出産への思いは変化し,さらに第3者に思いを語ることで出産体験の受容は促進されていた。