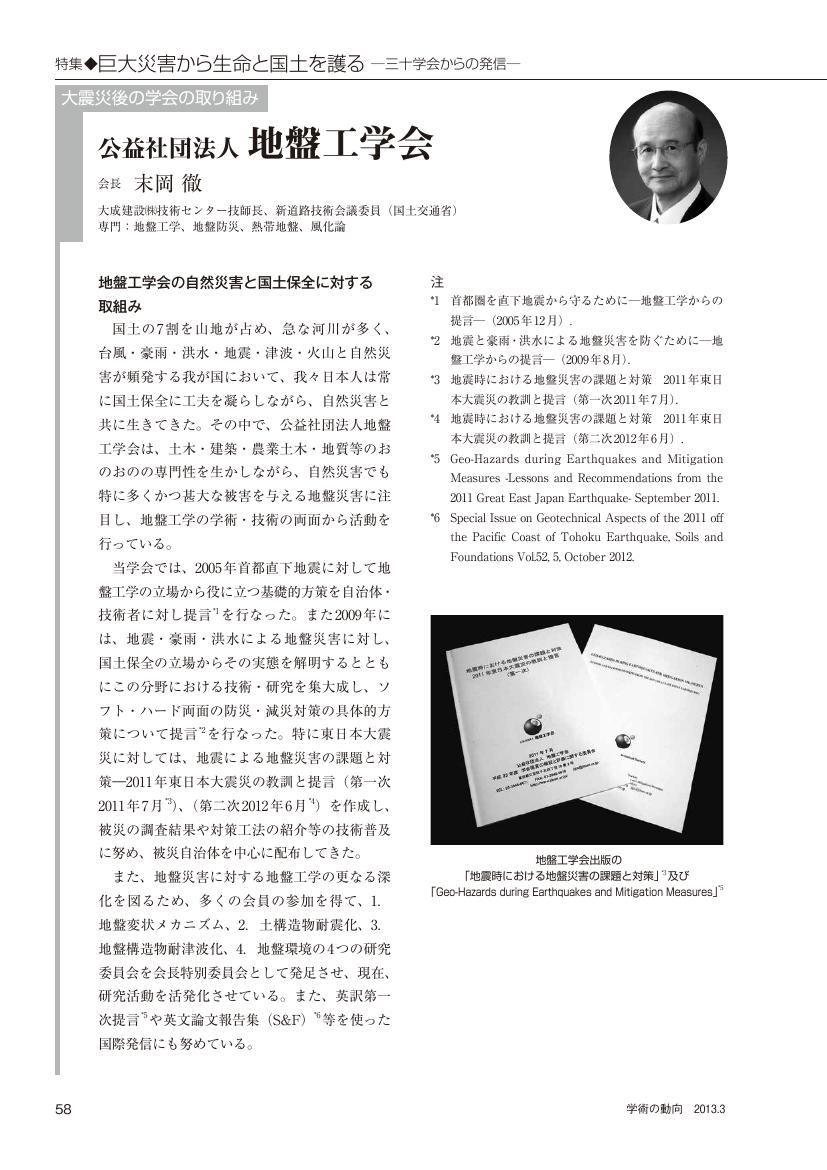1 0 0 0 IR スイーツ学思考論 : 『スイーツ学』とは
- 著者
- 松井 博司
- 出版者
- 大手前大学
- 雑誌
- 大手前大学論集 (ISSN:1882644X)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.127-134, 2012
大学に初めてスイーツ学専攻が開設された意義は何かを問う。スイーツの定義から始まり、大学教育としてスイーツ学を学ぶ根拠を明確にする必要がある。さらに、スイーツ学の学術体系を構築すべき内容について論じる。
- 著者
- 三宅 竜二 朱 庭耀 松本 俊之 熊野 厚
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 日本船舶海洋工学会講演会論文集 5E (ISSN:24241628)
- 巻号頁・発行日
- pp.5-8, 2007 (Released:2017-12-28)
1 0 0 0 OA 文献紹介
1 0 0 0 OA 大震災後の学会の取り組み
- 著者
- 公益社団法人 地盤工学会
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.3_58, 2013-03-01 (Released:2013-07-05)
1 0 0 0 OA 豪雨災害に関する地盤工学分野の取り組み
- 著者
- 公益社団法人地盤工学会
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.11, pp.11_79, 2016-11-01 (Released:2017-03-03)
- 参考文献数
- 1
1 0 0 0 OA 「因中説果」と「因中有果」の違い─『起信論』理解の中心点─
- 著者
- 織田 顕祐
- 出版者
- 東洋大学東洋学研究所
- 雑誌
- 東アジア仏教学術論集 = Proceedings of the International Conference on East Asian Buddhism (ISSN:21876983)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.291-318, 2016-02
「織田顕祐氏の発表論文に対するコメント」「朴昶奐氏のコメントに対する回答」含
本研究では本邦で行われた頚椎後縦靭帯骨化症(頚椎OPLL)のGWASで同定された疾患修飾候補遺伝子のひとつであるRSPO2のOPLL発症およびOPLL伸展における機能解明を目指して開始した。まずヒトサンプルおよびマウスのティッシュパネルにおいてRSPO2が後縦靭帯に発現していることを確認した。また手術で得られた頚髄症患者および頚椎OPLL患者の黄色靭帯での発現比較において頚椎OPLL群で有意にRSPO2の発現が高かったことからRSPO2がWnt活性化因子であることをあわせて、我々はRSPO2のgain-of-functionがOPLLの発症に関与しているという傍証をえた。またヒトOPLLサンプルやヒト黄色靭帯骨化症サンプルにおいて骨化前線部の靭帯細胞でコントロールと比較してRSPO2の発現が有意に上昇していることも確認した。次にヒト脊椎靭帯細胞で実際にRSPO2が骨化を誘導することが可能か検証すべく実験を行った。まず手術で得た黄色靭帯からCD90陽性の間葉系幹細胞とCD90陰性の靭帯細胞をフローサイトメーターを用いて分離培養する系を確立した。続いて同系にて得られたCD90陽性の細胞群にRSPO2を添加することで実際に骨芽細胞分化が誘導されることを確認した。またOPLLはメカニカルストレスのかかる部位で進展悪化することが知られているが、実際に上記系で得られたCD90陰性の靭帯細胞にメカニカルストレスをかけることでRSPO2の発現が上昇することも確認でき、靭帯内では靭帯細胞でのRSPO2の発現・分泌上昇が靭帯内間葉系幹細胞の骨芽細胞分化を促進している可能性が考えられた。最後にRSPO2のCre誘導性トランスジェニックマウスを作出し、様々なCreマウスを交配することで実際に靭帯骨化症が誘導できるかを検討したが現時点では、靭帯骨化が確認されるには至っておらず現在も交配と解析を継続しているところである。現段階までの成果を現在英語論文にまとめ、投稿中である。
1 0 0 0 OA 情報通信技術と脳科学の融合
- 著者
- 川人 光男
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 情報・システムソサイエティ誌 (ISSN:21899797)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.4, pp.3, 2013-02-01 (Released:2016-12-11)
1 0 0 0 OA コブレーションシステムによる下鼻甲介粘膜焼灼術の治療成績 : レーザー焼灼術との比較検討
- 著者
- 谷 鉄兵 瀬野 悟史 花満 雅一 清水 猛史
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.8, pp.1053-1060, 2008-08-30 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
【背景】レーザーによる下鼻甲介粘膜焼灼術は,保存的治療のみでは症状を充分改善し得ないアレルギー性鼻炎に対する外科的治療として広く行われている.レーザーによる手術は鼻粘膜表面を焼灼するが,近年鼻粘膜上皮には影響を与えずに粘膜下を焼灼する高周波手術装置(ENTECコブレーター2サージェリーシステム^[○!R],以下コブレーション)を利用した下鼻甲介手術が報告されている.【方法】対象は,当科にて平成16年11月から平成19年5月までにコブレーションを用いて下鼻甲介粘膜焼灼術を行った29例(男性17例,女性12例,平均年齢37歳)で,手術前後のくしゃみ・鼻汁・鼻閉・日常生活支障度の症状スコアの検討を行い,レーザー手術50例(男性27例,女性23例,平均年齢25例)の術後成績と比較検討した.【結果】手術1ヵ月後の治療成績には差が認められないが,1年後にはレーザー手術では症状が再燃することが多いのに対してコブレーション手術では高い症状改善率(くしゃみ65%,鼻汁71%,鼻閉76%)が維持され,2年後にも同様の良好な成績が得られた.【結果】アレルギー性鼻炎に対してコブレーションによる下鼻甲介粘膜焼灼術により良好な長期成績を得ることができた.
- 著者
- 菱川 晶子
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.136, pp.159-185, 2007-03
1 0 0 0 OA 清末の満州開放論について
- 著者
- 閻 立
- 出版者
- 大阪経大学会
- 雑誌
- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.6, pp.193, 2018 (Released:2018-04-04)
- 著者
- 來間 啓伸 佐藤 直人 中川 雄一郎 小川 秀人
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.407-416, 2020-02-15
計算機システムが実世界と密に連携して動作するためには,論理的に記述・分析できない不確実性に適合するソフトウェアが必要であり,未知の入力値に対して学習データからの推論により出力値を返す機械学習の適用が注目されている.一方,このようなソフトウェアは入力データ空間が定義できず出力値に予測不能性があるため,ソフトウェアの振舞いを確率的にしか把握できない.本稿では,機械学習適用ソフトウェアの高信頼化を目的に,段階的詳細化による演繹的な開発法と機械学習による帰納的な開発法の結合についてテスト・検証の観点から述べ,開発プロセスと制約充足性テスト方法を提案する.我々のアプローチは,演繹的モジュールと帰納的モジュールを分離し,それらをつなぐ部分仕様を設定するとともに,前者については部分仕様が満たされることを前提に論理的な検証を行う一方,後者についてはテストにより部分仕様の充足確率を評価し,論理的な検証結果に確率を付与する.これにより,帰納的に開発した機械学習適用モジュールと演繹的に開発した論理モジュールを,システムの信頼性評価のもとで整合的に結合する.形式手法Event-Bを用いたケーススタディにより,実現可能性を評価した.
1 0 0 0 OA セッション6「風洞実験法他」
- 出版者
- 一般社団法人 日本風工学会
- 雑誌
- 日本風工学会誌 (ISSN:09121935)
- 巻号頁・発行日
- vol.1999, no.79, pp.87-102, 1999-04-30 (Released:2010-09-28)
1 0 0 0 農業センサを用いたトルコギキョウの個体損失の確率モデリング
- 著者
- 本廣 多胤 花田 裕美 吉廣 卓哉
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.375-384, 2020-02-15
農業従事者の高齢化にともない,農業IoTの導入による農業の効率化が求められている.センサを農場に設置して常時観測し,客観的な指標に基づいて栽培における各種判断をすることが期待されている.従来の経験に基づいた栽培を脱し,客観的指標に基づいた農業のマニュアル化・大規模化が可能になる.しかし,センサを用いて大量のデータを取得し,植物の特性を把握したうえで適切な栽培判断の指標を確立するためには,多くの変数をともなうデータ分析が必要となる.本研究では,経済的価値の高い実用花卉であるトルコギキョウを対象として,栽培時に起こるロゼット化およびブラスチングと呼ばれる個体損失要因を分析する.土壌センサを用い,組合せ的に設計された試験からデータを取得し,階層ベイズモデルを用いた個体損失の予測モデルを構築することで,個体損失が発生する条件を解明することを目指す.トルコギキョウにおける既存の知見に基づいて個体損失モデルを設計し,センサの測定値と組合せ的な試験区設計に基づいて取得したデータを適用した.その結果,ロゼット化およびブラスチングに対する各要因の影響の度合いを数値化し,それらの結果が既存の知見と合致することを確認しただけでなく,個体損失に関する新規の知見を得られる可能性を見出した.
1 0 0 0 OA 白亜紀中期の生物事変と古環境変動
- 著者
- 栗原 憲一 川辺 文久
- 出版者
- 日本古生物学会
- 雑誌
- 化石 (ISSN:00229202)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, pp.36-47, 2003-09-20 (Released:2017-10-03)
- 参考文献数
- 47
This paper documents extinction-recovery patterns of ammonoids and inoceramids across the Cenomanian/Turonian boundary (CTB) including the Oceanic Anoxic Event 2 (OAE2) in the Hakkin-zawa River section, Oyubari area, Hokkaido, Japan, and the Pueblo section, Western Interior, USA. The timing of extinction and recovery in these molluscan faunas occurred synchronously in both areas, based on micro-and macrofossil biostratigraphy and carbon-isotope chemostratigraphy. In the Hakkin-zawa, an ammonoid diversity decreased 0.5 to 0.9 m.y. prior to the CTB (extinction interval), reached a minimum just after the CTB (survival interval), and recovered 0.2 to 0.5 m.y. after the CTB (recovery interval). Inoceramids became increasingly dominant during the extinction and survival intervals, and the genus Inoceramus was replaced by the genus Mytiloides in the latter part of the survival interval. In the Western Interior, the extinction interval spanned 0.42 m.y. before the CTB, and the recovery of faunas took place after 0.15 m.y. from the CTB. In the Western Interior, nekto-benthic ammonoids of acanthoceratids disappeared earlier than planktonic heteromorph ammonoids such as Sciponoceras and Allocrioceras in the extinction interval. By contrast, the nektobenthic desmoceratids also appeared in the later part of the extinction interval in Hokkaido. This inconsistency presumably resulted from different expansion processes for oxygen-depleted water in an open ocean setting (Hokkaido) and a restricted seaway (Western Interior).
- 著者
- Tatsuro Matsumoto Tamio Nishida Seiichi Toshimitsu
- 出版者
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター
- 雑誌
- 地質調査研究報告 (ISSN:13464272)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3-4, pp.131-159, 2003-04-30 (Released:2015-01-19)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 6 11
アンモナイト類Acanthoceratidae科のUtaturiceras及びGraysonitesの2属は,北海道北西部の添牛内地区の白亜系セノマニアン階下部にかなり産出する.それに基づき両属の特徴を改めて認定し,U.属の3種(内1種は新種)とG.属の2種を記載し,それらの特徴を明示した.U. vicinale (Stoliczka), U. chrysanthemum n. sp., G. wooldridgei Young, G. adkinsi Youngはセノマニアン最下部を特徴付ける.しかしこれらが国内でも海外でも散点した地区からその産出が報告されている事実が気付かれ,若干論述を試みたが,産状についての結論にはさらに研究を重ねるべきである.
- 著者
- 奥村 惠介
- 出版者
- アジア教育学会
- 雑誌
- アジア教育 (ISSN:18822088)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.26-39, 2019
This paper explores how Indonesian Students on Reparations Agreement (ISRA) experience the International Students Institute (ISI) in Japan and how the experience has had an impact on the development of their Japanese language education.Despite the long relationship between Indonesia and Japan, there is limited research on the topic of the ISRA. The original plan of the Indonesian government was to dispatch 500 students to Japan for five years. In reality, since 1960, 389 students have visited Japan for six years. Their mission has been to learn about Japan's newest technology and economic growth.At the same time, the Japanese government began to actively admit foreign students, without having in place the admissions systems, facilities, or Japanese learning materials for these students. Following a one-year Japanese language course at ISI, these foreign students entered national or private universities. However, their Japanese language skills were not adequate to understanding university-level lectures. Based on requests from the universities, the ISI and Ministry of Education (ME) sought to improve Japanese language text books and the other materials required for foreign students to learn Japanese.The ISRA program had an important early impact on the development of Japanese language education.
- 著者
- Zihao Zhao Liang Li 長谷川 恭子 Fadjar I. Thufail 田中 覚
- 雑誌
- じんもんこん2019論文集
- 巻号頁・発行日
- no.2019, pp.287-292, 2019-12-07
1 0 0 0 OA 空間識と身体の平衡
- 著者
- 中原 はるか 竹森 節子 鶴岡 尚志
- 出版者
- Japan Society for Equilibrium Research
- 雑誌
- Equilibrium Research (ISSN:03855716)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.435-442, 1998 (Released:2009-10-13)
- 参考文献数
- 17
Spatial orientation is influenced by many factors such as vision, hearing, vestibular input, and so on. However, the details of when and which factor exert influence on this process remain mostly unknown. We investigated the influence of height on spatial orientation under various conditions.Body movement was recorded by stabilometry for 30 seconds under each of three visual conditions (eyes open without gaze fixation, eyes closed, and eyes open with gaze fixation) at 0 m, 1 m, 2 m, and 10 m22 cm high in 30 normal volunteers (14 males and 16 females) who had no history of vertigo or dizziness. Eight of subjects claimed to be acrophobic.The total length of the gravity center movements reflected the body sway best. The sway was minimal with eyes open and gaze fixated, and maximal with eyes closed. The sway increased at 10 m22 cm high, but was almost the same at 1 m and 2 m high. The acrophobic group was clearly worse than the non-acrophobic group at 10 m22 cm high. Their total shifting length increased because they became tense and shivered fractionally.Visual information which served as the base was useful for spatial orientation, and the mental factor of fear caused tension and the sway increased especially in the acrophobic group at 10 m22 cm high.