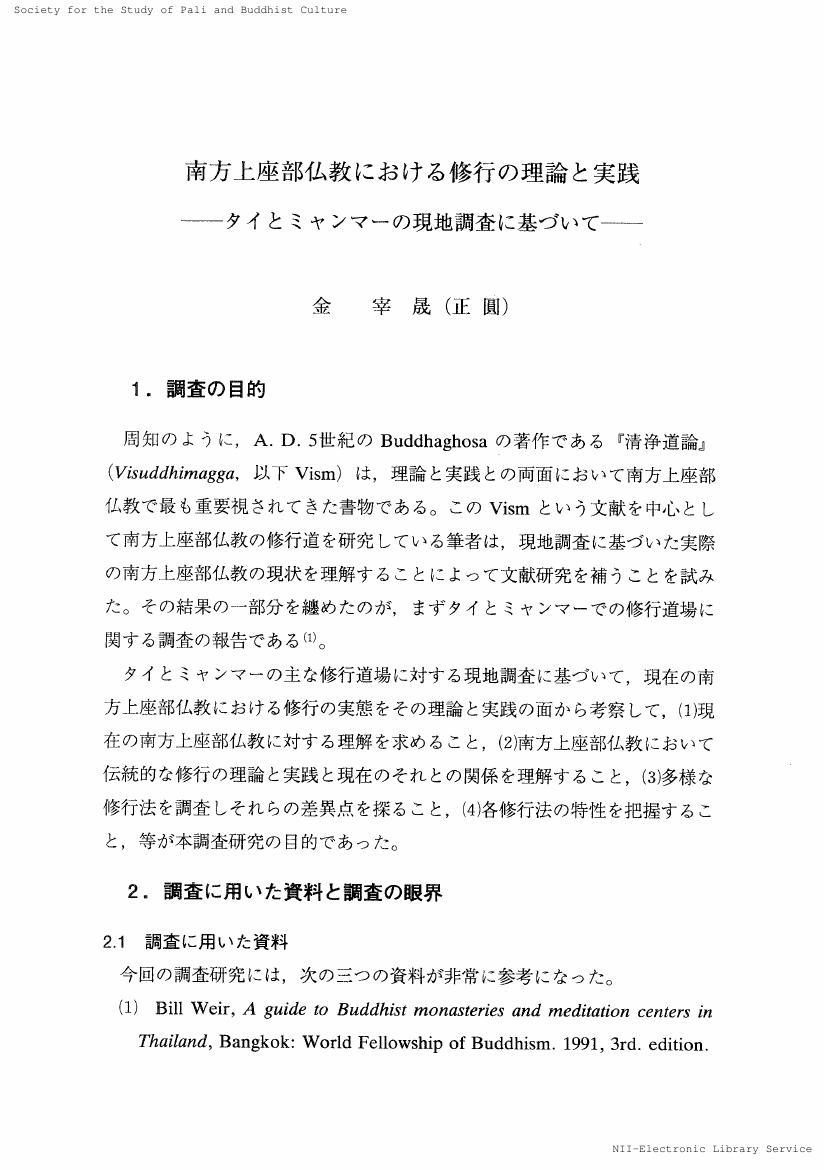- 著者
- Parth LODHIA Ken YAEGAKI Ali KHAKBAZNEJAD Toshio IMAI Tsutomu SATO Tomoko TANAKA Takatoshi MURATA Takeshi KAMODA
- 出版者
- Center for Academic Publications Japan
- 雑誌
- Journal of Nutritional Science and Vitaminology (ISSN:03014800)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.89-94, 2008 (Released:2008-04-04)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 38 56
Many food products are claimed to be effective in controlling halitosis. Halitosis is caused mainly by volatile sulfur compounds (VSCs) such as H2S and CH3SH produced in the oral cavity. Oral microorganisms degrade proteinaceous substrates to cysteine and methionine, which are then converted to VSCs. Most treatments for halitosis focus on controlling the number of microorganisms in the oral cavity. Since tea polyphenols have been shown to have antimicrobial and deodorant effects, we have investigated whether green tea powder reduces VSCs in mouth air, and compared its effectiveness with that of other foods which are claimed to control halitosis. Immediately after administrating the products, green tea showed the largest reduction in concentration of both H2S and CH3SH gases, especially CH3SH which also demonstrated a better correlation with odor strength than H2S; however, no reduction was observed at 1, 2 and 3 h after administration. Chewing gum, mints and parsley-seed oil product did not reduce the concentration of VSCs in mouth air at any time. Toothpaste, mints and green tea strongly inhibited VSCs production in a saliva-putrefaction system, but chewing gum and parsley-seed oil product could not inhibit saliva putrefaction. Toothpaste and green tea also demonstrated strong deodorant activities in vitro, but no significant deodorant activity of mints, chewing gum or parsley-seed oil product were observed. We concluded that green tea was very effective in reducing oral malodor temporarily because of its disinfectant and deodorant activities, whereas other foods were not effective.
3 0 0 0 OA 南方上座部仏教における修行の理論と実践 : タイとミャンマーの現地調査に基づいて
- 著者
- 金 宰晟
- 出版者
- パーリ学仏教文化学会
- 雑誌
- パーリ学仏教文化学 (ISSN:09148604)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.37-63, 1997-05-20 (Released:2018-09-01)
- 著者
- 八井田 朱音 大塚 理子 山田 安咲紀 中野 和彦 松井 久美 関本 征史 稲葉 一穂 伊藤 彰英
- 出版者
- The Japan Society for Analytical Chemistry
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.7.8, pp.341-350, 2020-07-05 (Released:2020-11-07)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 2
キレート固相抽出法を併用するICP-MS法により,多摩川の中流域から河口域までの15地点で採水した河川水試料を分析し,Sc,Y及びPmを除く14元素の希土類元素を定量した.分析結果をPAAS(Post-Archean Australian Average Shale)で規格化して希土類元素存在度パターン(希土パターン)を作成して考察したところ,多摩川では中流域の下水処理放流水合流地点から河口域までの試料で,Gdの存在度が隣接する他の希土類元素よりも明らかに高いGdの濃度異常が定常的に確認された.この濃度異常は,MRI造影剤として人体に投与されたGd化合物により引き起こされることが確認されており,Gd濃度を約20〜25年前の文献値と比べると,中流域と河口域の2地点について,それぞれ2〜4倍,3〜4倍の濃度であった.したがって近年,多摩川河川水においてはGd濃度が上昇していることが明らかになった.さらに,Gdの濃度異常について国内外の他の文献値と比較するために,Gdの濃度異常をGd異常度として数値化し,多摩川の潜在的人為汚染の現状を評価した.その結果,本研究で分析した多摩川中流域河川水のGd濃度及びGd異常度の最大値は,これまでの国内河川水の文献値と比較して最も高く,国外河川水のすべての報告値を含めて比較しても,ドイツのハベル川に次いで高いことが明らかになった.
3 0 0 0 OA 自己決定理論における動機づけ概念間の関連性
- 著者
- 岡田 涼
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.152-160, 2010-01-31 (Released:2010-02-28)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 2 4
自己決定理論(Deci & Ryan, 2000)では,さまざまな領域における動機づけをとらえる包括的な理論的枠組みを提供している。本研究では,メタ分析によって,自己決定理論における動機づけ概念間の相関係数の程度を特定し,動機づけ概念の背後にある次元を探ることを目的とした。レビューの結果,87論文115の相関行列を収集した。収集された相関行列から母相関係数を推定したところ,隣り合う動機づけ間の相関係数は,自己決定的なほうに進むにつれて大きくなる傾向がみられた。動機づけの次元について,自己決定性と統制的動機づけの2次元が見いだされた。動機づけ尺度の妥当性および動機づけの指標について論じた。
3 0 0 0 OA 救急隊による心電図判読の急性冠症候群に対する再灌流達成までの時間短縮効果
- 著者
- 中西 信人 説田 守道
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.5, pp.665-670, 2019-10-31 (Released:2019-10-31)
- 参考文献数
- 10
目的:心電図伝送システムの導入と維持には多大な経費がかかる。三重県では急性冠症候群が疑われる患者に対して救急隊による心電図判読を含むプロトコルを2013年10月より実施している。本研究の目的は,このプロトコル導入により,病院到着から再灌流までの時間が短縮するか否かを明らかにすることである。方法:プロトコル導入前後に当院に搬送された急性冠症候群,それぞれ149人および133人において,救急隊覚知および病院到着時から院内対応までの時間を比較検討した。さらに対象を日中搬送例,夜間搬送例に分類して検討した。 結果:プロトコル導入後,病院到着から再灌流時間を含む各対応時間はすべて有意に短縮し,夜間搬送例では救急隊覚知からの対応時間も短縮した。多変量解析から,プロトコルは再灌流時間短縮の独立した予測因子であった(p<0.01)。結語:救急隊による心電図判読は急性冠症候群に対する再灌流達成までの時間短縮に有用である。
- 著者
- 柴田 由紀枝 岩崎 雄一 竹村 紫苑 保高 徹生 髙橋 徹 松田 裕之
- 出版者
- 公益社団法人 日本水環境学会
- 雑誌
- 水環境学会誌 (ISSN:09168958)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.6, pp.183-188, 2020 (Released:2020-11-10)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
和賀川の清流を守る会 (以下, 守る会) は, 岩手県を流れる和賀川を公害から守り, 清流を保護することを目的として多様な利害関係者によって1972年に結成された。上流域に存在する休廃止鉱山の水質監視を主要な活動の1つとして, 守る会は, 会発足時から河川での水質調査, 1976年からは鉱山での水質調査を開始し, 測定結果を会報で報告している。排水基準を超過した場合も含むすべての測定結果が, 会報で公開・議論されている点は情報公開のあり方の点からも興味深い。また, 会報のテキスト分析によって, 1972年から2019年までの間に, ①公害への危惧, ②休廃止鉱山での水質監視や鉱害防止対策, ③水生生物など自然環境全体の保全, と会報の話題が変化していることが示された。守る会の活動を分析・整理した本研究の成果は, 排水基準の遵守のみに依拠しない休廃止鉱山における柔軟な坑廃水管理を検討する上で貴重な基礎資料となると考えられる。
3 0 0 0 OA 骨の健康とビタミンE:α-トコフェロールは本当に骨量を低下させるのか?
- 著者
- 笠井 俊二 福澤 健治
- 出版者
- 公益社団法人 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.10, pp.469-483, 2016 (Released:2017-12-26)
- 著者
- Kazuki Ide Hitoshi Koshiba Philip Hawke Misao Fujita
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- pp.JE20200506, (Released:2020-11-07)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 4
3 0 0 0 OA Dywidag工法による嵐山橋の設計,施工について
- 著者
- 中島 儀八 今井 勤 小田 純夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本材料学会
- 雑誌
- 材料試験 (ISSN:03727971)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.69, pp.519-527, 1959-06-15 (Released:2009-07-09)
3 0 0 0 OA ホスピタルアートに対する患者の鑑賞行動と印象の評価 -外来待合と連絡通路における調査
- 著者
- 吉岡 聖美
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.3_31-3_38, 2012 (Released:2012-11-30)
- 参考文献数
- 22
本論文では,病院に展示されたホスピタルアートに対する患者の鑑賞行動および印象の評価を調査することによって,ホスピタルアートの有効性を確認することを目的とする。方法は,病院の外来待合および連絡通路のホスピタルアートについて,患者の鑑賞行動と快・不快の印象についての評価,および,通院期間,通院頻度,当日の経過時間,平均的な病院滞在時間について外来患者から回答を求めて分析を行った。外来待合では,待ち時間が長い患者ほど,通院に対するホスピタルアートの鑑賞頻度が大きく,意識的に見て,快さが大きいことが示された。また,連絡通路では,通院期間が長い患者ほど,通院に対するホスピタルアートの観賞頻度が大きく,意識的に見て,快さが大きいことが示された。これにより,病院に展示するために制作されたホスピタルアートについての有効性が示された。
3 0 0 0 OA 『夕やけ雲』(1956)における木下惠介のクィアな感性 少年同士の情動表象をめぐって
- 著者
- 久保 豊
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.44-62, 2015 (Released:2017-04-03)
- 参考文献数
- 16
3 0 0 0 OA 病棟配置された軟膏剤やクリーム剤の衛生管理に関する複数施設での実態調査
- 著者
- 中川 博雄 伊東 潤一 岡田 昌之 岩村 直矢 今村 政信 北原 隆志 佐々木 均 室 高広
- 出版者
- 一般社団法人 日本環境感染学会
- 雑誌
- 日本環境感染学会誌 (ISSN:1882532X)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.176-181, 2019-05-25 (Released:2019-11-25)
- 参考文献数
- 6
病棟配置された処置用の軟膏剤やクリーム剤に対して,これまでに管理方法や微生物汚染の実態を複数施設で調査した報告はない.そこで本研究では,長崎県病院薬剤師会感染制御ワーキンググループの会員施設で協力が得られた3施設を対象に,病棟配置された処置用の軟膏剤やクリーム剤の衛生管理に関する聞き取り調査および微生物汚染の実態調査を行った.さらに,病棟配置された処置用の軟膏剤やクリーム剤の開封後の使用期限について検討する目的で,基剤の異なる代表的な軟膏剤やクリーム剤に手指の常在微生物を塗布する評価法を用いて,微生物汚染までの期間を調査した.その結果,3施設いずれにおいても軟膏剤やクリーム剤の衛生管理マニュアルは整備されていなかった.また,微生物汚染の実態調査では,3施設の軟膏剤やクリーム剤128個全てで微生物汚染は認められなかった.さらに,実験による評価では,基剤の違いや防腐剤の有無に関わらず,6か月間にわたり軟膏剤やクリーム剤で微生物汚染は認められなかった.よって,処置用の軟膏剤やクリーム剤は直接素手で採取しないなどの衛生管理に注意を払えば,開封後6か月間まで使用可能であることが示唆された.
- 著者
- 後藤 温
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.10, pp.694-697, 2020-10-30 (Released:2020-10-30)
- 参考文献数
- 7
3 0 0 0 OA 伝書にみる居合と剣術の関係について
- 著者
- 和田 哲也
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.10-16, 1986-07-31 (Released:2012-11-27)
- 参考文献数
- 28
The practical characteristics of Iai and Kenjutsu are quite distinct when they are phenomenally judged. In Iai, on the whole, unsheathing the sword is the most important technique and great weight is given to the process of unsheathing it. In Kenjutsu, on the other hand, the technique begins after unsheathing the sword and taking a certain posture (kamae). So we can regard the relation between the two as “mihatsu” (before unsheathing) and “ihatsu” (after unsheathing).Closer investigation, however, reveal that Iai has “kata” not only of “mihatsu”but also of“ihatsu”in the case of “tachiai” (initial moving from standing posture), and that Kenjutsu also has its own techniques to unsheathe the sword. Thus these two martial arts, in which to use the Japanese swords, have the technique in common with each other. But, the main purpose of Iai is to cope with emergencies in daily life, so the point of view was directed to various, broad aspects of daily life, and in Kenjutsu, the point of view was directed only to the aspects of fighting after taking a certain posture. On that point these two were remarkably different from each other.Iai and Kenjutsu, after Ede era, had tendency to develop in their own way and to specialize as well. But on account of this, there appeared reversed thought that these two should be regarded as compensating each other.
3 0 0 0 OA 外科結びのための新しい結紮法 (第2法)
- 著者
- 石井 正則
- 出版者
- 耳鼻咽喉科展望会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.419-420, 1984-08-15 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 1
Although the author reported a one-hand ligation method previously two disadvantages were noted later; firstly it required complicated manipulation, and secondly the thread would be prone to severing because of frequent tangling. The new method presented here using two hands is simple quick and secure, and can be used as easily as the conventional methods.
- 著者
- Ikuo Miura Masataka Tagami Takeshi Fujitani Mitsuaki Ogata
- 出版者
- The Genetics Society of Japan
- 雑誌
- Genes & Genetic Systems (ISSN:13417568)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.4, pp.189-196, 2017-08-01 (Released:2018-02-10)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 6
The present study reports spontaneous tyrosinase gene mutations identified in oculocutaneous albinos of three Japanese wild frog species, Pelophylax nigromaculatus, Glandirana rugosa and Fejervarya kawamurai. This represents the first molecular analyses of albinic phenotypes in frogs. Albinos of P. nigromaculatus collected from two different populations were found to suffer from frameshift mutations. These mutations were caused by the insertion of a thymine residue within each of exons 1 and 4, while albinos in a third population lacked three nucleotides encoding lysine in exon 1. Albinos from the former two P. nigromaculatus populations were also associated with splicing variants of mRNA that lacked either exons 2–4 or exon 4. In the other two frog species examined, missense mutations that resulted in amino acid substitutions from glycine to arginine and glycine to aspartic acid were identified in exons 1 and 3, respectively. The two glycines in F. kawamurai and G. rugosa, and the lysine deleted in one P. nigromaculatus albino, were highly conserved in vertebrates, which suggested that they were situated in regions of critical importance to tyrosinase function. In fact, the glycine of G. rugosa is located within a predicted copper-binding domain. The five mutations identified in the present study are candidates for causing the albinic phenotypes, and, if directly confirmed, they are all unique among vertebrates, which suggests that molecular analysis of albino frogs could contribute to research on albinos in humans and vertebrates by providing new information about tyrosinase structure and transcript processing.
3 0 0 0 OA 一主要新聞紙朝刊のテレビ番組表からみた自殺・メンタルヘルス関連の報道の実態
- 著者
- 篁 宗一 清水 隆裕 猫田 泰敏
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.73-81, 2015 (Released:2015-04-10)
- 参考文献数
- 29
目的 本研究は,新聞紙のテレビ番組表から,自殺およびメンタルヘルスに関する情報を抽出し分析することによってテレビ番組による自殺報道の実態を明らかにすることとした。方法 一つの主要新聞紙から2004~2009年 6 月までのテレビ番組表の紹介欄から情報を抽出した。情報抽出においては,精神保健を専門とする研究者 2 人が独立に判断し,信頼性を保った。分析データは,テレビ番組表内の地上波 6 局の「番組名および紹介」の欄(最終の一面全体,以下紹介欄)を対象とした。「自殺と関連情報について事前に決定した選択基準に沿って抽出を行った後番組内のサブテーマの情報抽出を行った。また体験談の有無など,その他の属性および番組ジャンルや専門性についても情報を分類した。これら収集した情報データは質的な分類を行った他,件数および割合(%)を時系列および属性で比較した。また番組紹介の内容に関する傾向とメディアにおいて,一事例を繰り返し取り扱った番組の分析をそれぞれ行った。結果 期間中コンスタントに自殺を取り扱う番組がみられた。季節は春と秋,曜日は火曜日と水曜日の順であった。同一の事例が繰り返し10回以上報道されたのは 8 ケースであった。自殺のサブテーマとしてはいじめや殺人,うつ病であった。対策なども含み専門性の高い番組は47件(7.6%)で,504件(81%)の番組は専門性の低い番組であった。結論 自殺はテレビ番組で継続的に取り扱われている。番組の動向から,季節や曜日によって変動がみられた。いじめなど注目を集めやすいテーマが多く,専門性が低い傾向にあることが予測された。集中する報道による当事者の二次的な被害も考えられた。
3 0 0 0 OA 各種微生物に対するホウ酸の抗菌力
- 著者
- 勝川 千尋 原田 七寛 津上 久弥 牧野 正直
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学療法学会
- 雑誌
- CHEMOTHERAPY (ISSN:00093165)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.11, pp.1160-1166, 1993-11-25 (Released:2011-08-04)
- 参考文献数
- 10
皮膚科領域の各種感染症治療における, ホウ酸利用の可能性について検討を行った。この目的のため, 標準菌株および臨床患者から分離された病原微生物に対するホウ酸の抗菌力の測定を行い, 以下の成績を得た。1.検査したすべての細菌および真菌が, ホウ酸1%(wt/vol) の濃度で発育が阻止され, 高濃度のホウ酸に耐性の菌は認められなかった。2.ホウ酸の各種微生物に対する発育阻止濃度は0.125%-1%の範囲に分布し, 菌種毎に以下のような特徴がみられた。同一菌種間は似た発育阻止濃度値を示したが, 同じ属であっても菌種が異なると, 発育阻止濃度も異なった値を示した。総じてグラム陽性菌に対する発育阻止濃度が高く, グラム陰性菌に対しては低かった。しかし, ブドウ球菌属中のStaphyloooccus aureusだけは異なり, Staphylococcus epidermidis やStaphylococcus hominis などのコアグラーゼ陰性ブドウ球菌に対する発育阻止濃度が高いのに対して, S. aureusに対しては低かった。3.S. aureusは近年, 多剤耐性化が問題となっているが, ホウ酸の発育阻止濃度はmethicillin-resistant S. aureus (MRSA) およびmethicillin-sensitive S. aureus (MSSA) の間に差は認められなかった。また, 他の菌種もホウ酸に対して耐性化の傾向は認められなかった。今回検査したすべての細菌および真菌に対する発育阻止濃度が1%以下であることから, 2-3%の低濃度での安全性の高い利用方法を考案することにより, ホウ酸を再び活用できる可能性があると考えられた。特にMRSAに対して耐性化の傾向の認められない点はMRSA感染予防の1つの打開策となり得ることを示唆している。
- 著者
- Hajime Inoue
- 出版者
- National Center for Global Health and Medicine
- 雑誌
- Global Health & Medicine (ISSN:24349186)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.131-132, 2020-04-30 (Released:2020-05-10)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1 27
Despite substantial inflow of infected cases at the early stage of the pandemic, as of the end of April, Japan manages the outbreak of COVID-19 without systematic breakdown of health care. This Japanese paradox – limited fatality despite loose restriction – may have multiple contributing factors, including general hygiene practice of the population, customs such as not shaking hands or hugging, lower prevalence of obesity and other risk factors. Along with these societal and epidemiological conditions, health policy options, which are characteristic to Japan, would be considered as one of the contribution factors. Some health policy factors relatively unique to Japan are described in this article.
3 0 0 0 OA 漆塗膜に関する研究 (第2報) 酸化鉄の影響
- 著者
- 見城 敏子
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.10, pp.470-474, 1971-10-30 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 3