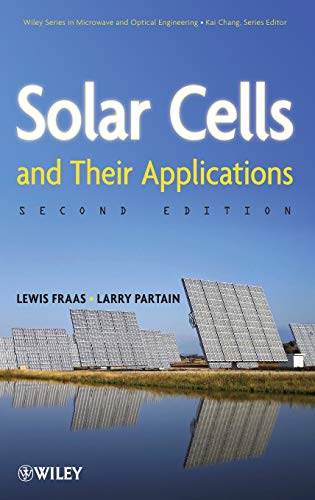1 0 0 0 度重なる勧告にも従わない日本政府 (国連人権勧告)
1 0 0 0 IR 8文型システムによる基本文型と派生文型の統合的分析
- 著者
- 河宮 信郎 Nobuo KAWAMIYA
- 出版者
- 中京大学文化科学研究所
- 雑誌
- 文化科学研究 (ISSN:09156461)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.1-14, 2005
英語文型に関しては、Onions以来の伝統的な5文型論がながらく標準であった。しかし、副詞を文型要素から一律に排除することは不合理であり、5文型では原理的にカバーできない構文が多数あった。R.Quirkらはこの点を是正し、「7文型論」を提起した。これにより、英語構文をひろくカバーできるようになった(網羅性の向上)。これをさらに改良したものが安藤貞雄の「8文型論」である。なお、「8文型」の枠に収まらない「派生文型」が4種ある。構文に対する網羅性を高めるために、文型数を増やすと簡明さや一覧可能性が損なわれる。高い網羅性と簡明さを兼ね備えた文型システムが望まれる。本考察は、8文型論の再検討と拡張によってこの課題に答えることを試みる。自動詞の文型はSV;SV+A or C;SVC+A or zのいずれかである。これを包括的にSVXYと表す(空白の項を含む)。他動詞の文型はSVOXで、Xは空白(Null)、O、A、or Cのいずれかである。本考察によれば、自動詞文型SVXY、他動詞文型SVOXに対して、文型要素の個数と品詞的機能からX、Yを容易に決めうる。この方法によれば、「派生文型」を含めた一般の構文に対して、的確な文型分析を簡明かつ迅速に行うことができる。
1 0 0 0 OA 最近全国新聞紙雑誌総目録
1 0 0 0 OA 中枢発生気管支カルチノイド: 気管支壁深達度のHRCT所見と病理所見を対比した2例
- 著者
- 松隈 治久 横井 香平 安楽 真樹 神山 由香理 森 清志 津浦 幸夫
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本肺癌学会
- 雑誌
- 肺癌 (ISSN:03869628)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.143-146, 2001-04-20 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2
中枢の気管支腔内にポリープ状に発育する定型的カルチノイドの2症例について, HRCT所見と病理所見を比較検討した. 1例は61歳男性で, 左主気管支内腔をほぼ閉塞する可動性のあるポリープ状の腫瘍を有し, 他の1例は39歳男性で, 右中間気管支幹内腔を占める可動性のあるポリープ状腫瘍を認め, 両者とも生検にて定型的カルチノイドと診断された. 術前に行われた造影HRCTではいずれも気管支内腔に軽度の造影効果を有する腫瘍としてとらえられ, 明らかな壁外進展の所見は認めなかった. 前者は残存肺の再膨張が得られず肺全摘術を, 後者は中間気管支幹管状切除術を施行した. 切除標本の病理検査では両者とも細い茎 (8mm, 9mm) を有しほぼ全体が気管支腔内に存在する腫瘍であったが (大きさ3.5×1.8×1.2cm, 2.0×1.3×1.0cm), いずれもわずかに気管支軟骨の外側にまで腫瘍浸潤を認めた. HRCTにて明らかな壁外成分や気管支壁の肥厚や不整所見を示さなかったが, 病理学的には気管支軟骨外まで浸潤していた中枢発生定型的気管支カルチノイド症例を2例経験したので報告した.
1 0 0 0 OA 肺, 気管支カルチノイド20手術症例の臨床的検討
- 著者
- 上林 孝豊 柳原 一広 宮原 亮 板東 徹 長谷川 誠紀 乾 健二 和田 洋巳
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本呼吸器外科学会
- 雑誌
- 日本呼吸器外科学会雑誌 (ISSN:09190945)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.5, pp.566-569, 2003-07-15 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2
目的・対象: 当院で手術を施行し, 病理組織学的に肺カルチノイドと診断された20症例 (定型15例, 非定型5例) の臨床的検討を行った.結果: 定型, 非定型の5年生存率は, それぞれ86.6%, 60%であった.定型の1期症例は術式に関わらず全例, 無再発で生存中である.非定型は全例, 葉切除および肺門縦隔リンパ節郭清が行われていた.1期3症例は, いずれも無再発で生存中であるが, T2N2のIIIA期症例, T4NOのIIIB期症例は, 集学的治療にも関わらずそれぞれ術後10ヵ月後, 61ヵ月後に遠隔転移にて癌死した.定型では観察期間1~250ヵ月間 (平均観察期間72.8ヵ月) において, 5年生存率は86.6%であった.非定型では観察期間10~251ヵ月間 (平均観察期間121, 4ヵ月) において5年生存率は60%であった.まとめ: T2の定型カルチノイドに対する縮小手術の可能が示唆された.またIII期以上の非定型カルチノイドに対しては有効な集学的治療の確立が望まれる.
1 0 0 0 アンカリング効果のメカニズムにおける「カバー効果」の検討
- 著者
- 杉本 崇 高野 陽太郎
- 出版者
- The Japanese Society for Cognitive Psychology
- 雑誌
- 認知心理学研究 (ISSN:13487264)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.51-60, 2014
従来アンカリング効果は数的な過程によって起こるとされていたが,近年ではアンカーによって実験参加者の持つ知識が選択的に活性化されるために起こるという意味的過程モデルが提唱されている(Mussweiler & Strack,1999a).杉本・高野(2011)では,このモデルを検討するために参加者が非常に乏しい知識しか持ち合わせない対象について推定させたところ,意味的過程によって効果が起こりえないときは数的過程によって効果が起こるというメカニズムが示された.本研究の目的はその「カバー効果」を再検討することである.そのため,「曹操」と「コバール」を推定対象として採用した二つの実験を行った.その結果,双方の実験で「カバー効果」を再現することができた.
1 0 0 0 OA 日米安保体制と台湾の国家安全保障 ―周辺事態法の適用を中心として―
- 著者
- 呉 春宜
- 出版者
- 京都大学人文科学研究所
- 雑誌
- 人文學報 = The Zinbun Gakuhō : Journal of Humanities (ISSN:04490274)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, pp.191-225, 2004-12
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1901年07月06日, 1901-07-06
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1889年12月17日, 1889-12-17
1 0 0 0 OA Webデータの新しい利用法の開拓を目指して
- 著者
- 山名 早人
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告データベースシステム(DBS)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.45(2004-DBS-133), pp.107-110, 2004-05-14
インターネット上のWWWサーバから発信される情報量は膨大であり、2004年4月時点で、テキストデータだけでも92.5億ページと推測される。また、2002年?2003年の増加傾向をみると、Webページは今後も1年間におよそ10億ページずつ増加を続けると予想される。このような膨大なWebページには、人間が一生かかっても学ぶことのできない情報、知識、ノウハウが凝縮されていると言っても過言ではない。本稿では、このような膨大なWebデータをどのように収集し更新すべきか、そして、このような膨大なWebデータをどのように有効活用すべきかについて、いくつかの研究事例を紹介すると共に、新しい利用法について考える。
1 0 0 0 IR デジタル空間に移行する大学教育(<特集>学術情報の電子化)
- 著者
- 船守 美穂
- 出版者
- 社団法人情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.6, pp.258-263, 2015-06-01
大規模公開オンライン講座(MOOC)は2012年に米国のエリート大学を中心に生み出され,世界的に一世を風靡した。この動きは,cMOOC,反転授業,パーソナライズド学習,ラーニング・アナリティクス,高等教育のアンバンドリングなど,デジタル時代の新たな学習方法にスポットライトを当てていったが,これは振り返ってみると,これまでの計算機やインターネットの発達とともに幾たびとなく取り上げられては,消え入っていた取り組みであった。しかし時代の進行とともに,これら取り組みは実質度を増し,着実に社会に定着している。本稿では,MOOCを軸に,これらデジタル時代における大学教育の学習形態等について紹介し,近未来の大学教育像を提示する。
1 0 0 0 OA ネットワーク構造の局所エネルギー最小化による可視化の高速化
- 著者
- 茂尾 亮太 鈴木 育男 山本 雅人 古川 正志
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告. MPS, 数理モデル化と問題解決研究報告 (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, no.7, pp.1-6, 2009-09-03
データ関係をノードとエッジで表すネットワーク構造は多くの分野で共通に利用されている.ネットワークの可視化技術は単なるノード間のつながりからは発見できないネットワークの構造や特徴を見出すのに有用な技術である.従来の研究で様々な可視化手法が提案されてきたが,本研究では力学的手法に焦点を当てる.力学的手法は実装と拡張が容易な最も一般的な可視化手法であるが,可視化のための計算量が大きく大規模なネットワークには適用することができない.しかし,比較的小規模なネットワークに対してはネットワークの特徴を捉え高速に可視化が可能である.提案手法では可視化対象のネットワークのある範囲内のノード群に対し,局所的エネルギー最小化によるノード配置をランダムに繰り返し行うことにより,ネットワーク全体の大域的なノード配置を導出する.これにより,計算量を削減し高速化に可視化を行う.また,従来手法との比較を行い提案手法の有用性を検証した.
1 0 0 0 OA 数理モデルを用いた作業環境における揮発性有機化合物のばく露評価に関する研究
- 著者
- Fumi YOSHIDA Akimasa TSUJIMOTO Ryo ISHII Kie NOJIRI Toshiki TAKAMIZAWA Masashi MIYAZAKI Mark A. LATTA
- 出版者
- 日本歯科理工学会
- 雑誌
- Dental Materials Journal (ISSN:02874547)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.6, pp.855-862, 2015-11-27 (Released:2015-12-01)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 2 37
This study investigates the influence of surface treatment of contaminated lithium disilicate and leucite glass ceramic restorations on the bonding efficacy of universal adhesives. Lithium disilicate and leucite glass ceramics were contaminated with saliva, and then cleaned using distilled water (SC), or 37% phosphoric acid (TE), or hydrofluoric acid (CE). Specimens without contamination served as controls. The surface free energy was determined by measuring the contact angles formed when the three test liquids were placed on the specimens. Bond strengths of the universal adhesives were also measured. Saliva contamination and surface treatment of ceramic surfaces significantly influenced the surface free energy. The bond strengths of universal adhesives were also affected by surface treatment and the choice of adhesive materials. Our data suggest that saliva contamination of lithum disilicate and leucite glass ceramics significantly impaired the bonding of the universal adhesives, and reduced the surface free energy of the ceramics.
1 0 0 0 地方独立行政法人の制度と評価 : 大阪府の出資法人改革からの考察
- 著者
- 南島 和久
- 出版者
- 地方自治総合研究所
- 雑誌
- 自治総研 (ISSN:09102744)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.6, pp.29-53, 2012-06
1 0 0 0 不在図書と複本について
- 著者
- 服部 金太郎
- 出版者
- 日本図書館協会
- 雑誌
- 図書館雑誌 (ISSN:03854000)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.11-13, 1952-01
1 0 0 0 OA 俳諧手挑灯
- 著者
- 桐淵貞山 (芦丸舎) 編
- 出版者
- 昌平楼
- 巻号頁・発行日
- 1884
- 著者
- edited by Lewis Fraas Larry Partain
- 出版者
- Wiley
- 巻号頁・発行日
- 2010
1 0 0 0 IR フッサールにおける「射映」の概念 : 表象媒体の研究の一環として
- 著者
- 小熊 正久
- 出版者
- 山形大学
- 雑誌
- 山形大學紀要. 人文科學 (ISSN:05134641)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.1-23, 2012-02-15
In der Analytik der Intentionalitat, hat Husserl zwei Momente von der "Vorstellung" geschieden, d.h. "Empfindungsdaten" und "Auffassung". Empfindungsdaten fungieren als "Abschattungen" in der "ausseren Wahrnehmung". Und sie sind gegeben in der phanomenologischen Reflexion. Aber, was fur eine Beziehung besteht zwischen diesen Momenten in der Wahrnehmung ? Diese Abhandlung versucht, Natur und Funktion von der "Abschattung" als dem Medium der Wahrnehmung zu erklaren, nach den Husserls Analysen in Ding und Raum 1907 und Einfuhlung in die Phanomenologie der Erkenntnis 1909 . Und dabei besondere Achtung wird gegeben auf die raumlichen und zeitlichen Momente von der Abschattung . Dafur mussen wir folgende Sachen betrachten : 1. Phanomenologische Methode und Analyse der Wahrnehmung 1) Transzendenz des Wahrgenommenen vom Bewusstsein und Phanomenologische Reduktion 2) Leibhaftikeit und Wirklichkeit des Wahrgenommenen 3) Immanente Wahrnehmung und Transzendente Wahrnehmung 4) Entsprechung von der Empfindungsdaten und der gegenstandlichen Qualitaten 2. Der Begriff der Abschattung 3. Die Raumliche Extension der Abschattung und das Feld der Wahrnehmung 4. Die Zeitliche Extension der Abschattung und das innere Zeitbewustsein 5. Probleme der phanomenologischen Reflexion Das Ergebnis dieser Studie ist folgendes: "Abschattung" kann als "Medium" der Wahrnehmug fungieren, wenn sie einerseits raumlich in dem Feld der Wahrnehmung , andererseits zeitlich in dem System der Retentionen etc. gegeben sind.