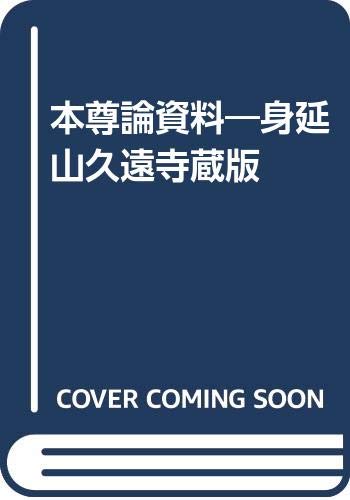1 0 0 0 植物生体電位を用いた人体活動モニタリング
- 著者
- 広林 茂樹 田村 祐輔 山淵 龍夫 大薮 多可志
- 出版者
- The Institute of Electrical Engineers of Japan
- 雑誌
- 電気学会論文誌E(センサ・マイクロマシン部門誌) (ISSN:13418939)
- 巻号頁・発行日
- vol.127, no.4, pp.258-259, 2007
- 被引用文献数
- 5 10
In this paper, we monitored the electromagnetic waves generated by human activity. We investigated a monitoring system that used the bioelectric potential of a plant. Four subjects walked on the spot at a distance of 60 cm from a rubber tree and we measured the variation in the bioelectric potential of the tree produced by the stepping motion. The results confirmed that the electromagnetic waves generated by a person walking on the spot produced a measurable response in the bioelectric potential of a plant. It was also found that this variation in the bioelectric potential varied in synchrony with the subject's walking pace.
1 0 0 0 平安期邸宅における所有と居住
- 著者
- 高 正樹
- 出版者
- 洛北史学会
- 雑誌
- 洛北史学 (ISSN:13455281)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.1-22, 2014
1 0 0 0 小児泌尿器科の内視鏡手術
- 著者
- 森 義則 川口 理作 島田 憲次 生駒 文彦
- 出版者
- 社団法人日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科學會雜誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.10, pp.1799-1811, 1983-10-20
- 被引用文献数
- 2
1974年から1982年までの9年間に兵庫医科大学泌尿器科において,201例の小児泌尿器科疾患,患者に対して内視鏡手術が施行された.その内訳は,後部尿道弁32例,前部尿道弁4例,先天性球部尿道リング状狭窄135例,後天性尿道狭窄16例,膀胱頚部狭窄8例および尿管瘤6例であった.10Charriereまたは13Charriere幼小児切除鏡を使用した.後部尿道弁および前部尿道弁に対しては TURによる弁の切除が施行されたが,結果はきわめて満足すべきものであった.先天性球部尿道リング状狭窄に対しては直視下内尿道切開が施行されたが, VUR,夜尿症,再発性尿路感染の各々に対して良い結果がみとめられた.後天性尿道狭窄のうち瘢痕組織の強いものでは数回の直視下内尿道切開を要したが,ほぼ満足すべき結果であった.膀胱頚部狭窄に対する TURの効果がはっきりみとめられたものはなかったが,これは小児の膀胱頚部狭窄は他の原因による二次的なものがほとんどであるためと思われた.その他尿管瘤に対する内視鏡手術の適応についても述べた.
- 著者
- 武田 幸作
- 出版者
- 日本薬史学会
- 雑誌
- 薬史学雑誌 (ISSN:02852314)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.111-116, 2012-12-30
- 著者
- 井上 裕太
- 出版者
- 國學院大學総合企画部
- 雑誌
- 國學院雜誌 = The Journal of Kokugakuin University (ISSN:02882051)
- 巻号頁・発行日
- vol.116, no.5, pp.1-17, 2015-05
1 0 0 0 豊和工業株式会社 本社工場
- 著者
- 加藤 明治
- 出版者
- 日本建設機械化協会
- 雑誌
- 建設の機械化 (ISSN:02855453)
- 巻号頁・発行日
- vol.598, pp.57-60, 1999-12-25
- 著者
- 山下 民治 米田 達雄
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.214-221, 1989
- 被引用文献数
- 3 6
デンプンをスケトウダラすり身に対し10%添加したかまぼこの物性に及ぼすデンプンの種類や加熱条件などの影響について検討を行い,次の結果を得た. <BR>(1) かまぼこのゼリー強度が最大になる加熱温度(T<SUB>m</SUB>)は,モチゴメデンプン添加区は75℃,コメやタピオカデンプン添加区は75~80℃,モチトウモロコシデンプン添加区は80℃,アミロメイズデンプン添加区は85℃,ジャガイモやコムギ,サツマイモ,トウモロコシ,クズデンプン添加区は90℃であった. <BR>(2) 魚肉すり身に添加したデンプンの糊化開始温度は,デンプン糊の糊化開始温度に比べて8~15℃高かった. <BR>(3) それぞれのデンプンを含むかまぼこをT<SUB>m</SUB>で加熱し続けたときに起るゼリー強度低下や圧出水分率の増加は, T<SUB>m</SUB>が85~90℃にあるデンプン添加区よりも,75~80℃にあるものの方が大きかった. <BR>(4) T<SUB>m</SUB>で40分間加熱したとき,ゼリー強度が最も大きかったのは,ジャガイモ,アミロメイズ,サツマイモ,トウモロコシデンプン添加区であり,次いでクズ,コムギ,コメ,タピオカデンプン添加区の順で,モチゴメ,モチトウモロコシデンプン添加区が最も小さかった. <BR>(5) それぞれのデンプンを含むかまぼこを,加熱温度を122℃にして, F<SUB>O</SUB>=4の条件で加熱したときのデンプンの種類によるゼリー強度や軟らかさの大小の順位は,T<SUB>m</SUB>で加熱したときのそれらの物性の大小と同じ順位であった.
1 0 0 0 ラッコ・オットセイ猟業の成立・変遷と資源管理論 (1)
- 著者
- 和田 一雄
- 出版者
- 「野生生物と社会」学会
- 雑誌
- 野生生物保護 : Wildlife conservation Japan (ISSN:13418777)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.93-120, 1997-01
- 被引用文献数
- 2
In Russia, sea otter (Enhydra lutris) harvest started in 1741 when Bering's expedition arrived at Bering Island and the animals nearly became extinct during the following twenty years. Shortly thereafter sealing of northern fur seals (Callorhinus ursinus) started and continued. A Russian monopoly, the Russian-American Company, managed Russian colonies and the land sealing industry from 1799 to 1867. Sealing of northern fur seals at sea started in 1866, and soon its harvest exceeded that of on land. For prohibiting sealing at sea Canada, Japan, USA and USSR contracted the Interim Convention on Conservation of North Pacific Fur Seals in 1911 (ICCNPFS). Since the eighteen century, sealing history is divided to three stages : 1) first stage of natural resource plundering with territory, 2) second stage of marketing management during the period of the Russian-American Company (1799-1867), 3) third stage of preliminary natural resource management during 1868 and 1911.
1 0 0 0 OA 「分析」とは何の謂いか : 「分析」概念の歴史におけるフロイト
- 著者
- 原 和之
- 出版者
- 東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻
- 雑誌
- Odysseus : 東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻紀要 (ISSN:13450557)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.83-113, 2014-03-17
- 著者
- 浦上 克哉 谷口 美也子
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.11, pp.841-844, 2009 (Released:2009-12-28)
- 参考文献数
- 16
アルツハイマー型認知症(AD)は"ありふれた疾患"と位置づけられている.現在ADの根本治療薬の開発が急速な勢いで進展中であり,ADの早期診断マーカーの開発が期待されている.本稿では,ADの早期診断マーカー研究の現状と展望を述べる.ADの早期診断マーカーの役割として2つあると考えられる.より確定診断に役立つもの,スクリーニングに役立つもの2つである.より確定診断に役立つバイオマーカーとして単独では,髄液中リン酸化タウ蛋白の測定がもっとも信頼性が高いと考えられる.スクリーニング検査としてはタッチパネル式コンピューターをもちいた認知症の簡易スクリーニング検査法(物忘れ相談プログラム,日本光電社製)が有用と考えられる.ADの早期診断マーカーの今後の展望として血液で測定可能なものが期待される.われわれのグループはWGA結合トランスフェリンを血液中で測定し,ADとコントロール間で有意差をみとめ,さらにアミロイドβ蛋白より先行する変化であることをみとめた.今後,血液中のバイオマーカーとして期待される.
1 0 0 0 本尊論資料 : 身延相傳 ; 諸山相傳
- 著者
- 身延山短期大学出版部編
- 出版者
- 臨川書店
- 巻号頁・発行日
- 1978
1 0 0 0 里見泰穏先生著作論文集
1 0 0 0 OA 発達2128 対象を操作するときの身振り表現 : はさみをチョキで表すのは未発達の証拠か
- 著者
- 西尾 民子
- 出版者
- 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集
- 巻号頁・発行日
- no.36, 1994-08-20
1 0 0 0 身延山資料叢書
- 出版者
- 身延山大学東洋文化研究所
1 0 0 0 OA フロイトの『妄想と夢』における文芸の精神分析の目的テクストを読むことと精神分析
- 著者
- 山本 淳 ヤマモト ジュン Jun Yamamoto
- 雑誌
- 雲雀野 = The Lark Hill
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.1-16, 2010-03-31
1 0 0 0 単腎サンゴ状結石症の結石破砕治療経験
- 著者
- 荒川 孝 久保 星一 真下 節夫
- 出版者
- 社団法人日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科學會雜誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.2, pp.174-182, 1992-02-20
- 被引用文献数
- 4
1984年12月から1989年12月までの約5年間に,11例の単腎サンゴ状結石に対し体外衝撃波結石破砕術(以下ESWL)を中心とした結石破砕治療を試みた.8例が結石にて対側の腎摘をうけたかまたは無機能となっており,3例が腎結核にて腎摘をうけている.男性6例,女性5例で平均年齢はそれぞれ60.0歳,48.6歳であった.結石の大きさは,最大がX線写真上85×44mm,最小が30×30mmである.11例中術前にシスチン結石の診断をえている1例に対してのみ経皮的腎結石破砕術(以下PNL)を先行させたが,他の10例はESWLから破砕治療開始とした.ESWLのみで治療しえたものは3例で,他の8例中6例に経皮的腎瘻造設術(以下PCN),2例にPNLがそれぞれ併用となった.3例では明らかな合併症は認めなかったものの,他の8例中7例で38.5℃以上の発熱を見,内2例では,敗血症にまで及んだ.さらに5例では血清クレアチニン値が2.0mg/dl以上に上昇したが,いずれも治療終了後に正常範囲内に回復した.死亡例の経験はなかった.以上のごとく単腎サンゴ状結石においてさえもESWLを中心とした結石破砕治療は可能と思われる.しかしながら,当疾患においては破砕片の尿管への嵌頓が即,急性腎不全,敗血症に直結することが予測されるため,より一層の経過観察が必要と思われる.