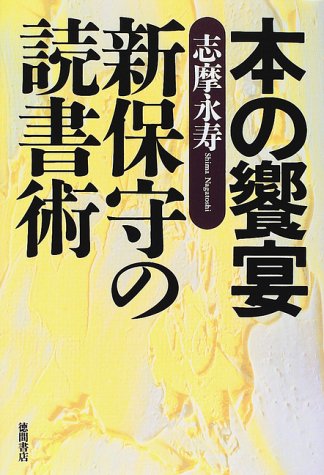- 著者
- 橋本 勝美
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.87-96, 2012
- 被引用文献数
- 1
この20年のWeb基盤技術の進歩により,研究者は研究に必要な文献情報を容易に得ることができるようになった。同時に,研究成果発表のプレッシャーを背負う研究者による科学研究の不正が顕在化している。研究成果を公表する学術ジャーナルでは,重複出版や剽窃・盗用を未然に防ぐ対応が求められ,剽窃検知ツールCrossCheckの利用が広まってきている。日本疫学会はJ-STAGE利用学会として,CrossCheck導入の検討ワークショップに参加した。CrossCheck導入の際に必要となる検討事項やCrossCheck利用の結果と対応案について日本疫学会誌Journal of Epidemiologyの事例を報告する。また,CrossCheckの利用によって明らかになった自己剽窃などの課題についても紹介する。
- 著者
- 橋本 勝美 久保田 壮一 張 朔
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報プロフェッショナルシンポジウム予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.25-30, 2011
論文誌のデジタル化、電子ジャーナル化が浸透するに伴い、他論文からのコピーアンドペーストに代表される論文誌の剽窃等の不正問題が顕在化している。今回テキストパターンマッチングによる不正検出ツールである CrossCheck を J-STAGE で導入検討を行った結果と検出後の学協会の対応案について日本疫学会での事例報告を行い、論文誌の不正防止についての考察を行う。
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1904年01月23日, 1904-01-23
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1904年07月16日, 1904-07-16
1 0 0 0 <卒論>浮世の好色 : 山東京伝『傾城買四十八手』をめぐって
- 著者
- 亀本 美由紀
- 出版者
- 法政大学
- 雑誌
- 日本文學誌要 (ISSN:02877872)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.69-78, 1997-07-12
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1941年07月12日, 1941-07-12
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1940年10月29日, 1940-10-29
1 0 0 0 OA 計測の多様化に伴う諸問題の調査研究
- 著者
- 森田 矢次郎
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.5, pp.570-574, 1982-05-10 (Released:2009-11-26)
1 0 0 0 OA <原著>医療処置をうける小児の痛みの程度と行動に表れる反応
- 著者
- 中村 美保 兼松 百合子 小川 京子
- 出版者
- 千葉大学
- 雑誌
- 千葉大学看護学部紀要 (ISSN:03877272)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.45-52, 1993-03
- 被引用文献数
- 5 3
本研究は,外来受診時に採血をうける3歳から7歳の小児を対象に,採血によって小児が感じる痛みの程度と行動に表れる反応について,発達段階や気質などによる特徴を明らかにすることを目的とした。本研究で見出された結果を以下に示す。1.小児によるFace Pain Scaleの評価と観察された行動スケールの総点とは高い相関が認められた。2.処置中に泣いていた小児は泣かなかった小児より年齢が低く,Face Pain Scaleの評価が高かった。3.年齢が高いほど行動スケールの総点が低かったが,Face Pain Scaleの評価は必ずしも低くなかった。4.行動スケールの総点は気質のカテゴリーである機嫌の点数と関連性があった。
1 0 0 0 OA 原子力発電所の計算機システム
- 著者
- 加藤 眞治 福地 博
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.7, pp.573-581, 1991-07-10 (Released:2009-11-26)
1 0 0 0 Golden years of Calypso
- 出版者
- オーディブック
- 巻号頁・発行日
- 1989
1 0 0 0 近代スポーツの日本的受容に関する研究
本研究は、バレーボール、水泳、テニスなどの近代スポーツの日本的受容について明らかにすることを目的としたものである。本年度は特に、games(遊戯)、スポーツマンシップ、テニス、バレーボールの日本的受容について研究した。その結果、それぞれ次のことが明らかになった。西洋の遊戯(game)の日本的受容は,必ずしも受動的なものではなかった。数多くの西洋の遊戯(game)を積極的に導入し、子供の自然性と快活さを擁護し、児童のレクリエーション習慣(遊戯世界)の形成、遊戯の持つ健康上の効用と道徳的効用という教育的認識を早く摂取した。しかしそれは日本の「国民教育」の形成期におけるナショナリズム、日本の児童、学校教育の実態から西洋的遊戯を膾炙し、「加工」して受容しようとする姿勢の上になされたのであった。テニスは、まず学校の中に取り入れられるが、外国のスポーツをそのまま吸収するのではなく、ゴム製の庭球ボールを開発するとともに、ダブルスを基本とする和式テニス(いわゆる軟式庭球)を普及させた。これは用具の経済的な効率を考えつつ、授業として展開できるように考案されたものであり、教育現場に適した日本的なスポーツの受容といえる。同様にバレーボールも、9人制が推進されたが、これも効率化と、身長や技術的な能力の差異を集団でカバーするという観点からも推進されており、やはり教育的な観点での日本的な受容と言える。以上の事から、日本における近代スポーツの受容については教育的な面、健康増進の面、さらには教育活動としての経済的効率の面から積極的に解釈され、それらの効果を高めるために、近代スポーツを受容、加工していったことが明らかになった。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経エレクトロニクス (ISSN:03851680)
- 巻号頁・発行日
- no.923, pp.98-103, 2006-04-10
「これ,1000ルピー(約2600円)でつい最近手に入れたんですよ。中古でね。2300ルピー(約6000円)で買ったばかりの新機種をなくしてしまって。残念だったけど,さすがに新品をもう1台買う余裕はありませんでした」。ニューデリーの空港からホテルに向かうタクシーの中で,ドライバーのNarinder Singh氏は,手にしたNokia社製の携帯電話機を見せながらこう語った。
1 0 0 0 OA 体育科の評価における潜在的カリキュラムと評価システム開発に向けた実証的研究
1 0 0 0 手書き曲線モデルの一構成法 : ファジースプライン補間法
- 著者
- 佐賀 聡人 牧野 宏美 佐々木 淳一
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌. D-II, 情報・システム, II-情報処理 (ISSN:09151923)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.8, pp.1610-1619, 1994-08-25
- 被引用文献数
- 24 9
本論文では,ペン入力システム上での手書きによる直接的な図形入力ヒューマンインタフェースを実現するための基礎技術として,手書き描画動作をあいまいな曲線としてモデル化する手法「ファジースプライン補間法」を提案している.本手法によって得られるあいまいな曲線のモデル「ファジースプライン曲線」は,曲線の幾何モデルとして有用なスプライン曲線をファジー理論に基づいて拡張することによって定義され,幾何学的な取扱いとファジー集合としての取扱いが同時に可能な手書き曲線の内部表現モデルを与える.従ってこれは,書き手の本来意図した理想的な曲線を必ずしも忠実に表していない手書き曲線をもとにして書き手の意図の幾何学的な意味を推論する問題を考える場合の基礎を与える.本論文の後半ではファジースプライン補間法の一応用として,一筆書きされた手書き曲線を書き手の意図したストロークごとに分割する手法を提案し,本手法の必要性を実験的に示す.
1 0 0 0 スパムメールをめぐる米国及び日本における法的規制
- 著者
- 岡村 久道
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. FACE, 情報文化と倫理 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.1, pp.1-6, 1999-04-08
インターネット上のスパムをめぐり、既に米国では幾つかの判例が出されている。また、スパムを規制するために複数の州では州法が制定されており、合衆国法についても法案Federal billsが審議されている。日本でも、ニフティサーブがスパム送信禁止を求める仮処分を日本で初めて提起し、浦和地方裁判所は、1999年3月9日、ニフティの請求を認める旨の決定を下すに至っている。
1 0 0 0 OA サービス・イノベーションを生み出す地域企業のコア形成に関する研究
観光地に存在する様々なアクターの諸力を総合するために、DMOやDMCと呼ばれる組織が、地域競争力を向上させるための活動を行っている。これらの組織はマーケティングやマネジメントのノウハウを持っているが、地域が提供するサービス品質を管理したりサービス・レベルを向上させようとするような視点は持っていなかった。本研究は、観光地においてサービス・イノベーションの創出を目指すには、製造業的なミクロ視点のイノベーション論だけではなく、地域イノベーション論的なマクロ視点を導入することが必要とし、実証研究を重ねることによって「地域サービス・プロフィットチェーン」の枠組みの有効性を提唱している点に意義がある。
1 0 0 0 OA (書評)熊谷開作著「「法史学と法社会学」(季刊法律学二六号)」
- 著者
- 青山 道夫
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1960, no.10, pp.262-262, 1960-03-30 (Released:2009-11-16)