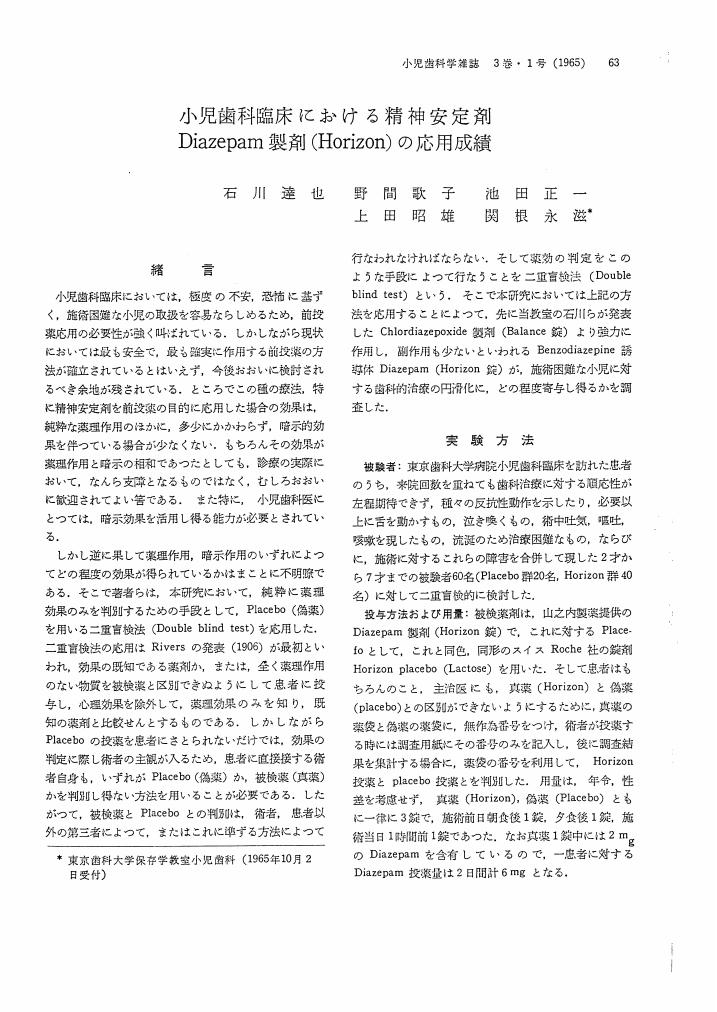1 0 0 0 OA 音の高さ, 音色, 音声の知覚と短期記憶に関する研究
1 0 0 0 OA 女子青年における痩身願望についての研究
- 著者
- 馬場 安希 菅原 健介
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.267-274, 2000-09-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 13 8
本論文では現代女性の痩身化の実態に注目し, 痩身願望を「自己の体重を減少させたり, 体型をスリム化しようとする欲求であり, 絶食, 薬物, エステなど様々なダイエット行動を動機づける心理的要因」と定義した。痩身は「幸福獲得の手段」として位置づけられているとする立場から, 痩身願望の強さを測定する尺度を構成するとともに, 痩身願望が体型への損得意識を媒介に規定されるモデルを検討した。青年期女子に質問紙による調査を行い, 痩身願望尺度の一次元構造を確かめ, ダイエット行動や摂食行動との関連について検討し, 尺度の信頼性, 妥当性が確認された。また, 体型への損得意識に影響を及ぼすと考えられる個人特性と, 痩身願望との関連性を検討した結果, 「賞賛獲得欲求」「女性役割受容」「自尊感情」「ストレス感」などに関連があることが示された。そこで, これらの関連を検討したところ, 痩せれば今より良いことがあるという「痩身のメリット感」が痩身願望に直接影響し, それ以外の変数はこのメリット感を媒介して痩身願望に影響することが明らかになり, 痩身願望は3つのルートによって高められると考えられた。第1は, 肥満から痩身願望に直接至るルートである。第2は, 自己顕示欲求から生じる痩身願望で, 賞賛獲得欲求と女性役割受容が痩身によるメリット感を経由して痩身願望と関連しており, 痩身が顕示性を満足させるための手段となっていることが示唆された。第3は, 自己不全感から発するルートである。自尊感情の低さと空虚感があいまったとき, そうした不全感の原因を体型に帰属し, 今の体型のせいで幸せになれないといった「現体型のデメリット感」を生じ, さらにメリット感を経由して痩身願望に至ることが示された。これらの結果から, 痩身願望が「女性的魅力のアピール」や「自己不全感からの脱却」を日的として高まるのではないかと考えられた。
- 著者
- 武中 泰樹 櫛橋 民生
- 出版者
- エム・イー振興協会 ; 1975-
- 雑誌
- 月刊新医療 (ISSN:09107991)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.8, pp.57-60, 2006-08
- 著者
- 森脇 睦子
- 出版者
- 独立行政法人国立病院機構本部(総合研究センター)
- 雑誌
- 若手研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2014-04-01
26年度は以下を実施した。1)夜間・休日時間外に受診した患者における必要性の低い救急患者の同定手法の開発を実施する目的で次の分析を行った。分析対象は、国立病院機構143病院のうち一般病床を有する110病院で、当該病院の夜間・休日時間外受診した患者(初診料・再診料の時間外・休日・深夜加算を算定した患者)とした。分析には、国立病院機構総合研究センターにおける診療情報データバンクに収集されている平成25年度のレセプトデータを使用した。分析内容は、初診および再診患者の判定(定義の検討)を行った。続いて診療区分(注射、処置、手術、麻酔、病理、画像診断、その他)別に軽症患者の判定に関するアルゴリズムを作成し、患者数や診療報酬点数ベースでの記述統計を行った。2)カルテレビューによる必要性の低い救急患者の判定を実施する目的で次の調査を実施した。1)の分析対象(休日・時間外受診した患者)から対象施設2施設を選定し、各施設150件、合計300件を年齢階級別に無作為層化抽出しカルテレビューの対象とした。調査項目は、①主訴、②主訴発生時刻、③診察時刻、④軽症もしくは軽症外の判定、⑤判定の根拠、⑥早期受診の必要性の有無等とした。調査方法は、医師および薬剤師2名によりカルテレビューを実施し、軽症判定を行った。レビュー後、判定結果に相違がある場合は再度検討により一致させた。検討により判定が一致しない場合は、医師の判定結果を採用した。今後は、カルテレビューの結果を基にレセプトデータによる軽症患者の判定モデル作成する分析を実施する。
1 0 0 0 OA 日本社会論のパラダイム再考
- 著者
- 小林 修一
- 出版者
- 東洋大学社会学部
- 雑誌
- 東洋大学社会学部紀要 = The Bulletin of Faculty of Sociology,Toyo University (ISSN:04959892)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.25-46, 2004-11
1 0 0 0 OA 小児歯科臨床における精神安定剤 Diazepam 製剤(Horizon) の応用成績
- 著者
- 石川 達也 野間 歌子 池田 正一 上田 昭雄 関根 永滋
- 出版者
- 一般財団法人 日本小児歯科学会
- 雑誌
- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.63-70, 1965-12-01 (Released:2013-01-18)
- 参考文献数
- 20
- 著者
- 山中 茂子 輿水 はる海 小林 倫子
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, 1966
1 0 0 0 OA 関西国際空港の建設について
- 著者
- 前田 進 古土井 光昭 森 好生
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 海洋開発シンポジュウム論文集 (ISSN:0912733X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.1-6, 1985 (Released:2010-03-17)
1 0 0 0 OA 非相同末端結合におけるNBS1の分子機能と染色体不安定化のメカニズム
1 0 0 0 符号化問題として解く日本語係り受け解析
- 著者
- 田村 晃裕 高村 大也 奥村 学
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告自然言語処理(NL) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.124, pp.17-24, 2006-11-22
- 被引用文献数
- 1
係り受け解析を符号化・復号化問題として解く手法を提案する.従来は,2文節間の係りやすさ,つまり係り受け木でいう親子関係になるかを基に係り受けを解析している.この従来の考えに従うと,親子関係の情報を表した符号を用いた符号化・復号化問題を解くことになる.係り受け解析を符号化・復号化問題と捉えると,符号化・復号化問題における,誤りがある程度生じても訂正できるように,符号に冗長な情報を加え,使用する符号間の距離を大きくする手法を係り受け解析に援用できる.そこで,本研究では,親子関係の情報の他に,祖先子孫関係になるかという情報を冗長な情報として符号に加えることで精度の向上をはかった.実際に本手法で係り受け解析をし,高い精度が得られたことを報告する.We propose a novel method for Japanese dependency analysis. In deterministic approaches to this task, dependency trees are constructed by actions of attaching a bunsetsu chunk to one of the nodes in the trees. Therefore the task is reduced to deciding the node for the new bunsetsu chunk to be attached.We propose to encode each decision with a sequence of binary values, that is, a code. This representation of decisions enables the model to incorporate ancestor-descendant relations between nodes in addition to parent-child relations. We also propose to concatenate the code of parent-child relation and the code of ancestor-descendant relation, so that the added redundancy in codes helps errors be corrected. Experimental results show that the proposed method achieves higher accuracy in the task of Japanese dependency analysis.
1 0 0 0 機能表現を考慮した統計的日本語係り受け解析
- 著者
- 注連隆夫 士屋雅稔 松吉俊 字津呂武仁 佐藤理史
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告自然言語処理(NL) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.7, pp.63-70, 2007-01-26
本稿では,SupportVectorMadline(SVM)を用いたチャンカーYamOhaを利用して,日本語機能表現検出器を学習し,その性能評価を行った機能表現を構成している形態素の数の情報,機能表現中における形態素の位置情報を素性として参照することにより,F値で約94という高精度の検出器を実現できることを示した.また,京都テキストコーパスに対して,機能表現の情報を人手で付与した後,SVMに基づく統計的係り受け解析器OaboOhaの学習を行い,その性能を評価した.機能表現を考慮して係り受け関係の学習をすることによって,機能表現を含む文節の係り受け解析の性能が改善することを示す.This paper proposes to learn a detector of Japanese functional expressions using the chunker YamCha based on Support Vector Machines (SVMs), and presents the result of evaluating the performance of the detector. Through experimental evaluation, we achieve the F-measure as 94. We then manually annotate parsed sentences of Kyoto Text Corpus with functional expressions, which are used for training dependency an alyzer CaboCha based on SVM. The dependency analyzer CaboCha of this paper is modified so that it can cope with annotation of functional expressions in the training corpus. We experimentally show that the modified version of the dependency analyzer improves the performance of the dependency analysis of functional expressions.
1 0 0 0 ギブスサンプリングを用いた係り受け解析
- 著者
- 中川 哲治
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告音声言語情報処理(SLP)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.47, pp.19-24, 2007-05-24
- 被引用文献数
- 1
本稿では,ギブスサンプリングを用いた係り受け解析手法を提案する.既存の解析手法ではしばしば変数間に独立性を仮定しており,利用可能な素性が限られているという問題があった.提案手法では,依存構造木全体をモデル化する確率分布を考えることで,依存構造木中の兄弟ノードに関する関係や,子ノードと祖父母ノードに関する関係などの,文中の任意の素性を利用することができる.複数のコーパスで実験を行った結果,提案手法は既存手法と比較して同程度以上の解析精度を持つことを確認した.In this paper, we present a method for dependency parsing with Gibbs sampling.Existing methods for dependency parsing often assume independence among variables, and have limitations in available features.Our method uses a probabilistic model of a whole dependency tree, and allows us to use arbitrary features in a dependency tree, which include relations between sibling nodes and relations between a child and its grandparent nodes.Experimental results on multiple corpora showed that the performance of our method was competitive with other state-of-the-art methods.
1 0 0 0 OA ポストコロニアル的観点から考察した日英文学図像にみるオリエント表象の分化と変容
- 著者
- 千森 幹子 DAME Gillan beer CLIVE Scott
- 出版者
- 山梨県立大学
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2009
本研究は、ポストコロニアル的観点から、19世紀から20世紀イギリスで出版された文学挿絵における、日本、中国、中東にいたるオリエント表象の分化と変遷を、政治(帝国主義と植民地主義政策)社会(オリエント諸国への西洋観)および、文化(ジャポニズムに代表される美術様式や万博などにみられる西洋の東洋文化理解)を通じて検証する学際研究である。
1 0 0 0 OA 翻訳名義集 : 支那撰述
1 0 0 0 OA 地方都市の復興事業におけるジャズ音楽の活用-日米地域文化の比較研究
本研究で実施した日米両国の中小都市での現地調査から明らかとなった課題は、以下のように分類できる。(1)日米間におけるジャズ音楽の文化的位置づけの差異、(2)米国内の地域間によるジャズ音楽の文化的重要性の差異、(3)日本のジャズ文化における主要都市(東京・横浜、京都・大阪・神戸)と地方都市との間にみられるジャズの文化的位置づけ及び意義の差異、(4)日本国内の地方都市間(地域間)にみられるジャズ音楽の文化的存在の差異、(5)地方都市の復興事業における音楽の一時的な活用(恒例のイベント等)vs.音楽を提供する個人経営のライブスポットや飲食店など永続的・営利的な空間が生み出す効果の差異。
1 0 0 0 OA 月経痛,月経周期異常に対する気剤による治療の試み : 5症例の経験から
- 著者
- 木村 容子 佐藤 弘
- 出版者
- 社団法人日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋醫學雜誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.453-458, 2006-07-20
- 被引用文献数
- 2 1
月経痛,月経周期異常に対し,気剤単独で,奏功した5例を報告した。症例1では,激しい心窩部痛及び月経痛が半夏厚朴湯で改善,症例2では,柴朴湯で月経不順及び月経痛が軽快,症例3では,半夏厚朴湯で月経痛が軽減した。〓血の所見を認めたが,気欝の症状に基づいて処方を選択した。症例4では,加味逍遥散から桂枝加竜骨牡蛎湯に変方して月経痛及び月経不順が改善,症例5では,主訴の蕁麻疹を桂枝加竜骨牡蛎湯加味方で治療中,月経周期が40日以上から30日に改善した。後者2例では,明らかな〓血症候を認めなかった。腹部動悸亢進や怖い夢,いやな夢がみられたため,桂枝加竜骨牡蛎湯を選択した。月経異常は,漢方医学的には,特に「血」に関連する病態が多いとされる。しかし,5症例の経験から,ストレス状況で発症した月経障害に対し,〓血の症候を認めても,気鬱や気逆など「気」の関与を考慮し,気剤が有効な症例もあることが示唆された。
1 0 0 0 OA 光遺伝学的手法を用いたマクロパイノサイトーシスの時空間的解析
光活性化Rac1(PA-Rac1)により顕微鏡下でマクロパイノサイトーシスを誘導する実験系を利用しマクロパイノサイトーシスの形態的特徴および分子基盤の解析を行った。その結果、PA-Rac1誘導性マクロパイノサイトーシスは、典型的なマクロパイノサイトーシスと異なりRab10が一過的に集積することを見出した。さらにRab10陽性のマクロパイノゾームは、チューブ構造を出芽した。Rab10陽性マクロパイノゾームおよびチューブ構造は、細胞外と行き来のある開いた構造であった。以上の結果から、PA-Rac1依存的マクロパイノサイトーシスは、従来型と異なる新規の取り込み経路であることが示唆された。
1 0 0 0 近代中国の伝染病対策-伝統医学と西洋医学の相互作用に着目して
- 著者
- [ジョ] 貞恩 (2012) 曹 貞恩 (2011)
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 特別研究員奨励費
- 巻号頁・発行日
- 2011
本年度には医療宣教師のアイデンティティ、中医学に対する認識について考察した。1)2011年9月に明清史学会において口頭発表した内容を修正・補完し、2012年韓国の学術雑誌『明清史研究』37集に掲載した。2)2012年9-10月に上海での史料調査を行った。上海档案館では、中国医療伝道協会の内部資料や档案史料を集めた。上海図書館では、電子資料として公開されている医療宣教師関係の雑誌や民国時代の医学雑誌を収集することができた。3}医療宣教師のアイデンティティー医療と伝道の間:本章では医療と伝道のどちらを優先するかという問題をめぐる医療宣教師の論争を紹介し、1900年代以降医療と伝道が分離分離され、医療宣教師は主に医師としての役割を果たすようになったことを明らかにした。医療と伝道の分離は、中国医療伝道協会の役割、ひいては中国での医療活動にも大きな変化をもたらしたのである。史料としては、医療宣教師が残した文章及び全中国プロテスタント宣教師大会の報告書を主に利用した。4)医療宣教師の中薬に対する認識:最初医療宣教師が中薬を研究した理由は、中国伝統医学を深く理解するためというより、薬の不足といった医療活動の現実的な問題を解決するためであった。ところが1920年代に入ってから、中国人による中薬研究が活発になり、中薬の新たな可能性を発見すると、医療宣教師の中薬に対する認識も大きく変化する。本章では、医療宣教師の中薬に対する認識の変化、それに影響を与えた中国人の中薬の研究活動を分析することで、西洋医学と中国伝統医学の相互作用の一面を明らかにしたい。
1 0 0 0 OA 注射器の内筒操作技術に関する研究
- 著者
- 國澤 尚子 新村 洋未 小川 鑛一
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム (ISSN:13487116)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.195-205, 2004 (Released:2005-04-15)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
The objectives of the current research were to clarify differences in beginners' and nurses' techniques for manipulation of a syringe and to propose methods of education for mastering quick and accurate techniques. In this paper, differences in techniques for manipulation of a syringe by nursing students and nurses are discussed from two perspectives. One is the effects of combining the syringe and injection needle in terms of the pressure in the syringe. The other is differences in methods of grasping the syringe. Based on these results, problems relating to adjustment of the force used by a nurse to manipulate a syringe and contact of the fingertip with the plunger become apparent.For measurement of the pressure in the syringe, a processed syringe is connected to a strain gauge type of force conversion device and strain is converted to pressure. For pressing of the plunger, hypodermic injection and extrusion of a drug solution into a vial were performed. For drawing of the plunger, collection of blood and suctioning from a plastic ampule were performed.With regard to pressure in the syringe, the maximum gauge pressure was large for a finer injection needle when the syringe was the same size in all techniques for nursing students as well as nurses. In simulated hypodermic injection, nursing students had a larger maximum gauge pressure with a larger syringe with the same injection needle. However, nurses considered the effects on the body and adjusted force so that the maximum gauge pressure did not increase. Because extrusion from a syringe and suctioning from an ampule are techniques that do not insert a needle in the body, nurses added substantial force and manipulated the syringe in a short period of time. In addition, limits for the addition of force were also considered.Based on classification of patterns of waveforms with regard to drawing of the plunger in suctioning from an ampule, nursing students often had multiple valley-shaped waveforms. Patterns produce waveforms like this because the syringe is passed from hand to hand. Differences in the appearance of waveforms due to the size of the syringe were noted for nurses, indicating separate use of methods of manipulating a syringe plunger as needed.With regard to the grasping of a syringe, nursing students grasp it so as not place their fingertip in contact with the plunger. This is because they are taught in class not to make contact with the plunger based on the perspective of preventing infection. However, a majority of nurses make contact with the plunger when drawing the plunger. That is, making contact with the plunger for drawing of the plunger is a technique in which the plunger is easy to manipulate. Nurses may have adopted an efficient method in clinical settings. Even if the stance that contact with the plunger should be avoided to prevent infection is learned, making contact with the plunger as experience is acquired leads one to conclude that education in techniques for manipulation of injections is vague. Having nurses change the techniques they have acquired is difficult, so sterile gloves should be worn as a general rule when manipulating a syringe.In the future, force added to the suction head of a syringe plunger will be measured and the relationship with internal pressure will be verified.