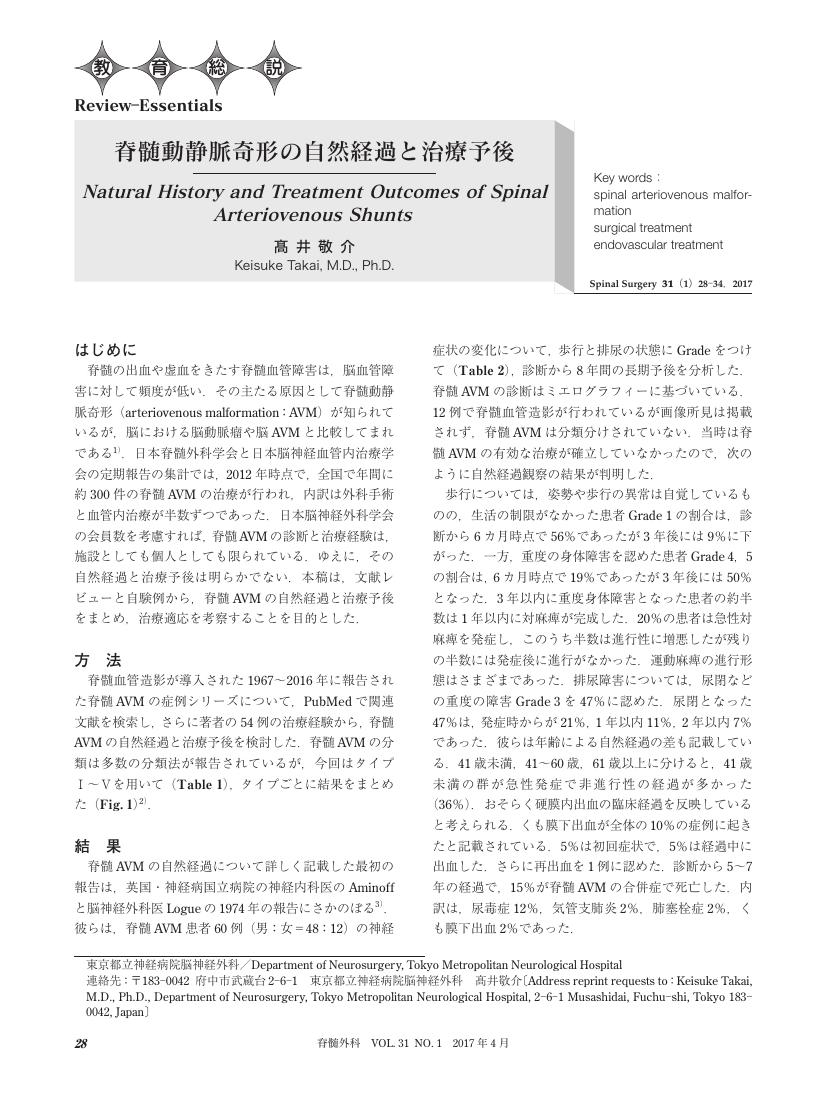2 0 0 0 OA 最近巡洋艦の發達
- 著者
- A.K.
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 造船協会雑纂 (ISSN:24331023)
- 巻号頁・発行日
- vol.144, pp.146-148, 1934 (Released:2018-02-25)
2 0 0 0 OA デカルト哲学における「客象的レアリタス」について
- 著者
- 村上 勝三
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, no.28, pp.116-126, 1978-05-01 (Released:2009-07-23)
2 0 0 0 OA 気管支喘息の病因
- 著者
- 光井 庄太郎 鹿内 喜佐男
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.198-212,241, 1969-03-30 (Released:2017-02-10)
According to the histories of the patients with bronchial asthma the factors involved in the occurrence of asthmatic attack were investigated and the following results were obtained. 1. Analysis of the season and occurrence of asthematic attack studied on 237 cases revealed that 55 had the attack in autumn, 52 regardless of the season, 31 in winter and 25 in both spring and autumn. 2. Of 685 asthmatics, the causes of the first asthmatic attack were presumed in 464 cases. They were common cold occurred in 245 cases, revealing the highest incidence, inhalation of sea-squirt substances in 80, pneumonia in 22, acute bronchitis in 17, fatigue in 14, cold and pregnancy in 11 each. Of 673 asthmatics, the causes or the inducing factors of asthmatic attack after the onset of bronchial asthma were presumed in 567 cases. They were related to: 1) physical conditions in 352 (common cold and influenza in 229, fatigue in 126, overeating in 34, psychic tension in 24, bathing in 19, etc.);. 2) weather in 222 (cold in 84, rainy day in 63, cloudy day in 33, sudden change in weather in 29, humid day in 21, etc.); 3) dust in 173 (sea-squirt substances in 83, house dust in 78, cotton wool in 9, etc.); 4) smoke and offensive odor in 91 (cigarette smoke in 38, smoke of mosquito stick and smoke of broiling fish in 9 each.) 5) food and drink in 79 (wine in 30, vegetable foods in 26, animal foods in 20, fatty foods in 9, etc.) ; 6) drugs in 9 (ACTH in 3, aspirin in 2, etc.) ; 7) animals in 6 (contact with domestic. animals in 4, furs and feathers in 2) ; 8) plants in 5 (newly-bult house in 3, pollen in 2); 9) molds in 5 (aspergillus in 2, other molds in 3). 3. The causes or the inducing factors of asthmatic attack above mentioned were studied as follows: l) those relating to the psychic and physical conditions were investigated from the view-point of the autonomic nervous function and the endocrine glands; 2) those relating to the infection of the upper respiratory tract were investigated from the view-point of bacterial allergy; 3) those relating to the inhalants and ingestants were investigated by the skin test with these substances; and the significant results were obtained from each of them. 4. The incidence rate of positive reaction in the intradermal test was 51.2% with house dust antigen, 41.8% with Paspat, 21.6% with ragweed pollen antigen, 15.5% with the mixed antigen of crab, lobster and oyster, 15.5% with sea-squirt antigen (except sea-squirt asthma patients), 11.8% with mixed antigen of cat hair and dog hair, 11.2% with yam antigen.
2 0 0 0 OA 脊髄動静脈奇形の自然経過と治療予後
- 著者
- 髙井 敬介
- 出版者
- 日本脊髄外科学会
- 雑誌
- 脊髄外科 (ISSN:09146024)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.28-34, 2017 (Released:2017-07-08)
- 参考文献数
- 21
2 0 0 0 OA 原子力市民委員会の目指すもの
- 著者
- 吉岡 斉
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.188-189, 2014 (Released:2019-10-31)
- 著者
- 土屋 靖明
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.88, pp.51-66, 2003-11-10 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 46
Le but de cet article est de dégager un principe de la théorie du devenir humain dans la philosophie bergsonienne, et par ailleurs, de souligner le discours sur le pragmatisme (particulièrement celui sur William James) chez Bergson. Les conceptions de la vie, du devenir, du changement de la réalité spirituelle, de l'effort spirituel, de la pluralité et de l'inventivité qui sont examinées dans cet essai sont des idées importantes pour la philosophie bergsonienne elle-même. Et Bergson montre son intérêt pour ces thèmes dans son discours sur le pragmatisme.Dans le bergsonisme et dans l'interprétation bergsonienne du pragmatisme, l'humain est la réalité spirituelle, soit en d'autres mots, l'âme et l'esprit. La réalité spirituelle vit; elle est en devenir continuel et se transforme et évolue par un effort d'esprit intime. Une telle théorie du devenir refuse le but comme point final. La finalité dans la théorie du devenir est le devenir indéfiniment soi-même, ou encore la pluralité qui signifie des évolutions divergentes. La pluralité du devenir se manifeste dans la faculté inventive. Le pragmatisme (dans l'interprétation de Bergson) vise des inventions scientifiques reflétées dans des utilisations pratiques. Le bergsonisme est tourné vers les créations artistiques reposant sur leur propre inspiration. L'utilisation pratique et l'inspiration artistique sont le produit d'un effort spirituel.
2 0 0 0 OA 経絡説に対する批判
- 著者
- 近藤 久美
- 出版者
- 公益社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 日本鍼灸治療学会誌 (ISSN:05461367)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.17-19, 1961-03-01 (Released:2011-05-30)
2 0 0 0 OA 日本人成人男女の平均体型を有する全身数値モデルの開発
- 著者
- 長岡 智明 櫻井 清子 国枝 悦夫 渡辺 聡一 本間 寛之 鈴木 保 河川 光正 酒本 勝之 小川 幸次 此川 公紀 久保田 勝巳 金 鳳洙 多氣 昌生 山中 幸雄 渡辺 敏
- 出版者
- 一般社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 医用電子と生体工学 (ISSN:00213292)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.4, pp.239-246, 2002 (Released:2011-10-14)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 11
We have developed high-resolution voxel models of the whole body from MR images of Japanese adult male and female volunteers. These models can be used for dosimetry simulation of exposure to radiofrequency electromagnetic fields over 1GHz. The MR images were taken by making a series of scans over several days; that is, a subject was scanned in several blocks. Scan parameters were optimized for head and body, respectively, in order to get practical contrast and to save data acquisition time. An implement was used to keep the position and form of the subject. All of the MR images were converted to TIFF format. The continuities between different blocks of the data were corrected to form a whole body. Furthermore, the resolution of the images was changed into 2×2mm. Male and female models were segmented into 51 tissues and organs. This segmentation was performed manually using popular image-processing software. The developed models consisted of isotropic voxels with a side of 2mm. Although the masses of the skin and small-sized tissues and organs of the models deviated from the averaged values for Japanese due to the limitation of spatial resolution, the masses of the other tissues and organs and the morphometric measures were nearly equivalent to those of the average Japanese. The models are the first voxel models of the average Japanese that can be used for the dosimetry of electromagnetic fields over 1GHz. Furthermore, the female model is the first of its kind in the world. The models can also be used for various numerical simulations related to Japanese human bodies in other fields of research.
2 0 0 0 OA 1.診断基準(RIFLE,AKIN,KDIGO分類の概要)
- 著者
- 藤垣 嘉秀
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, no.5, pp.1061-1067, 2014-05-10 (Released:2015-05-10)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2 1
AKIの概念が導入され,この10年間に国際的にRIFLE,AKIN,KDIGO診断基準・分類が提唱された.これらは,臨床的に使用可能な検査法でAKIを定義し,予後予測のための重症度分類を提案している.各基準・分類に基づきAKIの頻度が報告され,予後予測に関する妥当性が検証され比較検討されている.今後,運用上の問題解決をはかるとともに,早期診断と疫学研究に基づくAKIの予後改善に向けた取り組みが期待される.
2 0 0 0 OA ゴキブリ 4 種の生存と発育に対する冷温の影響
- 著者
- 辻 英明 水野 隆夫
- 出版者
- The Japan Society of Medical Entomology and Zoology
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.185-194, 1973 (Released:2016-09-05)
- 被引用文献数
- 7 8
本邦中部で越冬する能力を調べるために, 27℃または20℃で飼育したチャバネ, ワモン, クロ, ヤマトの4種のゴキブリを, 冬の平均気温に類似させた5.5℃条件下で長期間冷蔵する実験を行なった。またあらかじめ15℃に保ちその後5.5℃に移すことも試みた。チャバネゴキブリとワモンゴキブリの卵鞘は20日間の冷蔵で死亡し, 40日の15℃予備飼育さえも有害であった。幼虫や成虫では15℃予備飼育は冷蔵に対する耐性を高めた。しかし最も耐性のある終令幼虫と成虫に予備飼育期間28日を与えても30日間の冷蔵で死亡し, 予備飼育100日間でも40日間の冷蔵に耐えられなかった。また20℃で増殖を阻止されているチャバネゴキブリ成虫および発育の遅延しているワモンゴキブリの終令幼虫は, 共に40日間の冷蔵によって死亡した。したがって, これらの種が本邦中部の戸外や無加温の建物の中で3カ月にわたる冬を越えることはきわめて困難と思われる。クロゴキブリでは, 一定期間の予備飼育がすべてのステージの冷蔵に対する耐性を高めた。すなわち, 予備飼育28日間でかなりの老令幼虫が90日間の冷蔵に耐え, 約半数の卵鞘が予備飼育40日間で冷蔵80日間に耐えた。しかし成虫と若令幼虫は60日以下しか耐えられなかった。同様にヤマトゴキブリでは, 予備飼育28日間ですべての令期のほとんどすべての幼虫が120日間の冷蔵に耐え, 成虫でも90日の冷蔵に耐えた。卵鞘は予備飼育40日間のあとでも冷蔵40日で死亡した。この種では老令幼虫と成虫は予備飼育なしでも90日間の冷蔵に耐えた。ゴキブリのひそむ場所の冬の最高最低温度は平均温度とそれほどかけはなれたものとは考えられないので, これらの結果はクロゴキブリとヤマトゴキブリが本邦中部の戸外および無加温の建物の中で越冬できることを示しているといえよう。ヤマトゴキブリの2令と終令にみられる特異的な発育遅延は冷蔵によって消去され, 休眠の特性を示した。クロゴキブリの2令でも20℃で休眠様の発育遅延があるが, その幼虫を直接冷蔵した場合60日間で全部死亡した。しかし予備飼育を経過させた場合については未調査である。
2 0 0 0 OA 核爆発実験により生じた放射性降下物の定量, (I)
- 著者
- 上野 馨
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌 (ISSN:00047120)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.67-72, 1960-02-29 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 10
The gamma-ray spectrum emitted by present-day pine leaves reveals the presence of several peaks which do not belong to any naturally occurring nuclide. These peaks come from radioactive fission produts produced from nuclear weapon tests.The gamma-ray spectra of pine leaves collected in 1958 and 1959 show two remarkable peaks. 0.13 MeV peak is actually a combination of peaks of 131Ce and 144Ce-144Pr, while 0.76 MeV peak is assigned as a peak of 95Zr-95Nb.The decay curves of the gamma activity at 0.76 MeV correspond to curves of 95Zr-95Nb with half-life of 65 days. One gram pine leaves ash contains 26 mμc 95Zr-95Nb.
2 0 0 0 OA 「党外雑誌」読者から見た台湾の民主化
- 著者
- 家永 真幸
- 出版者
- 国立大学法人 東京医科歯科大学教養部
- 雑誌
- 東京医科歯科大学教養部研究紀要 (ISSN:03863492)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.71-76, 2017 (Released:2018-11-18)
- 著者
- 三重野 文晴
- 出版者
- 京都大学東南アジア地域研究研究所
- 雑誌
- 東南アジア研究 (ISSN:05638682)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.224-228, 2021-07-31 (Released:2021-07-30)
- 参考文献数
- 3
2 0 0 0 OA 12 不正融資における借手の刑事責任(背任罪・特別背任罪)
- 著者
- 関 哲夫
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.3, pp.548-551, 2006-04-30 (Released:2020-11-05)
- 著者
- 岡本 正明
- 出版者
- 京都大学東南アジア地域研究研究所
- 雑誌
- 東南アジア研究 (ISSN:05638682)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.228-231, 2021-07-31 (Released:2021-07-30)
- 参考文献数
- 6
2 0 0 0 OA 植物の重力屈性機構解明に向けた構造生物研究
- 著者
- 平野 良憲
- 出版者
- 日本結晶学会
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.77-78, 2021-05-31 (Released:2021-06-05)
- 参考文献数
- 9
2 0 0 0 OA 持続性と利活用性を考慮したデジタルアーカイブ構築手法の提案
- 著者
- 中村 覚 高嶋 朋子
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.56-60, 2021-01-12 (Released:2021-02-24)
- 参考文献数
- 11
日本社会においても、文化的資産としてのデジタルコンテンツを整備し共有することの意義が着実に認知されつつあるなかで、デジタルな研究資源を生かしたデータベース等の継続が立ち行かなくなるケースが散見される。そこで本研究では、デジタルアーカイブをいかに存続させるかという課題に対して、持続性と更には利活用性までを考慮したデジタルアーカイブ構築について、技術面に特化した手法を提案する。また実際にデジタルアーカイブを構築および活用を行うことで、提案手法の有用性を検証する。
- 著者
- 市川 寛也
- 出版者
- 美術科教育学会
- 雑誌
- 美術教育学:美術科教育学会誌 (ISSN:0917771X)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.43-56, 2015-03-20 (Released:2017-06-12)
本稿は,アートプロジェクトによる学びの有効性について考察することを目的としたものである。アートプロジェクトの現場では,鑑賞者が制作のプロセスに参加することによって,一人ひとりが創造的な主体性を獲得していく事例を見ることも少なくない。ここでは,完成された作品を視覚的に鑑賞することとは異なる新たな美的体験が生み出されている。本論では,参加型芸術の理論的な背景を明らかにするとともに,アートプロジェクト《放課後の学校クラブ》の運営を通して実践研究を行った。現代美術家の北澤潤によって構想されたこのプロジェクトでは,子どもが主人公になる「もうひとつの学校」がつくられていく。その結果として出現する場は,アートによる開かれた学びの可能性を提示する。
2 0 0 0 OA 1分子観察から見えてきた大腸菌ヘリカーゼUvrDのDNA巻き戻し機能と多量体形成
- 著者
- 横田 浩章
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.227-231, 2021 (Released:2021-07-30)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
The Escherichia coli UvrD protein is a superfamily 1, non-hexameric DNA helicase that plays a crucial role in repair mechanisms. Previous studies suggested that wild-type UvrD has optimal activity in its oligomeric form. Nevertheless, a conflicting monomer model was proposed using a UvrD mutant lacking the C-terminal 40 amino acids (UvrDΔ40C). Here, single-molecule direct visualization of UvrDΔ40C revealed that two or three UvrDΔ40C molecules were simultaneously involved in DNA unwinding, presumably in an oligomeric form, similar to that with wild-type UvrD. Thus, single-molecule direct visualization of nucleic acid-binding proteins provides quantitative and kinetic information to address their fundamental mechanisms.
2 0 0 0 DXの成功要素とDX人材の育成について
- 著者
- 岸 和良
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.7, pp.290-295, 2021-07-01 (Released:2021-07-01)
DX(Digital Transformation)は客との良好な関係の維持,企業や団体の業績向上,将来に向けた継続成長に必要である。しかし,日本ではDX導入に成功している事例はまだ少ない。今後成功事例を増やすためには,DXの成功要素を見つけることが重要である。DXが成功するか失敗するかは,DXの本質を理解しているかに依存する。DXの手段と目的を混同しないようにすることが重要である。DX成功要素は,客や社員に価値を提供する経営面での課題解決を実施すること,企業や団体の上層部が深く関与すること,適切な組織を設定すること,DX人材の能力定義を行うこと,適切な人材育成を行うことが必要である。