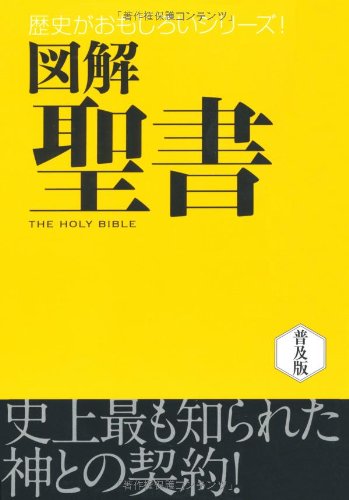1 0 0 0 IR 環境と経済(7)原子力法制と心の平和
- 著者
- 六車 明
- 出版者
- 慶應義塾大学大学院法務研究科
- 雑誌
- 慶應法学 (ISSN:18800750)
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.123-144, 2011-08
論説はじめにI 平和目的の33年─1945年(昭和20年)8月15日から1978年(昭和53年)9月30日 1 原子力法制の側面 2 環境法制の側面II 安全確保の33年─1978年(昭和53年)10月1日から2011年(平成23年)3 月11日 1 原子力法制の側面 2 環境法制の側面III 心の平和を─2011年(平成23年)3月11日からおわりに
1 0 0 0 IR 東日本大震災における総合情報基盤センターの支援状況と今後に向けたBCP対策
- 著者
- 黒田 卓
- 出版者
- 富山大学総合情報基盤センター
- 雑誌
- 富山大学総合情報基盤センター広報 (ISSN:13490796)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.24-25, 2012-03
平成23年(2011年)3月11日,東日本を中心とした日本の観測史上最大規模の震度7の地震とそれによって引き起こされた津波によって,東日本の太平洋沿岸地域は壊滅的な被害に見舞われた。これにより発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響を受け,被災地だけでなく,全国的に電力不足が発生し,関東エリアでは計画停電が実施される事態となった。本学は幸いなことに被災は免れたが,総合情報基盤センターの立地条件も呉羽山活断層帯や神通川流域の氾濫予測地域に位置し,今後のBCP(事業継続計画)対策の重要性を再確認させられる事態となった。本稿では,大震災時に総合情報基盤センターが実施した支援と,今後のBCP対策についての検討状況について述べる。
1 0 0 0 IR 東日本大震災の地域金融に及ぼす影響
- 著者
- 堀江 康煕 川向 肇
- 出版者
- 九州大学経済学会
- 雑誌
- 経済学研究 (ISSN:0022975X)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.2, pp.1-38, 2011-09
平成23年3月11日に発生した東日本大震災(気象庁は東北地方太平洋沖地震と命名) は、地震の直接的な被害に留まらず、津波による冠水や原子力発電所の事故が大きく深刻な影響を及ぼした。この地震は、日本経済が緩やかながらも回復途上に乗りつつあるなかで発生しており、今後需要・供給の両面から経済活動の下押し要因として作用していくとみられる。内閣府の資料(内閣府[2011]) 等によれば資本ストックでみた被災地域の推定毀損額は、ストック全体との対比では関東大震災時の約四分の一であるが、阪神・淡路大震災と比較するとその2倍前後に達すると推察される。こうした震災による資本ストック毀損の影響は、直接的な被害を強く被った農業・漁業のほか、製造業等にも波及している。生産活動への影響は、部品供給能力の低下等を通じて東北を中心とする東日本のみに留まらず、日本経済全体にマイナスの影響を及ぼしていくのである。それでは、対象をやや限定して被害の大きかった東北・関東地方の太平洋側地域について、地震の直接的な影響はどの程度生じたのであろうか。この場合、地震による建物の倒壊等に伴う被害も大きく、その早急な復旧は重要な課題である。しかし、影響のインパクトが大きく対応が極めて難しいのは、津波による毀損および原発事故の影響である。これらは、短期間では現状復旧が出来ないだけに、地域経済自体の崩壊を惹き起こす惧れも大きい。また金融面については、これまでのところ地震により誘発された津波および津波に伴う原子力発電所の事故の被害に関する分析は行われていない。地域金融機関が直接的な被害をどの程度受け、また地震による企業活動の落ち込み等に伴う営業地盤の劣化度合いはどのように生じているのか、そうしたなかで存続が可能であるのか等といった問題についても、早急に考えていく必要がある。本稿の分析の特徴は、①地理情報処理の手法を用いた津波の被害地域の特定、②金融機関毎の被害状況に関する狭義・広義両面からの算定、③それらを用いた金融機関毎の営業地盤面の被害・その劣化度合いについて推定したところにある。そうした分析結果を基に、対応すべき課題を検討する。本稿は、2011年3月末時点に於ける被害状況を基準としており、被災地域の多くは既に立ち直り傾向にあるとみられる。しかし、災害の規模や金融面への影響については未だに必ずしも明確ではない面が多いだけに、それらの把握が重要であることを考慮し、取り敢えず次のような考え方の下で進めた分析結果を示すこととした。
1 0 0 0 IR ユーザエクスペリエンスと満足度 : 学生満足度の概念と測定法の整備に向けて
- 著者
- 黒須 正明
- 出版者
- 放送大学
- 雑誌
- 放送大学研究年報 (ISSN:09114505)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.71-83, 2010
- 被引用文献数
- 1
機器やシステムの設計における人間中心設計(HCD) の枠組みは、教育におけるインストラクショナルデザイン(ID)の枠組みときわめて類似している。近年、HCDの分野においては、ユーザエクスペリエンス(UX:UserExperience)という概念が注目されており、著者も、購入前の期待感、購入時のインタラクションによる印象形成、購入後の実利用による評価という3 フェーズに分けたモデルを提唱している。特に3 番目のフェーズにおいては満足感が重要な指標とされ、それをどのように測定するかが課題となっている。本稿では、この考え方を学生の学習経験(LX:Learning Experience)と学生満足度(Student Satisfaction)にも援用しようと試みた。ただし、IDにおいては教育場面特有の事情を考慮しなければならない。本稿では学生満足度に関する概念構造とその測定法を、このようなHCD分野との比較において論じた。
- 著者
- Martinu̇
- 出版者
- Nippon Columbia [distributor]
- 巻号頁・発行日
- 1995
1 0 0 0 OA 文学的テロリズムの逢着点 : J・ポーラン『タルブの花』を巡るブランショの言説
- 著者
- 山邑 久仁子
- 出版者
- 上智大学
- 雑誌
- Les Lettres francaises (ISSN:02851547)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.43-55, 1990-06-25
- 著者
- 山田 日登志 池松 由香
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ベンチャ- (ISSN:02896516)
- 巻号頁・発行日
- no.272, pp.38-42, 2007-05
カイゼンは工場だけのものではない。販売や経営にも、カイゼンの考え方を生かせる。5年前から「山田流カイゼン」を学び、2006年からは販売にも導入する和菓子メーカー、叶匠壽庵の経営者と管理者の協力を得て、「極意」を聞いた。取材・文◎池松由香(編集部) 写真◎水野浩志〓〓山田流カイゼンを始めて約5年が経ちました。社長・芝田 はい。
1 0 0 0 プレスブルガー文真偽判定手続きを用いた算術演算回路の正しさの証明
- 著者
- 森岡 澄夫 柴田 直樹 東野 輝夫 谷口 健一
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. VLD, VLSI設計技術
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.299, pp.49-56, 1996-10-18
- 被引用文献数
- 5
加算器, 乗算器, ALUなど, 算術演算を行う組み合わせ論理回路が, そのワードレベル仕様F (整数上の論理式として書かれた入出力関係の記述) を正しく実現している事を, プレスブルガー文真偽判定手続きを用いて自動証明する方法と, 証明例について述べる. 証明は, いわゆるビットレベル検証 (各回路モジュールM_jごと, そのワードレベル仕様F_jがゲートレベルで正しく実現されていることの証明) とワードレベル検証 (各M_jの接続関係および各ワードレベル仕様F_jのもとで, Fが満たされることの証明) に分けて行う. 乗算など, プレスブルガー算術で直接扱えない演算を行う回路についても, その演算に関して数学的に成り立つ性質等を仮定することにより, 証明できる場合がある. 本手法の特徴は, 幾つかの工夫を行ったプレスブルガー真偽判定ルーチンを用いることにより, 各モジュールの演算ビット長 n が増えても, 回路中のモジュールの数や組合せ方が同じで, かつ仕様記述のサイズが n 依存していなければ, ワードレベル検証にかかる時間がほとんど増加しないことである. 例えば n ビット乗算器から 2n ビット乗算器を構成した場合のワードレベル検証を, 2分程度のCPU時間で行えた. ビットレベル検証についても, 演算ビット長が4ビット程度であれば, 例えば加減算・論理演算を行うALU (74382) について6分程度のCPU時間で行えた.
- 著者
- 青木 豊 綿貫 理明 楠 裕行
- 出版者
- 専修大学ネットワーク情報学会
- 雑誌
- 専修ネットワーク&インフォメーション (ISSN:13471449)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.25-32, 2009-01
- 著者
- Matsuda Takeshi Yano Junya Hirai Yasuhiro Sakai Shin-ichi
- 出版者
- Springer Verlag
- 雑誌
- The International Journal of Life Cycle Assessment (ISSN:09483349)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.6, pp.743-752, 2012-07
- 被引用文献数
- 47
[Purpose]Source-separated collection of food waste has been reported to reduce the amount of household waste in several cities including Kyoto, Japan. Food waste can be reduced by various activities including preventing edible food loss, draining moisture, and home composting. These activities have different potentials for greenhouse gas (GHG) reduction. Therefore, we conducted a life-cycle inventory analysis of household waste management scenarios for Kyoto with a special emphasis on food waste reduction activities. [Methods]The primary functional unit of our study was “annual management of household combustible waste in Kyoto, Japan.” Although some life-cycle assessment scenarios included food waste reduction measures, all of the scenarios had an identical secondary functional unit, “annual food ingestion (mass and composition) by the residents of Kyoto, Japan.” We analyzed a typical incineration scenario (Inc) and two anaerobic digestion (dry thermophilic facilities) scenarios involving either source-separated collection (SepBio) or nonseparated collection followed by mechanical sorting (MecBio). We assumed that the biogas from anaerobic digestion was used for power generation. In addition, to evaluate the effects of waste reduction combined with separate collection, three food waste reduction cases were considered in the SepBio scenario: (1) preventing loss of edible food (PrevLoss); (2) draining moisture contents (ReducDrain); and (3) home composting (ReducHcom). In these three cases, we assumed that the household waste was reduced by 5%. [Results and discussion]The GHG emissions from the Inc, MecBio, and SepBio scenarios were 123.3, 119.5, and 118.6 Gg CO2-eq/year, respectively. Compared with the SepBio scenario without food waste reduction, the PrevLoss and ReducDrain cases reduced the GHG emissions by 17.1 and 0.5 Gg CO2-eq/year. In contrast, the ReducHcom case increased the GHG emissions by 2.1 Gg CO2-eq/year. This is because the biogas power production decreased due to the reduction in food waste, while the electricity consumption increased in response to home composting. Sensitivity analyses revealed that a reduction of only 1% of the household waste by food loss prevention has the same GHG reduction effect as a 31-point increase (from 50% to 81%) in the food waste separation rate. [Conclusions]We found that prevention of food losses enhanced by separate collection led to a significant reduction in GHG emissions. These findings will be useful in future studies designed to develop strategies for further reductions in GHG emissions.
1 0 0 0 取調べの可視化における技術課題の明確化とシステム提案
- 著者
- 高間 浩樹 越前 功 吉浦 裕
- 出版者
- 情報処理学会
- 雑誌
- 研究報告コンピュータセキュリティ(CSEC) (ISSN:18840930)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, no.27, pp.1-6, 2009-05-21
取調べの可視化によって自白の任意性が客観的かつ容易に確認可能になるとの期待がある,一方,取調べの妨げや裁判の非効率化につながるとの指摘もある.①取調べの可視化に対する期待を実現するために技術によってどのような支援ができるか,②取調べの可視化について指摘される問題点を技術によってどのように軽減することができるか,という観点から取調べの可視化について分析し,(1)ヒューマンエラーの防止,(2)開示の完全性,(3)プライバシーの保護,(4)可視化記録の閲覧の効率化,という4つの技術課題を明らかにした.このうち(1)~(3)を解決する方法として,個々の被疑者を区別せず全ての取調べを自動的に記録し,一元管理する方法,顔・声紋識別を用いて一元管理された記録中から当該被疑者の記録のみを漏れなく検索する方法を提案し,これらを統合した取調べ可視化システムを提案する.In this paper, we analyze problems in visual interrogation recording and clarify four technical requirements for IT technologies to solve these problems; (1) preventing human errors, (2) guaranteeing completeness of record disclosure, (3) protecting privacy of irrelevant people, and (4) enabling effective survey of long record. To meet these requirements, we propose a method that automatically records interrogation without discriminating each suspects, a method that uses face and voice recognition techniques to retrieve all records of the target suspect without retrieving those of other suspects, and the system that integrates these methods.
- 著者
- 横浜美術館 マグナム・フォト東京支社 隈千夏編
- 出版者
- マグナム・フォト東京支社
- 巻号頁・発行日
- 2013
1 0 0 0 パッチテストによる皮膚反応の色彩学的分析
- 著者
- 松田 もと子 永井 成美 折笠 史明 多田 建造 辰巳 浩輝 藤原 麻紀 古川 良俊 石橋 寛二 井上 昌幸
- 出版者
- 社団法人日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科學會雜誌 (ISSN:03895386)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.588-595, 1994-06-01
- 被引用文献数
- 2 1
歯科用金属に起因すると考えられる金属アレルギーが注目されており,その診断にパッチテストが用いられている.しかし,判定は主観に頼り,皮膚の変化を的確,経時的に把握することは困難である.本論文はパッチテストにおける客観的な判定システムを開発することを目的として,パッチテスト後の皮膚色を分光測色し,色彩学的に分析したものである.その結果,皮膚の発赤反応に色彩学的に特徴のある変化が観察された.皮膚の発赤反応を判定する客観的指標を示したものとして興味深い.
- 著者
- 北村 直子
- 出版者
- 京都大学フランス語学フランス文学研究会
- 雑誌
- 仏文研究 (ISSN:03851869)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.115-130, 2002-10-15
1 0 0 0 OA かつとト輪廓
- 著者
- モトカヅ文様研究部 編
- 出版者
- 内田美術書肆
- 巻号頁・発行日
- 1926
1 0 0 0 OA 211 煙霧法による森林害虫の防除 (1)(昭和40年度日本農学会大会分科会)
- 著者
- 合田 昌義 酒井 清六 野上 寿 松石 一樹 米林 俵三 小柴 智
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会大会講演要旨
- 巻号頁・発行日
- no.9, 1965-03-30
- 著者
- 井伊谷 鋼一
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学會誌 (ISSN:00214728)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.436, 1955-05-05
- 著者
- 松尾 匡 熊澤 大輔
- 出版者
- 立命館大学
- 雑誌
- 立命館經濟學 (ISSN:02880180)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.6, pp.1471-1484, 2011-03