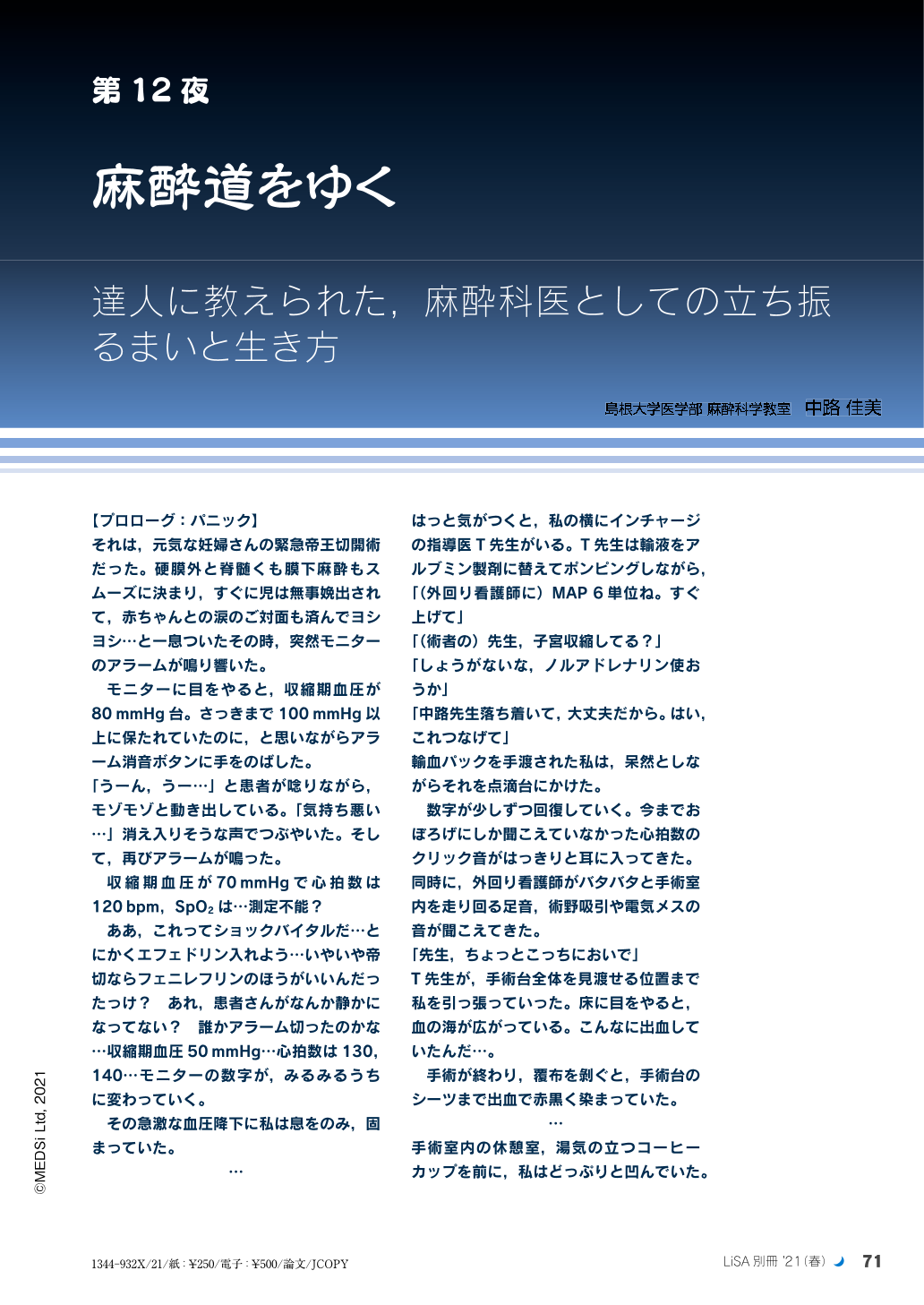4 0 0 0 OA 第二芸術論と雑誌「八雲」-久保田正文を軸に-
- 著者
- 内藤 明
- 出版者
- 早稲田大学社会科学部学会
- 雑誌
- 早稻田人文自然科學研究 = The Waseda journal of general science (ISSN:02861275)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.67-105, 1995-10
論文
4 0 0 0 OA チベットにおけるジャムチの設置
4 0 0 0 ハナ・アーレント著「全体主義の起源」
- 出版者
- 国際文化協会
- 雑誌
- コムミュニズムの諸問題
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.7, 1953-11
- 著者
- 三輪 昭尚
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンピュータ = Nikkei computer (ISSN:02854619)
- 巻号頁・発行日
- no.974, pp.48-51, 2018-09-27
大林組の元CIOで建設技術のプロフェッショナルが7月に政府CIOに就いた。省庁のデジタル改革やデータ活用による経済活性化などの難題に挑む。「目的と手段を混同しない」「成果を分かりやすく示す」などIT活用の本質重視で臨む。
4 0 0 0 OA 高齢者の時間感覚に関する研究 : 高齢者は時間経過をどのように感じるか
- 著者
- 和田 博美 村田 和香
- 出版者
- 北海道高齢者問題研究協会
- 雑誌
- 高齢者問題研究 (ISSN:09111859)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.79-85, 2001-03
50,60,70,80歳代の入院中の高齢者群と20歳代の若年者群を対象に,時間作成法を用いて時間判断の調査を行った。対象者は3,6,30,60秒の時間間隔を,ブザーを鳴らすことによって作成するよう求められた。若年者群は3,6,30,60秒の時間間隔を正確に作成することが出来た。しかし高齢者群は30秒と60秒の作成時間が減少した。50,70,80歳代の作成時間は,20歳代の作成時間より有意に短かった。3秒と6秒に対する高齢者群の作成時間は増大したが,年代間に有意差はなかった。時間判断の加速率(客観的時間に対する主観的時間の比率)は,加齢が進むほど,求めた作成時間が長いほど増加した。しかも70歳代と80歳代の加速率は,これまでの報告よりもはるかに高かった。入院という体験によって身体,心理,社会面での主観的幸福感が低下し,時間判断に影響を与えていた可能性が示唆された。結論として高齢者群の主観的な時間経過は若年者群よりも速まり,主観的時間の加速化が起こっていることが明らかになった。主観的時間の加速化が生じた結果,高齢者は周囲の時間や出来事がゆっくり経過するように感じるのかもしれない。改訂長谷川式簡易知能評価スケールの得点は,高齢者群で有意に低かったが,いずれも正常範囲であった。
- 著者
- 岩井 紀子 宍戸 邦章
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.3, pp.420-438, 2013 (Released:2014-12-31)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 5
内閣府, 全国紙, NHK, 国立環境研究所, 日本原子力学会などによる世論調査の結果を基に, 福島第一原子力発電所事故発事故が, 人々の意識に与えた影響について, 震災以前と以降を比較したところ, 原発事故は, 災害リスク認知や原発事故への不安感および環境汚染意識を高め, 原子力政策に対する人々の意識を大きく変えた. 専門家と一般住民の原子力政策に対する認識のギャップは, 震災前以上に大きい.JGSSデータに基づく分析では, 原子力への反対意識は, 女性で強く, 若年層の男性や自民党支持層で弱く, この点はチェルノブイリ事故後の結果と一致している. 原発から70kmの範囲に居住している場合には, 原発の近くに住んでいるほど原発事故が発生するリスクをより高く認知していた. また, 原子力政策に対する原発からの距離と地震発生のリスク認知には交互作用効果が存在しており, 地震発生のリスク認知が低い場合には原発近くに住む人ほど原子炉廃止への支持が少ないことが明らかとなった. 原発事故は, 人々の意識を変えただけではない. 日本では節電意識は以前から高かったが, 原発事故後, 電気をこまめに消す以上の, 消費電力を減らすさまざまな工夫を行い, 電力需要は2011年度には5.1%減少し, 12年度にはさらに1.0%減少した. 節電の工夫の頻度は, 原子力政策への態度と関連しており, 原子炉廃止層の8割が消費電力を減らす工夫に取り組んだ. 電力需要の減少は原子力政策の今後に対する人々の意思表明であろう.
4 0 0 0 OA 脳は文字をどこで読むのか?
- 著者
- 栗城 真也 平田 恵啓
- 出版者
- 北海道大学電子科学研究所
- 雑誌
- 電子科学研究 (ISSN:13402455)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.13-21, 1997-02
- 著者
- 中村 恵 ナカムラ メグミ Megumi Nakamura
- 出版者
- 東洋大学法学会
- 雑誌
- 東洋法学 = Toyohogaku (ISSN:05640245)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1・2, pp.67-80, 2007-03-10
- 著者
- 中路 佳美
- 出版者
- メディカル・サイエンス・インターナショナル
- 巻号頁・発行日
- pp.71-80, 2021-04-15
【プロローグ:パニック】それは,元気な妊婦さんの緊急帝王切開術だった。硬膜外と脊髄くも膜下麻酔もスムーズに決まり,すぐに児は無事娩出されて,赤ちゃんとの涙のご対面も済んでヨシヨシ…と一息ついたその時,突然モニターのアラームが鳴り響いた。 モニターに目をやると,収縮期血圧が80mmHg台。さっきまで100mmHg以上に保たれていたのに,と思いながらアラーム消音ボタンに手をのばした。「うーん,うー…」と患者が唸りながら,モゾモゾと動き出している。「気持ち悪い…」消え入りそうな声でつぶやいた。そして,再びアラームが鳴った。 収縮期血圧が70mmHgで心拍数は120bpm,SpO2は…測定不能? ああ,これってショックバイタルだ…とにかくエフェドリン入れよう…いやいや帝切ならフェニレフリンのほうがいいんだったっけ? あれ,患者さんがなんか静かになってない? 誰かアラーム切ったのかな…収縮期血圧50mmHg…心拍数は130,140…モニターの数字が,みるみるうちに変わっていく。 その急激な血圧降下に私は息をのみ,固まっていた。…はっと気がつくと,私の横にインチャージの指導医T先生がいる。T先生は輸液をアルブミン製剤に替えてポンピングしながら,「(外回り看護師に)MAP 6単位ね。すぐ上げて」「(術者の)先生,子宮収縮してる?」「しょうがないな,ノルアドレナリン使おうか」「中路先生落ち着いて,大丈夫だから。はい,これつなげて」輸血パックを手渡された私は,呆然としながらそれを点滴台にかけた。 数字が少しずつ回復していく。今までおぼろげにしか聞こえていなかった心拍数のクリック音がはっきりと耳に入ってきた。同時に,外回り看護師がバタバタと手術室内を走り回る足音,術野吸引や電気メスの音が聞こえてきた。「先生,ちょっとこっちにおいで」T先生が,手術台全体を見渡せる位置まで私を引っ張っていった。床に目をやると,血の海が広がっている。こんなに出血していたんだ…。 手術が終わり,覆布を剝ぐと,手術台のシーツまで出血で赤黒く染まっていた。…手術室内の休憩室,湯気の立つコーヒーカップを前に,私はどっぷりと凹んでいた。T先生はコーヒーを口に運びながら,「まだ若手なんだからさ,そんなこともあるよ」と,笑顔で慰めてくれた。 私はほとんど呆然とモニターを見ていた。術野も見たが,その時点で出血はそれほど多くなく,問題ないと判断してしまった。患者さんも見ていたつもりでいたが,その時の意識状態は,顔色は,手の冷たさは,呼吸は…何も思い出せない。私は患者さんの頭もとでパニックになり,視野狭窄を起こしていた。ただモニターの数字しか目に入らず,そして誰かに助けを求めることなく立ち尽くしていたのだ。「私,全然見えてなかったんです。体も固まってしまっていました。T先生,あんなとき麻酔科医って,どんな心構えで,どこに目を向けて,どう考えて動けばいいんでしょうか?」T先生は,天井を見つめながらしばらく考えたのち,口を開いた。「そうだな…じゃあ,達人たちにたずねてみるか?」…雲をつかむような命題に立ち向かう旅の始まりであった。
4 0 0 0 OA 水溶液中のクラスター構造と物性に関する質量分析法による解析
- 著者
- 脇坂 昭弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.9, pp.743-758, 2010 (Released:2010-11-11)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 2 3
溶液中の微視的構造に関する情報を得るために,液滴を真空チャンバー内でクラスターレベルに断片化し,その質量スペクトルを測定する分析技術を開発した.これにより水と有機化合物,及び電解質との相互作用によって形成されたクラスター構造とこれら水溶液の物性との関係を研究した.水-有機化合物系では,水-アルコール混合溶液のクラスター構造と,粘度,相分離特性,選択的溶媒和などの溶液の物性との関係を明らかにした.また,アルコール自己会合クラスターの生成が水によって促進されるのは,溶液中で生じる分子間相互作用の相対的関係によることを明らかにした.電解質水溶液系では,硝酸,硫酸,酢酸水溶液のクラスター構造を解析し,酸性度との関係を明らかにした.更に,水中の酢酸が水酸化ナトリウムにより中和され塩を生成する過程をクラスターレベルで観測した.
4 0 0 0 IR 能「松山天狗」が見せる崇徳院怨霊の鎮魂劇
- 著者
- 本多 典子
- 出版者
- 東京都立産業技術高等専門学校
- 雑誌
- 東京都立産業技術高等専門学校研究紀要 = Research reports of Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology (ISSN:18831990)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.30-39, 2021-03
4 0 0 0 OA 〔私党人名書上げ〕
- 著者
- 疋田 耕造
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1277, pp.138-141, 2005-01-31
創業してから26年、我々は業界の商習慣にのっとってやってきました。しかし社会が変わる中で、従来の慣習は現状にそぐわなくなってきたんでしょう。そこで今回の勧告をきっかけに、正すべきところは正さなければならないと考えたわけです。 近畿地方を地盤とするホームセンターのコーナン商事は2004年11月11日、公正取引委員会から独占禁止法違反で排除勧告を受けました。
- 著者
- 野口 修 加藤 詞史
- 出版者
- 一般財団法人 住総研
- 雑誌
- 住総研研究論文集・実践研究報告集 (ISSN:2433801X)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.73-84, 2021
千葉県我孫子市の手賀沼地域では,大正時代の同時期,白樺派同人の志賀直哉,武者小路実篤,柳宗悦が居住し,独自の創作活動をした。また,彼らと親交の深い芸術家が我孫子を訪ねたり,実際に移住した者もいたことから,この共同体は『我孫子コロニー』と表された。本研究で試みたのは,1.手賀沼地域の3旧邸に関する図面や写真資料,言説を掘り起こして整理・補完し,当時の住環境を復元すること,2.我孫子を起点に3者の住宅変遷を辿り,近代日本住宅史における白樺派建築の位置付けについて考察すること,3.研究で得た知見を基に『我孫子コロニー』を再評価し,3.旧邸跡の保全や活用を目的とした新しい地域計画を実践することである。
4 0 0 0 友情結婚にみる未婚化社会の友人関係と恋愛関係についての基礎研究
- 著者
- 小川 功
- 出版者
- 滋賀大学
- 雑誌
- 滋賀大学経済学部研究年報 (ISSN:13411608)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.55-78, 2004
4 0 0 0 IR 維新前夜に、栗本鋤雲がパリで見たこと聞いたこと : 「暁窓追録」を読む
- 著者
- 塩川 浩子 Hiroko Shiokawa
- 出版者
- 共立女子大学
- 雑誌
- 共立女子大学文芸学部紀要 (ISSN:03883620)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.35-47, 2014-01
4 0 0 0 OA 興味ある膀胱異物の4例
- 著者
- 田口 裕功 堀内 満水雄 熊谷 治己 石塚 栄一
- 出版者
- 一般社団法人 国立医療学会
- 雑誌
- 医療 (ISSN:00211699)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.6, pp.829-832, 1969 (Released:2011-10-19)
- 参考文献数
- 2
Four cases of bladder foreign body were reported. In all cases, onanism was motives from which they inserted foreign bodies into the bladder. First two cases had the bladder calculi might be formed by the bladder foreign bodies.Case 1: -A 21 years old male had a piece of metal wire in the bladder for almost 10 years which introduced through the urethra. The bladder stone removed through suprapubic vesicotomy sized 7.0×4.5×4.0cm.Case 2: -A 26 years old male had a bladder stone produced by the pin like needle which might be introduced almost 10 years ago. A stone removed transvesically sized 4.0×4.0×4.3cm.In these 2 cases, the ureters were definitely dilated and vesico-ureteral refluxes were visualized in X-ray examiations.Case 3: -A 14 yers old male inserted a candle into the bladder due to onanism. This was visualized to be broken into several pieces by the cystoscopic examination and was removed with the endoscopic technique.Case 4: -This 34 yers old male stated that he inserted a fine elastic string 15 cm in length into the bladder accidentally. Despite it had been in the bladder only for 20 days, massive urine crystals attached around the elastic string. It succeeded to withdraw by transurethral approaches.