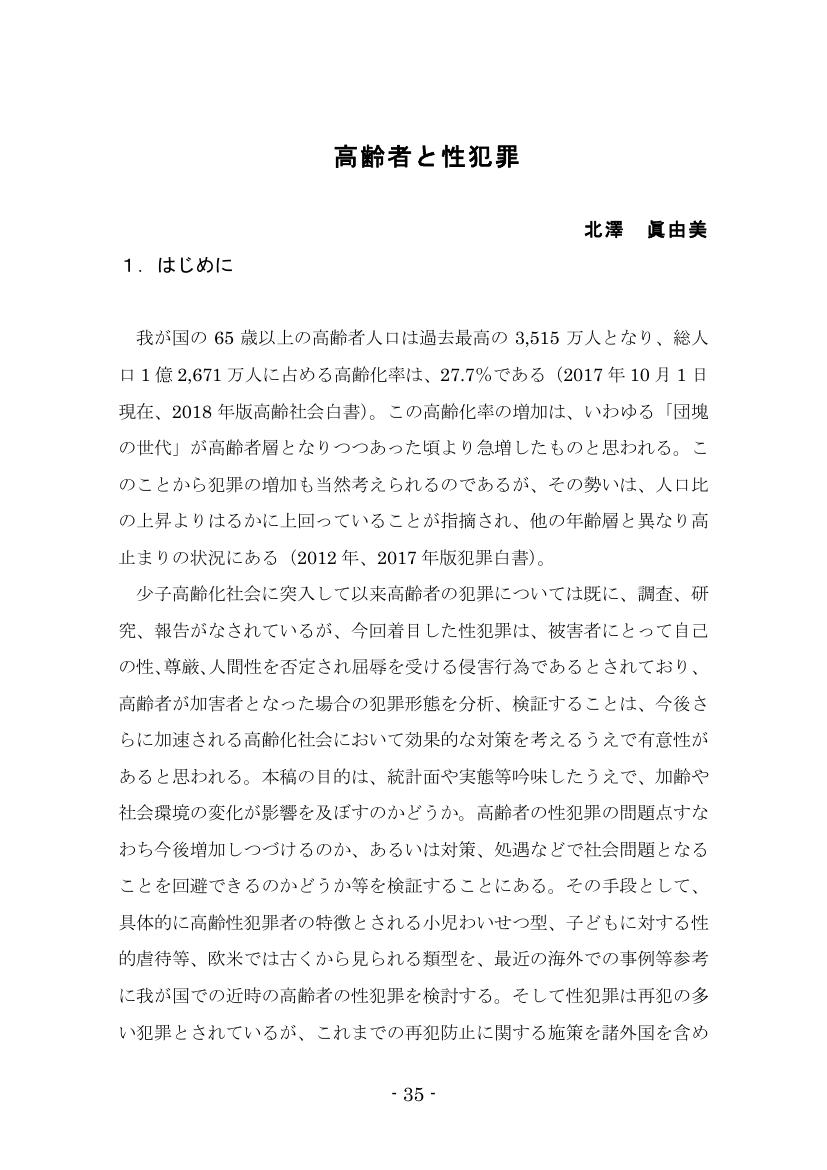4 0 0 0 OA 子どもの発達と母子関係・夫婦関係 : 幼児を持つ家族について
- 著者
- 数井 みゆき 無藤 隆 園田 菜摘
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.31-40, 1996-08-01 (Released:2017-07-20)
- 被引用文献数
- 9
本研究の目的は, 子どもの発達を家族システム的に検討することである。家族システムの3変数として, 子どもの愛着, 母親の認知する夫婦関係, 母親の育児ストレスをとりあげている。対象者は, 48組の母子で, 子どもの平均年齢は3.4歳であった。子の愛着の安定性には, 夫婦関係の調和性と親役割からのストレスとが関連していた。特にこの2つの変数の交互作用の要因が有意で, 親役割からのストレスが高くかつ夫婦関係が調和的でないときに, その子の愛着がもっとも不安定に予測された。また, 社会的サポートは親役割ストレスを低くする方向で関連していた。さらに, 家族関係の機能度という視点より, 柔軟性が適度に保たれている家族は, 家族システム的にも良好であった。母親の心理的状態や子どもへの行動・態度は, 夫との関係のありようと密接に関連しているという結果であり, 子どもの心理的状態を研究する上で母親ばかりではなく父親(夫)との相互作用・関係を考慮にいれなければならないことを示唆した。
4 0 0 0 OA 日常的コミュニケーションから予測する潜在的援助者のコスト
- 著者
- 竹ヶ原 靖子 安保 英勇
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.136-146, 2018 (Released:2018-03-03)
- 参考文献数
- 35
援助要請者は,援助要請の際に,自身のコストだけでなく,潜在的援助者のコストにも注目していることが示されているが,援助要請者が何から潜在的援助者のコストを予測するのかについてはあまり検討されていない。そこで,本研究では援助要請者と潜在的援助者の二者間におけるコミュニケーション・パターンに着目し,それが援助要請者の潜在的援助者コスト予測と援助要請意図に与える影響を検討した。大学生の同性友人ペア15組にそれぞれ10分間の日常会話をさせた後,潜在的援助者のコストを予測し,自身の援助要請意図について回答させた。その結果,相補的コミュニケーション(↑↓)と潜在的援助者の憂うつな感情との間に負の相関,相称的・競争的なコミュニケーション(↑↑)と援助要請意図の間には負の関連が示されるなど,日常会話におけるコミュニケーション・パターンと潜在的援助者のコスト予測,援助要請意図との間にいくつか有意な関連が示された。このことから,日常場面におけるコミュニケーションは,援助要請者が潜在的援助者のコストを予測する手がかりのひとつであることが示唆された。
- 著者
- 木下 央子 木下 正嘉 高橋 亜紀代 湯浅 慎介 福田 恵一
- 出版者
- 日本皮膚科学会西部支部
- 雑誌
- 西日本皮膚科 (ISSN:03869784)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.4, pp.427-431, 2012-08-01 (Released:2012-11-15)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1 6
皮膚老化は皮膚が人間の最も表面にある臓器ゆえに,経時的,遺伝的な内因的要因だけではなく,日光や大気などの外的要因も老化現象に影響を及ぼす。皮膚のたるみやしわの大きな原因は皮下組織の線維芽細胞の細胞数減少や結合組織構成タンパクの分泌能低下,日光などの外的ストレスが原因となるコラーゲン分解亢進などが主な原因となって起こることが知られている。フルボ酸は腐植物質より抽出される自然由来の物質であるが,キレート作用や pH 緩衝作用,細菌増殖抑制作用や,湿疹に対する有用性の報告がある。このフルボ酸が線維芽細胞やコラーゲン分解に直接的に関与する matrix metalloproteinase (MMP) に対してどのような効果をもたらすか調べた。細胞は正常人成人の皮膚線維芽細胞を使用し,細胞のバイアビリティは Calcein-AM を使用した細胞のエステラーゼ活性を測定することにより,MMP の阻害作用については FITC 標識コラーゲンの分解抑制試験にて観察した。フルボ酸1%では26.1% (P<0.01) 細胞バイアビリティ増加を認め5%でも細胞毒性を認めなかっ た MMP の抑制試験において MMP-8 0.25unit ではコントロールに比べフルボ酸1%は約47% (P<0.01),フルボ酸5%は約61% (P<0.01) の MMP 抑制効果を認め,MMP-8 0.5unit ではコントロールに比べフルボ酸1%は約23% (P<0.01),フルボ酸5%は約56% (P<0.01) の MMP 抑制効果を認めた。今回の実験よりフルボ酸は線維芽細胞のバイアビリティ増加と MMP によるコラーゲン分解を抑制するという二つの観点からアンチエイジングに対して有用である可能性が示唆された。
4 0 0 0 IR トルコの政教分離に関する憲法学的考察 : 国家の非宗教性と宗教的中立性の観点から
- 著者
- 小泉 洋一
- 出版者
- 甲南大学
- 雑誌
- 甲南法学 (ISSN:04524179)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.279-345, 2008-03-10
4 0 0 0 IR 性的マイノリティのカミングアウトの根拠としての「不可視」論再考
- 著者
- 大坪 真利子
- 出版者
- 早稲田大学総合人文科学研究センター
- 雑誌
- 早稲田大学総合人文科学研究センター研究誌 = WASEDA RILAS JOURNAL (ISSN:21878307)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.41-51, 2020-10-20
4 0 0 0 OA 再起奉公 : 傷痍軍人を中心とせる座談会
- 出版者
- 軍人援護会
- 巻号頁・発行日
- 1939
4 0 0 0 OA 高齢者の性犯罪
- 著者
- 北澤 眞由美
- 出版者
- NPO法人 全国犯罪非行協議会
- 雑誌
- NCCD -in JAPAN (ISSN:13416308)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, no.57, pp.35-51, 2018 (Released:2019-10-16)
4 0 0 0 IR 寺中作雄の公民教育観と社会教育観の形成
- 著者
- 上原 直人
- 出版者
- 東京大学大学院教育学研究科生涯教育計画講座社会教育学研究室紀要編集委員会
- 雑誌
- 生涯学習・社会教育学研究 (ISSN:1342193X)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.31-40, 2000
4 0 0 0 OA 鉄道旅客手小荷物運賃算出表
4 0 0 0 OA 若手研究者特別委員会のこれまでとこれから
- 著者
- 山田 祐樹
- 出版者
- 日本基礎心理学会
- 雑誌
- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.213-215, 2021-03-31 (Released:2021-06-05)
- 参考文献数
- 8
This note is a short report on the activity of the Young Researchers Committee of the Japanese Psychonomic Society (JPS). As the highlighted activity of the committee, we have held the oral session of the annual meeting of JPS seven times. We also have opened a social networking account and created a portal site for psychonomic labs across the country to increase interaction. We continue to update the committee members and their selection process to increase the mobility of the members. We are developing new activities to target a wider range of young or early career researchers. In the future, this committee should become a more open, diverse, and impartial organization.
4 0 0 0 IR ツェランとハイデガー : 詩「トートナウベルク」をめぐって
- 著者
- 宇京 頼三
- 出版者
- 三重大学
- 雑誌
- 人文論叢 : 三重大学人文学部文化学科研究紀要 (ISSN:02897253)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.A1-A15, 2004-03-25
パウル・ツェランはルーマニア生れのユダヤ人で、二十世紀後半のドイツ語表記の最大の詩人として後半生をパリで送った。マルティン・ハイデガーは二十世紀の哲学・思想を代表する哲学者の一人である。詩「トートナウベルク」はツェランが南西ドイツのシュヴァルツヴァルトにあるハイデガーの山荘を訪れたあと、ハイデガーのナチズム加担をめぐって書かれたものである。本稿では、この詩「トートナウベルク」が二人にとって如何なる意味をもっていたかを主として、新資料である、ツェランと夫人のジゼル・ツェラン=レストランジュが交わした膨大な『書簡集』(フランス語版)に基づいて考察している。
4 0 0 0 IR 重源上人から山頭火まで : 徳地町の語り部・赤木森さん大いに語る
- 著者
- 安渓 遊地 安渓 貴子
- 出版者
- 山口県立大学
- 雑誌
- 山口県立大学國際文化學部紀要 (ISSN:13427148)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.55-67, 2005-03-25
This is a collection of the narratives of Mr. AKAGI Hayashi, an eminent story-teller living in Tokuji Town, Yamaguchi Prefecture. Based on his field surveys begun five decades ago, he kindly invited us to visit sites of historical and folkloric interest scattered throughout Tokuji. Every time he guided us, we were happily surprised by his ability to narrate centuries-old oral traditions in detail as if they happened only yesterday. The core of his narratives was the Herculean acts of a Buddhist priest, Saint Chogen (1121-1206), who used timbers from the Tokuji forest to rebuild the Todaiji Temple, a World Heritage in Nara, which had been destroyed during the civil war of Genji and Heike. Although almost every cultural heritage in Tokuji, Buddhist statues, saunas, tea cultivation, paper-making and so on, is affiliated to Saint Chogen, Mr. AKAGI also expands his vivid biographic narratives to such recent times as Santoka (1882-1940), a famous poet of haiku, who lived and died as a vagabond mendicant.
- 著者
- Muhammad KOZIN Keisuke KUSAKABE Masatoshi ARAMAKI Naoya YAMADA Satoshi OUE Yukiko OZAKI Osamu FURUKIMI Masaki TANAKA
- 出版者
- Japan Society of Powder and Powder Metallurgy
- 雑誌
- 粉体および粉末冶金 (ISSN:05328799)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.173-181, 2020-04-15 (Released:2020-04-15)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
In the present study, we have examined the wear properties of the sintered pure iron subjected to two distinct heat treatments such as nitriding-quenching (NQ) and carburizing-quenching (CQ). Based on our current observations, the martensite layer was formed on the surface layer following each treatment, whereas the hardness of the NQ martensite was much higher than that of the CQ one. The wear of the CQ specimen was slightly smaller than that of the NQ martensite, despite the lower value of the initial hardness. Meanwhile, the hardness of the CQ surface after the sliding tests significantly elevated relative to the NQ surface resulting in the better wear resistance. EBSD analysis demonstrated that the plastic deformation on the CQ surface along the sliding direction. Furthermore, the micro area X-ray diffraction along the surface layer of the CQ surface showed that a small amount of the retained austeite which reduced locally during the test. Therefore, the CQ-treated surface showed the excellent wear resistivity due to the surface hardening by the stress-induced transformation of the retained austenite dispersed in the martensite, in addition to the strain hardening of the martensite itself. In contrast, the worn surface of the NQ specimen showed slight plastic deformations of the ferrite grains beneath the martensite layer, but not in the surface martensite layer. This deformation under the martensite layer was due to the hardness gap between inward and the heat-treated surface, and might contribute to form the concave profile on the sliding surface. Consequently, this study could demonstrate such the difference in the wear mechanisms between the CQ and the NQ specimens.
4 0 0 0 OA 初回利用までの期間を用いた顧客管理指標の提案 —契約型顧客関係の管理指標を目指して—
- 著者
- 上田 雅夫
- 出版者
- 日本行動計量学会
- 雑誌
- 行動計量学 (ISSN:03855481)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.97-106, 2019 (Released:2020-03-31)
- 参考文献数
- 31
The objective in this research is to propose an index for customer relationship management instead of utilizing RFM or share of wallet. This study examined whether the number of days from contract to initial usage can be used as the index for customer management. For this purpose, an empirical analysis was conducted by using a Bayesian model with purchase history data of a single year and three years regarding two kinds of credit cards and a customer master data. The results of the empirical analysis showed the shorter duration to the contract day, the amount of money for the one hundred eighty days from initial usage became higher. These results clarified that the days can be utilized as the index for customer management. In the conventional customer management index such as RFM, it is necessary to store purchase history data for several months in a data warehouse, however, this proposed method does not need to store transaction data since the duration data can be utilized. Hence, this index can promptly find problematic customers.
4 0 0 0 OA 従軍慰安婦裁判 : 原告の訴えるもの
- 著者
- 高良 沙哉
- 出版者
- 沖縄大学
- 雑誌
- 沖縄大学法経学部紀要 (ISSN:13463128)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.37-48, 2007-12-31
4 0 0 0 OA 院内トリアージ導入後の現状と課題-トリアージの質向上にむけた検証-
- 著者
- 前田 晃史
- 出版者
- ヒューマンケア研究学会
- 雑誌
- ヒューマンケア研究学会誌 = Japanese Society of Human Caring Research (ISSN:21872813)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.25-32, 2014-09-30
本研究は、院内トリアージシステム導入後、成人自己来院患者のトリアージの現状と課題を明らかにすることを目的とし、救急外来を受診した511 症例とこれらをトリアージしたトリアージナース19 名のトリアージ結果を事後検証した。未トリアージ数は、受診患者数と相関があり、煩雑時に増加していたため、マンパワー不足により発生している可能性があった。アンダートリアージは、トリアージナースの看護師経験年数や救急外来経験年数、救急関連の研修受講と相関はなく、それ以外の要因と関連していた。アンダートリアージが多かったのは、緊急群の全身性炎症反応症候群(Systemic Inflammatory Response Syndrome:以下SIRS とする)患者、トリアージナースがバイタルサイン値を優先してトリアージを行った場合であった。 今後、未トリアージの減少には、適切な人員配置や煩雑時に使用できるSimple Triage Scale の作成の検討が必要である。また、アンダートリアージの減少には、バイタルサインでのトリアージレベル決定の留意点やSIRS の勉強会を行う必要がある。
4 0 0 0 OA 先史文化を現代人はどう見たか デュルケム・マリノフスキー・ラドクリフ=ブラウン
- 著者
- 石塚 正英
- 出版者
- 特定非営利活動法人 頸城野郷土資料室
- 雑誌
- 頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要 (ISSN:24321087)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.13, pp.1-22, 2021 (Released:2021-06-06)
4 0 0 0 OA 先史社会を現代人はどう見たか トインビー・ヤスパース・フレイザー
- 著者
- 石塚 正英
- 出版者
- 特定非営利活動法人 頸城野郷土資料室
- 雑誌
- 頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要 (ISSN:24321087)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.11, pp.1-18, 2021 (Released:2021-05-19)
4 0 0 0 波束収縮と再現性の概念的差異
- 著者
- 遠藤 隆
- 出版者
- 科学基礎論学会
- 雑誌
- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.31-33, 1996-12-25
- 参考文献数
- 3