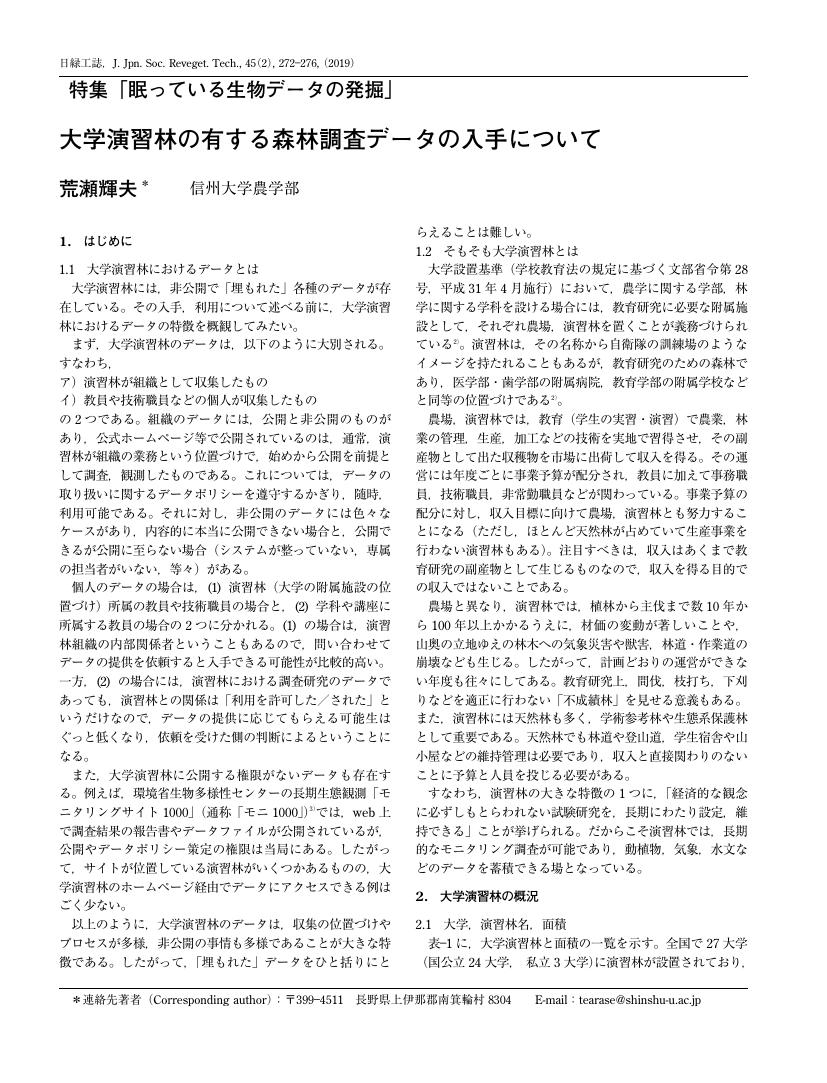3 0 0 0 OA 新型コロナウイルス感染症による死亡動向と複合死因分析:2020年
- 著者
- 別府 志海 篠原 恵美子 Motomi BEPPU Emiko SHINOHARA
- 出版者
- 国立社会保障・人口問題研究所
- 雑誌
- 人口問題研究 = Journal of Population Problems (ISSN:03872793)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.4, pp.477-492, 2022-12
特集Ⅰ
3 0 0 0 OA アメリカにおける精神科医療過誤訴訟
- 著者
- 飯塚 和之
- 出版者
- 日本私法学会
- 雑誌
- 私法 (ISSN:03873315)
- 巻号頁・発行日
- vol.1986, no.48, pp.202-208, 1986-08-30 (Released:2012-02-07)
3 0 0 0 OA 外国人材受入れの課題と地域日本語教室の役割 ―持続可能な地域づくりの観点から―
- 著者
- 仙田 武司 小菅 扶温
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.176, pp.1-15, 2020-08-25 (Released:2022-08-26)
- 参考文献数
- 13
人口減少が進む地域社会においては,持続可能な地域づくりとその担い手の確保が大きな課題となっている。課題解決への取組として,経済活動の担い手としての外国人材の受入れは,既にかなり広がってきているが,これからは社会活動の担い手としても外国人材の活躍が期待されている。本稿では,外国人材が単なる労働力にとどまらず,持続可能な地域づくりの担い手として活躍できるようにすることを目指した事例として,共同執筆者の一人である小菅の取組を取り上げた。そこから,外国人材が地域から望まれる形で受け入れられるようにするには,「外国人材に対する地域社会からの信頼の醸成」,「外国人材のキャリア形成支援」,「外国人材と地域社会とのつながりの形成」という三つの課題を達成することが重要であるとの示唆が得られた。これを踏まえて地域日本語教室を改めて捉え直すと,これら三つの課題の達成につながる五つの機能を地域日本語教室は潜在的に有しており,持続可能な地域づくりおける重要な役割を果たすことができると考えられる。
3 0 0 0 OA 神話・イメージ・言語(シンポジウム イメージと言語)
- 著者
- 松村 一男
- 出版者
- 和光大学総合文化研究所
- 雑誌
- 東西南北
- 巻号頁・発行日
- vol.2001, pp.20-26, 2001-03-19
3 0 0 0 島根県警察史
- 著者
- 島根県警察史編さん委員会編
- 出版者
- 島根県警察本部
- 巻号頁・発行日
- 1978
3 0 0 0 OA 東京都の公園におけるスケボー場所の調査研究 -スケボー活動場所に関する研究(その1)-
- 著者
- 矢部 恒彦
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.635, pp.185-192, 2009-01-30 (Released:2009-11-02)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2 1
There are two types of skateboarding places at public parks in Tokyo. One is the purpose build parks; the other is the appropriative sites. When skaters discover an appropriative site, they stay the site as they can, take their own boxes and ramps, and make a small group for the maintenance. They name there group “local” (e.g. “Akihabara Local”). In Japan, primary sites have been moving from the appropriative sites to the purpose build parks, science 1990's. Refers to an short interview with the 64 users of a park and two sites, the notions of the skaters has two tendencies as follows;(1) the needs for the adequate place to skateboarding move, (2) for the appropriation itself to make relationships of the skaters group. Corresponding this youth culture, the local governments has build and maintain the purpose build parks, and cooperated with the locals to keep a few appropriative sites.
3 0 0 0 コンピューター・ロールプレイングゲームの社会学的研究
言語ゲーム論によれば、世界とはルールの束である。ならば、逆に適切なルールの束を与えてやれば、そこに世界が構成されるはずだ。コンピューターロールプレイングゲーム(RPG)が行っているのはまさしくこれである。すなわちRPGは架空の世界を構成し、それにリアリティを与え、プレイヤーにその世界に生きているという感覚(社会参加感)を与えることを目的とするゲームだからである。よいRPG(人気ソフト)はこれに成功している。したがって、それらのソフトがどんなルールを提供しているかを見ることによってわれわれは、どんなルールが提示されればプレイヤーが世界にリアルティをもち、かつその世界に主体として積極的に関わっていると認識することができるのかを知ることができる。具体的には、いわゆるドラクエなどの人気ソフトに共通して見られるのは、自然法則、社会制度といったルールに加え、「人格化のルール」と呼びうるようなルールが提示されているということである。すなわち画面上の動きや変化を行為として認定し、その行為を何らかの人格(自己や他者)に帰属させ、その人格の動機によって説明するルールである。この「情報の人格化」がゲームのリアルティを高め、そのゲームの人気を高める。このように、社会参加の感覚を人々がもつか、それとも疎外感を感じるかは、人々がどんな人格化ルールのもとに置かれているかに依存するのだということ。また、RPGをかなり低年齢の子どもが楽しみうるということからみて、われわれはかなり早い時期にルールを読み解く能力を身につけているのだということ、以上2点がRPGの分析を通じて明らかとなった。今後さらに具体的・内容的な検討を加えたい。
3 0 0 0 対面とオンラインによる企業内技術研修の満足度を規定する要因の分析
- 著者
- 佐々 裕美 向後 千春
- 出版者
- 公益社団法人 日本工学教育協会
- 雑誌
- 工学教育 (ISSN:13412167)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.3, pp.3_57-3_63, 2023 (Released:2023-05-20)
- 参考文献数
- 25
This study aims to evaluate how satisfaction of technical training courses in in-house education was influenced by comprehension, goal achievement and training design factors: difficulties, trainers′ instruction ways, training materials and training volumes. Covariance structure analysis was conducted on questionnaire answer data from approximately 16,000 participants of training courses, which were classified into lecture and practical training types in comparison of face-to-face classes with online classes. The analysis revealed that goal achievement had a significant effect on satisfaction, and comprehension had an indirect effect on satisfaction through goal achievement. The influence of the training design factors on satisfaction, comprehension and goal achievement differed significantly with training types. In particular, the difficulties showed no significant effect on comprehension in online lecture-type trainings. This indicates subjective difficulties of online class participants may be different from those of face-to-face class participants.
3 0 0 0 OA 肉食性巻貝類アカニシとツメタガイの捕食行動と捕食痕の比較
- 著者
- 三倉 健吾 佐藤 慎一
- 出版者
- 日本古生物学会
- 雑誌
- 化石 (ISSN:00229202)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, pp.17-25, 2021-09-30 (Released:2021-10-15)
In order to extract information about predators from the drillhole characteristics, predatory behavior, drillhole-site selectivity, and preference of prey size and species were examined in Rapana venosa and Glossaulax didyma. Laboratory experiments used predators and the prey bivalves collected from Lake Hamanako in Shizuoka Prefecture, central Japan. Glossaulax didyma always drilled around umbo of bivalve shell, and it preferred similar prey size to its shell size. In contrast, observation of predatory behavior of R. venosa revealed that this species usually killed prey bivalve without drillhole but left slit-shaped scratches or nomarks using probably poisoning or suffocation. Rapana venosa preferred the largest individuals among the different sizes of Ruditapes philippinarum, and it consumed first Cyclina sinensis rather than R. philippinarum and Scapharca kagoshimensis. Our results made clear the differences of the drillhole characteristics and preference of prey size between R. venosa and G. didyma, and enabled to suggest the predator species from the dead and fossil shell.
3 0 0 0 OA 虚構としての<あいぬの風俗>国定国語教科書のアイヌ認識
- 著者
- 竹ヶ原 幸朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.250-261, 1994-09-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 60
3 0 0 0 OA 二酸化炭素を酸化剤とする燃焼 : 火星大気推進機関の可能性
- 著者
- 湯浅 三郎
- 出版者
- エネルギー・資源研究会
- 雑誌
- エネルギー・資源 (ISSN:02850494)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.28-37, 1993
3 0 0 0 OA 住民訴訟における行政判断尊重と民事法的思考
- 著者
- 高橋 正人
- 出版者
- 静岡大学人文学部
- 雑誌
- 静岡大学法政研究 (ISSN:13422243)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1-4, pp.176-151, 2012-03-31
3 0 0 0 OA 既婚女性からみた夫婦の家事分担 ――家事分担の平等化過程における規定構造の変化――
- 著者
- 乾 順子
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.39-56, 2014-10-31 (Released:2019-05-24)
- 参考文献数
- 33
The purpose of this article is to clarify the changes in the division of household labor and the structure of housework between husbands and wives in Japan using nationwide survey data. In recent years, work-life balance policies have been promoted in Japan and men’s working hours have been reduced. Therefore, it is believed that the division of housework between husband and wife has become more equal. To ensure gender equality in the future, it is important to understand the factors encouraging or preventing equality in the division of household labor. In previous studies, several theories, which can be described as the demands hypothesis, relative resources hypothesis, time constraints hypothesis, and gender ideology hypothesis, have been presented as explaining the determinants of who does housework. In this study, I explore two factors—women’s work outside their home and gender role attitudes—and their relationship with the division of housework. This is intended to test the hypothesis derived from feminism and proposed by the dual labor market theory. Through analyses using the second and third Japanese national family surveys (NFRJ03 and 08), we find that gender equality in the home has advanced slightly. The increased number of wives with regular employment appears to have caused the proportion housework done by husbands to increase by 2003. However, by 2008 the gender role attitudes of wives appeared to have a greater effect on the division of housework.In summary, the position of men and women in the labor market has been made equal as a result of social change, but because of the continuing influence of gender role attitudes, it seems that equality of housework burdens does not yet accompany this gender equality in the workforce.
3 0 0 0 OA 国会法の変遷と委員会制度の展開(3)
- 著者
- 岡﨑 加奈子
- 出版者
- 法学志林協会
- 雑誌
- 法学志林 = Review of law and political sciences (ISSN:03872874)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.3・4, pp.137-172, 2005-03-10
3 0 0 0 OA 名誉毀損罪と侮辱罪の間隙 : 人の出自,民族,属性に対する誹謗・中傷について
- 著者
- 金 尚均
- 出版者
- 立命館大学法学会
- 雑誌
- 立命館法学 = 立命館法学 (ISSN:04831330)
- 巻号頁・発行日
- vol.345/346, pp.3389-3416, 2013-03
3 0 0 0 OA 大学演習林の有する森林調査データの入手について
- 著者
- 荒瀬 輝夫
- 出版者
- 日本緑化工学会
- 雑誌
- 日本緑化工学会誌 (ISSN:09167439)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.272-276, 2019-11-30 (Released:2020-02-26)
- 参考文献数
- 9
3 0 0 0 OA 1970年代における国立医科大学誘致運動と地元負担問題
- 著者
- 大谷 奨
- 出版者
- 日本教育制度学会
- 雑誌
- 教育制度学研究 (ISSN:2189759X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, no.28, pp.56-73, 2021 (Released:2023-03-12)
3 0 0 0 OA 靴下の有無が靴着用時における歩行中の足甲接触圧に与える影響
- 著者
- 武末 慎 古達 浩史 村木 里志
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.6, pp.310-319, 2021-12-15 (Released:2022-03-24)
- 参考文献数
- 31
本研究は,足と靴のフィット性を評価するための指標としての足甲接触圧に対して靴下の有無が与える影響を検討することを目的とした.被験者は若年男性12名(年齢,23.6±1.0歳)を対象とし,普段通りの速度で歩行動作を行った.実験条件は,靴下を履かずに靴を履く,靴下に加えて靴を履くおよび靴下のみを履く3条件とした.薄型圧力センサを用いてそれぞれの靴条件での歩行動作中の母趾球上面,腓側中足点,第二楔状骨点および踵点の足甲接触圧を計測した.接触圧のデータは,歩行周期を荷重応答期,立脚中期,立脚終期,前遊脚期および遊脚期に分類し,各歩行相における平均値を算出した.足甲接触圧では,靴を履いた条件で靴下のみを着用した条件よりも接触圧が増加する部位および歩行相が多く,靴着用により接触圧増加が生じていることが示された.一方で,靴着用時の靴下の有無条件間では接触圧に有意な差がみられた部位および歩行相は認められず,靴着用時では足甲接触圧に対して靴下の有無が与える影響は小さいことが示唆された.