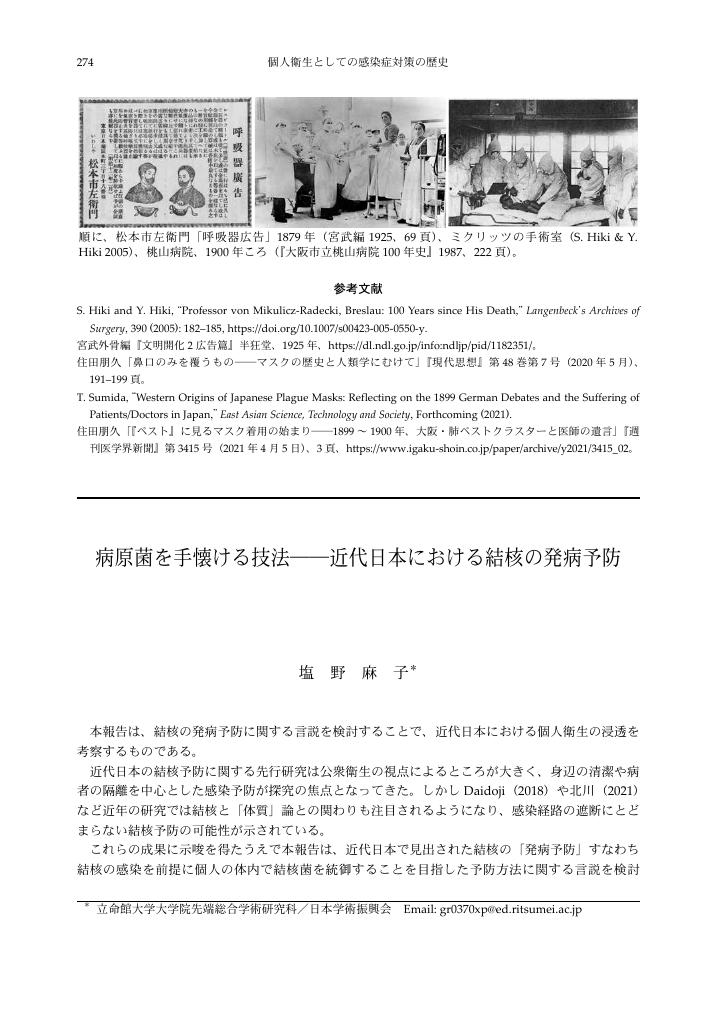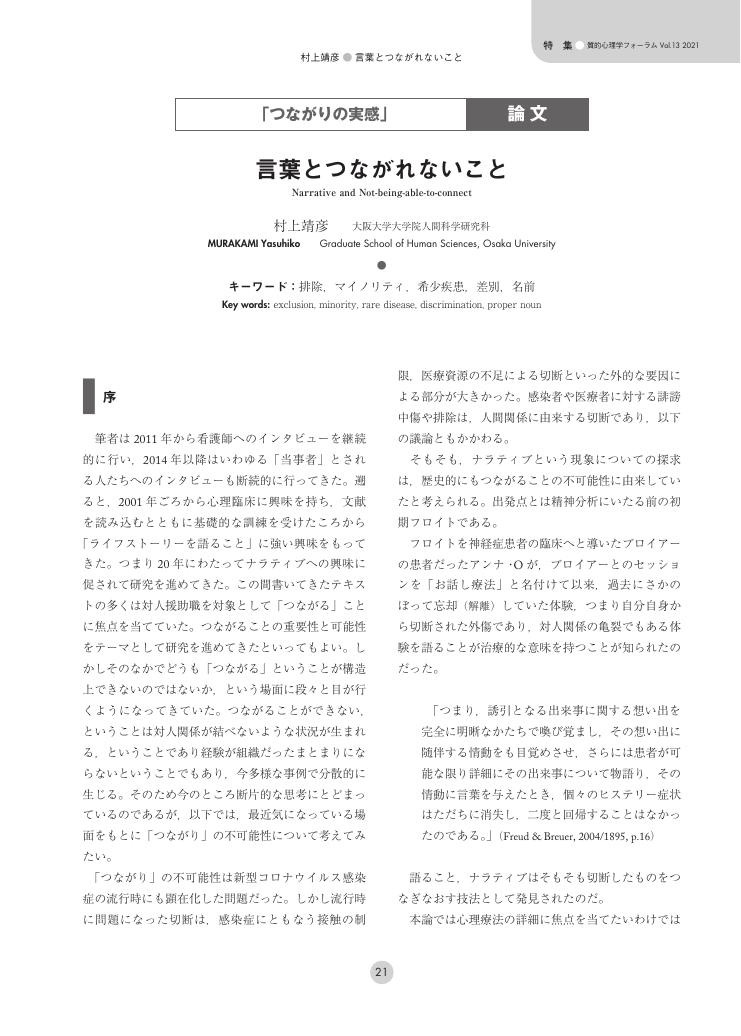3 0 0 0 OA 「涼宮ハルヒの憂鬱」が描く青年の妄想的世界 : 入門篇
- 出版者
- 京都
- 雑誌
- 同志社女子大学生活科学 = DWCLA human life and science (ISSN:13451391)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.64-68, 2012-02-20
資料
3 0 0 0 OA 新造語と錯語を呈した小児失語症1例の経過
- 著者
- 狐塚 順子 宇野 彰 北 義子
- 出版者
- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.131-137, 2003-04-20 (Released:2010-06-22)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1 1
モヤモヤ病術後の脳梗塞により左大脳後部に病巣を認め, 新造語, 錯語を呈した小児失語の1症例について, 呼称における誤反応の継時的変化を検討した.SLTAの呼称においても, 訓練時使用したすずき絵カードの呼称においても, 発症から時間が経つにつれ, 誤反応における新造語と語性錯語, 字性錯語の占める割合が減少した.これらの経過から, 本症例では意味処理過程も音韻処理過程も改善したのではないかと推察された.また小児失語症では新造語や錯語の報告は少なく, 新造語は発症のごく初期に限られ, その特有な経過は頭部外傷に関係するとされているが, 本症例では脳梗塞が原因で, 発症約1年後でも呼称において新造語が出現したことから, 成人失語症例と同様, 脳血管障害であっても新造語は生じ, かつ慢性期においても残存する可能性が考えられた.流暢性失語症である本症例の病巣は左大脳後部病変であったことから, 成人例での損傷部位と流暢性に関する対応関係が, 小児失語症例においても認められるのではないかと思われた.
3 0 0 0 OA 「完璧」を目指す選択と評価のはざまで─専業主婦の母親の子育て観を中心に─
- 著者
- 吉本 文子
- 出版者
- 共栄大学
- 雑誌
- 共栄大学研究論集 = The Journal of Kyoei University (ISSN:13480596)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.99-113, 2019-03-31
"本稿は,「完璧」を求めるミドルクラスの母親の子育て観・その背景について,実態調査をもとに考察したものである。調査方法は,幼稚園・幼児教室に子どもを通わせている母親へのアンケート調査とインタビュー調査である。「完璧」を求める母親は,目の前の子どもの姿に立脚した子育ての目標ではなく,外部にある目標から選択し,それに向かって邁進している。そして母親自身,子育ての評価を自分への評価に重ねている。母親は,他者を排除し,自分の世界に閉じこもり,不安を抱えている。その不安を回避するために「完璧」に向かっている。このような母親の行動には母親の社会経験が影響している。そして自らのキャリアを中断していることに,母親自身が葛藤していることを示した。"
3 0 0 0 深層予測学習を用いたロボット動作の複合生成
- 著者
- 鈴木 彼方 伊藤 洋 山田 竜郎 加瀬 敬唯 尾形 哲也
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.9, pp.772-777, 2022 (Released:2022-11-18)
- 参考文献数
- 26
3 0 0 0 OA 日本初のベンゼン精留装置と合成染料の歴史
- 著者
- 吉留 勲
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.8-11, 2018-01-20 (Released:2019-01-01)
- 参考文献数
- 4
1856年に合成染料が世界で初めて作られ,日本にも輸入されるようになったが,第一次世界大戦の勃発により,染料の輸入が途絶えてしまう。この染色業界の危機を救うべく,由良浅次郎は合成染料の原料であるアニリン合成の工業化に取組んだ。しかし,日本の機械工業は未熟だったため,独学で設計を行いながらのベンゼン精留装置の完成であった。これにより染色業界の窮地を打開し,我が国の合成染料工業を切り開いたのである。
3 0 0 0 関東自動車株式会社四十年史
- 出版者
- 関東自動車
- 巻号頁・発行日
- 1967
- 著者
- KAZUHIRO KAWACHI
- 出版者
- Japan Association for Nilo-Ethiopian Studies
- 雑誌
- Nilo-Ethiopian Studies (ISSN:1340329X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.27, pp.27.br01, 2022 (Released:2022-10-28)
- 参考文献数
- 18
3 0 0 0 OA 聖カスバート崇拝と『リンディスファーン福音書』の製作
- 著者
- 白井 直美 遠山 茂樹
- 出版者
- 東北公益文科大学
- 雑誌
- 東北公益文科大学総合研究論集 : forum21 (ISSN:18806570)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.A113-A136, 2004-05-30
The Lindisfarne Gospels is one of the masterpiece of the manuscripts made in medieval England. The Book is thought to have been made at the monastery of Lindisfarne in the kingdom of Northumbria. Eadfrith, the bishop of Lindisfarne (d.721), wrote and illuminated this Gospels with splendid skills which he might had studied in Ireland. And he made this Gospels under the influence of cultures from Irish and Mediterranean area. It is almost certain that the Gospels have been made for God and Cuthbert in the early 8th century. The reason why this Gospels have been made connects closely with the birth and expansion of the cult of St Cuthbert. And Eadfrith undertook this work to promote the Cuthbert's cult. After the birth of his cult, the Lindisfarne monastery needed a lot of fame in oder to establish the status as the leader of Northumbrian church. For this reason, Eadfrith bid the Lindisfarne monks together, Bede put the Life of St Cuthbert, and Eadfrith made this Gospels by himself. The making of the Lindisfarne Gospels must be considered under this historical context, and it is evident that the making of this Gospels constituted a very distinct landmark in the history of the Lindisfarne community and St Cuthbert's cult.
3 0 0 0 OA 聖カスバート崇拝の発生に関する一考察 : 二人の聖人とノーサンブリア王権
- 著者
- 白井 直美 遠山 茂樹
- 出版者
- 東北公益文科大学
- 雑誌
- 東北公益文科大学総合研究論集 : forum21 (ISSN:18806570)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.CXXI-CXXXIX, 2003-12-15
Cuthbert, a bishop of Lindisfarne, was one of the most important saint in the seventh century and a key figure in the ecclesiastical and political context of Northumbria. He was venerated for the christian virtues and the merit of faith. According to the decision of the synod at Whitby in 664, he led the community of Lindisfarne to accept the Roman Catholic rule and he consecrated as bishop of Lindisfarne in 685. After his death, his community enshrined him and vigorously promoted his cult in Lindisfarne opposed to Wilfrid's threat. Wilfrid, who was also seen as saint, ruled the Northumbrian church and had a lot of landed possessions and ecclesiastical powers, but he quarrelled with kings to expel twice. Through the development of the cult, the close connection was established between the community of Lindisfarne and Northumbrian royal family. Both of them had been bothered by Wilfrid, the community was eager for protections of the king and the king intended to set up Cuthbert as rival saint against Wilfrid. It was essential for them to collaborate each other. This connection prevented Wilfrid restoring his authority. As a result, the cult of Cuthbert could enhance the royal power with increasing the authority of Lindisfarne.
3 0 0 0 OA Global Warming Effect and Adaptation for a Flooding Event at Motsukisamu River in Sapporo
- 著者
- Yuka Kanamori Masaru Inatsu Ryoichi Tsurumaki Naoki Matsuoka Tsuyoshi Hoshino Tomohito J. Yamada
- 出版者
- 公益社団法人 日本気象学会
- 雑誌
- SOLA (ISSN:13496476)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.249-253, 2022 (Released:2022-11-26)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
A set of hydrological experiments for a flooding event on 11 September 2014 at Motsukisamu River in Sapporo were performed. Dynamical downscaling to 5-km resolution of a large-ensemble global simulation allowed us to estimate that a 99%-tile hourly precipitation in Sapporo would increase by 70% in a future climate, when the global-mean temperature increases by 4 K compared with the present climate. After developing a three-tank model of which parameters were optimized on the basis of the in-situ observation at the Motsukisamu River during the event period, the model was forced by hypothetical hyetographs of the event that would occur under the future climate. The results of this experiment suggested that the peak flow rate would increase by 75%. However, it was also revealed that an upstream aqueduct tunnel, just completed in autumn 2021, would effectively reduce the peak flow rate and mitigate the flooding risk even in extreme precipitation under the future climate.
3 0 0 0 OA 脱共同体社会における民俗宗教のダイナミズム : タイ華人宗教の動態からみる
- 著者
- 翁 康健
- 出版者
- 北海道大学大学院文学院
- 雑誌
- 研究論集 (ISSN:24352799)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.197-216, 2022-01-31
本稿は,民俗宗教研究と華僑華人研究の分野に位置付けられ,タイの社会的・宗教的文脈から,タイの華人宗教の動態を把握したうえで,脱共同体社会における民俗宗教のダイナミズムを見出すことをめざす。具体的には,民俗宗教はいかに社会の産業化・都市化に対応できるのかを考察する。そこで,本稿はタイにおける華人宗教の動態を取り上げる。タイにおいては,産業化・都市化への対応として,宗教実践に新しい現象が現れている。その中で,華人系以外のタイ人でも華人宗教施設を訪ねることが多くある。こういった華人宗教は,血縁,地縁に基づく華人社会を越え,タイの都市化・産業化社会に対応していると考えてよいだろう。では,そういった華人宗教は,タイの都市化・産業化に対してどのように対応しているのか。またどのような社会的意味を持っているのか。その問いに対して,本稿は華人系以外のタイ人も普遍的に実践している「ゲイ・ビーチョン」(厄払いの儀),「ギンゼイ(齋)」(ベジタリアン・フェスティバル)という2つの華人宗教の儀礼に焦点を当てた。その結果,都市化・産業化への対応として,ゲイ・ビーチョンは100バーツ(約350円)の冊子を購入することで,簡単に厄払いの儀を行うことが可能となっている。また,齋料理を食べて過ごすギンゼイは健康のためだけのものではなく,個人の修養として取り上げられる。このように,「ゲイ・ビーチョン」と「ギンゼイ」という華人宗教儀礼は,華人のエスニシティ,および血縁,地縁を越えて,消費パッケージ化および,禁欲的な修養によって,産業化・都市化社会における宗教儀礼実践の個人主義化に対応しているとみられる。そして,タイの華人宗教のような脱共同体的な民俗宗教は,共同体に依存していなく,かつ都市生活様式への個人実践に対応できることにより,ホスト社会に広く受け入れられることが可能となると考えられる。
3 0 0 0 OA 世界的研究に基づける日本太古史
3 0 0 0 OA 痛みの客観的評価とQOL
- 著者
- 髙橋 直人 笠原 諭 矢吹 省司
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.8, pp.596-603, 2016-08-18 (Released:2016-09-16)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2 1
疼痛は主観的なものであり,客観的に評価することは非常に困難である.しかし,痛みの治療を行ううえでは患者の痛みをできるだけ客観的に評価し,分析する必要がある.本稿では,痛みの強さ,痛みの心理社会的因子,および痛みによる活動性,各々の評価における代表的な評価法を解説し,実際の症例の評価を提示した.しかし,現時点ではまだ痛みに対する客観的評価が十分に確立されていない.
3 0 0 0 OA 大地表面の異常帯電:大地震の前兆? —江戸のエレキテルと地震窮理の光芒—
- 著者
- 榎本 祐嗣
- 出版者
- 公益社団法人 日本表面科学会
- 雑誌
- 表面科学 (ISSN:03885321)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.56-61, 2002-01-10 (Released:2009-02-14)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 2 1
Electromagnetic grand anomalies prior to large earthquake occurrence have been paid attention especially after the 1995 Hyogo-ken Nanbu earthquake, though there is much of the debate whether the grand electromagnetic anomalies rest on sound scientific bases or not. Recent laboratory experiments conduced by Ikeya and his group using a Van de Graaff electrostatic generator suggested that such anomalies should be attributed to electrification of the ground level. In this “popular science” note, similar pre-seismic magnetic anomaly that happened at Edo age about 150 years ago is highlighted. Ansei-kenmon-shi published in 1856 noted that at the time about 2 h before destructive Ansei-Edo earth-quake in 1855, a natural magnetic stone at the Ohsumi's spectacle shop in Asakusa, Edo (Tokyo) dropped some iron nails, which had been attached to it. This observation led to the invention of a magnetic seismo-scope for prediction of earthquake occurrence. It is of interest to note that a scientist of ‘elektriciteit (electricity)’ at Edo-age, Sohkichi Hashimoto (1743−1836) had already demonstrated about 190 years ago that electrification of a natural magnetic stone was able to drop iron nails attached to it. The electromagnetic anomalies that accompanied to the Ansei-Edo earthquake were discussed in terms of the ‘Evaluation of proposed earthquake precursors’ given by American Geophysical Union.
3 0 0 0 OA 病原菌を手懐ける技法――近代日本における結核の発病予防
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究 (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.299, pp.274, 2021 (Released:2022-08-01)
3 0 0 0 OA 特集論文 言葉とつながれないこと
- 著者
- 村上 靖彦
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.21-27, 2021 (Released:2022-04-20)
3 0 0 0 OA 高校野球投手における形態及び体組成の特徴 -球速・競技レベルとの関連に着目して-
- 著者
- 木村 征太郎 笠原 政志 山本 利春
- 出版者
- 日本トレーニング指導学会
- 雑誌
- 日本トレーニング指導学会大会プログラム・抄録集 第9回日本トレーニング指導学会大会 (ISSN:24337773)
- 巻号頁・発行日
- pp.O07, 2020 (Released:2022-04-22)
【目的】高校野球投手の競技力向上に向けた増量に関する情報が散見する中で、形態や体 組成を詳細に分析した報告は少ない。そこで本研究は高校野球投手の球速と競技レベルに 着目し、高校野球投手の形態及び体組成の特徴について明らかにすることを目的とした。 【方法】本研究における測定は各高校野球部のグラウンドまたは屋内施設にて実施した。 測定対象は全国の高校野球投手120 名(年齢:16.2±0.7 歳、身長:173.6±5.1cm、体 重:68.9±10.2kg)とした。測定項目は体組成(TANITA 社製MC-780A-N)、周径囲(ISAK 身 体計測方法)とした。さらにアンケート調査を行い、プロフィール、プレースタイル(投 球タイプ、最高投球速度など)について回答を得た。分析方法は、球速はアンケートから 得られた最高投球速度とし、高速群23 名(130km/h 以上)、中速群26 名(120km/h 以 上)、低速群37 名(120km/h 未満)に分類した。また、競技レベルをエリート群28 名(過 去5 年以内に春夏含め複数回甲子園出場校)と非エリート群18 名(都道府県予選敗退 校)に分類した。各群における体組成と周径囲の差に対する分析は、球速別の比較は一元 配置分散分析を行い、Tukey のHSD 法により多重比較検定を行った。競技レベル別の比較 は対応のないt 検定を行った。いずれも有意確率は5%未満とした。 【結果】球速別からみた高校野球投手における形態では前腕、上腕以外の全ての項目にお いて高速群が低速群に比べて有意に高値を示した(p<0.05)。また、体組成では体重、ア ーム長、除脂肪量において高速群が低速群に比べて有意に高値を示した〔体重、アーム長 (p<0.05)、除脂肪量(p<0.01)〕。投手の軸脚とステップ脚の下肢周径囲を比較した結 果、両脚ともに高速群が低速群よりも有意に高値を示した[大腿両脚(p<0.01)、両脚下 腿(p<0.05)]。競技レベル別の体組成及び周径囲はエリート群が非エリート群よりも有 意に高値を示した〔身長、除脂肪量、腹囲、大腿、下腿(p<0.05)〕。 【考察】高速群およびエリート群における投手の形態及び体組成の特徴については、上肢 の周径囲に差はない一方で、体幹および下肢の周径囲と除脂肪量が有意に高値を示した。 このことから、球速を向上させるためには、体幹および下肢における筋量の増加が必要で あることが示唆された。また、投手の軸脚とステップ脚については、一側有意性がなく、 両脚とも低速群よりも高速群の方が有意に高値を示し、球速向上のためには下肢全体の筋 量の増加が必要であることが示唆された。 【現場への提言】これまで高校野球投手の競技パフォーマンス向上に向けた増量の必要性 を示されていたが、本研究結果から球速向上や各大会上位へ勝ち進むための投手へのトレ ーニング指導の際には、主に筋量の増加と共に体幹や下肢を中心とした身体づくりをする 必要があると言える。なお、形態及び体組成の本研究結果は、高校野球投手に対して左右 共に下肢を鍛えることを支持する根拠となった。