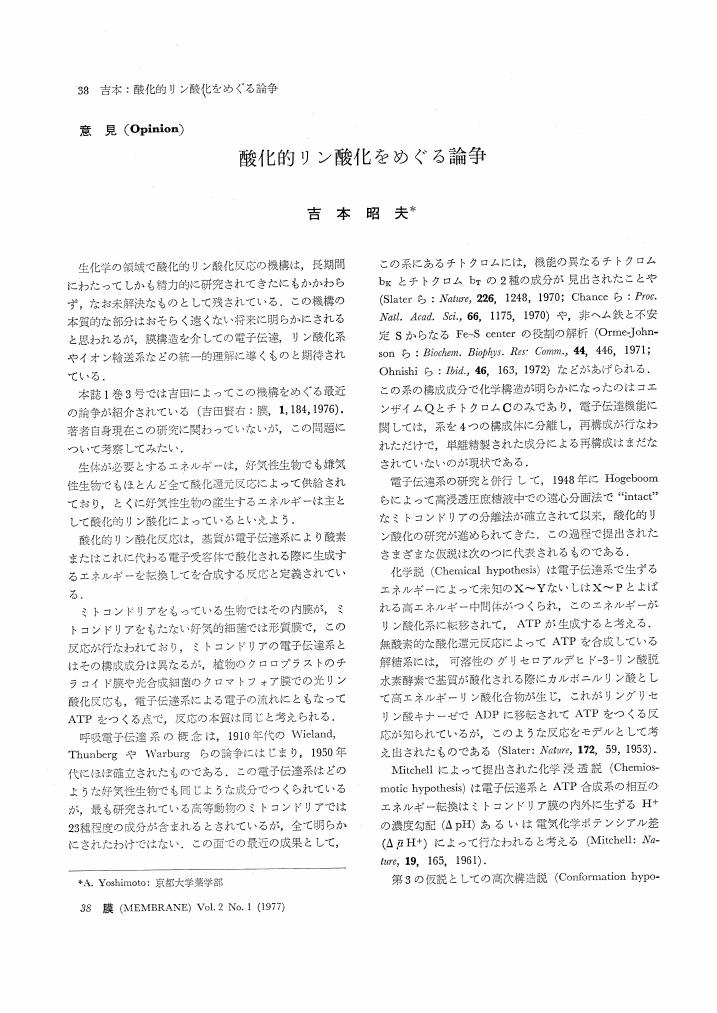3 0 0 0 OA 酸化的リン酸化をめぐる論争
- 著者
- 吉本 昭夫
- 出版者
- 日本膜学会
- 雑誌
- 膜 (ISSN:03851036)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.38-40, 1977-02-01 (Released:2010-10-21)
3 0 0 0 OA わが国における薬剤による有害事象に関する判例の検討:判例誌掲載例の分類
- 著者
- 江口 里加 加藤 正久 金子 絵里奈 草場 健司 吉川 学 山野 徹 瀬尾 隆 萩原 明人
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.135, no.3, pp.501-506, 2015 (Released:2015-03-01)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
Much of the damage to health caused by drugs could be prevented by appropriate care. A well-defined duty of care and further information are required for healthcare professionals. Although there are many litigation cases to use as references, neither the extent of the duty of care nor the obligation to explain medication according to the type of drug prescribed has yet been fully established. Thus, we systematically collected decided cases of adverse drug events, and assessed the degree of the duties of care and information. Specifically, we collected decided cases in which physicians, dentists, pharmacists, nurses, or hospitals had been sued. Data were derived from Bessatsu Jurist Iryo-kago Hanrei Hyakusen, Hanrei Jihou, and Hanrei Times from 1989 to November 2013, and information on precedents in the records of the Supreme Court of Japan from 2001 to November 2013. We analyzed the cases, and assessed the following according to the type of drug: (1) standards and explanations when dealing with drugs that were critical issues in litigation, and (2) the degree of the physician's or pharmacist's duties of care and information. In total, 126 cases were collected. The number of drug categories classified was 27, and 9 were considered of practical importance. After this systematic review, we found a trend in the degree of the required level of care and information on several drugs. With respect to duties of care and information, the gap between the required level and actual practice suggests that healthcare professionals must improve their care and explanations.
3 0 0 0 OA 潮干のつと
彩色摺狂歌絵本。「潮干のつと」とは「潮干狩りのみやげ」という意味。36種の貝と、初めと終わりに付した関連美人風俗図を、朱楽菅江(1740-99)と彼の率いる朱楽連の狂歌師たち38名が1名1首ずつ詠む。画工は喜多川歌麿(1753?-1806)。本書には波模様や「貝合せ図」の障子に映る手拭いの影の有無等、摺りが異なるものが数種存在するが、この本には波模様、影ともに無い。本書は安永から寛政にかけて蔦屋重三郎が刊行した狂歌絵本の代表的なもので、空摺りや雲母などが施され、当時の最高水準の技術を駆使して制作された華美で贅沢な作品である。(2019.9最終更新)
3 0 0 0 OA スパイナルドレナージ併用の胸部ステントグラフト内挿術後に急性硬膜下血腫を生じた1例
- 著者
- 後藤 徹 田崎 淳一 東谷 暢也 今井 逸雄 塩井 哲雄 丸井 晃 坂田 隆造 舟木 健史 堀川 恭平 安部倉 友 宮本 享 木村 剛
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.465-470, 2013 (Released:2014-09-13)
- 参考文献数
- 7
症例は77歳, 女性. 脳梗塞の既往あり, 胸部大動脈瘤 (70mm) を指摘され当院受診した. 手術ハイリスクのためステントグラフト内挿術 (thoracic endovascular aortic repair ; TEVAR) を施行した. 術前評価にてAdamkiewicz動脈がTEVARに伴い閉塞することが明らかであり, スパイナルドレナージ (cerebrospinal fluid drainage ; CSFD) を挿入したうえで, TEVARを施行した. 外腸骨動脈の石灰化および狭窄のため大腿動脈からのTEVAR用シース挿入困難であり, 後腹膜アプローチにて総腸骨動脈からシースを挿入し, TAGステントグラフトを留置した. シース抜去時に血管壁を損傷したため, 術中から輸血を要し, 外科的に修復して閉腹した. 術後, 播種性血管内凝固症候群 (disseminated intravascular coagulation syndrome ; DIC) となり輸血を要したが, 翌日に意識混濁と右共同偏視を認め, CTで右急性硬膜下血腫を認めたため, 緊急開頭血腫除去術を施行した. 開頭術後は頭部再出血および出血による神経学的後遺症は認めず, 輸血治療によりDICは改善した. TEVAR施行後にendoleakは認めず, 術後47日目に転院となった. TEVARによる重篤な合併症の1つに対麻痺があるが, その予防目的にCSFDは有用な手段である. 急性硬膜下血腫はCSFDの予後にかかわる重大な合併症であるが, TEVARにおけるCSFD後の急性硬膜下血腫の頻度は報告されていない. 今回われわれは, 早期発見と他科との連携により後遺症を残さず救命に成功した症例を経験したので報告する.
- 著者
- 馬場 正美 洲崎 英子 平良 梢 伊藤 友里 加地 ひかり 岡田 温
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.291-299, 2020-07-25 (Released:2020-09-04)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
目的:コラーゲンペプチドが骨格筋量に影響を及ぼすかどうかを検討するため,回復期リハビリテーション病棟において,コラーゲンペプチド含有経口栄養補助食品摂取群(以下 介入群)と非摂取群(以下 コントロール群)の間に,体組成,身体計測値,Activities of Daily Living,食事摂取栄養量に違いがあるかどうかを検討した.方法:2018年6月1日~2018年8月31日までの間に骨折または脳卒中で回復期リハ病棟に入院した65歳以上の患者19名を対象とし,介入群にはコラーゲンペプチド10ℊを含有するONSを摂取させた.結果:患者の平均年齢は介入群が78.3±7.0歳,コントロール群が75.2±5.5歳,男女比は介入群が男性3名,女性7名,コントロール群が男性2名,女性7名であり,患者の在院日数は介入群が72.9±29.7日,コントロール群が69.7±15.4日であった.介入前後におけるFFMの変化量は,介入群が+0.55±1.4 kg,コントロール群が-1.67±2.2 kg,SMMの変化量は介入群が+0.29±0.8 kg,コントロール群が-0.96±1.3 kg,SMIの変化量は介入群が+0.11±0.3 kg/m2,コントロール群が-0.31±0.4 kg/m2であり,FFM,SMM,SMIのいずれの項目においてもコントロール群に比べて介入群の変化量は有意に大きかった.また,介入群のSMIは1日あたり0.002±0.03 kg/m2増加した.結論:コラーゲンペプチドの経口摂取は,回復期リハビリテーション病棟患者の骨格筋量を増加させる可能性が示唆された.
3 0 0 0 OA 食品機能性成分としてのスフィンゴ脂質の消化と吸収
- 著者
- 菅原 達也
- 出版者
- Japan Society of Nutrition and Food Science
- 雑誌
- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.177-183, 2013 (Released:2013-08-16)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 3 2
スフィンゴ脂質は, 真核生物の細胞膜構成成分の一つであり, 細胞の分化やアポトーシスなどの生命現象に深く関わっていることが知られている。近年, 食品機能成分としても注目されつつあり, とくに皮膚バリア向上作用が期待されている。したがって, 経口摂取されたスフィンゴ脂質の消化と吸収の機構を明らかにすることは, その食品機能性を理解する上でも重要といえる。グルコシルセラミドやスフィンゴミエリンなどのスフィンゴ脂質は, 小腸内で消化を受け, その構成要素であるスフィンゴイド塩基にまで加水分解された後に小腸上皮細胞に取り込まれる。しかし, その分解効率は低く, 吸収率も低い。スフィンゴシンと比べて, それ以外の化学構造のスフィンゴイド塩基はP-糖タンパク質による排出を受けやすいため, 吸収はさらに低いことが示唆されている。スフィンゴ脂質の有効利用のためにも, その選択的吸収機構の詳細について, 今後明らかにされる必要がある。
3 0 0 0 OA プロテアーゼインヒビターの設計と新機能
- 著者
- 濱田 芳男 木曽 良明
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.12, pp.796-803, 2003-12-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2 2
- 著者
- Chun-Ka Wong Hayes Kam-Hei Luk Wing-Hon Lai Yee-Man Lau Ricky Ruiqi Zhang Antonio Cheuk-Pui Wong George Chi-Shing Lo Kwok-Hung Chan Ivan Fan-Ngai Hung Hung-Fat Tse Patrick Chiu-Yat Woo Susanna Kar-Pui Lau Chung-Wah Siu
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-20-0881, (Released:2020-09-26)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 33
Background:SARS-CoV-2 infection is associated with myocardial injury, but there is a paucity of experimental platforms for the condition.Methods and Results:Human-induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes (hiPSC-CMs) infected by SARS-CoV-2 for 3 days ceased beating and exhibited cytopathogenic changes with reduced viability. Active viral replication was evidenced by an increase in supernatant SARS-CoV-2 and the presence of SARS-CoV-2 nucleocaspid protein within hiPSC-CMs. Expressions of BNP, CXCL1, CXCL2, IL-6, IL-8 and TNF-α were upregulated, while ACE2 was downregulated.Conclusions:Our hiPSC-CM-based in-vitro SARS-CoV-2 myocarditis model recapitulated the cytopathogenic effects and cytokine/chemokine response. It could be exploited as a drug screening platform.
3 0 0 0 OA 再度発生した風しんの国内流行の背景と公衆衛生対策
- 著者
- 大石 和徳 佐藤 弘 多屋 馨子
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.140, no.7, pp.901-904, 2020-07-01 (Released:2020-07-01)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 6
Although rubella is usually a mild, febrile illness, and up to 50% of rubella infections are asymptomatic, congenital rubella syndrome (CRS) can occur in the developing fetus of a pregnant woman infected with rubella virus (RV) in early pregnancy. After a rubella outbreak from early 2012 to late 2013 in Japan, another outbreak re-emerged from mid-2018 in the Tokyo metropolitan area and other large cities. In 2018, and up to epidemiological week (EW) 25 in 2019, more than 4000 rubella cases had been reported. Three CRS cases were also reported up to EW 24. Seroepidemiological surveys among Japanese residents indicated that the susceptible pocket to RV in male adults aged 30-50 years, as determined in 2013, remained unchanged in 2018. To reduce the number of male adults sensitive to RV, in early 2019, Japan's Ministry of Health, Labour and Welfare decided to implement routine immunization of male adults aged 40-57 years between 2019 and 2021. These male adults have been determined to have low anti-RV antibodies, and were therefore designated as the target population for this routine immunization (as category A). Although one-third of male patients with rubella reported in 2018 were in their 20 s and 30 s, these younger generations were not included in the target population for routine immunization against rubella, because they had already received a routine vaccination. Rubella vaccination is also required for male adults aged 20-40 years to diminish the susceptible pocket.
3 0 0 0 OA ディスポーザブルタオルを用いた部分清拭が高齢者の皮膚に与える影響
- 著者
- 石井 和美 中田 弘子 小林 宏光 川島 和代
- 出版者
- 日本看護技術学会
- 雑誌
- 日本看護技術学会誌 (ISSN:13495429)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.17-25, 2019 (Released:2019-04-20)
- 参考文献数
- 14
本研究の目的は, ディスポーザブルタオル (以下, ディスポタオル) を用いた部分清拭が高齢者の皮膚に与える影響を明らかにすることである. 地域在住の65~74歳の高齢者27名を対象に, ディスポタオルと綿タオルを用いて左右の前腕の清拭を実施し, 清拭前後の清浄度, 水分量, pH, 皮膚温を測定した. これらの客観的測定に加えて, タオルの使用感について清拭後に主観的に評価を行った. 結果はディスポタオルによる清拭後の皮膚清浄度は綿タオルと同等で弱酸性を保持していた. ディスポタオルの清拭後15分までの皮膚水分量は高く (P<0.01) , 一方で, ディスポタオルの方が清拭後の皮膚温の低下が大きかった (P<0.01) . 主観的評価ではディスポタオルの「やわらかさ」と「肌触り」に差がみられた (P<0.05) . これらの結果からディスポタオルの清拭においても拭き取り後の気化による熱損失が大きいため, 皮膚上の水分を十分に拭き取る必要があることが示唆された.
- 巻号頁・発行日
- 1945
3 0 0 0 OA 盛り場「千日前」の系譜
- 著者
- 加藤 政洋
- 出版者
- 地理科学学会
- 雑誌
- 地理科学 (ISSN:02864886)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.71-87, 1997-04-28 (Released:2017-04-20)
- 参考文献数
- 76
Recently, we can find many studies which insist on appreciating the concept of place in a contextual way not only in the English speaking world but also in Japan. In this renewed concept, place is contended to be humanly (socially) constructed with spatial practices, We (the user) make sense of place by the spatial practices, through which the user creates his own behavior and acts place-ballet. In the socio-spatial studies, Sack (1988) and Shields (1991), for example, advocate this point of view and contend that understanding of many factors operating in the place-making, the invention of place, and the construct of place, should be a primary theme in this discipline. Drawing attention to the conceptual framework of 'genealogy of place', this paper aims at describing the historical transition of amusement quarters (Sakari-ba) of Osaka Sennichimae. Osaka Sennichimae is one of Sakari-ba, where marginality and 'carnivalesque' dominated and both ephemeral and temporal logic was considered as those alternative to everyday rife working. Originally, Sennichimae was a grave yard on the margin of built-up areas of Osaka city in Edo era. After Meiji Restoration, this grave yard changed to an amusement site at first, and then, this site gradually transferred to Sakari-ba. Therefore, the name of this place, Sennichimae, had evoked people with both horror and pre-modern 'Edo' nostalgia after redeveloping from the grave yard into Sakari-ba. In the case of Sakari-ba Sennichimae, this paper examine the very constructed place as a genealogy interwovened with the historical place-images, the interventions of political powers, the act of show-planners (Yashi), and the spatial practices of the walkers. The development of Sennichimae as Sakari-ba is outlined as follow. In the early Meiji period, Sennichimae changed its landuse from grave yard to amusement site. This change might suggest two aspects. Firstly, the place as grave yard was cleared out for the sanitary reason. Secondly, at the same fane, the government of Osaka prefecture carried out the project of improvement in the old section of the city. Neverthless, the former image of grave yard influenced contingently the proceeding devlopment of amusement quarter of Sennichimae. Introducing many of new leisure attractions, especially cinema, this place was gradually characterized as Sakari-ba, and created the typical landscape of amusement site, and, in the 1920's, Sennichimae attracted people who loved to walk around as flaneur, and enjoyed their practice of walking, seeing, and being in the space of Sakari-ba with the mass.
3 0 0 0 連歌作品と古注釈の成立について : 天文年間の宗牧注を起点として
- 著者
- 浅井 美峰
- 出版者
- 明星大学日野校
- 雑誌
- 明星大学研究紀要. 人文学部・日本文化学科 (ISSN:21862818)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.41-50, 2020
3 0 0 0 IR 大学生における化粧行動と主観的幸福感に関する日韓比較研究
- 著者
- 金 聡希 大坊 郁夫 Kim Chongfi Daibo Ikuo
- 出版者
- 大阪大学大学院人間科学研究科対人社会心理学研究室
- 雑誌
- 対人社会心理学研究 (ISSN:13462857)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.89-100, 2011-03
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA 天ぷら衣に酢を添加した場合の衣の評価
- 著者
- 原 知子 加藤 美香
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成14年度日本調理科学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.101, 2002 (Released:2003-04-02)
天ぷら衣に重曹やしょうが汁を添加することによって軽い衣に揚げあがることはよく知られているが、「酢」を添加した場合の影響については記述は少ない。そこで、身近な調味料である米酢を用いて、天ぷら衣に添加してみたところ、重曹と同様に、官能評価において「さくさく度」「軽さ」の向上が認められた。ただし、米酢の場合には添加量が粉の1/6(酢容量ml/粉重量g)程度でも酢自体の味が衣に反映されてくる。衣の生地の状態については、酢を添加することによって、衣の「流れやすさ」が有意に大きくなり、その結果、揚げ種に衣をつける際にも薄くつきやすいというメリットがあると考えられた。
- 著者
- 上野 ふき
- 出版者
- 名古屋大学大学院文学研究科教育研究推進室
- 雑誌
- メタプティヒアカ : 名古屋大学大学院文学研究科教育研究推進室年報
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.161-165, 2008-03-31
3 0 0 0 OA リリスボット―生活支援ロボット―の構想
3 0 0 0 OA シンクタンクの役割と影響―国政における事業仕分けの採用過程―
- 著者
- 飯塚 俊太郎 堤 麻衣
- 出版者
- 日本公共政策学会
- 雑誌
- 公共政策研究 (ISSN:21865868)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.104-115, 2015-12-25 (Released:2019-06-08)
- 参考文献数
- 74
本稿の目的は,「構想日本」というシンクタンクが,自ら考案した「事業仕分け」の国政における採用を実現した過程を解明することを通じ,シンクタンクの役割や影響を論じることにある。2009年の民主党を中心とする連立政権への政権交代を象徴する出来事となった事業仕分けは,構想日本が発案し,その全面的関与のもとに2002年から全国の地方自治体で実施を積み重ねてきた手法である。それは,政権交代後間もなく,内閣府に設置された行政刷新会議を司令塔とする官邸主導のプロジェクトとして,国政にて実施される運びとなった。本稿は,シンクタンクの役割と影響に着目して,事業仕分けが国政にて採用された過程を分析する。シンクタンクが実際の政策過程に及ぼした役割や影響の具体的考察は,それ自体稀有と言える。その上で,以下のような示唆を得る。従来のシンクタンク論の通説的見解では,自民党長期政権とそれに伴う行政・官僚主導の政策形成の在り方が日本のシンクタンクの脆弱性や未熟性の要因として指摘されてきた。それに対し,本稿の分析は,政権交代という出来事を機に,一シンクタンクの構想であった事業仕分けが国政の中枢にて採用された事例を提示する。また,そうした事象が起きた背景として,政権交代が契機であったことはもとより,1990年代以降の政治改革・行政改革を通じた制度的な変化により内閣機能の強化や官邸主導への流れが醸成されてきたという背景を仮説的に示す。今後の日本のシンクタンク研究では,このような政治環境の変動を,シンクタンクを取り巻く環境の変容として考慮する必要があることが示唆される。
3 0 0 0 OA 「日本文化」における音楽心理療法の適応:シンポジウムからの考察
- 著者
- 猪狩 裕史
3 0 0 0 OA 運動障害性構音障害の機能回復
- 著者
- 白坂 康俊
- 出版者
- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.331-335, 2002-07-20 (Released:2010-06-22)
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 1 1
運動障害性構音障害の機能回復において, 最も重要な要因の一つは, 発現機序の正確な特定である.しかし, これまでのような, 聴覚印象的な評価と各発声発語器官の粗大運動レベルの機能評価を結びつける方法では十分に特定できるとはいいがたく, また具体的な訓練プログラムも立てにくかった.今回, 日本語の各音素を実現するために必要な構音動作的要素を抽出し, この要素ごとに運動機能低下を評価する, いわば調音音声学的評価方法を提唱した.同時に, この評価方法で, 構音動作的レベルと各発声発語器官の粗大運動レベルの運動機能低下の関連性を評価できることも示した.さらに, 構音動作的要素の問題点に対し, 運動障害性構音障害のタイプ別の特徴に配慮した訓練アプローチ, いわば運動学的アプローチを適用することの重要性を提言した.