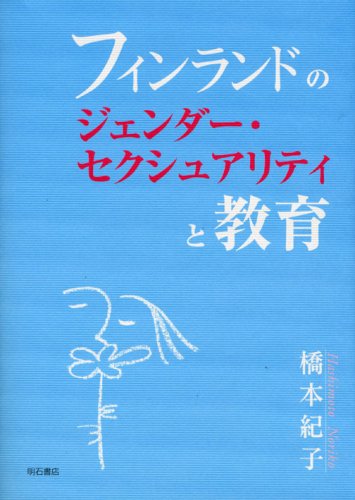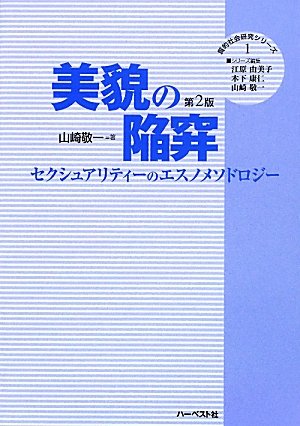3 0 0 0 OA 「風車は環境に優しいか?~自然保護との両立~」
- 著者
- 松田 裕之
- 出版者
- 東京大学生産技術研究所
- 雑誌
- 生産研究 (ISSN:0037105X)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.5, pp.447-452, 2015-09-01 (Released:2015-10-05)
3 0 0 0 OA 信号付横断歩道における歩行者クリアランス時間設定方法の日米比較
- 著者
- 井料 美帆
- 出版者
- 東京大学生産技術研究所
- 雑誌
- 生産研究 (ISSN:0037105X)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.345-349, 2014-07-01 (Released:2014-09-27)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
現在の日本の歩行者青点滅表示は,横断歩道上の歩行者が横断歩道を渡りきるのに必要な時間を確保していない.にも関わらず,多くの歩行者が青点滅開始後に横断歩道に駆け込み,青点滅終了時までに渡り切れないという安全上の問題がある.本稿では,日米の歩行者現示設定方式の比較を通じ,日本の歩行者赤・車両青時間の存在が,左折需要の小さい横断歩道における青点滅開始後の歩行者の横断を助長している可能性を示した.また,米国の歩行者現示設定方式を適用することで,青点滅後の残留歩行者を減らしつつ,サイクル長を減少させられる例を示した.
3 0 0 0 IR 物語としての連作短歌 : 俵万智「八月の朝」論
- 著者
- 朱 衛紅 Zhu Weihong
- 出版者
- 筑波大学比較・理論文学会
- 雑誌
- 文学研究論集 (ISSN:09158944)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.1-16, 2010-02-28
3 0 0 0 日本女装史 : 着装分解
- 出版者
- 高林輝雄
- 巻号頁・発行日
- 1978
- 著者
- 本山 功 板木 拓也
- 出版者
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター
- 雑誌
- 地質調査研究報告 (ISSN:13464272)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.1-4, 2019
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA ケアが分配されるとき
- 著者
- 田中 耕一郎
- 出版者
- 北星学園大学
- 雑誌
- 北星学園大学社会福祉学部北星論集 (ISSN:13426958)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.61-73, 2013-03
3 0 0 0 OA ストレス反応とその脳内機構
- 著者
- 尾仲 達史
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.126, no.3, pp.170-173, 2005 (Released:2005-11-01)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 2 4
キャノンとセリエにより医学の世界にストレスという言葉が持ちこまれた.キャノンは,ストレス刺激に対応した多様な反応が生体におきることとこの反応に交感神経系-副腎髄質ホルモン分泌が必須であることを示した.セリエは,刺激によらず非特異的な反応が生体におきることとこの反応に視床下部-下垂体前葉ACTH-副腎皮質ホルモンが必須であることを示した.近年になり,「ストレス」が多くの疾患の少なくとも増悪因子となることが様々な疫学的な調査により示されるようになった.さらに,ストレス刺激によりある程度共通した神経系が活性化されることが明らかになりつつある.このストレス時に活性化される神経系の代表が,延髄ノルアドレナリン/PrRPニューロン系である.この延髄ノルアドレナリン/PrRPニューロン系は恐怖刺激,痛み刺激による反応に重要であることが示されている.一方,新奇環境曝露によるストレス反応,あるいは,モルヒネ禁断のような刺激は,延髄ノルアドレナリンニューロンに依存しないことも示されている.今後,どのストレス神経系を活性化させるかによりストレスの分類分けが行われていくと思われる.
3 0 0 0 OA J・バトラーのジェンダー・パフォーマティヴィティとそのもうひとつの系譜
- 著者
- 藤高 和輝
- 出版者
- 国際基督教大学ジェンダー研究センター
- 雑誌
- Gender and Sexuality (ISSN:18804764)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.183-204, 2017-03-31
Gender performativity is the most famous and influential theory in Judith Butler. It questioned the sex/ gender distinction which some feminists took for granted at that time when Gender Trouble (1990) was published. This distinction regarded sex as the natural category on the one hand, gender as the cultural expression of sex on the other hand. It means naturalizing the dualistic representation of gender. On the contrary, Butler's performative theory suggested that sex is not a natural category, but is a fiction which is constructed by repeating gender performances. Through denaturalizing gender, her theory criticizes the representation of gender/ sexual minorities as "unnatural" and "abnormal," and seeks to theorize the way to make their survival possible. This paper examines how gender performativity was theorized from the 1980s to Gender Trouble. Interestingly, her performative theory cannot be reduced to speech act theory, but it was also formed in relation to other theories; feminist/ queer theory and performance theory. Indeed, in her article "Performative Act and Gender Constitution" (1988) in which she referred to "performative" at first, Butler started from Simone de Beauvoir's text, The Second Sex, and then reread Beauvoir's idea of "gender as act" as "social performance" in performance theory. Moreover, she extended Beauvoir's argument of denaturalizing sex, referring to Gayle Rubin's study of kinship, Monique Wittig's theory of sex, and Esther Newton's analysis of Drag Queen. Thus, her performative theory is found not only in the context of speech act theory, but also in contexts of feminist/ queer theory and performance theory. From this genealogical perspective, this article seeks to rethink gender performativity.
- 著者
- 寺田努 岡崎辰彦 塚本昌彦
- 雑誌
- マルチメディア、分散協調とモバイルシンポジウム2014論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, pp.1386-1393, 2014-07-02
- 著者
- 七沢 潔
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.66-92, 2014-02
- 著者
- 田邊 翔太 矢野 彰三
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.5, pp.924-931, 2017-01-31 (Released:2017-03-18)
- 参考文献数
- 28
中山間地域の中核病院におけるHAD 発症率とその危険因子を検討することを目的に公立邑智病院総合診療科の新規入院患者について入院時と退院時のADL を比較し,HAD発症率を調査した。また,入院時の栄養状態,認知機能,血液検査,介護認定の有無,在院期間を調査し,HAD 発症との関連を統計学的に解析した。 その結果,53例中8 例(15%)にHAD 発症を認めた。HAD 発症例は有意に高齢で,入院時のADL・栄養状態・認知機能が低く,血清アルブミンが低値であった。多重ロジスティック回帰分析から,栄養状態と認知機能がHAD 発症の独立した危険因子であることが示された。また,HAD 発症群は全例が介護認定を受けていた。 公立邑智病院におけるHAD 発症率は15%で,諸外国の既報に比して低値であった。認知機能と栄養状態は,年齢や入院前のADL と独立してHAD 発症の危険因子と考えられた。
3 0 0 0 OA 幼少期ストレス負荷による情動行動の変化
- 著者
- 菊水 健史 茂木 一孝
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.149, no.2, pp.66-71, 2017 (Released:2017-02-01)
- 参考文献数
- 30
動物,特にヒトを含む哺乳類における子の発達で最も特徴的な点は,発生初期を母親の胎内で過ごし,出生後においても哺乳行動を中心とした母子間のつながりが強いことである.この期間に子が母親から受ける様々な刺激は,身体発達に多大なる影響を与え,個体の内分泌系や行動様式に長期的な変化を引き起こす.ゆえに,哺乳類の発達期の社会環境は,個体の獲得するエピジェネティックな変化の解明において,最も重要な要素だといえる.このような発達期の社会的要素の一つとして,離乳が挙げられる.これまで離乳の早期化が,仔マウスの成長後の不安行動の増加,情動反応を変化させること,また早期に離乳された雌マウスでは,自分が母親になった際にも通常に離乳された雌マウスに比べ,排泄を促すためや母乳を飲むよう促すための仔をなめる行動の時間が短くなることが明らかとなった.そこで本稿では,早期離乳による情動行動の変化に加え,その神経機能の変化に関し,特に前頭葉に注目した最近の知見を紹介する.C57BL/6マウスを用い,生後15日で親から離乳する早期離乳を施し,成長後に高架式十字迷路試験による不安行動評価,恐怖条件付け試験による恐怖記憶の消去抵抗性評価を行った.そして,前頭葉における脳由来神経栄養因子(BDNF)タンパク質発現測定,各プロモーター由来BDNF mRNA発現量測定を行い,その背景となる分子メカニズム同定を試みた.その結果,恐怖条件付けを受けた早期離乳マウスでは消去学習過程における消去の抵抗性が増加し,前頭葉のBDNF III mRNA及びBDNFタンパク質が低下した.さらに,これらの間には負の相関もみられたことから,早期離乳による恐怖記憶の消去抵抗性には,前頭葉におけるBDNF III mRNAの発現低下を介したBDNF作用の減弱が関わっていることが予想された.これらの知見は,幼少期の早期の母子分離が永続的な前頭葉のBDNFを介した機能不全を導くことを示唆し,早期離乳マウスがヒトにおける前頭葉の機能不全のモデルとなる可能性を示した.
- 著者
- 佐々木 暢子 京極 重智 ササキ ミチコ キョウゴク シゲトモ Sasaki Michiko Kyogoku Shigetomo
- 出版者
- 大阪大学大学院人間科学研究科教育学系
- 雑誌
- 大阪大学教育学年報 (ISSN:13419595)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.17-30, 2014
本研究の目的は、大阪大学人間科学研究科・教育人間学研究分野を中心に教育と福祉の理論家と実践家によって行ってきた共同研究、「教育と福祉のドラマトゥルギー」のこれまでの研究成果と課題を考察することによって、今後の共同研究のあり方を展望することにある。その際、本共同研究の共通の観点として用いた「舞台」概念に着目し、その概念が持つ意味の射程を明らかにすることを目指した。そのためにまず、本共同研究の理論的基盤であるゴッフマン理論から見た「集まり」の輪郭を明らかにする。次いで、本共同研究の成果の一つを事例として、これまでの共同研究において曖昧なままであった「舞台」概念を四つの層に分類・整理し、「舞台」概念の再定義を行う。そこから、ゴッフマンが「集まり」とその外部の関係を考察の対象とはしていなかったのに対し、本共同研究では「舞台」間の関係を動的に捉えるとともに、物理的・可視的空間だけでなく、仮想的空間をも射程に収めるという点に特質があることを明らかにする。以上の考察から、今後の我々の共同研究の中で、様々な位相に属する「舞台」同士がどのように影響を与え合い、それらがどのように変容していくのかを具体的な事例の中から明らかにしていく必要があることを示す。This article discusses the objectives and results of our joint research, entitled "The Dramaturgy of Education and Welfare" focusing on "the stage." This constitutes a key concept of this study because of its originality and employability as an analytical concept. However, because the stage has not been fully considered in our studies, its use remains ambiguous. Therefore, we fi rst clarify the implications of "gathering" in Erving Goff man's "Dramaturgy", which forms our theoretical base. Originally, Goff man's primary concern was to reveal orders of gathering, so his "Dramaturgy" did not consider the relational aspect of gathering that is the relationship between a stage and the outside world. However, our study regards the gathering concept as possessing a dynamic relation with the outside world. Second, we extend and classify the stage concept into four categories ranging in density, from abstract to concrete, by using one case study. This categorization is termed "Multilayered Structure of Stage", a concept that spans not only the physical and visible spaces but also the virtual and imaginary. Finally, we indicate that the problem of this joint research is to clarify on the basis of particular cases how stages in their diff erent phases interact and transform.
3 0 0 0 5Gコアネットワーク向けアプリケーション処理連接基盤
- 著者
- 佐藤 友範 渡邊 大記 林 和輝 近藤 賢郎 寺岡 文男
- 雑誌
- 研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP) (ISSN:21888647)
- 巻号頁・発行日
- vol.2019-EIP-85, no.18, pp.1-8, 2019-09-12
第 5 世代移動通信方式 (5G) では超高信頼低遅延通信や大容量モバイル通信などの高機能な通信サービスが提供され,自動運転や高精細な拡張現実感 (AR) のようなサービスが普及すると考えられている.本稿はエッジサーバ,フォグサーバ,クラウドサーバを含むような 5G コアネットワークを 1 台の計算機のように見せる処理基盤として Application Function Chaining (AFC) を提案する.AFC は高精細 AR のようなアプリケーションを小機能(Application Function; AF) ごとに分割し,AF の連接によってアプリケーションを構成する.アプリケーションは Pub/Sub 方式または HTTP リクエストにより AFC を利用する.AFC 内ではアプリケーションメッセージ単位で AF が適用される.本稿では,プロトタイプ実装により AFC の基本性能を評価した.AFC の確立では AF の設置よりも AF の連接にかかる時間的オーバーヘッドが大きく,AFC 上でのデータ通信ではアプリケーションメッセージ長が10KB 以上の場合で 90% 以上の帯域使用率となった.
3 0 0 0 フィンランドのジェンダー・セクシュアリティと教育
- 著者
- 矢野 純
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.10, 2004
耳鳴は全人口の15〜20%にみられる症状であるが, 耳鳴を苦にして治療を求める人は少数である. 耳鳴のもたらす苦痛, 睡眠障害, 情緒的反応, 職業や日常生活への影響などは, 患者により異なる. 耳鳴を訴える患者の多くは難聴を伴うが, 20%は正常聴力である. 耳鳴を測定すると, それぞれの聞こえの域値上, 5〜15dB程度の大きさにすぎない. 多くの人は耳鳴をかすかな, 注意を向けるに値しない音として認知するが, 耳鳴に悩む人には大きな不快な音として聞こえるのである. 耳鳴には, カウンセリング, 抗うつ薬, 抗てんかん薬, 抗不安薬, 局所麻酔薬, 血管拡張薬などの薬物や手術, マスキング法, 心理療法, バイオフィードバック, 針治療, 高気圧酸素室, 側頭下顎関節の治療などが行われているが, 満足できる結果が得られていない. 耳鳴再訓練療法(tinnitus retraining therapy;TRT)は1980年代に提唱され, 1990年に最初の報告がなされた. 耳鳴の神経生理学的モデルに基づいて, 耳鳴の知覚と耳鳴への反応に慣れを誘導し維持しようとする方法であり, 慣れは聴覚系と大脳辺縁系, および自律神経系を結ぶ神経の連絡の変容の結果として得られる. 耳鳴の神経生理学的モデルから, 治療に重要な点を挙げると以下のようになる. (1)耳鳴の患者では, 聴覚系に加えて大脳辺縁系と自律神経系が耳鳴に関連した, および音響に誘発された活動に関与している, (2)自律神経系の交感神経系の過剰活動の維持が耳鳴に誘発された行動に関与している, (3)脳のさまざまな系の間の機能的な結合は, 条件反射の原則でつくられる, (4)これらの条件反射に慣れをつくることで耳鳴による行動へのネガティブな影響を除くことができる. TRTはカウンセリングとTCI(補聴器と同じような形の音響発生装置)の装用の2つからなる. カウンセリングでは, 耳鳴の理解(情報の提供), 心理面のサポート, リラクセーション法の指導, TCIの装用の指導を行う. 重要な, 注意に値する音として認知されてしまう耳鳴に心地よいかすかな音を併用することで, 耳鳴を無害な, 注意するに値しない音としての認知に変えてしまうことが目標となる. すなわち, TRTは耳鳴を止める治療ではなく耳鳴に慣れて気にしなくなる治療である. TCIは持続的に心地よい音を鳴らし続ける装置で, 耳掛型の補聴器の形をしている. 音量の設定は, 周囲の環境音と耳鳴がわずかに聞こえる程度に設定する. 1日6〜8時間装用して効果が明らかになるには6ヵ月, 継続的な改善が得られるまでには, 12ヵ月が必要である. 80%の患者で改善が得られた. 改善の得られた例では, 過去12年間, 再発はみられていない. 結論としては, (1)TRTはあらゆるタイプの耳鳴と聴覚過敏に適用できる治療で80%に有効である, (2)TRTは聴覚過敏に治癒をもたらす可能性がある, (3)TRTは頻回の通院が不要で副作用もない, (4)効果が得られるには治療者のトレーニングが必要である.
3 0 0 0 美貌の陥穽 : セクシュアリティーのエスノメソドロジー
- 著者
- 愼 英弘
- 出版者
- 四天王寺大学
- 雑誌
- 四天王寺大学大学院研究論集 (ISSN:18836364)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.5-22, 2015
3 0 0 0 「自己肯定」って、なに? : 特集
- 著者
- "人間と性"教育研究協議会企画編集
- 出版者
- エイデル研究所
- 巻号頁・発行日
- 2007