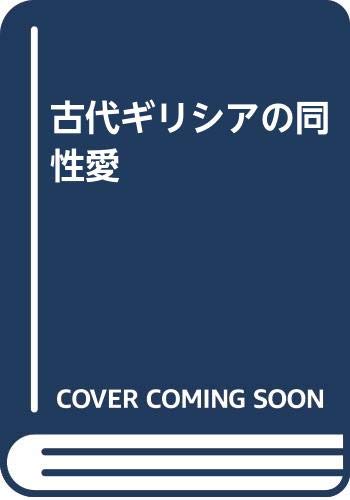3 0 0 0 OA 字音便覧
- 著者
- 佐藤重治 著
- 出版者
- 陸軍主計団記事発行部
- 巻号頁・発行日
- 1920
3 0 0 0 OA 環境省の行政事業レビューへの研究者の対応―効果的・効率的外来哺乳類対策の構築に向けて―
- 著者
- 山田 文雄 石井 信夫 池田 透 常田 邦彦 深澤 圭太 橋本 琢磨 諸澤 崇裕 阿部 愼太郎 石川 拓哉 阿部 豪 村上 興正
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.265-287, 2012 (Released:2013-02-06)
- 被引用文献数
- 2
政府の府省が進める各種事業の透明化と無駄遣いの防止をねらいとする「行政事業レビュー」において,2012年度に環境省の「特定外来生物防除等推進事業」が「抜本的改善」という厳しい評価を受けた.この事業レビューでは,おもにフイリマングースHerpestes auropunctatus(特定外来生物法ではジャワマングースH. javanicusの和名と学名を使用)やアライグマProcyon lotorの防除事業が取り上げられた.日本哺乳類学会はこの評価結果について,外来生物対策の基本的考え方や事業の成果についての誤解も含まれているとし,この判定の再考と外来生物対策の一層の推進を求める要望書を提出した.本稿では,環境省行政事業レビューの仕組みと今回の結果について報告し,根絶を目標とするマングース防除事業の考え方と実施状況,また,広域分布外来生物の代表としてアライグマを例に対策のあるべき姿を紹介した.さらに,学会が提出した要望書の作成経過と要点について説明し,最後に,行政事業レビューでの指摘事項に対して,効果的かつ効率的な外来哺乳類対策に関する7つの論点整理を行った.これらの要望書や日本哺乳類学会2012年度大会の自由集会における議論及び本報告によって,われわれの意見を表明し,今後の動向を注視するとともに,今後の外来種対策事業や研究のより一層の充実を期待したい.
3 0 0 0 OA ソビエト連邦における半導性有機物質の研究
- 著者
- 籏野 昌弘 野口 宏道
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.11, pp.1004-1009,980, 1960-10-20 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 73
3 0 0 0 OA 大学図書館施設改修に伴う館内利用の変化を量的に評価する試み
- 著者
- 稲葉 直也
- 出版者
- 国公私立大学図書館協力委員会
- 雑誌
- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, pp.2040, 2019-08-31 (Released:2019-09-05)
本稿は,ラーニング・コモンズ設置等に代表される,館内利用方針の変換を伴う施設改修の効果を検証するために,大学図書館の館内利用量(利用時間)を推定することで,館内利用の変化を量的に評価する手法を提案する。2018年8月から9月に行われた早稲田大学中央図書館2階のラーニング・コモンズ改修工事を対象に実証調査を行い,改修に期待する効果を事前に館内利用量を測定することで予測し,改修後に館内利用の変化の有無を確認することで,想定通りの改修の効果が表れているか検証と評価が可能であることを明らかにした。
3 0 0 0 OA 諏訪上社御柱祭りノート : 歴史の隠喩
- 著者
- 友杉 孝
- 出版者
- 京都大学東南アジア地域研究研究所
- 雑誌
- 東南アジア研究 (ISSN:05638682)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.315-332, 1980 (Released:2018-06-02)
Every seven years the Onbashira Matsuri (pillar festival) is held at Suwa shrine. The main event is the dragging of the Onbashira , a great log weighing 11 tons, from a mountain some 15 kilometres away to the shrine. The dragging of the Onbashira by thousands of people is a powerful attraction both to tourists and local people alike. The festival is divided into two parts, first, called Maebiki , being the procession from the mountain to the village, and the second, Satobiki , the journey from the village to the shrine. Between the two parts there is a month's intermission, Maebiki taking place in April and Satobiki in May. The former is characterized by its masculinity, as young men proudly ride the Onbashira as it is dragged through the crowd. Satobiki , on the other hand, involves gay processions, with groups of masked people and a feudal lord's procession adding to the cheerful atmosphere. During Satobiki people are freed from their everyday activities and jobs, so that they may enjoy along with visitors all there is to see. The social norm is reversed at this time as economy gives way to extravagance. With the planting of the Onbashira in a ritual performed by priests, the festival ends and everyone returns home and resumes normal life. They have, however, been vitalized by the excitement of the festival. In consequence, the Onbashira Matsuri can be interpreted as a renovation of life through a pillar which is believed to be the symbol of a supernatural power.
3 0 0 0 同性愛と生存の美学
- 著者
- ミシェル・フーコー著 増田一夫訳
- 出版者
- 哲学書房
- 巻号頁・発行日
- 1987
- 出版者
- 産労総合研究所
- 雑誌
- 労働判例 (ISSN:03871878)
- 巻号頁・発行日
- no.1200, pp.69-84, 2019-07-01
3 0 0 0 OA 専攻学問に対する価値と批判的思考力の関連
- 著者
- 松本 明日香 小川 一美
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.28-41, 2018-03-30 (Released:2018-04-18)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 4 5
本研究の目的は,大学で専攻する学問に対して,どのような価値を求めるのか,どのような価値評定をしているのかという専攻学問に対する価値と,大学教育を通じて培うべき力である批判的思考力との関連を探索的に検討することであった。批判的思考力として,質問力,質問態度,クリティカルシンキング志向性を測定した。専攻学問に対する価値を第1群,批判的思考力を第2群として正準相関分析を行った結果,以下の2点が示された。1点目は,専攻学問に対する4つの価値全てが高いと,質問態度やクリティカルシンキング志向性が高くなり,事実を問う質問数も多くなるという結果であった。2点目は,専攻学問の学びは他者から見て望ましいと思われているという価値である公的獲得価値は高いが,専攻学問は充実感や満足感を喚起する学問であると思うという興味価値が低いと,事実を問う質問数は多くなるが,クリティカルシンキング志向性および思考を刺激する質問数に負の影響を与えるという結果であった。専攻学問に対して価値を見出すことは,批判的思考力の獲得に有効な要素であることや,複数の価値を組み合わせて効果を検討することの意義などが考察された。
- 著者
- 加賀 秀雄 鈴木 敏夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会号
- 巻号頁・発行日
- vol.37, 1986
3 0 0 0 古代ギリシアの同性愛
- 著者
- ケネス・ドーヴァー著 中務哲郎下田立行訳
- 出版者
- リブロポート
- 巻号頁・発行日
- 1984
3 0 0 0 OA 2歳代の語彙発達 : 語彙チェックリストを用いた表出語彙の分析
- 著者
- 大森 史隆 笠井 新一郎 天辰 雅子 中山 翼 飯干 紀代子 山田 弘幸 オオモリ フミタカ カサイ シンイチロウ アマタツ マサコ ナカヤマ ツバサ イイボシ キヨコ ヤマダ ヒロユキ Fumitaka OHMORI Shinichiro KASAI Masako AMATATSU Tsubasa NAKAYAMA Kiyoko IIBOSHI Hiroyuki YAMADA
- 雑誌
- 九州保健福祉大学研究紀要 = Journal of Kyushu University of Health and Welfare
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.119-126, 2010-03
This study examined 300 children aged 24-35 months to clarify expressive vocabulary development using the vocabulary checklist questionnaire. Children were classified into 4 periods: first period, 24-26 months; second period, 27-29 months; third period, 30-32 months; and fourth period, 33-35 months. We analyzed median and quartiles of expressive vocabulary and performed one-way analysis of variance to determine which periods differed significantly from other periods. As a result, median total expressive vocabulary was 238.0 in the first period, 423.0 in the second period, 508.0 in the third period, and 661.0 in the fourth period. A clear correlation was seen between total expressive vocabulary, noun vocabulary, verb vocabulary, adjective vocabulary and child age. No significant difference in total expressive vocabulary was evident between second and third periods. These results indicate an incubation period in which the expressive vocabulary is invariable. A significant difference was apparent between the second and third periods in the verb vocabulary, suggesting a qualitative change in the expressive vocabulary. However, the term of increasing verb vocabulary was shorter than that for the noun vocabulary, which previous studies have reported in children aged 18-30 months.
3 0 0 0 OA Utilization of Social Media in the East Japan Earthquake and Tsunami and its Effectiveness
- 著者
- Brett D. M. PEARY Rajib SHAW Yukiko TAKEUCHI
- 出版者
- 日本自然災害学会
- 雑誌
- Journal of Natural Disaster Science (ISSN:03884090)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.3-18, 2012 (Released:2015-05-13)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 22 97
During the 2011 East Japan Earthquake and Tsunami, newly popular social media such as Twitter and Facebook served as a lifeline for directly affected individuals, a means of information sharing, and a way for people inside and outside Japan to volunteer and to provide information-based support to affected individuals. Social media was used to perform vital relief functions such as safety identification, displaced-persons locating, damage information provision, support for disabled individuals, volunteer organization, fund-raising, and moral support systems. This study discusses the potential for public, civil society, and government organizations to utilize social media in disaster preparedness and response.
3 0 0 0 OA 伏見伊東家旧蔵資料に関する調査の中間報告
- 著者
- 野村 朋弘
- 出版者
- 京都造形芸術大学
- 雑誌
- 京都造形芸術大学紀要 = Genesis
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.97-108, 2019-09-30
3 0 0 0 科学技術者とフェビアニズム
3 0 0 0 OA たばこの値上げの持つ意味
- 著者
- 中村 正和
- 出版者
- 日本健康教育学会
- 雑誌
- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.1-2, 2010 (Released:2011-11-12)
3 0 0 0 学習ポートフォリオシステムのログデータ評価方法論の提案
本研究の目的は, 学習ポートフォリオシステム(以下PFシステム)に蓄積されたログデータを, 大学生の授業内外の学びを包括的に促進するための手がかりとして活用する方法論を提案することである. 近年では個々の学習者を中心として授業外の学びも一連の学びとして評価することで学習の形成的評価やキャリア教育につなげようとする試みが盛んである. そこで本研究では, 大学での授業と日常生活が, 大学生の学習目標を設定し達成度を記録する場としてのPFシステムでどのように関連付けられているかを評価することとした.本研究では2つの分析を行った. 1つ目は, 大学生がPFシステムに書き込んだ学習目標と書き込み場所の関連性についての調査である. 静岡大学情報学部生のうち特にPFシステムの利用が多かった1年生約200名のデータを主に分析した結果, 学外の場所で記載された学習目標はボランティアやアルバイトといった大学外での生活に関係しており, 授業関係の学習目標の多くは大学内にて書き込まれていた. 2つ目は, PFシステムの大学内外での利用における事例分析である. PFシステムを恒常的に利用している就職活動中の大学生1名に対して1週間のPFシステム利用目的・回数等を尋ねるインタビューを行った. その結果, PFシステムへの書き込みは閲覧者からの反応が得られる場合に活発になり, 就職活動中は企業が閲覧・評価者としての役目を果たしていたことがわかった.以上より, 大学内外での大学生の学び・生活を一連の学びとしてPFシステムにまとめるには, (1)相互に閲覧し刺激し合うコミュニティをPFシステム上に用意すること, (2)大学外からもPFシステムに書き込みを行うよう動機づけること, が重要だと言える. 逆に言えば, これら条件を満たすことが, PFシステムに有意味なログデータを蓄積する上で必要不可欠だと考えられるため, いかに大学生の日常にPFシステムを組み込むかの工夫が急がれていると言える.
- 著者
- ズルキフリー ムハマド 田野 俊一 岩田 満 橋山 智訓
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌. D, 情報・システム (ISSN:18804535)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.3, pp.771-783, 2008-03-01
- 被引用文献数
- 4
近年の情報技術の発展により,多くの人は文書を作成するためにワードプロセッサを用いている.しかし,日本語入力は仮名漢字変換に起因する問題点を多く抱えているため,メモ書きのように,素早い入力,及び高い集中力が要求される作業においては,キーボード入力より手書き入力の方が有効ではないかと考えられる.そこで,本研究では入力速度,及び認知的負荷に着目し,日本語メモ書き作業における手書きとキーボードの比較実験を行い,手書き入力の有効性を定量的に評価した.被験者としては,22〜30歳の情報系大学院生10〜15名である.実験結果から,まず入力速度に関しては,キーボードよりも手書きの方が速く入力できるということが分かった.また,あらかじめ記憶させた内容を思い出しながら入力するタスクでは,キーボードよりも手書きの方が記憶した内容を多く入力できるということが分かった.更に,ビデオ及び音声を視聴しながら,手書き及びキーボードでメモを取るタスクでは,キーボードで入力されたメモの方が内容が不十分であり,被験者のビデオ及び音声の内容に対する理解度も低いということが分かった.
- 著者
- Maya Adachi Mai Watanabe Yasutaka Kurata Yumiko Inoue Tomomi Notsu Kenshiro Yamamoto Hiromu Horie Shogo Tanno Maki Morita Junichiro Miake Toshihiro Hamada Masanari Kuwabara Naoe Nakasone Haruaki Ninomiya Motokazu Tsuneto Yasuaki Shirayoshi Akio Yoshida Motonobu Nishimura Kazuhiro Yamamoto Ichiro Hisatome
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-19-0261, (Released:2019-09-13)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 5
Background:Treatment of myocardial infarction (MI) includes inhibition of the sympathetic nervous system (SNS). Cell-based therapy using adipose-derived stem cells (ASCs) has emerged as a novel therapeutic approach to treat heart failure in MI. The purpose of this study was to determine whether a combination of ASC transplantation and SNS inhibition synergistically improves cardiac functions after MI.Methods and Results:ASCs were isolated from fat tissues of Lewis rats. In in vitro studies using cultured ASC cells, mRNA levels of angiogenic factors under normoxia or hypoxia, and the effects of norepinephrine and a β-blocker, carvedilol, on the mRNA levels were determined. Hypoxia increased vascular endothelial growth factor (VEGF) mRNA in ASCs. Norepinephrine further increased VEGF mRNA; this effect was unaffected by carvedilol. VEGF promoted VEGF receptor phosphorylation and tube formation of human umbilical vein endothelial cells, which were inhibited by carvedilol. In in vivo studies using a rat MI model, transplanted ASC sheets improved contractile functions of MI hearts; they also facilitated neovascularization and suppressed fibrosis after MI. These beneficial effects of ASC sheets were abolished by carvedilol. The effects of ASC sheets and carvedilol on MI heart functions were confirmed by Langendorff perfusion experiments using isolated hearts.Conclusions:ASC sheets prevented cardiac dysfunctions and remodeling after MI in a rat model via VEGF secretion. Inhibition of VEGF effects by carvedilol abolished their beneficial effects.
3 0 0 0 OA QUANTUM THEORY OF A MASSLESS RELATIVISTIC SURFACE AND A TWO-DIMENSIONAL BOUND STATE PROBLEM
- 著者
- JENS HOPPE
- 出版者
- Soryushiron Kenkyu Editorial Office
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.3, pp.145-202, 1989-12-20 (Released:2017-10-02)
A massless relativistic surface is defined in a Lorentz invariant way by letting its action be proportional to the volume swept out in Minkowski space. The system is described in light cone coordinates and by going to a Hamiltonian formalism one sees that the dynamics depend only on the transverse coordinates X and Y. The Hamiltonian H is invariant under the group of area preserving reparametrizations whose Lie algebra can be shown to correspond in some sense to the Large N-limit of SU(N). Using this one arrives at a SU(N) invariant, large N-two-matrix model with a quartic interaction [X, Y]^2. The problem of N partices with nearest neighbors δ-function interactions is defined by regularizing the 2 body problem and deriving an eigenvalue integral equation that is equivalent to the Schrodinger equation (for bound states). The 3 body problem is discussed extensively and it is argued to be free of irregularities, in contrast with the known results in 3 dimensions. The crucial role of the dimension is displayed in looking at the limit of a short-range potential.