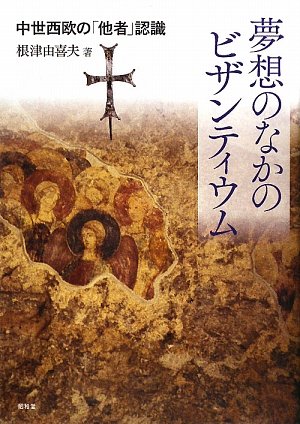3 0 0 0 OA 古代色素, シコニンとその誘導体の化学
- 著者
- 寺田 晁 田上 保博 谷口 博重
- 出版者
- 社団法人 有機合成化学協会
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.10, pp.866-875, 1990 (Released:2009-11-13)
- 参考文献数
- 81
- 被引用文献数
- 5 8
The roots of Lithospermum erythrorhizon Sieb. and Zucc., (violet root, Japanese name, Shikon) contain shikonin and its esters as purple pigments. The coloring matter of the root of Alkanna tinctoria in Europe is a mixture of the enantiomeric alkannin and its esters. The racemic compound of shikonin and alkannin was named shikalkin by R. Kuhn and H. Brockmann. From ancient times these purple pigments have been well-known as valuable materials having antiinflammatory, antibacterial, antitumor actions, and as ancient purple deys and cosmetics. Here, the history, structural determination, synthesis and pharmacology of shikonin, alkannin, and their derivatives will be reviewed.
3 0 0 0 IR 『魏志』の帝室衰亡叙述に見える陳寿の政治意識
- 著者
- 津田資久
- 雑誌
- 東洋学報 / The Toyo Gakuho
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.4, pp.393-420, 2003-03
This paper discusses the account of the fall of the Cao Wei 曹魏 imperial family (帝室) in the Weizhi 『魏志』 compiled by Chen Shou 陳寿 as a reflection of his political consciousness towards the Xi Jin 西晋 imperial family during the early part of the Taikang 太康 era of the reign of the Emperor Wu 武.At the time the Weizhi was compiled, it was a period of transition from a government of the imperial in-laws (外戚) under the Han 漢 dynasty to a government (輔政) of imperial clans (宗室) during the times after the Wei-Jin 魏晋. This tendency is reflected in Weizhi, as Chen Shou points out the origins of the fall of the Cao Wei imperial family as follows:1. The struggle over succession between Cao Pi 曹丕 (he was to found the Cao Wei dynasty and reign as Wendi 文帝) and his brother Cao Zhi曹植. 2. Cao Pi's later restraint towards the kin princes (至親諸王, his brothers).3.The government of imperial in-laws, and the installation of the empress from concubines.However, through a detailed examination of the descriptions in the Weizhi, we find emphasis put on the origin of the fall of the Cao Wei imperial family. In fact, it is a falsification of historical fact by Chen Shou. The author believes that Chen Shou's purpose was to emphasize the following lessons to be learned from the fall of the Cao Wei imperial family:I. Restraint towards the government of the kin princes.II. The exclusion of imperial in-laws from politics.III. A refutation of the installation of empresses from concubines who cause trouble for the order of Seraglios.Why Chen Shou dared to write such a description is because it was a mirror of the political situation during the early part of the Taikang era.① Excluding Wudi's brother Qiwang-You 斉王攸, who once struggled with Wudi over succession, from politics.② The rise of the Ynag Family (楊氏) of imperial in-laws, who planned to expel Qiwang-You from the central government.③ The problem of the Hu-guipin 胡貴嬪, an honored concubine, who had gained the favor of Wudi, exerted great influence on the succession.|
3 0 0 0 OA 放射線被ばくと健康管理システム―福島原発事故の健康への影響と広島の関わり―
- 著者
- 司会:八木 聰明 演者:神谷 研二
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.4, pp.427-428, 2017-04-20 (Released:2017-06-01)
3 0 0 0 OA ヤツブサの成分並びにトウガラシ変種中Capsi-amideの分布
- 著者
- 高橋 三雄 大沢 啓助 蔡 哲宗 阿部 昌宏
- 出版者
- 公益社団法人日本薬学会
- 雑誌
- 藥學雜誌 (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.2, pp.221-223, 1980-02-25
Nine kinds of fatty acids, fifteen hydrocarbons, three sterols, and six amino acids were detected by gas chromatography-mass spectrometry and amino acid analysis, from the dried fruits of Capsicum annuum L. var. fasciculatum IRISH. The distribution of N-(13-methyltetradecyl) acetoamide isolated from Capsicum annuum L., and named Capsi-amide, was investigated in four varieties of Capsicum annuum L., i.e. C. annuum L. var. fasciculatum IRISH, var. grossum SENDT., var. longum SENDT., and var. minimum ROXB. Capsi-amide was detected in all four varieties.
- 著者
- 大野 淳 北原 理雄 神谷 文子
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 東海支部研究報告集 (ISSN:13438360)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.485-488, 1989-02-17
3 0 0 0 OA 〔講演録〕佐賀藩と漢籍
- 著者
- 高山 節也
- 出版者
- 日本近世文学会
- 雑誌
- 近世文藝 (ISSN:03873412)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, pp.47-59, 2008 (Released:2017-04-28)
3 0 0 0 OA 精神看護学実習の「患者-学生」関係における困惑を改善するための指導方法の研究
- 著者
- 中野 あずさ 益子 育代 田村 文子
- 出版者
- 群馬県立県民健康科学大学
- 雑誌
- 群馬県立県民健康科学大学紀要 (ISSN:18810691)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.51-62, 2006-03
目的:本研究の目的は,精神看護学実習におけるプロセスレコードを使った指導の有効性について検討するものである.方法:対象は,精神看護学実習での困惑場面について再構成されたプロセスレコード44例である.プロセスレコードを使った指導は,1)ロールプレイ,2)かかわりの評価,3)縦読み,4)横読み,の手順に従って実施された.本稿は,学生の困惑状況とその問題要因について分析を行った.結果:学生の困惑状況は8つのカテゴリーに分類できる.さらに,その問題要田は,1)コミュニケーションスキルの未熟さによる状況把握の不足,2)察しの悪さによる共感性の欠如,3)わかったつもりになって患者へ不快感を喚起してしまうこと,4)精神症状に対する不安,の4つのパターンに整理された.学生はロールプレイを通して患者に対する共感性が高まり,縦読み・横読みから自分のかかわりの問題点と改善策を見出だすことができた.
3 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1888年02月17日, 1888-02-17
3 0 0 0 江戸幕府の公文書管理に関する基礎的研究
年度計画にもとづき、東京都、群馬県、山梨県、長野県などの史料保存利用機関において、江戸幕府の公文書に関する文献と史料の調査を行った。具体的には、幕府・朝廷間、幕府・藩間、幕府・旗本間、幕府・寺社間、幕府・町間、幕府・村間でやりとりされた史料に注目して調査・収集を行った。今年度は最終年度であるため、これまでの調査の成果を、文献と史料に大分類したうえで、上記のやりとりをもとにした小分類を用いて目録化した。地域史研究の進展の差や、調査地の制約などにより、目録は必ずしも完成されたものにはなっていない。しかし分類法を整理と、基礎的文献や基礎的史料を把握した意義は大きいと思われる。今後、対象地域や機関を拡大することにより目録を充実化させていきたい。これらの史料調査・分析の過程で、日本近世において、18世紀前半に8代将軍徳川吉宗によって展開された享保改革が、江戸幕府の公文書管理の重要な画期であったことが、あらためて確認されるとともに、吉宗の腹心ともいうべき大岡忠相が公文書政策に重要な役割を果していたことが明らかとなった。すなわち、大岡は町奉行時代に江戸の法令を集め、整理した『撰要類集』を編さんするなど幕府の情報蓄積に努め、その後寺社奉行に異動するとともに、公文書の持ち回りシステムを確立したのである。全国の代官所への公文書作成の指示もあわせて、享保改革の重要性があらためて確認された。
3 0 0 0 OA 自治体文化財団に関する研究:日本におけるアーツカウンシル的組織の現状と課題
- 著者
- 太下 義之 オオシタ ヨシユキ
- 雑誌
- 静岡文化芸術大学研究紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.133-150, 2017-03-31
本論文は,最初にSUAC 芸術経営統計を元に,自治体文化財団の概要について整理した。その結果,自治体文化財団の主要な業務は指定管理であり,文化芸術団体の支援は些末な位置づけしかないという実態を明らかにした。次に自治体文化財団の歴史を,国全体のマスタープランとも言える全国総合開発計画との関連も踏まえて考察した。その結果,全国で公立文化施設が多数整備された90年代において,文化振興ではなく,日米構造協議を契機とする内需拡大のために,国からの強い働きかけもあって地方債が多額に発行され,それを活用して箱物が多数整備されたことを明らかにした。最後に自治体文化財団の意義と課題を,「公立文化施設の柔軟な運営/二層の職員構成」「文化振興の専門職のプリカリアート化」「地域の文化政策自体の弱体化」「助成財団としての文化振興/助成金額の減少」「文化政策における自治体文化財団の位置づけの無さ」の5項目に整理した。
3 0 0 0 OA 蒸気機関車用練炭の性状とその燃焼性
- 著者
- 喜多 信之
- 出版者
- 一般社団法人 日本エネルギー学会
- 雑誌
- 燃料協会誌 (ISSN:03693775)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.32-50, 1962-01-20 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 31
本研究は主としてピッチ練炭の燃焼時の崩壊現象を究明し, 蒸気機関車の高燃焼率にともなう損失の増大に対処せんとするものである。練炭は機関車火床において多様の崩壊現象を呈するが, 一般に崩壊性は炭種, 製造条件および燃焼条件によつて変化することを述べた後, これを整理して4つの崩壊型すなわち凝結型, 花弁型, 細粉型および膨脹型に整理分類できることを指摘した。さらに諸型の生成機構について調べた結果, 急速加熱にもとずく加熱方向収縮差による亀裂, 膨脹抑制作用および石炭のピツチ接着面における粘結性による融合作用ならびに収縮性による剥離作用などの組合せによつて成立することを明らかにした。つづいて現車試験を行い崩壊型と燃焼損失の関係を求め, 凝結型は燃渣損失の増大, 細粉型はシンダー損失の増大, また膨脹型は焚火障害のため, いずれも不適当で, 花弁型が各種損失が最小で機関車用として最適であるとした。以上によつて (1) 機関車用練炭の具備条件として従来の発熱量, 強度などのほかに花弁型の崩壊性を持つこと6 (2) 花弁型の生成理論を応用することにより, たとえ単身では細粉型あるいは凝結型となる原料炭を用いても, その適度の配合によつて花弁型練炭を製造することができる。
- 著者
- 青木 加奈子
- 出版者
- 筑波大学大学研究センター
- 雑誌
- 大学研究 (ISSN:09160264)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.63-85, 2005-03
東京経済大学の青木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回の公開研究会のテーマは大学職員の自己啓発ということです。私自身が大学職員ですので、このテーマは、私の自己啓発と言い換えることができるわけです。しかし、私 ...
- 著者
- Vilma Ratia Kati Valtonen Anu Kemppainen Veli-Tapani Kuokkala
- 出版者
- (社)日本トライボロジー学会
- 雑誌
- Tribology Online (ISSN:18812198)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.152-161, 2012-02-15 (Released:2013-02-15)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 21
Energy can be saved by enhancing the service life of machinery and by designing lighter units. These design changes enable, for example, lower fuel consumption and larger payloads. The implementation of this kind of solutions, however, requires development of better wear resistant materials. In this study, the wear resistance of a structural steel and three grades of wear resistant steel was evaluated with granite abrasive in tests simulating the conditions in heavy machinery in mining and transportation. Two high-stress abrasion and one impact-abrasion wear testing methods were used. In all tests, higher hardness led to decreased mass loss, but in impact-abrasion the hardness dependence was smaller than in the heavy abrasion tests. This may, however, at least partly result from deformation of softer materials over the sample edges, which is not shown as mass loss. Wear surfaces of structural steel samples exhibited the highest degree of plastic deformation due to their lower hardness and higher ductility compared to the wear resistant steels. On the other hand, in harder materials the scratches were more visible, indicating a change in wear mechanism. Both differences and similarities in the behavior and wear mechanisms of the selected steels were observed in the applied conditions.
- 著者
- 平野 恭平
- 出版者
- 政治経済学・経済史学会
- 雑誌
- 歴史と経済 (ISSN:13479660)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.1-15, 2014-10-30
During World War II, Japanese companies pursued the development of synthetic fibers as substitutes for such natural fibers as cotton and wool. A well-known case is polyvinyl alcohol (PVA) fiber, industrialized after the war under the brand name Vinylon by Jurashiki Rayon (Kuraray) and Dai-Nippon Cotton Spinning. This paper considers the case of Kanebian, another variety of PVA fiberm produced by Kanegafuchi Cotton Spinning (Kanebo). Kanebian's development was advanced almost concurrently with that of Vinylon but ultimately was suspended, though its realization was close at hand. The reasons why Kuraray succeeded in industrializing Vinylon and establishing its own market lie in its shift from "negative substitution" - the goal of compensating for a shortage of natural fibers -- to "positive substitution," which brought out and commercialized the peculiar attributes and attractions of synthetic fibers as substitutes for natural fibers. This process was the necessary condition for the survival of wartime substitute fibers in the postwar environment. After the war Kanebo made the reconstruction of natural fibers its highest priority, thereby delaying the development of synthetic fibers and widening the gap with Kuraray's progress. The two fibers had reached similar levels of development by the end of the war. But Kanebo's management was negative about Kanebian's prospects because of its defects in quality and cost and therefore was cool toward its further development. Kanebo's engineers worked to address these weaknesses as they emerged in the postwar years, and sought out optimum markets while watching Vinylon's progress closely. Their unrelernting effort and confidence in Kanebian's potential did not sway management's assessment of the product, however, and ultimately Kanebo discontinued the development of Kanebian. The decision to suspend development seems at first glance to have been mistaken given Kuraray's success. It has its own validity and rationality, however, when we take into consideration Kanebo's founding and principal business which was cotton spinning, the postwar recovery of the cotton spinning industry, Kanebian's technical properties and its potential, and the limited support from industrial policy at the time. This article explains this assertion in detail by studying the process from development to suspension, and considers it as an aspect of the shift from "negative" to "positive substitution."
3 0 0 0 夢想のなかのビザンティウム : 中世西欧の「他者」認識
3 0 0 0 OA 2016 レポートの書き方講習会
- 著者
- 奥 敬一
- 巻号頁・発行日
- pp.1-5, 2016-06
2016年6月15日 : 富山大学高岡キャンパス講堂,2016年6月16日 : 富山大学中央図書館でそれぞれ開催された「2016 レポートの書き方講習会」の配布資料。 【内容】• レポートとその仲間達 •レポートの構造と作法 • レポートのTips• レポート?の実例• 参考になる文献
3 0 0 0 OA 3. 肝硬変に伴う糖尿病(肝性糖尿病)
- 著者
- 種市 春仁 藤原 史門 佐藤 譲
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.203-205, 2008 (Released:2009-05-20)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 2
- 著者
- ROBERT F.RHODES SARAH J.HORTON
- 出版者
- 大谷大学
- 雑誌
- 特別研究員奨励費
- 巻号頁・発行日
- 2004
平安時代中期から後期にかけて、仏教が民衆の間に広まったことは、従来より指摘されている。しかし、仏教の拡大において、比叡山などで行われた「講」が大きな役割を果たしたことは、あまり注目されてこなかったように思われる。本研究では仏像の宗教的・社会的役割を解明するために、平安時代から鎌倉時代に行われた各種の講に焦点を当て、仏教儀礼の研究を行った。その結果、平安・鎌倉時代における仏像の宗教的・社会的役割がごある程度把握できたと考える。この研究を進める上で、二つの方法を採用した。一つは文献的研究である。この一年間をかけて研究分担者のホートン教授とともに、いくつかの講式(仏教儀式の時に用いられる式次第)や説話集に散見する仏像や仏教儀礼の記述をに関する解読作業をおこなった。取り上げた文献の主なものは『日本霊異記』、『法華験記』、『今昔物語集』、永観の『往生講式』などであったが、それに加えて『源氏物語』や『枕草子』に見られる仏像に関する記述や『矢田寺縁起絵巻』なども検討した。第二の方法として、平安時代・鎌倉時代の仏像を安置する寺院で行われている儀式に参加し、調査を行った。特にホートン教授は、ほぼ毎週近畿圏で行われている各種仏教儀礼に参加し、その様子を写真やビデオに納めた。また、その際には住職や一般信者に聞き取り調査も行った。特に興味深かったのは、奈良の薬師寺や京都の知恩院と清浄華院で行われる仏像の身拭い式であったが、その他にも奈良の伝香寺の有名な年中儀礼である裸地蔵の着替え式や京都の本能寺で行われる放生会にも参加することができた。