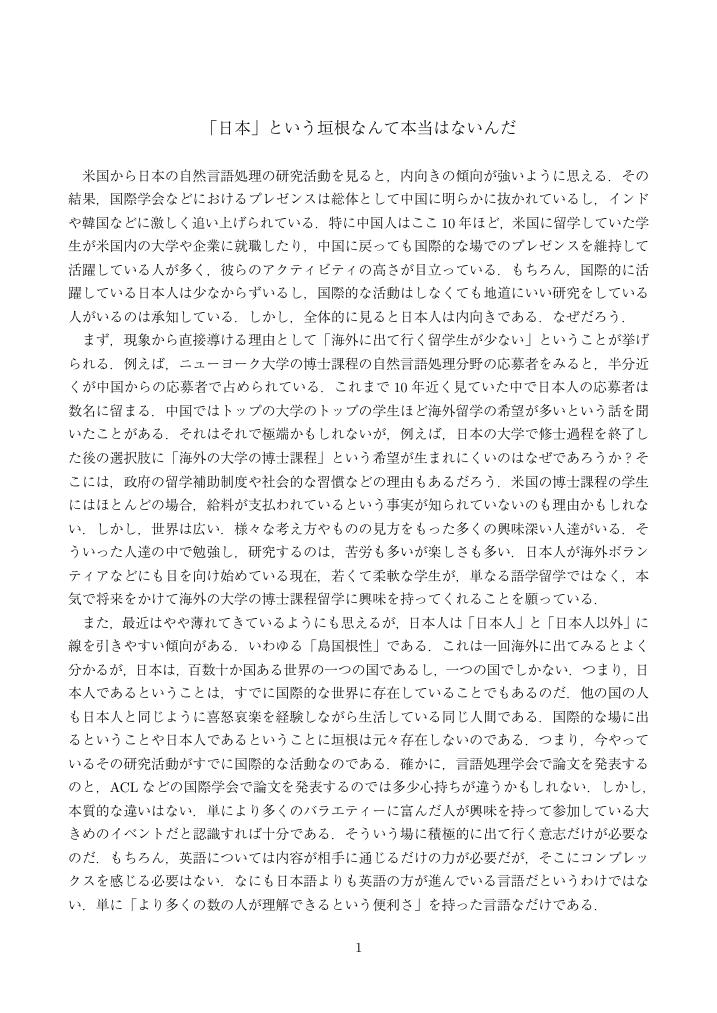3 0 0 0 OA 日本でのアゾラ利用の現状と将来 : アゾラ外来種が侵略的植物として法規制の対象に
- 著者
- 渡辺 巌
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.178-184, 2006-09-22
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA ストーリー形成のアルゴリズム
- 著者
- 李 哲榮 寺野 寿郎
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.4, pp.579-584, 1980-08-30 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 10
The story formation defined here means a process of connecting the given sentences, which are logically independent of one another, and creating a new story of which the plot is reasonable. Such a work will be very essential near future to automatic writing of scenario of abstract, but it is not easy because creation is an innate ability of a man. The method suggested here is as follows: (1) a man first makes a fuzzy graph where the verteces are the given short sentences, (2) next he finds the fuzzy labels of verteces and the fuzzy relations among the verteces, (3) according to a given strategy, the computer searches its subgraphs of which the plots are semantically reasonable.These subgraphs corresponds to the backgrounds and episodes of the candidate stories. A new fuzzy graph is mode of these episodes and backgrounds, and the same procedures are repeated until they are converged. As the result some candidate stories are induced. Though the final selection of the candidate stories is done by the computer, the man can easily intervene in it, because a fuzzy integral is adopted here as the criterion function and its fuzzy measures are difined subjectively.Some numerical examples show us the validity of this method.
- 著者
- 半澤 誠司
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.56-70, 2001-12-31
- 被引用文献数
- 8
本稿の目的は, 日本のアニメーション産業の特性を把握し, その集積要因を検討することにある.アニメーション産業は, 知識集約的な特徴を持つ, いわゆるコンテンツ産業の一つとみなされることが多いが, 実際の制作工程をみるとむしろ労働集約的な製造業としての側面が強い.作品周期が短く市場予測が難しい上に, 短期間での制作が求められるテレビシリーズアニメーションの開始によって, 1960年代に制作会社の垂直分割が進展し, 各工程に特化した中小零細企業が多数乱立するようになった.この結果として, 各制作会社間の物流と情報交換の利便性を図るために, 産業集積が生まれた.受発注関係はほとんどが東京都内で完結し, その取引内容は工程間で特色の違いがみられる.すなわち, 上位工程に位置する制作会社はさまざまな工程を持ち, 多くの企業から受注を受け, 外注比率も高いのに対し, 下位工程に位置する制作会社は一部工程に専門化し, 受注先が少なく, 外注比率が低い.1990年代におけるグローバル化の進展とデジタル化によって, 分散傾向も一部ではみられるが, アニメーション産業では取引先の能力把握と信頼性の構築が重視され, 人的繋がりから仕事が生じている面が強いので, それを生み出す場としての東京の重要性は大きくは変わらないと考えられる.
3 0 0 0 OA 参加型臨床実習生の質の確保のための獣医学共用試験の開発的研究
- 著者
- 吉川 泰弘 稲葉 睦 浅井 史敏 尾崎 博 遠藤 大二 澁谷 泉 山下 和人 北川 均 新井 敏郎 高井 伸二 杉山 誠 上地 正実 鎌田 寛
- 出版者
- 北里大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2012-04-01
わが国の全16獣医系大学における参加型実習に入る段階の学生の質を全国一定水準に確保することを目的とし、知識を評価するCBT (Computer-Based Testing)と技能と態度を評価するOSCE (Objective Structured Clinical Examination)の二つからなる獣医学共用試験について、CBT問題作成システム、問題精選システム、問題出題システム、評価システムを開発し、平成25年と26年に渡り、16大学を対象としてCBTトライアルを実施した。同時に、OSCE試験の態度と技能を確認する医療面接試験並びに実地試験を開発した。
3 0 0 0 OA インセスト的虐待の加害者たち (II)
- 著者
- 石川 義之
- 出版者
- 大阪樟蔭女子大学
- 雑誌
- 大阪樟蔭女子大学人間科学研究紀要 (ISSN:13471287)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.159-178, 2002-03-01
I referred to the actual conditions of incestuous abuse, particularly the prevalence of incestuous abuse and the gender of the perpetrators of incestuous abuse in American and Japanese society at the part I of my paper "The Perpetrators of Incestuous Abuse" contained in Journal of Social Systems, No.5,Faculty of Law and Literature, Shimane University, 2000. In this part II, I intend to throw light on the mechanism of the occurrence of incestuous abuse aimed at girls by male adults and the countermeasures for the prevention of incestuous abuse and the treatment of the victims. With respect to the former I will focus on the japanese patriarchal structure where men have control over women, and the way how the male children were socialized into capable perpetrators in Japanese society.
- 著者
- 川瀬 麻規子
- 出版者
- 金城学院大学
- 雑誌
- 金城学院大学論集 (ISSN:04538862)
- 巻号頁・発行日
- no.186, pp.55-99, 1999
3 0 0 0 OA 『グリム童話集』初稿、初版、第7版における「ヘンゼルとグレーテル」の変化について
- 著者
- 大島 浩英
- 出版者
- 大手前大学・大手前短期大学
- 雑誌
- 大手前大学論集 (ISSN:1882644X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.53-67, 2009
Jacob GrimmとWilhelm Grimmのグリム兄弟によって編纂されたKinder- und Hausmarchen(『子供と家庭の昔話』)の中のHansel und Gretel(「ヘンゼルとグレーテル」KHM 15)を題材に取り上げ、このメルヒェンを初稿(1810)、初版(1812)、第7版(1857、決定稿)とでそれぞれ比較し、その違いを検討した。(初稿(1810)でのタイトルはDas Bruderchen vnd das Schwesterchen)まず初稿では物語の進行が簡潔な平叙文(叙述文)で表現されることが多いのに対し、初版、第7版ではこれを登場人物の会話形式で説明する箇所が増加、さらに登場人物の動きや場面の描写がより詳しく、具体的な表現へと変化しており、特に第7版では新たな挿話も付け加えられている。各版におけるこういった変化を具体例に即して考察した。
3 0 0 0 OA 生命科学リテラシー育成を担う生物教育のあり方
- 著者
- 江上 有紀 椚座 圭太郎
- 出版者
- 富山大学人間発達科学部
- 雑誌
- 富山大学人間発達科学部紀要 = Memoirs of the Faculty of Human Development University of Toyama (ISSN:1881316X)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.139-155, 2016-10-25
本研究の目的は,「子宮頸ガン予防ワクチン接種の是非」を教材として用い,「生物基礎」を実際的に「日常生活や社会」に役立つようにする授業実践のあり方を提案することにある。学習指導要領では,日常生活や社会と関連した教材として「エイズ」や「糖尿病」といった疾患を挙げているが,生徒にとって当事者性の低い話題であり,免疫学習の一例に留まってしまう可能性が高い。また,先に述べたように子宮頸ガン予防ワクチン問題解決には,生物学のみならず,保健衛生学,医学から情報まで知識や活用力,すなわち生命科学リテラシーが必要である。そこで今回は,「生物基礎」の授業の中で,子宮頸ガン予防ワクチン関連分野として「免疫」「ガンの細胞学的理解」を丁寧に行い,それらを生かせる情報検索の時間を設け,自己決定力を育むことを目標とする授業展開を試みた。比較のため,「社会と情報」科目で同じテーマの情報検索を行う授業を行い,本研究の「生物基礎」授業の効果を調べた。授業実践の結果,拡張した「生物基礎」授業により,情報のリテラシーが高まり,さらに自己決定力,社会への関心が高まるという連鎖の効果が見いだされた。本論文では,実践結果を報告するとともに,科学的理解が自己決定力や社会性をもたらすメカニズムを論じ,それをふまえた高校教育における知識基盤社会,アクティブラーニング,合科授業,キャリヤ教育や18歳選挙権への対応について考察する。
3 0 0 0 OA 大阪画壇研究補遺 : 「北野恒富展」をめぐって
- 著者
- 橋爪 節也 Hashidume Setsuya
- 出版者
- 大阪大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 待兼山論叢. 美学篇 (ISSN:03874818)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.1-28, 2008-12-25
3 0 0 0 OA 禅竹集 : 能楽古典
3 0 0 0 IR バルカン戦争期のヘレニズム言説
- 著者
- 村田 奈々子
- 出版者
- 法政大学
- 雑誌
- 言語と文化 (ISSN:13494686)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.215-234, 2014-01-15
- 著者
- 佐々木 政文
- 出版者
- 公益財団法人史学会
- 雑誌
- 史學雜誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.4, pp.552-575, 2015-04-20
The present article examines the implementation of Japan's mass state ideology indoctrination policy through Buddhist temples and Shinto shrines within the undercaste ghettos (hisabetsu buraku 被差別部落) of Nara Prefecture during the 1910s, in relation to changing trends in religious belief systems on the local level. The majority of residents of the ghettos of Nara Prefecture, which remained as segregated residential communities originally created for scheduled castes under the social stratification system instituted in the premoden age were traditionally adherents of the Jodo Shinshu 浄土真宗 sect of pure land Buddhism and thus were not deeply versed in beliefs regarding Shinto gods or particularly active in related festivals promoted by the Meiji state since the 1870s. In response to this adherence to Buddhist beliefs and ceremony, Nara Prefecture adopted, following the Russo-Japanese War, a Buraku Improvement Program, which attempted to strengthen adherence to state religious ideology through such projects as revising Pure Land millenarian beliefs emphasizing the afterlife, inculcating the concept of "shinzoku nitai" 真俗二諦 (there being no contradiction between following the teachings of the Buddha, while submitting to the secular authority of the Emperor), the elimination of special social status for Shinto shrine patrons (ujiko 氏子), the installation of Shinto altars in the home, universal allegiance to the national flag and the promotion of pilgrimages to the national Shinto shrines. The author analyzes the program's implementation as a process by which modern Japan's policy regarding the ideological indoctrination of its imperial subjects proactively attempted to mobilize local residents alienated from their traditional beliefs and modes of worship into the state's new system of ritual centered upon the new Shinto pantheon, stressing the divinity of the Emperor. At the same time, as the agents of its Buraku Improvement Program the Prefectural authorities attempted to enlist the Buddhist priests of local ghetto temples, which had been for centuries an integral part of the daily lives of local residents. The Program also called for these priests to promote the Prefecture's austerity program of frugality and increased household saving. These activities were hindered by the fact these same clerics were totally dependent on the local community for their livelihood, in accordance with the Buddhist vow of poverty (dana 檀). As anexample of this dilemma, the author cites the expectations expressed by ghetto community leaders who had formed the Yamato Doshikai 大和同志会 prefectural civil rights advancement association in 1912 that their communities' temples and priests would participate in the activities of the improvement program, while on the other hand condemning the temples as religious organizations economically exploiting their parishioners. It was during the First World War, in 1916, that Nara Prefecture's policy of state ideology indoctrination of ghetto residents began to include the introduction of Shinto shrines directly into ghetto communities ; for example, preparing designated sanctuaries on the grounds of existing temples, from which to worship Emperor Meiji from afar. This change in policy was an attempt to place the community leaders of each ghetto as the key enablers for local religious reform, in the search for a new set of beliefs by which to promote state ideology.
3 0 0 0 OA 「日本」という垣根なんて本当はないんだ
- 著者
- 関根 聡
- 出版者
- 一般社団法人 言語処理学会
- 雑誌
- 自然言語処理 (ISSN:13407619)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.2_1-2_2, 2010 (Released:2011-06-23)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 山田 武司
- 出版者
- 岐阜経済大学学会
- 雑誌
- 岐阜経済大学論集 (ISSN:03865932)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.65-79, 2008-09
- 著者
- 紙谷 年昭 中山 祐一郎 山口 裕文
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究. 別号, 講演会講演要旨 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- no.42, pp.112-113, 2003-04-19
希少種を多く含む水生雑草であるミクリ属(Sparganium L.)植物は水辺の植物群落の復元などにおいて自然修復措置の素材として注目されている。しかし,ミクリ属では種の同定の難しさもあって研究が進んでおらず,環境修復を効率よく進めるために必要な生活史や生育環境についての基礎的な情報が不足している。ミクリ属は根茎断片による分布拡大や根茎によるクローン成長によって群落を形成する。この性質は修復地における移植初期の群落形成に重要な役割を果すと考えられる。そこで本研究では,ミクリ属のミクリとオオミクリ,ヒメミクリを環境修復素材として用いる際の基礎的な知見を得るため,3種を同一環境下で栽培し,根茎の伸長様式をはじめとするクローン成長に関する形質を調査した。
3 0 0 0 IR 他者との関係調整志向と規範選好
- 著者
- 谷 芳恵
- 出版者
- 神戸大学
- 雑誌
- 神戸大学大学院人間発達環境学研究科研究紀要 (ISSN:18822851)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.9-14, 2012-03-30
3 0 0 0 OA 山形県庄内地方における信仰の重層性と競合に関する地理学的研究
- 著者
- 筒井 裕
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.265-281, 2016-09-30 (Released:2016-10-11)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
1980年代以降,日本の宗教地理学の分野では信仰圏に関する研究が盛んに行われるようになった.これらの先行研究においては,特定の信仰の分布が疎らになる要因を「類似した属性をもつ他の信仰対象」,あるいは「近隣にある他の信仰対象」との「競合」によるものと単純に解釈する傾向にあった.そのような中で,地理学者たちは特定の信仰の分布が様々な信仰との関わりの中でどのように成立したかについて実証的に考察を行ったり,信仰対象間の「競合」とはいかなる状況を意味するかについて検討したりすることはなかった.以上を受け,本研究では山形県庄内地方の代表的な霊山である鳥海山とその崇敬者組織(講)を事例として,崇敬者に対する聞き取り調査の成果をもとに上記の点の解明を試みた.
3 0 0 0 OA 初期堀辰雄における抒情 : 中野重治との関連において(<特集>抒情)
- 著者
- 杉野 要吉
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.8, pp.42-54, 1968-08-01