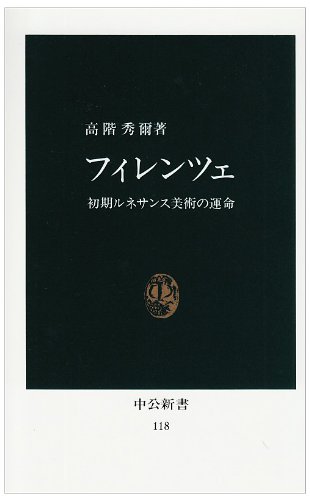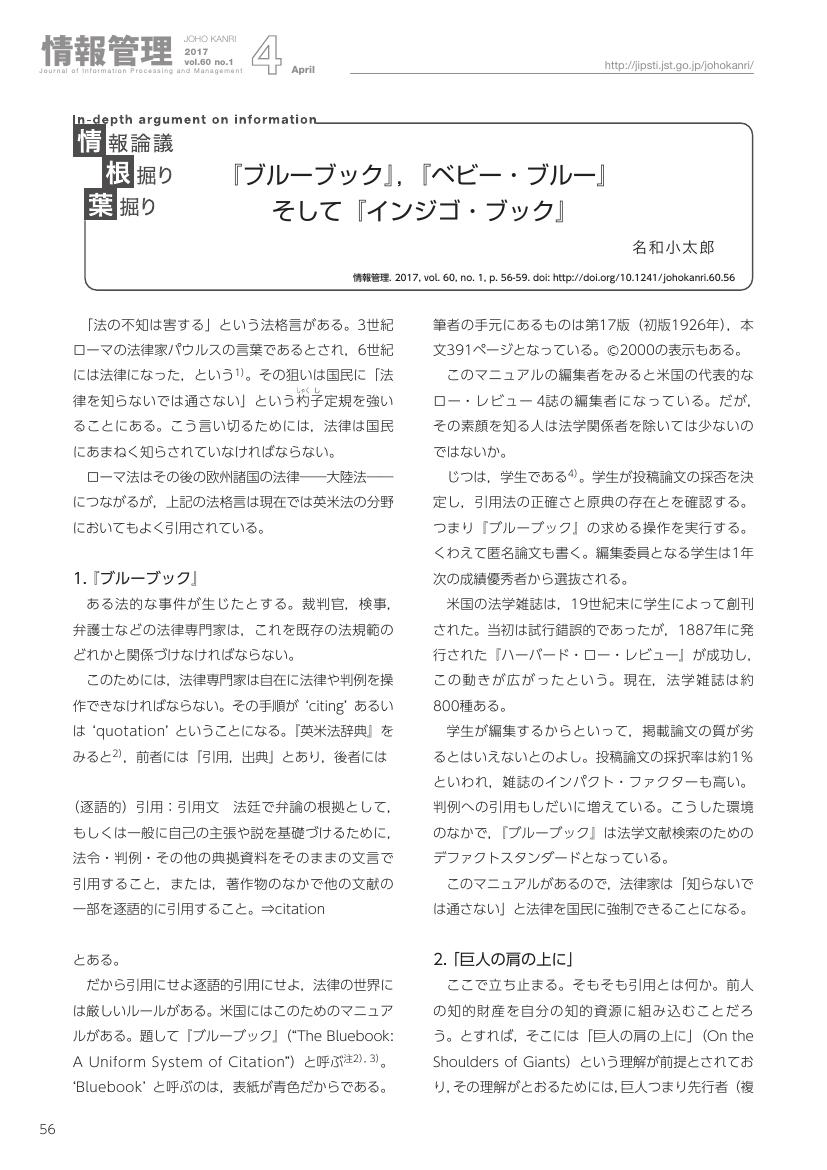3 0 0 0 想起と反復 : あるマプーチェの夢語りの分析
- 著者
- 箭内 匡
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:00215023)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.223-247, 1993-12-30
この論文は,チリ南部に住む先住民マプーチェの一老人のある語りの分析を通じて,今日のマプーチェの信仰に対する疑い,そんな疑いを持っていた頃にみたきわめて印象的な夢(「ヘリコプターの夢」),そしてその夢の本当の意味を理解するに至った数年前の儀礼での出来事,を回想する。筆者はまず,この語りの部分部分が喚起するイメージの連鎖と,全体の中で反復されるイメージを追ってゆくことにより,この語りが目指しているマプーチェ的な「真実」の全的な反復を跡付けする。そのあと,そうした反復の試みの中に含まれている差異を引き出して,老人の思考の中の新しいものを表出させる。筆者は,彼の思考の中にみられる,こうした伝統との間の差異と反復の運動を,今日,マプーチェの人々が自らの伝統を生きている姿の一端を示すものとして提出したい。
- 著者
- 鈴木 秀勇 スズキ ヒデオ Hideo Suzuki
- 雑誌
- 経済と経営
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.453-477, 1993-12-31
3 0 0 0 OA 音楽要素の分解再構成に基づく日本語歌詞からの旋律自動作曲
- 著者
- 深山 覚 中妻 啓 酒向 慎司 西本 卓也 小野 順貴 嵯峨山 茂樹
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.5, pp.1709-1720, 2013-05-15
日本語歌詞からユーザの意向を反映して多様な歌唱旋律を生成するための自動 作曲法があれば,歌のプレゼント,メールの歌い上げ,非専門家の創作支援な どが行える.本論文では初めに,自動作曲される旋律の多様性向上と音楽性の 保持の両立が難しいこ とを議論し,特に日本語歌詞から歌唱旋律を生成する際には,(1)音符数の変化 にかかわらず同じ印象を持つリズムの生成法と,(2)ユーザの意向,歌詞の韻律 と古典的な作曲法に基づ く制約条件を満たす音高列の生成法が必要であることを論じる.(1)については リズム木構造仮説に基づく方法,(2)については,動的計画法を用いた確率最大の音高系列 の探索により解決できることを示す.様々な制約条件のもと自動作曲した結果について専門家による評価を行ったと ころ,本手法によって古典的な歌唱旋律の作曲法からの逸脱の少ない旋律が生 成されることが示され,ユーザの意向を反映して多様な旋律を歌詞から生成す る方法として有効であることが分かった.
3 0 0 0 OA 島崎藤村に見るジャン=ジャック・ルソー(1) : 『告白』のもたらしたもの
- 著者
- 柏木 隆雄
- 出版者
- 大手前大学・大手前短期大学
- 雑誌
- 大手前大学論集 (ISSN:1882644X)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.65-82, 2012
明治以降の日本の近代社会に与えた思想的影響の大きさは、「おそらくマルクスに次ぐ位置を占め」、「特に『告白』を中心とする自伝は19世紀以降の近代文学の一つの方向を決定づけた」と小西嘉幸が述べるとおり、ルソーの『告白』は明治24年森鴎外によって独訳から『懺悔記』と題されてその一部分が新聞に訳載され、ルソー生誕200年を記念する形で石川戯庵の完訳『懺悔録』が大正元年に出て、たちまち多くの版を重ねた。同じく大正に入って他の自伝的作品も初訳が出て、ルソーの影響は従来の民権思想界から文学の世界に移って行く。おそらくは明治末年から覇を称えた自然主義文学の「告白」的志向もそれを迎える風潮を作ったに違いないが、その一方の雄である島崎藤村は、すでに英訳でルソーの諸作を知り、中でも『告白』にもっとも心を動かされた。 本稿では、藤村の『破戒』、『新生』といった従来影響が指摘されている小説を中心に藤村におけるルソー像を再検討する。
3 0 0 0 OA 鈴木中正編『千年王国的民衆運動の研究―中国・東南アジアにおける』
- 著者
- 土屋 健治
- 出版者
- 一般財団法人 アジア政経学会
- 雑誌
- アジア研究 (ISSN:00449237)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.61-70, 1983 (Released:2014-09-15)
3 0 0 0 フィレンツェ : 初期ルネサンス美術の運命
3 0 0 0 OA Open311による日本におけるオープンガバメントの新しい展望について
- 著者
- 吉田 博一
- 出版者
- 一般社団法人 経営情報学会
- 雑誌
- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2014年秋季全国研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.49-52, 2014 (Released:2015-01-30)
欧米で取り組まれているオープンガバメントは、透明性、住民参加、政府間及び官民の連携・協業の三原則で進められている。日本では、透明性にあたる行政データの民間開放(オープンデータ)のみに留まっているのが現状である。米国等では、官民の連携・協業の取組みとして、非緊急時の行政への通報電話番号である311をインターネットで投稿できるようにするOpen311の取り組みが進んでいる。この取組みにより、住民自らがそのデータを活用するアプリケーションを開発・提供することが可能になった。千葉市や大阪市で行われた実験を分析し、日本における連携の可能性と今後の展望を考察する。
- 著者
- 科学技術・学術基盤調査研究室
- 出版者
- 科学技術・学術政策研究所
- 巻号頁・発行日
- 2016-09 (Released:2016-09-01)
3 0 0 0 伏見宮文化圏の研究 : 学芸の享受と創造の場として
3 0 0 0 海水産魚類の行動と肝臓の組織生化学的相関に関する比較形態学的研究
- 著者
- 秋吉 英雄 井上 明日香 濱名 昭弘
- 出版者
- 島根大学
- 雑誌
- 島根大学生物資源科学部研究報告 (ISSN:13433644)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.7-16, 2001-12-20
- 被引用文献数
- 1
Background/Aims: Teleost livers are classified into two groups by histochemical properties in hepatocytes. One group contains the abundant glycogen, and the other contains the lipids in hepatocytes. The hepatic metabolism is in intimate connection of hepatic blood circulation and biliary pathway. We have studied on the correlation between behavior and histological components in livers by histochemical technique. Methods: Fifty species marine teleosts were collected from the local coasts of Shimane Peninsula and Oki Island. Livers were fixed by perfusion with paraformaldehyde, and observed by light microscopy in Osmium staining for lipid and PAS staining for glycogen. Sinusoids and vascular beds in blood capillaries were identified by immunohistochemistry for α-smooth muscle actin. Results: The lipid-rich livers had 13 fishes, the glycogen-rich livers had 33 fishes and both glycogen and lipid livers had 4 fishes. Hepatopancreas had 26 fishes. The glycogen-rich livers were well developed both the sinusoidal blood system and the bile ductal system. In contrast, the lipid-rich livers were poor developed of the sinusoidal capillaries. Conclusions: The present study indicates that there were differences in the pattern of hepatic histochemical components with different moving habits. A group of streamlined and well move fish has glycogen-rich liver, and a stocky body and poor move fish that live in the bottom of the sea, has lipid-rich liver.13;13;肝臓は生体を維持する上で中心的な役割を担う臓器で,身体へのエネルギ−供給と様々な消化吸収物質の処理を行う等,多様な代謝機能を有している.また,身体を構成するタンパク質の合成,糖原および脂質の貯蔵等の有機物質代謝,鉄・カルシウム等の無機物質代謝,ビタミンおよびホルモン代謝,胆汁産生,解毒排出など,その働きは多岐に渡っている.13; 一般に動物の運動能力は生体におけるエネルギ−産生系で作られたエネルギ−量に左右されており,常に遊泳している魚種は,海底にじっとしている魚種に比べ,消費エネルギ−量は大きい.このエネルギ−供給源となる糖・脂質の貯蔵様式はそれぞれの魚種の食性に直接影響をうけている可能性が高く(1−3),エネルギ−産生系に関連した肝細胞内における貯蔵物質の生化学的組成の質・量的な変異が各魚種間で存在することが推察される.一方,この貯蔵物質の質・量的変異は,成長過程(4)および繁殖(5,6),越冬(7)など魚の生活サイクルの中でも変動することが知られているが,その変動の幅と肝臓機能との相関関係は未だよく解っていない.13; 脊椎動物の肝臓は,一般に糖代謝すなわちグリコ−ゲンを主体としたエネルギ−代謝系を構築しているが,魚類から哺乳類に至る動物の中には,積極的に糖質から脂質転換を行って,トリグリセリド(TG)の形で肝臓に貯蔵し,このTG がβ−酸化を経てTCA サイクルに取り込まれて,エネルギ−代謝系を構築しているグループが存在する(8,9).このTG を主体とした貯蔵様式をとっている脂肪性肝臓は,病態時(10−12)におけるいわゆる脂肪肝(Fatty change)または脂肪変性(Fatty regeneration)とは明らかに異なっており,その成立要因はほとんど解明されていない.13; 脂肪性肝臓を有する代表的な動物種は軟骨魚類,硬骨魚類の一部であり,両棲類幼生であるオタマジャクシをはじめ,ヒト胎児期のある一定時期においても脂肪性の肝臓を有している(13).特に魚類の肝臓は,組織学的に主としてTG が貯蔵された脂肪性肝臓とグリコ−ゲンの貯蔵を主体としたグリコ−ゲン肝を有する群に2分され,それぞれの代謝系は肝内微小循環系(14)および胆管系(15−18)と密接に連動して機能している.13; 今回,海水産硬骨魚類50種の肝臓を用いて,魚類の行動と肝臓の組織生化学的特性の相関関係を解明することを目的に,光学顕微鏡によって形態学的に観察した.焦点は,肝臓内の生化学的特性とコレステロ−ルおよび脂質代謝に関与した胆道系と微小血液循環系の形態学的特徴に注目し,魚の生態および行動に関連した若干の考察を加えたので報告する13;
- 著者
- 小坂 亜矢子
- 出版者
- 大阪大学人間科学部社会学・人間学・人類学研究室
- 雑誌
- 年報人間科学 (ISSN:02865149)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.249-252, 2004
- 著者
- Li Yinxing Terui Nobuhiko
- 出版者
- 東北大学大学院経済学研究科
- 雑誌
- DSSR Discussion Papers
- 巻号頁・発行日
- no.63, pp.1-26, 2016-08
3 0 0 0 技能習得に関するベナーモデルのソーシャルワーカーへの適用
- 著者
- 吉川 公章 福田 俊子 村田 明子
- 出版者
- 聖隷学園聖隷クリストファー大学
- 雑誌
- 聖隷クリストファー大学社会福祉学部紀要 (ISSN:13481975)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.67-79, 2008
3 0 0 0 OA 福島県内外の一般市民および医師の福島第一原子力発電所事故後の放射線被曝に対する意識調査
- 著者
- 岡﨑 龍史 大津山 彰 阿部 利明 久保 達彦
- 出版者
- 学校法人 産業医科大学
- 雑誌
- Journal of UOEH (ISSN:0387821X)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.91-105, 2012-03-01 (Released:2017-04-11)
- 被引用文献数
- 2 7
福島第一原子力発電所(福島原発)事故後, 放射線被曝に対する意識について, 福島県内一般市民(講演時200名, 郵送1,640名), 福島県外一般市民(52名), 福島県内医師(63名), 福島県外医師(大分53名, 相模原44名, 北九州1,845名)および北九州のS医科大学医学部学生(104名)を対象にアンケート調査を行った. アンケート調査の回収率は, 福島県の一般市民は講演時86%と小児科医会を通じて郵送した50%と, 福島県外の一般市民91.3%および福島県内医師は講演時に86%回収, また福島県外の医師は, 相模原市85%および大分県は講演時に86%回収し, 北九州市はFAXにて17%回収となった. 福島原発後の放射線影響の不安度は, S医科大学医学部学生が12.2%ともっとも低く, 次に医師(福島県内30.2%, 県外26.2%)が低く, 福島県外一般市民(40.4%), 福島県内一般市民(71.6%)の順に高かった. 不安項目に関しては, S医科大学医学部学生や福島県医師は, 健康影響よりも環境汚染(食物や土壌汚染)に対し不安を持つ割合が高く, 福島県外医師や福島県内外の一般市民は健康被害および環境汚染の双方に不安を持っていた. 放射線の知識が高い人が, 現状に対する不安は少なく, 放射線知識の普及の必要性が結果として示された.
3 0 0 0 OA 草木錦葉集 緒巻,巻1-6
3 0 0 0 ガットマンモーネの諸様相
- 著者
- 谷口 真生子
- 出版者
- 大阪音楽大学
- 雑誌
- 大阪音楽大学研究紀要 (ISSN:02862670)
- 巻号頁・発行日
- no.53, pp.62-73, 2015-03-01
ガットマンモーネは、イタリアで品行の悪い子どもに対する脅かしのために引き合いに出される怪物のことである。ガットマンモーネの名称とその存在はディーノ・ブッツァーティの作品から知った。どうやらイタリア以外の国では見かけない怪物のようであり、さまざまな描写や解釈がなされているようである。本稿ではガットマンモーネという名称とその履歴をイタリアの怪物にからめて考察し、さらに数種類のガットマンモーネについてを記述し、ガットマンモーネとは何であるか、という到達目標に向かう途中経過を報告するものである。
3 0 0 0 OA 情報論議 根掘り葉掘り 『ブルーブック』,『ベビー・ブルー』そして『インジゴ・ブック』
- 著者
- 名和 小太郎
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.56-59, 2017-04-01 (Released:2017-04-03)
- 参考文献数
- 16
3 0 0 0 OA 介護保険料に関する一考察 : 公費方式導入の可能性
- 著者
- 柏崎 洋美
- 出版者
- 実践女子大学
- 雑誌
- 実践女子大学人間社会学部紀要 (ISSN:18800009)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.109-124, 2010-04-20