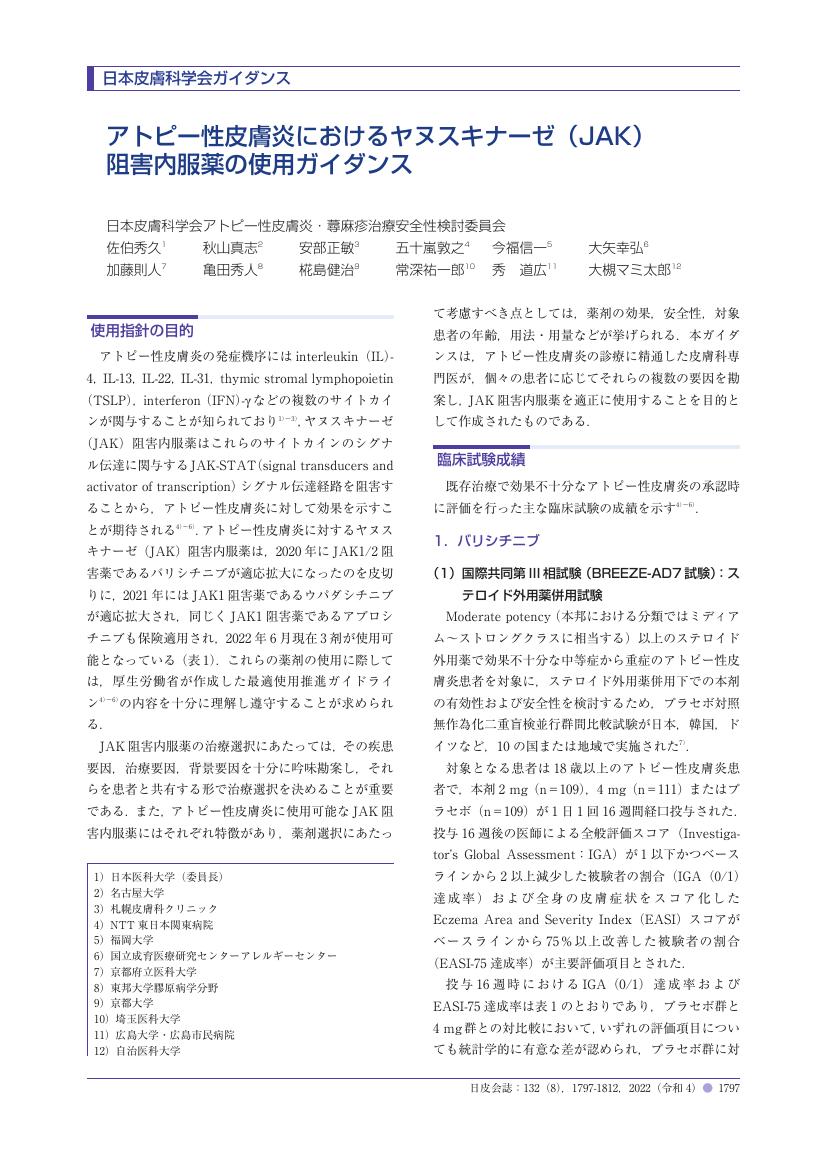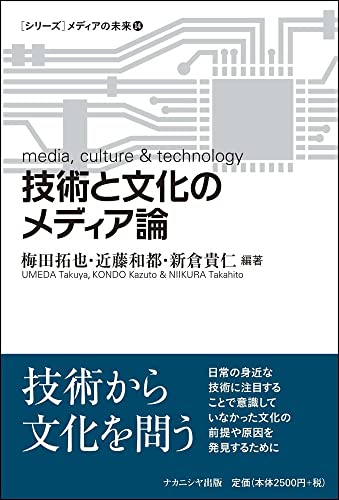2 0 0 0 超並列原理に基づく情報処理基本体系(成果とりまとめ)
重点領域研究・超並列は総括班と、4つの研究班、それぞれ(A)超並列アプリケーション班、(B)超並列プログラミング言語班、(C)超並列計算機用OS班、および、(D)超並列アーキテクチャ班で構成されている。本年度は成果とりまとめの年度として、各班がそれぞれの成果をリファインするとともに、最終のデモンストレーションに向けてそれぞれの成果や開発されたシステムの垂直的な統合化をを行った。総括班は研究全体の取りまとめを司り、約3か月ごとに会合を開き、各班の研究状況の確認や意見交換などを行った。本年度は、特に成果とりまとめ年度として、3月の第7回「超並列」シンポジウムの開催、その際のデモンストレーションの計画、成果をまとめた英文図書の出版、過去のシンポジウムの予稿集のCD-ROMの作成など、プロジェクトの成果を積極的に国内外にアピールしてゆく活動を幅広く敢行した。A班は、超並列計算における新たなアルゴリズムやアプリケーションの構築を目的とし、以下のような応用に対しB班が開発した超並列言語NCXなどへの移植を行い、各種の実験や性能評価、及び言語開発へのフィードバックを行った:・熱流体、渦発生のシミュレーション・弾性体の変形と応力の計算(境界要素法)・場の計算(境界要素法)とSORによるポアソン方程式求解 ・有限要素法における自動メッシュ分割・コンピュータグラフィックスにおける並列レンダリング・生態系(魚群)の自律型行動シミュレーション・並列遺伝的プログラミングによるニューラルネットの構造生成・実時間音楽情報処理システムB班では、超並列言語NCXの実装を改良すると共に、共有メモリ型計算機、分散メモリ型並列計算機、ワークステーションクラスタなど、種々なアーキテクチヤを持つ並列計算機への対応化を行った。また、幾つかの代表的なベンチマークプログラミングを移植し、それぞれの計算機上で性能評価を行った。更に、その他のMIMD型の超並列型プログラム言語V,ANET-LやABCL/fなどの並列計算機上での開発も行った。C班では、超並列計算機でのマルチユーザの保護と性能、複数のユーザのプログラミングモデルの提供、超並列用入出力機構のサポート、などの特徴を備えた超並列計算機用のOS・COSを設計・開発した。本年は、D班の作成する超並列計算機JUMPミ1へのCOSの実装に備え、並列ワークステーションをLANで接続した評価用の環境を用意し、その上にJUMP1ミ1のエミュレータとCOSマイクロカーネルをのプロトタイプを結合したCOSエミュレータを設計・実装した。また、D班の開発したプロトタイプボードJUMP-1/3(仮称)へのCOSエミュレータの移植を行った。D班では、様々な超並列計算のパラダイムに対応できる共有メモリ超並列計算機JUMPミ1の研究開発を遂行し、本年度は(1)主要コンポーネントであるメモリベースドプロセッサ(MBP)、キャッシュコントローラ、ネットワークル-タなどのを開発・デバッグを行い、(2)MBPをDSPでソフトウェアシミュレーションして他の部分はJUMP-1と同設計のシステムJUMP-1/2の設計・開発をし、(3)また、JUMP-1の特徴である高速プロセッサ間ネットワークRDTや高速シリアルI/OシステムStaff-Linkの開発・及びCOS開発のために、SUNワークステーションに接続して種々の実験が行える評価用ボードJUMP-1/3の設計・開発を行った。
2 0 0 0 「隠し売女」から「淫売女」へ―近世近代移行期における売春観の変容
2 0 0 0 OA WAIS-Ⅳ知能検査は獣医学生の進路選択に役立つか
- 著者
- 須賀 朋子 栗本 翔太
- 出版者
- 酪農学園大学
- 雑誌
- 酪農学園大学紀要. 人文・社会科学編 (ISSN:21870519)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.27-34, 2021-11
2 0 0 0 OA アトピー性皮膚炎におけるヤヌスキナーゼ(JAK)阻害内服薬の使用ガイダンス
2 0 0 0 OA 炎症性腸疾患のモニタリング―非侵襲性バイオマーカー―
- 著者
- 小林 拓
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, no.3, pp.229-234, 2021-03-10 (Released:2021-03-10)
- 参考文献数
- 35
炎症性腸疾患の診断や治療方針の決定において内視鏡はgold standardであるが,より非侵襲的なモニタリングの手法としてバイオマーカーが注目されている.便中カルプロテクチンは,炎症性腸疾患の診断,内視鏡的重症度との相関,治療効果判定,再燃予測など,さまざまな場面においてその有用性が報告されている.大腸癌スクリーニングに汎用されている便潜血反応検査も,特に潰瘍性大腸炎の内視鏡的活動性をもよく反映することが示されているほか,近年では血清leucine-rich glycoprotein(LRG),尿中プロスタグランジンE主要代謝産物(PGE-MUM)などの有用性も報告されている.
2 0 0 0 OA 男女別にみる事務職の数的特徴 : 「賃金構造基本統計調査」からの分析
- 著者
- 駒川 智子
- 出版者
- 北海道大学大学院教育学研究院
- 雑誌
- 北海道大学大学院教育学研究院紀要 (ISSN:18821669)
- 巻号頁・発行日
- vol.142, pp.73-83, 2023-06-26
2 0 0 0 OA ドイツの連邦親手当・親時間法 : 所得比例方式の育児手当制度への転換
- 著者
- 齋藤純子
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- no.232, 2007-06
- 著者
- 愛場 庸雅 森 淳子 小島 道子 梶本 康幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会報 (ISSN:24365793)
- 巻号頁・発行日
- vol.125, no.1, pp.43-49, 2022-01-20 (Released:2022-02-01)
- 参考文献数
- 14
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) では, 嗅覚障害, 味覚障害がよく見られる. その現状と病態を探るために, 2020年3月~2021年2月末までに大阪市立十三市民病院に入院した COVID-19 の中等症・軽症患者を対象として, 嗅覚味覚障害の頻度と転帰, およびその性別, 年齢による差について診療録に基づいて調査した. 嗅覚味覚障害の有無の評価が可能であった患者750名のうち, 嗅覚障害は208名 (27.7%), 味覚障害は216名 (28.8%) に見られ, うち181名 (24.1%) は嗅覚味覚両方の障害が見られた. 有症率に男女差はなかったが, 若年者では高く, 加齢とともに低くなっていた. 嗅覚障害患者の83%, 味覚障害患者の86%は, 退院までに治癒または軽快していた. 治癒に至るまでの平均日数は嗅覚障害9.4日, 味覚障害9.2日であった. 女性の改善率は男性よりやや低かった. COVID-19 の嗅覚障害は, 感冒後嗅覚障害と比較して, 年齢性別の頻度や改善までの期間が明らかに異なっているので, 両者の病態には違いがあることが推測された.
2 0 0 0 OA 「かわいい」を測る(<メカライフ特集>はかる)
- 著者
- 大倉 典子
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.1117, pp.850-851, 2011-12-05 (Released:2017-06-21)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1 1
2 0 0 0 OA 妊娠中絶に関する「自己決定権」 出生前診断をめぐって
- 著者
- 小島 妙子
- 出版者
- 日本法社会学会
- 雑誌
- 法社会学 (ISSN:04376161)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, no.80, pp.170-193, 2014 (Released:2021-05-04)
“The right to self-determination” about the abortion has been discussed as a part of the (disposal rights) ownership of the female body, but with the development of life science and improved technology of prenatal diagnosis, the opinion that women have no freedoms to choose the “quality” of children and do not allow the selective abortion have become to be supported. “The guideline for new prenatal diagnosis using maternal blood” which was published in March 2013, has the response inhibition about the “prenatal diagnosis,” saying that “a doctor need not inform actively to a pregnant woman about the new prenatal diagnosis,” and it has limited the pregnant women subject to inspection it, carrying out only in the accredited institution. Can the woman decide whether or not to give birth to a child, on the basis of prenatal diagnosis, and making the abortion on the grounds of failure of the fetus? This paper would reveal that the decision on abortion is related to the basis of self-definition, being guaranteed under the legal structure of “the freedom of the body” by Article 13 of the Constitution, and discussing the problems of the guideline for prenatal diagnosis and the possibility of the selective abortion.
2 0 0 0 OA 13年間介在した副鼻腔異物の1例 長期滞留した竹片異物
- 著者
- 堀 香苗 折田 洋造 竹本 琢司 藤田 浩志 山本 英一
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 補冊 (ISSN:09121870)
- 巻号頁・発行日
- vol.1994, no.Supplement69, pp.42-46, 1994-03-10 (Released:2012-11-27)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2 2
Foreign bodies in the paranasal sinus are not rare in the field of otorhinolaryngology. Here we report a case of a foreign body retained the paranasal sinus for 13 years.The patient was a 26-year-old woman whose chief complaint was postnasal drip. Thirteen years earlier, she had fallen from a bicycle into a bamboo thicket and a piece of bamboo had pierced the outer part of the right root of the nose. She had undergone operqtuon to remove the bamboo by an external incision, but a residual foreign body was observed by CT. We removed the foreign body by radical surgery on the paranasal sinus. Postoperative CT showed no residual foreign body and the course was good. There were no complications such as oculomotor disturbances before or after surgery.This case is reported as a patient with a long-term foreign body in the paranasal sinus. Some discussion of the literature also presented.
2 0 0 0 技術と文化のメディア論
- 著者
- 梅田拓也 近藤和都 新倉貴仁編著
- 出版者
- ナカニシヤ出版
- 巻号頁・発行日
- 2021
2 0 0 0 OA ICHガイドライン:指針は指針,目的を理解し,研究に活かそう
- 著者
- 田村 浩司
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.139, no.5, pp.207-210, 2012 (Released:2012-05-10)
- 参考文献数
- 13
ICHガイドライン(ガイダンス)は,より良い新薬をいち早く世界中の患者さんや医療現場に届けるために必要なデータを科学的かつ倫理的に取得あるいは利用するためのツールである.医療環境の変化や技術革新,時代の要請や経験の蓄積などを踏まえて,ガイドライン(以下,GL)の新規作成や改正が継続的に行われている.承認申請資料はICH GLに則って作成されなければならないため,創薬研究者は各自の担当分野に関するGLについて,定期的にフォローしておくといいであろう.
2 0 0 0 OA 桃と『古事記』
- 著者
- 彭 丹
- 出版者
- 法政大学国際日本学研究所
- 雑誌
- 国際日本学 = INTERNATIONAL JAPANESE STUDIES (ISSN:18838596)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.165-179, 2009-03-31
The Kojiki, Japan’s oldest book of history, was finished in 712, in the context of the nation’s foundation. In it, Amaterasu Ōmikami’s father Izanagi, the greatest god of the Yamato dynasty, is helped by three peaches. And Emperor Jinmu, the founder of the Yamato dynasty, is guided by a red crow. What is the significance of the peaches and the red crow in the Kojiki?Both the peaches and red crow were borrowed by the authors of the Kojiki from ancient Chinese mythology, where they are symbols of the sun god. In this fashion, Chinese sun worship is incorporated into this historical account of the Yamato dynasty. It was a strong desire of the authors of the Kojiki to acquire the grace of a sun god like that of the great dynasties of China. Moreover, the ambition of the authors of the Kojiki to assimilate the learning of Chinese civilization inspired them to use language that might even surpass it in excellence.
- 著者
- KUMAGAI Keichi
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- Geographical review of Japan series B (ISSN:18834396)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.1, pp.32-45, 2017-01-31 (Released:2017-01-31)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 1 1
The idea of place has been a common concern in human geography including among feminist geographers since the 1970s. While the question of place in Western cities has been critically discussed, place or place-making and displacement in the non-Western world have not been well developed. The author addresses the issue in terms of the idea of ‘fudo’ (milieu) which has been subject to particular attention in Japanese philosophy and geography since the 1930s, owing to popularization by Tetsuro Watsuji and Augustin Berque. In this paper, the author highlights the ideas of fudo through illustration of a grave historical case of suffering in Japan: Minamata Disease. Minamata Disease, caused by the consumption of fish contaminated by methyl mercury, emerged in the 1950s. This tragedy can be understood as the outcome of three scales of fudo relationship: 1) the interrelationship between the local marine ecosystem and fishers’ practice on the sea; 2) political and economic domination of Minamata city by the Chisso company; and 3) national sentiment and the human-environment relationship in Japan at the time. I highlight the narratives of two women in Minamata, Michiko Ishimure and Eiko Sugimoto, as cases that embody the local fudo relationship. Their narratives present essential interactions in Minamata between the sea, land, deities, embodied lives and survival, which collectively construct fudo. Simultaneously, these narratives illustrate Minamata, a place that now attracts people from elsewhere interested in curing their minds and bodies. By connecting divided localities, the local people’s movement reconstructed the fudo in Minamata that was once destroyed.
2 0 0 0 OA 裁判員裁判と控訴審の在り方 課題と展望
- 著者
- 酒巻 匡
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.395-403, 2015-07-30 (Released:2020-11-05)
2 0 0 0 OA Professor Quine on Japanese Classifiers
- 著者
- Takashi IIDA
- 出版者
- Japan Association for Philosophy of Science
- 雑誌
- Annals of the Japan Association for Philosophy of Science (ISSN:04530691)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.111-118, 1998-03-05 (Released:2009-03-26)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2 3
2 0 0 0 OA 『第二の性』を読むメルロ゠ポンティ
- 著者
- 酒井 麻依子
- 出版者
- 日本メルロ=ポンティ・サークル
- 雑誌
- メルロ=ポンティ研究 (ISSN:18845479)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.73-92, 2020 (Released:2020-12-09)
- 参考文献数
- 19
Le problème de la sexualité que Beauvoir a posé dans le Deuxième Sexe (1949) était aussi essentiel pour Merleau-Ponty dès la Phénoménologie de la Perception (1945). En outre, dans ses Cours de Sorbonne (1949-1952), présentant Le Deuxième sexe, il semble approfondir ses réflexions à propos de la sexualité et du corps sexuel de femme, qui sont encore lacunaires dans la Phénoménologie. Dans cette recherche, nous examinons comment les théories beauvoirienne et merleau-pontienne de la sexualité se recroisent. Nous mettons en évidence une différence entre leurs conceptions de la psychanalyse et du matérialisme historique. Après avoir examiné ces deux domaines « au sens large », Merleau-Ponty se réfère à l’étude culturaliste de Margaret Mead pour donner suite à la discussion beauvoirienne, et nie ainsi l’idée d’une « nature » permanente de femme (et de l’homme) qui n’aurait aucun rapport avec son environnement social et sa culture.
2 0 0 0 OA 禁錮刑以上の受刑者の選挙権制限 裁判所による判決の動向とその検討
- 著者
- 新井 誠
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.81-93, 2018 (Released:2021-07-16)
公職選挙法は,禁錮刑以上の受刑者の選挙権を制限しているが,これは「成年者による普通選挙を保障する」日本国憲法15条3項との関連において正当化されるのか。近年,これに関連する訴訟がいくつか提起され,それに対する判決が出されている。本稿は,こうした受刑者の選挙権制限をめぐる裁判所の判決動向とその検討を行う。これについてまず,選挙権制限と憲法との関係を示す。その後,在外国民の選挙権(行使)の制限を違憲とした最高裁平成17年判決と,その判断枠組みに関するその後の影響を踏まえつつ,近年見られた受刑者の選挙権制限に関する2つの訴訟(大阪訴訟,広島訴訟)の地裁判決,高裁判決を概説,分析する。そして,それらを比較検討する過程で,特に最近示された広島高裁判決の論理的問題について検討する。以上をふまえて受刑者の選挙権制限を論じるにあたっての今後の課題を示す。