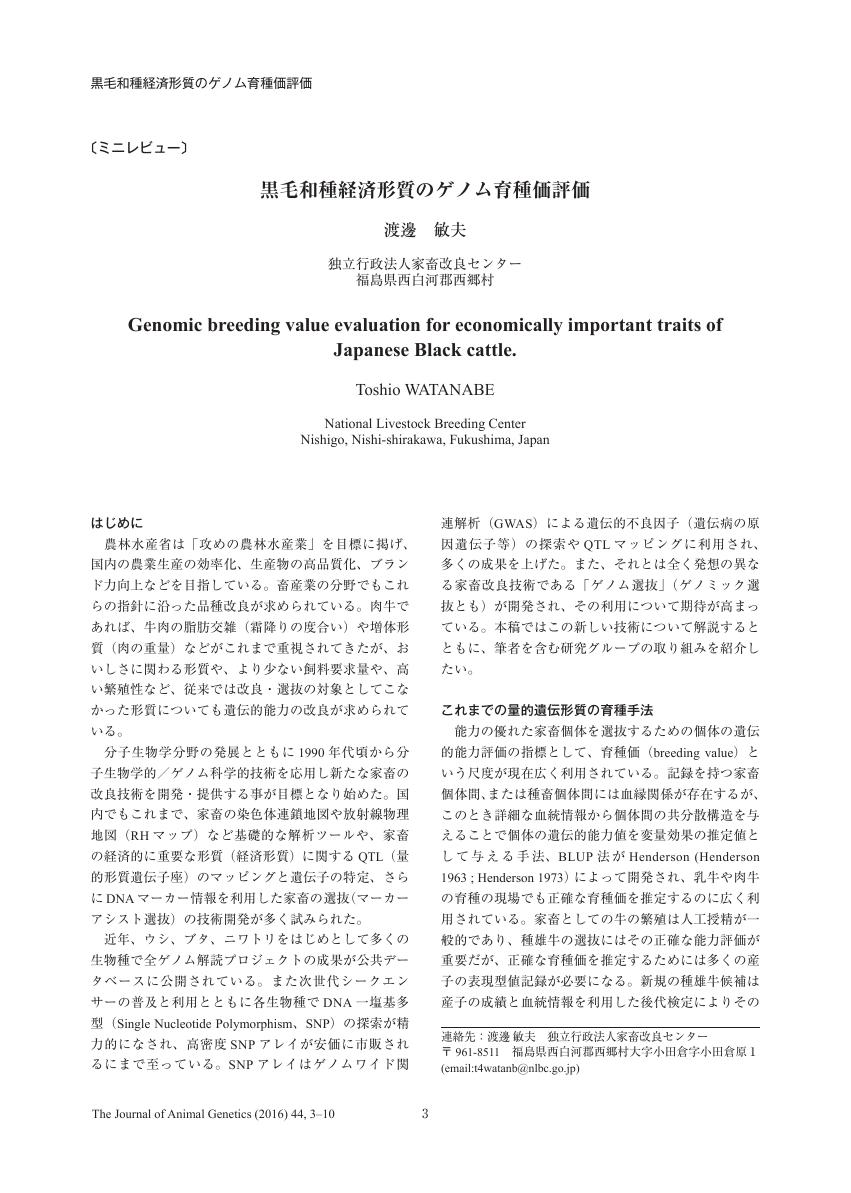- 著者
- 児玉 謙太郎 村上 久 阿部 廣二
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.6, pp.690-692, 2022-11-01 (Released:2022-11-01)
2 0 0 0 OA 嗅覚刺激療法への期待
- 著者
- 奥谷 文乃
- 出版者
- 日本鼻科学会
- 雑誌
- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.54-56, 2021 (Released:2021-04-26)
- 参考文献数
- 7
2 0 0 0 OA 国際社会での創造的研究開発
- 著者
- 長倉 三郎
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.21, 1986-01-01 (Released:2011-10-14)
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 怒りと怒りの近似概念の操作的定義の異同および怒りの操作的定義に影響を与えた要因
- 著者
- 中井 あづみ
- 出版者
- 明治学院大学心理学会
- 雑誌
- 明治学院大学心理学紀要 = Meiji Gakuin University bulletin of psychology (ISSN:18802494)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.13-30, 2012-03-30
怒りは一般的な感情体験である一方,攻撃性や敵意,いらいらなどの近似概念と混同され,定義が明確でなかった。本論では,怒りの操作的定義を,怒りの特性を説明する理論,怒りの生起を説明する理論から主に検討しつつ,類似概念と対照しながら展望することを目的とした。怒りは,感情,行動,認知の3つの成分の組み合わせであり,攻撃性や敵意の中心概念として考えることができる。怒りの測定は,怒りの特性,怒りの状態,怒りの表出から行うことができる。怒りの定義を方向付ける要因として,怒りと心身の健康との関係および対人関係に与える影響の2点が挙げられた。怒りのそれらへの負の影響については多く検討されているものの,怒りを健康や適応的な対人関係の維持増進に役立てるための実証モデルが見当たらないことが議論された。
2 0 0 0 OA アマミノクロウサギと共に暮らす島
- 著者
- 米山 太平
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.2, pp.114-115, 2022-07-30 (Released:2022-11-10)
2 0 0 0 OA ドイツ企業での博士課程
- 著者
- 佐藤 拓磨
- 出版者
- 公益社団法人 日本表面真空学会
- 雑誌
- 表面と真空 (ISSN:24335835)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.247-248, 2023-04-10 (Released:2023-04-10)
- 参考文献数
- 2
2 0 0 0 中世竹取説話分類の再検討(二) : 竹生篇
- 著者
- 飯田 さやか
- 雑誌
- 大妻国文 (ISSN:02870819)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.41-60, 2023-03-16
2 0 0 0 OA 黒毛和種経済形質のゲノム育種価評価
- 著者
- 渡邊 敏夫
- 出版者
- 日本動物遺伝育種学会
- 雑誌
- 動物遺伝育種研究 (ISSN:13459961)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1-2, pp.3-10, 2016 (Released:2016-02-05)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 6 10
2 0 0 0 遺伝子を刺激する磁性ナノ粒子の創製と血管形成療法への応用
- 著者
- 大矢根 綾子 QUAZI TANMINUL HAQUE SHUBHRA
- 出版者
- 国立研究開発法人産業技術総合研究所
- 雑誌
- 特別研究員奨励費
- 巻号頁・発行日
- 2015-04-24
本研究は、細胞への遺伝子導入機能と磁性を併せ示すDNA-磁性酸化鉄-リン酸カルシウム複合粒子を創製することを目的とする。研究代表者らはこれまでに、認可済みの医療用輸液を原料とする、安全性に優れたDNA-リン酸カルシウム複合層の合成技術を開発してきた。本研究では、この合成技術を利用し、磁性酸化鉄とDNAを複合担持させたリン酸カルシウム複合粒子を合成し、in vitroおよびin vivo機能評価を行った。平成28年度は、昨年度の基礎研究において獲得した合成指針を参考に、DNA(ルシフェラーゼのcDNAを含むプラスミド)および種々の濃度の磁性酸化鉄ナノ粒子(フェルカルボトラン)を添加したリン酸カルシウム過飽和溶液を用いて、DNA-磁性酸化鉄-リン酸カルシウム複合粒子を合成した。過飽和溶液への酸化鉄添加濃度が、得られる複合粒子のサイズ、表面ゼータ電位、酸化鉄およびDNA担持量に与える影響を明らかにし、細胞への遺伝子導入機能を最大化するための複合粒子の合成条件を見出した。最適化された複合粒子はサブミクロンサイズの大きさを持ち、合成後30分以内は分散状態を維持した。また、同複合粒子は、アモルファスリン酸カルシウムよりなるマトリックス中に多数の酸化鉄ナノ粒子を内包し、磁石の作用下において細胞への遺伝子導入機能を向上させた。さらに、マウス一過性脳虚血モデルを用いた予備的な動物実験を実施し、生体内における磁気ターゲティング応用の可能性について検討した。統計的処理に十分な数のデータは得られていないものの、複合粒子のin vivo磁気ターゲティング機能を示唆する予備的な結果が認められた。得られた複合粒子は、注射による生体内投与の可能なサイズ・分散性を持ち、遺伝子導入機能だけでなく、磁気ターゲティング機能を併せ示すと考えられることから、局所遺伝子治療用導入剤としての応用が期待される。
- 著者
- 鵜沼 亘 間邊 哲也 相原 弘一
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 A (ISSN:09135707)
- 巻号頁・発行日
- vol.J106-A, no.2, pp.40-56, 2023-02-01
本論文では,Wi-Fi RTT (Round Trip Time)を用いた測距ベースの位置特定手法であるLaterationにおいて,測距性能がどのようにして位置特定性能に影響を与えるかを調査し,調査により得られた結果を踏まえて策定したアクセスポイント選択方法に基づき,屋内廊下を対象とした位置特定性能評価を行っている.その結果,適切なアクセスポイントの選択により,今回の評価環境では,高品質な位置情報サービスに利用可能な性能が得られることを示している.また,アクセスポイントの数が減っても,位置特定性能を維持し,なおかつ,Wi-Fi RSSI (Received Signal Strength Indicator)を用いたScene Analysisと同程度若しくはそれ以上の性能が得られることを示している.更に,その他の条件においてもアクセスポイントの選択によって位置特定性能を改善できるという結果を得ている.このことから,アクセスポイント数が減ることによるコストの削減,データベースの構築・更新に要する労力の削減が期待できる.
- 著者
- 楊 思予
- 出版者
- 立命館大学ゲーム研究センター
- 雑誌
- REPLAYING JAPAN (ISSN:24338060)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.81-90, 2023-03
2 0 0 0 OA ペットボトル飲料における口内細菌数および大腸菌数の変化
- 著者
- 山田 節子 今野 祐子 三森 一司 出雲 悦子 大久 長範
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成18年度日本調理科学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.173, 2006 (Released:2006-09-07)
[目的]近年、ペットボトル飲料を日頃から水分補給のために利用する人が増えている。缶入り飲料に比べて、いつでも手軽に飲みたい分だけ飲め、そのうえキャップを閉めればどこへでも持ち運べるという利便性がある。また、消費者の健康志向も伴って、さまざまなペットボトル飲料の中でも、茶系飲料の売れ行きが好調である。しかし開栓後、直接口をつけて飲み、それを持ち運ぶことで様々な細菌に汚染されることが予測される。そこでペットボトル飲料に口内細菌と大腸菌を植え、どのくらい増殖および変化がみられるかを実験したので報告する。[方法]茶系飲料、スポーツドリンクおよびミネラルウォーターのペットボトル飲料に、自身の唾液より採取した口内細菌と、大腸菌をそれぞれ添加し、25℃で24_から_48時間保存したあと、菌数の変化をペトリフィルムで測定した。[結果]口内細菌を接種したところ、24時間後では、ブレンド茶は約、3.6倍、ミネラルウォーターは約、1.5倍と大きく増加する傾向が認められ、48時間後には無限大となった。ウーロン茶は、48時間後ではほぼ一定を保ち、緑茶は減少傾向を示した。PHが3.7と低いスポーツドリンクは口内細菌が減少する傾向にあった。大腸菌接種では、ウーロン茶、緑茶、ブレンド茶、スポーツドリンクは24時間で検出限界にまで減少し、ミネラルウォーターは一時的に減少したが、48時間後にも接種菌数の約、1/6が検出された。ペットボトル飲料が一般細菌に汚染された場合には、pHが中性に近づくに従い汚染が進行しやすく、pHが3付近では進行し難かった。
2 0 0 0 OA ハリーとニュートン : 航海学と天文学(<連載>科学史)
- 著者
- 鬼塚 史朗
- 出版者
- 日本物理教育学会
- 雑誌
- 物理教育 (ISSN:03856992)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.36-43, 1997-02-05 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 3
ニュートン力学が創始されたとき,フランスのデカルト派からは"ニュートン力学は,悪魔の算術に依拠した恣意的仮説である"と批判された。ニュートン力学の要諦は天界の力と地上界の力の統一にあったわけであるから,その観測的,実験的検証は不可欠であった。しかし,地球の半径や地球太陽間距離の測定ができなかった当時,その検証は困難を極めた。これらの値の確定に航海学は大きく寄与した。航海学の背後にはポルトガルとイスパニアの世界「2分割支配」がみえる。航海学が天文学の進歩をうながし,天文学の知見が近代科学成立の礎石となった。本稿では,ポルトガルとイスパニアを視座に航海の動機や目的を議論し,ニュートン力学の確立に寄与したハリーの足跡をたどる。
- 著者
- 鈴木 崇之
- 出版者
- 四日市大学
- 雑誌
- 四日市大学論集 (ISSN:13405543)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.39-59, 1991-09-25 (Released:2019-12-01)
2 0 0 0 OA 弁辰と加耶の鉄(セッション1. 加耶の鉄と倭国)
- 著者
- 東 潮
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, pp.31-54, 2004-02-27
『三国志』魏書東夷伝弁辰条の「国出鉄韓濊倭皆従取之諸市買皆用鉄如中国用銭又以供給二郡」,同倭人条の「南北市糴」の記事について,対馬・壱岐の倭人は,コメを売買し,鉄を市(取)っていたと解釈した。斧状鉄板や鉄鋌は鉄素材で,5世紀末に列島内で鉄生産がはじまるまで,倭はそれらの鉄素材を弁韓や加耶から国際的な交易によってえていた。鉄鋌および鋳造斧形品の型式学的編年と分布論から,それらは洛東江流域の加耶諸国や栄山江流域の慕韓から流入したものであった。5世紀末ごろ倭に移転されたとみられる製鉄技術は,慶尚北道慶州隍城洞や忠清北道鎮川石帳里製鉄遺跡の発掘によってあきらかとなった。その関連で,大阪府大県遺跡の年代,フイゴ羽口の形態,鉄滓の出土量などを再検討すべきことを提唱した。鋳造斧形品は農具(鍬・耒)で,形態の比較から,列島内のものは洛東江下流域から供給されたと推定した。倭と加耶の間において,鉄(鉄鋌)は交易という経済的な関係によって流通した。広開土王碑文などの検討もふまえ,加耶と倭をめぐる歴史環境のなかで,支配,侵略,戦争といった政治的交通関係はなかった。鉄をめぐる掠奪史観というべき論を批判した。
- 著者
- Daiichi Ogano Shawichi Kagayama
- 出版者
- Aquos Institute
- 雑誌
- 水生動物 (ISSN:24348643)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023, pp.AA2023-8, 2023-05-01 (Released:2023-05-01)
The Japanese pond turtle (Mauremys japonica) is endemic to Japan, inhabiting Honshu, Shikoku, Kyushu, and smaller islands. The ecology and distribution of M. japonica have been well studied in western Japan. In contrast, much less studies of this species have been performed in the Kanto and Hokuriku regions and its northern limit is not clear. Here, we report the discovery of a local population of M. japonica in a river in the Ibaraki Prefecture, representing the northern limit of its range on the Pacific Ocean side of Japan. This investigation revealed the inhabitation of over 50 turtles aged 0–10 years in the river. The predicted growth curves of both male and female turtles were comparable to those in other river and wetland populations previously reported, indicating that this population reproducing and growing normally. We also discuss future conservation strategies for this population.
2 0 0 0 OA 65年目のポートフォリオ選択理論
- 著者
- 本多 俊毅
- 出版者
- 日本ファイナンス学会 MPTフォーラム
- 雑誌
- 現代ファイナンス (ISSN:24334464)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.1-24, 2019-03-29 (Released:2019-03-31)
- 参考文献数
- 40
Markowitz[1952]によって平均分散ポートフォリオ理論が提案されて以来,およそ65年が経過した.平均分散モデルをそのまま実務で利用することは難しいし,最適化問題としても古典的な手法を用いた応用例のひとつに過ぎない.しかし,今日においても依然として重要な考え方であることは間違いない.本稿では,近年のファイナンス研究の展開を平均分散モデルと関連づけながら紹介し,資産市場の分析やポートフォリオ戦略の構築において,このモデルが現在でも非常に有効な方法論を提供していることを示してゆきたい.
2 0 0 0 OA ロシアのピアニズム : ワディム・サハロフ先生に聞く
- 著者
- 安原 雅之
- 出版者
- 愛知県立芸術大学音楽学部音楽学コース
- 雑誌
- ミクスト・ミューズ : 愛知県立芸術大学音楽学部音楽学コース紀要 = Mixed muses
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.37-46, 2010-03-31
2 0 0 0 IR 女子補導団の研究
- 著者
- Doaa SALMAN Eiji OOHASHI Adel Elsayed Ahmed MOHAMED Abd El-Raheem ABD EL-MOTTELIB Tadashi OKADA Makoto IGARASHI
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.6, pp.855-862, 2014 (Released:2014-07-01)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 11 13
The potential contamination of Toxoplasma gondii and Neospora caninum oocysts in the human environment is a concern from the public health viewpoint. However, estimation of their seroprevalences in humans cannot be performed in a manner that distinguishes between oocysts and tissue cysts as a source of infection. Rabbits are considered popular pet animals in Japan that can acquire natural infections by the aforementioned parasites only through the ingestion of oocysts. Therefore, this study was conducted to estimate the seroprevalences of T. gondii and N. caninum in pet rabbits in Japan as an indicator of the possible oocyst contamination in the environment surrounding human beings. Serum samples of 337 rabbits were examined by different serological methods. Enzyme-linked immunosorbent assays were performed to measure the titer of IgG and IgM antibodies. Samples revealed to be seropositive by ELISA were further analyzed by a latex agglutination test, Western blotting and an indirect immunofluorescence assay. The rates of seropositivity for T. gondii were 0.89% (3/337) and 0.29% (1/337) in IgG and IgM ELISA, respectively. SAG1 and SAG2 were detected as major antigens by the positive rabbit sera in Western blotting associated with strong staining observed by IFA in T. gondii tachyzoites. Regarding N. caninum, none of the serum samples showed a specific reaction in both Western blotting and the IFA. The results of this study indicate low seroprevalences of toxoplasmosis and neosporosis in pet rabbits in Japan, suggesting low oocyst contamination in the human environment.