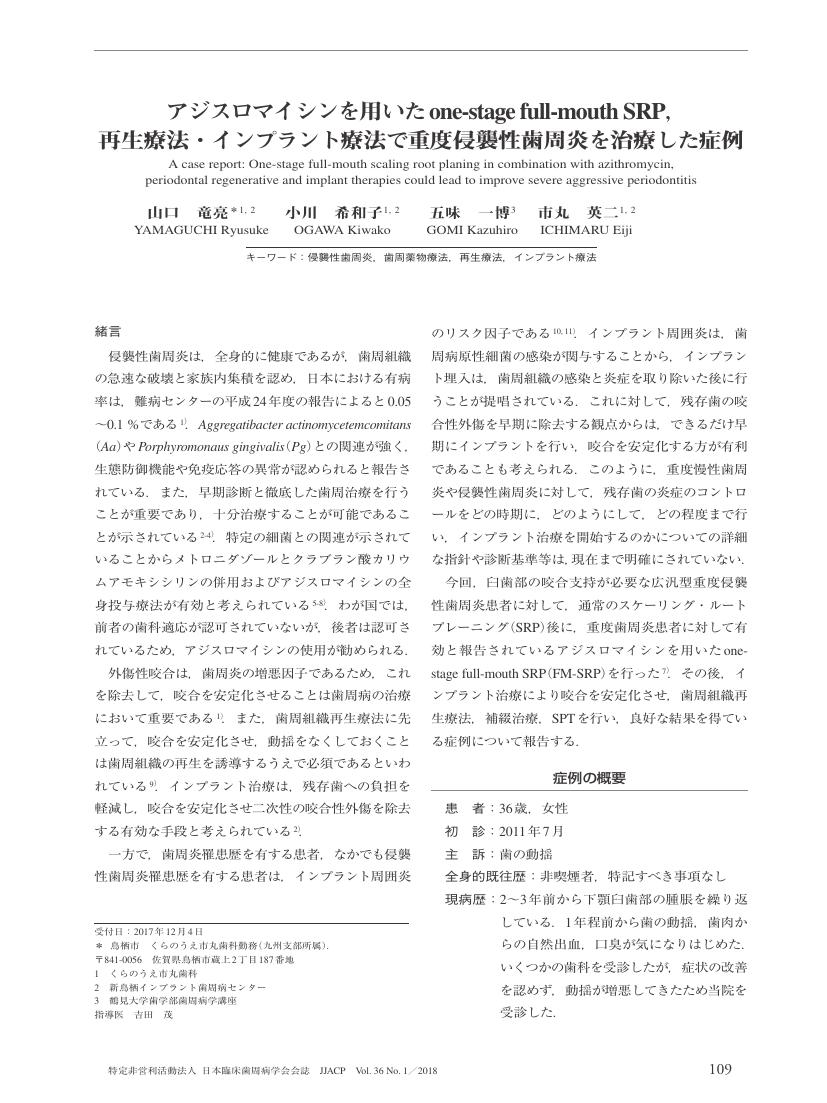2 0 0 0 OA 深宇宙探査機の自律化技術
- 著者
- 中谷 一郎 久保田 孝
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.9, pp.570-575, 2000-09-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- Sachiko Ono Tadahiro Goto
- 出版者
- Society for Clinical Epidemiology
- 雑誌
- Annals of Clinical Epidemiology (ISSN:24344338)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.3, pp.63-71, 2022 (Released:2022-07-01)
- 参考文献数
- 46
- 被引用文献数
- 5
Machine learning refers to a series of processes in which a computer finds rules from a vast amount of data. With recent advances in computer technology and the availability of a wide variety of health data, machine learning has rapidly developed and been applied in medical research. Currently, there are three types of machine learning: supervised, unsupervised, and reinforcement learning. In medical research, supervised learning is commonly used for diagnoses and prognoses, while unsupervised learning is used for phenotyping a disease, and reinforcement learning for maximizing favorable results, such as optimization of total patients’ waiting time in the emergency department. The present article focuses on the concept and application of supervised learning in medicine, the most commonly used machine learning approach in medicine, and provides a brief explanation of four algorithms widely used for prediction (random forests, gradient-boosted decision tree, support vector machine, and neural network). Among these algorithms, the neural network has further developed into deep learning algorithms to solve more complex tasks. Along with simple classification problems, deep learning is commonly used to process medical imaging, such as retinal fundus photographs for diabetic retinopathy diagnosis. Although machine learning can bring new insights into medicine by processing a vast amount of data that are often beyond human capacity, algorithms can also fail when domain knowledge is neglected. The combination of algorithms and human cognitive ability is a key to the successful application of machine learning in medicine.
- 著者
- 岩室 雅也 田中 健大 榮 浩行 安部 真 河野 吉泰 神崎 洋光 川野 誠司 河原 祥朗 岡田 裕之
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.29-36, 2022 (Released:2022-01-20)
- 参考文献数
- 18
【背景・目的】胃癌と非癌粘膜の白色球状外観(white globe appearance:WGA)の違いを明らかにする.【方法】胃WGA症例の内視鏡所見と臨床的特徴を後ろ向きに解析した.【結果】胃癌18例,非癌23例にWGAを認めた.胃癌症例は7例(38.9%),非癌症例は17例(73.9%)がプロトンポンプ阻害剤(proton pump inhibitor:PPI)を内服していた.病理学的には,胃癌症例(18例)のうち腺管の嚢胞状拡張は12例(66.7%),腺腔内壊死物質は12例(66.7%),壁細胞の過形成と内腔への鋸歯状の突出(parietal cell protrusion:PCP)は1例(5.6%)でみられた.一方,非癌症例のうち14例で生検が実施され,腺管の嚢胞状拡張は8例(57.1%),PCPは7例(50.0%)でみられたが,腺腔内壊死物質は指摘できなかった.非癌群において,自己免疫性胃炎を2例,内視鏡的粘膜下層剝離術後瘢痕を2例,腺腫を1例,ランタン沈着を1例,胃MALTリンパ腫を1例に認めた.【結論】胃癌粘膜と非癌粘膜ではWGAの成因は異なり,非癌症例ではPPI服用が関与している可能性が示唆された.
- 著者
- 吉田 尚弘 土山 寿志 中西 宏佳 辻 国広 冨永 桂 松永 和大 辻 重継 竹村 健一 山田 真也 津山 翔 片柳 和義 車谷 宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.12, pp.2449-2457, 2016 (Released:2016-12-20)
- 参考文献数
- 20
背景:白色球状外観(white globe appearance;WGA)は,狭帯域光観察併用拡大内視鏡検査(magnifying endoscopy with narrow-band imaging;M-NBI)で認識されることのある小さな白色球状物のことである.WGAは胃癌と低異型度腺腫を鑑別することのできる新しい内視鏡的マーカーであることが報告されている.しかし,胃癌と胃炎を含む非癌病変との鑑別にWGAが有用であるかどうかは不明である.方法:胃癌と非癌病変におけるWGAの頻度を比較するために,内視鏡検査を受ける予定の患者994人を対象とした前向き研究を計画した.すべての患者に対して白色光観察で胃癌が疑われる標的病変の有無を評価し,標的病変を認めた場合にはさらにWGAの有無をM-NBIで評価した.すべての標的病変に対して生検または切除を行い,病理学的に評価した.主要評価項目は胃癌と非癌病変におけるWGAの頻度,副次評価項目はWGAの胃癌診断における診断能とした.結果:標的病変として188病変(156人)が最終的に解析され,70病変が胃癌で118病変が非癌病変であった.WGAの頻度は,胃癌で21.4%(15/70),非癌病変で2.5%(3/118)であり,有意に胃癌で高かった(P<0.001).WGAの胃癌診断における正診割合は69.1%,感度は21.4%,特異度は97.5%であった.結論:胃癌におけるWGAの頻度は非癌病変のものに比べて有意に高かった.胃癌診断におけるWGAの特異度は高く,WGAの存在は胃癌診断に有用である.
2 0 0 0 OA 年齢による毛穴の目立ちの実態調査
- 著者
- 水越 興治 及川 みどり 伊藤 夕子 小林 和法 今村 仁 松本 克夫
- 出版者
- The Society of Cosmetic Chemists of Japan
- 雑誌
- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.4, pp.262-268, 2007-12-20 (Released:2010-08-06)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 5 2
本研究では10代から50代の, 248名の日本人女性の顔面を対象とし, 目立つ毛穴の実態調査を行った。その結果, 20代から30代で目立つ毛穴には角栓が存在し, 角栓の組成を分析した結果, タンパク質成分が約7割を占めることが判明した。一方40代以降では角栓が存在せずに開大した状態の目立つ毛穴が存在することが明らかとなった。また毛穴の開口部面積は10代から20代と, 30代から40代で各々急増するという, 2段階の変化を示す一方, 皮脂量との関連性は年齢とともに低下した。これらの結果から, 若年層では毛穴は角栓が詰まることによって目立ち, 年齢とともに毛穴の中に角栓が存在しなくなっても目立つ構造に変わっていくことが推察された。この調査結果から目立つ毛穴に対するケア方法は画一的ではなく, その性状, 年齢に応じて異なるべきであることが示唆された。
2 0 0 0 OA 行在所日誌
- 出版者
- [国立国会図書館] (私製)
- 巻号頁・発行日
- 1991
2 0 0 0 ねこのおばさんとよばないで
2 0 0 0 OA インターネット利用の不安に関する日米比較―在日外国人へのグループインタビュー調査―
- 著者
- 山本 太郎 植田 広樹 高橋 克巳 小笠原 盛浩 関谷 直也 小室 広佐子 中村 功 橋元 良明
- 雑誌
- 研究報告グループウェアとネットワークサービス(GN)
- 巻号頁・発行日
- vol.2012-GN-84, no.17, pp.1-8, 2012-05-10
我々は,インターネット利用に際する「安心」と「不安」に関する研究の一環として,9ヵ国の出身者を対象としたインターネット利用時の不安に関するグループインタビューを実施した.このインタビューは,日本を含む10ヵ国を対象とした同様の趣旨の国際電話調査結果の有用性の検討並びに各国の文化的・社会的背景を調査するために実施したものである.本稿は,日本との比較を交えつつ,前記グループインタビューの米国事例を報告するとともに,その結果により国際電話調査結果に対する考察を行うものである.
2 0 0 0 OA Metagenomic Analysis of Five Phylogenetically Distant Anammox Bacterial Enrichment Cultures
- 著者
- Mamoru Oshiki Yoshihiro Takaki Miho Hirai Takuro Nunoura Atsushi Kamigaito Satoshi Okabe
- 出版者
- Japanese Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Soil Microbiology / Taiwan Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Plant Microbe Interactions / Japanese Society for Extremophiles
- 雑誌
- Microbes and Environments (ISSN:13426311)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.ME22017, 2022 (Released:2022-07-09)
- 参考文献数
- 57
- 被引用文献数
- 8
Anaerobic ammonium-oxidizing (anammox) bacteria are slow-growing and fastidious bacteria, and limited numbers of enrichment cultures have been established. A metagenomic analysis of our 5 established anammox bacterial enrichment cultures was performed in the present study. Fourteen high-quality metagenome-assembled genomes (MAGs) were obtained, including those of 5 anammox Planctomycetota (Candidatus Brocadia, Ca. Kuenenia, Ca. Jettenia, and Ca. Scalindua), 4 Bacteroidota, and 3 Chloroflexota. Based on the gene sets of metabolic pathways involved in the degradation of polymeric substances found in Chloroflexota and Bacteroidota MAGs, they are expected to be scavengers of extracellular polymeric substances and cell debris.
2 0 0 0 OA アベマキ・コナラ薪炭林の10年周期による供給可能な薪エネルギー量
- 著者
- 金澤 洋一 上村 真由子 福井 美帆
- 出版者
- 日本景観生態学会
- 雑誌
- 景観生態学 (ISSN:18800092)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1_2, pp.105-111, 2009-06-30 (Released:2012-06-15)
- 参考文献数
- 12
アベマキ・コナラを中心とする里山薪炭林からの薪による家庭へのエネルギー供給量を推定した.兵庫県宍粟市の中山間地域に位置する集落において,聞き取り調査から「分け柴」と呼ばれる薪の採取システムを明らかにし,現地林分の伐倒による現存量調査から「分け柴」に必要な面積を計算した.またこれらの結果にもとづいて,「分け柴」によるエネルギー供給量を推定した.その結果,毎年,20~30 GJ程度が薪により供給されていたことがわかった.この量は,現在日本の一般家庭で消費されるエネルギー量である43 GJの半分あるいはそれ以上に相当し,現在でも「分け柴」によって日本の一般家庭が必要とするエネルギー量のかなりの部分を供給できることがわかった.「分け柴」として利用されていた面積は集落が利用してきた土地のごく一部で,本集落50世帯でも14 ha程度と推定され,現在残されている広葉樹林でも十分に足りることがわかった.
2 0 0 0 OA オランウータンのアンフランジ雄における交尾成功と繁殖成功:フランジ雄との比較から
- 著者
- 田島 知之
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 Supplement 第30回日本霊長類学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.66, 2014 (Released:2014-08-28)
オランウータンの雄には、二次性徴が発達した大型のフランジ雄と、未発達で小型だが生殖能力のあるアンフランジ雄の2形態が存在し、それぞれ異なる繁殖行動をとると考えられている。群れをつくらないオランウータンの生活様式において、アンフランジ雄は、フランジ雄が雌と近接していない間に交尾を試みていると考えられる。本研究では、行動観察からアンフランジ雄の交尾成功について調べるとともに、DNA分析を用いてそれが実際に繁殖成功に結びつくかどうかについて調べた。2010年から2012年にかけて、マレーシア・サバ州セピロク・オランウータン・リハビリテーションセンター周辺の森林内において、自由生活下のボルネオオランウータンの雄4頭(フランジ雄1頭、アンフランジ雄3頭)と、受胎可能な経産雌3頭を対象として個体追跡法による行動観察を1331時間おこなった。並行して、調査地で生まれた子ども8頭を含む28頭からDNA試料を採取し、12領域のマイクロサテライトマーカーを用いて父子判定をおこなった。フランジ雄は受胎可能な経産雌と最も長い時間近接していたが、3頭のアンフランジ雄も経産雌との交尾に成功していた。アンフランジ雄は未経産雌とも交尾していたが、フランジ雄では観察されなかった。受胎当時に調査地周辺に存在していた全てのアンフランジ雄の試料が採取できた7頭の子のうち、未経産雌による初産の子は1頭であり、アンフランジ雄が父親となったのはその1頭のみであった。フランジ雄が経産雌との間で高い繁殖成功を収めた一方で、アンフランジ雄はフランジ雄が不在の間に経産雌に対して交尾を試みるだけでなく、受胎可能性は低いと考えられるが未経産雌を交尾相手とすることでフランジ雄との競合を避け、繁殖成功を得ていることが示唆される。
- 著者
- 山口 竜亮 小川 希和子 五味 一博 市丸 英二
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本臨床歯周病学会
- 雑誌
- 日本臨床歯周病学会会誌 (ISSN:13454919)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.109-115, 2018-06-25 (Released:2022-03-29)
- 著者
- Samira R. Aili Phillip Lo Jeanette E. Villanueva Yashutosh Joshi Sam Emmanuel Peter S. Macdonald
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.1, pp.14-22, 2021-12-24 (Released:2021-12-24)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 1 10
Background:Frailty is prevalent in patients with heart failure (HF) and associated with increased morbidity and mortality. Hence, there has been increased interest in the reversibility of frailty following treatment with medication or surgery. This systematic review aimed to assess the reversibility of frailty in patients with HF before and after surgical interventions aimed at treating the underlying cause of HF. It also aimed to assess the efficacy of cardiac rehabilitation and prehabilitation in reversing or preventing frailty in patients with HF.Methods and Results:Searches of PubMed, MEDLINE and Academic Search Ultimate identified studies with HF patients undergoing interventions to reverse frailty. Titles, abstracts and full texts were screened for eligibility based on the PRISMA guidelines and using predefined inclusion/exclusion criteria in relation to participants, intervention, control, outcome and study design. In total, 14 studies were included: 3 assessed the effect of surgery, 7 assessed the effect of rehabilitation programs, 2 assessed the effect of a prehabilitation program and 2 assessed the effect of program interruptions on HF patients.Conclusions:Overall, it was found that frailty is at least partially reversible and potentially preventable in patients with HF. Interruption of rehabilitation programs resulted in deterioration of the frailty status. Future research should focus on the role of prehabilitation in mitigating frailty prior to surgical intervention.
2 0 0 0 OA 美容整形・美容医療を望む人々ー自分・他者・社会との関連から
- 著者
- 谷本 奈穂
- 出版者
- 関西大学
- 雑誌
- 情報研究 : 関西大学総合情報学部紀要 (ISSN:1341156X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.37-59, 2012-09-20
本論文は,美容整形や美容医療(プチ整形)が普及する現代社会において,それらの施術を受けたいと思う人々の①属性,②身体意識を明らかにする.また,以前行った調査で,美容整形を希望する理由に「自己満足のため」が最も多かったという結果をうけ,③美容実践が,身体を自分の所有物と感じてアイデンティティを再定義するような主体的な経験なのかも明らかにする.25~65 歳の男女800 人に調査票調査を行い,分析した結果は次の通り.①美容施術を望むのは男性よりも女性である.性別以外の,年代,世帯年収,学歴,既婚・未婚といった属性では有意差が見られなかった.②美容実践はあくまでも第一義的に「自分の心地よさ」(=自己満足)のために行われる.自分の心地よさという理由は,美容実践でない行為においても,美容実践を望む人が,望まない人より使用している.ただし,美容実践を望む人ほど「他者」の評価も求める傾向ももつ.③美容実践は,性別と世帯年収に規定される.また自己アイデンティティの再構築を目指すような主体的な行為というより,むしろ「外見の老化を感じる」こと,「身体に関する社会の常識を守るべきという考えを持たない」ことに規定される行為でもある.したがって,美容実践は,第一に「自分」という位相で語られる行為である.ただし,自分の心地よさの背後には「他者」の評価期待が含まれる.そして身体に関わる常識という意味での「社会」的影響は後景に退いている行為である.\nThis paper analyses people intending to undergo cosmetic surgery or cosmetic medical care in contemporary Japan. It aim to explore (1) their attributes, and (2) their body consciousness. The study found that the most popular motivation for cosmetic surgery was “self-satisfaction”. ーFollowing this, the study investigated (3) whether cosmetic practices can be regarded as subjective experiences, which promote the re-definition of identities. The results of this later survey (involving 800 informants) as follows.First, more women want to have cosmetic interventions than men. Other attributes, including age, academic background, income, and marital-status, did not show any significant influence on motivations. Second, some people want to have cosmetic interventions because of a sense of self-satisfaction, however, they tend to want positive evaluations from “others” too. Third, “awareness of aging” and “lack of a conviction to maintain common sense in relation to one’s body” are more likely to inderpin a desire to undergo cosmetic intervention than “the intention to reform self-identity.”Therefore, cosmetic interventions should be understood in terms of “the self,” positive evaluations by “the other,” and “self-comfort.” Although cosmetic practices are social practices, they are not significantly influenced by “the social.”
2 0 0 0 OA 実数値GAによるタンパク質立体構造の2層比較
- 著者
- 朴聖俊 高田 彰二 山村 雅幸
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.898-910, 2005-03-15
爆発的に増加するタンパク質立体構造を比較することは構造ム機能相関の解析にきわめて重要である.既存の立体構造比較手法はタンパク質全体を剛体として扱う.しかし,進化的に新しい機能を獲得する際にタンパク質構造は部分的特異的に変形を受けるため,剛体としての取扱いには限界がある.本論文では機能進化過程において,構造変形を受けにくいビルディングブロックと構造変形が顕著なループ部分が存在することを考慮に入れた立体構造比較手法を開発する.提案手法は部分構造比較と全体構造比較を2層で並列探索し,遺伝的アルゴリズムの集団探索性能を活用してタンパク質の機能進化における構造変形の柔軟性を可視化する.2層比較の基本的なアイデアと実装について説明したうえで探索アルゴリズムと評価関数の特徴と性能について述べ,構造-機能相関の解析ツールとしての有効性を示す.
2 0 0 0 OA 脳卒中患者における鏡像書字の検討
- 著者
- 井上 昌彦 若山 吉弘 野本 和彦 自見 隆弘
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.30-34, 1998-02-28 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 10
鏡像書字 (mirror writing) の出現機構, 責任部位は現在のところ不明であるが, 本態性振戦患者やパーキンソン病患者で高頻度にみられることから, 視床との関連を示唆する報告がある.今回, 脳卒中患者において, 視床と他の病変部での鏡像書字の出現率を調査し, 健常人および他の神経疾患患者での出現率と比較・検討した.対象は脳卒中31名 (視床10名, その他21名) , パーキンソン病34名, 本態性振戦18名, 健常人84名で計167名である.Mini-Mental Stateテストを施行し, 痴呆患者は除外した.それぞれ右手および左手で名前, 数字, アルファベット, 時計の図等を書かせた.書かれた文字の50%以上が鏡像パターンの場合を陽性とした.鏡像書字は, 脳卒中12.9% (視床10%, その他14.3%) , パーキンソン病26.5%, 本態性振戦33.3%, 健常人8.3%にみられた.パーキンソン病患者, 本態性振戦患者で頻度が高いことは過去の報告とほぼ一致したが, 脳卒中患者では視床と他の病変部位で, 鏡像書字の出現率に明らかな差を認めなかった.
2 0 0 0 OA グラフデータ処理に基づく意見集約とダイアログワークショップの統合手法
- 著者
- 芦野 由己 川本 達郎 安松 健
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第36回 (2022)
- 巻号頁・発行日
- pp.4Yin232, 2022 (Released:2022-07-11)
本研究は,定性的アプローチにて生成した自然言語データを,機械学習技術を活用したAskaにて分析を行い,結果を人が行った分析と比較することで有用性を評価し,自然言語データの分析手法の一つとして提言することを目的とした.方法については,創造的ワークショップ手法にて書き出した個々の考えの文章データをAskaに投稿し,各投稿データの相互評価を行った. そして, この関係データ(グラフデータ)の行列において要素の並び順を最適化してデータ集約を行い,このAskaとワークショップの結果を比較した.Askaによる分析結果は,文章に含まれる特定単語による単純な整理・分類ではなく,全体の意味を捉えたグルーピングが行われていることを確認した.人が行ったワークでは各々のデータの捉え方が加味されるため,機械学習よりも細分化されより抽象性の高いグルーピングが行われていた.しかしながら,Askaの結果は意見間の連続性がみられるとともにより概略的であり,全体像の把握が容易であった.このように,Askaと創造的ワークショップを統合的に用いることで, より合理的に意見を集約・理解することができることを示した.
2 0 0 0 OA 芸術作品から受ける感動についての構造分析
- 著者
- 田中 友理 加瀬 佳樹 安松 健
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第36回 (2022)
- 巻号頁・発行日
- pp.3Yin205, 2022 (Released:2022-07-11)
芸術分野においても人工知能による様々な作品が誕生しているが,「芸術家が人間であるからこそ,人間に伝わる感動があるのではないか」など疑問の声も少なくない.このような中で議論を進めるには,まず「人が芸術から受ける感動」とはどのようなものか理解していくことが重要である.そこで,本研究では「人が芸術作品から感動を受ける構造」を明らかにする.具体的には,「人生で"視覚を通し"最も感動した芸術作品」についての「感動要因」及び「人間的特性」を主な調査項目とした感動経験についてのアンケート調査を実施した.因子分析の結果,感動要因からは7つの因子,人間的特性からは8つの価値観が抽出された.更に,ベイジアンネットワークにて芸術作品情報,感動要因及び人間的特性等を構造化し,感度分析したところ,美学研究において論じられてきた美的範疇に関連する概念が,芸術作品情報,感動要因及び人間的特性等の関係性において定量的に表現されていることを確認できた.これらの美的類型と人間的特性の構造分析は,美的研究を裏付け,人間の芸術的感性を理解する基礎的知見の一つとなる.
2 0 0 0 OA 月の神話的表象 : 消された月を巡る一考察
- 著者
- 狩野 萌 Moe Kano
- 出版者
- 学習院大学文学部国語国文学会
- 雑誌
- 学習院大学国語国文学会誌 (ISSN:02864436)
- 巻号頁・発行日
- no.61, pp.66-81, 2018-03-15