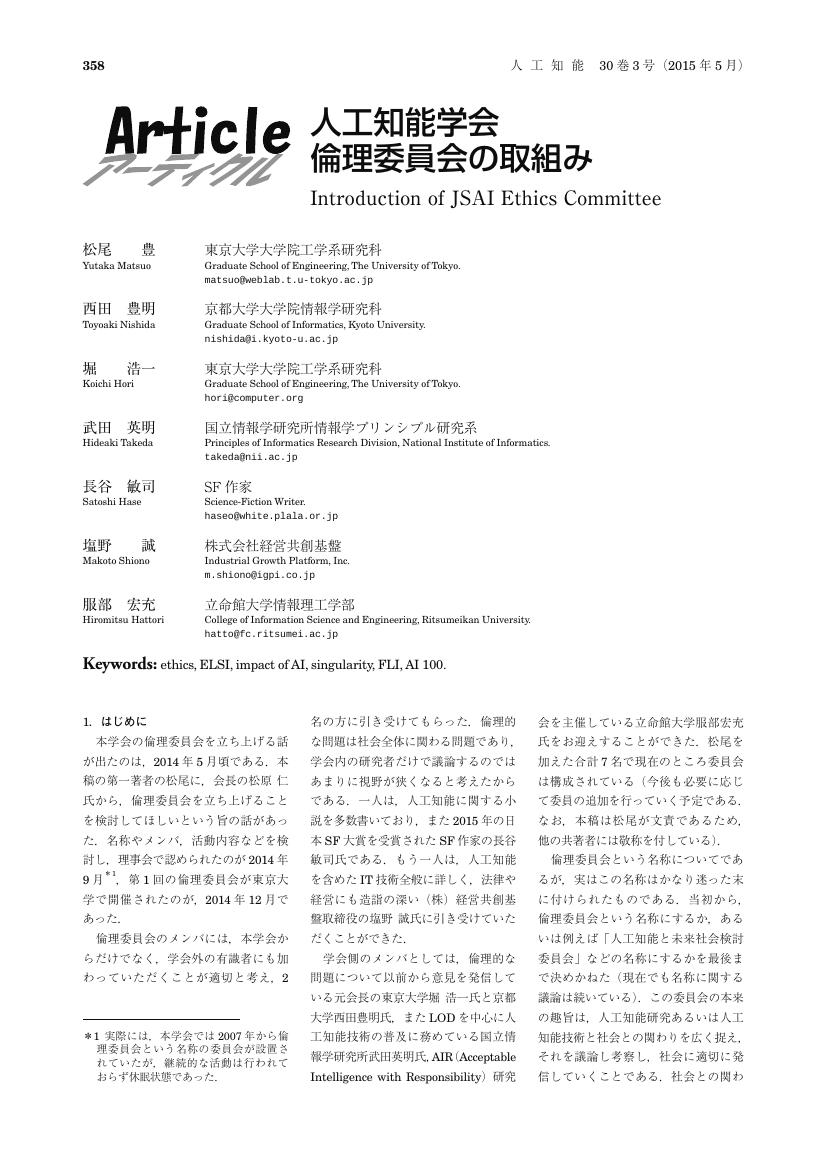2 0 0 0 OA 脳-機械インターフェイス研究開発の倫理実装
- 著者
- 福士 珠美 佐倉 統
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.10, pp.772-777, 2007-10-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 人工知能学会倫理委員会の取組み(アーティクル)
2 0 0 0 OA 各種甘味料がスポンジケーキに与える影響
- 著者
- 橘 庸子 〓
- 雑誌
- 和洋女子大学紀要. 家政系編
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.71-85, 1997-03-31
各種甘味料(オリゴ糖・低カロリー甘味料A・低カロリー甘味料B・低カロリー甘味料C・低カロリー甘味料D・低カロリー甘味料E・低カロリー甘味料F)を砂糖の代りに利用した時,これらの甘味料は砂糖と同様の調理効果を示すかを,卵白の起泡性に対する影響を取り上げ考察した。特に焼菓子であるスポンジケーキにおける調理効果について砂糖との比較において検討したところ次の様な結果が得られた。1.各種甘味料は砂糖と同様,卵白の起泡に安定性を与えた。更にオリゴ糖・低カロリー甘味料A・低カロリー甘味料B・低カロリー甘味料C・低カロリー甘味料D・低カロリー甘味料E・低カロリー甘味料Fは砂糖より卵白の起泡性を高める効果がみられた。2.低カロリー甘味料Fは共立て法の場合は起泡性を著しく低下させた。脂肪による消泡作用を受けやすい様に思われる。3.共立法によりスポンジケーキを作製した時オリゴ糖を用いたスポンジケーキは砂糖のものより表面の焼色もつきやすく,仕上り形態も良くない,内部の状態も味に於いても好まれなかった。4.低カロリー甘味料A・Cを用いたスポンジケーキは砂糖のものより表面の焼き色がうすく中央が山のように盛り上り,低カロリー甘味料A・Eと同様の外観である,内部の状態,味も同様に悪く全体的に好まれなかった。5.低カロリー甘味料Bを用いたスポンジケーキは唯一砂糖に次いで仕上り形態もよく,表面の焼色は砂糖に比べ,ややうすいが内部の状態はあまり良い評価ではない,甘味は砂糖に近いことから好まれた。6.低カロリー甘味料C・D・Eを用いたスポンジケーキは加熱による甘味の減少で非常に悪い評価を得ている。7.低カロリー甘味料Fを用いたスポンジケーキは他と同様の方法で作製した場合,外観,食感共に良い結果が得られなかった。甘味料を小麦粉に混ぜる方法で作製した場合は他の低カロリー甘味料と同様の外観を得ることが出来たが,いずれにしても良い結果はえられなかった。8.低カロリー甘味料を用いた焼き菓子であるスポンジケーキは製品としても品質が悪く又官能的にも好まれなかったことは砂糖として使用出来ない結果であった。しかし今回はこの方法でそうであったが,作り方,配合等が製品の性状を右左すると考えられたことから今後の検討課題にしたいと考える。9.低カロリー甘味料を用いたスポンジケーキは,砂糖と同程度の甘味になるように各甘味料を使用する場合は,保存性の低いことが観察された。
- 著者
- 中井 誠一 新矢 博美 芳田 哲也 寄本 明 井上 芳光 森本 武利
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.437-444, 2007-08-01 (Released:2007-09-14)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 11 14
The guidelines for the prevention of heat disorders during sports activities were established 13 years ago in Japan. Since then, various studies on preventive measures against heat disorders have been done, yielding new knowledge about its prevention. It has been reported that the incidence of heat disorders is high in children and the elderly, and heat acclimatization and clothing are the factors involved in this disorder. We proposed to lower the WBGT (wet-bulb globe temperature) limit for warning (discontinuation of hard exercise) from “28°C or more” to “25°C or more” (corresponding to an ambient temperature of 28°C) for non-acclimatized persons, children, the elderly, and persons wearing clothes covering the entire body. We also indicated that heat disorders can occur due to unpredictable causes, because the mechanism is very complicated.
2 0 0 0 デジタル・メディア・プラットフォームの憲法理論
- 著者
- 木下 昌彦
- 出版者
- 情報法制学会
- 雑誌
- 情報法制研究 (ISSN:24330264)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.16-33, 2021 (Released:2021-07-22)
The concentration of economic power threatens to erode not only consumer welfare, but also citizen welfare, such as the sustainability of democracies and the guarantee of individual freedom. The digital media platform companies that have emerged in recent years already have significant economic and media resources, and in addition to their economic dominance, they are also gaining political influence. If the present situation remains unchanged, the danger of a decline in citizen welfare could become apparent. This article argues that the introduction of new economic regulatory rules is necessary to prevent a decline in citizen welfare resulting from the concentration of economic power in digital media platform companies. The article then proposes three possibilities as new economic regulations: 1) strict application of conduct regulations in Antitrust Act, 2) separation of platforms and commerce, and 3) enactment of new regulatory Acts to ensure platforms neutrality and fair redistribution of their advertisement revenues.
- 著者
- 田端 真弓 山田 理恵
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- pp.1104250184, (Released:2011-05-02)
- 参考文献数
- 51
The purpose of this study is to clarify the transformation that occurred in a school (ryuha) of swordsmanship in the domain of Ohmura, Nagasaki, at the end of the Tokugawa period in Japan, focusing particularly on the invitation extended to Saito Kannosuke, one of the leading instructors in the Shinto Munen-ryu (school of swordsmanship), in 1854. This paper was based mainly based on two historical materials: Shugyo-chu Shohan Houmei-roku (1849) and Kuyo Jitsuroku (1849-1855). Ohmura Sumihiro, the 12th domanial lord, and Egashira Kandayu, his chief retainer, were tacitly interested in the utility of swordsmanship in Ohmura, and actively proposed the transformation of a school of swordsmanship. In 1854, they invited Kannosuke to act as the swordsmanship instructor. Kannosuke was the third son of Saito Yakuro, a famous instructor of the Shinto Munen-ryu, who had established and managed the Rempeikan, a swordsmanship school (dojo) in Edo. Saito Yakuro's eldest son, Shintaro, had embarked on a journey throughout the domains of Japan in order to train and practice against other warriors there. These training and practice were known as kaikoku-shugyo. Shugyo-chu Shohan Houmei-roku indicates that Shintaro visited many feudal domains, including Ohmura. Ohmura Sumihiro and Egashira Kandayu then became interested in the technique of the Shinto Munen-ryu, which was taught at the Rempeikan, because they considered it to be useful for actual fighting. Afterwards, they succeeded in inviting Kannosuke in 1854, and he became the instructor employed by the domain of Ohmura. His duty was to promote the training of the Shinto Munen-ryu with warriors in Ohmura. In 1855, the Itto-ryu and Shinkage-ryu instructors of swordsmanship were dismissed and forced to stop their teaching. According to Kuyo Jitsuroku, this transformation from the Itto-ryu and the Shinkage-ryu to the Shinto Munen-ryu occurred over a period of six years (from 1849 to 1855). It was brought about to achieve the political ambitions of Ohmura Sumihiro and Egashira Kandayu.
2 0 0 0 OA <聞き取り記録> 川合一良氏・葉子氏 同学会・原爆展・女子学生懇親会等について
- 著者
- 川合 一良 川合 葉子 西山 伸
- 出版者
- 京都大学大学文書館
- 雑誌
- 京都大学大学文書館研究紀要 (ISSN:13489135)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.59-84, 2007-01-31
2 0 0 0 OA 施工入門 ①コンクリート施工の変遷(総論)
- 著者
- 松岡 康訓 新藤 竹文
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.10, pp.10_50-10_56, 2009 (Released:2012-03-27)
- 参考文献数
- 18
2 0 0 0 OA 西周の「哲学」と東アジアの学問
- 著者
- 高坂 史朗 Shiro KOHSAKA
- 雑誌
- 北東アジア研究 (ISSN:13463810)
- 巻号頁・発行日
- vol.14-15, pp.151-167, 2008-03-31
2 0 0 0 光子の窓:イグアノドンの卵
- 著者
- 三木鮎郎
- 巻号頁・発行日
- vol.130, 1960-10-30
2 0 0 0 OA 本山コレクション金石文拓本
- 出版者
- 関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター
- 雑誌
- NOCHS Occasional paper
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.8-17, 2008-11-10
第4回文化遺産学フォーラム関連展示「企画展 なにわ・大阪の文化力~大阪文化遺産学の源流と系譜を辿る~」(関西大学博物館、平成19年11月24日~12月1日)
- 著者
- 土井 理美 横光 健吾 坂野 雄二
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.45-55, 2014-01-31 (Released:2019-04-06)
- 被引用文献数
- 4
本研究の目的は、Acceptance and Commitment Therapy(Hayes et al.,1999)の文脈で用いられる「価値」の概念を多面的に測定することが可能であるPersonal Values Questionnaire II(PVQ-II;Blackledge et al.,2010)の因子構造、内的整合性、妥当性を検討し、PVQ-IIがより活用されるよう精緻化を行うことであった。大学生、大学院生、一般成人388名を対象に項目分析、探索的因子分析を実施した結果、1項目が削除され、PVQ-IIは8項目3因子構造であることが示された。また内的整合性、妥当性ともに十分な値が示された。そして、413名を対象に確認的因子分析を実施した。その結果、第1因子と第3因子の相関を仮定した3因子構造モデルの適合度は十分な値を示していた。その結果、PVQ-IIの標準化に関するデータを追加し、わが国でもPVQ-IIの利用が可能であることが明らかとなった。今後は、PVQ-IIをわが国においても普及させていくために、わが国におけるPVQ-IIの特異性を明らかにしていく必要がある。
2 0 0 0 OA 感染症科のない地域基幹病院におけるカンジダ血症の現状と課題
- 著者
- 村上 穣 小松 裕和 高山 義浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.18-23, 2011-05-30 (Released:2011-08-18)
- 参考文献数
- 12
本邦ではいまだ感染症科のない医療機関が多く,そうした医療機関では院内感染への対応は各科の担当医師に委ねられている。とくにカンジダ血症のような重篤な感染症では必ずしも適正な診療が行なわれていないことが考えられる。我々は感染症科のない地域基幹病院である佐久総合病院において,2004年から2008年までに血液培養陽性でカンジダ血症と確定診断された全43例を対象に,カンジダの菌種,背景因子,治療の内訳,合併症,予後,米国感染症学会 (IDSA) ガイドラインの遵守率についてretrospectiveに検討した。カンジダの菌種はCandida albicansが最多であった。背景因子としては患者の84%に抗菌薬が投与され,79%に中心静脈カテーテル (CVC) が留置されていた。経験的治療としてはfosfluconazoleとmicafunginがそれぞれ35%を占めていたが,23%の患者は抗真菌剤が投与されていなかった。CVCが留置されていた34例中,診断後に抜去されたのは23例であった。カンジダ眼内炎の検索目的で眼科紹介が行なわれたのは42%であった。IDSAガイドラインの遵守率は42%で,カンジダ血症発症から28日後の死亡率は33%であった。本調査結果により当院ではカンジダ血症の診療について課題が多いことが明らかになったが,このような状況は感染症科のない地域基幹病院の一般的な現状と考えられる。今後はカンジダ血症に対するガイドラインに沿った適正な診療が行なわれる体制を,感染症科のない地域基幹病院でも定着させてゆくことが必要である。
2 0 0 0 OA 代謝ストレス応答 心筋の糖毒性と脂肪毒性
- 著者
- 都島 健介
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.12, pp.1383-1388, 2015 (Released:2016-12-15)
- 参考文献数
- 20
2 0 0 0 文検英語科予備試験合格者一覧(回,氏名,族籍,願書進達地方庁)
- 著者
- 茂住 實男
- 出版者
- 拓殖大学
- 雑誌
- 拓殖大学語学研究 (ISSN:13488384)
- 巻号頁・発行日
- no.112, pp.201-255, 2006-09
2 0 0 0 大田原市史
- 著者
- 大田原市史編さん委員会 編
- 出版者
- 大田原市
- 巻号頁・発行日
- vol.後編, 1982