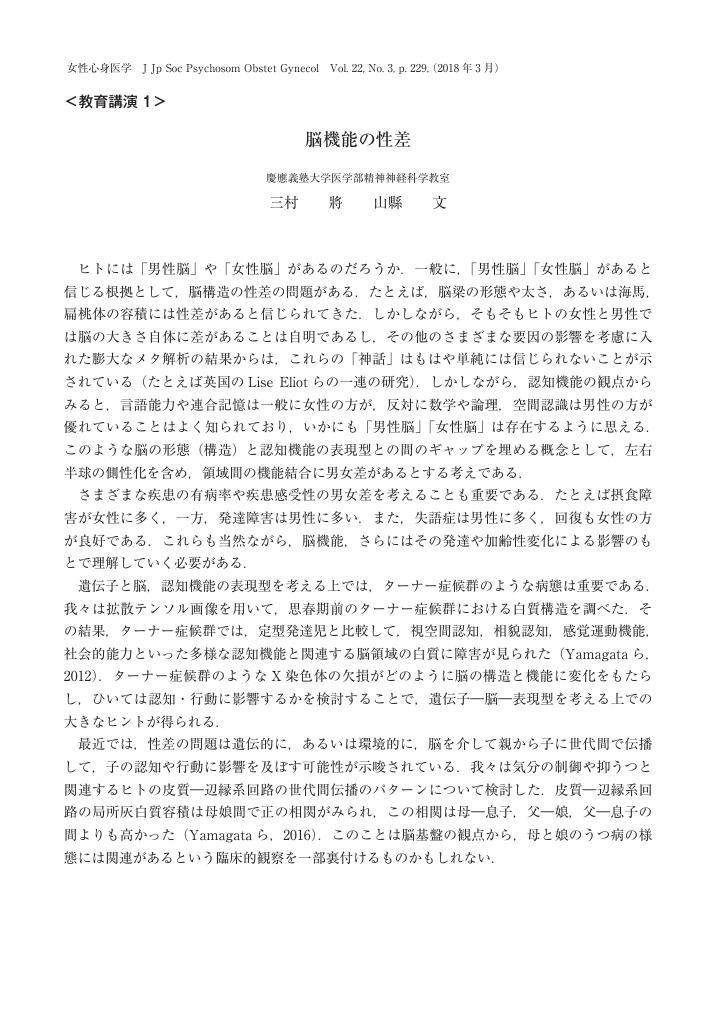2 0 0 0 OA 瞑想中に現れる光のイメージ ─ 上座部仏教における観の付随的煩悩への対処法をめぐって ─
- 著者
- 林 隆嗣
- 雑誌
- こども教育宝仙大学 = Bulletin of Hosen College Of Childhood Education
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.1-12, 2022-03-02
2 0 0 0 OA 音の高さに関する生理・心理学と楽器のチューニング
- 著者
- 大串 健吾
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.153-158, 2003-03-01 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 10
- 著者
- 綾塚祐二 暦本純一 松岡 聡
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)
- 巻号頁・発行日
- vol.1996, no.62(1996-HI-067), pp.23-30, 1996-07-11
ハードウェア技術の進歩は高機能な計算機を携帯可能にし、ユーザと現実世界の間に常に計算機が介在することが可能になってきている。一方、計算機上の世界ではWolrd Wide Webが普及し、多種多様な情報をユーザが手軽に得ることができる。これらの情報は現実世界のオブジェクトに関するものも多いが、その関連性は現実世界のオブジェクトからは自明ではない。本研究では現実世界のオブジェクトとWWWの世界との連携をとることを目的とするハイパーメディアシステムを提案する。具体的には、携帯型の計算機と、現実世界のオブジェクト群に添付されたIDを用い、現実世界のオブジェクトからWWW上の情報へ繋がるリンクを構築する。
2 0 0 0 IR 介護保険制度改革がもたらした介護の変化
- 著者
- 鈴木 奈穂美
- 出版者
- 専修大学社会科学研究所
- 雑誌
- 専修大学社会科学研究所月報 = The Monthly Bulletin of the Institute for Social Science Senshu University (ISSN:0286312X)
- 巻号頁・発行日
- no.685, pp.55-81, 2020-07-20
2 0 0 0 情報なき戦争指導 : 大本営情報参謀の回想
2 0 0 0 IR 旭日旗問題に見る韓国ナショナリズムの新側面
- 著者
- 木村 幹
- 出版者
- 神戸大学大学院国際協力研究科
- 雑誌
- 国際協力論集 (ISSN:09198636)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.21-46, 2019-07-31
2 0 0 0 IR 介護福祉士の「寄り添い」に関する探索的検討
- 著者
- 井川 純一
- 出版者
- 大分大学経済学会
- 雑誌
- 大分大学経済論集 (ISSN:04740157)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.1, pp.25-40, 2021-07
2 0 0 0 OA 正倉院籍帳に読まれる家父長像の歴史知的二類型
- 著者
- 石塚 正英
- 出版者
- 特定非営利活動法人 頸城野郷土資料室
- 雑誌
- 頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要 (ISSN:24321087)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.3, pp.1-16, 2022 (Released:2022-04-09)
2 0 0 0 OA 耳鼻咽喉科と漢方療法
- 著者
- 武藤 二郎
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.3, pp.325-336, 1989-03-01 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 76
Chinese Medicine helps to normalize and stabilize autonomic nervous system imbalances and endocrine and metabolic disorders.In the field of oto-rhino-laryngology, Chinese Medicine is very effective when it is applied according to the traditional Chinese medical diagnoses for: 1) Abnormal sensation in the pharynx in patients with autonomic dysfunction. 2) Chronic inflammation. 3) Recurrent otitis media and pharyngitis. 4) Tinnitus, vertigo and dizziness with circulatory disturbances.
- 著者
- 荒川 いつみ 小栗 卓也 中村 友紀 櫻井 圭太 湯浅 浩之
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.22-26, 2022 (Released:2022-01-28)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
73歳女性.夜間睡眠中の大声の寝言や日中覚醒時の異常言動,会話中に急に反応が乏しくなるエピソードが月単位で相次いで出現.他院にてレビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies,以下DLBと略記)と診断されるも,これらの頻度が徐々に増加したため,当院にて精査入院.終夜睡眠ポリグラフィの“筋活動の低下を伴わないレム睡眠”および18F-FDG PETの辺縁系糖代謝亢進より,レム睡眠行動異常症を合併した辺縁系脳炎と診断.ステロイドパルス療法2コース実施後,症状は徐々に軽減した.本例は後に血清抗voltage-gated potassium channel(VGKC)複合体/leucine-rich glioma-inactivated protein 1(LGI1)抗体陽性が判明した.本抗体関連辺縁系脳炎は臨床像がDLBに重なることがあり,診断に際し注意が必要である.
2 0 0 0 OA 長崎稲佐ロシア海軍基地をめぐる明治初期日露関係 : 借地交渉とその意義
- 著者
- 醍醐 龍馬
- 出版者
- 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター
- 雑誌
- スラヴ研究 (ISSN:05626579)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.45-70, 2021-09-08
In 1875, soon after the sealing of the St. Petersburg Treaty stipulating the exchange of Sakhalin and the Kurill Islands, Japan and Russia agreed on a land lease of Inasa Village in Nagasaki to the Russian navy. This was a juridical confirmation of the Russian Squadron’s long-standing practice of using this locality as its winter base, which would remain intact until the outbreak of the Russo-Japanese War in 1904. In fact, this agreement brought about stability of the bilateral relationship, serving as a prerequisite for Japan to embark on its subsequent Korean policy. This article attempts to contextualize this particular land lease in the increasingly entangled relationship between Japan and Russia. Nagasaki’s importance as a resort for the Russian navy increased, with its failure to obtain Tsushima as a strategic base under pressure from the British in 1861 and with its pivotal port moving from Nikolaevsk-on-Amur to Vladivostok in 1871. Against this backdrop in 1870 the Russians succeeded in renting a piece of land Hiradogoya for ten years by directly negotiating with the landowners and the Nagasaki administration. Two years later, when Grand Duke Alexei Alexandrovich visited Japan, he found it inconvenient to maintain a naval hospital and dock in Hiradogoya. This led one of his attendants, vice admiral of the navy Constantin Possiet, to propose to the Japanese government the Maruoyama foothills as an alternative for the Russian navy base. The Japanese government in turn rejected this proposal for two reasons. First, the Japanese navy was afraid that the occupation of this strategically important location by the Russian navy would raise security concerns. Second, the increase of places of mixed residence outside the fixed enclaves could threaten Japanese sovereignty. Undaunted, K. V. Struve, the Russian minister in Japan, tried to renegotiate in 1874, arguing that the lease of Maruoyama would have a positive effect on Russo-Japanese relations. However, the Japanese navy was a staunch opponent to this deal; it even purchased the disputed land for an admiralty house in haste so as to forge a fait accompli. Ultimately, the Japanese government was forced to propose an alternative land lease in Inasa in exchange for the old one in the same locality. In 1875, after Struve’s on-the-spot inspection of the proposed site along the coast of Nagasaki Bay, the Russian navy and a local landowner Shiga reached an agreement. The timing was crucial: this was right after the sealing of the St. Petersburg Treaty. While the establishment of a navy base in Inasa in the following year caused anxiety among the Japanese and the British, the Russians began to make efforts to maintain their friendship with Japan in order to keep this base. Together with the Maria Luz case in 1875, where the tsar worked as an arbitrator of the dispute between Japan and Peru, this Inasa controversy was a significant opportunity buttressing an improving bilateral relationship under the St. Petersburg Treaty. While the Russian Squadron’s utilization of Nagasaki as its winter base since the end of the Edo era had been possible thanks to the relatively good relationship between the two countries, the foundation of the Russian squadron’s berth in Inasa immediately following the St. Petersburg Treaty only reinforced the cemented friendship. Renewed in 1886, the land lease in Inasa continued to function until the Russo-Japanese War. Despite some negative reactions particularly from the British, the Meiji government’s recognition of the Russian navy base in Inasa alongside the St. Petersburg Treaty was an important factor in maintaining Russia as Japan’s ally and thereby allowing Japan’s strategic leeway in East Asia.
2 0 0 0 OA ロボット演劇
- 著者
- 石黒 浩 平田 オリザ
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.35-38, 2011 (Released:2011-02-25)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 3 8
2 0 0 0 OA 脳機能の性差
- 著者
- 三村 將 山縣 文
- 出版者
- 一般社団法人 日本女性心身医学会
- 雑誌
- 女性心身医学 (ISSN:13452894)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.229, 2017 (Released:2018-04-13)
2 0 0 0 OA 根拠に基づく臨床実践のための 帰結評価指標の有効利用法
- 著者
- 徳久 謙太郎 鶴田 佳世 梛野 浩司
- 出版者
- 保健医療学学会
- 雑誌
- 保健医療学雑誌 (ISSN:21850399)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.58-68, 2014-04-01 (Released:2014-07-31)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
根拠に基づくリハビリテーションの実践のため,帰結評価指標を用いた定期評価による治療効果判定の重要性が増している.そのためには適切な帰結評価指標を選択し,その情報を利用した臨床意思決定を行うことが求められる.本稿では臨床において最適な帰結評価指標を選択する基準である6 つの主要因子(評価の対象,評価の目的,指標のタイプ,測定尺度の種類と心理測定特性,対象者因子,時間・空間・物理的環境因子)について紹介するとともに,測定の標準誤差や最小検知変化などの有用な情報について説明する.さらにリハビリテーションにおいて対象とすることの多い身体動作能力に関する帰結評価指標であるFunctional reach test, 10m 最大歩行速度,脳卒中身体動作能力尺度を紹介し,その有効利用法について述べる.
2 0 0 0 IR 介護職員の職業選択要因と就労継続要因の研究 -介護職員へのインタビュー調査から-
- 著者
- 二渡 努
- 出版者
- 東北福祉大学
- 雑誌
- 東北福祉大学研究紀要 = Bulletin of Tohoku Fukushi University (ISSN:13405012)
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.161-178, 2021-03-18
2025 年度末までに年間6 万人程度の介護人材を確保する必要性が指摘され,介護人材の確保と定着は喫緊の課題となっている。本研究は,介護人材の確保と定着の促進に資する取組を明らかにすることを目的に,介護職員にインタビュー調査を実施し,設定した基本仮説,作業仮説に対して仮説検証を行った。 基本仮説は「介護業務と接する機会を有することが,介護分野に参入する職業選択要因となり,職場からのサポートを受け,勤続年数の上昇によって変化するやりがいを獲得することで,介護職員は就労を継続することができる」と設定し,作業仮説1 を「介護業務と接する機会を有することが介護分野での職業選択の要因となる」,作業仮説2 を「職場からのサポートが新人介護職員の就労継続要因となる」,作業仮説3 を「勤続年数の上昇によって,就労継続に必要となるやりがいは変化する」と設定した。作業仮説1, 2 は一部支持,作業仮説3 は棄却されたため,基本仮説は一部支持となった。 仮説検証を行う過程で,介護業務等に接する機会が少ないと思われる若年層には介護等体験により介護業務に対する理解を深める機会を提供することが介護分野への参入を促進する可能性があること,新人介護職員の一定期間の就労継続要因として,奨学金の返済免除などがあること,就労継続要因となるやりがいは,職位の向上,異動による施設種別や対象利用者の変更によって,変化することが示唆された。
2 0 0 0 OA 在日ドイツ兵捕虜のサッカー交流とその教育遺産
- 著者
- 岸本 肇
- 出版者
- 学校法人 三幸学園 東京未来大学
- 雑誌
- 東京未来大学研究紀要 (ISSN:18825273)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.25-32, 2009-03-20 (Released:2018-12-04)
第一次世界大戦中、日本に囚われていたドイツ兵捕虜のスポーツ活動の中でも、特にサッカー交流を取り上げ、その事実・背景と教育遺産について論じた。その内容は、おおむね、下記のごとくである。 1.似島、青野原および名古屋の捕虜収容所にいたドイツ兵のサッカー交流が、史料により確認されている。 2.交流相手は、主として、中学校、師範学校・高等師範学校であった。 3.サッカー試合を含む文化・スポーツ交流は、彼らの解放が近くなった1919 年に集中している。 4.ドイツ兵捕虜収容所があった自治体における、コンサート、スポーツ行事、展覧会の催行により彼らの諸活動を再現するとりくみ、および学校でドイツ兵捕虜の足跡を題材にした教材づくりや授業をする実践は、地域教育や平和教育、国際交流教育の観点から評価できる。
2 0 0 0 OA 看護・在宅介護の現場における吸引カテーテルと消毒剤の取り扱いに関する指導マニュアルの検討
- 著者
- 小森 由美子 赤澤 知美 森部 初美 荻野 賀子 劉 秀娥 二改 俊章
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.5, pp.478-483, 2002-10-10 (Released:2011-03-04)
- 参考文献数
- 16
Medical workers are continually faced with determining the appropriate usage of disinfectants in the areas of hospital nursing and home health care. The present study has been designed to provide answers to such questions as “what kind of technique is best for intra-airway and oral aspiration ?” and “what is the most effective use of disinfectants during aspiration procedures to prevent infectious diseases ?” First, the microbial contamination of suction catheters and disinfectant solutions, which have been in use for 24 hours, were investigated. The results indicated contaminations in 50% of catheters and one of the disinfectant solutions, which were presumably caused by the different aspiration techniques of nurses.Experiments were designed to improve the manual, and the results presented to nurses and pharmacists. Additional items to the manual are : (1) The necessity of removing saliva and sputum from the catheter prior to rinsing with the disinfectant solution; (2) The appropriate volume of rinse water and disinfectant solution necessary to achieve a complete de-contamination of the catheter; (3) Preventive techniques used to avoid microbial contamination of disinfectant; (4) Disinfectant soaking techniques for the catheter; (5) Advice for hospital/home health care personnel regarding the proper bedside use of a catheter and disinfectant bottle to maintain appropriate hygienic conditions.The results and subsequent improvement of the instruction manual had a pronounced effect on both the aspiration techniques of nurses, and upon the attitude of pharmacists in our hospital. The pharmacists now realize their leading role in the effective and proper usage of disinfectants.
2 0 0 0 OA 太平御覽 1000卷目録15卷
- 著者
- (宋) 李昉 等奉敕撰
- 出版者
- 歙鮑崇城刊
- 巻号頁・発行日
- vol.[42], 1818