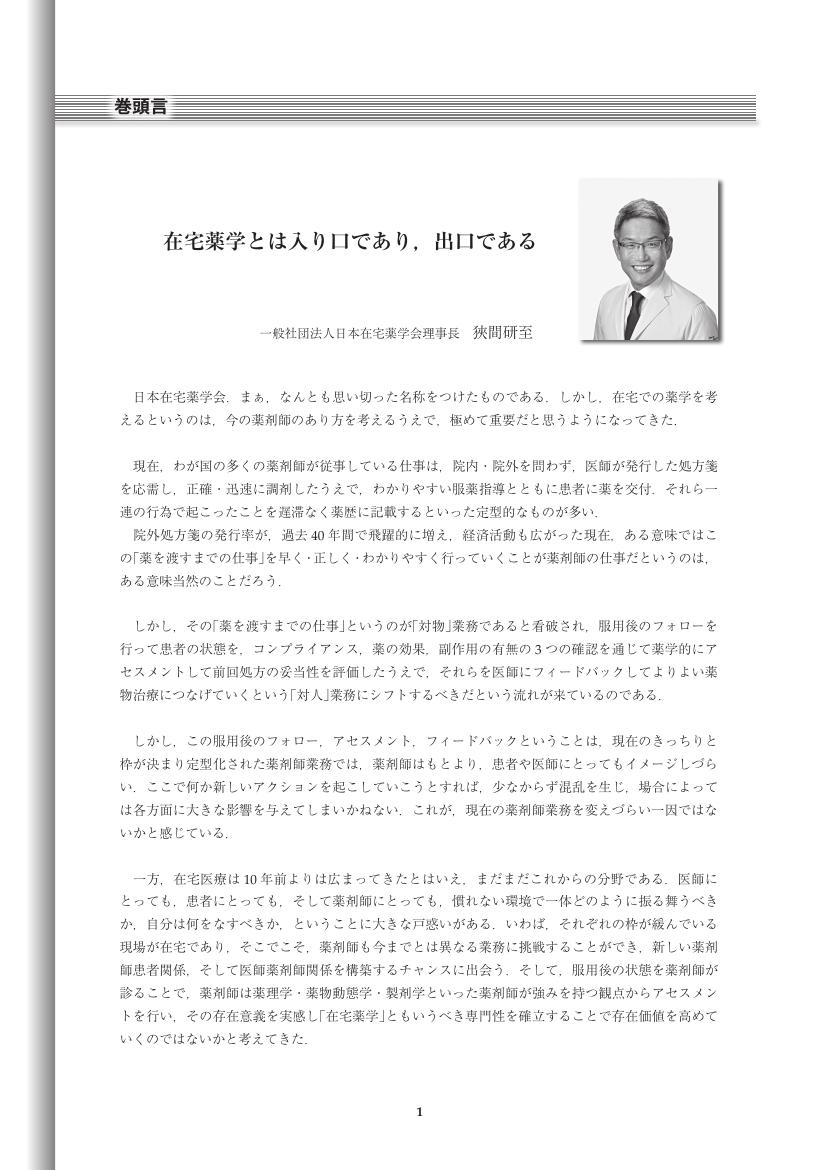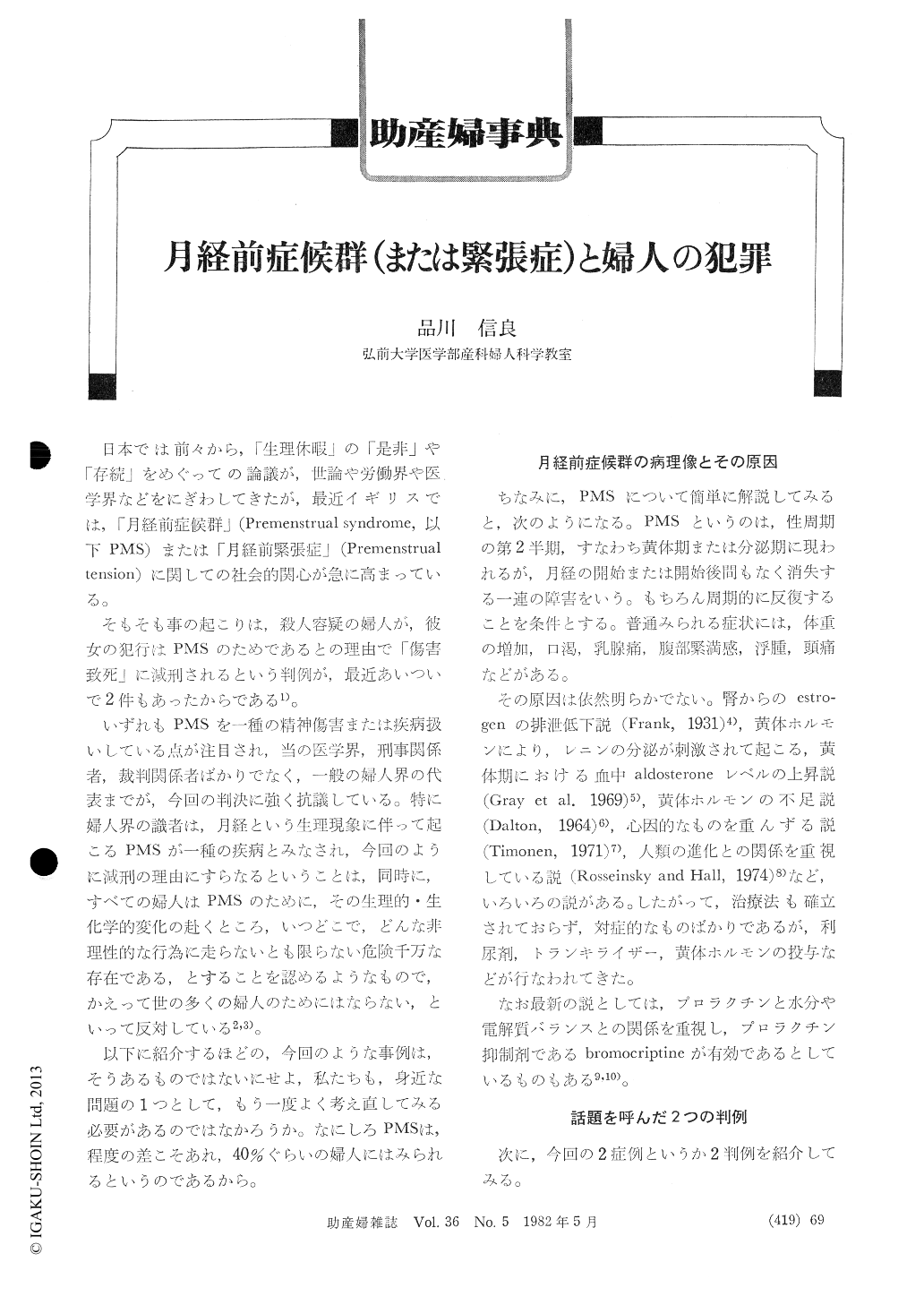2 0 0 0 OA 古代語の移動動詞と「起点」「経路」
- 著者
- 松本 昂大
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.4, pp.86-102, 2016-10-01 (Released:2017-04-03)
- 参考文献数
- 24
本稿では,移動動詞に係る格助詞「より」と「を」が,「起点」と「経路」のどちらを表すかを検討する。「より」「を」を承けるかどうかと,その助詞が「起点」と「経路」のどちらを表すかという観点から,移動動詞をA~D類の4種に分類した。A類の動詞は,「より」「を」を承け,「より」は「起点」と「経路」を表し,「を」は「起点」のみを表す。B類の動詞は「より」,C類の動詞は「を」,D類の動詞は「より」「を」を承け,それらはすべて「起点」のみを表す。D類の「出づ」は「出現」を表す場合は「より」,「出発」を表す場合は「を」と結びつくという傾向が見られ,「出現」はB類,「出発」はC類の動詞と意味的特徴が共通する。以上のことから,助詞の用法は移動動詞の意味的特徴によって決定されるということを主張する。
2 0 0 0 OA 改正歩兵射撃問答 : 下士上等兵用
2 0 0 0 OA 教育工学とインフォーマル学習(<特集>情報化社会におけるインフォーマルラーニング)
- 著者
- 山内 祐平
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.187-195, 2013-11-20 (Released:2016-08-10)
- 被引用文献数
- 2
情報化の進展により,学校教育外の学習機会が増加している.本論文では学校教育外の学習機会についてインフォーマル学習に関連する概念を整理した上で,教育工学会誌にこの10年間で掲載されたインフォーマル学習に関する研究の動向をまとめた.その結果,生涯教育施設でのインフォーマル学習・職場や仕事に関するインフォーマル学習・大学の課外活動におけるインフォーマル学習・ワークショップとインフォーマル学習・その他の領域のインフォーマル学習・インフォーマル学習の方法開発の6領域にわたる研究が行われていることが明らかになった.これらの既存の研究の課題をもとに本特集号の論文の位置づけを解説し,今後の展望について述べた.
2 0 0 0 妊娠中のアルコール摂取に関する最近の話題
- 著者
- 冨松 拓治
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.137-139, 2016 (Released:2016-06-29)
- 参考文献数
- 5
2 0 0 0 OA 在宅薬学とは入り口であり,出口である
- 著者
- 狹間 研至
- 出版者
- 一般社団法人 日本在宅薬学会
- 雑誌
- 在宅薬学 (ISSN:2188658X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.1-2, 2019 (Released:2019-05-20)
2 0 0 0 OA サルの安全な取扱いのために
- 著者
- 英国危険病原体諮問委員会 中村 志帆 光永 総子 中村 伸
- 出版者
- Primate Society of Japan
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.377-394, 1999 (Released:2009-09-07)
- 参考文献数
- 14
- 著者
- 村上 史朗
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.78-79, 2009-08-31 (Released:2017-02-20)
2 0 0 0 OA 学生の体格・体力・性格の相互関係
- 著者
- 徳永 幹雄 橋本 公雄 千綿 俊機
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.109-114, 1971-10-01 (Released:2017-09-27)
この研究は大学生の体格(身長,体重,ローレル指数),体力(体力診断テスト),性格(Y-G性格検査)の相互関係を明らかにするために行ない,つぎの結果を得た.1. 体格と体力の関係:体型の中間型が体力にすくれ,細長型が劣っていた.身長,体重と体力の間に有意味の関係があることが明らかになつた. 2. 性格と体格の関係: E類型に細長型が多く, Y-G得点では細長型と肥満に近い型には差はなく,中間型に比較し細長型は神経質大で,肥満に近い型は劣等感大であつた.また,外向的な学生は平均型の学生より体重が重かつた.3. 性格と体力の関係:D類型が最も体力がすくれE類型が最も体力の低い学生が多かつた.また,体力の低い学生は体力の高い学生に比較し劣等感大,神経質大,主観的,非協調的,のんきでない,服従的,社会的内向であつた.積極型の学生は消極型の学生より筋力にすくれていた.
2 0 0 0 月経前症候群(または緊張症)と婦人の犯罪
- 著者
- 品川 信良
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 助産婦雑誌 (ISSN:00471836)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.5, pp.419-421, 1982-05-25
日本では前々から,「生理休暇」の「是非」や「存続」をめぐっての論議が,世論や労働界や医学界などをにぎわしてきたが,最近イギリスでは,「月経前症候群」(Premellstrual syndrome,以下PMS)または「月経前緊張症」(Premenstrualtension)に関しての社会的関心が急に高まっている。 そもそも事の起こりは,殺人容疑の婦人が,彼女の犯行はPMSのためであるとの理由で「傷害致死」に減刑されるという判例が,最近あいついで2件もあったからである1)。
2 0 0 0 IR 弥生時代~古墳時代初頭の卜骨 -その系譜と消長をめぐって-
- 著者
- 國分 篤志
- 出版者
- 千葉大学大学院人文社会科学研究科
- 雑誌
- 千葉大学人文社会科学研究科研究プロジェクト報告書 (ISSN:18817165)
- 巻号頁・発行日
- vol.276, pp.97-121, 2014-02-28
原始・古代の日本列島で実修された占いとして、『古事記』・『日本書紀』などにみえる「太占」(ふとまに)がある。これは、例えば『古事記』神代巻天岩屋戸条において、「天の香山の眞男鹿の肩を内抜きに抜きて、天の香山の天の朱桜を取りて、占合いまかなはしめて...」とあるように、シカなどの肩胛骨を素材に、火箸状のもので焦げ目を付け(焼灼)、その罅を観て占うものであり、占いに用いた痕跡の残る獣骨が「卜骨」である。卜骨は、弥生時代から平安時代前期に至るまで、手法・形態・素材を変えつつも考古遺物として存在を確認できる。その消長を大局的にみると、帰属時期は弥生時代前期~古墳時代初頭と、古墳時代後期~奈良・平安時代の2つの時期に大別でき、中間に当たる古墳時代前~中期に帰属する事例は僅少である。本稿ではこのうち、より資料点数が多く分布範囲も広い前者の時期を中心に、型式学的な見地から扱うこととする。弥生時代~古墳時代初頭の卜骨は、全国で20都府県54遺跡での出土が報告されている(第1図・第1表)。当該期における時期差・地域差などを明らかにしたい。なお、引用した卜骨の実測図のうち、肩胛骨を素材としたものでは、関節窩が下になるように配置させていただいていることをお断りしておく。千葉大学大学院人文社会科学研究科研究プロジェクト報告書 第276集 『型式論の実践的研究II』柳澤 清一 編"Pratical Study of Typology II", Chiba University Graduate School of Humanities and Social Sciences Research Project Reports No.276
2 0 0 0 OA いわゆるハゲタカジャーナルに関する文献調査
- 著者
- 栗山 正光
学術文献データベースScopusとWeb of Scienceを利用して,ハゲタカジャーナルに関し,どのような文献が,いつ,どのような学術雑誌に発表されているか調査した.文献検索の過程でpredatoryという比喩的な語が検索の精度を落とすことが確認され,両データベースの検索結果の比較によって検索漏れや未収録データが発見された.ScopusもWeb of Scienceも単独では網羅的な文献収集には不十分なことが明らかになった.
2 0 0 0 OA 水素爆発を事例研究とした大規模野外爆発実験
- 著者
- 中山 良男
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.6, pp.412-420, 2005-12-15 (Released:2016-12-30)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
野外での大規模な爆発実験は,爆発現象の規模効果を検討するための重要な研究手法である.ここでは,国内において行われた大規模野外実験の例,文献調査によるTNT や開放空間におけるガス爆発などの代表的な研究を概説する.つぎに,筆者らが行っている野外実験の実施方法や計測方法について具体的に紹介する.最後に,研究事例として筆者らが行った水素の爆発実験について報告する.
2 0 0 0 OA 京都鴨川川中における明治期の夏季納涼営業の変遷―日出新聞・京都日出新聞の記事を中心に―
- 著者
- 林 倫子
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D1(景観・デザイン) (ISSN:21856524)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.1, pp.26-36, 2015 (Released:2015-04-20)
- 参考文献数
- 105
明治期までの鴨川納涼では,今日見られるような高床納涼席が沿岸に設置されるだけでなく,中州や橋の下など川中全体に盛り場としての納涼場が形成されていた.本研究では,納涼営業に関する制度面,物理環境面に着目して伝統的な納涼場の廃止までの変遷を追い,鴨川納涼場の変質をもたらした要因について考察した.その成果は以下のとおりである:1)官有地借用制度の変更と規制の強化が行われ,2)鴨川運河工事に伴う河床掘削で出店が敬遠され,構造規制の議論も始まった.3)それと同時に納涼場は徐々に衰退し,博覧会的要素導入という再興策も講じられたものの定着しなかった.
2 0 0 0 OA 選挙研究における「政党支持」の現状と課題
- 著者
- 西澤 由隆
- 出版者
- Japanese Association of Electoral Studies
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.5-16,268, 1998-02-28 (Released:2009-01-22)
- 参考文献数
- 62
The concept of partisanship has been one of the central topics of the voting research in Japan as in other democratic countries. While whether the original concept of party identification developed in the U. S. is transportable to other countries is still under debate, the party support variable (measured by the question, “which party do you usually support?”) is often treated as functional equivalent to the party identification measure in Japan.This review article reminds researchers of Japanese voting study of a need for a careful look at the party support variable. It does so by going “back to the basics.” It evaluates the party support variable against the four basic assumptions of the original party identification concept: the sense of identification, its stability, its unidimensionality, and its transitiveness.Citing the existing works and drawing some new data, the article concludes that 1) the party support variable is not exactly measuring the sense of self-idenification with a party, 2) it is not as stable as its counterpart is assumed to be, 3) it is increasingly difficult to map the Japanese current political parties on the left-right uni-dimensional scale, and 4) whether its operational definition meets the transitiveness assumption is questionable.
2 0 0 0 OA VI.Parkinson病の救急診療と周術期管理
- 著者
- 坪井 義夫 藤岡 伸助
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.8, pp.1578-1584, 2015-08-10 (Released:2016-08-10)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
Parkinson病(Parkinson's disease:PD)患者は中期から進行期にかけて救急受診,入院加療の頻度が増加する.原因は全身合併症,外傷あるいはPD症状の悪化など様々であるが,薬物療法の理解が不十分な場合に,重篤な状態に陥る可能性がある.手術の必要な場合,周術期にも合併症やPD症状の悪化を呈する頻度が高い.特にドパミン系治療の急な中断による悪性症候群類似のParkinsonism-hyperpyrexia syndromeは重症化しやすく,早期の診断,対処が必要である.神経内科医,救急医はPDの救急診療,周術期管理に習熟しておくことが望まれる.
2 0 0 0 OA 盛岡藩の罪と罰雑考(二)
- 著者
- 吉田 正志
- 出版者
- 東北大学法学会
- 雑誌
- 法学 = HŌGAKU (THE JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCE) (ISSN:03855082)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.5, pp.132-101, 2018-12-30
2 0 0 0 OA 五島列島における潜伏キリシタン墓地に関する分布の基礎的研究
- 著者
- 加藤 久雄 野村 俊之 Hisao Kato Toshiyuki Nomura 長崎ウエスレヤン大学現代社会学部経済政策学科 長崎ウエスレヤン大学地域総合研究所客員研究員 Faculty of Contemporary Social Studies Nagasaki Wesleyan University
- 雑誌
- 長崎ウエスレヤン大学地域総合研究所研究紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.61-70, 2016-03-31
2 0 0 0 刀工遺跡めぐり三三〇選
2 0 0 0 OA 動物の利用と世界における人間の地位
- 著者
- 柴嵜 雅子 Masako Shibasaki
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.99-112, 2018-10-31
Animal advocates are divided on the understanding of the position of humanity in the world; rightists regard Homo sapiens just as one species in the animal kingdom, whereas welfarists maintain that humans stand at the pinnacle of the hierarchy of life. This paper aims to offer some arguments against the latter view. First, the concept of human supremacy is based on Judeo-Christian values,which despite their long tradition in Western society, are not universal and can be seen as preposterous in other cultural settings such as premodern Japan. Second, some welfarists assume that denying humans a special status degrades human dignity and undermines universal human rights. However,as the histories of colonialism, slavery and racism in Christian countries have demonstrated, human exceptionalism does not guarantee that the rights of every person will be protected. Third, our anthropocentric practices have already started to endanger the very survival of humanity on this planet.
2 0 0 0 OA 地域公共交通網形成におけるタクシー事業者の参画と官民協働のあり方
- 著者
- 川端 光昭 佐野 可寸志
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.246-257, 2019 (Released:2019-07-03)
- 参考文献数
- 18
持続的な地域公共交通網形成には,地域の実情に合わせ多様な運行主体の組合せを検討する必要がある.本稿では,タクシー事業者の地域公共交通への参画状況,自治体のタクシー事業者の活用意向を明らかにする.加えて,先行事例の分析を通して,官民協働による地域公共交通のマネジメントに役立つ知見を得ることを目的とする.おおよそ半数の自治体が,公共交通事業をタクシー事業者に委託しており,タクシー事業者の参画が進んでいることがわかった.しかし,事業委託による運転士増等の雇用創出効果は限定的であること,委託事業者との情報共有が不十分な自治体が多いことが明らかとなった.先行事例の分析を通して,持続的な公共交通網形成には,タクシー事業者の経営資源を有効活用することの重要性を確認した.さらに,タクシー事業者の経営体力を十分に情報共有・理解し,実行可能な公共交通サービスを官民協働で制度設計するプロセスが不可欠と言える.