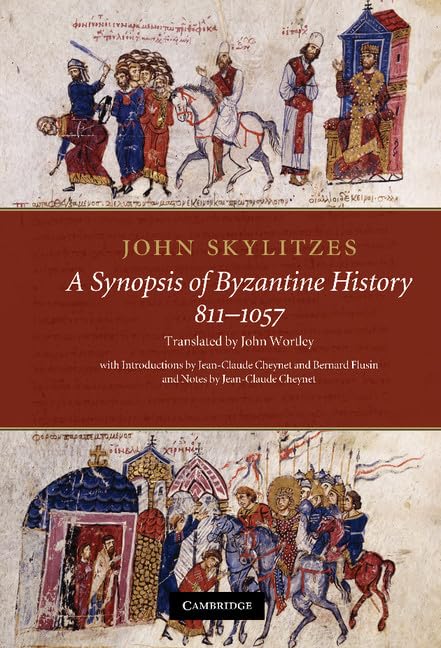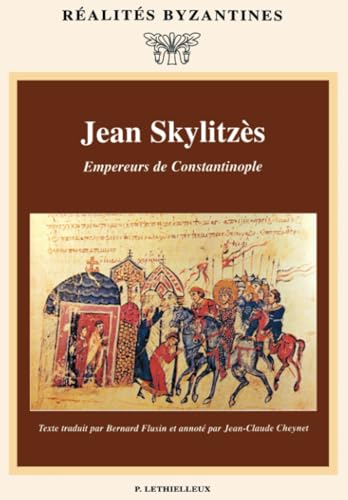2 0 0 0 OA 国鉄自動車の概況
- 出版者
- 日本国有鉄道自動車局
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和41年版, 1966
2 0 0 0 もち米,うるち米ならびにそれぞれのでんぷんのアミログラム特性
- 著者
- 庄司 一郎 倉沢 文夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.292-294, 1979
モチ米, ウルチ米の精白米粉末ならびにデンプン試料についてアミログラムによる粘度試験を行いつぎの結果を得た.<BR>1) モチ米, ウルチ米の精白米粉末のアミログラムからは最高粘度はウルチ米が大でモチ米は小となり膨潤しにくく, 崩壊度でもウルチ米は大となるがモチ米は小で崩壊しにくい値を示した.<BR>2) デンプン粒のモチ米, ウルチ米のアミログラムからは最高粘度はモチ米デンプンが大でウルチ米デンプンは小となり, 崩壊度でもモチ米デンプンは大となるがウルチ米デンプンは小で崩壊しにくい値を示し, デンプンレベルではモチ米がウルチ米より高い最高粘度を示し, 精白米のモチ米, ウルチ米の成績と逆の結果が得られた.<BR>米飯の粘着度はモチ米は大で, ウルチ米は小であった.デンプン粒の最高粘度は同様にモチデンプンは大でウルチデンプンは小であった.一方, 精白米粉末の場合はモチ米の最高粘度は小で, ウルチ米は大であった.これはモチ米デンプンに対して脂質あるいはタンパク質がとくに影響を与えているためでないかと考えられる.<BR>3) 種々の濃度 (5, 8, 10%) のモチ米, ウルチ米デンプンのアミログラムの結果, 各濃度においてモチデンプンはウルチデンプンに比較して最高粘度は大であった.
2 0 0 0 OA 新製品・新技術紹介 IBM漢字情報処理システム
- 著者
- 諏訪 秀策
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.7, pp.464-468, 1971-10-20 (Released:2016-03-16)
2 0 0 0 OA 大和国在地武士の動向と染田天神連歌
- 著者
- 勢田 勝郭
- 出版者
- 中世文学会
- 雑誌
- 中世文学 (ISSN:05782376)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.91-101, 1996 (Released:2018-02-09)
2 0 0 0 OA 運河における悪臭発生に関する調査・研究
- 著者
- 堀口 孝男 堀江 毅 菊地 政信 小島 伸一
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 海岸工学論文集 (ISSN:09167897)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.901-905, 1991-11-05 (Released:2010-03-17)
- 参考文献数
- 3
2 0 0 0 OA 柳田國男「青ヶ島還往記」を読む : 地域に誇りをもつということ
- 著者
- 土屋 久
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 生活科学研究 = Bulletin of Living Science (ISSN:02852454)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.281-285, 2017-03-30
本稿は、柳田國男「青ヶ島還住記」を読み込むことで、この作品に込められた、柳田の主たる想いを検討したものである。それと同時に、その想いは青ヶ島の今日的な課題に届くのか、こうした問いにも一定の考察を試みた。その結果、先の作品の主たる想いは、島の少年達に誇りをもたせたいとのことであり、彼のこの想いは、今日、地域おこしに、ますます重要な意味をもってきている点を指摘した。
- 著者
- 劉 芳
- 出版者
- 日中人文社会科学学会
- 雑誌
- 知性と創造 : 日中学者の思考 (ISSN:18848621)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.128-139, 2015
2 0 0 0 OA 日常的な看護行為に伴う手の接触が対象者にもたらす意義の検討
- 著者
- 明野 伸次
- 雑誌
- 北海道医療大学看護福祉学部学会誌 (ISSN:13498967)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.67-72, 2016-03-31
2 0 0 0 Empereurs de Constantinople
2 0 0 0 OA 女子プロ野球投手における投球フォームと肘関節最大内反トルクとの関連
- 著者
- 東 善一 松井 知之 瀬尾 和弥 平本 真知子 盛房 周平 森原 徹
- 出版者
- 日本肘関節学会
- 雑誌
- 日本肘関節学会雑誌 (ISSN:13497324)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.5-8, 2016 (Released:2019-05-27)
- 参考文献数
- 15
われわれはトップレベルである全女子プロ野球投手における投球フォームと肘関節最大内反トルクとの関連について検討した.対象は全力投球可能な女子プロ野球投手12名とした.全力投球時の球速をスピードガンで,投球フォームを三次元動作解析装置で測定した.球速および投球動作中の各関節角度と肘関節最大内反トルクとの関係をPearsonの相関係数によって検討した(P<.05).球速と肘関節最大内反トルクとの間には相関を認めなかった(r =.17, P=.61).投球動作中の各関節角度と肘関節最大内反トルクとの間では,9変数との関連を示し,特に投球方向への腰椎回旋角度と最も高い正の相関を認めた(r =.83,P <.01).体幹によってエネルギーを産出できない場合,代償として上肢依存の投球となり,肘関節最大内反トルクは高値を示したと考えた.
2 0 0 0 OA 高校野球投手における身体機能の非投球側差と投球肩・肘障害について
- 著者
- 幸田 仁志 甲斐 義浩 来田 宣幸 松井 知之 東 善一 平本 真知子 瀬尾 和弥 宮崎 哲哉 木田 圭重 森原 徹
- 出版者
- 日本ヘルスプロモーション理学療法学会
- 雑誌
- ヘルスプロモーション理学療法研究 (ISSN:21863741)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.127-131, 2018-10-16 (Released:2018-10-19)
- 参考文献数
- 25
〔目的〕投球肩・肘障害を有する高校野球投手の特徴を,関節可動域や筋力の非投球側差より分析した。〔方法〕京都府下の野球検診に参加した高校野球投手76名を対象とした。測定項目は,投球肩・肘障害の判定,関節可動域および筋力とした。関節可動域および筋力は両側に対して実施し,投球側から非投球側の値を減算することで非投球側差を算出した。統計解析には,投球肩・肘障害ごとに,対応のないt 検定を用いて陽性群と陰性群の関節可動域および筋力の非投球側差を比較した。有意水準は5%とした。〔結果〕投球肩障害では,陽性群の肩関節内旋可動域の非投球側差は陰性群と比較して有意に低値を示した(p<0.05)。投球肘障害では,陽性群の肩関節外旋可動域の非投球側差は,陰性群と比較して有意に低値を示した(p<0.05)。〔結論〕肩関節外旋可動域や内旋可動域の非投球側差による分析は,野球選手の機能低下や障害予測を判別する一助となる可能性がある。
2 0 0 0 OA 時間評価に関する心理学的研究 ―青年期における男女差の検討―
2 0 0 0 OA 核酸機能の効果的時空間解析のための励起子制御イメージング
- 著者
- 岡本 晃充
- 出版者
- 独立行政法人理化学研究所
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2008
励起子相互作用による蛍光消光を効果的に使用した新しい発想のオン-オフ蛍光核酸プローブ(近赤外)を設計・作成した。このプローブは、プローブだけのときには色素の二量化によってほとんど蛍光を示さないが、標的配列(DNA・RNA)とハイブリダイゼーションしたとき二量体構造が崩れ、強い蛍光発光を与えた。
- 著者
- 見学 美根子 (2011) 岡本 晃充 (2010) WANG D. オウ タン
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 特別研究員奨励費
- 巻号頁・発行日
- 2010
神経細胞内のmRNA動態観察において、RNA配列の染め分け、つまりマルチカラー核酸解析は、mRNAのライブセルイメージングの原点としてどうしても確立したい技術である。それが可能になれば、アメフラシの神経細胞の中でのmRNAのトラフィックスのモニタリングへ応用できるようになる。本年度は、まずモデル系として、励起子制御機構にのっとった新規蛍光プローブ群を用いて、ヒトガン細胞(HeLa細胞)およびマウス神経細胞(海馬から取り出す)における新規mRNA蛍光検出法へと展開した。ここで検討されたプローブは、チアゾールオレンジ色素の色素間励起子結合効果を利用しており、標的のmRNAと結合した場合にだけ488nm励起により強い蛍光を発する。われわれは、まず細胞内mRNA分布の静的観察のために、このプローブを用いた蛍光in situハイブリダイゼーション法を確立した。この方法は、ガラスプレート上に固定化した細胞に対し、新規蛍光プローブを含む溶液を加えるだけである。これにより、従来までの蛍光in situハイブリダイゼーション法で用いられてきた工程を大きく簡便化することができた。この新規観察法を通じて、mRNAが細胞内でどのように分布しているかを蛍光発光によって確認することができた。この方法は、次の段階として目指すべきである神経細胞内のmRNAのトラフィックの観察に有用であると思われ、引き続き研究を進めることによって、新たな蛍光観察法の確立を目指したい。
2 0 0 0 OA 質問紙法によるトラック運転労働者の健康問題における労働関連性の検討
- 著者
- 甲田 茂樹 安田 誠史 杉原 由紀 大原 啓志 宇土 博 大谷 透 久繁 哲徳 小河 孝則 青山 英康
- 出版者
- 公益社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.6-16, 2000-01-20 (Released:2017-08-04)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 6 23
運輸労働者の健康問題に影響を与える職業要因を評価するために, 1997年に541名の運輸労働者を対象に労働・勤務条件, 運転労働に係わる職業性要因, 身体の自覚症状や疾病罹患の状況について質問紙法で調査を実施した.有効回答率は85.7%, 134名の集配業務に従事する運転労働者(集配群)と199名の長距離輸送に従事する運転労働者(長距離群), 71名の事務職員を分析対象とした.まず, 三つの群での職業性要因と健康問題を検討するために, 労働・勤務条件や身体の自覚症状や疾病罹患の状況を比較検討した.ついで, 集配群と長距離群における職業要因が健康問題に与える労働関連性を検討するために, ロジステック回帰分析を実施し, オッズ比と95%CIを計算した.健康問題に影響を与える職業要因, すなわち, 不規則交代制勤務, 労働環境, 作業姿勢, 重量物取り扱い, 多い仕事量や長時間労働への不満, 休憩時間の取得困難の要因で, トラック運転労働者の訴え率が事務職に比べて有意に高かった.耳鳴り, 頚の痛み, 腰痛の自覚症状と高血圧, 胃十二指腸潰瘍, 腰背部打撲, むち打ち症, 痔疾の疾患でトラック運転労働者の訴え率が事務職に比べて有意に高かった.ロジスティック回帰分析の結果では, 年齢やBMI, 喫煙習慣を以外の多くの労働関連要因で, 身体の自覚症状や疾病罹患に関する有意に高いオッズ比を認めた.集配群の循環器疾患及び関連した自覚症状に関するオッズ比は, 経験年数, 腰の捻転動作, 振動, 運転労働に伴うストレスで有意に上昇していた.消化器系疾患及び関連した自覚症状に関するオッズ比は, 狭い作業空間, 車中泊, 長い走向距離, しゃがみ姿勢, 運転労働に伴うストレスで有意に上昇していた.集配群の自覚症状の耳鳴りに関するオッズ比は, 経験年数, 長時間労働, 狭い作業空間, 車中泊, 運転労働に伴うストレスで有意に上昇していた.腰痛や頚部痛等の筋骨格系疾患及び関連したに自覚症状に関するオッズ比は, 残業, 振動, 狭い作業空間, 座り姿勢, 少ない休憩時間で有意に上昇していた.疲労症状に関するオッズ比は, 少ない休憩時間, 振動, 運転労働に伴うストレスで有意に上昇していた.運輸労働者の健康問題を解決するためには, 上記の労働・勤務条件や運転労働に関連した課題を改善する必要がある.
2 0 0 0 OA 『n次創作観光』とは?
- 著者
- 岡本 健
- 巻号頁・発行日
- 2013-03-08
『n次創作観光』出版記念イベント : 北海道で「n次創作観光」は可能か? : 観光とコンテンツの出会いが拓く北海道の未来. 2013年3月8日(金). 紀伊國屋書店札幌本店1Fインナーガーデン, 札幌市.
2 0 0 0 OA 薬物効果のループ
- 著者
- モハーチ ゲルゲイ
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.4, pp.614-631, 2017 (Released:2018-02-23)
- 参考文献数
- 45
臨床試験(治験)は、開発中の医薬品などを病人や健常者に投与し、新薬の安全性と効率性を評価する仕組みである。実薬と偽薬を比べる実験の場である一方で、病気を患っている人びとの苦痛を和らげるという臨床実践でもある。本稿では、ハンガリー西部にある小規模臨床試験センター(DRC)の事例を取り上げ、製薬をめぐる実験的状況に焦点を当てることで、もの・身体・世界を生成していく関係性の特徴を明らかにしていく。DRCは、1990年代前半に行われた市場開放以降、糖尿病と骨粗しょう症に関する研究と治療を中心に、外資系製薬企業と周辺の地方病院のネット ワークを徐々に拡大してきた研究病院である。そこで行われている臨床試験においては、新薬の効果によって実行(enact)される化学物質と身体と社会の間の三つのループが生成されている。まず、臨床試験の土台となる二重盲検法と無作為化法の実験的設定にしたがう実薬と偽薬のループが、新薬の効果を統計データとして生み出していくという過程がある(方法のループ)。次に、このデータがDRCと周辺の外来医院との連携を促す中で、薬を対象とする実験と、治療を受ける集団は組織化の中でループしていくことになる(組織化のループ)。さらに、多くの被験者の家族から血液サンプルを採集・保管するバイオバンク事業では、いわゆる「実験社会」における政治性を伴った治療と予防の相互構成が見えてくる(政治のループ)。本稿では、これらの三つのループを踏まえ、メイ・ツァンが人類学に導入した「世界化(worlding)」という概念を用いながら、医薬化に対する政治経済学的な批判を、薬物代謝の効果として捉え直すことを試みる。実験と治療の間の絶え間ないループを通じて新たな治療薬が誕生する過程に焦点を絞り、自然と文化の二項対立に対する批判的研究の視点から医療人類学への貢献を図る。
- 著者
- 大塚 清
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 日本造船学会誌 (ISSN:03861597)
- 巻号頁・発行日
- vol.745, pp.411-416, 1991