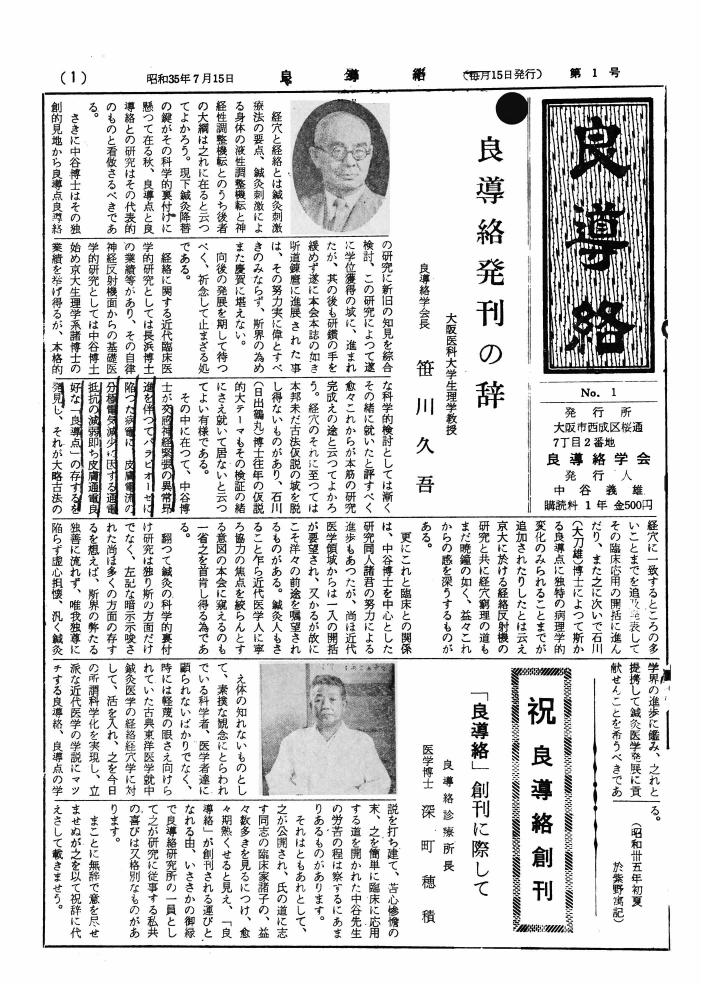1 0 0 0 OA わが国小学校における祝日大祭日儀式の形成過程
- 著者
- 佐藤 秀夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.205-214, 1963-09-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 49
- 著者
- Yanfeng ZHAO Donghai WANG Zhaoming LIANG Jianjun XU
- 出版者
- (公社)日本気象学会
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.2, pp.111-125, 2017 (Released:2017-03-17)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 6
Persistent severe rainfall (PSR) events during the rainy season (April to July) in southern China were studied in terms of the dynamic features of the large-scale circulation. The aim of the study was to understand the formation mechanism and improve forecasting. The circulation field and spatiotemporal distribution of waves at 500 hPa for different types of PSR were analyzed. The results reveal the following: (1) During the pre-flood season (April to June) in southern China, troughs have the same phase in the middle latitudes as those in the high latitudes. The East Asia major trough (3–5 wave numbers) in the middle latitudes strengthens southwards and interacts with the 30°N subtropical high (1–2 wave numbers) from three days prior to the PSR events. (2) During the post-flood season (June to July) in South China, the weather regime transitions occur on five days prior to the PSR events. The 40°N trough (2–4 wave numbers) strengthens southwards and interacts with the subtropical high (1–2 wave numbers). It is also affected by the blocking ridge (3 wave number) in the high latitudes. (3) During the Mei-yu period (June to July) over the Yangtze–Huaihe River basin, the transitions of circulation pattern start three days prior to the PSR events. With the northwest development of the subtropical high, there is a transfer process from long to short waves in terms of energy for the trough at 50°N.
- 著者
- Kento Umeki Yutaka Watanabe Hirohiko Hirano
- 出版者
- 日本大学松戸歯学部 口腔科学研究所
- 雑誌
- International Journal of Oral-Medical Sciences (ISSN:13479733)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3-4, pp.152-159, 2017-03-10 (Released:2017-03-27)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 6
Maintenance and improvement of masticatory function in nursing care elderly persons (NC) is an important issue, and it is speculated that sarcopenia is related to declining masticatory function. The decrease in skeletal muscle index(SMI), a major diagnostic criterion for sarcopenia, has been reported to be associated with swallowing function in NC.However, the relationship between SMI and masticatory function is unknown. Therefore,we investigated the relationship between masseter muscle thickness(MMT)and SMI, with the aim of examining the specific relationship between decreased masticatory function and sarcopenia in NC. MMT and SMI were measured by ultrasonography and bioelectrical impedance analysis in 275 NC participants in Omori Town, Yokote City, Akita Prefecture in the Tohoku region in Japan. Cognitive functions measured from all participants using questionnaire. Participants were classified into low-MMT or high-MMT group based on the median of each of MMT, and SMI and related items in each gender. In addition, to examine the factors related to MMT, logistic regression analysis was conducted by entering age,sex, SMI, nutrition status, severity of dementia, and other items as explanatory variables and MMT as objective variable. SMI in high-MMT group were significantly higher than low-MMT group(high-MMT: 4.8±1.4 kg/m2, low-MMT: 4.4±1.4 kg/m2, P=0.010).Furthermore, logistic regression analysis indicated that SMI were significantly associated with a MMT(Odds Ratio=0.83, 95% Confidence Interval=0.69-0.99, P=0.049). Our result suggested that the mass of the masseter muscles decreased with NC due to sarcopenia, possibly contributing to a decrease in masticatory function.
- 著者
- Piotr Mazur Ewa Wypasek Bogusław Gawęda Dorota Sobczyk Przemysław Kapusta Joanna Natorska Krzysztof Piotr Malinowski Jacek Tarasiuk Maciej Bochenek Sebastian Wroński Katarzyna Chmielewska Bogusław Kapelak Anetta Undas
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-16-1166, (Released:2017-03-24)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 3 10
Background:Valve calcification is well estimated by ex-vivo micro-computed tomography (micro-CT). The objective of this study was to investigate the associations between micro-CT findings and biological indices of calcification in aortic stenosis (AS), as well as differences between bicuspid aortic valve (BAV) and tricuspid aortic valve (TAV).Methods and Results:Aortic valves and plasma were obtained from patients undergoing valve surgery. Valves were dissected and underwent micro-CT, genetic analyses, and calcium content assessment. Plasma levels of calcification markers were measured. Forty-two patients with isolated severe AS, including 22 with BAV, were studied. BAV patients had a lower median CT value (140.0 [130.0–152.0] vs. 157.0 [147.0–176.0], P=0.002) and high-density calcification (HDC) fraction (9.3 [5.7–23.3] % vs. 21.3 [14.3–31.2] %, P=0.01), as compared with TAV. Calcification fraction (CF) correlated with AS severity (measured as maximal transvalvular pressure gradient [r=0.34, P=0.03], maximal flow velocity [r=0.38, P=0.02], and indexed aortic valve area [r=–0.37, P=0.02]). For TAV patients only, mRNA expression of integrin-binding sialoprotein correlated with CF (r=0.45, P=0.048), and the receptor activator of the nuclear factor κ-B ligand transcript correlated with HDC corrugation (r=0.54, P=0.01).Conclusions:TAV patients with AS present more mineralized calcifications in micro-CT than BAV subjects. The relative volume of calcifications increases with the AS severity. In TAV patients, upregulated expression of genes involved in osteoblastogenesis in AS correlates with leaflet mineralization in micro-CT.
1 0 0 0 OA バランス・テクノロジー
- 著者
- 研野 和人 神出 瑞穂
- 出版者
- 公益社団法人 日本工学教育協会
- 雑誌
- 工業教育 (ISSN:18839002)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.10-13, 1979-01-20 (Released:2009-04-10)
1 0 0 0 OA 創刊の言葉
- 著者
- 笹川 久吾
- 出版者
- 公益社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 自律神経雑誌 (ISSN:03870952)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.3-3, 1948-09-15 (Released:2011-05-30)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 兵頭先生と良導絡(1)
- 著者
- 編集部
- 出版者
- 日本良導絡自律神経学会
- 雑誌
- 日本良導絡自律神経学会雑誌 (ISSN:09130977)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.9, pp.198-223, 1996-09-15 (Released:2011-10-18)
1 0 0 0 OA 良導絡発刊の辞
- 著者
- 笹川 久吾
- 出版者
- 日本良導絡自律神経学会
- 雑誌
- 良導絡 (ISSN:09130942)
- 巻号頁・発行日
- vol.1960, no.1, pp.1-1, 1960-07-15 (Released:2011-10-18)
1 0 0 0 OA 良導絡の発生とその背景(1)
- 出版者
- 日本良導絡自律神経学会
- 雑誌
- 日本良導絡自律神経学会雑誌 (ISSN:09130977)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.9, pp.229-233, 1991-09-15 (Released:2011-10-18)
1 0 0 0 OA 手術室配属となった新人看護師が知覚する仕事に関する就職前のイメージと就職後の実際の相違
- 著者
- 松浦 一恵 亀岡 智美
- 出版者
- 日本看護教育学学会
- 雑誌
- 看護教育学研究 (ISSN:09176314)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.69-84, 2015-03-31 (Released:2016-11-10)
研究目的は、手術室配属となった新人看護師が、何に対し「仕事に関する就職前のイメージと就職後の実際の相違」を知覚しているのかを解明し、その知覚の特徴を考察することである。全国196病院に勤務し、新人看護師として手術室配属となった経験を持つ臨床経験4年未満の者954名を対象に、郵送法による調査を行なった。測定用具には、対象者背景と「仕事に関する就職前のイメージと就職後の実際の相違」に対する知覚を問う自由回答式質問を含む質問紙を用いた。454名(回収率47.5%)から質問紙を回収し、自由回答式質問に回答していた186名の記述をBerelson, B.の方法論を参考にした看護教育学における内容分析を用いて分析した。その結果、【患者や家族との相互行為機会や時間の多少、その獲得の難易】等の手術室配属となった新人看護師が知覚する「仕事に関する就職前のイメージと就職後の実際の相違」を表す30カテゴリが形成された。Scott, W. A.の式に基づき算出したカテゴリ分類の一致率は、看護学研究者2名ともに92.3%であり、30カテゴリが信頼性を確保していることを示した。30カテゴリと文献との照合は、手術室配属となった新人看護師による「仕事に関する就職前のイメージと就職後の実際の相違」の知覚が、6つの特徴を持つことを示唆した。周囲の看護師や医療従事者がこのような特徴を理解し支援することは、手術室配属となった新人看護師の学生からの役割移行、職場適応や就業継続を促進する。
1 0 0 0 OA 新卒看護師の看護技術に対する看護教員と看護実践者の評価の視点と到達基準
- 著者
- 新美 綾子
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.4, pp.4_33-4_44, 2011-09-01 (Released:2016-03-05)
- 参考文献数
- 42
新卒看護師が実施する輸液ラインのある患者の寝衣交換技術を看護教員と看護実践者が同時に観察する方法を通して,新卒看護師の看護技術に対する看護教員と看護実践者の評価の視点と到達基準を明らかにした。看護教員は技術面に焦点をあて,⑴教授内容である基本的な方法で行われているか,⑵患者を尊重した丁寧な実施であるか,⑶一人でやり遂げることができるかを評価の視点とし,看護技術を一人でやり遂げることを到達基準としていた。看護実践者は,臨床現場のやり方を基準に,⑴声かけなどの患者応対面はどうか,⑵患者に苦痛や危険がなかったかを評価の視点とし,臨床現場と同じ状態で患者に苦痛,負担なく安全にできることを到達基準としていた。さらに,看護実践者には,声かけと出来栄えにより看護技術全体の評価を決定づける傾向を認めた。また,看護実践者が評価の基準としている臨床現場のやり方を,看護教員は基本から離れている実施としてとらえる相違を認めた。
1 0 0 0 OA 赤とんぼの故郷で(環境保全型農業の展開と有機、特別栽培農産物の生産)
- 著者
- 石附 徹太郎
- 出版者
- 北陸作物・育種学会
- 雑誌
- 北陸作物学会報 (ISSN:03888061)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.136-139, 1998-03-31 (Released:2016-12-07)
1 0 0 0 OA 視覚障害児の発育・発達
- 著者
- 中田 英雄
- 出版者
- 日本発育発達学会
- 雑誌
- 発育発達研究 (ISSN:13408682)
- 巻号頁・発行日
- vol.1995, no.Appendix, pp.67-75, 1995 (Released:2010-03-16)
- 参考文献数
- 46
It is reported that physical growth of blind and partially sighted children is in a poor level and the adolescent growth spurt is earlier in the blind than in the partially sighted and the sighted. Most of studies of age at menarche have noted earlier onset in the blind than in the sighted. These studies have suggested that blindness is associated with an age of menarche which is earlier than sighted adolescents. Previous studies described delays in the appearance of motor skills, especially agility, with poor physical work capacity and balance. A recent research has suggested that the physical work capacity and postural control of the blind and partially sighted can be developed by appropriate training. By some well-designed program, the blind and partially sighted children should be able to enhance the ability to use their potential to the fullest. The adapted physical activity should be better understood.
1 0 0 0 OA 「集団コラージュ療法」を活用した新人看護師のストレスケアの試み
- 著者
- 倉益 直子 田内川 明美 宮内 幸子
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.49-54, 2012-05-30 (Released:2012-09-20)
- 参考文献数
- 9
2004年に看護協会が実施した「新卒看護職員の早期離職等実態調査」において,新人の9.3%が1年以内に離職していたという結果は,看護界を驚かせた。離職理由としては,「基礎教育終了時の能力と現場で求められる能力のギャップ」「肯定的なストロークが少ない職場風土」「教育的配慮の不足」などが挙げられている1)。新人看護師にとっての入職後1年間は,これまでになくストレスフルな毎日であることがこの調査により明らかになった。事実,新人看護師の中で「眠れない」「食べられない」「仕事に行けない」などの深刻な症状を呈し離職に至る者もいる。 心理学によると,ストレス反応を低下させる要因は,「自尊感情 (self-esteem)」「自己効力感 (self-efficacy)」「アイデンティティ (identity) の確保」の3つであると言われている2)。ところが,医療現場では常に「完全」を求められることや,対人援助職特有の「やってもきりがない」等の不満足感が,自尊感情や自己効力感を低下させる。このことからも新人看護師が初めて接する看護現場は,ストレス反応が起こりやすい環境であると言える。そのため,当院では以前より新人看護師の心身のリラックスを図る新人研修として「集団コラージュ療法」を取り入れてきた。「コラージュ療法」はこれまで,精神科臨床や非行対応臨床などから始まり,最近は,末期がん患者や認知症患者などにも活用されて成果を挙げている。我々が検索した文献では,健康な専門職への適用は見られなかったが,当院では10年前から実施しており,その安全性はすでに確認されている。今回,当院における新人看護師対象の「集団コラージュ療法」について検討したところストレスケアとして有用と考えられる所見が得られたので報告する。
1 0 0 0 OA 勤労者におけるストレス評価法(第1報)
- 著者
- 夏目 誠 村田 弘 杉本 寛治 中村 彰夫 松原 和幸 浅尾 博一 藤井 久和
- 出版者
- 社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業医学 (ISSN:00471879)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.4, pp.266-279, 1988 (Released:2009-03-26)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 10 8
私たちは勤労者のストレス度,特に職場生活のそれを数量化するために,下記のストレス調査表を作成した.Holmesが作成したストレス度を測定する,社会的再適応評価尺度の主要項目に,職場生活ストレッサー18項目,および「私の耐えられるストレス度」,「現在の私のストレス度」の2項目を追加した67項目より構成されている.1,630名の勤労者を対象に結婚によるストレス度を50点とし,それを基準に0~100点の任意数値記入方式により自己評価させた,得られた結果は以下のとおりである.1. 各項目について1,630名と性,年齢,職種,職階,勤続年数(以下,各条件とする)別対象者数から得られた点数の平均値を求めた.私たちは,このようにして得た各項目の平均点数をストレス点数と仮称した.65項目のストレス点数を,高い順にランキングした. 1位は「配偶者の死」82.7で,「収入の増加」が24.7と最下位であった.27項目が50点以上の得点を示した.次に65項目を,個人,家庭,職場,社会生活ストレッサーの4群に分類した.2. 職場適応力をみるために私たちが考案した「私の耐えられるストレス度」は73.7で「現在の私のストレス度」は48.8であった.3. ストレス点数の平均値から,各条件別でt検定により比較検討を行い,差異を求めた.その結果は, 30歳代では20歳代に比べ,課長と班長は部長より,点数が高かった.同様に,上記の4群間でそれを求めたところ職場生活ストレッサー群のみ差が認められた.同群において, 30, 40, 50歳代は20歳代よりも,課長と班長は一般職に比し,高得点であった.勤続年数では, 21年以上の勤務者は, 10年以内の者に比較して点数が高かった.以上の結果や調査表の意義と活用を中心に考案を加えた.
1 0 0 0 OA 戦前の東京における汲取便所の構造に関する規程について
- 著者
- 安野 彰 櫻内 香織 内田 青藏 藤谷 陽悦
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.33, pp.739-742, 2010-06-20 (Released:2010-06-18)
We tried to arrange many notifications and regulations for cesspit toilets announced by Department of Interior and Tokyo Metropolitan Police Department. At last, it revealed that they thought cholera breeds especially with human waste, Department of Interior showed concrete model of the regulation for Tokyo in prevalence of disease, and the regulation didn’t much change from 1887. And we considered that changes of materials for cesspit-pool reflected spread of technology in those days.
- 著者
- Yosuke Tashiro Hiroaki Eida Satoshi Ishii Hiroyuki Futamata Satoshi Okabe
- 出版者
- 日本微生物生態学会 / 日本土壌微生物学会 / Taiwan Society of Microbial Ecology / 植物微生物研究会
- 雑誌
- Microbes and Environments (ISSN:13426311)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.40-46, 2017 (Released:2017-03-31)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 19
A conjugative F plasmid induces mature biofilm formation by Escherichia coli by promoting F-pili-mediated cell-cell interactions and increasing the expression of biofilm-related genes. We herein demonstrated another function for the F plasmid in E. coli biofilms; it contributes to the emergence of genetic and phenotypic variations by spontaneous mutations. Small colony variants (SCVs) were more frequently generated in a continuous flow-cell biofilm than in the planktonic state of E. coli harboring the F plasmid. E. coli SCVs represented typical phenotypic changes such as slower growth, less biofilm formation, and greater resistance to aminoglycoside antibiotics than the parent strain. Genomic and complementation analyses indicated that the small colony phenotype was caused by the insertion of Tn1000, which was originally localized in the F plasmid, into the hemB gene. Furthermore, the Tn1000 insertion was removed from hemB in the revertant, which showed a normal colony phenotype. This study revealed that the F plasmid has the potential to increase genetic variations not only by horizontal gene transfer via F pili, but also by site-specific recombination within a single cell.
1 0 0 0 OA マシンビジョンによる精密ほ場管理のための作物窒素ストレスセンシングシステム (第1報)
- 著者
- 飯田 岳 野口 伸 石井 一暢 寺尾 日出男
- 出版者
- 農業食料工学会
- 雑誌
- 農業機械学会誌 (ISSN:02852543)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.87-93, 2000-03-01 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 40
精密ほ場管理技術による適切な窒素施肥管理が, 収量増加, 環境保全や生産コスト削減の面から期待されている。本研究はマシンビジョンを用いた作物窒素ストレスのリモートセンシングシステムの開発を最終目標とし, 本報ではシステムの構想を概略した。既往のディジタル葉緑素計や葉色カラースケールに対し, 葉面反射率を測定するマシンビジョンによる窒素ストレス診断法を提案した。トウモロコシ葉面の分光反射特性を調べた結果, 反射測定においては550nm, 650nm分光が窒素ストレス推定に適していると判断し, 今後屋外実験においてマシンビジョンに装備する光学バンドパスフィルタの波長帯を550nm, 650nmに決定した。
1 0 0 0 OA グローバル化する韓国の自動車産業
- 著者
- 藤川 昇悟
- 出版者
- 産業学会
- 雑誌
- 産業学会研究年報 (ISSN:09187162)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.22, pp.29-42,155, 2007-03-31 (Released:2009-10-08)
- 参考文献数
- 11
Recently Hyundai has increased its presence in the world automobile industry by expanding overseas production. But, when an automobile producer expands into a foreign country, its productivity is decreased through increased transportation costs. Thus it is necessary for automobile producers to also take parts suppliers to the foreign country. In other words, location with parts suppliers matters.In this paper, to estimate the current growth of Hyundai and the Korean automobile industry in general, we analyzed the location of Korean parts suppliers in comparison with that of Japanese parts suppliers.The results are summarized as follows:1. Korean parts suppliers are concentrated in China, while Japanese parts suppliers are located close to their production centers in North America, Europe, and Asia.2. In North America and Europe, there is a large disparity between the number of Korean automobile producers' production plants and the number of their parts suppliers.3. In comparing the Hyundai Alabama plant and the Toyota Canada plant in North America, it can be seen that Toyota has 82 Japanese suppliers located nearby, while there are only 11 Korean suppliers around the Hyundai plant meaning that Toyota's local procurement rate of parts is higher than Hyundai's by 10-20%.4. In order to maintain growth, Hyundai must raise the rate of procurement of parts from already established local parts suppliers. This expansion of transactions with non-Korean parts suppliers would be accompanied by M & A or strategic alliances between Korean and non-Korean parts suppliers.
1 0 0 0 OA 膝前十字靱帯損傷の受傷機転調査
- 著者
- 森口 晃一 鈴木 裕也 原口 和史
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.33 Suppl. No.2 (第41回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.C0300, 2006 (Released:2006-04-29)
【はじめに】 膝前十字靭帯(ACL)損傷の受傷機転は、非接触型損傷(非接触)が多く、受傷機転はジャンプ着地、ストップ動作、方向転換などが代表的である。非接触では詳細な受傷機転を把握することで、ACL損傷後の理学療法やACL損傷の予防において競技特性を踏まえたプログラム立案につながると思われる。そこで今回、当院でACL再建術を受けた患者の受傷機転を調査し、競技別の受傷機転の特徴について若干の知見を得たので報告する。【対象・方法】 平成16年4月から平成17年10月までに当院でACL再建術を受けた26例を対象とした。カルテと問診より受傷形態を非接触と接触型損傷(接触)に分け、非接触において競技、受傷機転、受傷側を調査した。【結果】 非接触20例、接触6例であった。非接触の競技別数は、バスケットボール(バスケ)8例、バレーボール(バレー)4例、バドミントン(バド)4例、サッカー2例、野球1例、陸上が1例であった。また非接触における受傷側数は左15例(バスケ7例、バレー4例、バド4例)、右5例(バスケ1例、サッカー2例、野球1例、陸上1例)であった。競技別で受傷数の多かったバスケ、バド、バレーの受傷機転は以下の通りであった。バスケは、走行速度を減速した際1例、右へ方向転換した際3例(フェイントで左に踏み込み即座に右に方向転換した際1例、急停止し右に方向転換した際1例、ドリブルの進路を右方向へ変えた際1例)、フェイントされて右へステップした際2例、右から左へジャンプし左下肢で着地した際1例、(以上受傷側左)、フェイントされて左へステップした際1例(以上受傷側右)。バドは、左後方のシャトルを打った際4例で受傷側は全て左。バレーは、スパイク着地時4例で受傷側は全て左。このうち1例は左に流れたトスを打った後の着地で、1例は通常よりもスパイク位置(上肢位置)が後方であった。【考察】 バスケ、バド、バレーでは左膝の損傷が多い傾向にあった。これは右利きが多く左下肢が軸足となることが多いためだと思われる。競技別の受傷機転の特徴は、バスケは特に右への方向転換やステップ時の左膝の損傷が多い傾向にあった。ACL損傷後の理学療法やACL損傷予防のポイントの1つとして、右方向への速い動きでの左下肢機能が重要であると考えられる。バドの受傷機転や受傷側の結果から、左後方への動きの際の左下肢機能がポイントと思われる。さらに左後方に飛んできたシャトルを打ち返すときに体幹を左方向へ傾斜させながら打ちにいったという患者のコメントもあり、体幹の制御能力も重要になると思われる。バレーについては、受傷機転としてスパイク着地時の損傷が多いことから、従来から言われている着地時にACL損傷危険肢位を避けることが大切であるが、空中での体幹制御能力が着地に影響を与えることも考えられるため、体幹機能も重要な要因となると思われる。今後症例数を増やし検討を深めたい。