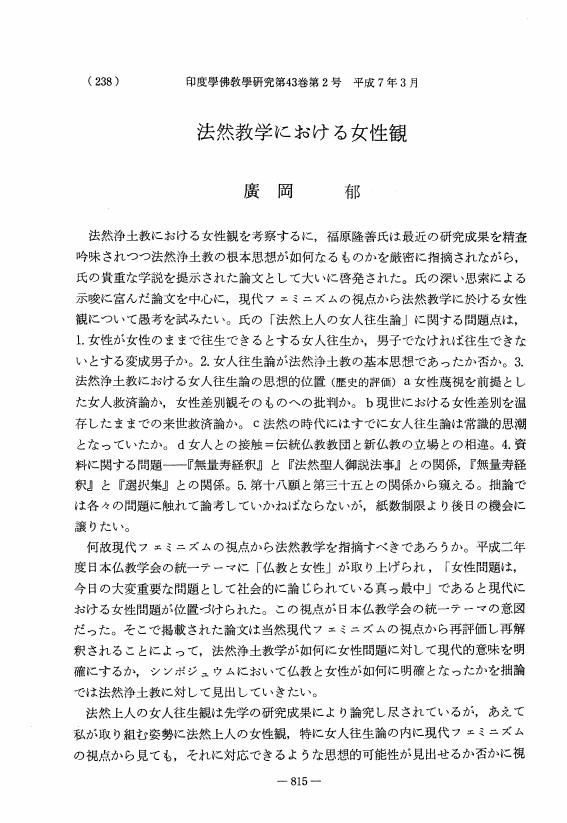1 0 0 0 OA Strategy and Structure Follow Technology
- 著者
- Nobuo TAKAHASHI
- 出版者
- グローバルビジネスリサーチセンター・東京大学MERC
- 雑誌
- Annals of Business Administrative Science (ISSN:13474464)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.15-27, 2016-02-15 (Released:2016-02-15)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 2 7
This study reconfigures part one of Thompson (1967) as a theoretical restatement of Chandler's (1962) historical evidence. When organizations grow, their growth orientations and strategies emerge from their technical rationality, according to Thompson's first criteria of technology instrumentality. Regarding instrumentally reasonable/rational organizations, according to his second criteria of economy, organizational structures such as horizontal departmentalization, vertical hierarchies, and multidivisional forms become necessary to minimize coordination costs. In other words, when discussing growth strategies and multidivisional forms, Chandler claimed that “structure follows strategy,” but Thompson rightfully claimed that “strategy and structure follow technology.”
- 著者
- Yufu KUWASHIMA
- 出版者
- グローバルビジネスリサーチセンター・東京大学MERC
- 雑誌
- Annals of Business Administrative Science (ISSN:13474464)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.1-14, 2016-02-15 (Released:2016-02-15)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 6
Existing studies have shown that highly conspicuous brands are strongly impacted by word of mouth. Bandwagon and snob effects are opposite; however, existing studies have not shown the conditions under which these opposite effects occur. If we assume that they work simultaneously, they would negate each other and become meaningless. Thus, this paper surveys brand-name goods sold in duty free shops and personal networks constituting friends and acquaintances. Results of this social network analysis reveal that people owning many of the same items have no relation with cohesion but have a relation with structural equivalence (SE). In other words, considering the characteristics of a consumer network, (a) the snob effect operates under conditions of cohesion while (b) the bandwagon effect operates under conditions of SE.
- 著者
- Raffaele Pernice
- 出版者
- 日本建築学会(AIJ)、大韓建築学会(AIK)、中国建築学会(ASC) 編集事務局:AIJ jaabe(at)aij.or.jp
- 雑誌
- Journal of Asian Architecture and Building Engineering (ISSN:13467581)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.357-363, 2004 (Released:2005-06-21)
- 参考文献数
- 53
- 被引用文献数
- 1 8
This paper analyzes and considers the main features of the Japanese avant-garde movement ″Metabolism″ that appeared on the scene of the architectural world in the early 60s. The originality of the concepts developed by its members and the innovative design of their projects captured the attention of many critics, in Japan as well as abroad, who often either misunderstood or neglected most of the original theories of the group. Therefore, it seems that furthermore analysis could be necessary to clarify some points of metabolist group′s activity, and to reach a better understanding of the historical context in which Metabolism has originated and developed, as well as of its aims.
1 0 0 0 OA 紐の構造に基づいた織パターンの生成
- 著者
- 森田 克己
- 出版者
- 日本図学会
- 雑誌
- 図学研究 (ISSN:03875512)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.Supplement1, pp.113-118, 2008 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 2
われわれの日常に密接に関わりのある紐は, 古くから実用的あるいは装飾的な目的で, 世界中の国々において様々な状況で使用されてきている。造形的な視点から見れば, 大変魅力的な存在であるといえる.紐はその制作方法の選択肢によって, 制作された紐の構造の相違を示すが、本稿では、紐の制作方法における「織る」という操作に注目した。そして, 織ることによってできるパターンを織パターンと定義し、CGを用い、造形的に魅力のある織パターンのバリエーションを生成し、紐の構造に基づいた織パターンの造形性について検討した。
1 0 0 0 OA 超音波の生体効果を利用したガン治療
- 著者
- 梅村 晋一郎
- 出版者
- 社団法人 日本伝熱学会
- 雑誌
- 伝熱 (ISSN:13448692)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.180, pp.16-23, 2004 (Released:2010-12-16)
- 参考文献数
- 10
1 0 0 0 OA 中世紀における東西の分裂
- 著者
- ハンス・ユルゲン マルクス
- 出版者
- 日本基督教学会
- 雑誌
- 日本の神学 (ISSN:02854848)
- 巻号頁・発行日
- vol.1980, no.19, pp.32-58, 1980-12-25 (Released:2010-01-22)
- 参考文献数
- 92
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA Chemical Composition and Anti-inflammatory Effects of Essential Oil from Farfugium japonicum Flower
- 著者
- Ji-Young Kim Tae-Heon Oh Byeong Jin Kim Sang-Suk Kim Nam Ho Lee Chang-Gu Hyun
- 出版者
- 公益社団法人 日本油化学会
- 雑誌
- Journal of Oleo Science (ISSN:13458957)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.11, pp.623-628, 2008 (Released:2008-10-04)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 10 35
In this study, the chemical composition and anti-inflammatory activities of hydrodistilled essential oil from Farfugium japonicum were investigated for the first time. The chemical constituents of the essential oil were further analyzed by GC-MS and included 1-undecene (22.43%), 1-nonene (19.83%), β-caryophyllene (12.26%), α-copaene (3.70%), γ-curcumene (2.86%), germacrene D (2.69%), and 1-decene (2.08%). The effects of the essential oil on nitric oxide (NO) and prostaglandin E2 (PGE2) production in lipopolysaccharide (LPS)-activated RAW 264.7 macrophages were also examined. The results indicate that the F. japonicum essential oil is an effective inhibitor of LPS-induced NO and PGE2 production in RAW 264.7 cells. These inhibitory effects of the F. japonicum essential oil were accompanied by dose-dependent decreases in the iNOS and COX-2 mRNA expression. In order to determine whether F. japonicum essential oil can safely be applied to human skin, the cytotoxic effects of F. japonicum essential oil were determined by colorimetric MTT assays in human dermal fibroblast and keratinocyte HaCaT cells. F. japonicum essential oil exhibited low cytotoxicity at 100 μg/mL. Based on these results, we suggest that F. japonicum essential oil may be considered a potential anti-inflammatory candidate for topical application.
1 0 0 0 OA メタゲーム理論と囚人のディレンマにおける条件付方略の拡張
- 著者
- 藪内 稔
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.57-65, 1986-08-20 (Released:2010-11-26)
- 参考文献数
- 20
Howard (1966) のPDディレンマに対する解の定式化は条件付方略のいくつかのレベルを許す“メタゲーム”の概念に基づくものである。プレヤーBがプレヤーAの方略に対して反応するとき, これはメタゲームBGを形成する。メタゲームBGにおいては結果 (d, d/d) だけが均衡である。ここにAがcを選ぶならばx/y=x, Aがdを選ぶならばx/y=yである。AがAの方略選択に対するBの反応に対処して方略を策定する場合, これはメタゲームABGを形成する。メタゲームABGにおいては (c, c) と (d, d) がメタ均衡であり, これらはGにおいて安定的であり得る。本研究の目的は, 仮定された相手側プレヤー (プレヤーB) の可能な方略選択に対する被験者 (プレヤーA) の反応を検討し, メタゲーム理論による予測を評価することにある。159名の被験者は5つの利得行列のいずれかに無作為に割付けられた。各利得条件において, 被験者の課題は, 質問紙によって表された基本ゲームG場面, 4つのメタゲームAG場面, および4つの拡張されたメタゲームABG場面に対して, cまたはdを選択することである。主な結果は以下のとおりである。(2) 基本ゲームG場面, およびすべてのメタゲームAG場面においては, 利得行列の如何によらず, ほとんどの被験者がdをためらわずに選択した。(2) 拡張されたメタゲームABG場面においては, 利得行列の如何にかかわらず, 仮定された相手側プレヤーBがc/dを選択したとき, かつそのときに限り, 多くの被験者はcを選択し, 結果 (c, c) を安定的であると期待している。これらの結果は, 高次なレベルに至る相互期待として定義される共有期待 (mutual expectation) が, プレヤー相互が互いの行動を調整するうえに重要であることを示唆するものである。
1 0 0 0 OA 列車運行と強風規制
- 著者
- 荒木 啓司 日比野 有 鈴木 実
- 出版者
- 一般社団法人 日本風工学会
- 雑誌
- 日本風工学会誌 (ISSN:09121935)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.10-16, 2015-01-31 (Released:2015-05-22)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 OA リアルな謎のリアリティ
- 著者
- 東 賢太朗
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第43回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.44, 2009 (Released:2009-05-28)
人類学のフィールドにおいて、「わかる」ための努力がなされる一方で、「わからない」ことが必ず残されていく。そのような解き明かされない「謎」の持つリアリティについて、本発表では考察する。フィクションの諸ジャンルでは、非現実や非日常の要素がリアリティの表現として効果的に用いられるのに対し、人類学には民族誌のもつ虚構性に対する批判が向けられる。両ジャンルの並置と比較から議論を展開したい。
1 0 0 0 OA 〈趣旨説明〉 ミステリーの人類学
- 著者
- 東 賢太朗
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第43回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.43, 2009 (Released:2009-05-28)
本分科会では、人類学(者)がフィールドで出会う謎と秘密、不思議と驚き、すなわち「ミステリー」の魅力と可能性について議論を展開する。具体的には、人類学とフィクション(ミステリー、ファンタジー、SF)との関係、フィールドワークのプロセスにおけるフィクションとリアリティ、そして調査対象自体に内在するミステリーといった問題系に着目する。
1 0 0 0 OA 局所的特徴に基づく対象物同定の一手法
- 著者
- 中村 庸郎 川嶋 稔夫 青木 由直
- 出版者
- 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.152-159, 1990-04-15 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2
To realize intelligent robot, it is necessary to establish an effective method for visual and tactile recognition. Much of the existing work on tactile recognition has assumed that tactile sensors derive only data on object surfaces so as to generalize recognition algorithm. With tactile sensors which provide local features of contact areas, e. g, vertex, edge, etc., it is possible to prune inconsistent interpretations more effectively than existing methods.This paper proposes a method for object identification using local feature sensors. In the method, interpretations at each step of identification process are represented as a set of subsets of 3-D space where a sensor to be located. With the progress of identification process, the set will be narrower. Consequently local constraints become strict and inconsistent interpretations will be efficiently pruned. In the pruning, local constraints are compared considering the error bounds of measurement in sensor data.
1 0 0 0 OA 法然教学における女性観
- 著者
- 廣岡 郁
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.815-811, 1995-03-25 (Released:2010-03-09)
- 著者
- Jun TAMURA Naohiro HATAKEYAMA Tomohito ISHIZUKA Takaharu ITAMI Sho FUKUI Kenjiro MIYOSHI Tadashi SANO Kirby PASLOSKE Kazuto YAMASHITA
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医学会
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.15-0159, (Released:2016-02-11)
- 被引用文献数
- 24
The pharmacological effects of intramuscular (IM) administration of alfaxalone combined with medetomidine and butorphanol were evaluated in 6 healthy beagle dogs. Each dog received three treatments with a minimum 10-day interval between treatments. The dogs received an IM injection of alfaxalone 2.5 mg/kg (ALFX), medetomidine 2.5 µg/kg and butorphanol 0.25 mg/kg (MB), or their combination (MBA) 1 hr after the recovery from their instrumentation. Endotracheal intubation was attempted and dogs were allowed to breath room air. Neuro-depressive effects (behavior changes and subjective scores), and cardiorespiratory parameters (rectal temperature, heart rate, respiratory rate, direct blood pressure, central venous pressure and blood gases) were evaluated before and at 2 to 120 min after IM treatment. Each dog became lateral recumbency, except for two dogs administered the MB treatment. The duration was longer in the MBA treatment compared with the ALFX treatment (100 ± 48 min vs. 46 ± 13 min). Maintenance of the endotracheal tube lasted for 60 ± 24 min in five dogs administered the MBA treatment and for 20 min in one dog administered the ALFX treatment. Cardiorespiratory variables were maintained within clinically acceptable ranges, although decreases in heart and respiratory rates, and increases in central venous pressure occurred after the MBA and MB treatments. The MBA treatment provided an anesthetic effect that permitted endotracheal intubation without severe cardiorespiratory depression in healthy dogs.
- 著者
- Daisuke Uga Yasuhiro Endo Rie Nakazawa Masaaki Sakamoto
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.154-158, 2016 (Released:2016-01-30)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2 8
[Purpose] This study aimed to clarify activation of the infraspinatus and scapular stabilizing muscles during shoulder external rotation at various shoulder elevation angles. [Subjects] Twenty subjects participated in this study and all measurements were performed on the right shoulder. [Methods] Isometric shoulder external rotation strength and surface electromyographic data were measured with the shoulder at 0°, 45°, 90°, and 135° elevation in the scapular plane. The electromyographic data were collected from the infraspinatus, upper trapezius, middle trapezius, lower trapezius, and serratus anterior muscles. These measurements were compared across the various shoulder elevation angles. [Results] The strength measurements did not differ significantly by angulation. The infraspinatus activity was 92%, 75%, 68%, and 57% of the maximum voluntary contraction, which significantly decreased as shoulder elevation increased. The serratus anterior activity was 24%, 48%, 53%, and 62% of the maximum voluntary contraction, which significantly increased as shoulder elevation increased. [Conclusion] Shoulder external rotation torque was maintained regardless of shoulder elevation angle. The shoulder approximated to the zero position as the shoulder elevation increased so that infraspinatus activity decreased and the scapular posterior tilting by the serratus anterior might generate shoulder external rotation torque.
1 0 0 0 OA ターボチャージャー用繊維強化樹脂製インペラー
- 著者
- 飯尾 光
- 出版者
- 日本複合材料学会
- 雑誌
- 日本複合材料学会誌 (ISSN:03852563)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.5, pp.174-180, 1995-09-15 (Released:2009-08-11)
1 0 0 0 OA 4. 劇症1型糖尿病
- 著者
- 花房 俊昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.3, pp.479-481, 2006-03-10 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- Long Zhe Guo Tae-Hee Kim Seongho Han Sung-Whan Kim
- 出版者
- 日本循環器学会
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-15-1169, (Released:2016-02-05)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 2 6
Background:Although stem cells have been regarded as a promising therapeutic option, the marginal therapeutic effects of stem cells are limitations that must be overcome for the development of effective cell therapy. This study sought to identify the angio-vasculogenic properties of endothelial differentiated mesenchymal stem cells (MSCs) and to determine whether these cells are effective for vascular repair.Methods and Results:Adipose MSCs were cultured for 10 days under endothelial cell (EC) culture conditions. These endothelial cell differentiated adipose MSCs (EA) and undifferentiated adipose MSCs (UA) were characterized via angiogenesis and adhesion assays. These cells were transplanted into a hindlimb ischemia (HLI) model to determine therapeutic effects and their underlying mechanisms. EA displayed low adhesion and angiogenic properties in vitro compared with UA. When implanted into mouse HLI models, EA exhibited the decreased recovery of blood perfusion in limb ischemia than uncultured UA. Histology data showed that injected EA exhibited lower retention, angiogenic cytokine levels, and neovascularization in vivo than did UA. Short-term differentiated EA display less cell engraftment and angio-vasculogenic potential, and are less effective for peripheral vascular repair than UA.Conclusions:EC differentiation of MSCs may not present an effective strategy for the promotion of therapeutic neovascularization.
1 0 0 0 OA ナイシンA
- 著者
- 島 純
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.37-37, 2008-01-15 (Released:2008-02-29)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1
ナイシンAは,バクテリオシンと総称される抗菌性ペプチドの1種であり,乳酸球菌Lactococcus lactisにより生産される.2005年にCotterらが提唱した分類に従うと,バクテリオシンは抗菌特性や化学構造からクラスIおよびクラスIIに分類される.ナイシンAが含まれるクラスIバクテリオシンは,ランチビオティクと呼ばれる細胞膜攻撃性の耐熱性低分子ペプチド(<5kDa)である.ランチビオティクの特徴は,デヒドロアラニン,デヒドロブチリン等の修飾アミノ酸を含むことである.また,デヒドロアラニン,デヒドロブチリンの一部は,システインとの分子内縮合によりモノスルフィド結合を有するランチオニンや3-メチルランチオニンを形成する.ナイシンAの抗菌スペクトルは,他のクラスのバクテリオシンと比較して広く,他種乳酸菌やグラム陽性の食中毒細菌の多くに抗菌活性を示す.また,ナイシンAと部分的に構造が異なる天然類縁体であるナイシンZ及びナイシンQの存在が報告されている.ナイシンAの化学構造を模式的に図1に示した.一方,クラスIIバクテリオシンは,ランチオニン等の修飾アミノ酸を含まない低分子ペプチド構造を有するバクテリオシンの全てを包括するとされている.乳酸菌の生産するバクテリオシンが注目される大きな理由は,バイオプリザベーションへの応用の可能性が大きいことにある.有害食品微生物の制御の代表的手法は加熱であるが,全ての食品素材に加熱処理を適用することは出来ない.その場合には,食品保存料の使用が必要となるが,消費者の安全性指向の高まりにともない,化学合成された食品保存料の使用を敬遠する傾向にある.このようなことから,生物由来の安全な抗菌作用を有する天然抗菌物質を活用して,有害食品微生物を制御しようとするバイオプリザーベーション技術の開発が期待されている.バイオプリザーベーションに用いる保存料はバイオプリザバティブと呼ばれ,食経験が十分にあることや有害作用がないことが確認されている必要がある.ナイシンA等を生産する乳酸菌は,ヨーグルトやチーズ等の発酵乳製品や味噌,醤油等の発酵食品の製造に用いられてきており,長年に及ぶ食経験を有していることから,安全が確保されているGRAS(Generally recognized as safe)微生物と認識されている.そのような観点から考えて,ナイシンAをはじめとする乳酸菌バクテリオシンは,バイオプリザバティブとして最適な条件が揃っていると言える.バクテリオシンの食品への利用には,様々な手法が考えられる.1つは,精製したバクテリオシンを食品添加物として利用する手法である.また,バクテリオシン生産菌を発酵食品のスターターとして用いることで,発酵を行いながらバクテリオシンを生産させて有害細菌の増殖を防ぐ手法も考えられる.これらの方法ばかりでなく,食品の種類や形態等に合わせて,多様なバイオプリザベーション手法の構築が可能である.ナイシンAを代表とするクラスIバクテリオシンは,バイオプリザバティブとしての活用が最も期待されている天然抗菌物質であると思われる.実際に,ナイシンAは世界50カ国以上で既に食品保存料として使用されている.我が国においては,現段階ではナイシンAの食品添加物としての使用は認可されていないが,食品安全委員会においてナイシンAに係る食品健康影響評価が進められており,今後の動向が注目される.バクテリオシン生産能を含めた乳酸菌の潜在機能を有効活用することにより,食品の安全性向上が強く期待できる.
1 0 0 0 OA ナイシンの食品工業への応用
- 著者
- 慶田 雅洋
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.31-40, 1967-01-15 (Released:2010-01-20)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 1