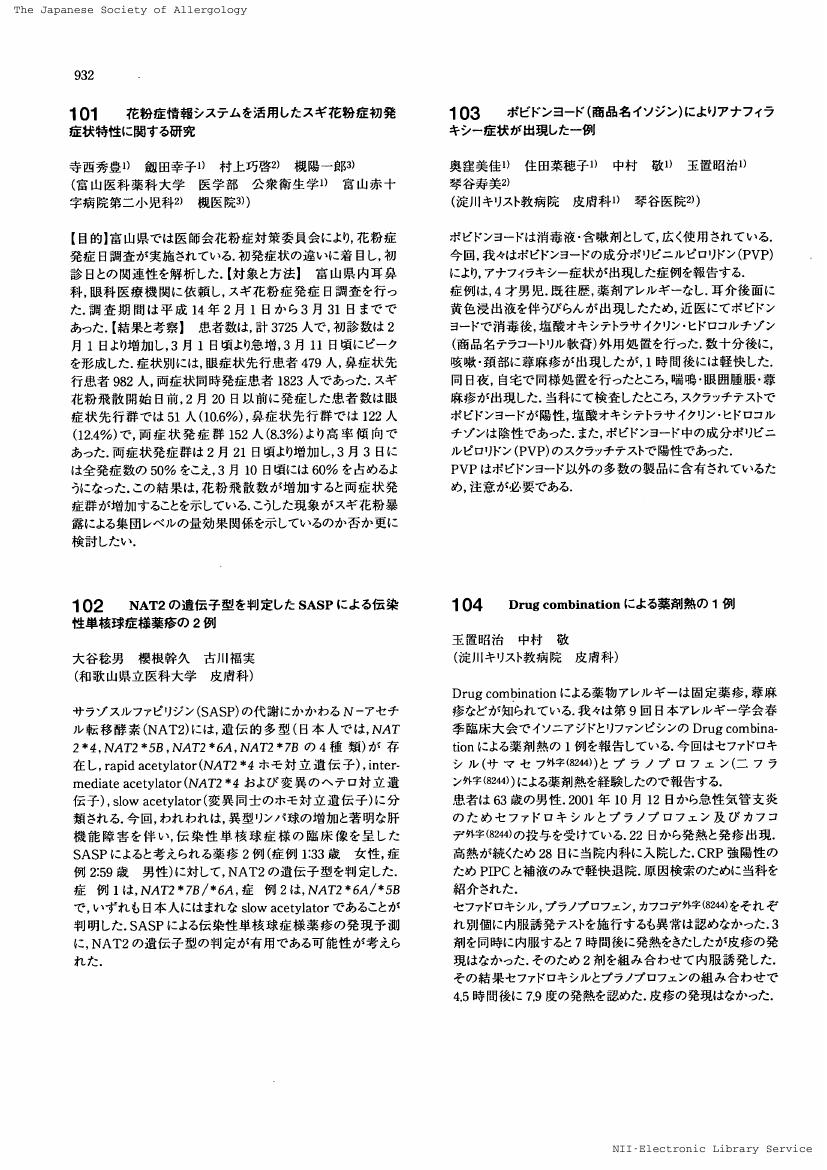23 0 0 0 OA 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言期間における予防行動の関連要因:東京都在住者を対象とした検討
- 著者
- 樋口 匡貴 荒井 弘和 伊藤 拓 中村 菜々子 甲斐 裕子
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- pp.20-112, (Released:2021-06-11)
- 参考文献数
- 21
目的 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は2020年前半に世界規模に広がった。日本においても同年4月7日に緊急事態宣言が発出され,国民生活に大きな影響を与えた。本研究では,COVID-19の感染予防および感染拡大予防行動として個人が行う外出・対人接触の回避行動および手洗い行動を取り上げ,東京都在住者を対象に緊急事態宣言中のこれらの行動の関連要因について検討した。方法 2020年4月26~29日に,東京都在住の20~69歳の男女を対象としたインターネット調査を行った。検討の枠組みとして,リスク低減行動を説明する防護動機理論と,他者による行動が自身の行動実施へ与える影響を説明する規範焦点理論を組み合わせて用いた。最近1週間での外出・対人接触の回避行動および手洗い行動の頻度,COVID-19へのリスク認知に加え,各行動の評価として,どの程度効果があるのか(反応効果性認知),どの程度実行できるのか(実行可能性認知),必要なコスト(反応コスト),どの程度すべきかの認識(命令的規範),他者がどの程度実行しているかの認識(記述的規範)について測定した。各行動を目的変数とする階層的回帰分析を行った。結果 分析対象は1,034人(男性520人,女性514人,平均年齢44.82歳,標準偏差14.00歳)であった。外出・対人接触回避行動については,命令的規範が高いほど行動をとる傾向にある(標準化偏回帰係数(β)=0.343, P<0.001)一方で,記述的規範が高いほど行動をとらない傾向にある(β=−0.074, P=0.010)ことが示された。さらにリスク認知・反応効果性認知・実行可能性認知の交互作用が有意であり(β=0.129, P<0.001),反応効果性認知および実行可能性認知のいずれかが低い場合にのみリスク認知と外出・対人接触回避行動に正の関連が見られた。また手洗い行動については,命令的規範(β=0.256, P<0.001)および実行可能性認知(β=0.132, P<0.001)が高いほど行動をとる傾向にあり,一方で反応コスト(β=−0.193, P<0.001)が高いほど行動をとらない傾向にあることが示された。結論 防護動機理論および規範焦点理論の変数がCOVID-19の予防行動と関連していた。予防行動の関連要因を検討する上で,これらの理論の適用が有用であることが示唆された。
23 0 0 0 OA 頭書増補訓蒙圖彙 21巻
22 0 0 0 OA ついに拓かれた1,000テスラ物性科学への道――電磁濃縮法の世界記録の達成
- 著者
- 中村 大輔
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.6, pp.346-354, 2020-06-05 (Released:2020-10-14)
- 参考文献数
- 39
強磁場マグネットと聞いて多くの方が思い浮かべる装置は,研究室での運用が可能で1~10 T程度の磁場を発生できる,市販の電磁石や超伝導マグネットではないだろうか.国内では,それ以上の強磁場は東北大学金属材料研究所の31 T定常ハイブリッドマグネットや,東京大学物性研究所等の75 T非破壊パルスマグネットによって発生できる.これらはソレノイドコイルに電流を流して繰り返し磁場発生ができるマグネットである.物性研究所では,これらとは全く異なる発想で,磁場発生後にマグネットが破壊されることと引き換えに100 T以上の磁場発生が可能な「破壊型」パルスマグネットの開発に長年にわたって取り組んできた.中でも,300 T以上の磁場を発生できる電磁濃縮法を用いた装置は物性研究所でしか運用されていない世界唯一の装置である.電磁濃縮法では数mmの空間に再現性良く磁場を発生できるため,1,000 T級の磁場を用いた物性研究を目標とした技術開発が1970年代から進められてきた.その結果,1995年には550 T,2002年に620 T,2008年には730 Tの最高磁場に到達し,これまでに600 Tに至る磁場下において磁性体やナノカーボン物質を対象とした物性研究が行われた.しかし,1,000 Tを凌駕する超強磁場の発生には,磁場発生電源(コンデンサバンク)の根本的な見直しと,信頼性のある超強磁場測定法の確立という,2つの大きな壁を乗り越える必要があった.そのため,2010年度より開始された新プロジェクトでは,コンデンサバンク電源,電源からの電流が集約される集電板,主コイルのクランプ装置など電磁濃縮法装置の構成要素すべてを刷新し,1,000 T級の磁場発生が可能な総エネルギー5 MJの装置が2018年に完成した.これらの大規模な装置開発と並行して,筆者は1,000 Tを超える磁場の効率的な発生方法を提案した.最適な実験パラメータを数値計算によって探索した結果,磁束濃縮前の初期磁束を抑制することによって,磁束濃縮を行うライナーの最終的な内径がより小さくなり,発生する最大磁場が増加することが示された.しかし,磁場計測に使用されてきたピックアップコイルによる誘導起電力測定では,電磁ノイズの影響や測定リード線の絶縁破壊などにより,従来より小さい径に発生する超強磁場を計測することは困難であった.そこで,筆者は磁気光学的手法であるファラデー回転法を用いた磁場計測プローブを開発した.総エネルギー5 MJの新型電磁濃縮法装置を用いて初期磁束がある程度抑制された下での実験を行ったところ,2018年4月18日に1,200 Tの磁場発生・計測に成功し,電磁濃縮法によって1,000 Tの壁を越えるという長年の宿願が成就した.1,000 T級の超強磁場による効果は,室温の熱エネルギーや物質中でのファンデルワールス結合エネルギーを凌駕し,電子のサイクロトロン運動が原子間隔程度にまで小さくなる.そのため,超強磁場特有の新現象・新機能が現れるだけでなく,既存の強磁場物質科学研究の枠組みを超えて,化学反応や生命科学などの分野との融合的な研究が芽生えることが期待できる.
22 0 0 0 OA スポーツクレー射撃による衝撃音と選手の聴力
- 著者
- 矢部 多加夫 澤木 誠司 中本 吉紀 伊藤 茂彦 小寺 一興 中村 雅信
- 出版者
- Japan Audiological Society
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.4, pp.223-230, 1997-08-30 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 17
スポーツクレー射撃時の衝撃音が射手に与える影響について検討するために, 衝撃音測定用のダミー人形装置 (KEMAR) を用いて衝撃音を測定し, 63名のクレー射手を対象に純音聴力検査と質問紙調査を実施した。 1) 衝撃音のピーク音圧は約155dBで, 2msec前後にピークをもち, 約50msecで減衰した。 2) 銃口側耳と反対側耳間にピーク音圧差が認められ, 耳介の集音作用が考えられた。 3) 音響外傷予防用具の遮音効果についてはイヤープラグとイヤーマフの併用, イヤープラグ, イヤーバルブ, イヤーマフの順であった。 4) 高音域で明らかな高音急墜ないしC5 dipを示した異常群は非異常群に比べ平均年齢が高く, 平均経験年数が長く, 予防用具使用率が低率を示した。 音響外傷予防用具は遮音に効果的で, 予防用具の必要性と適切な使用法についての今後の一層の普及, 使用率の向上が望まれる。
22 0 0 0 OA 理科における授業実践の効果に関するメタ分析―教育センターの実践報告を対象として―
- 著者
- 中村 大輝 田村 智哉 小林 誠 永田 さくら 大森 一磨 大野 俊一 堀田 晃毅 松浦 拓也
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 科学教育研究 (ISSN:03864553)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.215-233, 2020 (Released:2021-02-05)
- 参考文献数
- 65
This study aims to determine the expected effect size of intervention studies in science lessons through meta-analysis. Intervention studies were collected from education-center websites in every Japanese prefecture to calculate the average effect size and examine the moderation effect. The results of the quantitative analysis showed that the mean effect size of multi-valued items was g=0.594 [0.557, 0.630] (k=626, N=9122). The moderator analysis revealed relatively low effect sizes for learning in the geology domain, and differences in effect size for various types of academic indicators. In addition, we provided basic statistics to help determine the sample size needed for future studies.
22 0 0 0 OA 頭書増補訓蒙図彙大成 21巻
- 著者
- 中村惕斎 編
- 出版者
- 谷口勘三郎[ほか8名]
- 巻号頁・発行日
- vol.[3], 1789
22 0 0 0 IR タイ国産食用植物の発癌抑制活性とその活性物質
- 著者
- 村上 明 中村 宜督 大東 肇 小清水 弘一
- 出版者
- 近畿大学
- 雑誌
- 近畿大学生物理工学部紀要 = Memoirs of the School of Biology-Oriented Science and Technology of Kinki University (ISSN:13427202)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.1-23, 1997-02
現在、癌の化学予防は癌撲滅のための一つの有力な手段と考えられている。なかでも、多段階発癌におけるプロモーション過程の抑制は特に有効である。なぜなら、プロモーションは、多段階にわたる発癌過程において、唯一、可逆性を示す過程であり、しかもその成立に長い期間を要することが動物実験の結果から示唆されているからである。このような背景から、タイ国産食用植物112種(122試料)を無作為に選び、発癌プロモーション抑制活性の短期検定法である、Epstein-Barr virus (EBV)活性化抑制活性をスクリーニングした。プロモーターとして12-O-hexadecanoylphorbol-13-acetate (HPA)を用い、細胞はRaji(ヒトBリンパ芽球様細胞)を使用した。試験の結果、全体の60%の試料が200μg/mLの濃度で30%以上の抑制活性を示した。この抑制活性の発現割合は、以前に行った和産食用植物の試験で得られた割合(26%)を有意に上回るものであった。次いで、8種のタイ国産食用植物から10種の活性化合物を見出した。なかでも、コブミカン((Citrus hystrix、ミカン科)から単離した1,2,-O-di-α-linolenoyl-3-O-β-galactopyranosyl-sn-glycerol(DLGG)とナンキョウ(Languas galanga、ショウガ科)から得られた1'-acetoxychavicol acetate (ACA)のEBV活性化抑制活性は特に高いものであった。7,12-dimethylbenz[a] anthracene (DMBA)と12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA)を用いたマウス皮膚発癌2段階実験では、DLGGはTPAの10倍の塗布量で腫瘍の発生数を50%抑制し、ACAはTPAと同じ塗布量でも有効(抑制率44%)であった。DLGGの重要な作用機構は、プロスタグランジン類生成系の抑制作用であり、ACAのそれは、白血球による過剰な活性酸素の産生の対する抑制作用であると推察された。タイ国産食用植物が示す高い発癌抑制作用、活性物質、その作用機構を中心に述べた。
21 0 0 0 OA 南極大型大気レーダーPANSY
- 著者
- 佐藤 亨 佐藤 薫 堤 雅基 中村 卓司 西村 耕司 冨川 喜弘 橋本 大志 山岸 久雄 山内 恭
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.44-49, 2015-06-01 (Released:2015-06-01)
- 参考文献数
- 3
21 0 0 0 OA 電子レンジの加熱原理に関する誤解
- 著者
- 中村 聡
- 出版者
- 日本物理教育学会
- 雑誌
- 物理教育 (ISSN:03856992)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.103-107, 2006-06-16 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
電子レンジの加執原理を説明する際に,振動する水の分子同士の摩擦熱を考える場合があるが,真実に反している上,熱の分子運動論や摩擦現象のミクロなイメージの涵養を妨げる。いくらかの調査の結果,摩擦熱の説明はかなり流布していて,生徒もテレビなどを通じて聞き,更に学校教育までも荷担していることが判明した。摩擦熱を考える代わりに,「分子が振動していれば,そのエネルギー自体が熱である」と述べた方か良い。もし分子運動論を避けるのであれば,逆に電子レンシの加熱原理についても触れない方が良いと思われる。
- 著者
- 山﨑 俊信 福原 正博 中村 辰之介 朝倉 俊成
- 出版者
- 一般社団法人 日本くすりと糖尿病学会
- 雑誌
- くすりと糖尿病 (ISSN:21876967)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.256-262, 2020-12-20 (Released:2021-01-27)
- 参考文献数
- 9
糖尿病の自己注射療法において,カートリッジゴム栓の消毒不徹底,患者の皮膚組織や血液が逆流する「逆血」などが原因で,細菌が薬液内に入ってしまう(細菌混入の)可能性が否定できない.そこで本研究では,薬液内に混入してしまった細菌が繁殖あるいは死滅する時間的推移を確認した.試料は,インスリン製剤3種とGLP-1受容体作動薬1種,インスリンとGLP-1受容体作動薬の合剤1種,そして生理食塩水とし,細菌は表皮ブドウ球菌(Staphylococcus epidermidis)を用いた.菌数が104 CFU/mLになるように調整した菌試験液を試験温度4℃/25℃環境に保持し,定期的にCFUを測定した.結果は,1h(4℃)で細菌数が増加した製剤はリラグルチド(ノボノルディスクファーマ:ビクトーザ®)とインスリンアスパルト(ノボノルディスクファーマ:ノボラピッド®),1h(25℃)ではビクトーザ®であり,他は減少していた.その後,6hでは全製剤において4℃に比べて25℃の細菌存在比は小さかった.なお,インスリングラルギン(サノフィ:ランタス® XR)は両温度条件でも1h時点で細菌の存在が極めて少ない状況であった(比率はほぼ0).また,全ての製剤において,表皮ブドウ球菌の細菌存在比は4℃に比べて25℃保管の方が小さく,m-クレゾールなどの殺菌作用が温度に影響されることが推察された.また,4℃保管でも全製剤が6h時点で細菌存在比が減少しており,臨床においては次回の注射時刻までには細菌の増殖を抑えていることが確認された.考察として,ランタス® XRはいずれの温度でも1h時点の細菌存在比が極減していたが,その理由はpH3.5~4.5であるためと推測できる.また,ランタス® XRおよびインスリンデグルデク/リラグルチドの配合注(ノボノルディスクファーマ:ゾルトファイ®)以外の3剤においては,菌の存在比率がインスリンリスプロ(イーライリリー:ヒューマログ®)<ノボラピッド®<ビクトーザ®であり,m-クレゾール含有量と相関が取れていた.手技指導において,注射開始時はゴム栓表面の十分な消毒を励行して細菌混入を防止し,保管方法について,使用前はインスリン成分の変質を防ぐために冷所で,また使用中は細菌の増殖を防ぐために室温に保管することを原則とする必要があるという結論を得た.
21 0 0 0 OA 103 ポビドンヨード(商品名イソジン)によりアナフィラキシー症状が出現した一例
- 著者
- 奥窪 美佳 住田 莱穂子 中村 敬 玉置 昭治 琴谷 寿美
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.9-10, pp.932, 2002-10-30 (Released:2017-02-10)
21 0 0 0 IR 学生の自殺 : 富山大学生の自殺事例を通して
- 著者
- 中村 剛 西村 優紀美
- 出版者
- 富山大学保健管理センター
- 雑誌
- 学園の臨床研究 = Clinical Study of Campus Life, 富山大学保健管理センター [編集] (ISSN:13464213)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.13-17, 2000-06
21 0 0 0 コンドーム使用・使用交渉行動意図に及ぼす羞恥感情およびその発生因の影響
- 著者
- 樋口 匡貴 中村 菜々子
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.151-157, 2010
The proper use of condoms is one of the most effective types of protection against HIV. One of the major factors that negatively affect the use of condoms is embarrassment caused by using or negotiating to use condoms. To clarify the causes and effects of embarrassment on using or negotiating to use condoms, 186 undergraduate student volunteers were investigated. The results showed that patterns of types of embarrassment were unclear when they used or negotiated to use condoms. Moreover, structural equation modeling revealed that the embarrassment felt by males was strongly promoted by apprehension of the partner's evaluation, while the embarrassment felt by females was strongly promoted by vagueness in the kind of guidelines aimed at behavior regarding condom use or negotiation to use condoms. Implications of this study on HIV prevention, especially the intervention method of promoting condom use or negotiation to use condoms, are also discussed.
21 0 0 0 OA 火山現象に対する原子力発電所の安全確保についてJEAG4625 改定版の背景とその技術的根拠
- 著者
- 中村 隆夫 中田 節也 岩田 吉左 小野 勤 濵﨑 史生
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会和文論文誌 (ISSN:13472879)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.75-86, 2014 (Released:2014-08-15)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2 4
Japan is one of the countries with abundant active volcanoes and has a long history of developing countermeasures to mitigate volcanic disasters. In the field of nuclear energy, it is also necessary to assess safety against volcanic hazards, and in 2009, a voluntary guideline was published as JEAG 4625 in order to set up requirements of site assessments and basic designs of nuclear power plants (NPPs). This guideline has been revised to satisfy the requirements for examining the necessity of considering volcanic phenomena and concrete countermeasures in detailed designs of NPPs. This paper focuses on the background and technical basis of this voluntary guideline and shows the basic policy to ensure the safety of NPPs and the requirements to prevent nuclear hazards due to volcanic phenomena based on the Defense in Depth Concept.
20 0 0 0 OA 主権批判としての「哲学的宗教」 後期シェリングの『啓示の哲学』を 「政治神学」として読む
- 著者
- 中村 徳仁
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.91-102, 2023-07-01 (Released:2023-07-01)
Seit der Veröffentlichung des Saitya Brata Das' Werks The Political Theology of Schelling (2016) hat die Strömung an Schwung gewonnen, Schellings Schriften als „Politische Theologie“ zu lesen. Ausgehend davon versucht der vorliegende Aufsatz, Motive der eschatologischen Politikkritik in Schellings Spätwerk Philosophie der Offenbarung und vor allem in seinem Projekt der „philosophischen Religion“ zu finden. Im ersten Abschnitt werden die Textentstehung und der Inhalt der Philosophie der Offenbarung zusammengefasst. Im zweiten Abschnitt wird die Schelling-Interpretation von Das vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf dem Konzept der "Exception without Sovereignty" liegt. Der dritte Abschnitt untersucht die Motive der Politikkritik, die in Schellings Verständnis des Christentums verborgen sind, insbesondere in der 9. und 33. Vorlesung der Philosophie der Offenbarung.
- 著者
- 小渕 浩平 務台 均 矢口 優夏 小宮山 貴也 中村 裕一
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.279-288, 2023-06-15 (Released:2023-06-15)
- 参考文献数
- 25
急性期病床入院中の脳損傷者に対して,ドライビングシミュレーター(以下,DS)を用いた評価と,自動車運転再開・非再開の関係性を調査し,急性期病床におけるDSの下位検査項目のカットオフ値と予測精度を検討した.対象は,当院に入院した脳損傷者のうち,評価を完遂した88名であった.分析の結果,誤反応合計,発信停止合計,全般合計,判定得点合計でカットオフ値が算出され,3つ以上カットオフ値を上回った症例は,非再開となる精度が77%であった.また,決定木分析の結果から,神経心理学的検査を含めた複合的な判断が必要である一方,DS評価は急性期病床においても運転再開可否の判定に有用な可能性が示唆された.
20 0 0 0 OA 新しいジェンダー・アイデンティティ理論の構築に向けて―生物・医学とジェンダー学の課題―
- 著者
- 中村 美亜 ナカムラ ミア Mia NAKAMURA
- 雑誌
- Gender and Sexuality : Journal of the Center for Gender Studies, ICU
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.3-24, 2006-12-31
20 0 0 0 OA 作曲家・今史朗の音楽創作史研究――忘れられた作曲家の再評価への試み――
作曲家今史朗(コン・シロウ)は1940年代から1977年に没するまで創作活動を福岡で行っていた.早くから電子音楽に取り組み,前衛的な音楽を次々と作曲・発表していた.しかし彼は福岡以外ではまったく知られていない.福岡においても,死後,彼は忘れられた作曲家になってしまった.私は偶然のキッカケで彼の作品の楽譜と録音を預かることになった.そこではじめて彼の作品に触れ,その作品のレベルの高さに驚嘆した.彼の作品の素晴らしさを多くの人に知らせたい.そのために,本発表では,彼の作曲活動の軌跡を明らかにし,代表的な作品を分析紹介した.今史朗は当時の前衛音楽の歴史を体現した作曲家である。