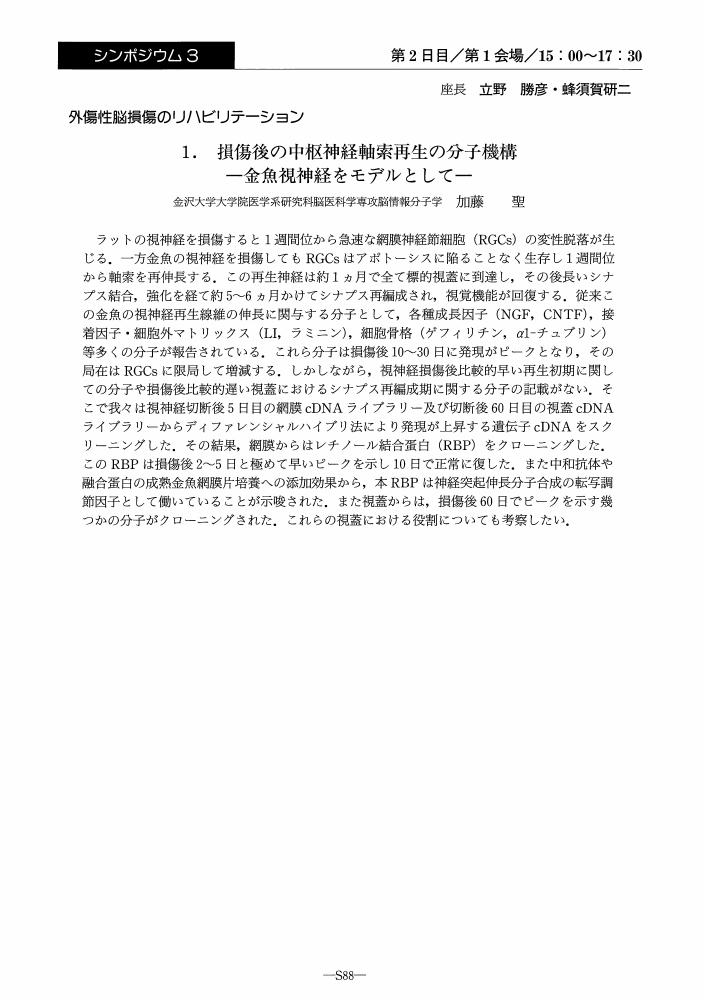- 著者
- 中西 宏明 加藤 雅浩 内田 泰
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経エレクトロニクス = Nikkei electronics : sources of innovation (ISSN:03851680)
- 巻号頁・発行日
- no.1213, pp.77-80, 2020-03
─2020年1月16日に経済産業省が主催した産業アーキテクチャーに関するセミナーの講演で、中西会長は「Society 5.0時代に求められるアーキテクチャーの考え方」と題した講演をしました。なぜ、今のタイミングでそれが重要だというメッセージを出されたのですか。中…
1 0 0 0 OA 0420906 運動前のサウナ浴が呼吸循環機能に及ぼす影響
- 著者
- 加藤 好信 永田 晟 韓 在都
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会号 第42回(1991) (ISSN:24330183)
- 巻号頁・発行日
- pp.324, 1991-09-10 (Released:2017-08-25)
1 0 0 0 OA EPDMブレンドPP/炭酸カルシウム・タルク複合(ハイブリッド)フィラーの力学特性
- 著者
- 永田 員也 日笠 茂樹 酒木 大助 小林 淳 宮原 謙二 和泉 俊弘 須田 敬也 豊原 麻美 加藤 淳 中村 吉伸
- 出版者
- 一般社団法人 日本接着学会
- 雑誌
- 日本接着学会誌 (ISSN:09164812)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.9, pp.343-349, 2007-09-01 (Released:2015-04-30)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1 1
高速撹拝ミキサーを用い炭酸カルシウム(CaCO3;平均粒子径1.4μm)とタルク(3.2μm)の複合化とステアリン酸表面処理とを同時に行い調製したハイブリッドフィラー(Hybridized Filler),,エチレンープロピレンージエン三元共重合体(EPDM)およびPPとを二軸押出機により混練し,複合材料を調製した。得られた複合材料はマトリックスPPにタルク,CaCO3,EPDMがそれぞれ単独に均一分散していた。PPにHybridized Fillerを充填した複合材料の衝撃強度はタルク充填複合材料に比べ優れていた。さらに,EPDMをPPに添加(ブレンド)によりHybridized Filler充填複合材料の衝撃強度は大きく向上した。EPDM(2mass%)ブレンドPPにHybridized Fillerを充填した複合材料の衝撃強度はタルクを充填した複合材料に比較し50%以上向上し,弾性率はタルクを充填した複合材料とほぼ同じであった。複合材料の弾性率向上にはCaCO3に比較してタルクが大きく寄与しており,衝撃強度の向上にはCaCO3が寄与していると考えられる。さらに,CaCO3による衝撃強度の向上においてEPDMのブレンドがその効果を著しく向上させおり,CaCO3粒子とEPDM粒子が共存するとその衝撃強度が相乗的に向上することが明らかとなった。アイゾット衝撃強度試験の破壊を顕微鏡観察した結果,マトリックスとは構造の異なる領域(白化領域)が観察され,これは,フィラー粒子界面に形成されるボイド,エラストマー粒子近傍に形成されるPPのクレーズ,フィラー粒子間でのせん断降伏に起因して形成されたと考えられる。この白化領域が形成される体積が大きいほど複合材料の衝撃強度が大きいことが明らかとなった。
- 著者
- 加藤 洋治
- 出版者
- 公益社団法人日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 咸臨 : 日本船舶海洋工学会誌 (ISSN:18803725)
- 巻号頁・発行日
- no.8, 2006-09-10
1 0 0 0 食べるお茶が効く! : お茶をおいしく食べてぐんぐん元気になる
- 著者
- 大森正司 加藤みゆき 中村羊一郎著
- 出版者
- 主婦と生活社
- 巻号頁・発行日
- 2004
- 著者
- 田中 貞俊 加藤 嵩大 浦野 悟 永吉 雄太
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.197-204, 2015
- 被引用文献数
- 3
中央自動車道上長房橋(上り線)において,既設RC床版のプレキャストPC床版への床版取替え工事と,床版上面増厚工事を実施した。工事は,反対車線(下り線)の対面通行が確保できない現場状況下であったため,施工車線(上り線)の交通を確保しながら,半断面ごとに床版取替えおよび床版上面増厚を実施した。工事時期は,工事内容から昼夜間の連続車線規制が必要であることから,中央自動車道において毎年5月のゴールデンウィーク明けに実施されている2週間の集中工事とした。なお,集中工事における半断面施工は,特に床版取替え工事では高速道路で初の試みであった。本稿は,床版取替え工事および床版上面増厚工事について報告する。
1 0 0 0 OA 山手線新型電車における電気機器について
- 著者
- 加藤 洋子
- 出版者
- 一般社団法人 電気設備学会
- 雑誌
- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.8, pp.568-571, 2015-08-10 (Released:2015-08-11)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 OA 露地夏秋どりミニトマトのソバージュ栽培における収量および品質
- 著者
- 北條 怜子 柘植 一希 樋口 洋子 山初 仁志 加藤 正一 藤尾 拓也 岩崎 泰永 元木 悟
- 出版者
- 一般社団法人 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学研究 (ISSN:13472658)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.137-148, 2017 (Released:2017-06-30)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 6
ミニトマトは,リコピンなどの機能性成分を多く含み,日持ち性もよく,食味が優れることから需要が増えている.しかし,慣行栽培(以下,慣行) では,誘引やつる下ろしなどの作業に多くの労力を要することが問題となっており,栽培管理の省力化や軽作業化が図れる栽培技術の開発が望まれている.著者らは,露地のミニトマトの新栽培法として,慣行に比べて疎植にし,側枝をほとんど取り除かない栽培法を,2010年に開発した.その新栽培法は,ソバージュ栽培(以下,ソバージュ)と呼ばれ,全国的に普及し始めているものの,収量や品質,生育などについて慣行と比較検討した報告がない.そこで本研究では,露地夏秋どりミニトマトにおけるソバージュの栽培体系の確立を目指して,品種特性が異なるミニトマト2品種を用い,ソバージュと慣行を2年間にわたって比較検討した.その結果,ソバージュは慣行に比べて株当たりの総収量および可販果収量が多いことが明らかになった.また,単位面積当たりでも,ソバージュは株数が慣行に比べて6分の1程度であるにも関わらず,慣行と同等または同等以上の収量が見込めることが明らかになった.さらに,ソバージュは茎葉の繁茂による日焼け果の軽減効果も認められた.また,糖度は慣行と同等か低い傾向であったが,リコピン含量は慣行と同等か高まる傾向であった.
- 著者
- 藤原 謙一郎 加藤 由紀乃 御幡 寿
- 出版者
- 茨城県畜産センター
- 雑誌
- 茨城県畜産センター研究報告 (ISSN:13466488)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.31-36, 2006-09
抗菌製剤無添加飼育法を検討するため、無薬飼料を用いてコクシジウムワクチンと生菌剤を使用した区を設け、コクシジウム症の発生や発育成績に及ぼす影響について検討した。その結果、コクシジウムワクチンを使用することにより、コクシジウム症の発生を予防することが可能であることがわかり、無薬飼料による飼養が可能であることが示唆された。また生菌剤を飼料に配合することにより、発育体重及び飼料要求率が改善されたことから、抗菌性物質と同程度とはいかないものの、増体改善効果があることがわかった。これらのことより、コクシジウムワクチンと生菌剤を使用することにより、無薬飼料による飼養が可能であることが示唆された。
1 0 0 0 OA ライフログに基づくテレビ広告の Three-hit theory の検証
- 著者
- 加藤 拓巳 津田 和彦
- 雑誌
- SIG-KSN = SIG-KSN
- 巻号頁・発行日
- vol.23, 2018-09-28
- 著者
- 加藤 雄士 Yuji Kato
- 雑誌
- 産研論集 (ISSN:02881667)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.59-73, 2014-03-24
- 著者
- 加藤 雅子 荒井 洋 小松 光友 ラトン 桃子 立山 清美 西川 隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.10-14, 2021 (Released:2021-02-05)
- 参考文献数
- 18
【目的】日本における青年期脳性麻痺児・者の主観的QOLを評価するため, 国際的に普及しているCerebral Palsy Quality of Life Questionnaire for Adolescents (CPQOL-Teen) 自己回答版を和訳し, その臨床的有用性を検討した. 【方法】原著者の許可を得て和訳したCPQOL-Teen自己回答版を脳性麻痺児・者57名 (cerebral palsy ; CP群) と定型発達児・者58名 (typically developing ; TD群) に実施した. 【結果】日本語版CPQOL-Teen自己回答版は, 両群で十分な検査-再検査信頼性と内的整合性およびJ-KIDSCREEN-27こども版を外的基準とした妥当性を示した. CPQOL-Teenの5領域のうち『機能についての満足度』は, CP群においてJ-KIDSCREEN-27のいずれの領域とも相関せず, CPの特性を反映する可能性が示された. 『コミュニケーションと身体的健康』『学校生活の満足度』『機能についての満足度』の3領域でCP群の得点はTD群よりも低く, 『全体的満足度と参加『社会生活の満足度』の2領域では両群で差がなかった. 【結論】日本語版CPQOL-Teen自己回答版は, 青年期脳性麻痺児・者の特性を踏まえた主観的QOLを把握できる有用な評価尺度であり, 有効な包括的支援の基盤になり得る.
1 0 0 0 金融実務者による知識創造と人工知能実装
- 著者
- 加藤 惇雄 長尾 慎太郎
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.294-301, 2021-05-01 (Released:2021-05-01)
- 著者
- 大野 勝巳 安藤 将人 小竹 庄司 長沖 吉弘 難波 隆司 加藤 篤志 中井 良大 根岸 仁
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌 = Journal of the Atomic Energy Society of Japan (ISSN:00047120)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.10, pp.685-712, 2004-10-30
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
<p> 核燃料サイクル開発機構は, 電気事業者などの参画を得て, オールジャパン体制の下, 1999年からFBR (高速増殖炉) サイクルの実用化戦略調査研究を実施している。本研究のフェーズⅠ (1999~2000年度) に引続き, 2001年度より5ヵ年計画で開始したフェーズⅡ研究の前半部分の終了を受け, 本特集では, これまでに検討されたシステム候補概念の設計研究や要素技術に係わる試験結果などについての進捗状況およびこれまでに得られた成果について解説する。</p>
- 著者
- 加藤 信介 伊藤 一秀 村上 周三
- 出版者
- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会
- 雑誌
- 空気調和・衛生工学会 論文集 (ISSN:0385275X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.78, pp.45-56, 2000-07-25 (Released:2017-09-05)
- 参考文献数
- 9
空気調和・衛生工学会で提案されたHASS 102換気規準では,室内の換気効率(=排気濃度で無次元化された居住域平均濃度,規準化居住域濃度)を加味した換気設計を行うことを推奨している.本研究では,各種換気システムを採用したオフィス空間を対象として,空調吹出空気に含まれるReturn Air(再循環空気)の割合を変化させた場合のこの室内の換気効率,すなわち規準化居住域濃度の構造をVisitation FrequencyおよびPurging Flow Rateの指標を用いて詳細に解析する.本稿においては,筆者らが提案・導入している換気効率指標(Visitation FrequencyおよびPurging Flow Rate)とHASS 102換気規準で定義されている規準化居住域濃度の関係を,室内における循環流とReturn Air(再循環空気,即ち室全体に対する循環流)の相似性から考察する.更に具体的解析事例として一般的オフィス空間を対象として行ったReturn Air(再循環空気)が変化した場合の規準化居住域濃度,Visitation FrequencyおよびPurging Flow Rateの解析結果を示し,3種の異なる換気システムの評価を行うことで,それら換気効率指標の有用性を確認する.
1 0 0 0 IR 4つの成人愛着スタイルにおける愛着対象・手段・方略間での愛着行動の一貫性と安全欲求の検討
- 著者
- 中尾 達馬 加藤 和生
- 出版者
- 九州大学大学院人間環境学研究院
- 雑誌
- 九州大学心理学研究 (ISSN:13453904)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.9-19, 2006
The purpose of this study was twofold: (1) To investigate whether the pattern of frequency differences in attachment behaviors among 4 attachment styles are consistent across attachment figures, means, and strategies, and (2) to examine their differences in security needs that have been theoretically assumed. 211 college students were asked to respond to a questionnaire. Main findings were as follows, (1) Secure and Preoccupied engaged in attachment behaviors more frequently than Dismissing and Fearful-avoidant, regardless of the types of attachment figures (e.g., mother, romantic partner), means (e.g., mail, telephone), and strategies (proximity-maintenance, expressing own feelings more openly). (2) Secure, Preoccupied, and Fearful rated higher for security needs than Dismissing. Those findings were interpreted to demonstrate the validity of the implicitly held, but prevailing, hypothesis: Adult attachment styles do reflect the corresponding patterns of attachment behaviors.
1 0 0 0 OA 損傷後の中枢神経軸索再生の分子機構 金魚視神経をモデルとして
- 著者
- 加藤 聖
- 出版者
- 社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.Supplement, pp.S88, 2004-05-18 (Released:2010-02-25)
1 0 0 0 集中治療部で治療された産科患者の分析
- 著者
- 加藤 浩子 宮脇 郁子 山崎 和夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.41-45, 1999
総合集中治療部で治療を要した産科患者の頻度,原因,転帰を調査し,産科重症患者の内容を分析した。1985~1996年に当院集中治療部に入室した産科患者は40名で,頻度は同時期の全ICU入室患者数の0.17%であった。入室理由は産科的合併症によるものが75%,内科疾患合併が25%で,主たる産科合併症は妊娠中毒症,分娩後出血,胎盤早期剥離であった。入室経路で比較すると,転送患者は院内患者に比し入室時のAPACHE IIスコア,妊娠中毒症の重症度,濃厚治療を要した合併症率が有意に高く,ICU在室日数も有意に長かった。40症例中26症例(65%)が1日でICUを退室し,死亡は羊水塞栓の1症例のみであった。産科重症患者は迅速かつ適切な処置を行えば予後は良好であり,その意味で集中治療部の存在の意義は大きい。産前管理の重要性が再認識されたとともに,今後妊娠中毒症の解明により重症患者の頻度の軽減が期待される。
- 著者
- 宇佐美 太一 加藤 宗規
- 出版者
- 社団法人 日本理学療法士協会関東甲信越ブロック協議会
- 雑誌
- 関東甲信越ブロック理学療法士学会 (ISSN:09169946)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.257, 2017
<p>【目的】</p><p>発症3 ヶ月時点で,トイレの動作と移乗が全介助でオムツを使用していた重度右片麻痺患者に対して行った,課題指向型の立位訓練による効果を検討した.</p><p>【方法】</p><p>80 代男性,左内頚動脈閉塞による重度片麻痺と全失語.Brunnstrom recovery stage(以下,BRS)は右側上下肢,手指全てI.</p><p>97 病日の基本動作は寝返り・起き上がり:中等度介助,座位:見守り,移乗:重度~中等度介助,立ち上がり:中等度介助,歩行:重度介助であった.トイレ介助を目標に縦手すりを用いた立位保持90 秒を目標として介入を追加した.縦手すりを用いた立位保持をベースライン期として,介入1 期は左肩を壁に寄りかかりながら縦手すり使用,介入2 期は左肩を壁に寄りかかることを除去し,縦手すりのみ使用した.いずれも顔の前方にタイマーを配置した.介入は1 日3 回とし,成功した場合には即時に称賛するとともに,3 回終了後はグラフを提示しながら結果のフィードバックを行い,前回よりも改善した場合も称賛を行った.1 日の3 回連続成功により段階達成と判断した.</p><p>【説明と同意】</p><p>本報告はヘルシンキ宣言に基づき、家族に書面にて説明を行い、同意を得た.【結果】</p><p>95 ~98 病日のベースライン期では30 秒の立位保持も困難,介助数は平均10 回を超していた.99 病日の介入1 期初日より改善がみられ徐々に介助数が減少し,介入15 日目には3 回とも成功,介入2 期初日の介入16 日目には縦手すりのみで3 回とも成功した.これらの期間において,機能的自立度評価法(97 →122 病日)は、トイレ動作1 →2 点,トイレ移乗1 点→3 点となった.その間に失語・BRS の結果に変化はなかった.</p><p>【考察】</p><p>発症後3 ヶ月が経過した重度片麻痺と全失語の患者に対して用いた壁に肩をつけるプロンプト・フェイディング法を用いた立位保持訓練は課題指向型の練習として有効であったと考えられた.</p>
1 0 0 0 段階的難易度調整を用いた麻痺側への移乗練習効果の検討
- 著者
- 上村 朋美 加藤 宗規
- 出版者
- 社団法人 日本理学療法士協会関東甲信越ブロック協議会
- 雑誌
- 関東甲信越ブロック理学療法士学会 (ISSN:09169946)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.P-13, 2020
<p>【目的】段階的難易度調整による麻痺側への移乗練習の効果を検討した.</p><p>【方法】80歳代,男性.診断名は,両側大脳梗塞,右慢性硬膜下血腫,肺炎であり,障害名は右片麻痺,失語症,構音障害,嚥下障害であった.入院後のADLは全介助であり,基本動作も介助を要した。立位は右へ傾き,7病日の立位の荷重率(正中位)は右50%,左43%,最大荷重率は評価困難であった.42病日の立位も荷重率は変化を認めなかった.また,移乗の介助量も変化なく,非麻痺側への方向転換は軽介助であったが,麻痺側への方向転換は全く行なうことができなかった.そこで,非麻痺側への移乗練習を介入1,麻痺側への移乗練習を介入2として練習を開始した.環境は,縦手すりを使用した.そして,車いすに対し椅子を30°に配置し,方向転換開始と終了の足の位置をビニールテープで示した.最終目標は非麻痺側・麻痺側共に90°の方向転換見守りとし,30°,45°,90°の順に実施した.角度の変更は,3日連続成功後に行った.評価は,介助量の変化を身体的ガイダンス0点,タッピング+口頭指示1点,口頭指示2点,見守り3点とし,3回の合計点数を記録した.介入2は,介入1の90°方向転換が実施可能となった後に開始した.</p><p>【倫理的配慮】本研究は,ヘルシンキ宣言に則り行われ,症例の家族から承諾を得た.当院研究倫理委員会の承諾を得た(倫理番号1572).</p><p>【結果】42病日目から非麻痺側への方向転換を開始し,90°の方向転換が50病日目で行見守りとなった.同日に麻痺側への方向転換練習を開始し,90°の方向転換が64 病日目で見守りとなった.なお,この期間に認知機能,運動麻痺は不変であった.</p><p>【考察】今回の移乗練習は,難易度の低くい非麻痺側から再構築したため,無誤学習として有効に機能したと考えられた.</p><p>【まとめ】今後の課題は,難易度調整によって,非麻痺側への移乗練習がより早期に開始できる可能性を検討する必要がある.</p>