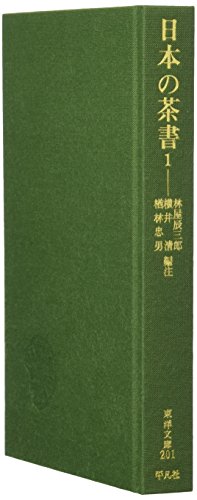1 0 0 0 白髪首刎らるるとも恨みなし : 神澤杜口が橘南谿に語ったこと
- 著者
- 小林 敏男
- 出版者
- 渋沢栄一記念財団
- 雑誌
- 青淵 (ISSN:09123210)
- 巻号頁・発行日
- no.827, pp.34-37, 2018-02
1 0 0 0 大相撲、双葉山時代と昨今
- 著者
- 小林 仲治
- 出版者
- 渋沢栄一記念財団
- 雑誌
- 青淵 (ISSN:09123210)
- 巻号頁・発行日
- no.827, pp.28-30, 2018-02
1 0 0 0 メタステレオタイプと平等主義的な信念が集団間相互作用に及ぼす影響
- 著者
- 小林 智之 及川 昌典
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.6, pp.574-579, 2018
<p>It has been widely documented that egalitarianism motivates people to avoid stereotype use, which in turn facilitates intergroup interactions. However, in addition to perceptions of how the outgroup is perceived by the ingroup (stereotypes), perceptions of how the ingroup is perceived by the outgroup (meta-stereotypes) may also play an important role in intergroup interactions. We hypothesized that when negative meta-stereotypes are perceived, egalitarianism may increase vigilance toward stereotype use by the outgroup, thus exacerbating feelings of anxiety in intergroup interactions. Japanese participants were asked to report how they felt during an intergroup interaction with a Korean confederate, after being exposed to an article documenting positive or negative views Koreans might have of Japanese. The results were consistent with the notion that when negative meta-stereotypes are perceived, participants with high (versus low) egalitarianism experienced more anxiety in the intergroup interaction.</p>
1 0 0 0 学業場面における誘惑対処方略の有効性の検討
- 著者
- 小林 麻衣 堀毛 一也 北村 英哉
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.6, pp.525-534, 2018
- 被引用文献数
- 1
<p>This two-part study aimed to examine the effects of temptation coping strategies on self-control when faced with a conflict between academic goals and temptations. The results of Study 1 indicated that the general use of temptation coping strategies promoted goal pursuits. Study 2 investigated whether differences in the difficulty of goal achievement had an effect on the effectiveness of temptation coping strategies. Goal Verification, Temptation Avoidance, and Goal Execution, which are subscales of the Scale of Temptation Coping Strategies in Academic Situations, were effective strategies to facilitate self-control regardless of the difficulty of goal achievement. However, Mood Changing, which is another subscale of the Scale of Temptation Coping Strategies in Academic Situations, was a strategy that did not affect self-control. These findings indicated that the temptation coping strategies were largely effective in academic situations. The implications of adaptive self-control are also discussed.</p>
1 0 0 0 OA IT法における責任
- 著者
- シュピンドラー ジェラルト 若林 三奈
- 出版者
- 龍谷大学
- 雑誌
- 龍谷法学 (ISSN:02864258)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.97-118, 2006-06
本稿では、IT法領域における責任法(Haftungs- und Verantwortlichkeitsrecht)の展開をとりあげる。その際、2つのテーマを特徴的なものとしてとりあげる。1つは、不完全なソフトウエアに関する責任である。もう1つは、インターネットプロバイダ(Dinste im Internet)に関する責任である。後者は、とりわけ他人のコンテンツの仲介や、それについての準備(Bereithalten)に対する責任である。全体としていえば、法律上はいろいろと新しくなっているものの、依然として、旧来の基本的な問題が、重要な意味をもっているといえる。これらの新しくて古い問題を、PtoP (Peer-to-Peer-Filesharing)、ハイパーリンク、検索エンジン、そして妨害者責任(Storerhaftung)を手がかりに、その概略を展望する。
1 0 0 0 OA アントレプレナー教育におけるコーチング手法導入の有効性
- 著者
- 島岡 未来子 高田 祥三 朝日 透 小林 直人 田上 誠司
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 年次学術大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.592-597, 2017-10-28
一般講演要旨
1 0 0 0 都市近郊の小規模ブドウ産地にみる観光農園経営の意義
- 著者
- 林 琢也
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, 2017
1.研究目的<br> 観光農園とは,都市住民を対象に農業者の生産した農産物の収穫体験や鑑賞,直接販売等を行うために整備した農園を指す。農村の自然環境と農業生産をレクリエーションの対象として利用している点に特徴がみられ,農村空間の商品化を体現する典型的な農業経営といえる。本研究では,岐阜市長良地区のブドウ狩りを例に観光農園経営の展開を検討し,その有効性と課題について考察することを目的とする。<br> <br>2.「長良ぶどう」の誕生と発展,ブドウ狩りの衰退<br> 岐阜市長良地区のブドウ栽培は,山梨県より移住した窪坂宗祐氏らが1922(大正11)年に長良河畔の農地にブドウを植栽したのが始まりである。当地域では,当時,養蚕が盛んで,桑園が広がっていた。ブドウの栽培が面的に拡大していくのは,昭和に入ってからで,高度経済成長の最中の1961年8月にブドウ狩りは開始された。最盛期の1964年には「長良川畔観光園芸組合」の会員数は54戸に達した。名鉄と提携し,市や農協,観光協会,バス会社等の支援を受け,大々的に行われていた。しかし,ブドウ狩りの人気は長くは続かず,集客力の低下した1970年代半ば以降は,沿道でのブドウの直売の方が販売方法の主流となっていった。さらに,生協との取引や農協の運営する直売所への出荷,住宅地への近接性を活かし,庭先や農地に幟を立てた簡易型の直売などの方法を重視する農家も増えていった。その結果,1990年代にはブドウ狩りに対応する農家は6戸となり,2017年現在,「長良ぶどう部会」には39戸が加入しているものの,ブドウ狩りを行う農家は2戸となっている。<br> <br>3.ブドウ狩りの再興<br> 1980年代~2000年代にかけて観光農園数は減少し続けたものの,その間も一定程度の需要は存在していた。こうしたなか,2008年以降,ブドウ狩りの入園者数は増加傾向に転じ,再び活況を呈するようになった。この変化に大きな影響を及ぼしているのが,同年より開始されたタウン誌への割引券の添付である。これによって,身近な地域の住民に「長良ぶどう」を再認識させるとともに,新たな観光需要を喚起することが可能になったのである。こうしたタウン誌は地元の飲食店や観光・レクリエーションに関する情報が多数掲載されているため,小さな子どもをもつ親や孫の手を引いた祖父母の入園を促すことに効果を発揮した。また,旅行専門雑誌にも長良地区のブドウ狩りの記事が掲載されている。こうした雑誌への掲載は,岐阜市および周辺地域からの入園だけではなく,「一宮」や「名古屋」ナンバーに代表される愛知県北部からの自家用車での訪問も増加させている。インターネットやSNSを通じて全世界に情報を発信可能な時代ではあるものの,長良地区のブドウ狩りは,岐阜・愛知周辺の住民が日常的に目を向ける多種の情報誌を上手く活用することで,身近な地域の潜在的な観光需要を実際に入園してくれる現実の観光客に転換させることを可能にしたのである。<br><br> 4.長良地区における観光農園経営の意義<br> 岐阜市長良地区のブドウ栽培は市街化区域内に多くの農地が包摂されているため,規模も小さく,ローカルなブドウ産地に過ぎない。ただし,周辺には競合するブドウ産地もなく,岐阜市から名古屋市に至る地域に居住する都市住民の観光レクリエーション需要を一手に引き受けることが可能なため,農園数やキャパシティ(受け入れ可能人数)に比して,需要過多の状態にある。ただし,現時点で観光農園経営に新たに参入する意思をもった農家はおらず,需要はあるのに,供給が足りないという状況に陥っている。これは,市街地に近接し,就業先にも恵まれ,通勤も容易なことから農家子弟にとって,農業での利潤の最大化を追求する必要性に迫られていないことも影響していよう。その一方で,沿道や庭先で直売のみを行う農家直売所では,販売量が停滞傾向にある農家も少なくない。<br> 両者の差異はどこにあるのだろうか。ここでは,ブドウの生産現場を訪問し,ブドウを自ら収穫し,その場で消費するという行動自体に依然として大きな需要が存在し,それが,新鮮な農産物の購入や生産者との交流を目的とする直売や朝市よりも代替のきかない重要な存在となっていることを示している。<br> その意味では,日本において人々の生活や日常から農業にまつわる活動が縁遠いものとなっていることが,観光農園のニーズを高めているといえるが,根本的には,担い手の問題等が改善しなければ,人々の求める農業生産(物)や農村景観を維持することは難しく,観光農園による農村空間の商品化自体も刹那的なものになりかねないといえる。農村空間の商品化という視点は,単なる余暇やレクリエーション需要への対応のみならず,都市住民に「農」の価値を考えてもらうきっかけづくりの場としても機能させていくことが重要である。
1 0 0 0 医療機関へのアクセシビリティに基づく新しい医療圏
- 著者
- 小林 優一 河端 瑞貴
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, 2017
2011年,厚生労働省は医療圏の設定において,従来の人口規模に加え,基幹病院までのアクセシビリティを考慮するとの指針を示した.そこで本研究では,医療機関へのアクセシビリティに基づく新しい医療圏(医療アクセス圏)を提案し,沖縄の事例を通じて医療の受けやすさを比較する.対象地域は,地理的に内外の流入の少ない沖縄本島とし,対象医療機関は基幹病院の1つである救急告示病院とした.<br> まず,保健医療サービスの需要(人口)の分析を行った.医療サービスを受診する需要サイドの2010年から2050年にかけての人口総数の推移を調べた.その結果,沖縄本島の3つの医療圏の中で,北部医療圏の総面積が沖縄本土の36.2%と最も大きく,2010年から2050年にかけての人口減少率が2倍以上に該当する地区数が,他の医療圏と比較して著しい多いことがわかった.沖縄本土の2倍以上減少率をする地区全体に占める,北部医療圏の割合は39.8%である.<br> 次に,沖縄本島における,救急告示病院から30分圏域を表す医療アクセス圏を作成した.移動限界距離は,カーラー救命曲線(Cara,1981)を基に,多量出血を伴う疾患の致死率が50%以上に高まる30分圏域と定めた.その結果,沖縄北部医療アクセス圏では医療アクセス圏外で暮らす人が101,272人中20,620人になっていた.さらに,各医療圏の救急告示病院数と医療アクセス圏内の地区数を比較した.北部医療圏の総面積は中部医療圏に比べ,約1.9倍大きい.しかし,救急告示病院の圏域内の総数は同数である.これらの数値から,北部医療圏の救急医療を受療出来る機会は相対的に少ないと予想された.<br> さらに,北部医療アクセス圏と隣接する圏域との救急医療の受診しやすさを比較するために,各医療圏のアクセシビリティ指標を算出した.アクセシビリティ指標の算定式は, two-step floating catchment area (2SFCA) 手法(Luo and Wang,2003)を用いた.当初は,北部医療圏は沖縄本島の3つの医療圏内で面積が最も大きく,救急告示病院も少ないことから,需要に比べ供給が少ない,いわゆる需要過多になろうと予測していた.しかし,アクセシビリティ指標を計算することにより,医療アクセス圏内だけで,隣接する圏域同士を比べたら,北部医療圏は中部医療圏に比べ約2.8倍受診しやすいことがわかった.<br> 上記の様な,圏域ごとのアクセシビリティ指標を用いた比較だけでは,具体的に圏域内の,何処の地区から救急告示病院までのアクセシビリティにコストが生じるのか見えづらいという課題があった.これを改善するために,アクセシビリティの算出にODコストマトリクスのデータを用いて,北部医療圏内の医療サービスが相対的不足地区を見つけるための分析を行った.ODコストマトリクスのデータには,3つの救急告示病院と町丁字毎の重心からの1.距離と2.病院病床数,これら2つの変数を用いて(Huff,1964)の修正ハフモデルを用いて,分析した.修正ハフモデルとは,商業施設の集客力を測るためには,売り場の面積に比例し,距離の2乗反比例するというモデルである.今回は,北部医療圏にある3つの救急告示病院における吸引力を算出するために,商業施設の売り場面積に当たる変数に病床数を用いた.北部医療アクセス圏の小地域(町丁字)毎に修正ハフモデルを参考としAccess Cost Index(ACI)を求めた.2010年より,厚生労働省が沖縄県の医療圏見直し対象圏域として指摘した北部医療圏を対象に,救急告示病院へのアクセシビリティを小地域毎にACIを算出した.その結果,北部医療圏の中心市街地の北西部から南部にかけて,3つの救急告示病院から離れるに従いACIは徐々に下がることが確認された.<br> 本研究では,アクセシビリティ指数を医療アクセス圏毎に計算し,比較することで,隣接する医療アクセス圏同士の受診のしやすさが明確になった.2013年,沖縄県保健医療計画(第6次)によると,北部医療圏は今後も医療過疎地域として指摘されており,人口対医療従事者数や人口対病床数で同県他医療圏同士を比較する分析方法だと,救急医療へのアクセスのしやすさに関してやや現状に即していない結果が出てしまっていた.<br> 本研究では,救急医療へのアクセスのしやすさをより現状に即した分析をする為に,医療の受診しやすさに関して,アクセシビリティという指標に着目して,医療圏の現状を分析した.具体的には,救急医療を受診する際に用いる医療アクセス圏マップを作成した.さらに,医療アクセス圏同士を,アクセシビリティ指標を用いて比較することで,医療アクセス圏ごとの受診しやすさが明らかになった.
- 著者
- 河合 成文 中川 勝利 中川 大樹 土橋 孝政 小林 千恵子
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, 2017
<p>【はじめに,目的】</p><p></p><p>近年,共働きや少子高齢化により近隣同士の繋がりや,新旧住民の交流,多世代の交流,さらに家庭内でも交流が減少傾向である。各家庭で多くの介護問題を抱えている現状がある。奈良県橿原市では,「地域の課題は,地域自らが解決する」との観点から,市民が自主的かつ自発的に取り組む公益性のある活動や社会貢献活動を支援しており市民活動の活性化を図るとともに,市民と行政とが協働して地域課題の解決に取り組み,住民サービスの向上を目指している。今回,イベントを通し橿原市,行政,企業,住民同士,自治会,近隣の商店に至るまでの広くて強い繋がりをつくる事を最重要目的とした。地域全体で助け合える地域力向上を目指し,その第一歩として,海のない奈良県で海の日に「第1回橿原ウォーターガンバトル」を実施した。</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>【方法】</p><p></p><p>地域で暮らす現役子育て世代を中心に34名で橿原市から公認された市民活動団体(WAKUWAKU@橿原)を立ち上げた。キャラクターを作成し,ポスターを市内の商店や遊技場,施設などに設置した。SNSを使い参加の募集をした。競技は,5人で1チームとし,子供,大人の部をそれぞれ16チーム,未就園児40名の計200名が参加。勝敗は,頭にポイを装着し,制限時間は2分間とし水鉄砲で打ち合い破れると負け。最終,コートに残った人数が多いチームを勝ちとした。昼食は地域の名店街などでとってもらい交流を図った。コート横に応援スペースを設置した。大会開催場所は橿原市資産経営課に使用許可を得て県立橿原文化会館前広場で実施した。さらに県立橿原文化会館の更衣室,控え室,トイレも使用許可を得た。使用する水は,橿原市水道局と連携し,競技用の水を給水車から直接使用。さらに防災意識の啓発活動も実施。イベント終了後に参加された方や孫を見に来た方にアンケートをとった。</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>【結果】</p><p></p><p>応援スペースには孫を見ようと自ら会場まで足を運ぶ高齢者の方が多く,直接外に出ようというのではなく,2次的に外出意欲がでることが分かった。アンケートからは①家族で話す時間が増えた②近隣の人と話をするいい機会になった③近所にある飲食店やお店を知った④市役所や行政の方と話がしやすくなった⑤相談窓口などの存在を知った⑥楽しかったので是非来年も参加したいという意見が多かった。</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>【結論】</p><p></p><p>橿原市,橿原市教育委員会,橿原市水道局,近鉄八木駅前商店街振興会,近鉄八木駅名店街,橿原市市民協働課,橿原市資産経営課,橿原市水道局,奈良県中和保健所,橿原警察署,橿原消防署と我々理学療法士含め,地域住民が関わることで,市役所や行政の職員とも話がしやすくなったのではないかと考えられる。近隣でも介護の工夫などを共有することや,助け合える関係に近付いたと考えられる。来年はシニアの部や障がい者の部も実施し,地域住民が顔見知りで相談できる環境になり,地域力向上に繋がると考えられる。</p>
1 0 0 0 日本の茶書
- 著者
- 林屋辰三郎 横井清 楢林忠男編注
- 出版者
- 平凡社
- 巻号頁・発行日
- 1971
- 著者
- 三林 洋介 大久保 堯夫
- 出版者
- Japan Ergonomics Society
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.294-295, 1992
1 0 0 0 IR キャンプ集中授業における学生の変化 : 自己概念の変化について
- 著者
- 甲斐 知彦 佐藤 博信 河鰭 一彦 林 直也
- 出版者
- 関西学院大学
- 雑誌
- スポーツ科学・健康科学研究 (ISSN:13440349)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.9-14, 2007-02
The purpose of this study was to examine the change of Self-concept of undergraduates who participated in a camping intensive course. There were 28 subjects of both sexes. For a questionnaire, the self Enhancement Scale created by Kajita was used. The survey was conducted on the undergraduates before and after the camp. As a result, the following findings were obtained: 1) The self-growth points of undergraduates who had participated in the Camping Intensive course increased after the camp. Thus, the Camping Intensive course had helped to improve their self-concept.2) "Effortism," a component of self-concept, increased dramatically after the camp (P<0.05) .3) As a result of a factor analysis of the study results, we were able to sample the four factors of "achievement motivation and self-confidence," "inferiority complex," "effort/challenge," and "other-consciousness." 4) After the camp, we observed a decline in the rank of the "achievement motivation and self-confidence factor" and a rise in the ranks of the "inferiority complex factor" and "effort/challenge factor."
1 0 0 0 OA 日蓮文書の研究
- 著者
- 小林 正博
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.277-274, 2003-12-20 (Released:2010-03-09)
- 著者
- 岩瀬 正典 平田 泰彦 石橋 大海 林田 一洋 永渕 正法 柏木 征三郎 大久保 英雄 松原 不二夫
- 出版者
- The Japan Society of Hepatology
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.8, pp.1053-1060, 1984
慢性肝炎を合併したDubin-Johnson症候群(DJS)の1例を報告する.本症例で興味ある点は,1)肝は肉眼的にほぼ正常の色調を呈した,2)胆汁酸負荷試験で再上昇現象を示したことである.症例は22歳の男性.2年前に急性肝炎(非B型)に罹患.トランスアミナーゼの中等度の上昇,直接型優位の高ビリルビン血症およびBSPの再上昇を認め,腹腔鏡検査で肝はほぼ正常の色調を呈した.組織像は慢性肝炎非活動型の所見であり,主に中心帯の肝細胞内に少量の色素顆粒を認めた.空腹時血清総胆汁酸は増加,ウルソデオキシコール酸500mgを経口負荷後,総胆汁酸濃度は30分で最高値をとった後低下し,90分より再上昇を示した.空腹時総胆汁酸の増加は合併している慢性肝炎の影響も考えられたが,再上昇現象はDJSの胆汁酸代謝異常によるものと考えられた.
- 著者
- 小林 良太郎 小川 行宏 岩田 充晃 安藤 秀樹 島田 俊夫
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.349-366, 2001-02-15
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 7
近年のマイクロプロセッサは,スーパスカラ・アーキテクチャにより,より多くの命令レベル並列(ILP: Instruction-Level Parallelism)をプログラムより引き出し高性能化を図ってきた.しかし,この方法は,スーパスカラ・プロセッサが引き出すことのできる命令レベル並列の限界や,ハードウェアの複雑さの増加により,限界が見え始めてきた.これを解決する1つの方法は,ILPに加えスレッド・レベル並列(TLP: Thread-Level Parallelism)を利用することである.本論文では,レジスタ値の同期/通信機能を備え,複数のスレッドを並列に実行するSKYと呼ぶマルチプロセッサ・アーキテクチャを提案する.SKYは,非数値計算応用で高い性能を達成することを目的としている.このためには,細粒度のTLPを低オーバヘッドで利用することが要求され,SKYでは,命令ウィンドウ・ベースの同期/通信機構と呼ぶ機構を新たに導入した.この機構は,従来のレジスタ・ベースの同期/通信機構と異なり,受信待ちの命令に後続する命令の実行を可能にするノンブロッキング同期を実現している.これにより,TLPとILPを同時に最大限利用することを可能とする.SPECint95を用いた評価により,8命令発行の2つのスーパスカラ・プロセッサにより構成したSKYは,16命令発行のスーパスカラ・プロセッサに対して,最大46.1%,平均21.8%の高い性能を達成できることを確認した.Current microprocessors have improved performance by exploiting more amount of instruction-level parallelism (ILP) from a program through superscalar architectures.This approach, however,is reaching its limit because of the limited ILP available to superscalar processors and the growth of their hardware complexity.Another approach that solves those problems is to exploit thread-level parallelism (TLP) in addition to ILP.This paper proposes a multiprocessor architecture, called SKY,which executes multiple threads in parallel with a register-value communication and synchronization mechanism.The objective of SKY is to achieve high performance in non-numerical applications.For this purpose, it is required to exploit fine-grain TLP with low overhead.To meet this requirement,SKY introduces an instruction-window-based communication and synchronization mechanism.This mechanism allows subsequent instructions to waiting instructions for receiving registers to be executed unlike previously proposed register-based mechanisms.This capability enables fully exploiting both TLP and ILP.The evaluation results show that SKY with two eight-issue superscalar processors achieves a speedup of up to 46.1% or an average of 21.8% over a 16-issue superscalar processor.
- 著者
- 早川 久雄 黒谷 寿雄 一階 正晴 竹林 松二
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学教育 (ISSN:24326542)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.244-251, 1971-06-20 (Released:2017-09-22)
- 著者
- 林 英一
- 出版者
- 獨協大学国際教養学部言語文化学科
- 雑誌
- マテシス・ウニウェルサリス (ISSN:13452770)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.一-四一, 2015-11
The legend or the tradition of the island that sank in the sea is strongly related to “Kami” and is explained. Particularly, in "Heshima" of Kochi Prefecture and "Kanmurijima" of Kyoto Prefecture, an epiphany is connected with an island sinking in the sea. In "Heshima", an island sinks by intention of worshiped “Kami”, and, at this time, "Kami" begins to flow, but appears again afterwards. In "Kanmurijima", "Kami" gets down on the place where an island sank in the sea, and it is considered to be ancestor assumed ancestor Kami of “Kaifu-shi”, and the island comes to be recognized as “Tokoyo”. In "Okameiso" of Tokushima Prefecture, the next world was conscious of to the trace which an island sank in the sea, and after all existence of “Kami” was conscious of. These "Kami" was taken to explain a disaster or to explain the divine nature that was tired to the disaster, not “Kami” as the faith. Therefore we can think with "Kami" as the logic.
1 0 0 0 OA 奈良名所八重桜 12巻
- 著者
- 大久保急鑑秀興, 本林伊祐 作
- 出版者
- 柏屋仁右衛門
- 巻号頁・発行日
- vol.[1], 1678
1 0 0 0 北海道特集: Book Train in Hokkaido
- 著者
- 佐々木 裕道 福井 堅一 直江 理子 小林 真木子 齋藤 温子 小岩 重治 中村 満枝 長崎 ゆかり 中野 禎子 岡田 立美 浦川 利幸 渡邊 忠則 野口 迪子 木田橋 喜代慎 瀬川 幸子 後藤 義朗 地原 かおり 高井 康博 九里 拓人 小林 治雄 窪田 恭子 久司 留美 佐藤 千春 浦谷 孝義 児玉 不二雄 帰山 雅人 高橋 延昭 佐藤 卓 末次 博 中村 昌弘 入田 衛善子 下平 貴子 小川 聡
- 出版者
- The Japan Medical Library Association
- 雑誌
- 医学図書館 (ISSN:04452429)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.161-212, 1994