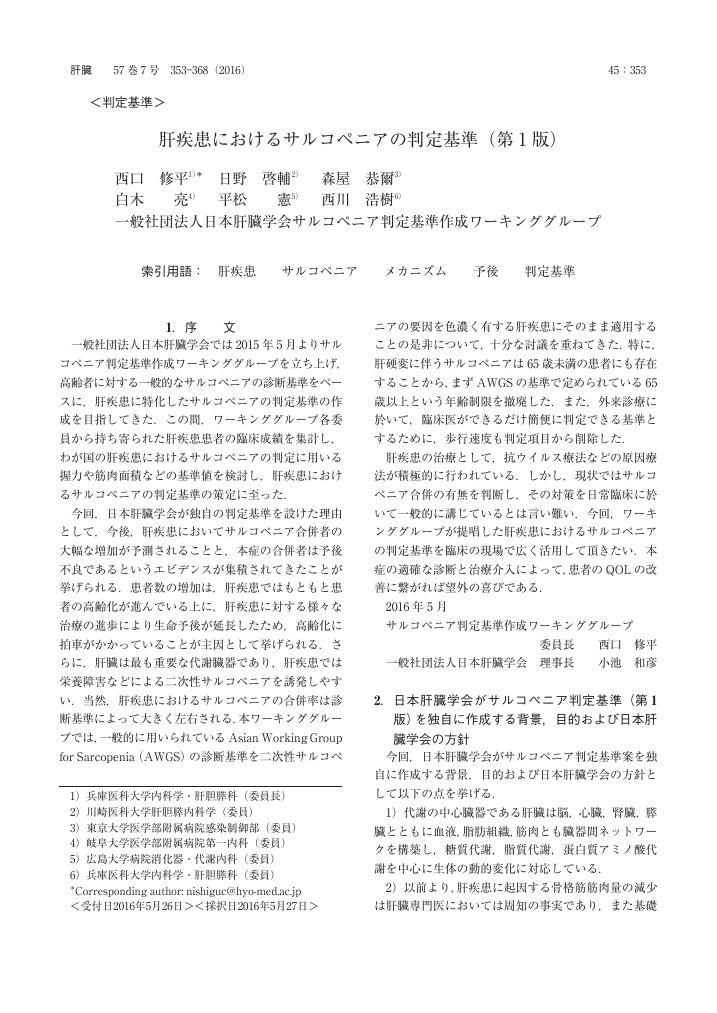1 0 0 0 焼きメレンゲにおけるグラニュ糖と粉砂糖の影響
- 著者
- 坂本 薫 森井 沙衣子 井崎 栞奈 小川 麻衣 白杉(片岡) 直子 鈴木 道隆 岸原 士郎
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.27, 2015
【目的】日本の市販グラニュ糖やザラメ糖のスクロース純度は,99.9%以上と大変高くスクロース結晶とみなすことができるため,製品間で品質に差はないと考えられてきた。しかし,グラニュ糖の融点にはメーカーによって異なるものがあり,融点の異なるグラニュ糖は加熱熔融状況が異なり,示差走査熱量分析(DSC 分析)において異なる波形を示すこと,さらに,スクロース結晶を粉砕することにより,その加熱特性が変化することをすでに明らかにした。焼き菓子の中には,マカロンや焼きメレンゲなど粉砂糖の使用が通常とされるものがある。そこで,グラニュ糖と粉砂糖を使用して焼きメレンゲを調製し,焼き菓子における砂糖の粒度の違いによる影響を検討した。<br><br>【方法】3社のグラニュ糖(W,X,Z)およびそれぞれを粉砕した粉砂糖(Wp,Xp,Zp)を用いた。砂糖のみについて,焼きメレンゲと同条件で加熱し,色差測定,HPLC分析を行った。また,焼きメレンゲを調製し,外観観察および重量減少率測定,密度測定,色差測定,破断強度測定を行った。<br><br>【結果】砂糖のみの加熱では,グラニュ糖のほうが色づきやすく,粉砂糖のほうが着色の度合いは小さかった。また,加熱により,W,Xでは顕著に還元糖が生成していた。砂糖のみと焼メレンゲでは,加熱後の色づき方の逆転現象が認められ,粉砂糖メレンゲのほうが色が濃い結果となった。外観では,粉砂糖メレンゲでは表面はなめらかであったが表面が硬い傾向が認められ,表面に亀裂や気泡が見られた。グラニュ糖メレンゲは,色が白くきめが粗かった。本研究により,砂糖の粒度の違いにより,焼き上がりの外観,色調やきめ,テクスチャーが大きく左右されることが明らかとなった。
1 0 0 0 上代言語資料としての仏典注釈書 (上代語・上代文学の研究)
- 著者
- 白藤 礼幸
- 出版者
- 至文堂
- 雑誌
- 国語と国文学 (ISSN:03873110)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.10, pp.149-161, 1969-10
1 0 0 0 OA 肝疾患におけるサルコペニアの判定基準(第1版)
- 著者
- 西口 修平 日野 啓輔 森屋 恭爾 白木 亮 平松 憲 西川 浩樹 一般社団法人日本肝臓学会サルコペニア判定基準作成ワーキンググループ
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.7, pp.353-368, 2016-07-20 (Released:2016-07-29)
- 参考文献数
- 64
- 被引用文献数
- 1 6
1 0 0 0 OA 戦争とジェンダー
- 著者
- 白井 洋子
- 出版者
- アメリカ学会
- 雑誌
- アメリカ研究 (ISSN:03872815)
- 巻号頁・発行日
- vol.1999, no.33, pp.37-57, 1999-03-25 (Released:2010-10-28)
- 参考文献数
- 91
1 0 0 0 OA 眼皮膚白皮症診療ガイドライン 補遺
1 0 0 0 OA オーバートレーニング症候群
- 著者
- 白山 正人
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.3, pp.395-398, 1996-06-01 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1 1
- 著者
- 白木沢 旭児
- 出版者
- 政治経済学・経済史学会
- 雑誌
- 歴史と経済 (ISSN:13479660)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.31-39, 2010-04-30 (Released:2017-08-30)
- 参考文献数
- 43
This paper first considers whether the controlled economy in the first half of the 1930s was directly connected with the controlled economy of wartime Japan, and second, aims to clarify the meaning of the terms "modification of capitalism" and "reorganization of capitalism". Regarding the first point, in the first half of the 1930s it was thought that a controlled economy and market monopolization were almost the same thing. However, the evils of monopolization were well recognized after economic recovery from the Great Depression, such that the view of the controlled economy as monopolization came to be criticized. Moreover, confrontation between vocational organizations intensified in the first half of the 1930s. Although control regulation for small and medium-sized enterprises existed, for example, in the form of industrial guilds, this was not available to major companies. This problem was solved at last by the 1940 Key-Industries Association Act. Concerning the second point, in the first half of the 1930s, correction of capitalism meant the abolition of laissez-faire capitalism. On the other hand, profit control at companies aiming at low prices was asserted late in the 1930s, and companies were expected not just to pursue profit, but also to work for the improvement of the public good. However, profit controls were not instituted, and bureaucrats who tried to do so in earnest were arrested. As such, controlled economy theory came to have no meaning. In contrast, I term the theory of controlled economy which prospered in 1940s Japan the Japanese-principle controlled economy theory. Controlled economy theory and profit control was not inherited in the postwar period. Consequently, it is suggested that the theory of the controlled economy was different in each of the prewar, wartime and postwar periods. Future research will focus on postwar vocational organizations and control organizations, such as industrial guilds, which continued in existence from the prewar into the postwar period.
1 0 0 0 現実世界との関連を意識したSqUeakカリキュラムの開発
- 著者
- 白井 康雄 竹村顕大朗 上善 恒雄 高田 秀志
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告コンピュータと教育(CE) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.12, pp.77-84, 2007-02-16
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
SqueakeToysは,小学生でも直感的にプログラミングを行うことができる環境として注目されてきており,近年,Squeakを利用した教育の実践例が増えてきている。我々も京都市内の2つの小学校を中心としてSqueakを利用した授業実践を行ってきた。本稿では、それらの実践経験から得られたいくつかの知見や,Squeakの授業導入に関心を持つ教師らを対象としたアンケートの結果を踏まえ、今後のSqueak教育のあり方として,コンピュータ内外の活動を関連させたカリキュラム作りについて提案する。またその一例として 時計を題材に,自然現象を観察する能力や身の回りのものの仕組みに対する興味・関心を養うことを目指した,"時計の再発明,,カリキュラムを紹介し,その実践結果についても報告する。Squeak elbys is an easy-to-learn environment that allows even elementary school students to create their own projects intuitively through programming. Recently, the number of educational activities using Squeak has been increased And we have practiced Squeak-based workshops at two elementary schools in Kyoto. In this paper, based on such experiences and responses to our questionnaire for teachers who are interested in introducing Squeak to their classes, we propose a new design of Squeak-based curricula that include two aspects of activities with and without computers. In addition, as an example of such kind of curricula, we introduce '"Reinvention of the Clock" curriculum aiming for the acquisition of scientific thinking process and interest in the mechanism of industrial products, and report the workshop using this curriculum.
1 0 0 0 OA 小腸広範切除術後の脂肪肝の一例
- 著者
- 白石 公彦 伊藤 博道 沢田 征洋 白地 孝 溝口 実 川野 芳郎 松本 博 安倍 弘彦 谷川 久一
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.6, pp.656-662, 1982-06-25 (Released:2009-07-09)
- 参考文献数
- 20
69歳男性,上腸間膜動脈血栓症のため広範囲小腸切除術を受け約6ヵ月後退院したが,術後9ヵ月を経過した時点で体重減少および全身倦怠感を主訴として当科入院となった.入院時軽度の黄疸および下肢の浮腫を認め,圧痛を有する軟らかな肝を右肋骨弓下一横指触知した.臨床検査より消化吸収障害を示唆する所見が得られ,肝生検にて著明な脂肪肝が認められ,またMallory体も散見された.患者は約2年6ヵ月前より断酒しており,低栄養により脂肪肝を来たしたと思われた.入院後も患者の栄養状態は徐々に悪化し,12ヵ月後に嚥下性肺炎のため死亡した.剖検肝組織に於ては肝生検時に比して脂肪変性は軽減し,Mallory体は増加して見られた.
1 0 0 0 常温硬化型導電性ペーストによるEMI対策効果の簡易評価方法
- 著者
- 由利 伸治 松浦 充徳 白井 治夫
- 出版者
- The Japan Institute of Electronics Packaging
- 雑誌
- 回路実装学会誌 (ISSN:13410571)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.123-127, 1995
プリント配線板に常温硬化型の導電性ペーストをコートすることにより, EMI対策プリント配線板と同様の効果を表現することが可能かどうかを検討した。部品実装完了後の回路板の上から簡易的に導電層を形成する限りでは, 部品の下やICのピン間にペースト処理を施すことができないため, 十分なEMI低減効果は表現できないことがわかった。一方, 部品実装前のベアボード状態からであれば, 常温硬化型導電性ペーストをコートすることにより, EMI対策効果が熱硬化型と同様の結果となり, EMI対策プリント配線板試作を容易にすることができることがわかった。
1 0 0 0 OA ストレスによる腎機能の変化に対する六君子湯の効果
- 著者
- 白取 美幸
- 巻号頁・発行日
- no.63, 2003
1 0 0 0 IR 『新石垣空港』建設に関連して : サンゴ問題を考える (二)
- 著者
- 白井 祥平
- 出版者
- 太平洋学会
- 雑誌
- 太平洋学会学会誌 (ISSN:03874745)
- 巻号頁・発行日
- no.42, pp.69-100, 1989
1 0 0 0 IR イケモテュッベからドゥームへ--「求愛」、「正義」、「紅葉」再読
- 著者
- 白川 泰旭
- 出版者
- 近畿大学語学教育部
- 雑誌
- 近畿大学語学教育部紀要 (ISSN:13469134)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.15-28, 2008
1 0 0 0 IR シフトする視点 : 「紅葉」試論
- 著者
- 白川 泰旭
- 出版者
- 近畿大学
- 雑誌
- 近畿大学語学教育部紀要 (ISSN:13469134)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.87-101, 2007
W.フォークナーは1930年7月、彼自身としては初めてのインディアンに纏わる物語「紅葉」を『サタデイ・イブニング・ポスト』誌に送付し、10月発行の同誌に掲載される。その後、章の構成に改訂が加えられて、フォークナーにとっての最初の短編集『これら13編』(1931)に、続いて十数年の年月を経てマルカム・カウリー編纂の『ポータブル・フォークナー』(1946)、そして最終的に『ウィリアム・フォークナー短編集』(1950)に収録されることになる。さらに、フォークナーはその数章を改訂し、短編集『大森林』(1955)の中の一つの物語「昔の人々」の序章として組み込んでいる。フォークナーの短編作品で、雑誌に掲載された後にあらためて短編集などに再録されたものはかなりの数にのぼる。しかし、「紅葉」が以上のように繰り返し収録された跡をたどると、この作品がフォークナーの数多くの短編作品の中でもきわめて重要な意味を持っていることが窺える。また、批評家J.ファーガソンがこの作品に含まれているさまざまな要素を挙げて、「フォークナーの最もすぐれた短編作品の一つ」と評しているのも十分首肯できる。「紅葉」は、チカソー族の酋長イセティッベハの死に伴い、部族のしきたりに則って彼とともに生きたまま埋葬されるはずの「側仕え」の黒人奴隷が、イセティッベハの死ぬ直前に逃げ出したために、部族の者たちが彼を追跡し、捕えるまでの6日間の様子を描いた物語で、展開されるストーリー自体は単純である。しかし、物語の焦点は追跡それ自体ではなく、その背後に横たわっているこのインディアン部族が抱えるさまざまな問題、言い換えればこの部族の過去および現在の「暗部」に当てられている。ドゥームからイセティッベハへ、そしてモケチュッベへと親子三代にわたって酋長の座が引き継がれていく間に、部族を取り巻く状況はますます悪くなっていくのであるが、その背景には、ドゥームが酋長の座を手に入れた経緯、ドゥームの死後、酋長の座を引き継いだイセティッベハの行動、さらにはその息子モケテュッベとの「赤い踵の上靴」をめぐる父子の相剋などが複雑に絡み合っている。しかし、こうした「暗部」の核心や部族の歴史に暗い影を投げかける隠された事実については曖昧さを残したままである。一方、そのようなインディアンの世界を呈示しながら、それと並行して、逃亡する黒人に焦点が当てられ、彼の生命力にあふれた姿も描き出される。彼は死と向かい合った自分を突き放して冷笑的に見ながら、ただ死から逃れようと走り続けるうちに、生きることに必死だった過去の自分を思い出し、自分の中に生きたいという気持ちが湧き起こってくるのに気づく。その描写は生き生きとして、インディアンたちの姿を描くときの語りとは明らかに異なる。このように、読者はこの物語の中に2つの世界を見ることになるのであるが、それぞれの世界が描かれた章は明確に区別され、章によって視点も変わるために、読者は異なった人物の「目」を通してそれらを見ることになる。逃亡奴隷の追捕という、軸となるストーリーそのものの単純さにもかかわらず、この作品が多くの批評家によって高く評価されているのは、この作品の整った章構成と語りの妙ゆえであろう。本論では、この語りの技法と構成を考察し、物語におけるその効果を分析することを目的とする。
- 著者
- 白土 裕子
- 出版者
- 日本端末研究会
- 雑誌
- オンライン検索 (ISSN:02863200)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.75-91, 2015-06
- 著者
- 白田 由樹
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会
- 雑誌
- フランス語フランス文学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.97, 2010
1 0 0 0 新聞記事の自動要約によるニュース速報配信
1 0 0 0 ベトナム戦争と帰還兵詩人
- 著者
- 白井 洋子
- 出版者
- 日本女子大学
- 雑誌
- 日本女子大学紀要. 文学部 (ISSN:02883031)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.63-51, 2011-03-20