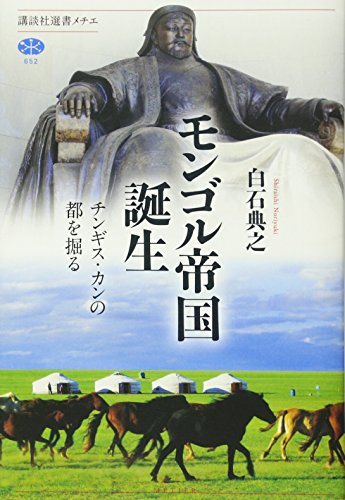2 0 0 0 OA 広島-岩国地域の広島花崗商岩の化学組成
- 著者
- 天白 俊馬
- 出版者
- Japan Association of Mineralogical Sciences
- 雑誌
- 岩石鉱物鉱床学会誌 (ISSN:00214825)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.4, pp.125-136, 1982-04-05 (Released:2008-08-07)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1
The Cretaceous Hiroshima granite of the Hiroshima-Iwakuni area is divided petrographically into two types, e. g. biotite granite and hornblende-bearing biotite granite. The dark inclusions in the latter are characterized by containing hornblende commonly, while those associated with the former granite are hornblende-free, tiny in size, and also small in amount. Plotting the chemical compositions on the normative An-Ab-Or diagram, these two types of granite are quite different in trend, although there is no distinct difference on the Thornton-Tuttle's variation diagrams. This cannot be explained by the difference of fractionation and also by the change in partial PH2O of magma under cooling condition. Irregular shape and uneven distribution of hornblende in hornblende-bearing biotite granite indicate that this hornblende was not the crystallization product of granite magma, but was accidental xenocryst transported into the magma. This fact and the difference of trend in the An-Ab-Or diagram suggest the contamination of granite magma by the hornblende-bearing dark inclusions.
2 0 0 0 OA 卵子の提供を受けて母親になるということ
- 著者
- 白井 千晶
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.8, pp.8_30-8_34, 2017-08-01 (Released:2017-12-09)
- 参考文献数
- 5
- 著者
- 白戸 由理 中野 和俊 中山 智博 大澤 眞木子
- 出版者
- 東京女子医科大学学会
- 雑誌
- 東京女子医科大学雑誌 (ISSN:00409022)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, pp.E91-97, 2013-01
【目的】,従来ミトコンドリア(Mt)は細胞外では培養不可能とされてきた。中野らはヒトの血小板とHela mitochondria-less (Rh0)を融合させたCybrid細胞を形質変換させ、Mtの性質を保ちながら核のない細胞株の分離・増殖に成功し、ミトコンドリア細胞(MitoCell)と命名した。MitoCellの生物学的特性を見いだすため、エネルギー代謝の検討を行った。,【対象・方法】, MitoCellの嫌気培養は嫌気培養キットでO2濃度を0.1%以下とし、CO2濃度が21%前後、温度は37℃で培養し光学顕微鏡にて観察した。次に、エネルギー代謝経路の検討のため、MitoCellのTCA回路のクエン酸合成酵素(CS)、リンゴ酸脱水素酵素(MDH)、サクシネート脱水素酵素(SDH)、イソクエン酸脱水素酵素(IDH)とピルビン酸脱水素酵素(PD)をウエスタンブロット法により解析した。さらに、MitoCellの電子伝達系酵素(ETE)活性とTCA回路の酵素活性と検討するため、Cybrid細胞を対照としてETEである複合体II+III、IVとCS活性を測定した。,【結果】,MitoCellでは嫌気的環境下でも4週間の観察で生存・増殖が認められた。ウエスタンブロット法ではMitoCellのCSのみが陽性、PD、MDH、IDH、SDHが陰性であった。酵素活性では、MitoCellは複合体II+III、IVの活性は保たれているがCS活性は欠損していた。,【考察】,MitoCellではTCA回路が好気的代謝経路として機能していない可能性が示唆され、嫌気的代謝経路の関与が推測された。MitoCellが真核細胞であるヒト細胞から形質変換したことを考えると、ヒトの核DNAには嫌気的代謝遺伝子が保存されていると推測され、嫌気的代謝経路が賦活化されたとも考えられる。臨床上がん細胞は体内において低酸素下で存在し嫌気的代謝の関与が示唆されている。MitoCellのエネルギー代謝経路の解明は、がん細胞の治療に繋がる可能性が考えられた。,【結論】MitoCellでは嫌気的環境下でも生存・増殖が認められ、低酸素下で存在し嫌気的代謝の関与が示唆されているがん細胞の性質と関連している可能性が示唆された。
2 0 0 0 IR ドビュッシーの和声美と象徴主義における一考察
- 著者
- 前田 菜月 Natsuki MAEDA 目白大学人間学部子ども学科
- 雑誌
- 目白大学人文学研究 = Mejiro journal of humanities (ISSN:13495186)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.273-282, 2013
- 著者
- 白 才恩 徐 有珍
- 出版者
- 三田図書館・情報学会
- 雑誌
- Library and information science (ISSN:03734447)
- 巻号頁・発行日
- no.77, pp.27-50, 2017
2 0 0 0 IR アブラムシ抵抗性物質,DIMBOA, のコムギにおける消長
- 著者
- 兼久 勝夫 Awan Rustamani Maqsood 鄭 文儀 積木 久明 白神 孝
- 出版者
- 岡山大学資源生物科学研究所
- 雑誌
- 岡山大学資源生物科学研究所報告 (ISSN:0916930X)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.17-26, 1995
Aphids sometimes severely infest wheat plants, mainly sucking phloem sap and disrupting tissues, and in a few cases act as virus vectors. There are resistant and susceptible varieties of wheat against aphids. DIMBOA (2,4-dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3-one) is a substance causing resistance to animals including aphids. The change in the amounts of DIMBOA with growth in eight wheat varieties was estimated in 1990 and 1991. Wheat seeds were sown at mid-November in the former year and harvested in mid-June. Aphids appeared from early April, increased with the growth of the wheat, and finally decreased with the senescence of the wheat. Rhopalosiphum maidis appeared early in the season, R. padi appeared late, Schizaphis graminum and Sitovion akebiae appeared intermittently in the season. S. graminum appeared more frequently on wheat than barley. DIMBOA was detected from wheat but not from barley. Gramine (N,N-dimethyl-indole-3-methanamine) was detected from barley, and is known as an important resistance substance. However gramine could not be detected in wheat. DIMBOA was found in higher amounts in young wheat, and gradually decreased with growth. A clear relationship between the aphid population and DIMBOA amounts could not be observed. However, all the wheat varieties used in this experiment seemed to have resistance against aphids. The resistance was compared with barley susceptible lines. DIMBOA was presumed to share the property of resistance with aconitic acid in wheat.コムギもオオムギと同様に系統・品種によってアブラシによる寄生の程度に差がみられた。数百のコムギ品種について、寄生程度の調査を1989年に予備的に行い、選別した8品種について、1990年と1991年にコムギの抵抗性物質とされているDIMBOAの消長を調べた。寄生程度の比較調査は1989年から1992年まで調べ、年と場所による変動を調べた。数千のオオムギの系統間においてはアブラムシ類の寄生数で百倍以上の差があり、抵抗性と感受性の系統を容易に選別できている。しかし、コムギにおいては数十倍の寄生数を示す系統は見出せなかった。系統間に年と場所での抵抗性と感受性の差が見られても、遺伝的であることが確認された系統はなかった。オオムギと比較して、供試した数百のコムギ系統の中には、アブラムシの寄生が非常に多い感受性系統はなく、供試した全てが多少とも抵抗性の形質を示した。コムギの抵抗性物質であるDIMBOAは冬期2月下旬で約1μg/g新鮮葉の含量であり、生育に伴って減少した。減少の程度は系統間で差が余りなかった。換言するとDIMBOAのない、あるいは極端に少量の系統はなく、全ての系統で抵抗性の一因となっていると考察された。コムギにおいては、オオムギで顕著な抵抗性物質と考えられているインドールアルカロイドのグラミンは検出されなかったが、オオムギで検出されなかったDIMBOAが顕著な抵抗性成分として検出され、これによって両ムギの質的な差異が示された。コムギはもう一つの抵抗性物質である水溶性のアコニット酸をオオムギの約10倍も含有しており、コムギではDIMBOAとアコニット酸の両者がアブラムシ抵抗性物質として作用していると考えられた。
2 0 0 0 高校生における違法性薬物乱用の調査研究
- 著者
- 鈴木 健二 村上 優 杠 岳文 藤林 武史 武田 綾 松下 幸生 白倉 克之
- 雑誌
- 日本アルコール・薬物医学会雑誌 = Japanese journal of alcohol studies & drug dependence (ISSN:13418963)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.5, pp.465-474, 1999-10-28
- 被引用文献数
- 20
2 0 0 0 OA オートクレーブ製法によるCFRPスケルトンカウルの作製
- 著者
- 長坂 明彦 竹把 悠 諏訪 琢眞 松原 達郎 三尾 敦 時村 祐介 磯部 浩己 白川 伸幸
- 出版者
- 長野工業高等専門学校
- 雑誌
- 長野工業高等専門学校紀要 = Memoirs of Nagano National College of Technology (ISSN:02861909)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.2-2, 2013-06-30
2 0 0 0 eスポーツと景品表示法
- 著者
- 白石 忠志
- 出版者
- 東京大学法科大学院ローレビュー編集委員会
- 雑誌
- 東京大学法科大学院ローレビュー = The Univerisity of Tokyo law review (ISSN:21872902)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.86-101, 2017-11
2 0 0 0 OA 焼き物調理に関する研究 (第8報)
- 著者
- 中里 トシ子 白石 芳子 水上 恵美 山崎 清子
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.38-44, 1974-02-20 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 10
小型ガスオーブンを用いて焙焼条件がパウンドケーキの品質におよぼす影響について研究した.焙焼温度は150℃から190℃までの範囲で, 焙焼時間は25-55分の範囲で行なった.本実験によって得た事項を要約すると次のとおりである.1) 焙焼温度と焙焼時間によっては, ケーキの膨化率, かたさ, 水分には有意差は認められなかった.2) 焼き色は各温度ともに第2, 第3水準の焙焼時間がよかった.形状の点からは170℃で40分と45分, 180℃で35分と40分, 190℃では30分と35分焼いたケーキがよかった.評価の合計点から見ると180℃, 35分のケーキが最もすぐれ, α化度は75%であった.3) 焙焼中のガス消費量は焙焼温度5水準問には有意差がなく, 焙焼時間3水準間には有意差が認められた.
2 0 0 0 OA 大昭和製紙鈴川工場の悪臭問題の歴史
- 著者
- 白石 昌春 室伏 力
- 出版者
- JAPAN TECHNICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY
- 雑誌
- 紙パ技協誌 (ISSN:0022815X)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.6, pp.399-405, 1980-06-01 (Released:2009-11-16)
- 参考文献数
- 1
1. 悪臭対策以前の状況鈴川は, 北に富士山, 南は駿河湾に面した静かな農村であった。昭和12年, 内地で最初のクラフト工場が建設されたが, 工場の規模は拡大され, 他の産業も立地し, 工業地帯と変った。公害問題は, 当初粉じん, 次いで田子の浦港のヘドロ, そしてクラフト工場の悪臭が問題となった。2. 新施策鈴川工場は, 1971年に新たなポリシイを決めた。(1) 鈴川工場は公害を出していることを認識する。(2) 隣接住民との対立を最小にすべく努力する。(3) 最も効果的な部分より設備改善を進める。(4) モニターを置いて潜在的な公害原因を探知する(5) 公害の発生源, 量と, 住民に対するインパクトを調査する。3. 工程の改善(1) 悪臭ガスの集合と, キルンとRBでの燃焼。(2) 排水の蒸気加熱真空型ストリッピング。(3) RB関係の改善。モードースクラバーの設置, 無臭化ボイラーの設置。大昭和一荏原 (D-E プロセス) の設置。4. 隣接住民の工程改善に対する反応ガス集合は, 悪臭減少の評価が出たが, 3~6カ月後には, 悪臭が元にもどった, と言われた。鼻が鋭くなったためである。ストリッピングも評価が高かったが, 同じく3~6カ月後には元にもどった, と言われた。回収ボイラーについては反応が出なかったが, 工場の態度は好感が持たれた。重要なのは緊急時に濃い悪臭物質が流れた場合, 無臭に馴れた住民にインパクトが大きい点である。鈴川工場は, 1971年以来, 40名のモニターを配置し, 粉じん, 騒音, 悪臭, 振動のデータを集めている。工場はこれをもとにして, 設備改善を進めたが, その結果が良くモニターの記録に表われた。悪臭に対する感覚は, 悪臭物質が1/10になって, 1/2になったと感ずると言われる。鈴川工場の悪臭物質は, 1972年と比較して, 8.7%以下であるが, 未だ隣接居住者は, 悪臭が消えたとは思っていない。
2 0 0 0 モンゴル帝国誕生 : チンギス・カンの都を掘る
2 0 0 0 OA 人狼知能におけるモンテカルロ木探索に基づく人狼陣営の戦術選択手法
- 著者
- 成瀬 雅人 白松 俊
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, 2016
2 0 0 0 IR <場>とはなにか
- 著者
- 河野 秀樹 Hideki KONO 目白大学外国学部日本語学科
- 雑誌
- 目白大学人文学研究 = Mejiro journal of humanities (ISSN:13495186)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.39-60, 2010
2 0 0 0 OA アスベストの代替品ロックウールの特性と安全性について
- 著者
- 田崎 和江 朝田 隆二 渡邊 弘明 白木 康一
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉱物科学会
- 雑誌
- 岩石鉱物科学 (ISSN:1345630X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.22-33, 2006 (Released:2006-03-01)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1 2
Characterization of man-made rock-wool fibers were investigated by using optical and electron microscopic techniques and discussed how to affect on human health. The rock-wool fibers were collected from spraying on the roof. Mineralogical analyses were carried out by X-ray powder diffraction. Most fibers can exist as straight or curved fine threads with sharp points μm-nm in diameter under electron microscopy observations. The rock-wool is complex agglomerates of fibers and fumes with cement of calcite. The shape and size are significantly important factors for hazardous assessment of man-made fibers. The fibers are easily adhering to protein-rich spherical materials in 1% BSA (bovine serum albumin) and in ringer’s solution for few days aging. Spherical protein-like materials are similar to “asbestos body” with dumbbells shape. Man-made fibers have been manufactured for over 20 years, but there have been few concerns raised regarding the safety of rock-wool, were considered to be non-hazardous, because of the different durability in the lung. Present study consistently suggests that man-made fibers with fine and sharp points have similar risk as carcinogen of asbestos. The results of both patch test and adhesion materials with dumbbells shape provide clues regarding the mechanisms of tolerance in the lungs of exposed animals, and may be relevant for humans.
2 0 0 0 配偶者控除見直しに関するマイクロシミュレーション(Ⅱ)
- 著者
- 高山 憲之 白石 浩介
- 出版者
- 公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構
- 雑誌
- 年金研究
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.1-37, 2017
<p>1) 本稿では、個人住民税において配偶者控除を見直す場合の増減税効果、および所得税と個人住民税の双方において配偶者控除を同時に見直す場合の増減税効果、の2つを推計した。本稿は所得税のみの見直しを考察した高山・白石(2016)の続編である。</p><p>2) 利用したデータは『国民生活基礎調査』(2013年実施)であり、2012年分の所得データを使用した。個人住民税は2013年の制度を前提とした。ただし、その均等割部分は等閑視した。制度見直しに当たって、全体として増減税同額(税収中立)になるように配慮した。</p><p>3) 高山・白石(2016)では、専業主婦を「収入を伴う仕事をしていない家事専業の妻」と定義していた。本稿では、その定義を最狭義に変更し、夫が被用者であり、かつ「収入を伴う仕事をしていない家事専業の妻」に限定した。ただし、参考計数として高山・白石(2016)と同じ定義をした専業主婦の場合についても推計結果を掲載している。</p><p>4) 個人住民税を単独で見直す場合の主要な推計結果は次のとおりである。</p><p> ① 配偶者控除(配偶者特別控除を含む。以下、同様)を廃止すると、年間6600億円の税収増となる。全体として61%の世帯で税負担の増減はない。税負担が増えるのは39%の世帯であり、妻が専業主婦の世帯ないし非正規で就業している共働き世帯がその中核を占めている。税負担増は平均で年間3万2000円であり、世帯年収が高くなっても、この金額はほとんど変わらない。</p><p> ② 33万円の配偶者控除を廃止し、同額の夫婦控除(所得控除方式:世帯年収600万円までの所得制限つき)を導入すると、全体として15%の世帯が負担増、12%の世帯が負担減となる。負担増が負担減を世帯数で上回っており、所得税の見直し結果とは逆である。負担増が相対的に多いのは、世帯年収600万円以上の専業主婦世帯、および妻が非正規で就業している世帯年収700万円以上の世帯である一方、妻が正規で就業している共働き世帯では負担減組が多数派となる。</p><p> ③ 配偶者控除を廃止し、3万3000円の夫婦税額控除(世帯年収600万円までの所得制限つき)に移行しても、その効果は上記②で述べた所得控除方式の夫婦控除を導入したときと、全く変わらない。個人住民税が10%の比例税だからである。</p><p> ④ 個人住民税が累進税率を採用していれば、夫婦税額控除への移行で負担減組の方を負担増組よりも多くすることができる。</p><p> ⑤ 2017年度税制改正法は所得税と同様、パート主婦特権を中間所得層に限って拡大・強化する性格を有している。</p><p>5) 所得税と個人住民税を同時に見直す場合の主要な推計結果は以下のとおりである。</p><p> ① 所得控除方式の夫婦控除(所得税38万円、個人住民税33万円)に世帯年収制限(所得税800万円、個人住民税600万円)つきで移行する場合、税負担減となる世帯は15%、税負担増世帯14%となり、前者の方が後者より若干ながら多い。さらに、世帯年収400万円以上700万円未満の中間所得層では減税組が増税組を世帯数で圧倒する一方、年収700万円以上では逆に増税組の方が多くなる。また専業主婦世帯では増税組が減税組よりも多い一方、妻が正規または非正規で就業している世帯では総じて減税組の方が増税組よりも多い。</p><p> ② 夫婦税額控除(所得税3万8000円、個人住民税3万3000円)に世帯年収制限(所得税670万円、個人住民税600万円)つきで移行する場合においても、減税組(30%)が増税組(12%)を世帯数で圧倒する。この点は妻の働き方が違っても、質的に変わりがない。また、世帯年収100万円以上700万円未満の中低所得層では減税組の方が増税組より多い。所得税のみを見直す場合と同様に、所得税・個人住民税の双方を同時に見直す場合においても、「負担増=多数派」説「中間所得層=負担増」説は、いずれも事実に反していることが確認された。</p>
- 著者
- 中山 浩太郎 伊藤 雅弘 ERDMANN Maike 白川 真澄 道下 智之 原 隆浩 西尾 章治郎
- 出版者
- The Japanese Society for Artificial Intelligence
- 雑誌
- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.6, pp.549-557, 2009
- 被引用文献数
- 3 4
Wikipedia, a collaborative Wiki-based encyclopedia, has become a huge phenomenon among Internet users. It covers a huge number of concepts of various fields such as arts, geography, history, science, sports and games. As a corpus for knowledge extraction, Wikipedia's impressive characteristics are not limited to the scale, but also include the dense link structure, URL based word sense disambiguation, and brief anchor texts. Because of these characteristics, Wikipedia has become a promising corpus and a new frontier for research. In the past few years, a considerable number of researches have been conducted in various areas such as semantic relatedness measurement, bilingual dictionary construction, and ontology construction. Extracting machine understandable knowledge from Wikipedia to enhance the intelligence on computational systems is the main goal of "Wikipedia Mining," a project on CREP (Challenge for Realizing Early Profits) in JSAI. In this paper, we take a comprehensive, panoramic view of Wikipedia Mining research and the current status of our challenge. After that, we will discuss about the future vision of this challenge.
2 0 0 0 OA 地場産地における起業と「新しさの不利益」
- 著者
- 近藤 弘毅 Hiroki KONDO 目白大学経営学部
- 雑誌
- 目白大学経営学研究 = Mejiro journal of management (ISSN:13485776)
- 巻号頁・発行日
- vol.(7), pp.25-37, 2009 (Released:2017-10-20)