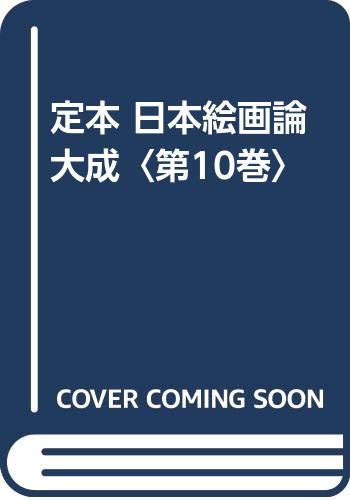2 0 0 0 認知科学と学習科学における知識の転移(<特集>知識の転移)
- 著者
- 白水 始
- 出版者
- 社団法人人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会誌 (ISSN:09128085)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.347-358, 2012-07-01
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 IR 東京の池泉庭園の変遷に関する研究 : 水源の変化を対象として
- 著者
- 白井 彦衛 貫井 文雄 竹林 昭廣
- 出版者
- 千葉大学
- 雑誌
- 千葉大学園芸学部学術報告 (ISSN:00693227)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.67-79, 1983-12-25
本論文は,東京の池泉136カ所,池泉庭園65カ所を調査することにより,江戸から東京にかけての水源の変化と池泉庭園の変質状況を解明することを目的としている.江戸の庭園の特徴は,池泉を効果的に利用するところにある.庭園の水源は,海,河川,地下水(湧水,井戸水),上水に依存していたが,その中で湧水の利用が圧倒的に多かった.江戸が東京と呼称を変えたころから,市街地は構造的に大きな変貌をとげた.その結果,水辺の埋立,上水の廃止,地下工事による湧水の涸渇など水系の変化を生じ,同時に池泉庭園もまた大きく変質した.とくに,上水型庭園は7カ所から0カ所に,潮入型庭園は6カ所から1カ所に,湧水型庭園は37カ所から18カ所に減少したが,河川水型庭園の4カ所には変化がなかった.その他に特殊なタイプが若干あり,また15カ所の庭園の水源は不明であった.
2 0 0 0 OA ライオンマン : 冒険大活劇
2 0 0 0 OA 日本語入力用新キー配列とその操作性評価
- 著者
- 白鳥 嘉勇 小橋 史彦
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.6, pp.658-667, 1987-06-15
本報告は 文字キー数が少なく かつシフトキー操作を必要としない利点を有するローマ字入力について日本語入力に適したキー配列を検討したものである.キーボードの打けん速度を向上することをねらいとして ?交互打けん率の向上 ?キーストローク数の低減 ?ホーム段キー使用率の向上 ?各指使用率のバランス ?同指段越え打ちの減少の5項目を設計指針として取上げた.この結果 子音と母音を左右に分離し かつ1キーに複数の文字を割りつけた複合キーを含む3段10列のローマ字配列を得た.この配列の交互打けん率は91% ホーム段キー使用率は68%であり 従来のQWERTY配列を用いたローマ字入力の場合(同:各69 29%)に比べて高い操作特性値を有する.3名の被験者について操作実験を行った結果 文字入力速度の習熟曲線は各被験者とも早い立上り特性を示した.うち1名のかな文入力速度は 約330時間の練習後に 240字/分(360ストローク/分)の高い値に達した.また エラー率は 練習によって0.5%に低下し操作上の問題はみられない.以上のことから 本配列が日本語入力に適していることが分かった.
2 0 0 0 OA 小石川後楽園の水景の変遷に関する史的考察
- 著者
- 五島 聖子 藤井 英二郎 白井 彦衛
- 出版者
- 社団法人日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 : 日本造園学会誌 : journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.272-279, 1999-01-30
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 2 3
これまでの小石川後楽園に関する研究では,もともと後楽園の大泉水の池尻は北東方向に向けられていたことが指摘されているが,その背景については明らかにされていない。そこで本論文では,大泉水を中心とする水系の変更の背景について,現在残されている後楽園に関する文献と絵図をもとに考察した。その結果,後楽園の水景の変更は,元禄期から享保期にかけて起こった天災に起因すると考えられ,それに伴い「渡月橋」の位置も変更されたと考えられる。また,江戸中期に記された『遊後楽園記並序』や同時期に描かれた絵図により,大泉水の中島は,江戸時代中期ごろまでは現在と異なる形状であった,と推定した。
2 0 0 0 OA 詳細解体による廃パソコン中の金属含有量の推定
- 著者
- 白波瀬 朋子 貴田 晶子
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物資源循環学会論文誌 (ISSN:18835856)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.217-230, 2009 (Released:2009-09-16)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 5 6
廃パソコンを詳細解体し,化学分析により40元素について全含有量を求めた。パソコン1台中の基板約1kg (電源基板を除く) には,Ag, Au, Pd, Al, Cu, Pbがそれぞれ,0.79, 0.14, 0.19, 91, 187, 17.8g含まれ,そのうちマザーボードに含まれる割合は,Ag, Au, Pdは58%,Cuは66%であった。廃パソコン11kgに含まれるAg, Au, Pd, Al, Cu, Fe, Zn, Nd, Pbの含有量はそれぞれ,0.79, 0.14, 0.19, 420, 320, 7,200, 77, 23, 20gであった。また,Ni, Sn, Sb, Mg, Mnは57, 28, 2.1, 1.6, 1.0gと推定した。含有量が0.02g以下の金属元素は,Co, Nb, Cd, Te, V, Ga, Sc, 0.01g以下の金属元素は,Se, Ta, As, Bi, In, Hf, Ir, Li, Pt, Tl, Y等であった。2004年の廃パソコンの発生量747万台から,年間に廃棄されるパソコン中の金属量 (廃製品から回収しうる最大量) を推定し,Au, Ag, Pdについてそれぞれ,1.1, 5.9, 1.4tonと見積もった。
2 0 0 0 OA 固体の低温熱容量
- 著者
- 白神 達也 齋藤 一弥 阿竹 徹
- 出版者
- Japan Society of Calorimetry and Thermal Analysis
- 雑誌
- 熱測定 (ISSN:03862615)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.134-143, 1994-07-30 (Released:2009-09-07)
- 参考文献数
- 44
Andersonらの理論的見地から,固体の低温熱容量について,近年の実験的および理論的研究を紹介した。Andersonらが仮定した二準位系のほかに,最近数多くの非晶質固体において“余分の”低エネルギー励起が見い出されてきた。コンピュータシミュレーションもそのような励起の存在を支持している。それらはまた“ソフトポテンシャル”理論によって説明された。熱容量や音速の異常な温度依存性は,固体電解質や高温超伝導体,純金属などの結晶性固体においても認められるようになってきた。これらの振舞いは非晶質固体の場合とよく似ており,Andersonらの理論によって説明できる。
2 0 0 0 画乗要略 . 近世逸人画史
- 著者
- [白井華陽著] . [中尾樗軒著]
- 出版者
- ぺりかん社
- 巻号頁・発行日
- 1998
2 0 0 0 エルヴィン・バルトの生涯とその造園上の業績
- 著者
- 白幡 洋三郎
- 出版者
- 社団法人日本造園学会
- 雑誌
- 造園雑誌 (ISSN:03877248)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.5, pp.37-42, 1982
- 被引用文献数
- 1
エルヴィン・バルトの活躍した時期はおおよそ1910・20年代である。その間リユベック市, シャルロッテンブルク市 (1920年ベルリン市と合併) ベルリン市の造園局長を歴任し, 29年にはベルリン農科大学の正教授となった。両大戦間のドイツ造園界に彼の仕事は重要な位置を占める。装飾緑地より保健緑地を尊重し, フォルクスパルクの設計を数多く手がけたが, そこから時代思潮を反映した彼の造園観をうかがうことができよう。
2 0 0 0 IR 英語のリズム、日本語のリズム : 言語と音楽の相関性
- 著者
- 眞田 亮子 Ryoko SANADA 目白大学外国語学部英米語学科
- 雑誌
- 目白大学人文学研究 = Mejiro journal of humanities (ISSN:13495186)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.201-207, 2008
2 0 0 0 OA 対象物の引き剥がし支援動作 (DAM) の発見とロボットハンドへの応用
- 著者
- 白井 達也 金子 真 原田 研介 辻 敏夫
- 出版者
- The Robotics Society of Japan
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.57-64, 2002-01-15 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
Through grasp experiments by human achieving an enveloping grasp for a small cylindrical object placed on a table, we found an interesting grasping motion, where human changes the finger posture from upright to curved ones after each finger makes contact with the object. During this motion, the object is automatically lifted up through either rolling or sliding motion between the finger tip and the object. A series of this motion is called as Detaching Assist Motion (DAM) . An advantage of DAM is that most of grasping motions can be done on the table instead of in the air. Therefore, we can avoid the worst scenario where the object falls down to the table. We first discuss the basic mechanism of DAM by human experiments. We then apply the DAM to a grasping motion by a multi-fingered robot hand. We show that the DAM can be explained by using Self-Posture Changing Motion. We also show some simulation and experimental results to confirm that a small object can be grasped easily by applying the DAM.
2 0 0 0 IR 日本人大学生に見られる不正確な発信の原因に関する考察 : 知識不足か練習不足か?
- 著者
- 藤森 吉之 Yoshiyuki Fujimori 白鴎大学
- 出版者
- 白鴎大学教育学部
- 雑誌
- 白鴎大学教育学部論集 = Hakuoh Journal of the Faculty of Education (ISSN:18824145)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.189-213, 2013-05-01
2 0 0 0 OA なじみ深さのマッチング: 認知プロセスと生態学的合理性の実験的検討
- 著者
- 白砂 大 松香 敏彦 本田 秀仁 植田 一博
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.328-343, 2017-09-01 (Released:2018-03-01)
- 参考文献数
- 22
Previous studies show that, in a binary choice task, people often choose one object between two objects using a simple heuristic (e.g., recognition, familiarity, or fluency heuristic), and that such a simple strategy is ecologically rational. These studies almost exclusively pay attention to subjective knowledge (i.e., familiarity) about two alternatives. However, we pointed out that familiarity of an object presented in a question sentence might affect people’s inferences. Specifically, we hypothesized that, in a binary choice task, when an object in a question sentence was familiar (unfamiliar) to a decision maker, he or she would choose a more familiar (unfamiliar) object from the two alternatives. We call this heuristic “familiarity-matching.” We examined whether people actually employed familiarity-matching and whether familiarity-matching was an ecologically rational strategy. The results of three experiments generally confirmed usage and ecological rationality of familiarity-matching. Experiment 1 showed that if an object in a question sentence was familiar (unfamiliar) to participants, then they were likely to choose a more familiar (unfamiliar) object from the two alternatives;that is, participants indeed employed familiarity-matching. Experiment 2 showed that when participants felt difficult to make a decision, they were more likely to employ familiarity-matching. Experiment 3 showed that familiarity-matching could be applied in an ecologically rational manner in real-world situations. The results of present study collectively shed light on important cognitive mechanisms involved in inference tasks. We believe that the present findings make a substantial contribution to reveal unsolved human cognitive processes.
2 0 0 0 OA 老化バイオマーカー研究
- 著者
- 清水 孝彦 白澤 卓二
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.138, no.2, pp.60-63, 2011 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
加齢と共に変動し,老化や加齢を予測できる因子を老化バイオマーカーと位置付けている.これまでに,性ホルモンのエストロゲンやテストステロンが知られている.Insulin-like growth factor-1やビタミンDなどの成長因子やビタミンも加齢性の変動を示す.カロリー制限アカゲザルの研究からdehydroepiandrosterone sulfate,インスリン,体温の変化が長期縦断研究の加齢性変化データと一致することが判明し,注目されている.さらに最近では,生活習慣病と強くリンクする成分も加齢性変化を示すことが明らかとなった.高齢社会を迎えた現在において,現在の健康状態や老化状態を客観的に評価する老化バイオマーカーの利用価値は高まっている.
2 0 0 0 OA 阿蘇カルデラ東部濁川左岸沿いに出現した正断層群とその活動履歴
- 著者
- 白濱 吉起 宮下 由香里 亀高 正男 杉田 匠平
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2018年大会
- 巻号頁・発行日
- 2018-03-14
2016年熊本地震に伴い,布田川・日奈久断層帯に沿って地表地震断層が出現した.地震断層は従来推定されていた布田川区間の北端を約4 km越え,阿蘇カルデラ内東部にまで及んだ.阿蘇カルデラ内に出現した地震断層は,立野付近から北東南西走向の右横ずれ変位を主体とするトレースと,東西走向の上下変位主体のトレースに分岐する.この内,東西方向の地震断層は濁川左岸の地溝帯に沿って断続的にやや左ステップしながら約2.5 km続く様子が確認された.この地溝帯が熊本地震のような断層活動によって形成された変動地形であるとすれば,地表地震断層が活断層である可能性が示唆される.そこで我々は,九州大学からの委託業務「平成28年熊本地震を踏まえた総合的な活断層調査」の一環として,新しく阿蘇カルデラ内に現れた地表地震断層が活断層であるか否か,また,活断層である場合はその活動履歴を明らかにすることを目的に,熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽沢津野地区においてトレンチ調査を実施した.掘削地点は立野地区から2 km東の2~4 mの崖に挟まれた地溝内に位置する.そこでは,地構内の平坦地を利用した水田に,幅20~30 mでほぼ並走する東西走向の二本の地表地震断層が確認された.南側のトレースは北落ち,北側のトレースは南落ちを示し,地形と調和的に中央部分が落ち込む様子が見られた.トレンチ掘削前にボーリング調査を行ったところ,地溝外のコアでは地下7~8 mで草千里ヶ浜降下軽石層(Kpfa)が見られたのに対し,地構内では地表から約16 m下で見られた.この深度の差は地形的な落差と比べると明らかに大きく,累積的な沈降が示唆された.そこで,南北の地震断層トレースを横切りつつ,導水管を避けるように,長さ34 m,幅7 m,深さ4 mのトレンチをクランク状に掘削した.壁面には地表地震断層につながる断層と,地層の変形が明瞭に確認された.地層は主に阿蘇火山を起源とするローム層で構成され,河川性堆積物は見られなかった.また,地層中には年代指標となる鬼界-アカホヤ火山灰,姶良Tn火山灰,Kpfaといった広域テフラが確認されるとともに,弥生土器が出土した.断層はトレンチ北側では南傾斜,南側では北傾斜を示した.地層は断層に近づくに従って緩やかに撓み下がり,その撓みに伴う開口亀裂が多数生じていた.断層で上下に地層が食い違うとともに,いくつかの層準では断層を境に地層の厚さが増しており,変位の累積が見られた.これらの観察結果と14C年代測定結果を元に,約3万年前以降の活動履歴の推定を行った.発表では本トレンチが示す活動履歴について議論する.
2 0 0 0 レーニンの政治思想 : 比較思想の試み
2 0 0 0 OA ぺた語義:関西地区における教員免許状更新講習
2 0 0 0 OA 経済活動における違法行為に対する制裁手段の在り方に関する総合的研究
2 0 0 0 IR フランスにおける音楽著作権保護と管理の史的展開
- 著者
- 石井 大輔 Daisuke ISHII 目白大学社会学部メディア表現学科
- 出版者
- 目白大学
- 雑誌
- 目白大学総合科学研究 = Mejiro journal of social and natural sciences (ISSN:1349709X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.23-34, 2010