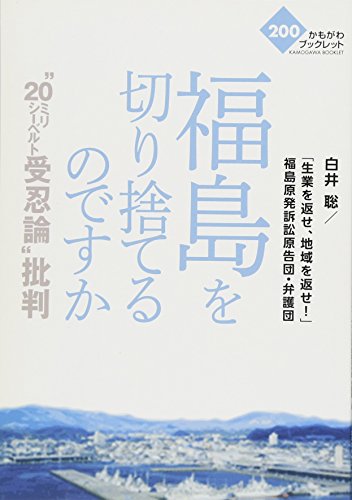2 0 0 0 OA 訂正増譯采覽異言
- 著者
- [新井白石] [著]
- 巻号頁・発行日
- vol.巻1, 1800
- 著者
- 白井 千晶
- 出版者
- 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 : SCJフォーラム = Trends in the sciences : SCJ Forum (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.8, pp.30-34, 2017-08
2 0 0 0 IR パーソンズ文化概念の超克可能性 : 文化的転回との関連から
- 著者
- 白石 哲郎
- 出版者
- 佛教大学
- 雑誌
- 佛大社会学 (ISSN:03859592)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.1-16, 2015-03-20
人類学者であるC. ギアーツが先鞭をつけた「解釈学的転回」は,とりわけ文化を分析の主軸に据える後期近代の社会科学者に多大な影響をもたらし,「文化的転回」の潮流を生む契機となった。「社会的なものから文化的なものへ」というパラダイム・シフトは,意味の社会学(意味学派)をはじめ,同時期に台頭した他の人文・社会科学にも共通して認められる傾向である。一方で,文化的転回と通底する問題群に関し,いちはやく定式化に努めた社会学者がT. パーソンズであった。彼自身が「文化の社会学」の名でさらなる純化を志向した行為システム論は,「文化システムと社会システムの相互依存と相互浸透の分析」に動機づけられており,その問題関心自体は,普遍的な妥当性をもつものとして評価すべきである。 しかしながら,社会構造の均衡を重視する機能主義的パラダイムに立脚しているがゆえに,また分析的リアリズムの姿勢に徹しているがゆえに,パーソンズの文化概念は「二重の現実遊離性」を孕んでおり,文化と社会をめぐる今日的状況の分析にそのまま援用することは困難である。 本稿の目的は,「文化的転回」を構成する三つの次元のうち,文化の概念規定次元からパーソンズの「文化の社会学」を再定式化することにある。本論では第一に,ギアーツにも影響を与えたS. K. ランガーやE. カッシーラーのシンボル概念に関して,社会科学における文化概念としての有効性を吟味し,第二に,カルチュラル・スタディーズの抗争的かつ流動的な文化理解を摂取することで両名のシンボル概念のさらなる補完を試みる。このような段階的,連続的な取り組みは,パーソンズの文化概念が抱える陥穽の超克を企図したものである。
2 0 0 0 トキイロヒラタケ色素成分の特徴
- 著者
- 白坂 憲章 山口 裕加 吉岡 早香 福田 泰久 寺下 隆夫
- 出版者
- 日本きのこ学会
- 雑誌
- 日本きのこ学会誌 : mushroom science and biotechnology (ISSN:13487388)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.147-153, 2012-10-31
- 参考文献数
- 14
トキイロヒラタケ子実体よりピンク色と黄色の色素を分離した.ピンクの色素は,硫安塩析,DEAEトヨパール,トヨパールHW55によるクロマトグラフィーにより色素タンパク質として精製され,分子量はSDS-PAGEおよびHPLC-GPCによって,それぞれ24.5kDa,30kDaと推定された.本色素タンパクは267,348,493nmに吸収極大を示し,28℃およびpH4から10で安定であった.一方,黄色色素からはSephadex G-25を用いたゲルろ過により3つの色素が精製され,分子量はHPLC-GPCにより10.8kDa,5.3kDa,4.4kDaであると推定された.これらの色素は可視領域に特徴的な吸収極大が見られず,水のみに溶解性を示した.本色素はH_2O_2,KMnO_4,NaOClといった強力な酸化剤で脱色され,Fe^<3+>をFe^<2+>へと還元した.これらの性質は,メラニン色素の性質によく合致した.
2 0 0 0 福島を切り捨てるのですか : "20ミリシーベルト受忍論"批判
- 著者
- 白井聡 「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟原告団・弁護団著
- 出版者
- かもがわ出版
- 巻号頁・発行日
- 2015
2 0 0 0 IR 鈴屋にみる文字コミュニケーション
- 著者
- 白石 克己
- 出版者
- 佛教大学総合研究所
- 雑誌
- 佛教大学総合研究所共同研究成果報告論文集 (ISSN:21896607)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.1-12, 2016-03-25
書簡の交流を基礎とする鈴屋の遠隔教育では文字コミュニケーションが重要な意味をもっていた。もちろん宣長の遊学時代も鈴屋での門人指導も,対面教育での口頭コミュニケーションが欠かせなかった。しかし,宣長はおびただしい書写や熱心な公刊活動などによって文字コミュニケーション主体の遠隔教育や対面教育を実施していた。言語は経験から遊離した抽象との批判から会読のような対面教育が推奨されるけれども,言語と経験との往復運動を図る指導であれば,文字コミュニケーションは遠隔教育にも対面教育にも欠かせない。宣長は書簡の交流によって門人一人ひとりへの添削指導を実施したが,これは相手の「情報構造」に従った指導といえる。会読講釈問答体遠隔座文字コミュニケーション
2 0 0 0 OA 電気-油圧式パルスモータ
- 著者
- 稲葉 清右衛門 伊藤 康平 白藤 良孝
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 自動制御 (ISSN:04477235)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.194-197, 1961-06-15 (Released:2010-10-29)
2 0 0 0 OA 信念の人:小林欣吾さんとルービンシュタイン
- 著者
- 白木 善尚
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.5-13, 2013-07-01 (Released:2013-07-01)
- 参考文献数
- 4
2 0 0 0 「Cyber尺八」のコンセプトとテクノロジー
- 著者
- 志村 哲 片寄 晴弘 金森 務 白壁 弘次 井口 征士
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告音楽情報科学(MUS) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.1996, no.124, pp.1-6, 1996-12-13
- 被引用文献数
- 1
我々は、「ヴァーチャル・パフォーマー」プロジェクトの一環として、1993年から現在までに、芸術創作面からの要望と、感性情報処理・ヒューマンコミュニケーション技術の研究・開発面を対等な立場に置いて「Cyber尺八」の共同制作をおこなってきた。Cyber尺八は、日本の楽器・尺八とその奏者の身体の両方に取り付ける各種センサ、シグナルプロセッサを伴うパーソナルコンピュータによって構成されるハードウェアと、尺八の伝統的演奏技法および、MAXプログラミングによるソフトウェアによって実現される楽器システムである。また、マルチメディア環境においては、その演奏情報によってデジタル映像やCGのリアルタイム・コントロールをも可能にしている。本稿は、システムと作品「竹管の宇宙」の概要を音楽的側面を中心に解説し、楽器・作曲ツールとして広く公開し活用する方向性を探る。Since 1993, up to the present, the creation of "Cyber Syakuhati (Shakuhachi)" has been integral part of the Project "Virtual Performer", the collaboration in which we equally respect both the demands/desires from artists and the studies/developments for the technology of the KANSEI Information Processing and Human communication. The Cyber Syakuhati is a musical instrument system being realized by the followings: The hardware which consists of the various sensors attached both to the syakuhati, traditional Japanese musical instrument, and to the body of the performer who plays it, and the personal computers with signal processors; traditional performing techniques of the syakuhati; and the software system designed/written by the MAX programing. It also enables to conduct the real-time control of the digital pictures and the computer graphics through the information from the performances, when the system is situated in the multi-media circumstances. This paper illustrates the outline of the system as well as the piece tikukan no utyu [The cosmology of the bamboo pipes]" composed by the present authors, chiefly from the musical viewpoint, and investigates the ways how the system will be known to the public and used efficiently as an instrument and/or a tool of creating musical compositions.
- 著者
- 片寄 晴弘 金森 務 白壁 弘次 井口 征士
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告音楽情報科学(MUS) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.1996, no.75, pp.47-50, 1996-07-27
- 被引用文献数
- 4
イメージ情報科学研究所では,Virtual Performerという研究の一環として,インタラクティブマルチメディアアートの制作を行っている.それらのうち,本稿では,尺八を題材にしたコンピュータミュージック「竹管の宇宙」とダンスを題材にしたDMIプロジェクトの制作状況および技術的なトピックスを紹介する.This paper describes the current overview of the Virtual Performer which is designed to compose and perform interactive multimedia arts with it. The Virtual Performer consists of sensory facilities, presentation facilities and authoring facilities. As for sensory facilities, this paper focusses on a motion capture sensor based on image processing and ATOM which is designed for the smallest Analog/MIDI conversion. The paper also desciribes applications of the Virtual Performer to the Computer Music and the Stage arts.
2 0 0 0 OA 劇症肝不全を合併した熱中症III度症候群の一救命例
- 著者
- 米満 弘一郎 白 鴻成 前野 良人 大西 光雄 西野 正人 木下 順弘 定光 大海
- 出版者
- 一般社団法人 日本救急医学会
- 雑誌
- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.7, pp.440-444, 2008-07-15 (Released:2009-07-25)
- 参考文献数
- 11
発症第 3 病日に劇症肝不全を合併したが,保存的加療にて軽快した熱中症III度症候群を経験した。症例は39歳の男性。マラソン中に意識消失した。Japan coma scale(JCS)200,腋窩温40.9°C,ショック状態だった。前医入院後,意識・全身状態は改善したが,第 3 病日に肝酵素,CPKの著明な上昇及びDICを認め当院転院となった。第 4 病日に肝性昏睡II度,PT活性20%,HPT 20%,AKBR 0.69,AST 3,330 IU/l,ALT 5,880 IU/l,NH3 155μg/dlとなり劇症肝不全と診断し,血漿交換及び持続血液濾過透析を行った。肝障害は速やかに改善し第33病日,独歩転院となった。熱中症III度症候群に合併する重症肝障害は,ショック,DICを契機に第 3 病日前後に顕在化すると考えられる。適時的な血液浄化などで保存的に軽快する例が多いが,早期より肝障害を想定した慎重な輸液管理,集中管理が重要である。
2 0 0 0 OA 大学の教職課程における発達障害学生支援と合理的配慮
- 著者
- 池田敦子 田部絢子 石川衣紀 内藤千尋 神長涼 石井智也 髙橋智 AtsukoIKEDA AyakoTABE IzumiISHIKAWA ChihiroNAITOH RyoKAMINAGA TomoyaISHII SatoruTAKAHASHI 池田敦子(秋田大学学生支援総合センター) 田部絢子(大阪体育大学教育学部、東京学芸大学非常勤講師) 石川衣紀(長崎大学教育学部) 内藤千尋(白梅学園大学子ども学部、東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科博士課程) 神長涼(特定非営利活動法人東京都自閉症協会専任職員) 石井智也(東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科博士課程) 髙橋智(東京学芸大学 特別支援科学講座 特別ニーズ教育分野) AtsukoIKEDA(Akita University) AyakoTABE(Osaka University of Health and Sport Sciences) IzumiISHIKAWA(Nagasaki University) ChihiroNAITOH(Shiraume Gakuen University / United Graduate School of Education Tokyo Gakugei University) RyoKAMINAGA(NPO Tokyo Autism Society) TomoyaISHII(United Graduate School of Education Tokyo Gakugei University) SatoruTAKAHASHI(Tokyo Gakugei University)
- 出版者
- 東京学芸大学学術情報委員会
- 雑誌
- 東京学芸大学紀要. 総合教育科学系 (ISSN:18804306)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.125-133, 2017-02-28
2 0 0 0 IR 豊臣公儀としての石田・毛利連合政権
- 著者
- 白峰 旬
- 出版者
- 別府大学史学研究会
- 雑誌
- 史学論叢 (ISSN:03868923)
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.18-72, 2016-03
関ヶ原の戦いに至る政治的経過において、慶長5年(1600)7月に石田三成と毛利輝元を中心とした石田・毛利連合政権が成立し、豊臣秀頼を直接推戴して豊臣公儀として政権が形成されたことを拙稿「慶長5年7月~同年9月における石田・毛利連合政権の形成について」(1)においてすでに指摘した。 この時期の石田三成、毛利輝元などの動向については、石田・毛利連合政権というとらえ方はしていないものの、すでに布谷陽子「関ヶ原合戦の再検討-慶長五年七月十七日前後-」(この論考は「研究ノート」であるため、以下、布谷ノートと略称する)(2)、同「関ヶ原合戦と二大老・四奉行」(この論考は「論文」であるため、以下、布谷論文と略称する)(3)において検討がされている。 布谷氏が指摘した具体的な論点については後述するが、石田・毛利連合政権の当該期(慶長5年7月~同年9月)における具体的な動向を知るためには発給書状の検討が必要不可欠であり、その意味で本稿では、石田・毛利連合政権によって発給された書状を時系列データベース化することにより(4)、そこから読み取ることができる諸点について考察する。 また、阿部哲人「慶長五年の戦局における上杉景勝」(5)は、慶長5年の関ヶ原の戦いに至る政治的・軍事的過程における上杉景勝の役割・位置付けについて諸史料を綿密に検討して、新しい見解を提示している。阿部氏が指摘した具体的な論点については後述するが、こうした阿部氏の新見解も踏まえて、豊臣公儀としての石田・毛利連合政権の歴史的意義についても考察したい。
2 0 0 0 OA アモーダル補完が視覚探索に及ぼす影響は偏心度に依存する
- 著者
- 白間 綾 石口 彰
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.2, pp.114-122, 2009 (Released:2012-03-06)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1 1
Does amodal completion occur homogeneously across the visual field? Rensink and Enns (1998) found that visual search for efficiently-detected fragments became inefficient when observers perceived the fragments as a partially-occluded version of a distractor due to a rapid completion process. We examined the effect of target eccentricity in Rensink and Enns's tasks and a few additional tasks by magnifying the stimuli in the peripheral visual field to compensate for the loss of spatial resolution (M-scaling; Rovamo & Virsu, 1979). We found that amodal completion disrupted the efficient search for the salient fragments (i.e., target) even when the target was presented at high eccentricity (within 17 deg). In addition, the configuration effect of the fragments, which produced amodal completion, increased with eccentricity while the same target was detected efficiently at the lowest eccentricity. This eccentricity effect is different from a previously-reported eccentricity effect where M-scaling was effective (Carrasco & Frieder, 1997). These findings indicate that the visual system has a basis for rapid completion across the visual field, but the stimulus representations constructed through amodal completion have eccentricity-dependent properties.
2 0 0 0 OA ダイアグラムに基づく法的論争支援システム
- 著者
- 新田 克己 柴崎 真人 安村 禎明 長谷川 隆三 藤田 博 越村 三幸 井上 克巳 白井 康之 小松 弘
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.32-43, 2002 (Released:2002-04-04)
- 参考文献数
- 23
We present an overview of a legal negotiation support system, ANS (Argumentation based Negotiation support System). ANS consists of a user interface, three inference engines, a database of old cases, and two decision support modules. The ANS users negotiates or disputes with others via a computer network. The negotiation status is managed in the form of the negotiation diagram. The negotiation diagram is an extension of Toulmin’s argument diagram, and it contains all arguments insisted by participants. The negotiation protocols are defined as operations to the negotiation diagram. By exchanging counter arguments each other, the negotiation diagram grows up. Nonmonotonic reasoning using rule priorities are applied to the negotiation diagram.
- 著者
- 白水 繁彦 蕪木 寛子
- 出版者
- 広島大学留学生センター
- 雑誌
- 広島大学留学生教育 (ISSN:13428934)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.47-67, 1999
2 0 0 0 IR 尿路結石1,500個の分析結果 マイクロコンピューター使用による集計の試み
- 著者
- 池田 龍介 鈴木 孝治 田中 達朗 谷口 利憲 白岩 紀久男 卞 在和 津川 龍三 中村 武夫 岩佐 嘉郎 田近 栄司
- 出版者
- 泌尿器科紀要刊行会
- 雑誌
- 泌尿器科紀要 (ISSN:00181994)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.183-189, 1984-02
当科において1974年より1981年までの7年4ヵ月,富山県立中央病院泌尿器科において1961年より1981年までの20年11ヵ時間と経験した尿路結石のうち,赤外線分光分析が行なわれた1514結石についてマイクロコンピューターを用いて臨床的分析を試みた.男子930例,女子344例,年齢は1歳より90歳に及び平均は男子44.7歳,女子41.6歳であった.結石成分分析には日立赤外線分光光度計EPI-G3型を,マイクロコンピューターとしてはSHARP MZ-80Cを用い,年齢,性別,発生部位,内層成分,外層成分,血清電解質,尿中電解質などを入力し,color display, green display, printer, X-Y plotterに出力,表示させた.4年前に報告した300個の結石における成績と比較すると,若干の変化が見られ,年齢分布において腎結石,膀胱結石含有患者の老齢化の傾向が認められたIn our laboratories, more than 1,500 urinary calculi have been analyzed by infrared spectroscopy. These data were statistically analyzed by microcomputer. The most frequent type was calcium oxalate combined with calcium phosphate, followed by pure calcium oxalate and magnesium ammonium phosphate combined with calcium phosphate. In particular, the composition of magnesium ammonium phosphate combined with calcium phosphate increased as compared with that four years earlier. Four years ago, we spent one month to statistically analyze 300 urinary calculi. But in this study, only sixteen days was required to analyze 1,500 urinary calculi by using a microcomputer.
- 著者
- 豊川 修平 田村 英一 仕幸 英治 新庄 輝也 安藤 裕一郎 ラザロフ ヴラド 廣畑 貴文 白石 誠司
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. MR, 磁気記録 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.416, pp.29-32, 2013-01-18
C_<60>-Coグラニュラー薄膜はC_<60>マトリクス中に単磁区構造を持つCo微粒子が分散した構造をした超常磁性体である。これまで、C_<60>-Coグラニュラー薄膜の電気伝導特性や磁気輸送特性について、Co微粒子やC_<60>/Co界面に関する様々な研究がされてきた。それぞれのCo粒子は粒子の小ささ故に大きな帯電エネルギーを有しており、それよりエネルギーが低い電子の伝導を阻害する。これをクーロンブロッケード(CB)効果と呼ぶ。我々は、C_<60>-Coグラニュラー薄膜においてCBの外部磁場による閾値電圧のシフトとヒステリシスを観測し、低温で100万%を超える磁気抵抗効果を得た。この現象を反強磁性結合した二粒子ボトルネックモデルにより説明し、モデルの妥当性について磁化曲線の面から検証した。
- 著者
- 小林 慎一 粂野 文洋 白井 康之 犬島 浩
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 研究技術計画 (ISSN:09147020)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.192-206, 2010-03-01
ソフトウェア分野の研究開発力を強化するための一つの方策として,研究開発対象にする重点テーマを策定する方法論を提案する。この方法論では,ソフトウェア技術に関する複数のトレンドがそれぞれ独立に進展することによって対立概念が顕在化し,その解消のために新たな技術の創出が求められると考える。将来の対立点がどこに発生するかを推測することが重点分野の検討につながる。従来課題とされていた対立点の推測はソフトウェア工学の知見を活用したFURPS+モデルによるトレンドの対立度計算手法による。本方法論を用いて公的な研究費配分機関における重点的な研究開発テーマの検討を行い,25の重点分野を策定した。これらの重点分野の妥当性を評価するために,デルファイ法にもとづいて実施された文部科学省技術予測調査で得られた主要課題との比較分析を行った。本方法論で得た重点分野は文科省調査の主要課題の89%(8テーマ/9テーマ)をカバーしており,高い精度で両者が一致している。本方法論の重点分野の36%(9テーマ/25テーマ)は文科省調査の主要課題には存在しないテーマである。この部分は文科省調査に対する本方法論の独自性を示している。本方法論によって重点分野の検討プロセスに体系的な手順と一定の網羅性が得られ,複数人での検討作業が過度に発散せず,系統的で見通しの良いものになることを示した。
2 0 0 0 OA 鈍的腹部外傷による胃破裂とIIIa型膵損傷合併の1例
- 著者
- 白石 好 森 俊治 磯部 潔 中山 隆盛
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器外科学会
- 雑誌
- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.6, pp.488-492, 2003 (Released:2011-06-08)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
非常にまれであるハンドル外傷による胃破裂とIIIa型膵損傷を合併した1例を経験し, 胃切除と膵胃吻合による尾側膵温存術式にて救命しえたので報告する. 患者は64歳の男性で, 交通事故による腹部打撲と吐血を主訴に救急搬送された. 腹部CTでFree Air, 腹腔内出血を認めたため胃破裂疑いで緊急手術となった. 手術所見は胃前壁の体下部から幽門前庭にかけて約7cmの破裂創と胃角部小彎に出血性潰瘍を認めた. また, 上腸間膜静脈右縁にて膵の完全断裂を認めた. 出血は胃潰瘍によるものと判断した. 止血のために胃切除施行し膵温存のため膵尾側の膵胃吻合を施行した. 急性期の経過は順調であったが, 軽度の膵液瘻を認めた. 退院6か月経過後でも血糖値, 膵外分泌機能には異常を認めなかった. 自験例と文献的考察から消化管破裂や大量出血を合併した症例では, 膵温存術式として膵胃吻合は適した再建法であると考えられた.